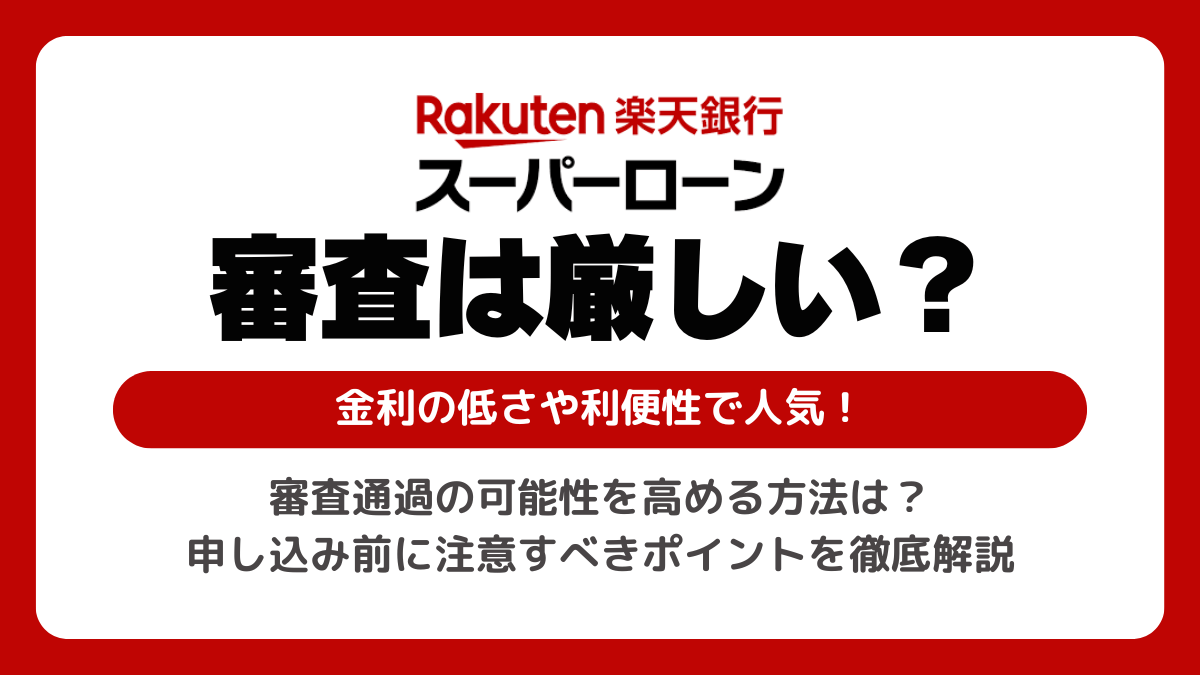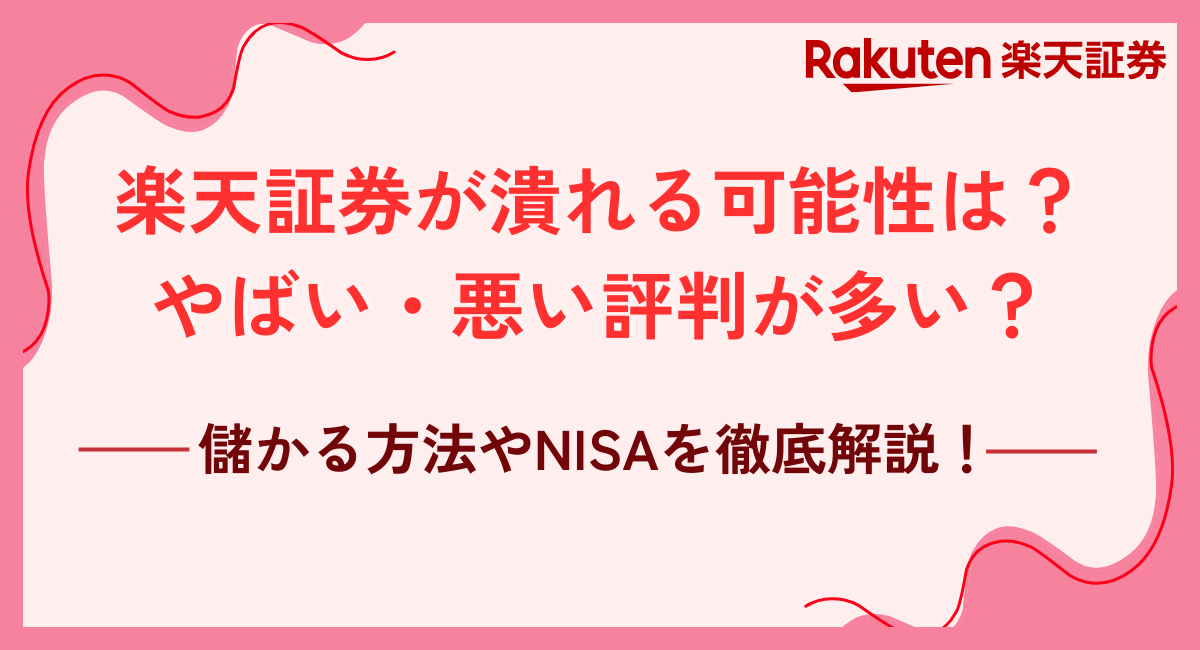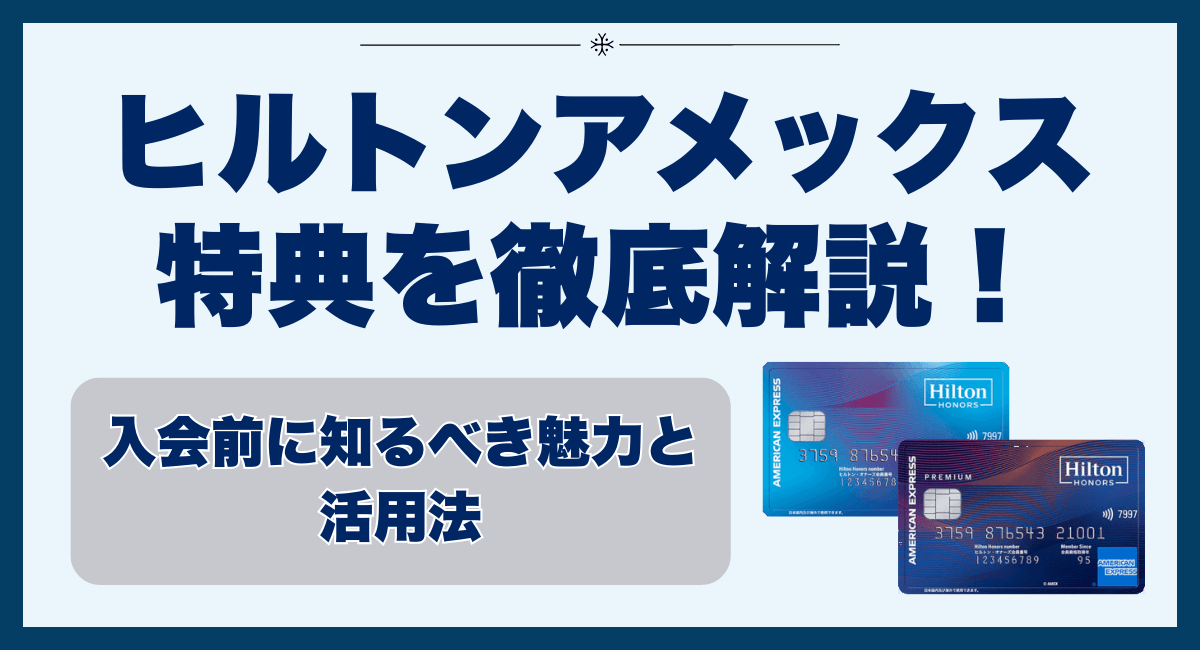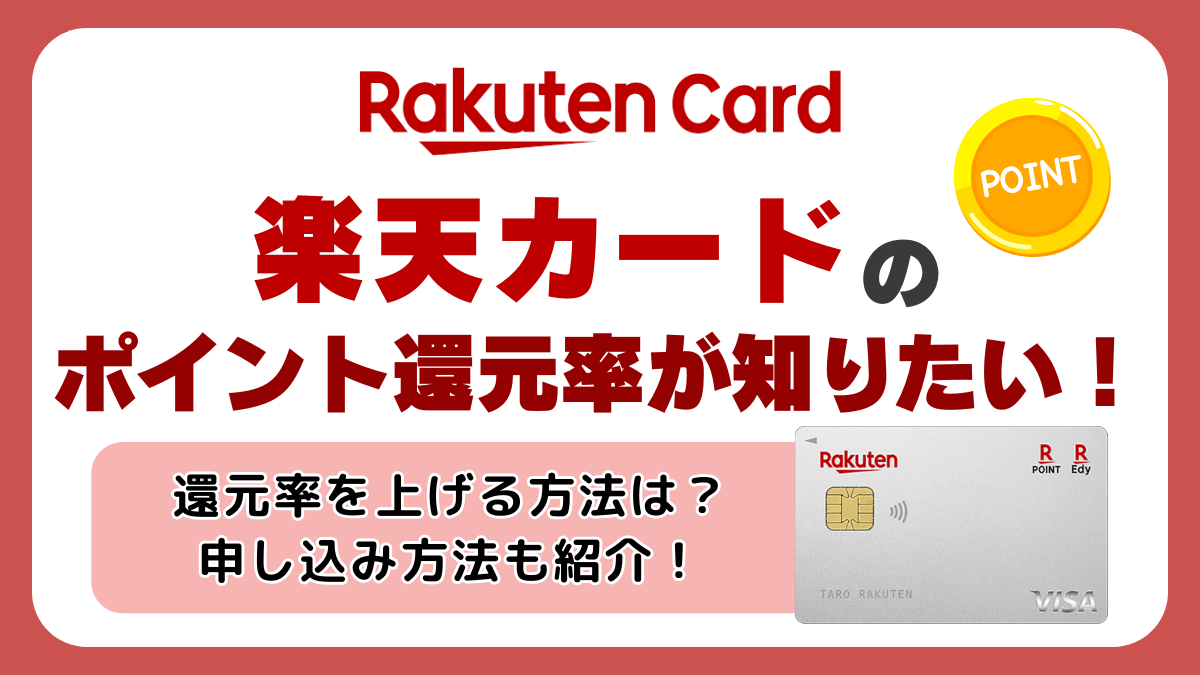子どもの成長は一人ひとり異なり、中には発達に特別なサポートが必要な子どももいます。そんな時に役立つのが「療育」という支援システムです。これは発達に課題を持つ子どもたちの可能性を最大限に引き出すための専門的なアプローチで、身体機能の向上から社会性の獲得まで幅広くカバーしています。
個別指導や集団活動を通じて、日常生活スキルの習得、運動能力の向上、認知行動の改善、言葉の発達促進などが丁寧に行われます。こうした取り組みは子どもの自立を助けるだけでなく、保護者にとっても心強い相談の場となっています。
しかし、サービス開始までに時間がかかったり、どこに相談すべきか分かりにくかったりといった課題も存在します。まずは地域の児童相談所や医療機関への相談から始め、専門家による評価を受けることが第一歩です。
療育は、子どもの個性を尊重しながら社会参加を促す大切な取り組みです。この記事では療育の基本から利用方法まで詳しく解説します。
目次
療育とは

療育とは、障害を持つ子どもに対する医療と教育のことで、東京大学名誉教授の高木憲次によって提唱された考え方です。療育には、治療しながら教育するという考え方が含まれています。*1)
目的
療育の目的は、発達に特別な配慮が必要な子どもが、日々の暮らしや社会との関わりをスムーズに送れるよう支援することです。身体機能や心の発達を促進し、生活の豊かさを高めていきます。
子ども一人ひとりの成長段階や特性に合わせたサポートを提供することで、将来的な社会への参加や自立を後押しします。
また、家族への助言や地域の様々な機関との協力体制を築くことも大切な役割です。これにより、子どもと家族が安心して過ごせる環境づくりを目指しています。
適切な支援によって、子どもの持つ可能性を最大限に引き出し、自分らしく生きる力を育むことが療育の本質的な狙いといえます。*2)
発達支援との違い
療育と発達支援は似た言葉ですが、微妙な違いがあります。療育は元々、体に不自由のある子どもの自立を目指す医療的な支援として始まり、現在では障害が確定した子どもへの援助という印象が強くあります。
一方、発達支援はより広い概念で、診断がついていない「発達が気になる」段階の子どもも対象としています。また、子ども本人だけでなく、家族へのサポートや保育園などの地域機関への助言も含んでいるため、子どもが地域で健やかに育つための総合的な取り組みとして考えられています。*3)
療育の種類
療育は、個別療育と集団療育の2つに分けられます。
| 個別療育 | 集団療育 | |
| 支援の形態 | 支援者と子どもが1対1で対応 | 複数の子どものグループ活動 |
| 主な内容 | 発達状況や特性に応じたオーダーメイドの個別プログラム | 遊びや制作、集団でのコミュニケーションや社会性の練習 |
| 目的の違い | 個々の課題や発達段階に合わせたピンポイントの支援 | 集団生活の適応力やコミュニケーション能力の向上 |
*5)
また、療育のプログラムもさまざまです。
| プログラム名 | 概要 |
| 応用行動分析(ABA) | 行動の前後関係を分析し、望ましい行動を強化し問題行動を減らす療法 |
| TEACCHプログラム | 自閉症の特性に配慮した構造化支援で自立と社会参加を促す包括的プログラム |
| ソーシャルスキルトレーニング(SST) | 挨拶や会話など対人関係スキルを練習し社会性や協調性を高める訓練 |
| 言語療法 | 発語や言語理解力を高め、コミュニケーション能力の向上を図る訓練 |
| 感覚統合療法 | 感覚の過敏や鈍麻を調整し、運動や行動のバランスを整える療育技法 |
*4)*5)
療育を受けられる施設は?
療育が受けられるのは以下の施設です。
| 施設名 | 概要 |
| 児童発達支援センター | 障害児の発達支援と家族相談を行う |
| 放課後等デイサービス | 小学生以上の生活スキル向上支援 |
| 療育センター・発達支援センター | 多職種連携で専門的療育や評価を実施 |
| 医療型児童発達支援施設 | 医療ケアと療育を一体的に提供 |
| 特別支援学校 | 障害児への教育と療育を一体で行う学校 |
| 児童相談所 | 療育開始相談・児童福祉全般の相談窓口 |
これらの施設は、子どもの発達段階や特性、ニーズに応じた支援を提供し、家族への相談・助言も行う地域の重要な支援拠点です。
療育の具体的な内容
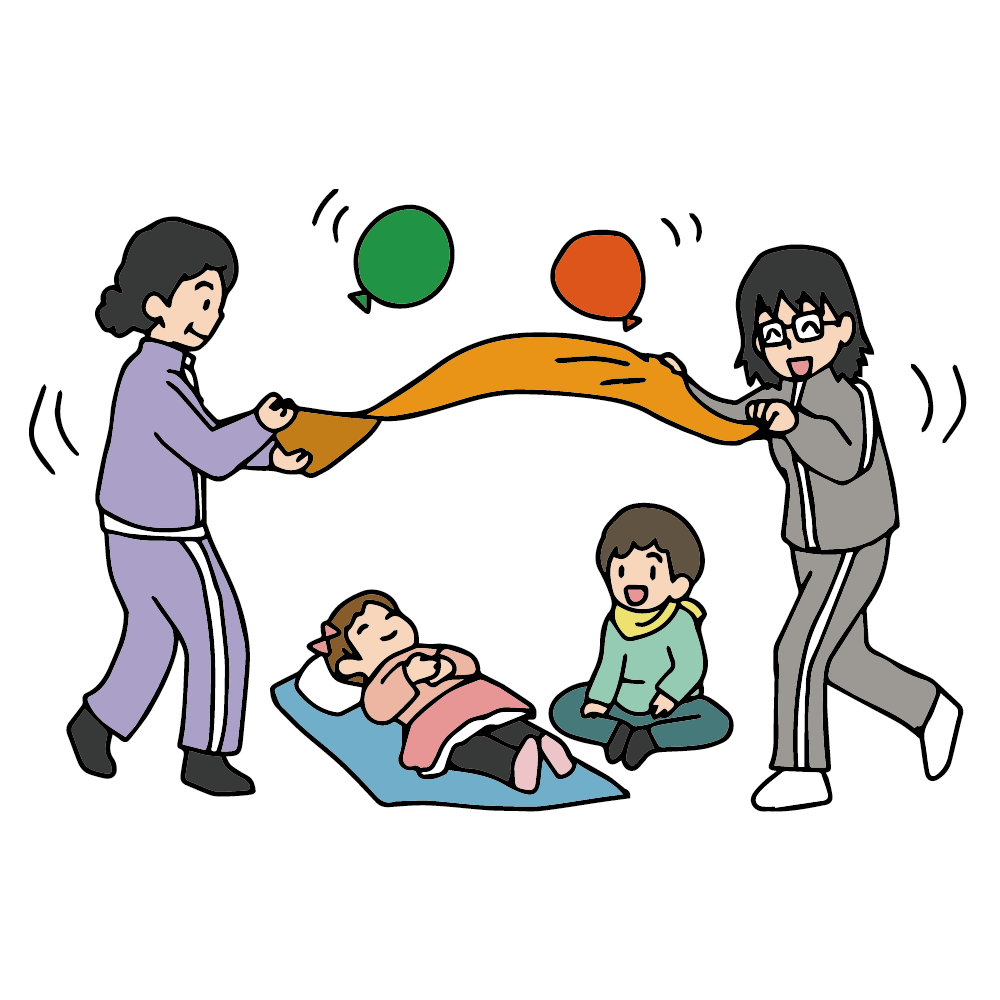
療育の具体的活動は、5つの領域に分けられます。
- 健康・生活
- 運動・感覚
- 認知・行動
- 言語・コミュニケーション
- 人間関係・社会性
それぞれの内容を見てみましょう。
それぞれの具体的な内容を見てみましょう。
健康・生活
健康・生活面の具体的な活動は以下の通りです。
- 体調管理と適切な対応
- リハビリプログラムの実施
- 食事、睡眠、トイレなどの習慣づけ
- 日常生活を助ける道具の活用
これらの活動に加え、生活習慣や生活リズムの形成、基本的な生活スキルの獲得についてもサポートします。*2)
運動・感覚
運動・感覚面の具体的な活動は以下の通りです。
- 正しい姿勢の保持と基本動作の練習
- 移動能力の向上
- 補助器具の使い方
- 視覚、聴覚、触覚などの感覚訓練
- 感覚過敏や鈍さへの対応
体の動かし方や感覚器官の向上を目指します。
認知・行動
認知・行動に関する活動は以下の通りです。
- 認知機能の発達促進
- 大小、数、時間などの概念理解
- 状況に合わせた行動の学習
- 問題行動の予防と対応策
物事の理解と適切な行動の習得を目指します。
言語・コミュニケーション
言語・コミュニケーション分野は以下の通りです。
- 意思伝達の基本スキル
- 言葉の獲得と使い方
- 手話やタブレットなどの代替手段
- 読み書き能力の育成
この分野では、言葉の理解と表現力の向上を目指します。
人間関係・社会性
人間関係や社会性に関する分野では、以下の活動を行います。
- 信頼関係の構築
- 模倣や象徴遊びの経験
- 集団活動への参加練習
- 自己認識と感情コントロール
他者との関わり方や社会ルールの習得を目指します。
療育のメリット

療育の良い点は、子どもの成長を専門的に支え、将来の自立に向けたスキルを身につけられることです。適切な関わりを通じて「自分はできる」という前向きな気持ちが育まれます。
また、家族にとっても子育ての悩みを相談できる場となり、同じ立場の方々とつながれる安心感が得られます。専門家からの助言は日常生活での関わり方にも役立ち、子どもと家族全体をサポートする大切な機会といえます。
子どもの発達促進と自立支援
療育を受けることで、子どもの成長が専門的な視点からサポートされます。発達段階や特性に合わせた適切な関わりにより、心と体の総合的な発達が促進されます。
健康面や運動能力、物事の理解力、言葉の獲得、人との関わり方など、さまざまな面での成長を包括的に支援するため、バランスの良い発達が期待できます。また、子どもの特性に合った環境を整えることで、不適切な対応による二次的な問題の発生を防ぐことができます。*2)
さらに、日常生活に必要な着替えや食事などの基本スキルの習得や、集団活動を通じた社会性の向上により、将来の自立に向けた土台が築かれていきます。子どもが自分の力を発揮しながら、主体的に生きていくための支援といえるでしょう。
自己肯定感の向上
療育では、子どもの特性や個性を十分に理解した環境の中で支援が行われるため、自分らしさを受け入れられる経験ができます。また、一人ひとりの発達に合わせた目標設定により、「できた!」という成功体験を積み重ねる機会が増え、自信につながります。
プログラムの中では子どもの意見や気持ちが尊重され、自分で選んだり決めたりする場面が大切にされます。こうした主体性を重んじる関わりを通して、「自分は大切な存在だ」という感覚が育まれていきます。
さらに、専門家の支援によって家族との関係も安定し、周囲からの温かい言葉かけや肯定的な関わりを受けることで、「自分は愛されている」という基本的な安心感が育ちます。これらの体験の積み重ねが、子どもの健やかな心の成長を支えます。*2)
保護者への支援と相談の場の提供
子どもだけではなく、保護者への支援も受けられます。専門家から子どもの特性や適切な関わり方についてアドバイスを受けられるため、日常生活での対応に自信が持てるようになります。
また、不安や悩みを気軽に相談できる場が確保されることで、子育ての負担感が軽減されます。専門家に質問できる安心感は、家族の精神的な支えとなり、より落ち着いた子育てにつながります。
さらに、同じような状況の家族と出会える貴重な機会でもあります。経験や情報を共有し合うことで、「一人ではない」という連帯感が生まれ、心理的な孤立を防ぎます。
療育のデメリット・課題

療育は子どもにとっても、保護者にとっても大きなメリットがある取り組みです。しかし、課題もいくつか存在しています。ここでは、2つの課題についてピックアップします。
すぐに対応してもらえない可能性がある
療育サービスを希望しても、すぐに支援が始まらない場合があることは大きな課題です。地域によって差はありますが、新規相談から初診までに1~2か月程度の待機期間が生じるケースがあり、その間、子どもと家族が適切なサポートを受けられないことがあります。
特に就学後に発達の心配が出てきた子どもへの対応が遅れがちで、早期介入の機会を逃してしまう可能性もあります。療育に対する需要が年々増加し多様化する中、相談したいときにすぐ対応できる体制が十分整っていない自治体もあるのです。*6)
この問題の背景には、専門スタッフの不足や施設の受け入れ枠の限界があります。行政や関係機関の連携強化、人材育成・確保が急務となっていますが、すぐには解決が難しい状況です。待機期間中も子どもの成長は続くため、家族にとって大きな不安要素となっています。
人材確保が難しい
療育の現場では専門知識を持つスタッフの確保が大きな課題となっています。保育士や教員、リハビリの専門家、心理士など必要な職種は多岐にわたりますが、これらの専門家を系統的に育成するシステムやカリキュラムが十分に整備されていません。
現場からは人材確保の難しさやスキルアップの方法について悩む声が多く寄せられており、行政による専門的なバックアップを求める意見も少なくありません。
特に近年は医療技術の進歩により、重い障害を持つ子どもや医療的なケアが必要な子どもが増加傾向にあります。こうした子どもへの支援には高度な専門知識と技術が求められますが、そうした能力を持つ人材は十分に確保できていないのが現状です。
質の高い療育サービスを広く提供するためには、専門家の育成と定着を促す仕組みづくりが急務といえます。
療育を受けるためには

子どもに療育を受けさせたい場合、どのようにすればいいのでしょうか。ここでは、多くの自治体で共通する療育相談の流れを説明します。
療育相談の流れ
多くの場合、自治体が療育相談の窓口となっています。ここでは、石川県白山市の事例を取り上げ、療育相談の流れを解説します。
療育相談は、以下の手順で行われます。
- 電話予約
- 初回相談
- 関係機関からの情報収集
- 支援提案
- 継続支援
*8)
療育を受けるには、まず最初に家族から専門機関へ電話で予約をします。これは対面での相談となるため、事前の連絡が必要です。予約なしの来所や電話・メールでの相談は基本的に受け付けていません。
予約日には初回相談として約1時間の面談が行われ、専門スタッフが子どもの状況や成長の経過、家族の心配事などを丁寧に聞き取ります。
その後、より適切な支援を検討するため、保育園や学校、病院など、子どもが関わっている機関から情報を集めることがあります。
これらの情報をもとに、子どもの特性に合った関わり方や環境の調整方法、将来に向けた進路、利用できる福祉サービスなどの提案がなされます。
支援が始まると、担当者を中心に様々な専門家がチームとなって継続的にサポートし、必要に応じて他の機関とも連携しながら、成長の段階に合わせた支援を行っていきます。
療育に関してよくある疑問
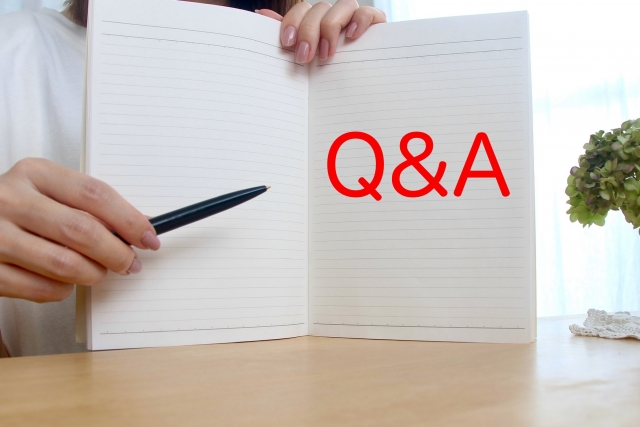
療育についてよくある2つの質問にQ&A形式で答えます。
意味がない・後悔したと言われることがあるのはなぜ
療育に対して「意味がない」や「後悔した」という声が聞かれる背景には、いくつかの要因があります。まず、提供される支援の内容や質にばらつきがあり、十分な専門性を持ったスタッフが関わっていないケースがあります。人材不足や専門家の確保が難しい現状では、適切な評価や支援が行き届かないことも少なくありません。
また、療育は短期間で劇的な変化が見られるものではなく、長い時間をかけて少しずつ成長を促していくものです。目に見える効果がすぐに現れにくいため、焦りや不安を感じる家族も多いでしょう。
さらに、「療育を受ければすぐに改善する」といった過度な期待を抱いてしまうと、現実とのギャップに失望感を覚えることがあります。子どもの特性や発達のペースは一人ひとり異なるため、他の子どもと比較して焦りを感じることも、不満につながる原因となっています。
療育を受けていたが健常児だった。どうすれば良い?
子どもが療育を受けていたものの、実際には特別な支援が必要ない「健常児」と判断された場合、まずは別の専門医にセカンドオピニオンを求めることをお勧めします。発達の判断は専門的で難しく、医師によって見解が異なることもあるため、複数の意見を聞くことが大切です。*9)
必ずしも療育を即座に中止する必要はありません。子どもの成長に不安がある場合は、療育の場で得られる子育てのヒントや専門家のアドバイスは、どの子どもの育ちにも役立つものです。
療育を通じて子どもの特性や行動パターンをより深く理解できれば、家庭での関わり方も自然と良い方向に変わっていくでしょう。
診断や支援内容に疑問や不安を感じる場合は、そのままにせず専門機関に相談することが大切です。子どもの成長に関わる重要な事柄なので、家族が納得して進められる方法を見つけていきましょう。
療育とSDGs
療育は、SDGsとどのように関係しているのでしょうか。ここでは、療育とSDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」との関わりを解説します。
SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」との関わり
療育はSDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」と深い関わりを持っています。この目標が掲げる「あらゆる年齢のすべての人の健康な生活を確保し、福祉を促進する」という理念は、発達に特別な配慮が必要な子どもへの支援にも当てはまります。
療育では、子どもの心と体の健やかな成長を促し、将来の社会参加や自立を支えるための専門的なサポートを提供します。これは単なる医療的ケアにとどまらず、子どもの可能性を最大限に引き出し、より豊かな生活を実現するための総合的な取り組みです。
また、家族への相談支援や情報提供も行うことで、子どもを取り巻く環境全体の福祉向上にも貢献しています。
「誰一人取り残さない」というSDGsの基本理念に沿って、すべての子どもが適切な支援を受けられる社会づくりを目指す療育の取り組みは、持続可能な福祉社会の実現に欠かせない要素といえるでしょう。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
今回は、療育について解説しました。療育とは発達に特別な配慮が必要な子どもの可能性を広げるための専門的な支援活動です。健康・生活面の基本習慣から運動能力の向上、認知機能の発達、言葉の獲得、社会性の育成まで、幅広い領域での成長をサポートしています。
この取り組みは、子どもの自立を促すだけでなく、自己肯定感の向上や、ご家族への相談支援という大きなメリットがあります。しかし一方で、すぐに利用できない場合や専門スタッフ不足といった課題も存在します。
療育を受けるには専門機関への相談から始まり、子どもの特性に合わせた支援プランが作成されます。「すべての人に健康と福祉を」というSDGsの理念にも沿った療育は、多様な個性を持つ子どもが共に育つ社会の実現に貢献しています。
参考
*1)日本大百科全書(ニッポニカ)「療育」
*2)子ども家庭庁「児童発達支援ガイドライン (令和6年7月)」
*3)厚生労働省「第3回障害児支援の在り方に関する検討会」
*4)LITALICO Life「【専門家監修】療育(発達支援)とは?種類や指導方法、対象、受けられる施設、効果について」
*5)ソラジョブ保育士「療育とは|厚生労働省のガイドラインからわかりやすく解説」
*6)さいたま市「さいたま市療育における現状と課題」
*7)コペル「発達相談から療育を受けるまでの流れを徹底解説!」
*8)白山市「発達相談センター相談の流れ(対象年齢 3歳4か月健診後~64歳)」
*9)たまひよ「発達障害と診断された子のうち、2割は誤診の可能性が セカンドオピニオンの重要性【専門医提言】」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。