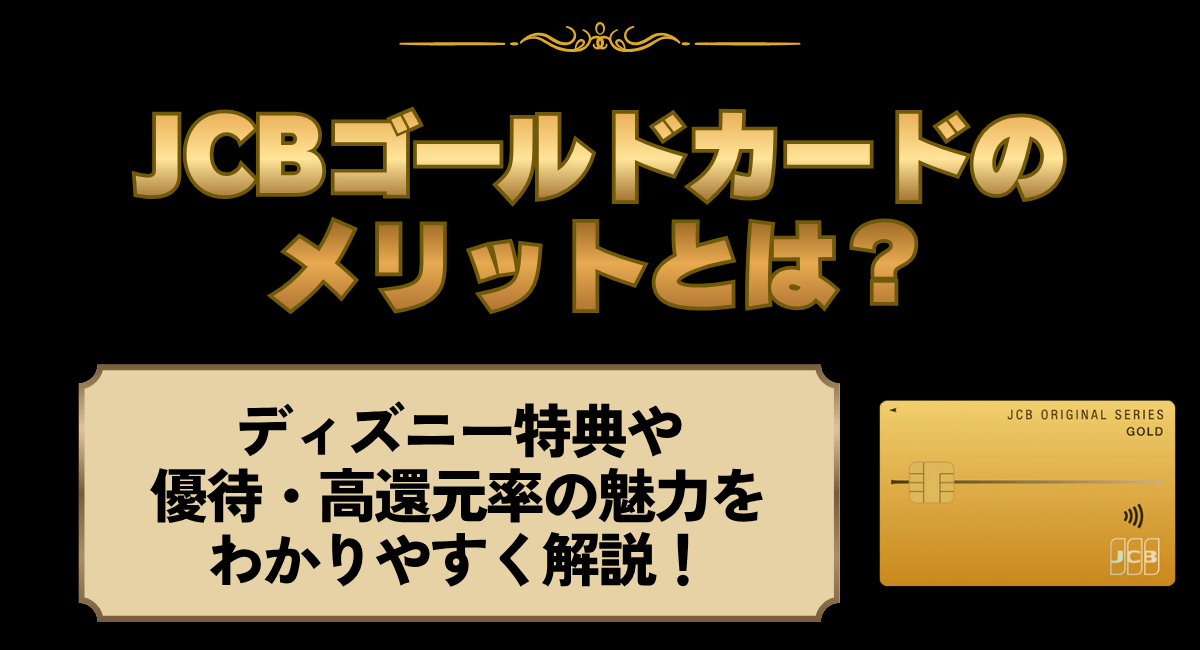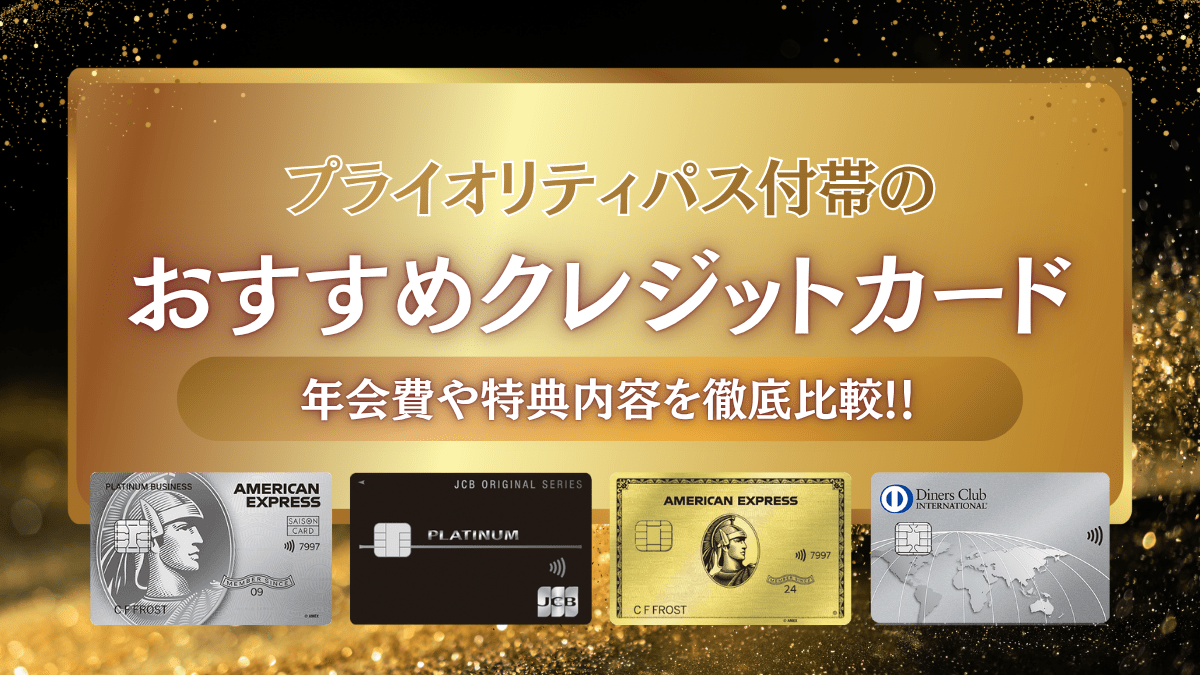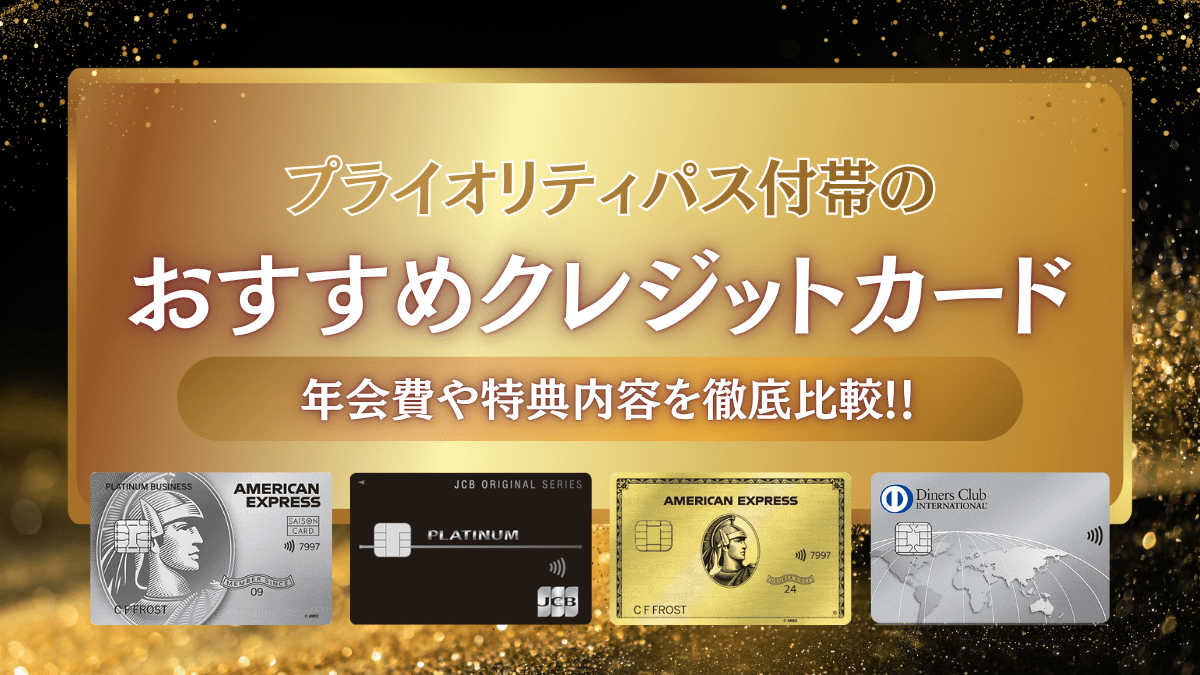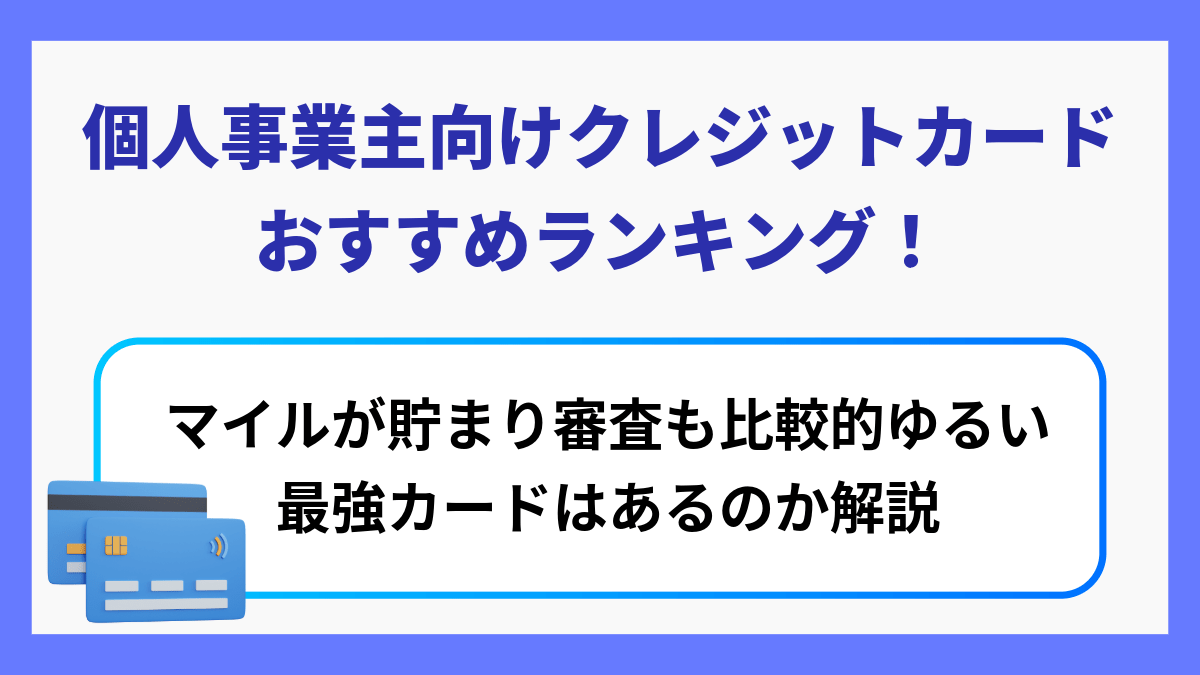「現金がなくなる日」は来るのでしょうか。その鍵を握るのが、日本銀行も準備を進める中央銀行デジタル通貨(CBDC)です。このデジタル通貨には、便利なメリットだけでなく、プライバシーに関わるデメリットも存在します。
日本でも実験が進むCBDCは、私たちの生活や経済活動にどのような影響をもたらすのでしょうか。国家が価値を保証するデジタル通貨の本質を理解することは、未来のお金の形を選択するために欠かせません。
目次
中央銀行デジタル通貨(CBDC)とは

中央銀行デジタル通貨(CBDC:Central Bank Digital Currency)は、各国の中央銀行が発行するデジタル形式の法定通貨です。日本銀行では、CBDCを次の3つの条件を満たすものと定義しています。
- デジタル化されている
- 円などの法定通貨建て
- 中央銀行の債務として発行される
これらの特徴により、CBDCは現金と同様に法定通貨としての地位を持ちながら、物理的な紙幣や硬貨ではなく、電子的なデータとして存在します。
このCBDCが世界中で急速に検討されるようになった背景には、
- 社会全体のデジタル化の進展
- 民間企業によるデジタル通貨の台頭
といった要因があります。特に大きな契機となったのは、2019年にフェイスブック(現メタ)が発表したグローバルなデジタル通貨構想「リブラ」です。
これは国境を越える巨大な通貨圏が誕生する可能性を示し、各国の通貨主権や金融政策への影響、さらにはプライバシー保護やマネーロンダリング対策といった課題への懸念を呼び起こしました。これに加え、中国が開発を進める「デジタル人民元」の存在も、各国のCBDC研究を加速させる大きな要因となっています。
国際決済銀行(BIS)が2024年に実施した調査によれば、世界93カ国・地域の中央銀行のうち91%がリテールCBDC、ホールセールCBDC、またはその両方について何らかの研究・実証に取り組んでおり、世界的な潮流となっていることが明らかです。
CBDCの主要な2つの形態:ホールセール型とリテール型
CBDCは、その利用対象者によって大きく「ホールセール型」と「リテール型」(一般利用型)の2つに分類されます。それぞれの目的や仕組みは大きく異なり、金融システムにおいて異なる役割を果たします。
①ホールセール型CBDC
ホールセール型CBDCは、中央銀行と中央銀行に口座を持つ金融機関との間の資金移動にのみ用いられる、いわば業務用のCBDCです。主な目的は、金融機関同士が行う国債や証券といった大規模な取引決済を、より速く、安全に、そして低コストで行うことにあります。
金融システムの基盤を強化する役割が期待されており、2024年の調査では先進国を中心にホールセール型への関心が高まっている傾向が見られます。
②リテール型CBDC
リテール型CBDCは、個人や一般企業など、幅広い利用者が日常的な支払いや送金に使えるCBDCです。「デジタル現金」として、私たちがスマートフォンなどを通じて利用することが想定されています。
2020年10月に世界で初めて導入されたバハマの「サンドダラー」や、中国で実証実験が進むデジタル人民元もこのリテール型にあたります。バハマでは、700以上の島々からなる国土で銀行へのアクセスが困難な住民に金融サービスを提供する手段として、また、ハリケーンなどの自然災害時にも利用可能な決済インフラとして導入されました。
リテール型CBDCは、さらに「直接型」と「間接型」(二層構造)に分けられます。直接型は中央銀行が発行から取引処理まで直接行う方式ですが、中央銀行の業務範囲が大幅に拡大し、民間銀行の役割を低下させるリスクがあります。そのため、多くの国では間接型が検討されています。
二層構造による発行・流通の仕組みと民間サービスとの決定的な違い
日本を含む多くの国で検討されているCBDCの発行・流通は、現金と同様の「二層構造」を前提としています。この仕組みでは、以下のように、中央銀行と民間の仲介機関がそれぞれ役割を分担します。
- 仲介機関が自らの中央銀行当座預金を減額し、それと引き換えに中央銀行からCBDCが発行されます。
- 利用者は仲介機関に現金や預金を預け、それと交換する形でCBDCの払出を受けます。
- 払出されたCBDCは、店舗での支払いや個人間送金など、利用者間で移転します。
- そして仲介機関がCBDCを受け入れると、それは中央銀行当座預金と引き換えに還収されます。
中央銀行は基礎的な決済手段であるCBDCを発行し、台帳の管理・運営を担う一方、仲介機関は顧客管理やウォレット提供など、利用者に対する直接的なサービスを提供します。さらに民間事業者は、CBDCを土台として家計簿サービスやプログラマブルな決済(特定の条件が満たされた時に自動的に支払いが実行される仕組み)など、ユーザーのニーズに応じた多様な追加サービスを開発できます。
このプログラマビリティ機能により、例えば企業間取引における納品と同時の自動決済や、寄付金の使途制限といった、従来の現金ではできなかった新しい決済の形が実現可能になります。
電子マネーとの違い
CBDCと既存の電子マネーとの決定的な違いは、その「発行主体と信用の裏付け」にあります。
- 電子マネー:民間企業が発行するサービスであり、私たちがチャージしたお金は法的にはその企業に対する債権です。万が一、発行元の企業が破綻した場合、その価値が完全に保証されるとは限りません。
- CBDC:中央銀行が直接発行し、その債務として位置づけられます。これは私たちが使う現金(日本銀行券)が日本銀行の負債であることと同じで、国がその価値を保証することを意味します。
この「中央銀行による信用の裏付け」が、民間デジタル通貨との最も本質的な違いであり、CBDCが「第三の通貨形態」と呼ばれる理由です。
こうした役割分担により、公共財としての安定性を確保しつつ、民間のイノベーションを促進する設計が実現されます。CBDCは既存の通貨システムを置き換えるのではなく、現金や銀行預金と共存する新たな選択肢として、私たちの決済手段を豊かにすることが期待されています。*1)
中央銀行デジタル通貨と仮想通貨の違い

デジタル通貨という言葉を聞くと、ビットコインやイーサリアムといった仮想通貨(暗号資産)を思い浮かべる方も多いでしょう。しかし、CBDCと仮想通貨は、同じ「デジタルなお金」でありながら、その本質は根本的に異なります。
この章では、CBDCと仮想通貨を区別する重要なポイントを、3つの観点から見ていきましょう。
①発行主体と法的地位:国家の信用か、技術への信頼か
最も根本的な違いは、「誰が発行し、何がその価値を保証するのか」という点にあります。
CBDCの発行主体
CBDCは、日本銀行やイングランド銀行のような各国の中央銀行が発行する法定通貨のデジタル版です。現金(紙幣や硬貨)と同じく、国家の信用を裏付けとして発行され、中央銀行の債務として位置づけられます。
そのため、10ポンドのCBDCの価値は10ポンドの紙幣と完全に等しく、法定通貨としての「強制通用力」を持ちます。これは法律上、債務の弁済時に受取人が原則として拒否できないことを意味し、CBDCは現金と同等の法的地位を持つ最も信頼性の高い決済手段となります。
仮想通貨の発行主体
一方、仮想通貨は2008年にサトシ・ナカモトという匿名の人物(あるいは集団)が提唱したビットコインに代表されるように、特定の中央管理者が存在しません。ブロックチェーン技術を用いた分散型の仕組みで運営され、国家による価値の保証はなく、法的な強制通用力も持ちません。
その価値は、
- 改ざんが困難な暗号技術
- 利用するコミュニティの信頼
- 市場での需給関係
によって支えられています。決済を受け入れるかどうかは個人や店舗の自由な判断に委ねられており、多くの店舗では受け付けていないのが現状です。
国際決済銀行(BIS)と主要7カ国の中央銀行が共同で公表した報告書では、「CBDCは暗号資産ではない。暗号資産は中央銀行によって発行されておらず、変動が非常に大きくなりうるほか、現在決済に広く用いられてはいない」と明確に区別されています。
②価値の安定性と主な利用目的:決済手段か、投資対象か
価値が安定しているかどうかも決定的な違いであり、日常での使いやすさに直結する重要な要素です。
CBDCの価値の変動
CBDCは自国の法定通貨と常に1対1の価値を保つように設計されています。
- 「1デジタル円=1円」
- 「1デジタルドル=1ドル」
のように価値が固定されているため、デジタルと現金の間で価格が変動することはありません。そのため、日々の買い物や給与の受け取り、家賃の支払いといった日常的な取引に安心して利用できる、安定した「決済手段」としての役割が期待されています。
仮想通貨の価値の価値の変動
これに対して、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨は、暗号資産取引所における需要と供給によって価格が常に大きく変動します。短期間で大きく値上がりすることもあれば、急落することもあり、このボラティリティ(価格変動幅)の大きさから、仮想通貨は決済手段というより「金融商品」「投資・投機対象」として主に扱われているのが現状です。
店舗での支払いに使おうとしても、価格変動リスクから受け入れている店舗は限定的です。
一例として、2021年にエルサルバドルがビットコインを法定通貨に採用しましたが、価格変動の激しさや技術的な課題から国民の間での普及は限定的であり、国際通貨基金(IMF)からも懸念が表明されています。2024年12月には、IMFから14億ドルの融資を受ける条件として、ビットコインの利用拡大策を見直すことに合意しました。
また、両者の中間に位置するのが「ステーブルコイン」です。民間企業が発行し、米ドルなどの法定通貨を裏付けとすることで価格の安定を目指すデジタル通貨で、CBDCと一般的な仮想通貨の特性を併せ持つ存在として注目されています。
③管理システムと利用目的:公共インフラか、自由な取引の追求か
技術的な仕組みと、それぞれが目指す目的の面でも明確な違いがあります。
CBDCの管理システム
CBDCは、中央銀行がシステム全体の発行・管理を担う「中央集権型」の仕組みです。技術的には必ずしもブロックチェーンに基づくものではなく、より伝統的な中央集権型の技術でも構築できます。
日本銀行が公表した資料によれば、「ブロックチェーン技術の基本的な組織原則は、システム内に信頼できる主体が存在しないというものだが、CBDCシステムでは、発行主体としての中央銀行がCBDCの保有者から暗黙の信頼を得ている」とされています。重要なのは、
- 金融システムの安定性
- 決済の効率性
- 利用者のプライバシー保護
- 金融包摂の促進
といった公共政策上の目的を達成することを最優先とする点です。社会全体の利益を重視した「公共インフラ」として、既存の金融システムを補完・強化する役割が期待されています。
仮想通貨の管理システム
仮想通貨は、参加者全員が同じ取引記録を共有するブロックチェーン技術を基盤とした「分散型」の仕組みです。ビットコインは「プルーフ・オブ・ワーク(PoW)」というコンセンサスアルゴリズム※を採用し、膨大な計算作業を行う「マイニング」で取引を検証します。
イーサリアムは「スマートコントラクト」※と呼ばれる自動実行プログラムの基盤として、分散型金融(DeFi)やNFT市場などの新しいサービスを可能にしています。特定の管理者に依存せず国境を越えた自由な取引を目指す一方、
- 取引の確定に時間がかかる
- 多大な電力を消費する
- 詐欺被害に遭っても救済の仕組みが限定的
といった課題も抱えています。
このように、CBDCは国家が発行・管理する安定した法定通貨であり、既存の金融システムを補完する公共インフラとして設計されています。対照的に、仮想通貨は民間の技術革新から生まれた実験的なデジタル資産であり、現状では投資対象としての性格が強く、決済手段としては限定的な利用にとどまっています。それぞれの特性を理解し、目的に応じて適切に選択することが、今後のデジタル社会において重要となるでしょう。*2)
中央銀行デジタル通貨(CBDC)のメリット

各国がCBDCの導入を検討する背景には、既存の現金や決済システムが抱える課題を解決し、デジタル社会にふさわしい金融インフラを構築するという明確な目的があります。CBDCがもたらす恩恵は多岐にわたり、国際通貨基金(IMF)もその可能性を指摘しています。
CBDCが社会に提供する主なメリットを具体的に見ていきましょう。
決済の効率化と社会的コストの削減
CBDCがもたらす最も直接的なメリットは、決済システム全体の効率化と、現金流通に伴う膨大な社会的コストの削減です。
現在、現金の製造や輸送、ATM網の維持管理には多くのコストがかかっています。経済産業省の試算によれば、この現金インフラの社会コストは年間約2.8兆円にも上ります。CBDCが普及すれば、こうした物理的な現金の取り扱いに関わるコストを大幅に削減できる可能性があります。
また、銀行の営業時間に関わらず24時間365日、ほぼリアルタイムでの送金や決済が可能となり、企業や個人の経済活動をより円滑にします。
さらに、CBDCは「プログラマビリティ」という特性を持つことで、これまでにない革新的なサービスを生み出すと期待されています。これは、お金に「特定の条件が満たされたら自動的に支払う」といったプログラムを組み込める機能です。
例えば、企業間の取引で「商品が納品された瞬間に代金が自動で支払われる」といった仕組みを構築し、支払いの遅延や未払いを防ぐことができます。
金融包摂(ファイナンシャル・インクルージョン)の促進
CBDCのもう一つの重要なメリットは、「金融包摂」を促進する点にあります。金融包摂とは、年齢や地域、経済状況にかかわらず、誰もが必要な金融サービスにアクセスできる状態を目指す考え方です。
世界銀行によれば、世界には依然として約14億人もの銀行口座を持てない成人が存在します。CBDCは、スマートフォンさえあれば銀行口座がなくても安全に利用できるため、こうした人々に金融サービスへの扉を開きます。
実際に、世界で初めてCBDCを導入したバハマの「サンドダラー」は、700以上の島々からなる国土において銀行サービスが行き届かない人々へ金融アクセスを提供することが、導入の大きな目的の一つでした。また、政府からの給付金をCBDCで直接配布すれば、銀行口座を持たない人々にも迅速かつ確実な支援を届けることが可能になります。
国際送金の改善と効率化
国際決済銀行(BIS)の報告では、国際送金の平均コストは送金額の約6.3%に達しています。現在の国際送金は、複数の仲介銀行を経由するため、手数料が高額で、着金までに数日かかるという大きな課題を抱えています。
国際決済銀行(BIS)などが主導する実証実験「プロジェクトmBridge」では、各国のCBDCを直接連携させることで、国際送金のコストを最大で半減させ、時間も数秒に短縮できる可能性が示されています。これが実現すれば、海外で働く人々から本国の家族への仕送りや、企業間の貿易決済などが、より安く、速く、安全に行えるようになります。
透明性の向上と不正行為の抑制
CBDCは、適切な設計により、資金の流れの透明性を高め、違法な活動を抑制する効果も期待されています。
匿名性の高い現金は、マネーロンダリング(資金洗浄)や脱税といった不正行為に利用されやすい側面があります。CBDCはデジタルデータであるため、取引記録を追跡しやすく、違法な資金の流れを特定しやすくなります。
これらのメリットは、社会全体の経済的な発展に寄与することが期待されますが、導入には課題やリスクも存在するため、次章ではデメリットについて詳しく見ていきます。*3)
中央銀行デジタル通貨(CBDC)のデメリット
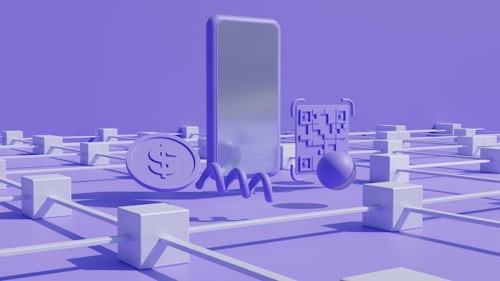
多くのメリットが期待されるCBDCですが、導入にあたっては慎重に検討すべき課題やリスクも存在します。国際決済銀行(BIS)も「CBDCの金融安定上の含意は、慎重に検討される必要がある」と指摘しており、慎重な検討が必要です。
プライバシー保護と国民監視への懸念
CBDCの導入で最も懸念されるのが個人のプライバシー保護です。取引記録がデジタルデータとして残るため、現金が持つ匿名性が失われ、「いつ、誰が、何に」お金を使ったかという情報が国家に把握される可能性があります。
これは、国民の経済活動への過度な監視に繋がりかねないという深刻な懸念を生みます。特に権威主義的な国家においては、CBDCが国民監視の道具として利用されるリスクが指摘されています。
実際に、ナイジェリアのイーナイラでは、ユーザーの層に応じて1日の取引限度額や保有できる額に上限が設定されており、政府が日常的な金融取引に制限を課すこともできるという事実は、個人のプライバシーや自由を大幅に損なう可能性があると指摘されています。この課題に対し、多くの国では小額決済では匿名性を保ち、高額決済になるほど本人確認を厳格にする「段階的な匿名性」の導入が検討されていますが、プライバシーと安全性のバランスは極めて重要な論点です。
デジタル取り付けと金融システムの不安定化リスク
CBDCの導入が、金融システムを不安定化させる可能性も指摘されています。特に懸念されるのが「デジタル取り付け(デジタル・バンクラン)」のリスクです。経済不安が高まると、人々がより安全なCBDCを求め、銀行預金をスマートフォンから一斉かつ瞬時に引き出す事態が起こり得ます。
2023年の米シリコンバレーバンク破綻では、わずか1日で預金全体の24%にあたる約420億ドルが引き出され、デジタル環境下で預金が極めて急速に流出したことが混乱を加速させました。
このような預金の大量流出は、銀行の融資機能(金融仲介機能)を低下させ、経済全体に深刻な影響を及ぼすリスクがあります。この問題に対処するため、多くの中央銀行はCBDCの保有上限を設定するなどの対策を検討しています。
サイバー攻撃や災害時の脆弱性
デジタル通貨であるCBDCは、サイバー攻撃や自然災害に対する脆弱性も課題です。国家の通貨システムはサイバー攻撃の格好の標的となり、もし攻撃が成功すれば経済に壊滅的な打撃を与えかねません。
また、地震や台風などによる大規模な停電や通信障害が発生した場合、CBDCが使えなくなるという脆弱性も指摘されています。こうした事態に備え、オフラインでも利用できる機能の開発が重要な課題となっていますが、オフライン機能を拡大するとセキュリティ上の新たなリスクも生じます。
このため、多くの中央銀行は、CBDCを導入しても現金を廃止せず、両者を併存させる方針を明確にしています。
これらのデメリットは、CBDC導入の可否や設計を検討する上で避けて通れない課題です。メリットとデメリットを慎重に比較検討し、適切な制度設計とセキュリティ対策を講じることで、リスクを最小化しながらCBDCの利点を最大限に活かす取り組みが、世界各国で進められています。*4)
世界における中央銀行デジタル通貨(CBDC)の導入状況

中央銀行デジタル通貨(CBDC)を巡る動きは世界中で前進し、理論から実践の段階へと確実に移行しています。2025年7月時点で世界の137カ国が何らかの形で関与し、G20諸国はすべて開発・研究に着手しています。
ただし、その進捗や目的は各国の事情に応じて大きく異なっています。ここでは、世界の潮流を理解するため、特に動きの活発な国々の状況を見ていきましょう。
導入・実用化フェーズの国々
一部の新興国では、国内の課題解決のため、すでにCBDCが正式に導入・運用されています。
- バハマ(サンドダラー): 2020年に世界で初めて導入。700以上の島々からなる国土で、銀行サービスが行き届かない住民への金融アクセス提供(金融包摂)を主な目的としています。
- ジャマイカ(ジャムデックス): 2022年に導入。金融包摂のため、銀行口座を持たない国民でも利用しやすい簡素化された本人確認を特徴としています。
- ナイジェリア(イーナイラ): 2021年にアフリカ初のCBDCとして導入。成人の銀行口座保有率が低いという課題の解決を目指しています。
また、主要国の中で突出して先行しているのが中国です。「デジタル人民元(e-CNY)」は世界最大規模のパイロットプロジェクトを展開しており、2024年6月までの取引総額は約9,860億ドルに達するなど、日常の幅広い場面で実際に利用されています。
実証実験・準備フェーズの主要国
多くの先進国や新興大国は、実用化を視野に入れた大規模な実証実験や、導入に向けた準備の段階にあります。
欧州中央銀行(ECB)は、「デジタルユーロ」について2029年頃の導入を現実的な目標として示し、現在はルール策定やシステム開発を行う準備段階にあります。民間企業とも協力し、公共交通機関での自動決済といった具体的な利用方法の検証を進めています。
インドも、「デジタルルピー」のリテール版とホールセール版の両方でパイロット運用を行っています。特に、広大な国土での金融包摂を実現するため、インターネットに接続できない環境でも利用できるオフライン決済機能の開発を重要な課題として位置づけています。
このように、世界各国は金融包摂や決済の効率化といった、それぞれの経済状況や社会課題に応じたCBDCの設計と導入を進めており、この動きは今後さらに加速していくことが予想されます。*5)
日本における中央銀行デジタル通貨(CBDC)の導入状況

2025年5月時点で、日本におけるCBDCの取り組みは慎重かつ段階的に進められています。日本銀行は「現時点でCBDCを発行する計画はない」としつつも、将来の環境変化に備える重要性を強調しています。
政府も制度設計の議論を深めており、技術と制度の両面から準備が着実に進んでいます。ここでは、日本の最新状況を2つの側面から見ていきましょう。
日本銀行によるパイロット実験の進展
日本銀行は、CBDCの技術的な実現可能性を探るため、2021年4月から実証実験を進め、2023年4月からはより実践的な「パイロット実験」に移行しています。
この実験では、実験用システムを構築して大規模取引への耐性を検証するとともに、「CBDCフォーラム」という場で民間企業と具体的な課題を議論しています。フォーラムは7つのワーキンググループに分かれ、
- KYC(本人確認)のあり方
- 既存の決済サービスとの共存
- スマートフォンやカードといった利用手段
など、実用化を見据えた幅広いテーマが話し合われています。プライバシー保護の観点から、日本銀行が個人の取引情報を直接扱わないシステム設計を前提としている点も大きな特徴です。
政府による制度設計の検討と主な課題
技術検証と並行して、政府もCBDCを社会に導入する場合の法律やルール作り(制度設計)の検討を進めています。財務省を中心とした関係省庁と日本銀行による連絡会議は、2025年5月に「第2次中間整理」を公表しました。主な論点は以下の3つです。
- 法律上の位置づけ:CBDCを法貨(法定通貨)として現金と同等に扱うための法的整理。
- プライバシー保護とAML/CFT:個人のプライバシーを守りつつ、マネーロンダリング・テロ資金供与対策といった公的要請への対応を両立させる仕組み。
- 民間決済サービスとの役割分担:すでに普及している多様なキャッシュレス決済と、どのように共存・連携していくか。
主な課題
発行に向けた主な障壁としては、
- 法整備の複雑さ
- 銀行預金流出など金融システムへの影響
- 災害時の可用性確保
が挙げられます。これらの議論は将来導入する場合の「たたき台」であり、現時点で導入を決定したものではありません。日本銀行の植田和男総裁も「CBDCの発行については、利便性向上などのメリットが、必要な社会的コストの見込みを上回ることが不可欠」と慎重な姿勢を示しています。
CBDCが社会にもたらす便益と課題を見据えた国民的な議論が、今後ますます重要となるでしょう。*6)
中央銀行デジタル通貨(CBDC)とSDGs

CBDCの導入は、金融サービスへの平等なアクセスを実現し、経済的機会を拡大するという点でSDGsの理念と共通しています。誰もが安全な決済手段を利用できる環境を整備することは、貧困削減や格差是正といった持続可能な開発の基盤となります。
CBDCが特に貢献できる3つのSDGs目標について見ていきましょう。
SDGs目標1:貧困をなくそう
CBDCは、銀行口座を持てずに金融システムから排除されてきた世界約14億人の人々に、安全な決済手段を提供します。スマートフォンなどを通じて政府の給付金を直接受け取ったり、安全に貯蓄したりできるようになることは、貧困から抜け出すための経済的基盤を築く上で極めて重要です。
これにより、人々は教育や小規模ビジネスへの投資機会を得やすくなり、経済的自立への道が開かれます。
SDGs目標8:働きがいも経済成長も
CBDCは、決済インフラを効率化することで、中小企業の取引コストを削減し、経済活動を活性化させます。特に、国際送金の手数料を大幅に引き下げる可能性は、海外で働く人々が本国の家族へ送金する際の負担を軽減し、開発途上国の経済を支えます。
G20は2024年までにクロスボーダー送金のコスト削減目標を設定しており、CBDCを活用した国際決済の効率化がその実現に重要な役割を果たします。また、契約と支払いを自動化する「プログラマビリティ」機能は、企業間取引の効率を高め、新たなビジネス創出にも繋がります。
SDGs目標10:人や国の不平等をなくそう
現在の金融システムでは、身分証明や最低預金額といった障壁が、低所得層や地方居住者など、特定の人々のアクセスを阻んでいます。CBDCはこれらの障壁を低減し、性別、年齢、地域、経済状況に関わらず、誰もが平等に金融サービスを利用できる環境を整えます。
G7の公共政策原則でも、「CBDCは金融包摂を促進し、デジタル決済のための公共インフラとして、格差への対処に向けた民間部門のイノベーションを促進するように設計されるべき」と明記されており、経済的な不平等の是正に大きく貢献することが期待されています。*7)
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ

中央銀行デジタル通貨(CBDC)は、国家が価値を保証する「第三の通貨形態」として、決済の効率化や金融包摂といった社会課題を解決する大きな可能性を秘めています。一方、その導入は単なる技術革新に留まらず、プライバシーや金融システムの安定性といった根幹を揺るがしかねない課題も抱えています。
世界は今、大きな転換期にあります。日本政府が「骨太の方針2025」で法制度の検討を明記し準備を具体化する一方、米国では民間発行のステーブルコインを優先する議論が強まるなど、各国の戦略は一つではありません。
この多様なアプローチは、CBDCを巡る国際的な協調と競争が同時に進行していることを示しており、今後の焦点は、個人の自由と社会の安全を両立させる国際的なルールをいかに構築していくかにあります。
このような知識は、個人にとっても、未来のお金、さらに社会の形を選択するための指針となります。私たち一人ひとりが、その利便性とリスクを理解し、議論に参加することが求められます。
あなたは、利便性と引き換えに、自身の購買情報がどこまで利用されることを許容できますか。そして、新しいデジタル通貨は、本当に「誰一人取り残さない」金融システムを実現できるでしょうか。
デジタル時代の通貨のあり方は、私たちの未来を大きく左右します。今こそ関心を持ち、学び、そしてより良い未来のために何を選択すべきか、考えるときです。*8)
<参考・引用文献>
*1)中央銀行デジタル通貨(CBDC)とは
日本銀行『中央銀行デジタル通貨について知っておきたいこと』(2024年3月)
日本銀行『中央銀行デジタル通貨:基本的な原則と特性』(2020年10月)
財務省『CBDC(中央銀行デジタル通貨)に関する関係府省庁・日本銀行連絡会議 第2次中間整理について』(2025年5月)
国際通貨研究所『中央銀行デジタル通貨・暗号資産・トークン化 三つの潮流が交差する2024年国際決済銀行アンケート調査結果』(2025年10月)
Japan Business Press『ステーブルコイン「リブラ」撤退、米メタの決断の背景』(2022年2月)
*2)中央銀行デジタル通貨と仮想通貨の違い
金融庁『G7 英国 2021年 リテール中央銀行デジタル通貨(CBDC)に関する公共政策上の原則(仮訳)』(2021年10月)
JRI『デジタル・マネーの普及がもたらす銀行システムへの波紋』(2022年)
Monex『CBDC(中央銀行デジタル通貨)とは?仮想通貨やブロックチェーンとの関係を解説』(2025年7月)
三井住友フィナンシャルグループ『ブロックチェーンとは?その仕組みや技術、活用分野などを解説』(2024年10月)
*3)中央銀行デジタル通貨(CBDC)のメリット
国際通貨基金『CBDCの台頭』(2022年9月)
国際通貨基金『Technology Solutions to Support Central Bank Digital Currency with Limited Connectivity: A Review of Existing Approaches』(2025年8月)
日本銀行『CPMI等共同報告書「クロスボーダー送金のためのCBDCへのアクセスおよび相互運用性の確保に向けた選択肢」の公表について』(2022年7月12日)
日本銀行『中央銀行デジタル通貨に関する日本銀行の取り組み方針』(2020年10月)
日本銀行『決済システムにおけるプログラマビリティの実現』(2022年6月)
*4)中央銀行デジタル通貨(CBDC)のデメリット
財務省『CBDC(中央銀行デジタル通貨)に関する関係府省庁・日本銀行連絡会議』(2024年4月)
帝国データバンク『CBDC(中央銀行デジタル通貨)とデータ保護・プライバシー問題』(2024年7月)
コインテレグラフ『【論説】中央銀行デジタル通貨は個人のプライバシーと自由を脅かす恐れ』(2023年4月)
大和総研『日本版CBDCを先読みするための7つの論点』(2022年6月)
東洋経済オンライン『取り付けでスピード破綻するのは特別な銀行か シリコンバレー銀の破綻が示す新たなリスク』(2023年3月)
*5)世界における中央銀行デジタル通貨(CBDC)の導入状況
FIDX『【2025年最新】CBDCを巡る米・中・欧の思惑と日本の立ち位置』(2025年8月)
日本総合研究所『中央銀行デジタル通貨(CBDC)の国際的な検討状況 ~先進国においてホールセール型の検討が先行する一方、リテール型は大きく進展せず~』(2025年9月)
国立印刷局 CBDC 研究会『中央銀行デジタル通貨(CBDC)に関するレポート (令和4年度)』(2023年6月)
コインテレグラフ『ジャマイカのタクシーやバス会社 CBDC「ジャムデックス」導入へ』(2023年8月)
電通総研『中国発・次世代金融インフラの実像:デジタル人民元最前線』(2025年6月)
*6)日本における中央銀行デジタル通貨(CBDC)の導入状況
日本銀行『中央銀行デジタル通貨に関する実証実験「パイロット実験」の進捗状況』(2025年5月)
財務省『CBDC(中央銀行デジタル通貨)に関する関係府省庁・日本銀行連絡会議 第2次中間整理』(2025年5月)
日本経済新聞『日銀総裁、デジタル円導入は「国民的議論で決まるべき」』(2024年3月)*7)中央銀行デジタル通貨(CBDC)とSDGs
金融庁『G7 英国 2021年 リテール中央銀行デジタル通貨(CBDC)に関する公共政策上の原則(仮訳)』(2021年10月)
CGAP『持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けて:金融包摂の役割』(2016年4月)
日本総合研究所『デジタル金融包摂や金融ウェルビーイングを促進するASEAN諸国』(2024年)
UNDP『Inclusive and future-smart public goods and services』
*8)まとめ
国際通貨研究所『デジタル通貨の現状と今後の展望~CBDC、Tokenized Deposit、Stable Coin~』(2025年4月)
野村総合研究所『米国で進むステーブルコインの規制整備(7):世界のCBDC開発の現状』(2025年8月)
NEC『通貨主権を懸けた欧州中央銀行(ECB)の戦い』(2025年10月)
日本経済新聞『中央銀行デジタル通貨とは 世界の中銀の9割が研究』(2024年4月)
この記事を書いた人
松本 淳和 ライター
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。