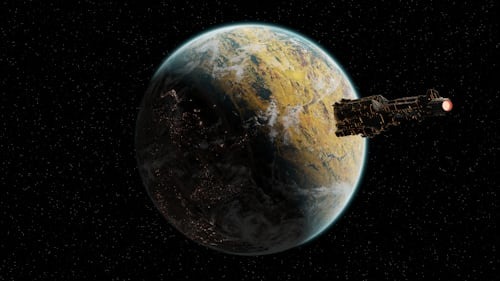みなさんはデフリンピックという大会をご存じでしょうか。おそらく多くの方は知らないか、何となく聞いたことがあるくらいではないかと思います。
今回の記事では、そんなデフリンピックの概要や歴史、主要な競技などについて紹介していきます。デフリンピックについての知識を深めることで、ろう者スポーツの意義を知り、開幕を目前に控えた東京大会を応援するきっかけになってもらえればと思います。
目次
デフリンピックとは
デフリンピックとは、デフ(Deaf=耳が聴こえない、聴こえづらい人)のオリンピックのことであり、国際ろう者スポーツ委員会(CISS:仏語/ICSD:英語)の主催で4年に一度、オリンピックやパラリンピックとは別に行われる、デフアスリート、つまり聴覚障害選手による国際スポーツ大会です。
1949年以降は冬季大会も開催され、オリンピック・パラリンピック同様、夏季大会と冬季大会が交互に行われています。
参加できる選手

デフリンピックに参加できる選手の資格は
両耳の聴力が55dB(通常の会話が困難とされているレベル)以上の聴力損失
のみであり、それ以外のクラス分けは行われません。
同時に、各国のろう者スポーツ協会に登録しており、記録などで出場条件を満たせば出場できます。
デフリンピックでは公平を期するため、試合中・練習中を問わず補聴器や人工内耳の体外パーツを外さなければなりません。
パラリンピックとの違い

同じ障害者スポーツとしてはパラリンピックが良く知られていますが、デフリンピックはパラリンピックとは全く別の大会として開催されています。
そこには参加アスリートの障害の違いだけではなく、運営組織同士の問題、そしてろう者のアイデンティティなども関連しています。
違い①成り立ちの違い
2つの大会はそれぞれ成り立ちに大きな違いがあります。
次の章でも説明しますが、デフリンピックの場合は始まる前からろう者のスポーツ団体がヨーロッパ各国で活動していました。その活動に弾みをつけるために、オリンピックへの関心の高まりを利用して国際大会が開かれたという経緯があります。
まず競技大会ありきで、障害者スポーツ組織の整備は後からなされてきたパラリンピックとは、スタートから異なっていたのです。
違い②運営組織の違い
2つの大会は大会運営組織も違います。
デフリンピックはCISS/ICSD(国際ろう者スポーツ委員会)が開催しますが、パラリンピックはIPC(国際パラリンピック委員会)が主催します。
両大会が別々に開催されるようになった背景には、CISS/ICSDとICC(障害者スポーツのための国際調整委員会)との意見の相違があります。
1980年代に行われた両者の関係についての協議では
- CISSの立場の違い
- ICCがろう者も含む障害者スポーツ全体の調整役としての立場を主張
- CISS=独自にIOC(国際オリンピック委員会)と協議することに固執
- 財政上の問題:会議での手話通訳費用の負担
- 手話通訳は福祉ではなく社会全体が用意すべき義務というCISS/ICSDの考え方
- デフリンピックとパラリンピックの開催年次の調整問題
などで両者の意見は隔たりを見せます。
そのため1990年にはデフリンピックはパラリンピックとは独自に大会を行うことになり、1995年にCISS/ICSDは正式にIPCのメンバーシップから離脱して現在に至ります。
違い③身体性の問題
パラリンピックとの最も大きな違いとしては、選手の身体性があります。
心身に何らかのハンディがあるパラアスリートと違い、デフアスリートは耳が聴こえない/聴こえづらいこと以外は健常者との違いはほぼありません。
そのため過去には、オリンピックに出場してメダルを獲得したデフアスリートも少なからずおりました。このこともデフリンピックとパラリンピックの違いを決定的なものにしており、同時にデフアスリートの障害者としてのアイデンティティにも影響しています。
デフリンピックの歴史
デフリンピックの歴史は古く、前身となる大会が1924年に開催されてから2024年で100年目を迎えます。
ろう者によるスポーツはそれ以前からヨーロッパを中心に盛んに行われており、1871年にはイギリスで世界初のろう者のスポーツ団体「グラスゴーろうあサッカークラブ」が設立されています。
1924年パリ:国際サイレント大会開催
1924年に、フランス・パリで2人のろう者によってCISS(国際ろう者スポーツ委員会)が設立されます。
これは、同年パリで開催された第8回オリンピックでスポーツへの関心が高まったことがきっかけです。CISSはこの機会を利用して、ろう者のためのスポーツの祭典「国際サイレント大会」をパリで開催します。
9か国から148人が参加したこの大会は、障害のある人が対象の大会としてはパラリンピックより36年早い、世界初の国際大会となりました。
第二次世界大戦後
その後、この国際サイレント大会は第二次世界大戦の時期を除きほぼ4年に一度開催され、
- 1949年:冬季大会(オーストリア・ゼーフェルト)初開催
- 1955年:IOCがCISS/ICSDを「オリンピック資格を持つ国際連盟」と認定
- 1969年:ベオグラード大会から「世界ろう者競技大会」に名称変更
- 1985年以降、IOCは大会を後援
といった経緯をたどりながら発展していきます。
1980年代には、前述の通りCISS/ICSDとICCとの間で、パラリンピックとの関係について協議がもたれましたが合意には至らず、独立した大会となることが決められました。
2001年ローマ大会〜:デフリンピックと名称を変更
2001年のローマ大会から、世界ろう者競技大会は名称をデフリンピックに変更し、現在に至っています。この間には、
- 2006年:CISS/ICSDが世界アンチ・ドーピング機関(WADA)に正式加入
- 2013年:世界ろう連盟(WFD)とCISS/ICSDとの間の協力協定署名
などの出来事がありました。2013年のWFDとの協定では、
- 全国から地域レベルでの国のろう協会と国家ろうスポーツ協会の協力を促進
- 人権の促進および手話の認識への支援の重要性を強調
- WFDとCISS/ICSDの間での公式言語を国際手話と英語に決定
などが定められています。
2024年1月にはブラジル・サンパウロで第1回世界ろう者ユースゲームが開催され、世界16か国・71人の14歳から18歳までの若いデフアスリートが、陸上、バドミントン、3×3バスケットボール、水泳の4競技で参加しています。
デフリンピックの主な競技
現在、デフリンピックでは夏季大会では21競技、冬季大会では6競技が行われています。
それぞれで実施される競技と特徴は以下の通りです。
夏季大会
デフリンピックでは、ほとんどの競技が健聴者と同じ国際ルールに準拠しており、基本的なルールもほぼ変わりません。そのため各競技とも視覚情報をどのように選手に伝えるかがポイントになっています。
| 競技 | 種目 | 視覚情報保障などの特徴 |
| 陸上競技 | トラック | スタートランプ(スタート音を光の合図で知らせる装置)を選手の視線に配置ピストルと連動し、色の変化によって選手に合図し、健聴者と同条件でスタートできる |
| フィールド | ||
| ロード | ||
| 混成競技 | ||
| バドミントン | ダブルスではパートナーの特徴やプレースタイルを深く理解パートナーとの十分な連携確認・戦術の共有などのコミュニケーションが重要 | |
| バスケットボール | フラッグマン=旗を振って審判の笛の音やタイマーの音などを視覚的に表すスタッフ | |
| ビーチバレーボール | 主審や副審がネットを揺らして反則や指示を気づかせる手話言語通訳者をコートサイドに配置 | |
| ボウリング | 投球開始・終了や試合の中断などの情報はモニターで視覚的に伝える | |
| 自転車 | ロード | 旗でスタートを伝えるタイム表示などを目で見てわかるようにする |
| MTB | ||
| サッカー | 選手はピッチ上でアイコンタクトや手話言語を使う主審・副審計5名の審判全員がフラッグを所持、競技中の状況を多方向から選手へ伝達 | |
| ゴルフ | 落雷の危険などプレーの中断や再開時は旗を利用 | |
| ハンドボール | ライトやフラッグは使わず、健聴者同様審判のハンドジェスチャーで合図 | |
| 柔道 | 「待て」などの指示は選手の肩を叩いて知らせる | |
| 空手 | 審判が試合を止める「やめ」の合図はライトを使って視覚的に知らせる | |
| オリエンテーリング | スタートの合図は係員の旗や電光掲示板などで伝える選手がコントロールを通過する際には確認音だけでなく、光でも確認する | |
| 射撃 | 「開始」「止め」などの合図はモニターなどで伝える | |
| 水泳 | スタートランプの色の変化でスタートを合図スタートランプがない大会ではスターターの身振りとシグナル(光合図)を使用 | |
| 卓球 | ダブルスでの戦術確認の際は、相手に背を向けて手話でやり取りをすることが多い | |
| テコンドー | キョルギ(組手) | 「開始」「止め」など選手への合図はランプを用いるなどで視覚的に伝える |
| プムセ(型) | ||
| テニス | 相手が打つボールを目で見ながら反応し攻守に備えるダブルスではポイント毎にサインでポジションや攻守を決めるセルフジャッジはスコアのコールを手や指でカウントを表現する「競技サイン」で行う | |
| バレーボール | 手話言語や読話(唇の動きや表情で状況を推測し、話の内容を読み取る)、手話通訳などでコミュニケーションをとり、アイコンタクトで高度な連携を見せる | |
| レスリング | フリースタイル | 選手へ開始・終了や試合の中断はジェスチャーなどで視覚的に伝える |
| グレコローマン |
デフリンピック特有の競技がボウリングとオリエンテーリングです。
オリエンテーリングは、地図とコンパスを持って、山野の地図上に指定されたチェックポイント(コントロール)を順番に回り、ゴールに着くまでの速さを競う競技です。
自分の歩幅や体感での距離感、地図で進路を選択する決定力や判断力、荒野や湿地などを走る体力がトータルに要求されます。
冬季大会
冬季デフリンピック大会で行われるのは以下の6競技です。
- アルペンスキー
- クロスカントリースキー
- スノーボード
- カーリング
- フットサル
- チェス
2015年のハンティ・マンシースク大会(ロシア)では、日本の花島良子選手がスノーボードのハーフパイプで金メダルを獲得しています。
チェスは日本ではスポーツというよりボードゲームのイメージが強くあると思いますが、多くの国では頭の中で激しく戦うマインドスポーツと考えられています。
2025年は東京で開催

そして今年2025年のデフリンピック夏季大会は東京で開催されます。
東京2025デフリンピックは、1924年にフランスのパリで第1回大会が開催されてから100周年となる記念大会であり、日本での開催は初めてとなります。
東京大会は
- 2025年11月15日~26日(12日間)
- 70~80の国・地域から参加予定
となっており、東京都内17の会場と、静岡県伊豆市(自転車)、福島県楢葉町(サッカー)の会場で行われます。
ボランティアの活動内容と申し込みについて

2021年の東京オリンピックでは、数多くのボランティアが大会の運営を支えました。
今回の東京2025デフリンピックでも同様にボランティアの働きが重要になることは間違いありません。
ボランティアの主な活動内容は、
- 競技会場での選手・関係者や観客の誘導・案内
- 国内外メディア・プレス対応の補助
- 会場内での飲食補充、 IDチェック
- 競技リザルト整理、 表彰状印刷サポート
- 手荷物検査サポート
などです。
東京大会のボランティアは1月31日に募集が終了しており、現在は申し込むことはできません。今大会では3,000人の募集に対して18,903人の応募があり、最終的な当選者は3,500人となっています。
ここでは参考までに、東京大会の応募方法と応募要件について説明していきましょう。
- 応募方法:大会所定のQRコードのWebサイトから申し込む
- 応募要件
- 2025年4月1日時点で満18歳以上
- 活動期間中、日本国籍または日本の滞在資格がある
- 各種研修への参加が可能である
となっています。
応募にあたって特別な資格は必須ではなく、手話やろう者の文化理解などは研修で行われます。とはいえ、当選した3,500人の内訳をみると
- 手話でコミュニケーションが可能:1,641人(うち447人が国際手話が可能)
- 英語で円滑なコミュニケーションが可能:641人
など、手話や英語が使えることが選考に際しては有利に働く可能性はあります。
デフスポーツの課題

東京開催で盛り上がるデフリンピックですが、選手を育成するデフスポーツの現場においては対策が急がれる以下のような課題があります。
- デフスポーツの知名度の低さ→対策:広報活動や報道機会の増加
- 選手・コーチの金銭的負担→対策:報奨金の増額やスポンサーシップの強化
- 体力・技術面や精神面の問題→対策:健聴者との合同練習を増やし強化を図る
- 手話通訳者の問題→対策:専門性を備えた手話通訳者の養成を強化する
- 健聴者とのコミュニケーション
特に手話通訳者の問題は重要です。デフスポーツの手話通訳は、国内/国際手話の技術、競技に関する知識や語学など多岐にわたる資質が要求されます。
さらに手話通訳者は食料の調逹や英訳、連絡事務や選手の生活面のサポートなど、本業以外にもさまざまな業務を課されているのが実情です。
こうした個人的奉仕に依存する状況から、どのように役割分担を明確にできるかも今後の課題と言えましょう。
デフリンピックとSDGs
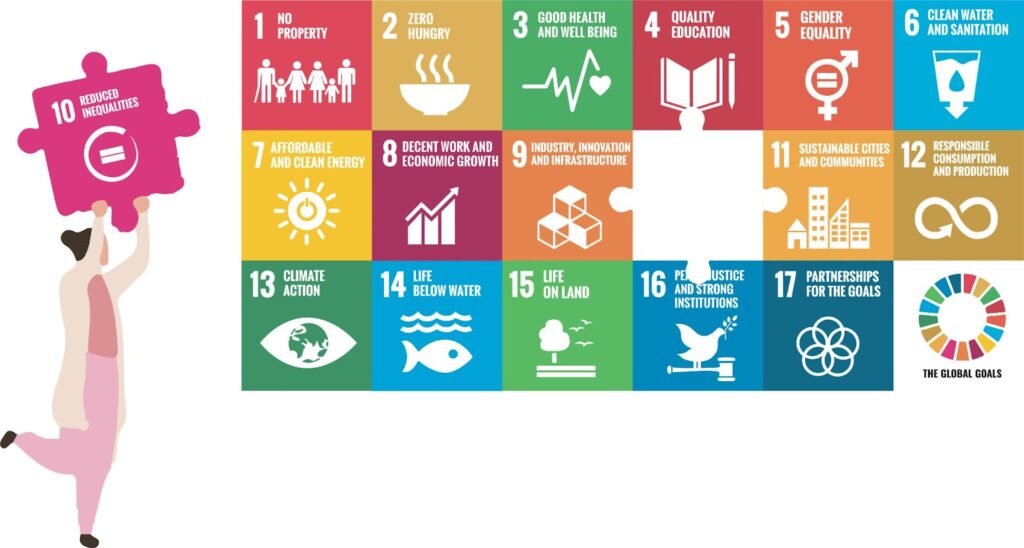
スポーツイベントとしてのデフリンピックは、聴覚障害を持つ人々の心身の健康増進を、スポーツを通じて図るものです。これをSDGs(持続可能な開発目標)との関連で言うと、
目標3「すべての人に健康と福祉を」
の実現を目指すものと言えます。
そして、デフリンピックを開催することは障害、人種、民族、宗教などの違いを超え、参加するすべての人々の能力強化を図ることにつながります。これは「各国内及び各国間の不平等を是正」する
目標10「人や国の不平等をなくそう」
の目標実現と大きく関わってきます。
>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ

デフリンピックはその歴史が古いにもかかわらず、パラリンピックほどには世間で知られていません。しかし、デフスポーツは黎明期から現在に至るまでろう者を中心に運営され、着実に発展を遂げてきました。そこには、ろう者自身の強いアイデンティティに支えられた、社会に対する強い眼差しと確かな自負の念がうかがえます。
今年の東京大会は、デフリンピックの認知度と意義が広く世間に伝わる絶好の機会です。
熱戦を繰り広げる選手たちに、表情や仕草、もちろん声でもエールを送り、共にこの祭典を盛り上げていきましょう。選手たちの姿を通して、多様性と共生の本質をあらためて感じ取ることができるはずです。
参考文献・資料
世界に挑む!デフアスリート : 聴覚障害とスポーツ 森埜こみち著. — ぺりかん社, 2024.
東京2025デフリンピック | TOKYO 2025 DEAFLYMPICS
デフスポーツとデフリンピック Doll-Tepper Gudrun 日本財団パラリンピックサポートセンターパラリンピック研究会紀要 22 (0), 23-47, 2024
デフリンピックの歴史,現状,課題及びパラリンピックとの比較 小倉和夫 日本財団パラリンピックサポートセンターパラリンピック研究会紀要 8 (0), 1-16, 2018
東京2025デフリンピックのボランティアについて|スポーツTOKYOインフォメーション
この記事を書いた人
shishido ライター
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。