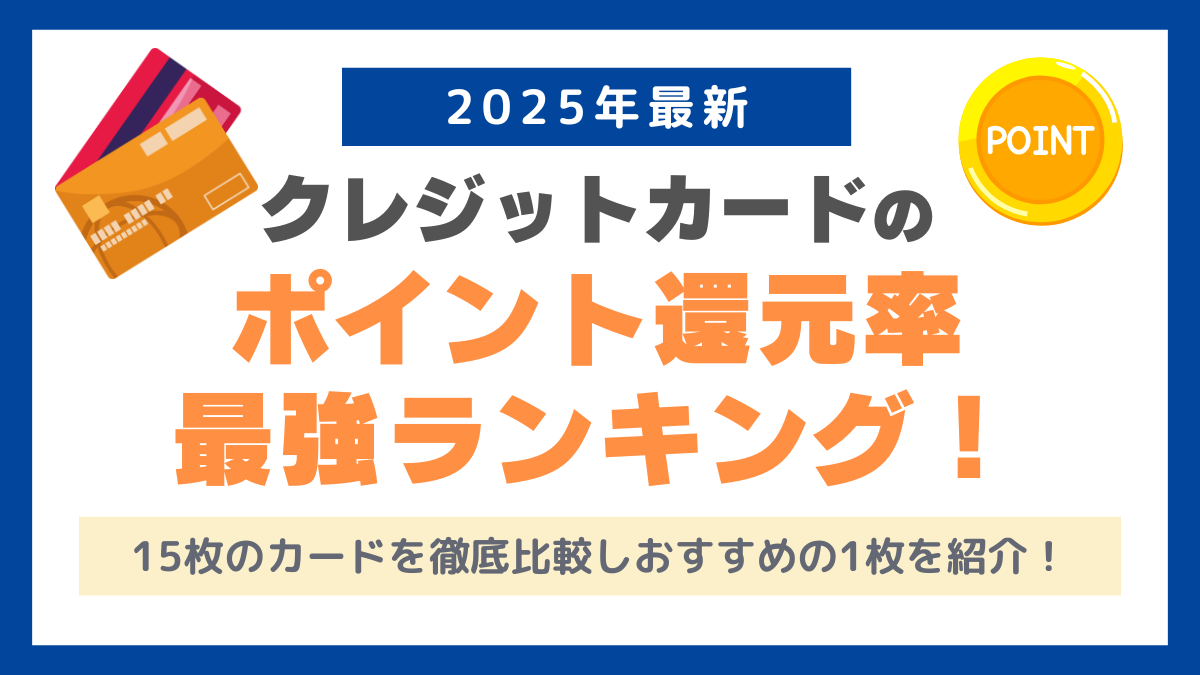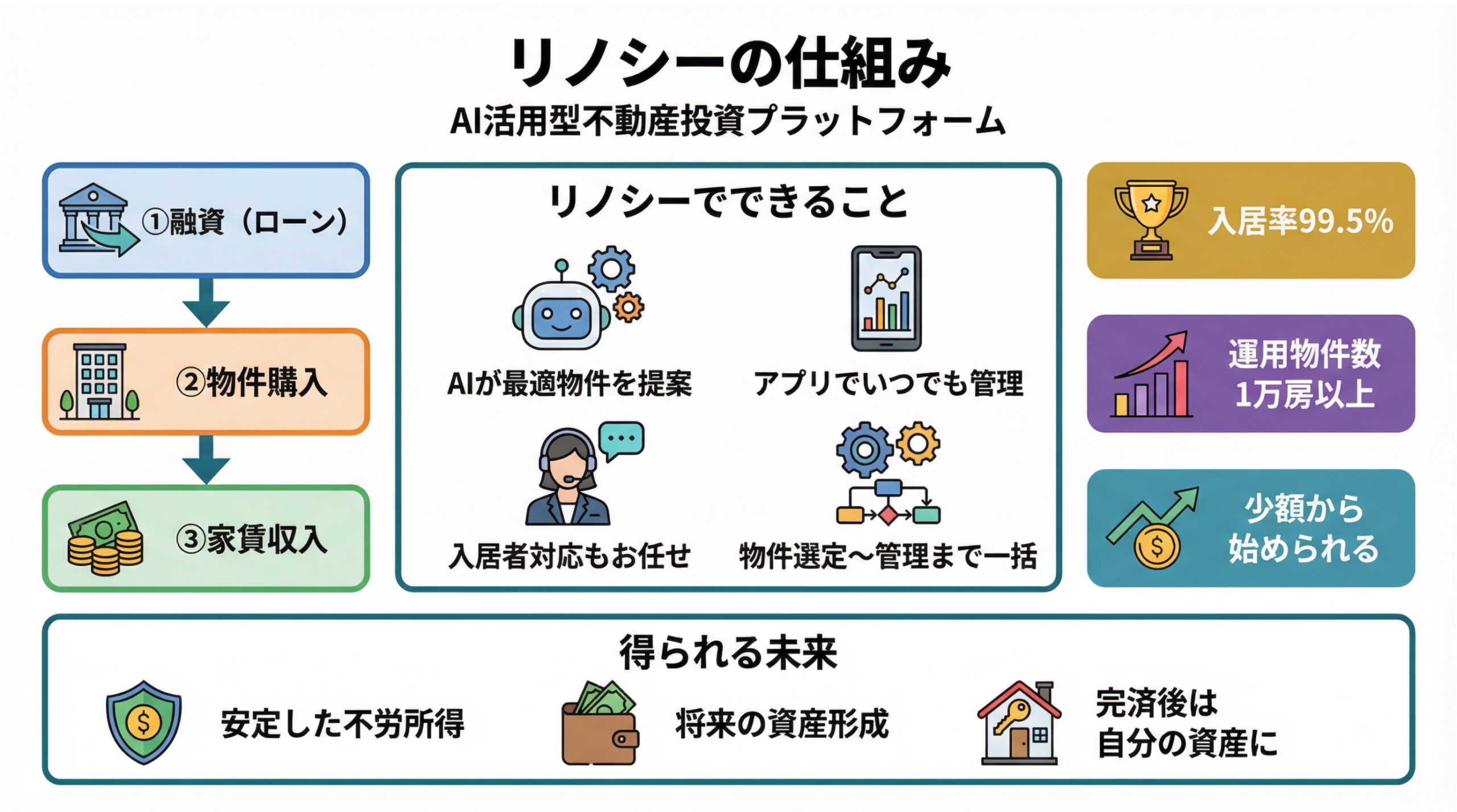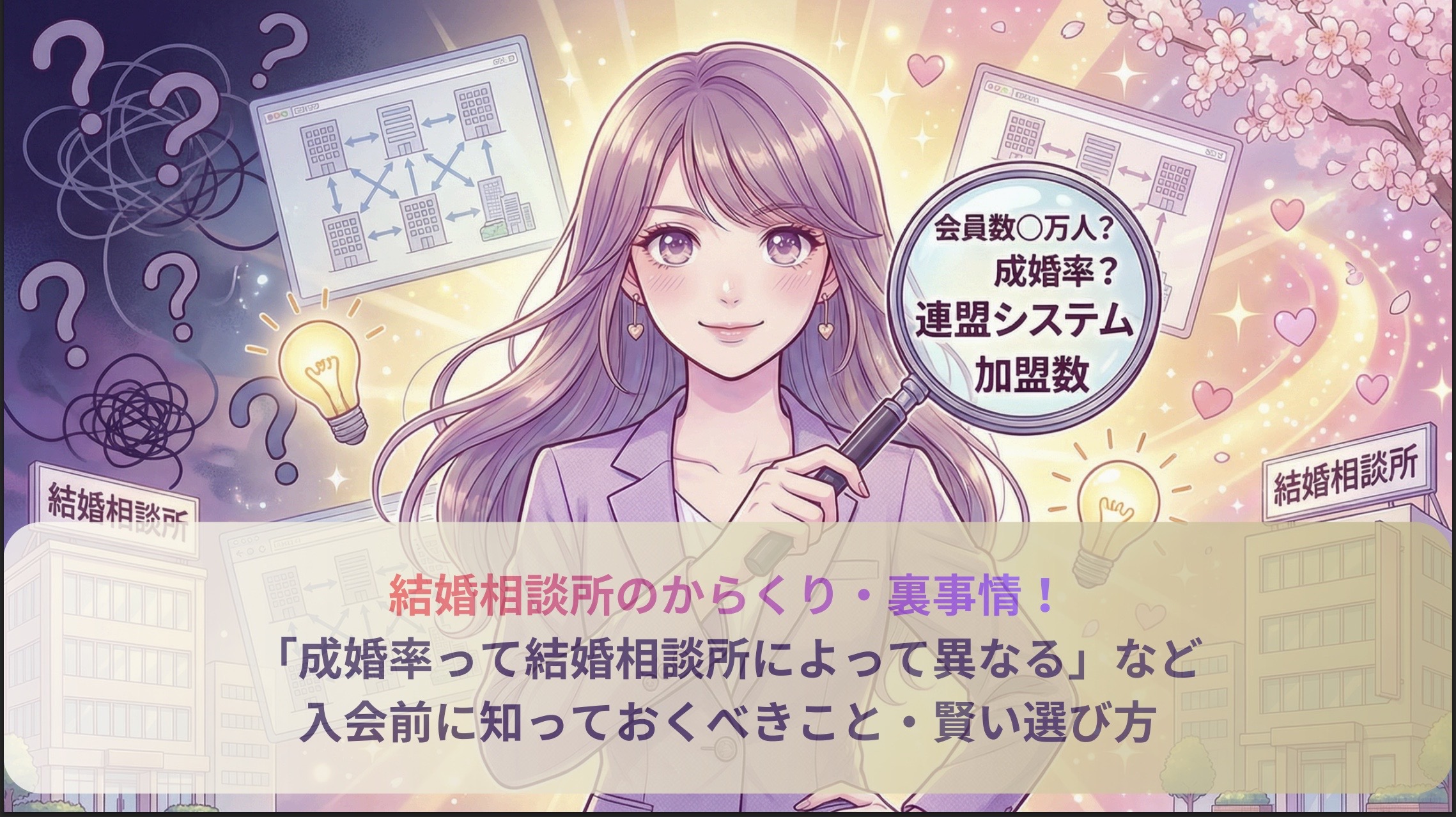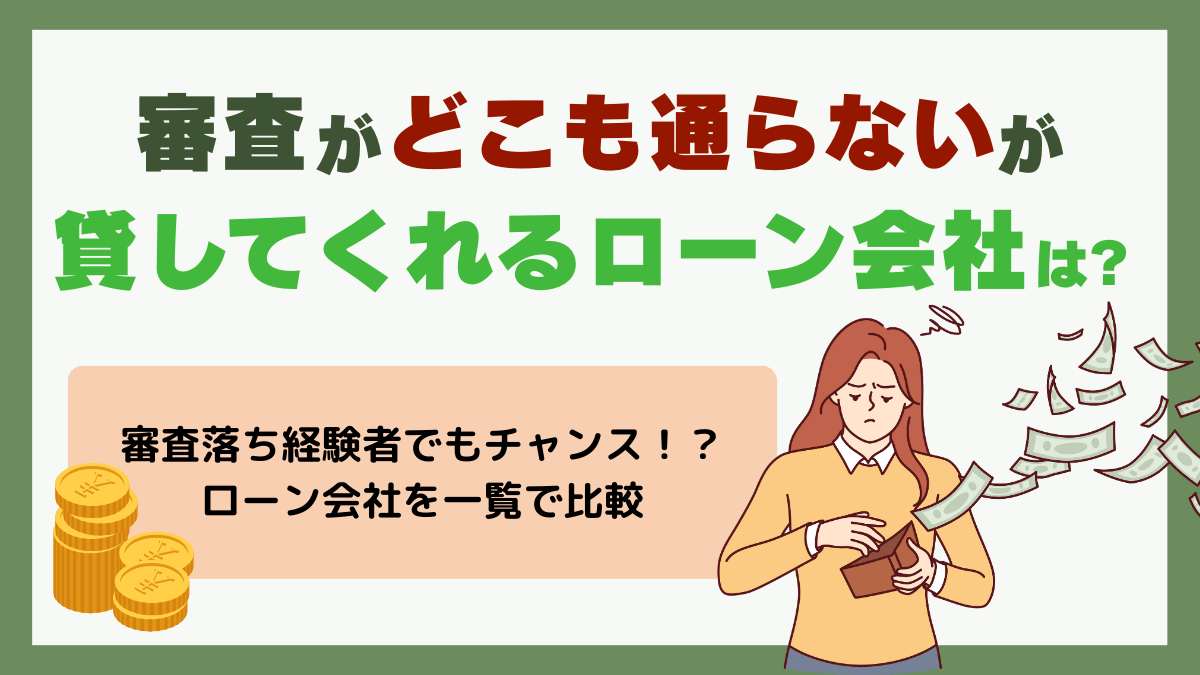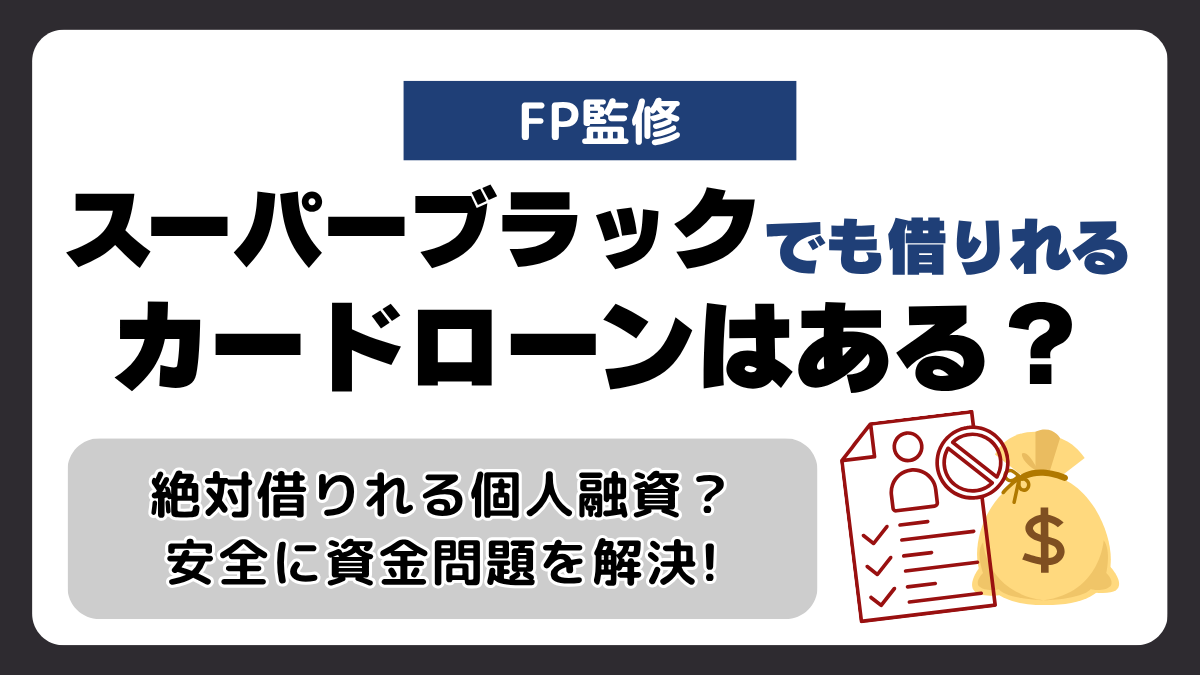性差別やジェンダー差別というと、多くの方はまず女性に対する差別を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、私たちの社会には男性への差別も確かに存在し、そのことで生きづらさを感じている方も少なくありません。
では、なぜ男性差別は世間でほとんど注目されないのでしょうか。その問題を考えるには、身近な例や過去からの社会背景を紐解きながら、男性の抱える問題と女性の権利をどのように両立させるべきかを考える必要があります。
目次
男性差別とは

男性差別とは、読んで字のごとく男性に対して不利益となるさまざまな性差別を言います。
近年のジェンダー平等の流れを受け、女性差別と比較されることが多いものの、女性差別が長い歴史の中で女性全体が抑圧され、根本的な自由・平等・権利を奪われ続けてきたのに対し、男性差別は、
- 奪われることではなく、与えられないこと
- 男性であることの生きづらさが主
など、女性差別を解消する過程で生じてきた問題である、といった点で、女性差別とは異なってきます。
男性差別≒男性蔑視(ミサンドリー)?
男性差別と同じような言葉として、(男性蔑視=英語:ミサンドリー)とも言われます。これは、男性への嫌悪感による差別的な発言や言動、あるいはそうした考えのことを言います。男性蔑視は男性優位社会で不利益を被ったと感じる女性によるものが多く、男性差別を生む原因のひとつになっています。
男性差別の身近な具体例

男性差別の具体的な内容としては、公的制度やサービスなどで男性が不利益を被るようなものから、男性に対する社会の考え方や行動規範などの社会習慣に至るものまで、多くの差別的とも言える事例があります。
公的制度上の差別
公的な制度で男性が不利となる例として、DV(家庭内暴力)に対する対応があります。
日本では配偶者からのDV被害経験がある男性は2024年の時点で5人に1人以上ですが、都道府県が設置している公的シェルターは42の自治体が女性専用で、民間委託などで男性も避難できるシェルターは20の自治体のみです。
それ以外でも、
- DV関連の相談窓口の受付時間が短かい、曜日が限定されている自治体が少なくない
- 11の自治体で対面相談を受け付けず、電話やオンラインでの相談のみ
など、男性のDV被害者は、制度的に救済される機会が女性に比べ低いことがわかります。また、男性はDV被害だけではなく、性被害を受けても深刻に取り合ってもらえない、離婚後の親権を獲得し子どもと同居できるのは1割以下など、不利な立場に追い込まれる例が少なくありません。
女性専用車両
日常生活で最もよく男性差別だと指摘されるのが女性専用車両です。
もともとは痴漢など性犯罪の防止効果に加え、男性の痴漢冤罪防止のために設けられたものですが、同一料金ならば同一のサービスを提供すべき、という立場からは、男性差別ではないかという意見もでています。
ただし、女性専用車両の多くは階段や改札から遠く不便であること、痴漢被害の問題は現実に無視できず安心感は重要であることなどから、廃止するのは適切ではありません。そのため、平等という観点からは男性専用車両の設置が適切である、という案も議論されています。
女性限定サービス

その他に男性差別と見なされるものには、飲食店や映画館、宿泊施設などの各種サービス業で行われている女性限定サービスがあります。一例としては
- 飲食店でのデザートなどの無料進呈
- ガソリンスタンドでのアメニティグッズなどの無料進呈
- パチンコ店での女性専用の台(勝ちやすくする釘の設定)
などです。こうした女性限定サービスは、平日に客数を増やせるなどで利益につなげやすい、収入や社会進出などの男女格差があるなどの理由で正当化され得るものの、
- 収入格差が問題になるのは独身者や母子家庭などで、割合としては少数
- 性別という変更のほぼ不可能な属性で差をつけるのは倫理的に不当な差別
など、同一料金で同一のサービスを提供しないのは男性差別に当たるのでは、といった批判も上がっています。
「男らしさ」の押し付け
その他の男性差別と言うべきものとして、世間から向けられる「男らしさ」の押し付けがあります。これは、男性は仕事ができて稼げる、地位が高いのが理想的だ、などという思い込みから、
- 稼ぎの少ない男性や女性に稼いでもらっている男性
- 高い地位や出世を望まない男性
- 内向的、消極的な男性
などに対して「頼りない」「男のくせに」などの批判的な態度を向けるものです。
筆者自身もまさにこれらの条件に該当するため、直接的に言葉で言われなくとも、そうした批判やまなざしを感じてきたことがあります。
ちなみにこれは「女性から男性」に対してだけではなく、「同じ男性」から向けられることもあり、むしろそちらの方が多いと感じます。
なぜ男性差別は許される風潮があるのか
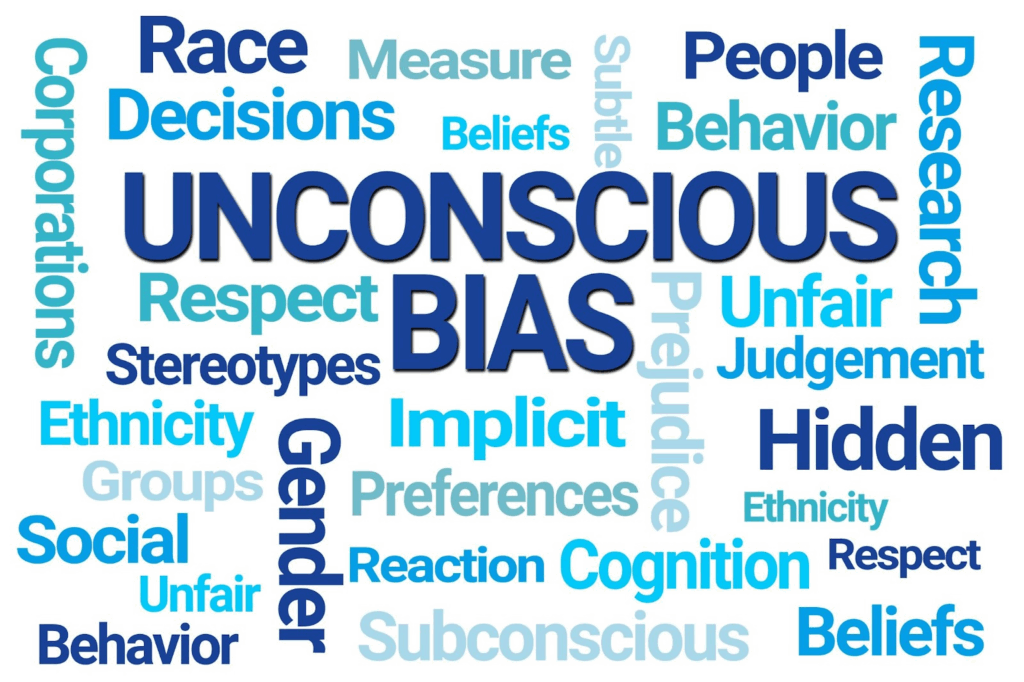
近年、批判されるようになってきた女性差別に比べ、男性への差別はまだそこまで厳しく批判されているとは言えません。ではなぜ、男性差別は許容される風潮があるのでしょうか。
女性差別へのカウンター
まず大きな理由として「男性はこれまで女性をさんざん抑圧し、都合よく利用してきたのだから差別されるのは当然」という、女性差別への逆襲、カウンターとして男性差別を容認するというものです。
実際、長い歴史の中、世界的に性差による不平等は存在してきました。
- 家事労働を強いられ、「勉強は必要ない」と教育を受ける機会を奪われてきた
- 参政権や賃労働などの社会参加を制限されてきた
- 性的な欲求を満たすための性的虐待や暴力を受けてきた
など、女性の方が社会から抑圧されてきた歴史があるのは確かです。
もちろん男性も性被害に合うことはありますが、男性差別によって大きな抑圧や身の危険に晒されることはほぼありません。
そのため「男性差別は大したことない」「これまでの報いを受けるのは当然」という認識が許容されがちです。もちろんそうした報復が正当化できないのは言うまでもありません。
ジェンダーバイアスの影響
もう一つの理由は、男性に対するジェンダーバイアスの影響です。
これはアンコンシャス・バイアス、つまり無意識の偏見から来ており、
- 「男なら我慢できる」「男は泣かない」という決めつけ
- 男らしさ=乱暴、不真面目、大雑把である
というステレオタイプな男らしさが長い間社会に共有されて来たことが影響しています。
そのため、私たちの社会の中には男性なら多少辛く当たっても耐えられる、多少雑に扱っても大したことない、という感覚が残り、男性差別を受け入れがちになってしまうのです。
男性差別が起きないための対策

ジェンダー平等に基づいて女性差別が是正されてきたのと同様、男性差別に対してもそれが起こらないような対策が求められています。
ではそのために、私たちの社会ではどのような対策が必要になるのでしょうか。
対策①男性差別やジェンダーバイアスへの理解を深める
ひとつ目の、そして最も基本的な対策は、男性差別やジェンダーバイアスについての理解を深めることです。これは対象が女性でも男性でも変わりません。
前述のように、私たちが男性差別を軽視し容認してしまう背景には、男性は不当な扱いにも耐えられる強さや、受け流せる不真面目さ、鈍感さを持つという思い込みがあるためです。
しかし、実際には男性の生き方や考え方も多種多様であり、画一的な男らしさを押し付けてその人の行動や人生を縛るのもまた性差別以外の何物でもありません。
そうならないように、私たちは日々の生活のあらゆる場面で、「男らしさ」「女らしさ」という無自覚の思い込みをしていないか、常に気にかける必要があります。
対策②「男性学」の理解と啓発
対策①と関連してきますが、男性に対するジェンダーバイアスを無くすためには、私たちが「男性学」を理解し、より広く知られるようにすることも大事です。
男性学とは、1970〜80年代頃から始まった、男性の抱えるさまざまな問題を研究する学問であり、
- 稼ぎ手男性や「泣いてはいけない」など、「男らしさ」の押しつけや社会的抑圧からの解放
- 男性優位の社会構造が生む男性の「権力性」の問題
- 男性内の差異や不平等
など、男性の生きづらさの正体を解明し、多様な生き方、多様な価値観を示すものです。
近年では専門的な学術書だけでなく、『男性学入門 そもそも男って何だっけ?』(周司あきら、光文社)や『これからの男の子たちへ 「男らしさ」から自由になるためのレッスン』(太田啓子、大月書店)など、より読みやすい一般書が多数出版されています。
対策③男性稼ぎ手体制の転換
男性差別や、男性の生きづらさを解決するために最も必要なのは「お金を稼ぎ、家族を支えるのは男性の仕事である」という男性稼ぎ手社会の意識をなくしていくことです。
そしてそのための理解や啓発は、個人レベルの取り組みだけでは限界があります。
国や行政、企業など、より大きな主体が明確に基本政策を打ち出し、
- 事実上夫が妻を扶養する方が経済的に得な制度設計を根本から見直す(第3号被保険者制度や配偶者扶養手当など)
- 残業や転勤など、家庭や私生活を犠牲にする働き方の是正する
など、賃労働と家庭内ケア労働のそれぞれを、男女どちらかに完全に依存させないと成り立たない社会を変えていくような取り組みが求められています。
企業が男性差別に対してできること

日本の産業界では、多くの企業がジェンダー平等に真剣に取り組み、女性が自分の能力を発揮しやすい環境が整いつつあります。しかしその陰で、男性への差別についてはまだそこまで真剣に取り組んでいるとは言い切れません。企業にできること、すべきこととはどんなことなのでしょうか。
社内制度を改める
望ましい取り組みとして挙げられるのは、先述したように「稼ぎ手=男性」が前提ではない社内制度を作ることです。具体的には、
- 給与や福利厚生の内容、昇進の条件などに、性別に基づく差を付けない
- 女性に対し、産休・育休後の職場復帰をしやすい雰囲気や環境をつくる
- 男性に育休を奨励すると共に、育休前後の仕事の引き継ぎ体制を整える
などの取り組みが必要となります。
特に、女性にも男性と同様の役割と賃金を保証することは重要です。性別に基づく給与の差別をやめ、純粋なスキルや経験で待遇を約束すれば、従業員の離職率を下げ、生産性を高めることにもなります。
フィードバックを集め課題を検証
職場においては、ただ制度を作るだけでは不十分です。制度の運用にあたっては、
- 実際に男性がどの程度育休を取得できているか
- 取得しづらい空気や環境はないか
- ジェンダー平等のための制度が、女性に偏り男性に著しい不利益が生じていないか
などのフィードバックを集め、改善すべき課題を特定し解決策を策定することが大事です。
そのためには、アンケート、グループウェア、ミーティングなどのさまざまな手段を活用し、匿名性や機密性を維持したうえで情報を集めていきましょう。
男女問わず柔軟な働き方を提示する

社会において男性稼ぎ手体制を維持してきたのは、週5日8時間などの固定的な働き方でした。これを男女問わずより自由度の高い柔軟な働き方、具体的には、
- リモートワークやサテライトオフィスの推進
- 短時間正社員制の導入
- 時差出勤や時短勤務
などのような制度を導入することで、子育てや家事、介護などとの両立、趣味や学びなおしなど、さまざまな事情に対応できる働き方の選択肢を提示できます。
このような制度を女性だけでなく、男性を含めた多くの従業員に適応することは、男性を稼ぎ手プレッシャーから解放し、旧来の男らしさを問い直す契機ともなり得ます。
私たちが男性差別に対して注意すべきこと

私たちは男女を問わず、ジェンダーバイアスや男性学への理解を深めながら男性差別をなくす取り組みをしていく必要があります。ただしそこには気をつけなければいけないこと、陥りやすい罠にはまらないようにしなければいけません。
女性差別と対立するものではない
注意しなければいけないのが、男性の側が男性差別に反発するあまり、かえって女性差別を助長するような言動や考え方をしてしまうことです。
男性の生きづらさは社会が女性優位の社会になっているからでもなければ、そうなりつつあるせいでもありません。
男性差別と感じるものの元凶は、男性優位の社会を維持するための代償であり、その代償を払い続けてきたのは、女性であり、男らしさを押し付けられて苦しんできた男性たちなのです。
主張すべきことはする

逆に男性側は、男性差別あるいは不当だと感じたことに対しては、是々非々で主張することを恐れないことも大事です。ルーマニア語作家の済東鉄腸氏は、著書『クソッタレな俺をマシにするための生活革命』の中で、女性に対する差別や抑圧と責任を持って向き合いながらも、自分たちへの納得のいかない非難や批判には堂々と反論することで、フェミニストやクィア当事者にも顔向けできるシスヘテロ男性になれるとしています。
大事なのは、男性差別だと開き直って反発するのでもなく、差別されるのは仕方ないと卑屈になるのでもない、正しい自己肯定感を持った冷静でフェアな視点です。
男性差別とSDGs

SDGs(持続可能な開発目標)では、目標5に「ジェンダー平等を実現しよう」を掲げています。とはいえここでは男性差別や男性の生きづらさについて具体的に言及している項目はありません。
しかし、ジェンダーとはそもそも社会や文化によって形作られた性別を指すものですので、社会によって押し付けられた「男らしさ」「女らしさ」から解放され、ジェンダーによる差別を受けないことは、目標5の達成そのものでもあると言えるでしょう。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ

男性差別は女性差別よりも見えにくく、社会的にも軽視されがちな問題です。しかし、誰もが尊重される社会の実現には、女性だけでなく男性への差別も無くさなければなりません。多くの男性は、その内部に弱さや苦しみを語れる環境を必要としています。正しく公正な知識によって男性の抱える問題にも目を向け、無意識の偏見や固定観念を取り除いて理解し支え合う姿勢が、よりフェアな社会への第一歩となるでしょう。
参考文献・資料
男性学入門 そもそも男って何だっけ?:周司あきら著/光文社,2025年
男がつらいよ-絶望の時代の希望の男性学:田中 俊之著/KADOKAWA,2015年
ジェンダーで読み解く男性の働き方・暮らし方 ワーク・ライフ・バランスと持続可能な社会の発展のために:多賀太著.時事通信出版局, 2022.
「ジェンダー差別」って何? 男にも関係あるの? – わたしたちのSRHR
実は男だって生きづらい。男性学から考える「ジェンダー平等」の意義とは? | 日本財団ジャーナル
三谷,竜彦 いわゆる男性差別の問題について(1) : 女性専用車両の是非を考える 名古屋大学哲学論集12巻, p.59-70, 名古屋大学学術機関リポジトリ
三谷,竜彦 いわゆる男性差別の問題について(2) : 女性限定サービスの是非を考える 名古屋大学哲学論集 13巻, p.97-108, 2017-03.名古屋大学学術機関リポジトリ
ジェンダー・バイアスの打破:包括的な職場を築くためのステップ
「DV被害者は女性」の偏見 男性用シェルター確保、20自治体のみ:朝日新聞
男性学(men’s studies)|日本女性学習財団|キーワード・用語解説
ミサンドリーとは?男性蔑視といわれるその意味や具体例、ミソジニーとの違いやその課題について徹底解説! – あしたメディア by BIGLOBE
クソッタレな俺をマシにするための生活革命:済東鉄腸著/左右社,2024年
この記事を書いた人
shishido ライター
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。