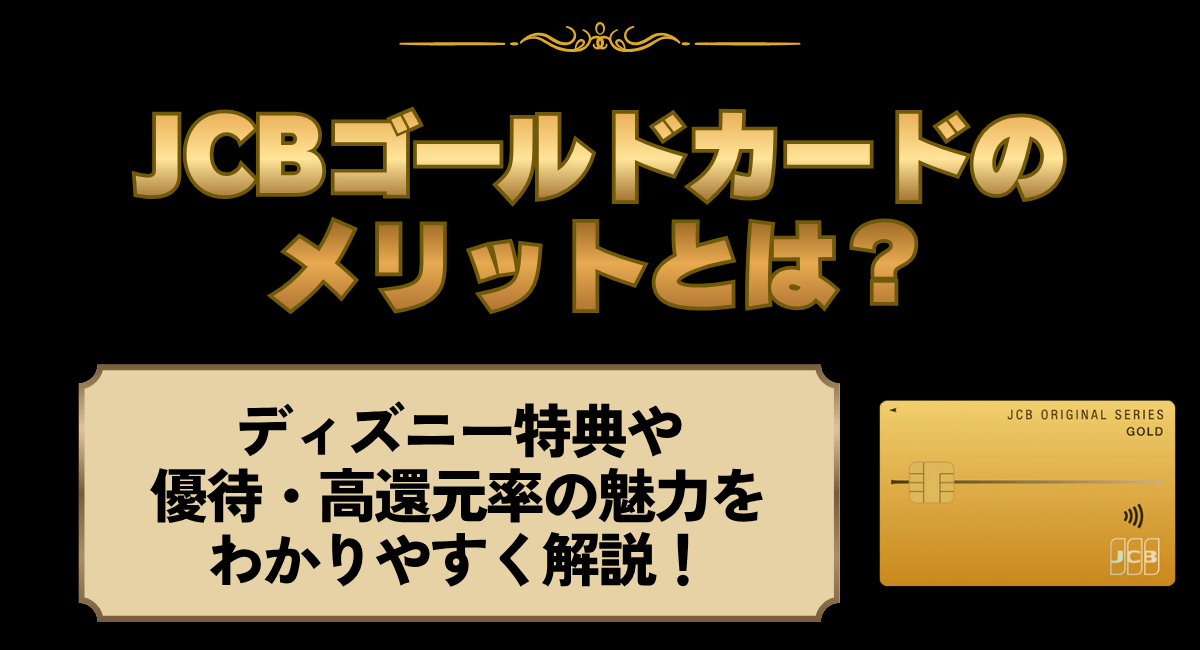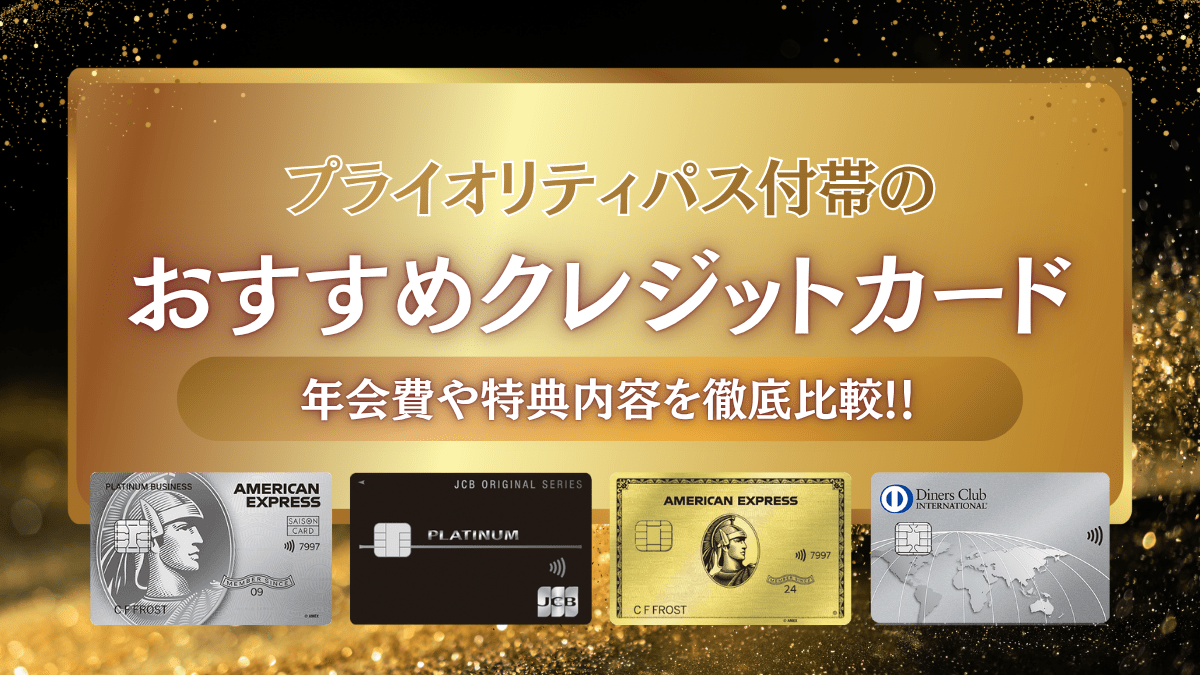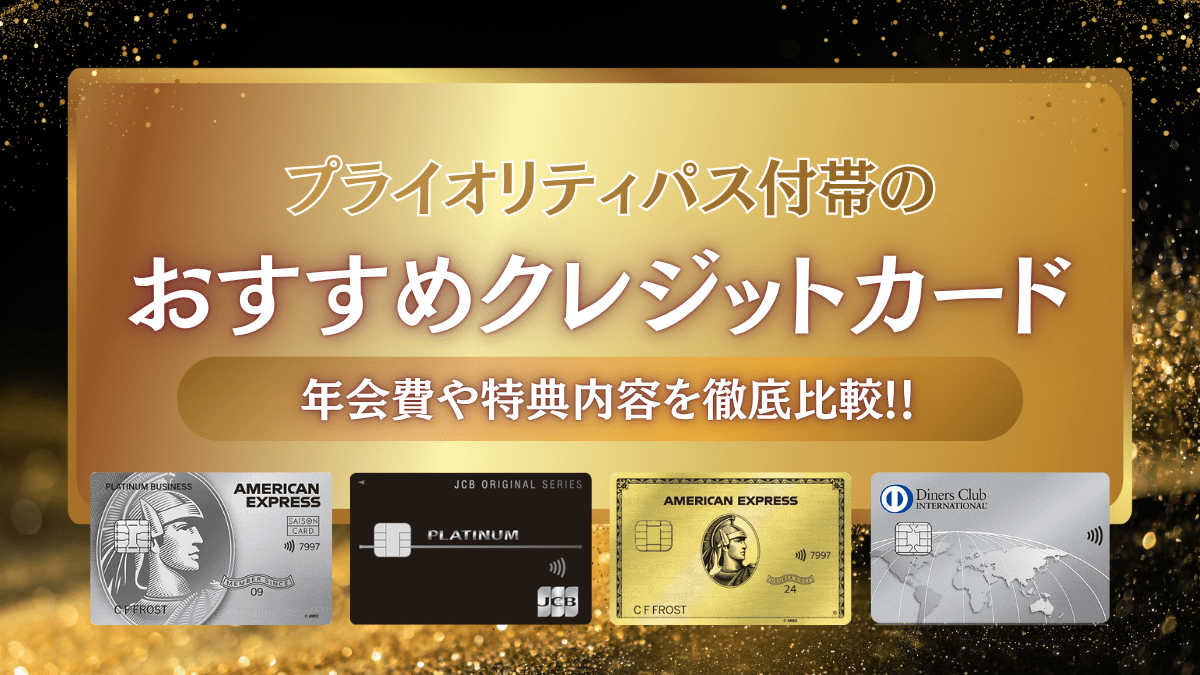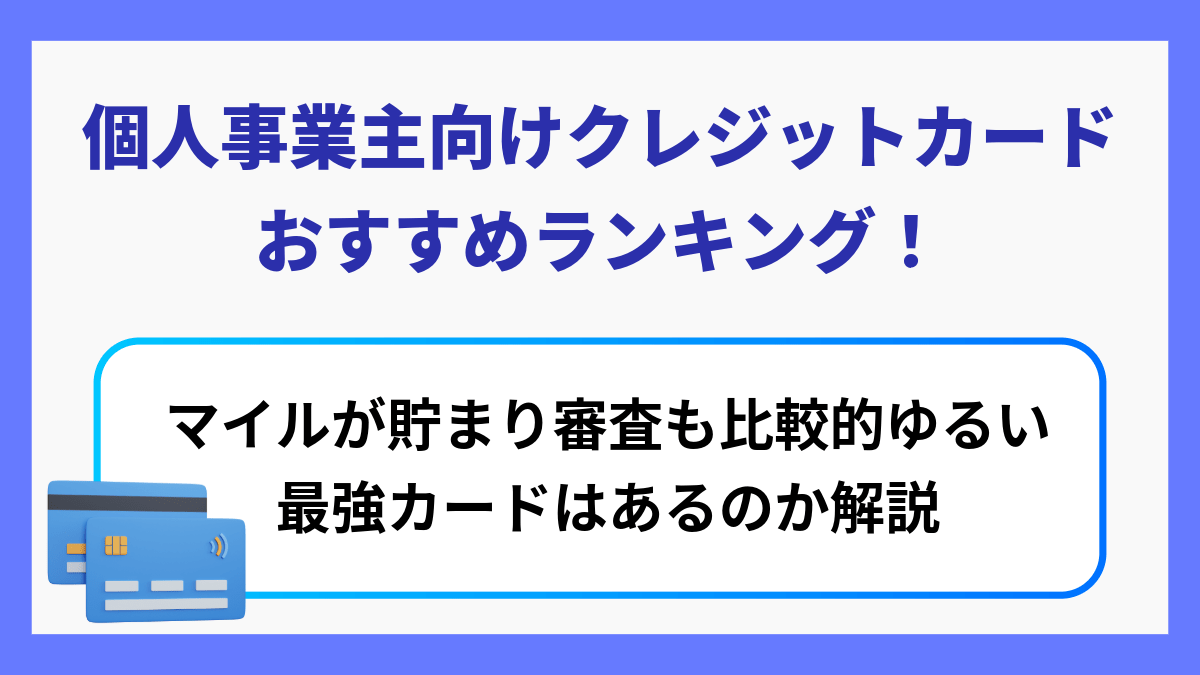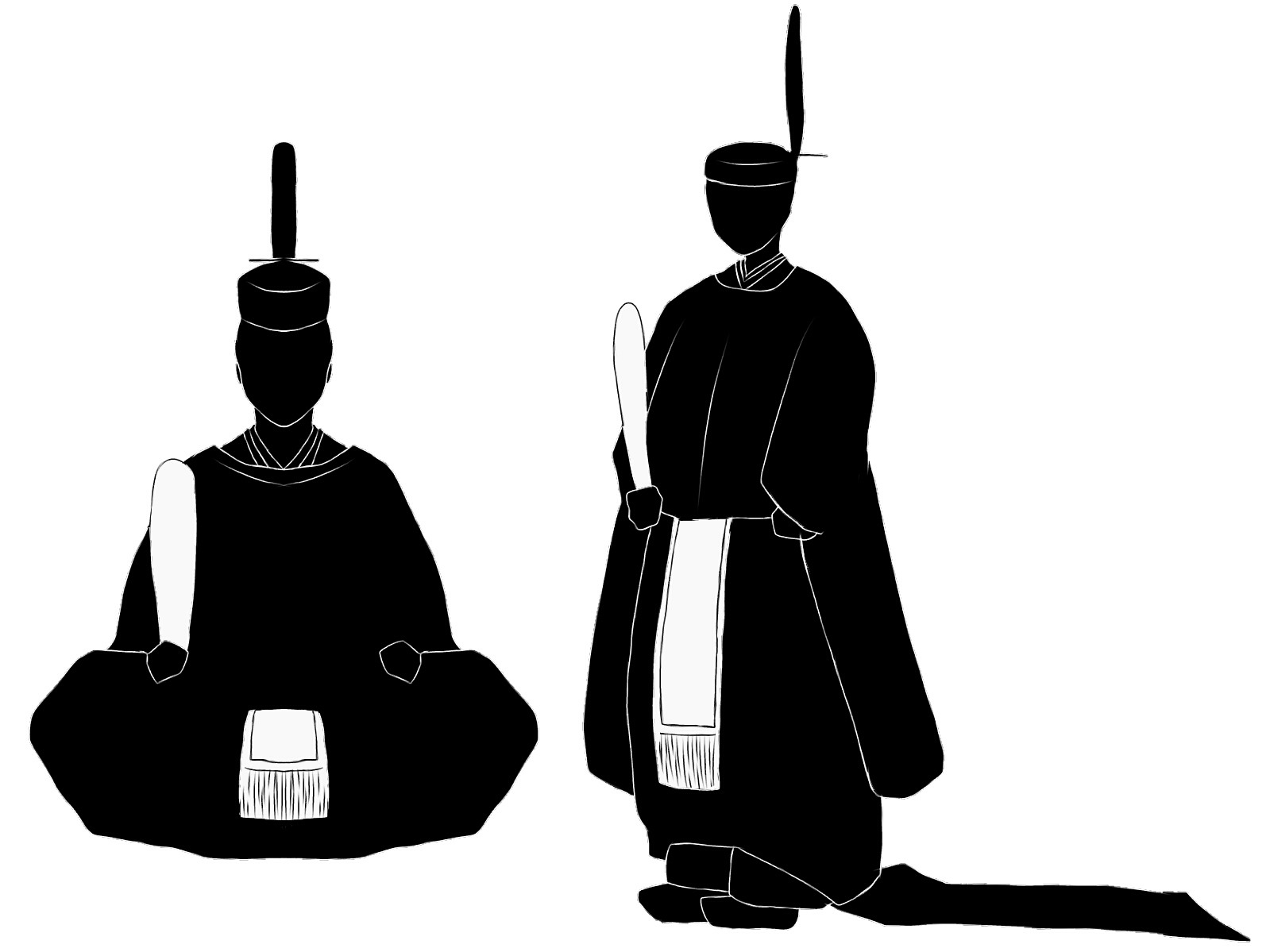
「この世をば我が世とぞ思ふ…」という「望月の歌」は藤原道長の作です。彼が月を見上げながら詠んだこの一首は、彼の権力が満ち足りていたことを象徴しています。
平安時代中期、道長は藤原氏の勢力を背景に朝廷の実権を握り、誰もが恐れ、また羨む存在となりました。しかし、その栄華の裏には、激しい政治闘争や家族の思惑が絡み合う複雑な現実がありました。
彼は冷静沈着で度胸がありながらも、大胆に行動する一面を持ち、時に人間らしい優しさも見せます。さらに、政治だけでなく文化の発展にも深く関わり、紫式部など才能ある人々を支援しました。
法成寺の建立など社会的貢献も多く、教育や信仰を重んじた姿勢は現代のSDGsにも通じるものです。今回は、そんな藤原道長の人物像や功績を、逸話とともにわかりやすく解説します。
目次
藤原道長とは

藤原道長は、平安時代中期に活躍した貴族で、父は有力者の藤原兼家です。幼いころから姉たちに可愛がられ、明るく人懐っこい性格だったと伝えられています。一方で、『大鏡』には肝が据わり、どんな場面でも動じない冷静沈着な人柄だったと記されています。弓比べの逸話などからも、大胆で自信に満ちた人物像がうかがえます。
晩年は病に苦しみ、死因は癌や糖尿病ともいわれますが、詳細は不明です。その生涯は、栄華と人間味が交錯する波乱に満ちたものでした。
父は藤原兼家
藤原道長は、平安時代中期に活躍した藤原北家の出身で、父は摂政・関白・太政大臣を務めた藤原兼家です。母は藤原中正の娘・時姫で、道長は兼家の五男として生まれました。*1)
幼いころから恵まれた家柄にありながら、兄たちが上位にいたため、当初は自分が一族の頂点に立つとは思っていなかったといわれます。しかし、持ち前の冷静さと行動力で着実に昇進し、やがて藤原氏の権力を極める存在となっていきました。
性格①:肝が据わっている
『大鏡』という歴史物語によると、才能にあふれた藤原公任(四条の大納言)を父・藤原兼家が「わが子らはその影さえ踏めぬ」と嘆いた場面があります。兄たちは沈黙し、気落ちしている中、五男の藤原道長は「影をば踏まで、面をや踏まぬ」と大きく宣言しました。陰どころか顔を踏んでやるといったのです。
この言葉は単なる若気の至りではなく、後に実現されます。こうした一連のエピソードは、道長が若年ながらも揺るがぬ覚悟と強い意志を持っていたことを物語り、「肝が据わっている人物」という評価を裏付けるものです。
性格②:大胆不適
兄で最高権力者であった藤原道隆の邸「南院」にて、甥の藤原伊周(道隆の子)が人々を集めて弓の遊び(競射)を開いていました。その場に道長が突然現れ、身分では伊周より劣るにもかかわらず、伊周よりも先に射るよう手厚く扱われます。
道長はまず的を射て、伊周より二本多く当てる勝利を挙げました。さらに延長となった際、「我が家から天皇・皇后が出るべきならばこの矢当たれ」と宣言し、見事に的の中心に命中させてみせます。
道長は兄・道隆をはじめ周囲の期待や序列をものともせず、自らの意志を宣言し、実際に結果を出す姿を見せました。このエピソードは、彼がただ権力を握るだけの人物ではなく、胆力と挑戦心を持った大胆不敵な貴族であったことを端的に物語っています。
死因は糖尿病?
藤原道長の最期の病は、糖尿病によるものであった可能性が高いと考えられています。
当時の貴族の食生活は非常にぜいたくで、米を中心に魚や肉、果物などが豊富に使われ、さらに甘い調味料や酒が頻繁に用いられていました。宴会も多く、濃い味つけの料理や甘酒が日常的に供されていたため、糖分や脂肪の摂り過ぎが慢性化していたといわれます。また、華美な衣装と儀礼中心の生活は体を動かす機会を奪い、運動不足につながりました。
『御堂関白記』などの史料には、道長が晩年に体調を崩し、体のむくみや疲労、視力の低下など、糖尿病に似た症状を抱えていたことが記されています。さらに、一族にも同じ病に苦しんだ者が多く、遺伝的な体質も影響したとみられます。加えて、長年の政治的な緊張や疫病の流行による心身の負担も、病状を悪化させた要因と考えられます。
つまり、藤原道長の病はぜいたくな食生活と運動不足、過度な精神的重圧が重なって発症した可能性が高く、現代にも通じる「生活習慣病」としての糖尿病だったと推測されます。*4)
藤原道長が行ったこと
藤原道長はいったいどのような人生を送ったのでしょうか。はじめに、彼の人生を年表形式で整理します。
| 966年 | 藤原兼家の五男として誕生 |
| 980年 | 従五位下に任じられ、殿上人(貴族)となる |
| 987年 | 従三位に任じられ、公卿(上級貴族)となる |
| 987年 | 源倫子と結婚 |
| 988年 | 長女の彰子誕生源明子とも結婚 |
| 990年 | 藤原兼家が引退し、兄の道隆が摂関を継ぐ |
| 995年 | 道隆と道兼(もう一人の兄)が死去甥である伊周との争いに勝って権力を握る |
| 996年 | 長徳の変で藤原伊周と藤原隆家が失脚道長は左大臣に昇進 |
| 999年 | 彰子が入内 |
| 1000年 | 道長が彰子を皇后とする |
| 1011年 | 一条天皇が崩御し、三条天皇が即位 |
| 1017年 | 三条天皇が退位し、後一条天皇(道長の孫)が即位道長は摂政として後一条天皇を補佐 |
| 1019年 | 道長が出家し、法成寺の造営を開始 |
| 1027年 | 道長死去(享年62歳) |
道長は996年の長徳の変で政権を握ってから1019年に出家するまで、30年以上にわたって政権の中枢にいたことになります。
権力闘争に勝利し朝廷のトップに
藤原道長は、兄たちの死後に起こった混乱の中で、見事に権力を掌握しました。父・兼家の引退後、関白の地位を継いだ兄・道隆、さらにその後を継いだ道兼が相次いで亡くなり、朝廷では後継をめぐる争いが激化しました。特に、兄・道隆の子である伊周との対立は深刻で、藤原北家内部の分裂を生むほどでした。
しかし、道長には強力な支援者がいました。姉の藤原詮子は一条天皇の母であり、その後ろ盾によって道長は内覧(天皇の意向を伝える最高職)の地位を得ます。その後、右大臣・左大臣へと昇進し、実質的に朝廷のトップとなりました。*5)
さらに、伊周・隆家兄弟が花山法皇に矢を射かけたことや藤原詮子を呪ったことなどを理由として失脚(長徳の変)したことで、道長の地位は完全に確立します。*6)
彼は名門・藤原公任を抑え、源俊賢や藤原行成ら有能な官人を登用して政権を固めました。こうして道長は、血縁と政治力を駆使し、摂関政治の全盛期を築く礎をつくったのです。
摂関政治の全盛期を築いた
藤原道長は、摂関政治を頂点に導いた人物です。彼は自らの娘たちを次々に天皇の后に迎え入れることで、外祖父としての立場から政治の実権を掌握しました。
長女・彰子を一条天皇の中宮とし、二女・妍子を三条天皇に嫁がせることで、朝廷に強い影響力を持つようになります。さらに、藤原氏との血縁が薄い三条天皇の譲位を促して外孫の敦成親王(後一条天皇)を即位させ、自ら摂政に就任しました。のちにその地位を息子・頼通へと譲り、家としての権勢を盤石にします。
その結果、彰子は太皇太后、妍子は皇太后、威子は中宮という“三后の父”となり、まさに権力の絶頂を迎えました。この栄華の極みに詠まれたのが、有名な「この世をば我が世とぞ思ふ望月のかけたることもなしと思へば」という歌です。
満月のように欠けることのない栄光を誇った一首は、彼の政治的成功と一族繁栄の象徴となりました。道長は優れた政策よりも、巧みな人脈と後宮戦略で平安貴族社会を支配した、まさに摂関政治の完成者だったのです。*1)
三条天皇との対立
三条天皇は、冷泉天皇の第2皇子で、実権を握っていた藤原道長としばしば対立しました。特に、即位後に道長の娘・妍子を皇后としたのち、自らが寵愛していた藤原済時の娘・娍子を中宮に立てようとしたことが対立の引き金となりました。道長はこの人事に強く反発し、立后の儀式を妨害するほどでした。
さらに、天皇が眼病で政務に支障をきたすようになると、道長は譲位を迫り、外孫である敦成親王(後の後一条天皇)を即位させます。三条天皇はこれに抗いながらも、最終的に譲位を受け入れ、失意のうちに崩御しました。この一連の出来事は、天皇の誠実さと道長の権力の強大さを象徴しています。*1)
法成寺を建てる
藤原道長が晩年に建てた法成寺(ほうじょうじ)は、彼の信仰と人生観を象徴する壮麗な寺院でした。
病に苦しみながらも出家した道長は、1019年、自邸の東にある鴨川のほとりに自らの念仏堂「中河御堂」の建築を始めます。のちにこの寺は「法成寺」と呼ばれ、金色に輝く九体の阿弥陀像が安置されるなど、まさに極楽浄土を地上に再現したような壮観さであったことが『栄花物語』に記されています。
そして1027年、病の床に伏した道長は、阿弥陀仏の指先から伸びる五色の糸を自らの手に結び、念仏を唱えながら静かに息を引き取ったと伝えられます。
満月のように権力を極めた男が、最後には仏にすがり極楽往生を願った。その姿は、栄華と無常が交錯する平安貴族の人生を象徴しています。法成寺は後に焼失しましたが、その壮麗さと道長の最期は、後世に伝わっています。
藤原道長とSDGsの関わり
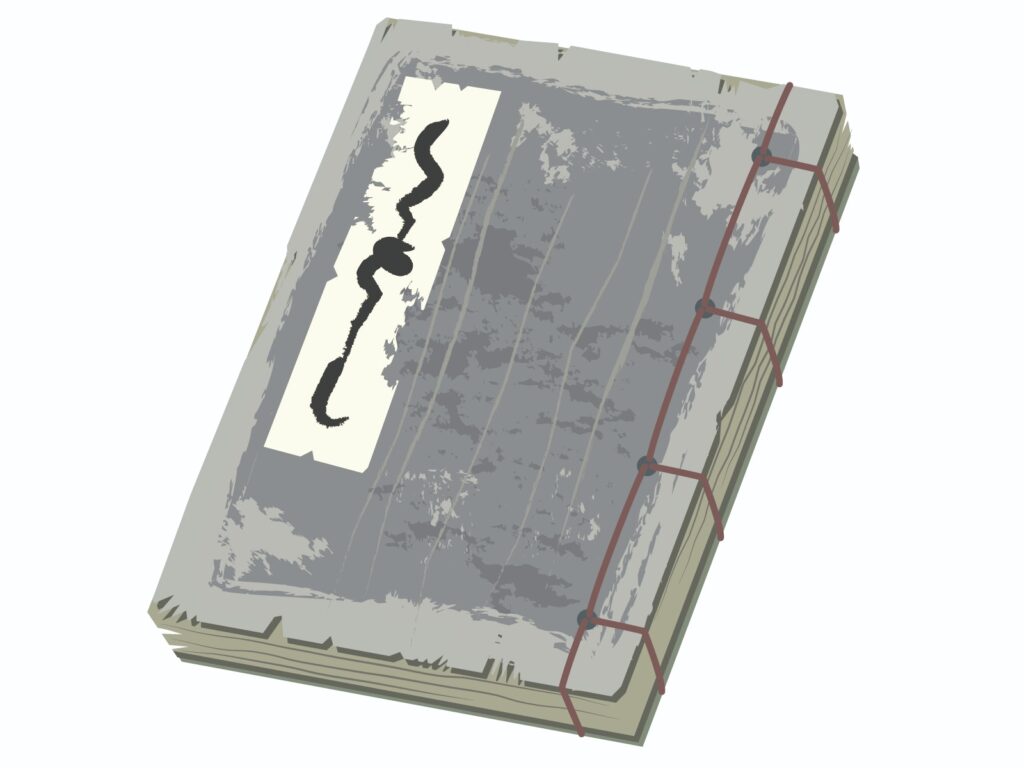
藤原道長は、権力者でありながら文化や教育の発展にも尽力しました。紫式部ら才能ある女性を支援し、王朝文学の発展に貢献した彼の姿勢は、現代のSDGs目標4「質の高い教育をみんなに」に通じるものがあります。
SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」との関わり
藤原道長は、平安時代の王朝文化を支えた最大の後援者の一人でした。彼は娘の彰子を一条天皇の中宮とした際、その教育と教養を高めるために紫式部を女房として迎え入れます。道長の庇護のもとで紫式部は『源氏物語』を完成させ、清少納言や和泉式部らとともに王朝文学の黄金期を築きました。
このように、才能ある人々に学びと創作の機会を与えた道長の姿勢は、SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」に通じるものがあります。
しかし、その教育支援は貴族社会という限られた世界の中で行われたものでした。学問や文学に触れられるのは一部の上流階級の女性や知識人に限られ、庶民に教育の機会が広がることはありませんでした。
道長の活動は当時としては文化振興の先進的な取り組みでしたが、教育の平等化やすべての人への学びの保障という点では、現代のSDGsが掲げる「誰一人取り残さない」理念とは異なっていたのです。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
藤原道長は、平安時代中期に摂関政治を極めた貴族でありながら、文化や教育にも深く関わった人物です。冷静で胆力に富み、政治闘争を勝ち抜いて朝廷の頂点に立ち、「この世をば我が世とぞ思ふ」と詠んだ歌に象徴される栄華を誇りました。
一方で、紫式部を支援し『源氏物語』誕生を後押しするなど、学びと創造の場を育てた功績もあります。これらの行動は現代のSDGs目標4「質の高い教育をみんなに」に通じる一方、教育の恩恵が貴族に限られている点で現代との違いも見られます。
政治力と文化力の両面で時代を動かした道長の生涯は、権力の頂点に立ちながらも学びと信仰を重んじた、華やかで奥深いものでした。
参考
*1)日本大百科全書(ニッポニカ)「藤原道長」
*2)デジタル大辞泉「北家」
*3)デジタル大辞泉「大鏡」
*4)ノボ ノルディスク ファーマ「国内インスリンの歴史 第10回 誰もがうらやむ地位と栄華を誇った藤原道長と糖尿病」
*5)改定新版 世界大百科事典「藤原道長」
*6)日本大百科全書(ニッポニカ)「藤原伊周」
*7)ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「三条天皇」
*8)日本大百科全書(ニッポニカ)「法成寺」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。