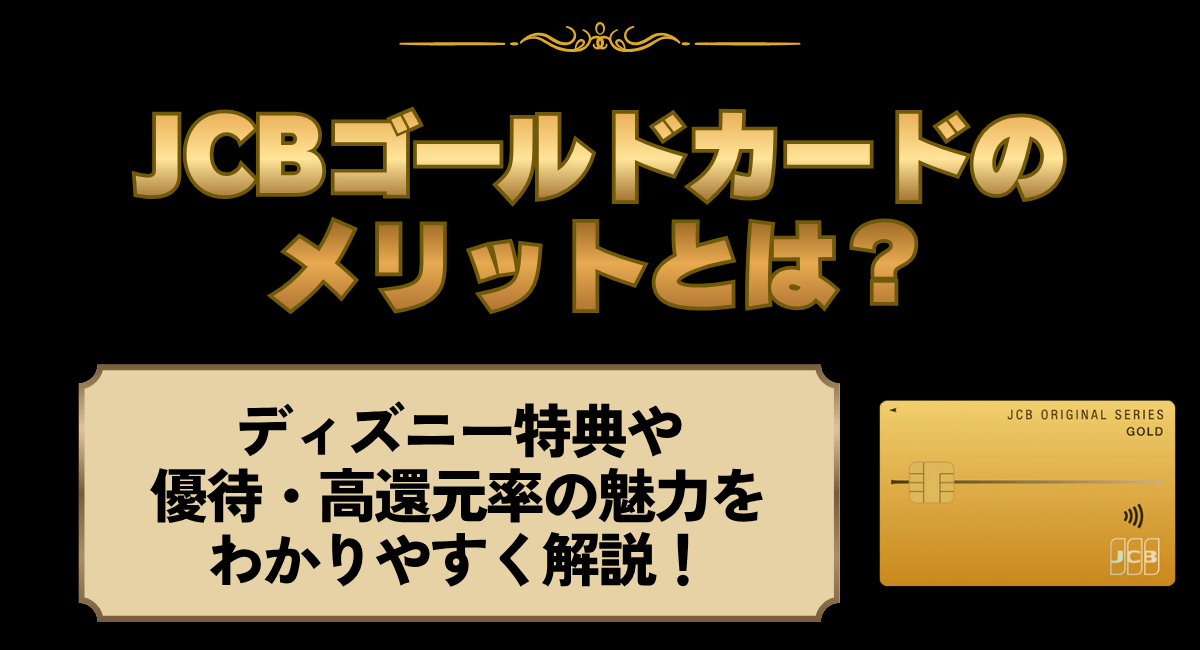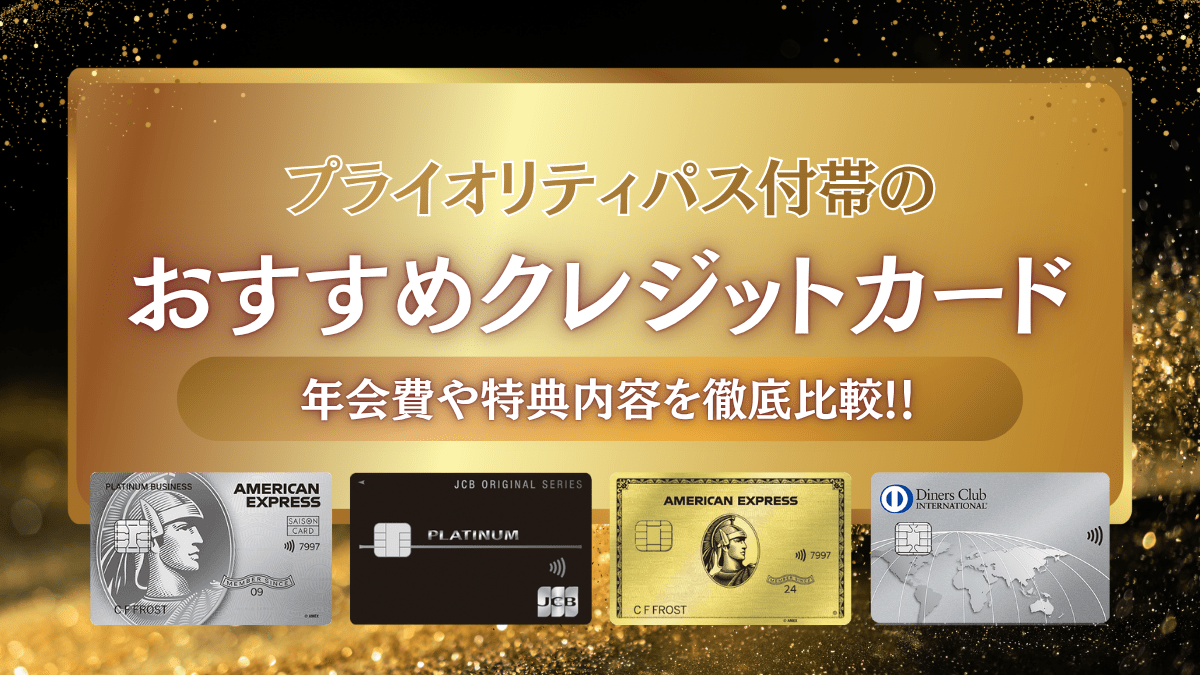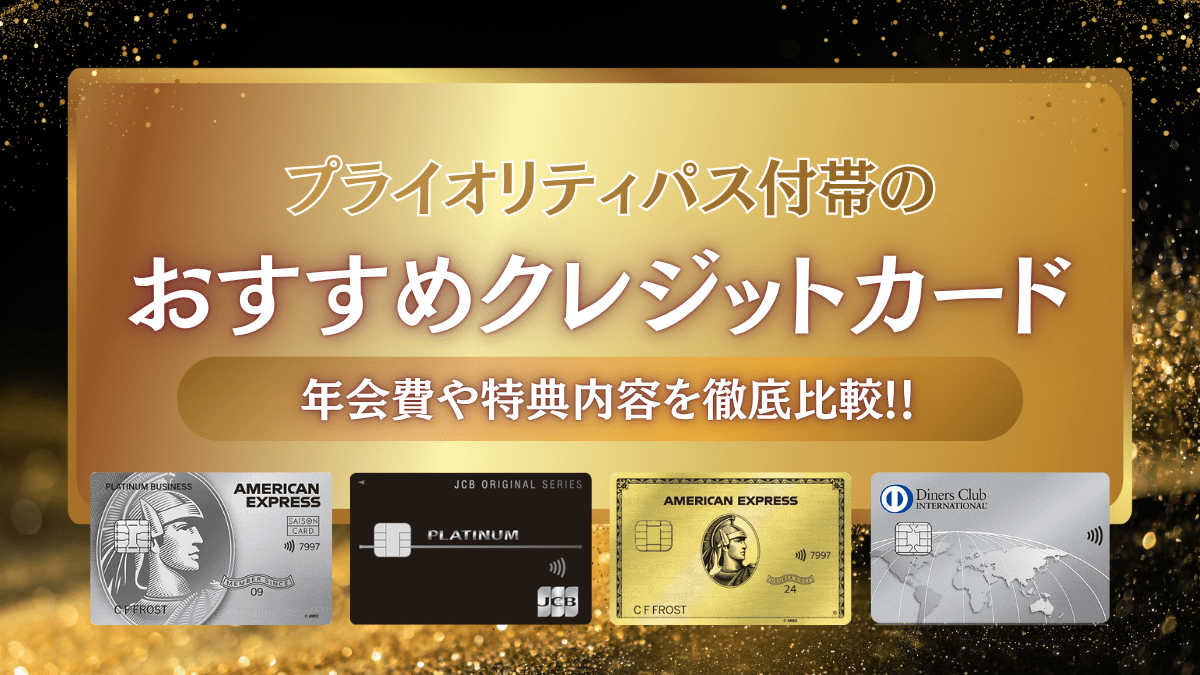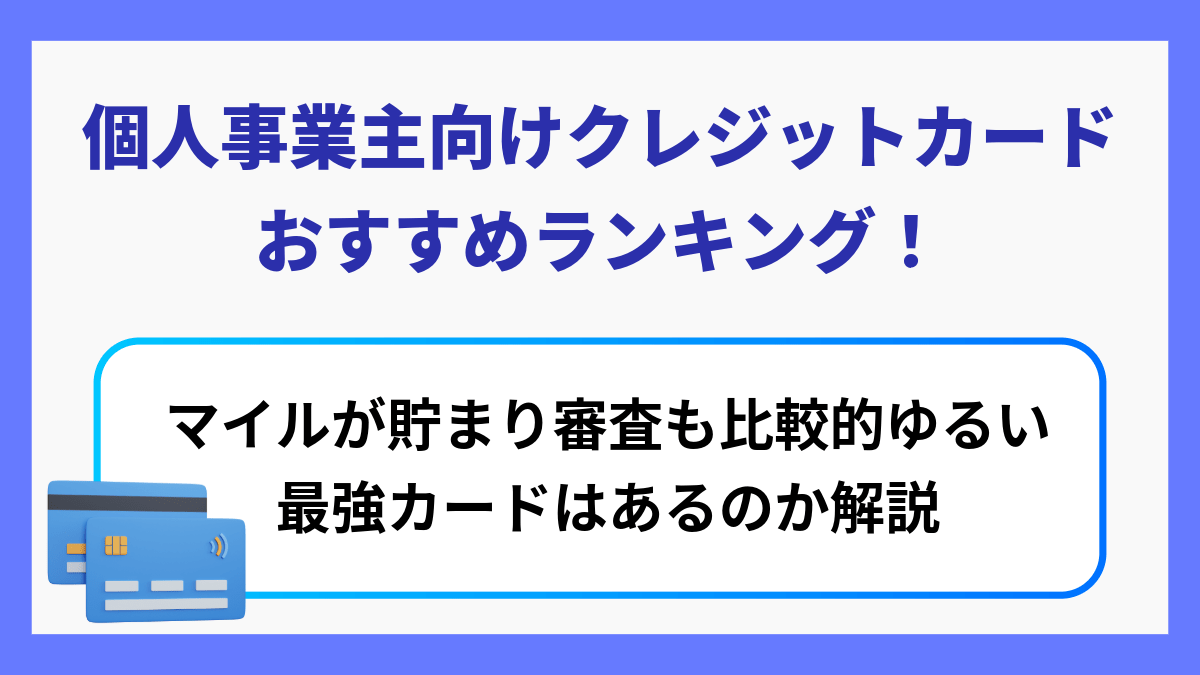戦乱と混乱が続く鎌倉時代、平和と公正を重んじた一人の武士がいました。その名は北条泰時。父・北条義時のあとを継いで幕府の中心に立ち、混乱する政治を整えた人物です。
力ではなく「話し合い」と「道理」を重視し、仲間と協力しながら政治を行いました。さらに、武士が守るべき決まりをまとめた日本初の法律「御成敗式目」をつくり、公平な社会の基礎を築いたことでも知られています。
一方で、子に先立たれる不孝や朝廷・寺院との対立など、苦難も多い人生でした。質素で誠実な生き方を貫き、人々から信頼された泰時の姿は、現代社会における「理想のリーダー像」として、今も学ぶべき点が多い人物です。
目次
北条泰時とは

北条泰時は、鎌倉幕府を安定へと導いた名執権であり、公正で誠実な政治を行った人物です。父・北条義時の子として生まれ、幼い頃から政治と武士の在り方を学びました。
石清水八幡宮や興福寺、比叡山延暦寺などが僧兵の武力を背景に要求を押し通そうとした際は、「武力で秩序を守る」といった果断な措置を講じています。人柄は質素で誠実、権力におごらず「公平な裁き」を重んじたため、多くの人から信頼を集めました。
ここでは、北条泰時の人となりを中心に解説します。
北条義時の子として生まれる
北条泰時は、鎌倉幕府の実力者・北条義時の長男として1183年(寿永2年)に生まれました。幼いころの名前は「金剛(こんごう)」といい、1194年(建久5年)に成人の儀式である元服を行い、その際に源頼朝が烏帽子親となりました。*1)
このとき、頼朝から「頼」の字を与えられ、当初は「頼時(よりとき)」と名乗りましたが、のちに「泰時(やすとき)」と改めています。
若いころは「江間太郎(えまたろう)」とも呼ばれ、父のもとで武士としての教えを学びながら、のちに幕府の中心人物となる礎を築いていきました。
子に次々と先立たれる
北条泰時は、家庭において多くの悲しみに見舞われました。1227年、次男の時実が家臣に殺害され、3年後には後継ぎとして期待していた長男・時氏が病で亡くなります。
そのわずか1か月後には、娘が出産後まもなく子とともに命を落とし、泰時は深い悲しみに包まれました。立て続けに愛する家族を失いながらも、泰時は政務を務めました。
寺院の横暴に武力で対抗
北条泰時は、興福寺や比叡山延暦寺の僧たちが武力で勝手な行動をとるのを、武士の力でおさえました。当時の日本では、大きな寺院が自分たちの武装した僧(僧兵)を抱えており、朝廷や幕府に対して力づくで要求を通そうとすることがありました。
奈良の興福寺と比叡山延暦寺は「南都北嶺」と呼ばれ、とくに強い影響力をもっていました。こうした寺院の横暴に対し、泰時は僧たちに武器を捨てさせ、不当な要求をやめさせようとしたのです。宗教の力にも屈せず、法と秩序を守る姿勢を貫いた泰時の強い信念がうかがえます。*1)
人格的に高く評価された
北条泰時は優れた人格者としても知られています。鎌倉時代に書かれた『沙石集』には、以下のようなエピソードが記されています。
「下総の御家人と代官が争いごとをしていた際、議論の末に御家人の誤りが明らかになり、彼は素直に負けを認めました。泰時はその正直さに深く感動し、涙ながらに称賛するとともに、御家人の滞納していた年貢の半分を免除しました。」*5)
この話から、北条泰時が道理を重んじると同時に、人の誠実さを評価する優しい心を持っていたことがうかがえます。『沙石集』の著者である無住は、この出来事を「負けたればこそ勝ちたれの風情」と評し、正直に非を認めることの大切さを説いています。
こうした泰時の行動は、当時や後世の武士たちに大きな影響を与えたかもしれません。
泰時の死は後鳥羽上皇の祟り?
1241年、北条泰時は病に倒れました。幸い一度は回復したものの、このときすでに自分の命が長くないことを感じていたのかもしれません。翌年、泰時は静かに出家し、「上聖房観阿(じょうしょうぼうかんあ)」と名を改めます。しかしそのわずか1か月後、1242年6月15日、60歳で生涯を終えました。
このとき、世の人々の間である噂が広がります。「泰時の死は、承久の乱で敗れた後鳥羽上皇の祟りではないか」というのです。というのも、泰時が亡くなった日が、奇しくも承久の乱で彼が宇治川を突破し、勝利を決定づけた日と同じ6月15日だったからです。偶然とは思えない一致に、人々は恐れと畏敬の念を抱きました。
しかし、史料をたどると実際の死因は迷信とは無関係のようです。当時の公家の日記によれば、泰時は長年の働きすぎに加え、赤痢による高熱で衰弱していたと記されています。その症状は、かつて高熱で亡くなった平清盛にも似ていたといわれます。
さらに一説では、皇位継承に関わったことを深く気に病み、心をすり減らしていたとも伝わります。名執権・北条泰時の最期には、政治と信仰、そして人々の想いが複雑に交差していたのです。
北条泰時が行ったこと

ここでは、条泰時がどのようなことを行ったのかについて、年表形式でまとめます。
| 1183年 | 北条義時の子として誕生 |
| 1194年 | 源頼朝を烏帽子親として元服 |
| 1199年 | 源頼朝死去 |
| 1204年 | 2代将軍源頼家死去 |
| 1213年 | 和田合戦で幕府を守備する活躍 |
| 1219年 | 従五位下駿河守に任じられる3代将軍源実朝が死去 |
| 1221年 | 承久の乱で幕府軍の総大将として上洛 |
| 1224年 | 父義時の死で鎌倉に戻り、3代執権となる |
| 1225年 | 北条政子死去評定衆を設置 |
| 1232年 | 御成敗式目を制定 |
| 1242年 | 四条天皇死後の皇位継承に介入北条泰時死去 |
北条泰時は、鎌倉幕府の政治を安定させ、より公正で秩序ある社会を築いた人物です。承久の乱では的確な判断で勝利に貢献します。父・北条義時の死後、幕府の中心に立ち、混乱する政局を冷静にまとめ上げました。その後は「評定衆」を設けて話し合いによる政治を実現します。
さらに、武士の行動の基準となる日本初の法律「御成敗式目」を制定し、公正な裁きを制度として確立しました。幕府の権威を確立させた泰時の政治は、後の時代にも大きな影響を与えました。
承久の乱で活躍
承久の乱(1221年)は、後鳥羽上皇が鎌倉幕府を倒そうとして起こした戦いです。このとき北条泰時は、幕府軍の総大将として重要な役割を果たしました。上皇側が義時追討の命を出すと、泰時は叔父の北条時房とともに19万の大軍を率いて京都へ進軍します。
泰時は冷静で的確な判断を下し、宇治川の戦いでは上皇軍の防衛線を突破して勝利を決定づけました。結果、幕府軍は圧倒的な勝利を収め、後鳥羽上皇は隠岐へ流されます。
この戦いによって公家の力は大きく衰え、北条氏を中心とした幕府の支配体制が全国に広がりました。泰時の活躍は、鎌倉幕府の権威を確立させる大きな転機となったのです。乱の終結後、北条泰時は六波羅探題として事後処理に当たりました。*7)
父の死で執権になる
承久の乱後も京都にとどまって戦後処理を行っていた泰時のもとに、父である執権北条義時の死が伝えられると、鎌倉に戻ります。北条氏の家督を相続した泰時は3代執権に就任します。当時、泰時は42歳でした。翌年に北条政子が死去すると、名実ともに泰時が鎌倉幕府のトップとなったのです。
評定衆を設置
評定衆(ひょうじょうしゅう)とは、北条泰時が鎌倉幕府の政治をより公正で安定したものにするために設けた合議制の機関です。
1225年(嘉禄元年)、泰時は叔父の北条時房を補佐役(連署)とし、有力な御家人や学識のある文官11人を任命して「評定衆」を設置しました。これにより、幕府の重要な決定は一人の独断ではなく、複数の意見を出し合って判断する合議制へと変わりました。
評定衆の会議である「評定」は幕府政治の最高の議決機関とされました。構成員には北条氏の一族や三浦氏・安達氏などの有力武士、そして三善氏・二階堂氏といった文筆官僚も参加し、武と知の両面から政治を支えました。
泰時のこの制度は、独裁を避け、意見を尊重し合う政治の基盤を築いたものといえるでしょう。
御成敗式目の制定
御成敗式目は、1232年(貞永元年)に北条泰時が制定した、鎌倉幕府の基本となる法律です。「貞永式目」「関東御式目」とも呼ばれ、守護や地頭の役割、土地の支配、訴訟や処罰の方法など、武士の社会に必要な決まりごとを51か条にまとめたものでした。
この法律をつくった目的は、裁判を公正に行うためにあらかじめ判断の基準を示し、御家人たちが安心して行動できるようにすることでした。承久の乱の後、地頭や御家人たちは全国に広がり、貴族や寺社と土地をめぐって争うことが増えていたため、統一したルールが求められていたのです。泰時は、従来の公家の法律(律令)とは異なり、武士の現実に合った新しい法の形を目指しました。
御成敗式目が制定されたことで、幕府の裁きはより公平で透明になり、武士の信頼を集めました。また、この法律は後の室町幕府や戦国大名にも受け継がれ、日本の法制度の礎となりました。
北条泰時は、権力ではなく「道理」に基づいて政治を行うことを信条としていました。御成敗式目には、人々が正しく生き、公平に扱われる社会を築きたいという泰時の強い思いが込められていたのです。
北条泰時とSDGs

北条泰時は、一人で政治を行わず、仲間と話し合って決める「合議制」を取り入れました。この姿勢は、SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」に通じています。ここでは、北条泰時とSDGsの関わりを考えます。
SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」との関わり
北条泰時の政治姿勢は、SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」に通じるものがありました。泰時は、鎌倉幕府の中心人物として絶大な権力を握りながらも、独断で物事を決めることを避け、「評定衆」という合議制の仕組みを整えました。
そこでは、有力な御家人や学識ある文官たちと意見を交わし、政治の重要な判断を話し合いによって行いました。この制度は、複数の立場や視点を尊重するという意味で、まさに「協力と連携」による統治を体現していたといえます。
また、泰時自身が思いやりのある人格者であったことも、この合議制の背景にあります。彼は家臣や庶民の声にも耳を傾け、正直で道理にかなう人を評価しました。力ではなく「道理」と「人の心」で政治を動かそうとする姿勢は、現代のリーダーシップにも通じるものがあります。
しかし、泰時の合議は現代の民主的な話し合いとは異なり、発言権をもつのは限られた上層の武士に限られていました。庶民や女性の意見が政治に反映されることはほとんどなく、平等な参加という点では中世的な限界がありました。
それでも、当時の権力構造の中で「一人の力に頼らない政治」を実現した泰時の試みは、時代を超えて協働の重要性を教えてくれます。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
今回は、北条泰時について解説しました。泰時は、鎌倉幕府の仕組みを整え、公平で安定した政治を実現した名執権です。承久の乱での活躍をはじめ、評定衆の設置によって合議による政治を行い、さらに御成敗式目を制定して武士の社会に法と秩序を築きました。
誠実で思いやりのある人柄は多くの人に慕われ、道理を重んじた政治姿勢は、現代の「協働」と「公正」の理念にも通じます。泰時の生き方は、今なお学ぶ価値のあるリーダー像といえるでしょう。
参考
*1)改定新版 世界大百科事典「北条泰時」
*2)精選版 日本国語大辞典「烏帽子親」
*3)デジタル版 日本人名大辞典+Plus「北条時氏」
*4)デジタル大辞泉「僧兵」
*5)太田丈也「『沙石集』出版考-巻一ノ九・巻三ノ二について―」
*6)日本大百科全書(ニッポニカ)「後鳥羽天皇」
*7)ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「承久の乱」
*8)山川 日本史小辞典 改定新版「御成敗式目」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。