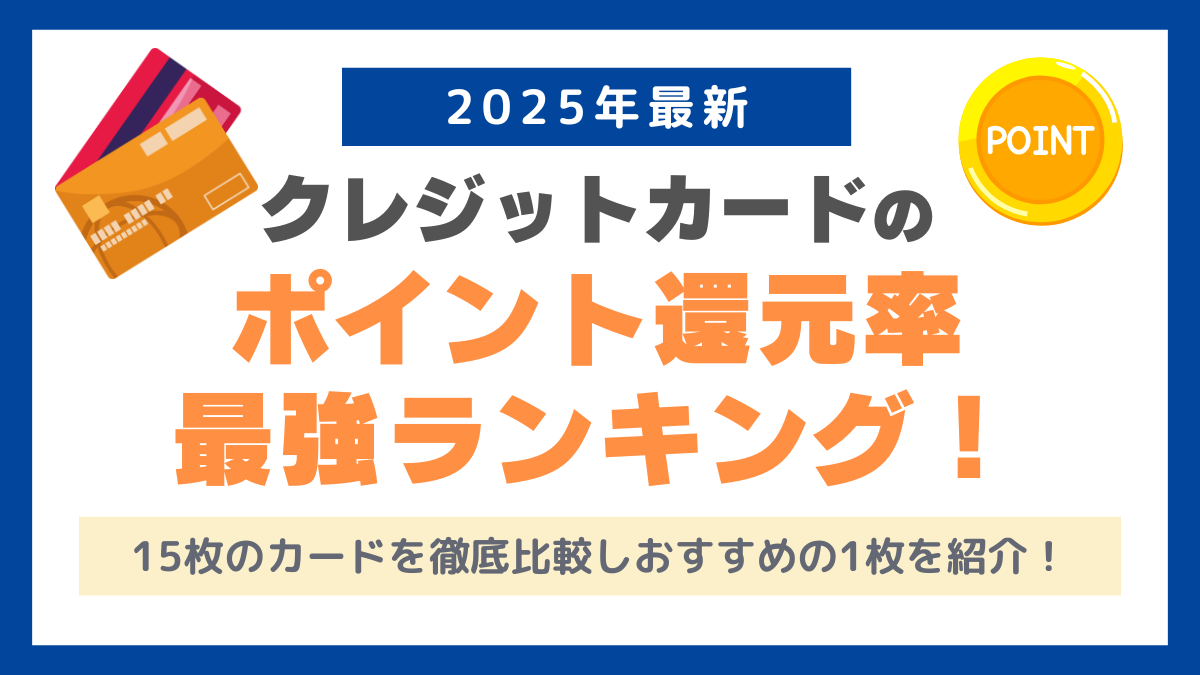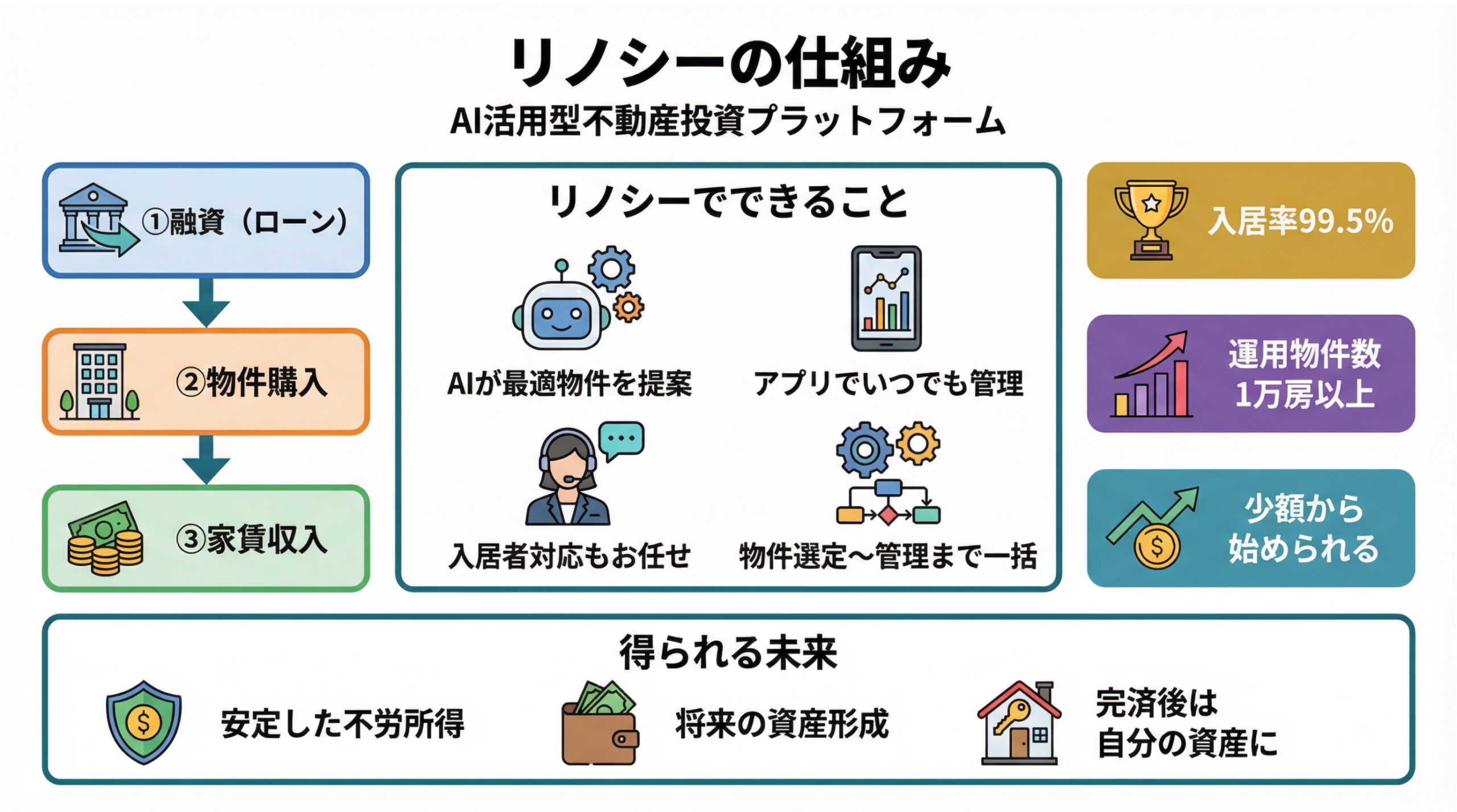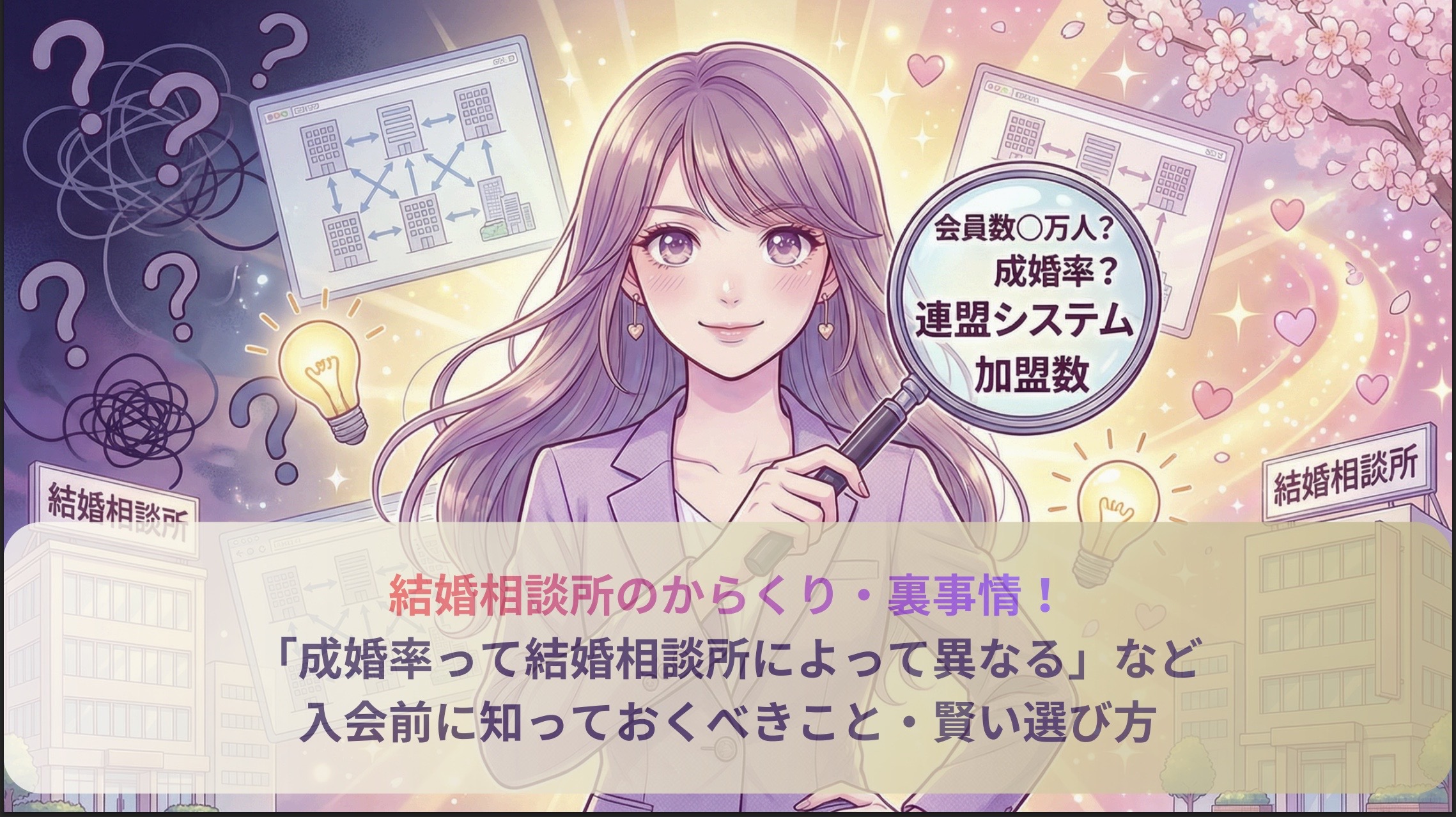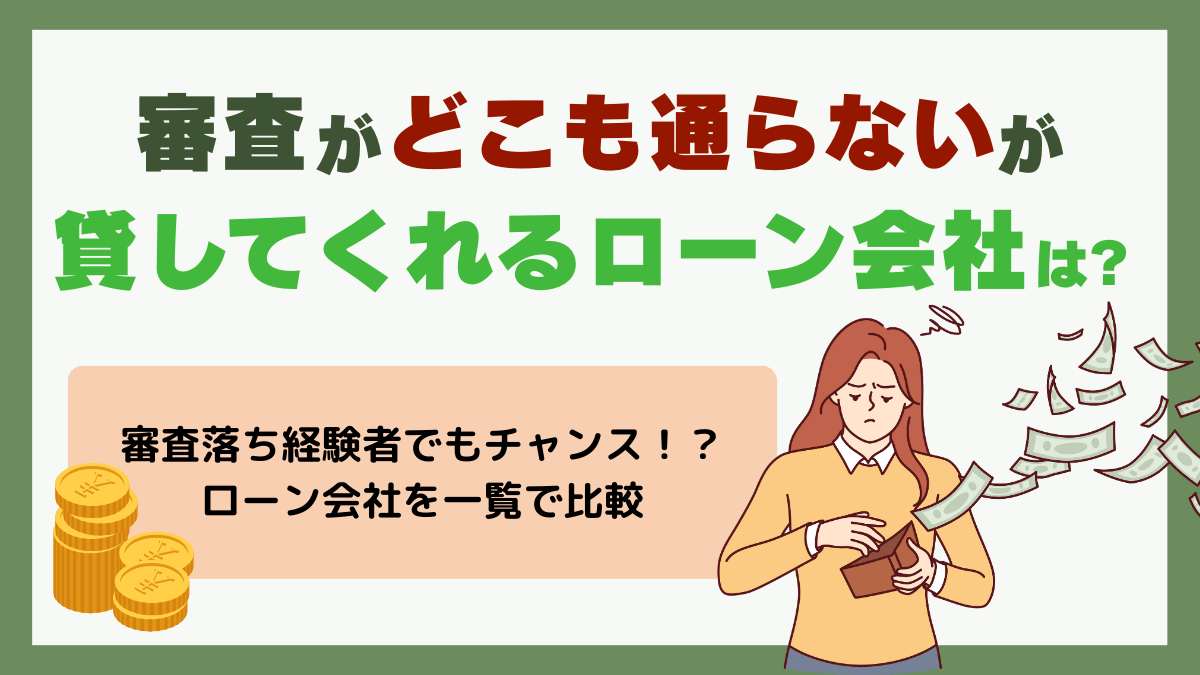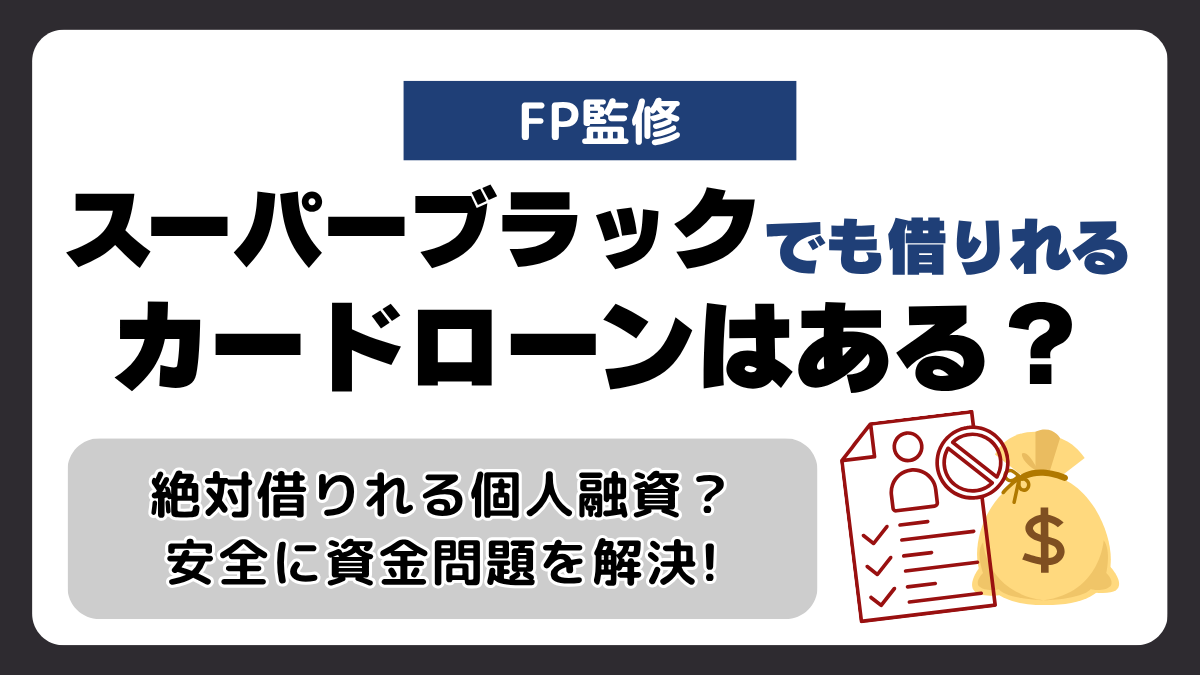マイナ保険証の利用率はいまだ30%台と低く、「マイナンバーカードに健康保険証を登録すべきか迷っている」という声が多く聞かれます。医療費の削減や薬剤情報の共有といったメリットがある一方、システムトラブルや個人情報の漏洩リスクなど、デメリットも指摘されています。
2025年夏以降、従来の健康保険証は順次、有効期限を迎える予定です。マイナ保険証の仕組みを正しく理解し、あなたと家族にとって最適な選択を見つけていきましょう。
目次
マイナ保険証とは
【マイナ保険証の使い方】
マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証としての機能を持たせ、医療機関や薬局で利用できるようにしたものです。2024年12月2日をもって従来の紙やカード型の健康保険証の新規発行は停止され、マイナ保険証が標準となります。
【令和6年12月2日から従来の健康保険証は発行されなくなりました】
ただし、発行済みの健康保険証はすぐに使えなくなるわけではありません。券面に記載されている有効期限まで利用可能です。多くの保険証は最長で2025年12月1日まで使用できますが、国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険証については、それぞれ設定された有効期限(2025年夏頃など)までとなりますので注意しましょう。
マイナ保険証の基本的な仕組み
【顔認証付きカードリーダーの例】
マイナ保険証は、マイナンバーカードのICチップに内蔵された「利用者証明用電子証明書」を用いて、
- 本人確認
- 保険資格の確認
を同時に行います。ここで重要なのは、医療機関の窓口でマイナンバー(12桁の個人番号)そのものが扱われることはない、という点です。
医療機関に設置された顔認証付きカードリーダーにカードをかざすだけで、安全なネットワークを通じて最新の保険資格が即座に確認されます。その際、暗証番号の入力が不要なため、誰でも簡単に利用できます。
万が一、暗証番号の入力を3回間違えてICチップがロックされた場合でも、お住まいの市区町村の窓口で再設定が可能です。
従来の健康保険証との主な違い
従来の保険証は、受付窓口で職員が券面情報を目視で確認し、手作業でシステムに入力していました。一方、マイナ保険証はカードリーダーによる自動読み取りのため、受付がスムーズになり、入力ミスや資格を喪失した保険証の誤使用を防ぐことができます。
また、患者側にも大きなメリットがあります。例えば、高額な医療費がかかる際に、マイナ保険証を利用して本人が同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます。
これにより、事前の申請手続きが原則不要となりました。さらに、政府のオンラインサービス「マイナポータル」を通じて、自身の薬剤情報や医療費を確認できるため、健康管理にも役立てられます。
【オンライン資格確認の導入(マイナンバーカードの保険証利用)】
導入が目指す、より良い医療の実現
マイナ保険証とオンライン資格確認の導入は、単に手続きのデジタル化だけを目的としているわけではありません。その根底には、医療現場の事務的な負担を減らし、より安全で質の高い医療サービスを全国民に提供するという大きな目標、すなわち医療DX(デジタルトランスフォーメーション※)の推進があります。
医療機関での受付業務の効率化や、正確な情報に基づく重複投薬の防止などは、その一例です。
では、なぜ国を挙げてこのような変革が進められているのでしょうか。その背景や社会的な意義について、次の章で解説していきます。*1)
マイナ保険証導入の背景
【マイナ保険証によって進む医療のDX】
少子高齢化と医療費抑制の必要性が高まる中、日本の医療システムは大幅な変革を求められています。この背景を三つの視点から整理します。
①医療DX推進による社会変革
医療DXは、保健・医療・介護の情報をクラウドで統合し、診療の質向上と業務効率化を目指す取り組みです。厚生労働省は医療DX推進工程表を策定し、マイナ保険証を基盤とした全国医療情報プラットフォームの構築を進めています。
このシステムにより、過去5年分の診療・薬剤情報や特定健診結果を医療機関間で安全に共有でき、重複検査や相互作用リスクの低減を図ります。今後は遠隔診療や在宅医療への活用拡大により、地域医療格差の解消も期待されています。
②非効率的な医療事務の改革
従来の健康保険証システムでは、転職や引っ越しによる保険変更の際、医療機関での資格確認に時間がかかり、資格過誤による返戻(保険資格の誤りによる診療報酬の差し戻し)処理が大きな問題でした。オンライン資格確認の本格導入後、令和4年10月から令和5年9月の12か月間において、前年同期間比で約81万件の資格関係返戻が削減され、医療機関の事務負担が大幅に軽減されています。
一部の小規模医療機関等には経過措置がありますが、2023年4月に導入が原則義務化された結果、ほぼ全ての医療機関において導入が進んでいます。
③不正利用防止と適正な医療提供
従来の保険証では、資格喪失後の利用やなりすましといった不適正利用が課題となっており、その対策が急務でした。一部の推計によれば、健康保険証の資格誤りや返戻件数は年間数百万件規模にのぼるとされ、返戻や事務対応全体のコストも大きな負担となっています。マイナ保険証では顔認証とICチップによる本人確認を強化し、不正請求やなりすまし受診の未然防止を目指しています。
これらの改革により、医療の質向上と制度の持続可能性を両立させる基盤の整備が進められています。次の章ではマイナ保険証のメリットに焦点を当てていきましょう。*2)
マイナ保険証のメリット
【平デジタル大臣が、スマートフォンのマイナンバーカードで受付している様子】
マイナ保険証は、患者の費用負担軽減と医療の質向上、医療現場の効率化という大きなメリットをもたらします。それぞれ具体的に見ていきましょう。
手続きの簡素化で時間と手間を節約
マイナ保険証の利用は、医療費に関する面倒な手続きを大幅に簡略化し、時間と手間の節約につながります。
特に大きなメリットは、高額な医療費がかかる際の「限度額適用認定証」の事前申請が原則不要になる点です。対応している医療機関であれば、マイナ保険証を提示して同意するだけで、自己負担限度額を超える支払いがその場で不要になります。
さらに、確定申告の医療費控除も簡単になります。マイナポータルと連携させれば、1年間の医療費情報が自動で入力されるため、領収書を一枚ずつ保管し計算する手間から解放されます。
より安全な医療と健康管理の実現
情報提供に同意すると、医師や薬剤師が過去5年分の薬剤情報や特定健診結果を閲覧できます。これにより、お薬手帳に記載のない他院処方薬の重複投与や、相互作用リスクのある組み合わせを未然に防ぎ、パーソナライズされた質の高い医療が可能になります。
受付業務の効率化と生涯利便性
顔認証付きカードリーダーで本人確認と保険資格の確認が瞬時に完了し、受付業務の手間と待ち時間を削減します。転職や引っ越しで保険者が変わっても、マイナンバーカードを保険証として継続利用でき、新たなカード発行を待つ必要がありません。
さらに、2025年7月ごろから関東圏など一部医療機関で実証実験が実施され、全国的には2025年9月頃から、機器の準備が整った医療機関・薬局から順次、スマートフォンをマイナ保険証として利用できるようになる予定です。
【スマートフォンでマイナ保険証が利用できるように】
このようなメリットにより、マイナ保険証はより質の高い医療を支えるインフラとして期待されています。*3)
マイナ保険証のデメリット・課題

マイナ保険証は多くのメリットをもたらす一方で、実際の導入や利用において様々な課題も生じています。医療現場や患者から寄せられている具体的な問題点を正しく理解することで、制度の現状を多角的に捉えることができます。
システムトラブルと技術的課題
マイナ保険証で最も頻繁に指摘されるのが、カードリーダーの技術的なトラブルです。全国保険医団体連合会(保団連)の2023年9月に公表された全国調査の結果では、8割以上の医療機関が「顔認証がうまくいかない」「カードが読み取れない」などのトラブルを経験したと報告されています。
特に問題となるのは、システム障害やメンテナンス時に全く利用できなくなることです。この場合、医療機関は「緊急時医療情報・資格確認機能(システム復旧後に患者の券面情報を用いて資格確認を行う機能)」で対応しますが、それも困難な場合、マイナ保険証しか持たない患者は一時的に医療費の10割負担を求められる事例※も発生しています。
※このような事例では、医療機関の判断により、患者に一旦医療費の全額(10割)を自己負担で支払ってもらい、後日、保険資格が確認できた際に自己負担分を除いた差額を返金(償還払い)するという対応が取られることがあります。
利用の困難さと高齢者への負担
高齢者や障害のある方にとって、マイナ保険証の利用が大きな負担となることも少なくありません。
- 車椅子の方が顔認証の位置に合わせることが困難
- 認知症の方が暗証番号を覚えられない
など、物理的・心理的な障壁が課題となっています。また、発熱外来などで院外対応する際に、持ち運び可能なカードリーダーの配備が追いついていないといった、現場ならではの問題も指摘されています。
日常での「面倒」とプライバシーへの不安
利用者からは「手続きが逆に面倒になった」という声も多く聞かれます。実際、前述の保団連の調査では約6割の医療機関が窓口業務に「負担を感じる」と回答しており、「操作ができない高齢者が多く、通常業務が中断される」などの声が寄せられています。
また、プライバシーに関する懸念も根強くあります。
- マイナンバーカードには公金受取口座の登録もできるため、重要な情報が集約されたカードを毎日持ち歩くのが心配
- 多くの個人情報が入っているカードを紛失するのが怖い
といった不安の声は、多くの人が感じているデメリットと言えるでしょう。
これらの課題に対し、国は改善を進めていますが、現時点では患者と医療現場の双方に一定の負担をもたらしているのが実情といえます。*4)
マイナ保険証の登録方法
【マイナ保険証の利用方法】
「登録手続きが難しそう」と感じている方も、ご安心ください。マイナ保険証の利用登録(申込み)は、ご自身の状況に合わせていくつかの簡単な方法から選べます。
分かりやすい順番でマイナ保険証の登録方法を確認していきましょう。
一番簡単:医療機関や薬局の窓口で登録
【顔認証付きカードリーダーでの利用登録】
最も簡単で確実なのが、病院や薬局に行った際に、その場で登録する方法です。受付にある顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置き、画面の指示に従うだけで登録が完了します。
操作が分からなくてもスタッフが補助してくれるため、デジタル機器が苦手な方に最適です。ただし、一部の小さなクリニックなどでは、まだカードリーダーが設置されていない場合もあります。
24時間いつでも:セブン銀行ATMで登録
【セブン銀行ATMからの申請】
全国のセブン銀行ATMでは、24時間いつでも登録手続きができます。必要なものはマイナンバーカードと4桁の暗証番号(カード受取時に設定したパスワード)のみです。
画面の案内に従って操作するだけで、簡単に手続きが完了します。
スマートフォンやパソコンが得意な方向けの方法
【マイナポータルから申請】
スマートフォンやパソコンの操作に慣れている方は、政府のウェブサイト「マイナポータル」からご自宅で登録することも可能です。現在はスマートフォン※があれば、パソコンでも特別な機器を購入する必要がありません。
詳しい手順はマイナポータルの公式サイトに分かりやすい案内がありますので、そちらを参照してください。
※スマートフォン対応機種:NFC対応Android、iOS16以上のiPhone8以降
【事前に準備するもの】
どうしても難しい場合は自治体の支援も
上記の方法がどうしても難しいと感じる場合でも、諦める必要はありません。多くの自治体では、高齢者などを対象に職員が登録をお手伝いする「出張申請サポート」や、専門の相談員がいる窓口を設けています。
不安な場合は一人で悩まず、居住地の市区町村の役所に問い合わせてみることをお勧めします。
これらの方法から、ご自身に最も適した手段を選んでみてください。一度登録すれば、その後の医療機関での受付がよりスムーズになります。*5)
マイナ保険証に関してよくある疑問
【マイナ保険証が使える医療機関・薬局の目印】
マイナ保険証について様々な疑問をお持ちの方が多いのではないでしょうか。ここでは、多く寄せられる疑問や質問とその回答を、分かりやすくまとめました。
廃止になる可能性はある?
現在のところ、政府は2025年12月1日までに従来の健康保険証を廃止し、マイナ保険証への移行を完了させる方針を継続中です。政治的な情勢により、延期の議論が継続的に行われていますが、現段階では予定通りに進んでいます。
義務化される?
マイナンバーカードの取得自体は任意であり義務ではありません。マイナ保険証を利用しない場合は「資格確認書」が発行され、従来の保険証と同様に医療機関で使用できます。
マイナ保険証に登録しないとどうなる?
登録しなくても医療を受けることはできます。マイナンバーカードを持っていない方や利用登録していない方には、保険者から「資格確認書」が自動的に交付され、これを医療機関の窓口で提示すれば保険診療を受けられます。
【資格確認書の見本】
マイナ保険証の登録に必要なものは?
マイナンバーカードと4桁の利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)のみです。健康保険証は不要で、
- 医療機関の顔認証付きカードリーダー
- セブン銀行ATM
- マイナポータル
から簡単に登録できます。
暗証番号を忘れたり、ロックされた場合はどうすればいい?
お住まいの市区町村の窓口で利用者証明用電子証明書パスワードの初期化・再設定を行ってください。
マイナ保険証を紛失したらどうなる?
すぐに、
- マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に連絡してカードの一時利用停止
- 警察に遺失届または盗難届を提出
をしてください。その後、お住まいの市区町村で再発行手続きを行います。カードが悪用される可能性は低いものの、迅速な対応が重要です。
家族(子ども・高齢者)も同じカードで利用できる?
マイナンバーカードは個人ごとに発行されるため、家族間でも別々のカードが必要です。ただし、保育園などでは事前にダウンロードした資格情報を印刷物として提示することも認められています。
転職や引っ越しで保険者が変わっても使い続けられる?
一度登録すれば、転職や引っ越しで保険者が変わっても新たな手続きは不要です。自動的に新しい保険資格情報に更新されるため、そのまま継続して利用できます。
退職後・国保加入時の登録変更手続きは?
特別な手続きは不要です。退職により健康保険が変わっても、マイナ保険証の利用登録は自動的に新しい保険資格に紐づけられます。
国民健康保険に加入した場合でも同様に継続利用できます。
緊急時(災害・システム障害)に利用できないことは?
システム障害時には「緊急時医療情報・資格確認機能」により対応しますが、それも困難な場合は一時的に10割負担となることがあります。災害時や停電時にも利用できない場合があるため、資格確認書との併用が推奨されます。
マイナポータル連携による医療費控除の活用方法は?
マイナポータルと連携すれば、2021年9月以降の医療費通知情報を確定申告書に自動入力できます。家族の医療費も代理人登録により一括取得可能で、医療費控除の申請が大幅に簡素化されます。
マイナ保険証にすると、医療費が安くなるって本当?
2024年12月以降は医療費に差はありません。従来は初診料で6円程度安くなっていましたが、診療報酬改定により現在は一律となっています。
ただし、限度額適用認定証の自動適用などの利便性は維持されます。
このように、様々な場面を想定した仕組みが整えられています。不明な点・よくわからない点があれば、お住まいの市区町村の窓口に相談してみましょう。*6)
マイナ保険証とSDGs

マイナ保険証の導入は、単なる保険証のデジタル化に留まらず、SDGsが目指す「誰一人取り残さない」持続可能な社会の実現と深く連動しています。医療データの活用による健康格差の解消や、デジタル技術を通じた国際的な医療連携の基盤づくりは、持続可能な開発目標の達成に不可欠な取り組みです。
マイナ保険証は医療DX推進の起点として、効率的で公平な医療システムの構築を目指し、将来世代にとって持続可能な社会保障制度の確立に貢献します。これらの取り組みがSDGsの複数の目標達成にもたらす効果を見ていきましょう。
SDGs目標3:すべての人に健康と福祉を
マイナ保険証は、医療アクセスの平等化と医療の質向上に大きく貢献します。オンライン資格確認により、患者の過去の薬剤情報や特定健診データが医療機関間で共有できるため、重複投薬の防止や適切な診療が可能になります。
特に、地方や過疎地域における医療格差の解消に向けて、遠隔医療や電子処方箋システムとの連携し、居住地に関係なく質の高い医療が受けられる環境整備が進んでいます。また、マイナポータルを通じた健康情報の一元管理により、個人の予防医療や健康管理の質が向上し、生活習慣病の予防や重症化防止にも寄与します。
SDGs目標10:人や国の不平等をなくそう
デジタル技術を活用した医療システムは、経済状況や地理的条件による医療格差の是正に重要な役割を果たします。マイナ保険証により、都市部と地方の医療機関が同じ基準でデータを共有できるため、医療の地域格差縮小が期待されます。
高額療養費制度の自動適用機能も、経済的負担による受診控えを防ぎ、所得格差による健康格差の解消に貢献しています。
SDGs目標17:パートナーシップで目標を達成しよう
マイナ保険証を起点とした医療DXは、政府・自治体・医療機関・民間企業・市民社会が連携した包括的な取り組みです。全国医療情報プラットフォームの構築により、異なる組織間での情報連携が促進され、持続可能な医療システムの実現に向けたマルチステークホルダー・パートナーシップが形成されています。
このような医療分野でのデジタル基盤整備は、他国への技術移転や国際的な医療協力の基盤ともなり、グローバルな健康課題解決に向けたパートナーシップ強化にも寄与する可能性があります。
これらの取り組みを通じて、マイナ保険証は単なる行政手続きのデジタル化を超えて、持続可能な社会の実現に向けた重要な社会インフラとしての役割を担っています。*7)
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
【マイナ保険証の使い方まとめ】
マイナ保険証は、従来の健康保険証に代わる新たな医療基盤として、効率化と安全性の向上を目指しています。2024年12月に従来の保険証の新規発行が停止され、最長1年の経過措置期間が終了に近づく中、マイナ保険証普及にあたっての最重要課題は医療アクセスの平等性確保と制度への信頼回復です。
最新の動向を見ても、厚生労働省が発表した2025年6月のマイナ保険証利用率は30.64%に留まっています。このような状況から、8月以降に多数の国民健康保険証が有効期限切れを迎える問題に対応し、期限切れの保険証でも2026年3月まで受診可能とする暫定措置が導入されました。
これは制度移行の複雑さと国民の不安を物語っており、技術的課題と社会的受容の両面での改善が急務であることを示しています。
高齢者や障害者、また、デジタルリテラシーの低い人にとって、この変化は医療アクセス権に直結する、大きな不安要素となっています。国際的にも注目される日本のこの取り組みは、包摂的なデジタル社会実現のモデルケースとして注目されています。
このような状況の中で、私たちに求められるのは、この制度を単なる行政手続きではなく、より良い医療社会実現への参加として捉えることです。また、できる範囲で周囲に目を向けることも心がけましょう。
あなたの家族や地域の高齢者は、この変化にどのような不安を抱いているでしょうか?そして、私たち一人ひとりは、デジタル格差を埋めるためにどのような支援ができるでしょうか。
制度の完璧性を求めるだけではなく、共に学び、支え合う社会を築くことこそが、真の持続可能な医療システム構築への第一歩となります。変化を恐れず、しかし誰も置き去りにしない未来を、協力して創り上げていきましょう。*8)
<参考・引用文献>
*1)マイナ保険証とは
マイナポータル『マイナンバーカードの健康保険証等利用がはじまりました。』
厚生労働省『医療機関等を受診の際はマイナンバーカードをご利用ください』(2025年1月)
デジタル庁『マイナンバーカードの健康保険証利用』(2025年3月)
厚生労働省『オ ン ラ イ ン資格確認 の導入 で事務 コ ス ト の削減 と よ り良 い医療 の提供 を~ デ ー タ ヘ ル ス の基盤 と し て~』(2023年4月)
政府広報オンライン『マイナ保険証 2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ』(2025年5月)
厚生労働省『マイナンバーカードの健康保険証利用について』
デジタル庁『マイナンバーカードの健康保険証利用』(2025年3月)
デジタル庁『8月以降順次切り替え!健康保険証の注意点は?(後期高齢者医療制度・国民健康保険の被保険者の方)』(2025年7月)
マイナポータル『マイナンバーカードの健康保険証等利用がはじまりました。』
Wikipedia『マイナ保険証』
*2)マイナ保険証導入の背景
厚生労働省『医療DXについて』
総務省『行政のデジタル化と基盤としてのマイナンバー制度』
政府広報オンライン『医療のデジタル化~マイナ保険証~』(2024年7月)
厚生労働省『デジタル庁と共同開催!医療機関・薬局向けマイナ保険証利用促進セミナー』
厚生労働省『保険証認証のためのデータ交換基準に関する研究(総括研究報告書)』
デジタル庁『自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)』(2025年8月)
デジタル庁『マイナポータルの機能追加について』(2021年11月)
デジタル庁『「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました』(2025年3月)
全国保険医団体連合会『マイナカードで「不正請求が減らせる」「なりすまし防止」は本当か』
全国保険医団体連合会『【平デジタル相】不正利用の実態調査なし 「可能性」だけで保険証廃止するの?』(2024年10月)
ビジネス+IT『マイナ保険証は誰のため? なぜ政府は普及を急ぐ? 理解できない“不合理”政策の謎』(2023年8月)
*3)マイナ保険証のメリット
デジタル庁『平デジタル大臣・福岡厚生労働大臣が、スマートフォンをマイナ保険証として利用可能とする実証事業を視察しました』(2025年7月)
厚生労働省『スマートフォンのマイナ保険証利用について』
厚生労働省『マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット』
厚生労働省『マイナンバーカードで受診をすると、どんないいことがありますか?』
全国保険協会『これからは、マイナンバーカードを持っていけば、「マイナ保険証」として使用いただけます。』
全国健康保険協会『今から使おう!マイナ保険証』
日本経済新聞『マイナ保険証移行で医療DX参入の波 DeNAやサイバー』(2025年1月)
NTT DOCOMO BUSINESS『マイナ保険証移行のタイムリミット迫る!「医療DX」が国民にもたらすメリットとは』(2024年9月)
Jin Clinic『なぜ保険証をマイナンバーカードに変えるのか?元厚生労働省室長が、その先の医療DXを解説』(2024年5月)
*4)マイナ保険証のデメリット・課題
Yahoo!ニュース『「紛らわしい」の声も…「資格確認書」&「資格情報のお知らせ」の“違い”とは?【マイナ保険証】』(2025年8月)
Yahoo!ニュース『マイナ保険証 有効期限切れトラブル急増 なぜ?利用率は低迷のまま 医療現場の実情』(2025年5月)
Yahoo!ニュース『なぜ「日本人の命を人質」にマイナ保険証強制か? 「官公庁の末端入力作業は中国人」と知りながら』(2024年12月)
Google Play『マイナポータル』
全国商工団体連合会『マイナ保険証作りたくない…!これまでの健康保険証は使えない?
資格確認書って?登録解除も!QA解説! <全国商工新聞より>』
全国商工団体連合会『保険証廃止は事実上のマイナカード強制になるのでは? 河野大臣「まったくならない」』(2024年8月)
日経XTECH『マイナ保険証ひも付け作業の実態と、誤登録が続発する「なぜ」』(2023年8月)
*5)マイナ保険証の登録方法
厚生労働省『マイナンバーカードの健康保険証利用方法』
厚生労働省『スマートフォンのマイナ保険証利用について』
厚生労働省『カンタン!便利!マイナンバーカードの健康保険証利用』
厚生労働省『マイナンバーカードの健康保険証利用方法』
厚生労働省『スマートフォンのマイナ保険証利用について』
厚生労働省『9月からマイナ保険証がスマホでも使えます』
デジタル庁『マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード』(2025年7月)
デジタル庁『マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法』(2024年7月)
デジタル庁『資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)』(2024年11月)
マイナポータル『04 健康保険証情報を確認する』
デジタル庁『8月以降順次切り替え!健康保険証の注意点は?(後期高齢者医療制度・国民健康保険の被保険者の方)』(2025年7月)
全国健康保険協会『今から使おう!マイナ保険証』
全国健康保険協会『マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方)』
*6)マイナ保険証に関してよくある疑問
マイナポータル『マイナンバーカードの健康保険証等利用がはじまりました。』
厚生労働省『マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問』
デジタル庁『よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について』(2025年3月)
全国商工団体連合会『マイナ保険証作りたくない…!これまでの健康保険証は使えない?
資格確認書って?登録解除も!QA解説! <全国商工新聞より>』
マイナポータル『マイナンバーカード(健康保険証)は、受診の度に提示が必要ですか。』(2022年12月)
日経XTECH『「マイナ保険証」で何が変わる? 10の疑問を徹底解説』(2024年11月)
*7)マイナ保険証とSDGs
厚生労働省『医療DXについて』
経済産業省『新しい健康社会の実現』(2024年2月)
全国健康保険協会『協会けんぽとSDGs』
東京財団『地域に根ざした医療DXの実装に向けた人材開発に関する政策提言』(2025年3月)
NTT DATA『医療・製薬のDXが実現する患者体験(Medical Experience)の変革』
Fujitsu『医療DXでクリニックはどう変わる?~国策動向から導入効果まで徹底解説~』(2025年5月)
*8)まとめ
厚生労働省『医療機関等を受診の際はマイナンバーカードをご利用ください』(2025年1月)
デジタル庁『マイナ保険証に関する現状』
日経メディカル『医療DX推進体制整備加算、マイナ保険証利用率の要件を段階的に引き上げへ』(2025年7月)
日本経済新聞『マイナ保険証、医療DXの基盤に 免許証も一体化前倒し』(2022年10月)
NTT『マイナ保険証の影響とは?自治体の対応事項とアウトソーシングの重要性』(2025年1月)
日経XTECH『生活者の4割は「医療DX」をイメージできず、データ活用のメリットを周知せよ』(2024年2月)
日本経済新聞『マイナ保険証移行へ対策腐心』(2024年11月)
この記事を書いた人
松本 淳和 ライター
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。