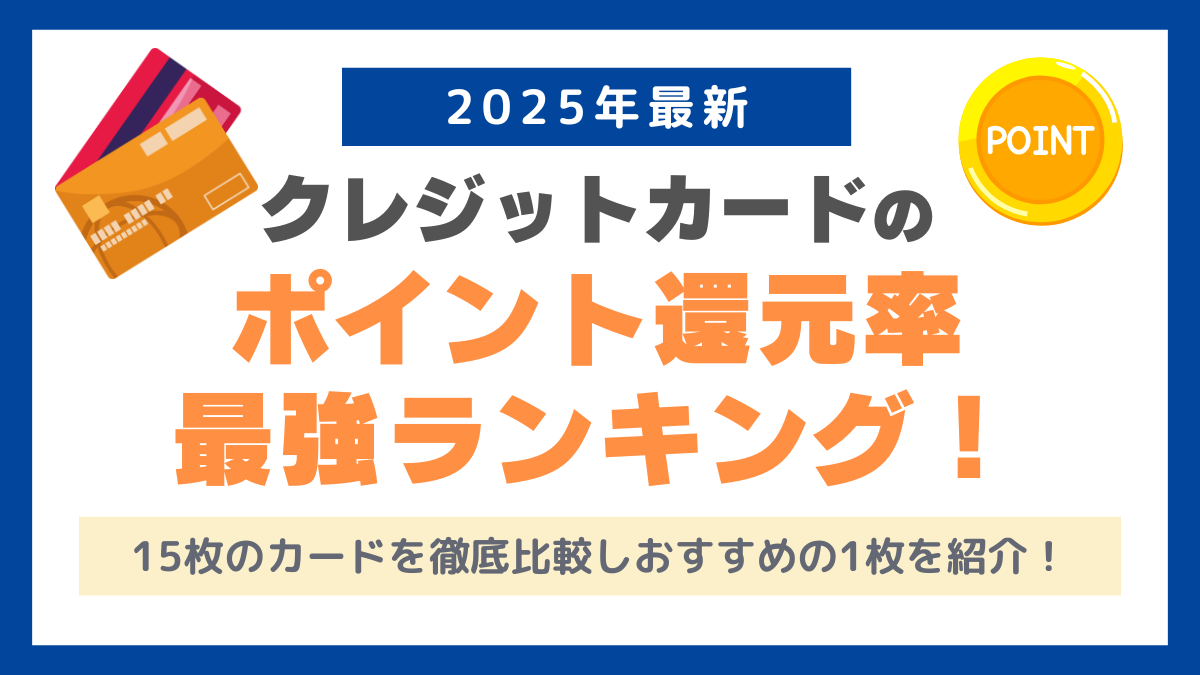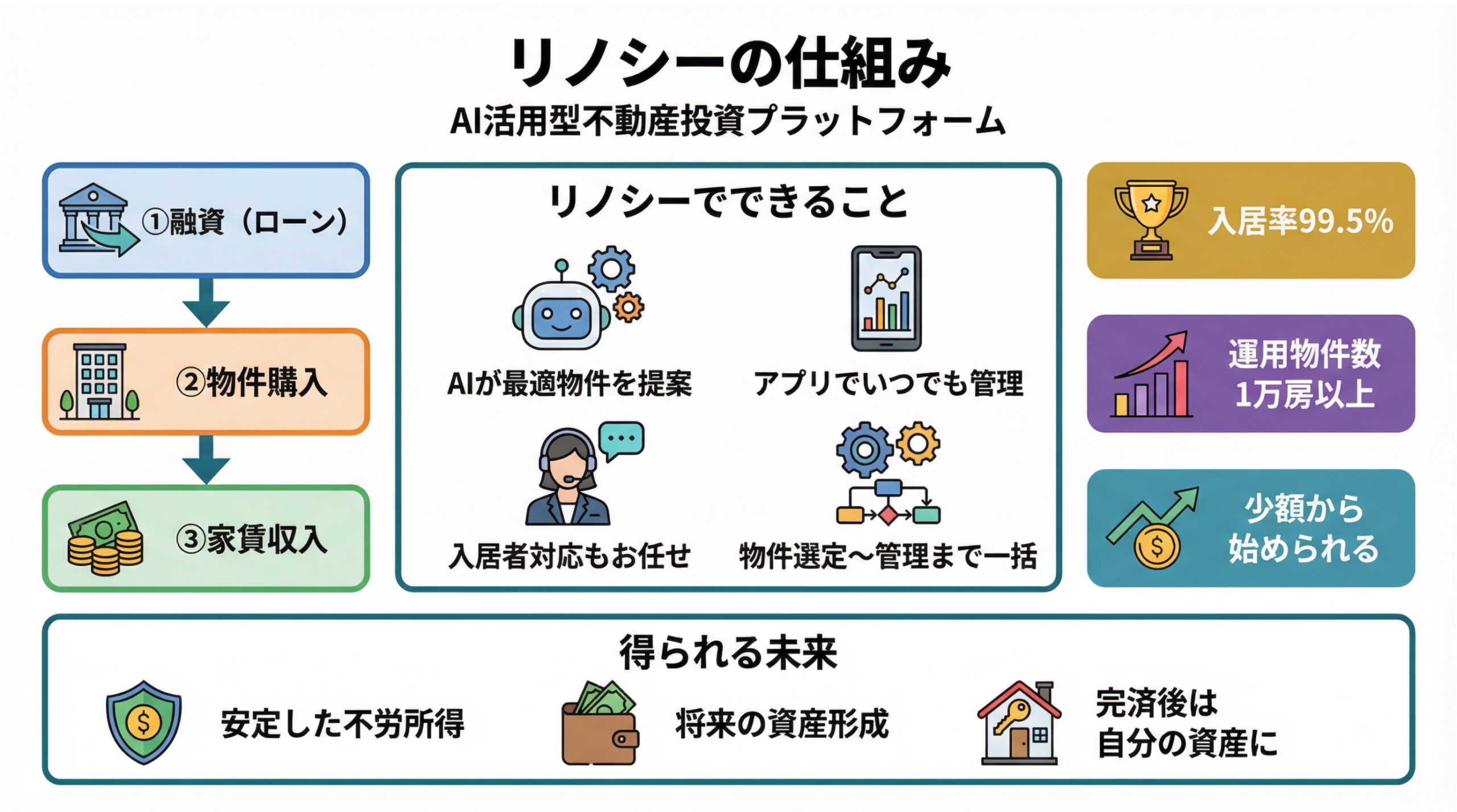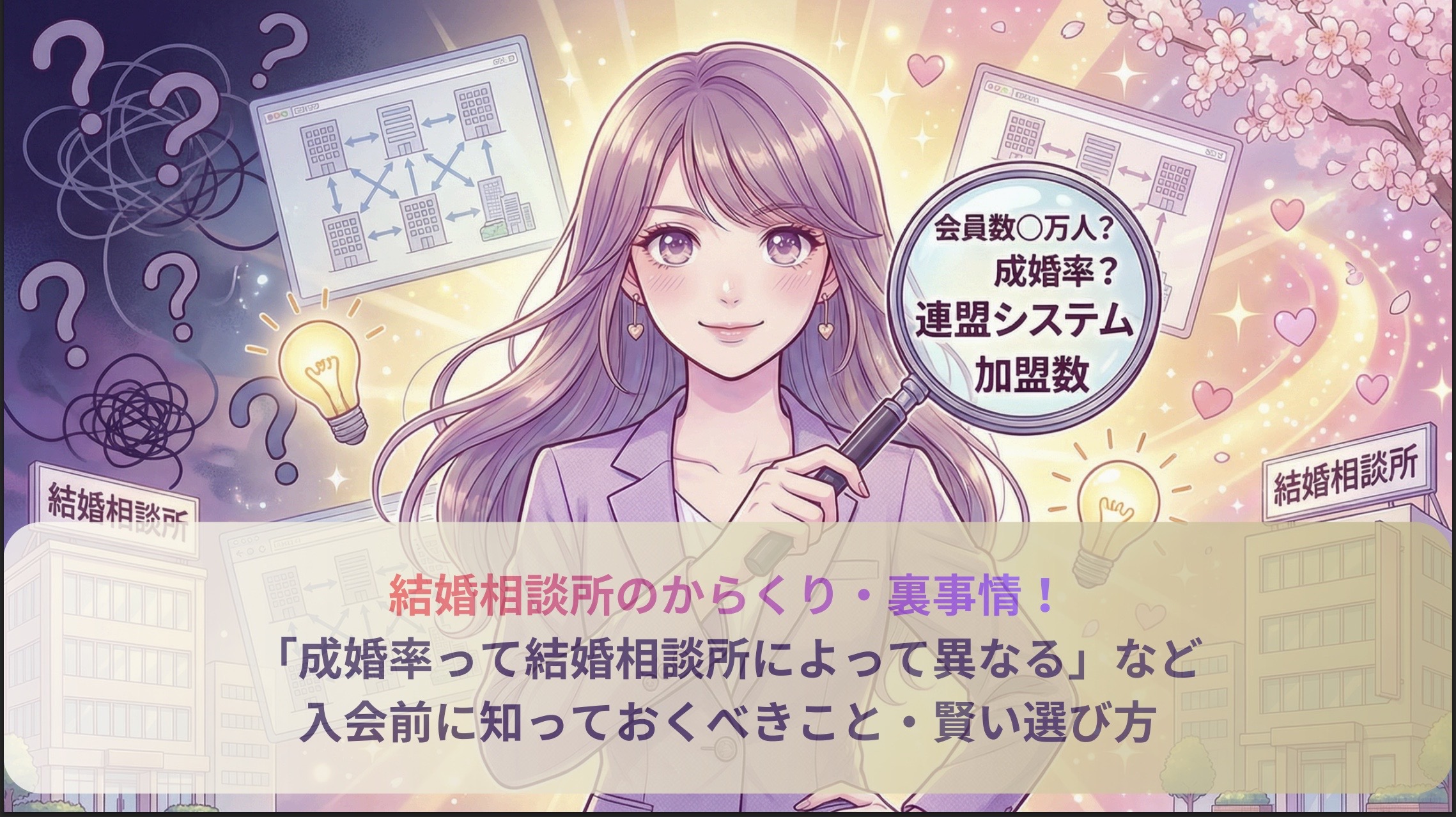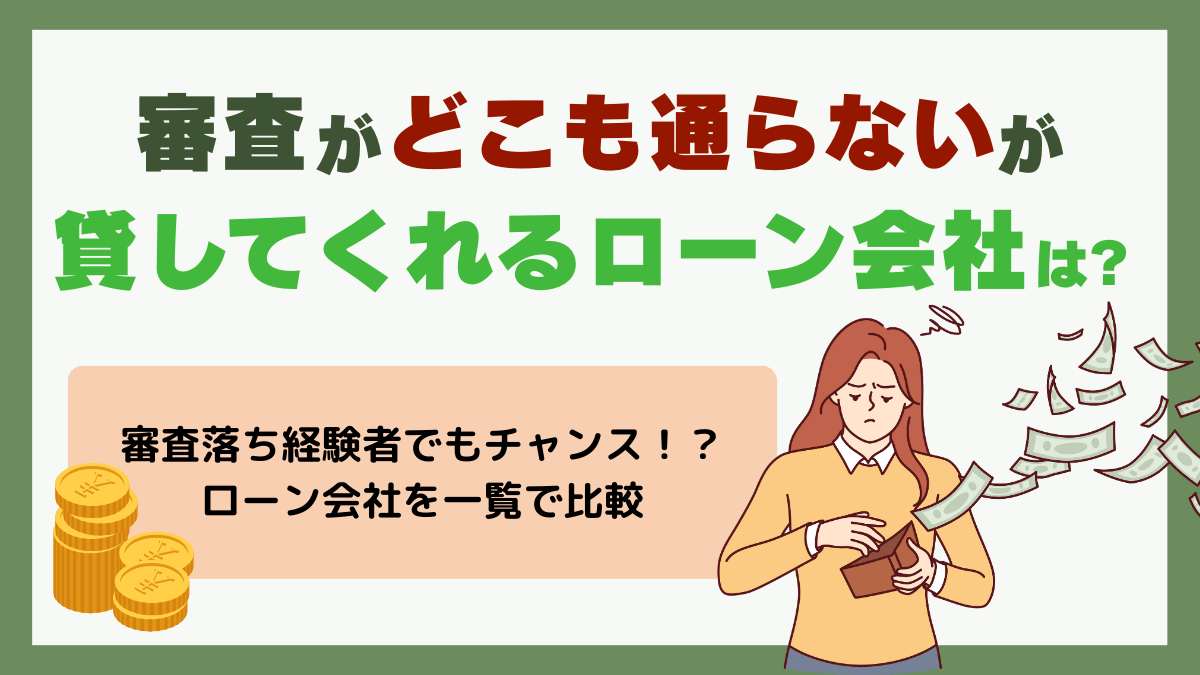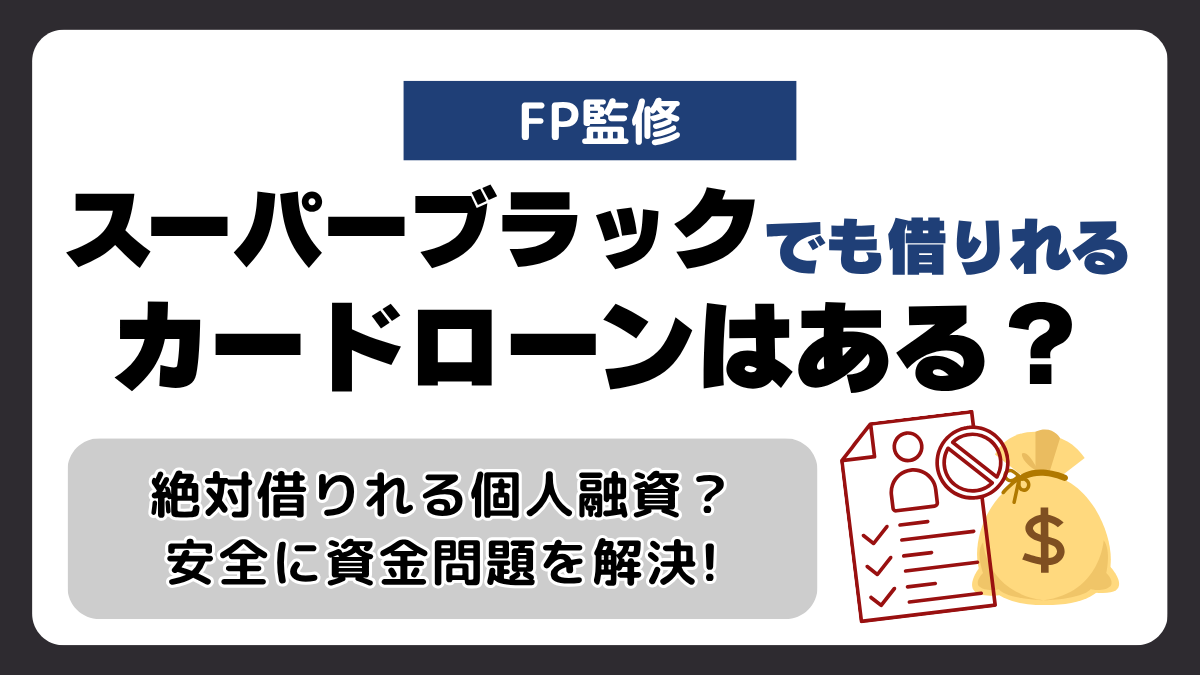地球の表面の約7割を占める海には、波や潮の流れ、温度差など、膨大なパワーが秘められています。これらの自然の力を電気に変換する技術が「海洋エネルギー」です。
波力、潮流、海流、温度差など多様な方式があり、枯渇の心配がなく環境への負荷も少ないことから、持続可能な発電方法として世界中で注目を集めています。
四方を海に囲まれた日本にとっては特に有望な選択肢であり、安定した電力供給や淡水生成といった副次的効果も期待できます。
ただし、漁業との共存や初期投資の高さなど、解決すべき課題も存在します。本記事では、海洋エネルギーについて様々な角度からわかりやすく解説します。
目次
海洋エネルギーとは?
海洋エネルギーとは、広大な海に蓄積された自然の力を活用する環境配慮型の発電手法です。波や潮の流れ、温度の違いなど様々な形で存在するこれらの資源は、石油や石炭に代わる次世代の電力源として期待されています。
生み出された電気は水素製造にも応用可能で、持続可能なエネルギー社会への転換を促進する重要な要素となっています。現在も多方面での研究開発が進み、地球環境を守りながら私たちの暮らしを支える新たな可能性を拓いています。
海洋エネルギーは再生可能エネルギー
海洋エネルギーは、再生可能エネルギーです。再生可能エネルギーとは、太陽光や風力など自然界に存在し、使っても枯渇せず繰り返し利用できる持続可能な資源です。温室効果ガスを出さず、国内生産が可能な環境に優しいエネルギー源として、将来の主力電源化が期待されています。*2)
海洋エネルギーの種類と仕組み

海洋エネルギーには多様な形態があり、それぞれ独自の仕組みで電力を生み出します。ここでは、以下の2点について解説します。
- 海洋エネルギーの種類
- 各発電方法の仕組み
詳しく見ていきましょう。
海洋エネルギーの種類
海洋エネルギーにはいくつかの種類がありますが、ここでは主な5種類についてまとめます。
| 発電方法 | 説明 |
| 洋上風力発電 | 海上の風の力で発電 |
| 波力発電 | 波の運動エネルギーで発電 |
| 潮流発電 | 潮流を利用して発電 |
| 海洋温度差発電 | 海の温度差を利用して発電 |
このほかにも、海洋濃度差発電や海洋エネルギーで水素を生成する水素エネルギー発電などの研究が進められています。*1)
各発電方法の仕組み
簡単に、各発電方法の仕組みを紹介します。
| 発電方法 | 説明 |
| 洋上風力発電 | 海上に風力発電施設を設置風の力でタービンを回して発電 |
| 波力発電 | 波の上下運動を利用運動エネルギーを電力に変換 |
| 潮流発電 | 潮流の速い場所に設置水車を回転させて発電 |
| 海洋温度差発電 | 表層の温かい水と深層の冷たい水の温度差を利用熱交換器やタービンで発電 |
*3)
どの発電方法も、海の自然の力を利用しているため、化石燃料のような枯渇を心配する必要がありません。
海洋エネルギーが注目されている理由

海に存在する膨大なパワーである海洋エネルギーを活用した発電は、全世界的に注目を浴びています。注目されている理由は以下の3つです。
- クリーンなエネルギーだから
- 安定して発電できるから
- 副産物で淡水が得られる可能性があるから
注目されている理由を掘り下げます。
クリーンなエネルギーだから
海洋エネルギーは、二酸化炭素(CO2)を排出しないクリーンな自然エネルギーです。地球温暖化を防止するために、環境にやさしいエネルギーの開発が進められており、太陽光や風力と並んで注目されているのです。
日本は四方を海に囲まれており、海は半永久的に利用可能な無限のエネルギー源として期待されています。海洋エネルギーは、環境負荷を抑えつつ持続可能なエネルギー供給を可能にし、地球温暖化対策への貢献が期待されているのです。*4)
安定して発電できるから
海洋エネルギーが注目されている理由の一つは、「安定して発電できる」ことにあります。特に潮力発電や海洋温度差発電は、天候に左右されにくく、季節や昼夜の変動も小さいため、安定した電力供給が可能です。
例えば、海洋温度差発電は昼夜の別なくほぼ一定の温度差を利用し、設備利用率は約88%と非常に高い安定性を持ちます。潮力発電は満ち引きの規則的な潮汐を利用し、年間を通じて安定した電力を供給できる点がメリットです。*5)
また、波力発電も波が完全に止むことはほぼなく、天候の影響も他の再生可能エネルギーに比べて小さいため安定した発電が可能です。これらの特性は、変動の大きい太陽光や風力発電に対して大きな強みとなり、電力系統のバランスを保ちやすく、都市部や大規模需要への対応も期待されています。
副産物で淡水が得られる可能性があるから
海洋エネルギーの一つである海洋温度差発電の場合、表層の暖かい水と深層の冷たい水の温度差を利用する過程で、貴重な真水を得られることが大きな魅力です。暖かい海水を蒸発させて発電した後、その蒸気が凝縮されることで、塩分のない水が生成されます。*6)
この純水は飲料用や農業用として活用可能で、特に水源が限られた島々では重要な資源となります。また、冷たい深層水を活用した冷房システムや、栄養豊富な海水を利用した魚の養殖なども併せて実現できる総合的なシステムとして評価されています。*7)
海洋エネルギーのメリット
海洋エネルギーには、大きなメリットが2つあります。
- 安定した電力が得やすい
- 化石燃料よりもCO2の排出が抑えられる
それぞれの特徴について詳しく解説します。
安定した電力が得やすい
海洋エネルギーは潮の満ち引き、海流、温度差などの規則的な自然現象を活用するため、発電の安定性に優れています。特に海洋温度差発電では年間を通じて水温変化が少なく、昼夜問わず安定した出力が得られます。
| 比較項目 | 海洋エネルギー | 太陽光発電 |
| 天候依存性 | 比較的低い | 天候に大きく左右される |
| 昼夜の発電差 | ほとんどない | 夜間は発電不可 |
| 季節変動 | 小さい | 季節変動が大 |
同じ再生可能エネルギーであっても、太陽光発電よりも安定性に優れていることがわかります。*8)
火力発電よりもCO2の排出を抑えられる
海洋エネルギーの最大の環境的メリットは、発電過程における二酸化炭素排出量の大幅削減です。従来の火力発電では、石炭や天然ガスといった化石燃料を燃焼させて熱を得るため、必然的に温室効果ガスが発生します。特に石炭を用いた発電では、1キロワット時の電力生産あたり約975グラムものCO2が大気中に放出されています。*9)
これに対し、波の動きや潮の流れ、海水温の差を利用する海洋エネルギー発電では、燃料を燃やす工程がないため、運用時の二酸化炭素排出がほぼゼロです。設備の製造や設置時には若干の環境負荷が生じるものの、長期的な発電活動を通じてその影響は最小限に抑えられます。
気候変動対策が世界的課題となる中、この特性は極めて重要です。海洋エネルギーの積極活用は、カーボンニュートラル社会の実現に向けた有力な選択肢として、今後さらに注目されるでしょう。
海洋エネルギーのデメリット・課題

海洋エネルギーは優れた面が多々ありますが、デメリットや課題も存在しています。なかでも、漁業者との調整が非常に重要です。
漁業との調整が必要
海洋エネルギー設備は海域に設置されるため、その設置や運用が漁業の作業区域や漁場に影響を及ぼす可能性があります。これにより、漁獲量の減少や漁業活動の制約が懸念され、漁業者の生活や地域経済に直接影響を与えることもあります。
漁業権は長い歴史を持ち、地域漁業者の生活基盤を守る重要な制度です。そのため、設備設置に当たっては漁業者との十分な協議と合意形成、環境影響評価が不可欠です。漁業者が納得しなければ抵抗や反対の声が出ることが多く、地域社会の信頼を得るためにも丁寧なコミュニケーションと調整が求められます。
一方で、漁業者と海洋エネルギー事業者が協調し合うことで、新たな産業や地域振興が期待できる可能性もあります。したがって、漁業との調整は課題でありながらも、双方にとってメリットとなる共存関係を築くことが重要とされています。*10)
日本における海洋エネルギー活用の現状
日本における海洋エネルギー活用は、まだまだ始まったばかりです。ここでは、以下の2つの事例を紹介します。
- 洋上風力発電の推進
- 久米島の海洋温度差発電の実証実験
現状について確認します。
洋上風力発電の推進
日本政府は、洋上風力発電を再生可能エネルギーの中核として積極的に推進しています。四方を海に囲まれた国土の特性を活かし、2030年までに導入規模を大幅に拡大する目標を掲げています。
特に注力しているのが、海底に固定せず水面に浮かべるタイプの風車技術(浮体式風車)です。この方式は深い海域でも設置可能で、日本の海域特性に適しています。政府は研究開発への資金提供や実海域での実証実験を支援し、発電コストの低減と信頼性向上を目指しています。
同時に、事業者が参入しやすい環境づくりも進行中です。海域利用に関する法律の整備、環境影響評価手続きの効率化、電力系統への接続問題の解決など、制度面での障壁除去にも取り組んでいます。地域との共存や漁業との調整も重視され、地元経済への貢献も含めた総合的な普及戦略が展開されています。

経済産業省を中心とした省庁横断的な支援体制も構築され、助成金や税優遇などの支援策が提供されています。
久米島の海洋温度差発電の実証実験
沖縄県久米島では、表層の暖かい海水と深層の冷たい海水の温度差を活用した発電の実証実験が進められています。県立海洋深層水研究所に最大50kWの設備が設置され、低沸点の媒体を用いてタービンを回す仕組みで電気を生み出しています。
この取り組みは「低炭素島しょ社会」実現を目指す地域計画の一環であり、商船三井や佐賀大学などが連携して推進しています。
使用後の冷たい深層水は農業や水産業にも活用され、2026年頃には大規模商用化を目指しており、持続可能な地域発展のモデルケースとして注目されています。
海洋エネルギーの活用に取り組む企業事例

海洋エネルギーの活用に取り組んでいるのは、国や地方自治体だけではありません。ここでは、2つの企業事例を紹介します。
- ひびき灘沖浮体式洋上風力発電所の商用運転
- 株式会社日本海ラボの取り組み
民間の取り組みにフォーカスします。
ひびき灘沖浮体式洋上風力発電所の商用運転
福岡県北九州市の響灘では、水に浮かぶ風車による電力生産が始まっています。この「ひびき灘沖浮体式洋上風力発電所」は水深50~100mの場所に設置され、3,000kWの発電能力を持ちます。
「ひびきフローティングウィンドパワー合同会社」が運営し、6社が資金を出し合って事業を展開しています。もともとは国の研究開発機関による実証研究として2014年に始まり、2024年3月に民間へ移管されました。
生み出された電気は全て九州電力へ販売され、国内では2例目となる浮体式の風力発電所です。特殊な技術により浅い海でも設置可能な点が特徴で、地元漁業との共存を図りながら20年間の運転を予定しています。*13)
株式会社日本海ラボの取り組み
日本海ラボは、北陸地域を拠点とするエネルギー企業グループの投資・新事業開発部門として活動しています。既存のガス事業で得た知見を基盤に、新興企業と協力して革新的な事業創出を目指しています。
2024年末には富山新港で波の力を利用した発電設備の試験を支援し、悪天候や夜間でも安定した電力生産が可能なことを確認しました。この成果は、天候に左右される他の自然エネルギーを補完する電源として期待されています。
将来的には海上に浮かべるタイプの発電装置開発も計画しており、企業間連携を通じて海の力を活用した持続可能なエネルギーの実用化と地域発展を推進しています。*14)
海洋エネルギーとSDGs

海の力を活用した発電技術には無限の可能性があります。資源の少ない私たちの国にとって、安定したエネルギー確保と環境保護を両立できる海洋発電は極めて重要な選択肢といえるでしょう。
以下では、この自然の力を利用した電力生産と、国連が掲げる持続可能な開発目標(SDGs)の7番目「すべての人に手の届く価格で持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する」との関連性について詳しく見ていきます。
SDGs目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」との関わり
海洋エネルギーは、安定供給とCO2削減を同時に実現する理想的な選択肢として、クリーンで持続可能な未来への道を切り拓いています。
海洋エネルギーとSDGs目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」の関係は密接です。広大な海に眠る自然の力を活用することで、電力供給の未来を変える可能性を秘めています。波の動き、潮の流れ、水温差など様々な形で存在する海のパワーは、太陽や風と異なり昼夜や季節を問わず安定して利用できる特徴があります。
この安定性は電力網の信頼性向上に貢献し、遠隔地や島嶼部など従来エネルギーアクセスが困難だった地域への供給も可能にします。特に四方を海に囲まれた日本では、この無尽蔵の資源を活用することで輸入燃料への依存度を下げられます。
また、燃焼を伴わないため温室効果ガスを排出せず、地球温暖化対策として大きな意義があります。一部の発電方式では真水生成といった副次効果も期待でき、水資源問題解決にも貢献します。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
今回は、海洋エネルギーについて解説しました。広大な海に存在する波や潮流、温度差などの自然の力を電気に変える技術は、環境への負担が少なく安定した発電が可能な未来の選択肢です。
四方を海に囲まれた日本にとって特に有望で、発電だけでなく真水生成など副次的効果も期待できます。現在、国内では北九州市の浮体式風車や沖縄久米島の温度差発電など実用化に向けた取り組みが進行中です。
漁業との共存や初期費用の課題はありますが、持続可能な社会実現に貢献する重要な資源として、今後さらなる発展が期待されています。
参考
*1)佐賀大学「海洋エネルギーとは」
*2)資源エネルギー庁「総論|再エネとは|なっとく!再生可能エネルギー」
*3)佐賀県「海エネって?」
*4)日本海学推進機構「環境にやさしい海洋エネルギー」
*5)日本総研「大規模需要に向けた海洋エネルギー発電の適用可能性」
*6)佐賀大学「海洋温度差発電(OTEC)の分類」
*7)国立大学付属研究所・センター会議 「第13回 佐賀大学 海洋エネルギー研究所(2022.9.2)
*8)千葉大学「海洋再生可能エネルギーに係るメリット・デメリットとして考えられるもの」
*9)原子力産業協会「(4)各種電源別のCO2排出量」
*10)東京海洋大学「第3回 『水産海洋プラットフォーム』」
*11)資源エネルギー庁「2025年、日本の洋上風力発電~今どうなってる?これからどうなる?」
*12)久米島町「海洋温度差発電実証設備」
*13)ひびきフローティングウィンドパワー合同会社「「 ひびき灘沖浮体式洋上風力発電所 」の商用運転開始について」
*14)株式会社日本海ラボ「波からクリーンエネルギーを生成 海洋の再エネ利用に向けた「波力発電設備」の 実証実験を富山県にて実施」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。