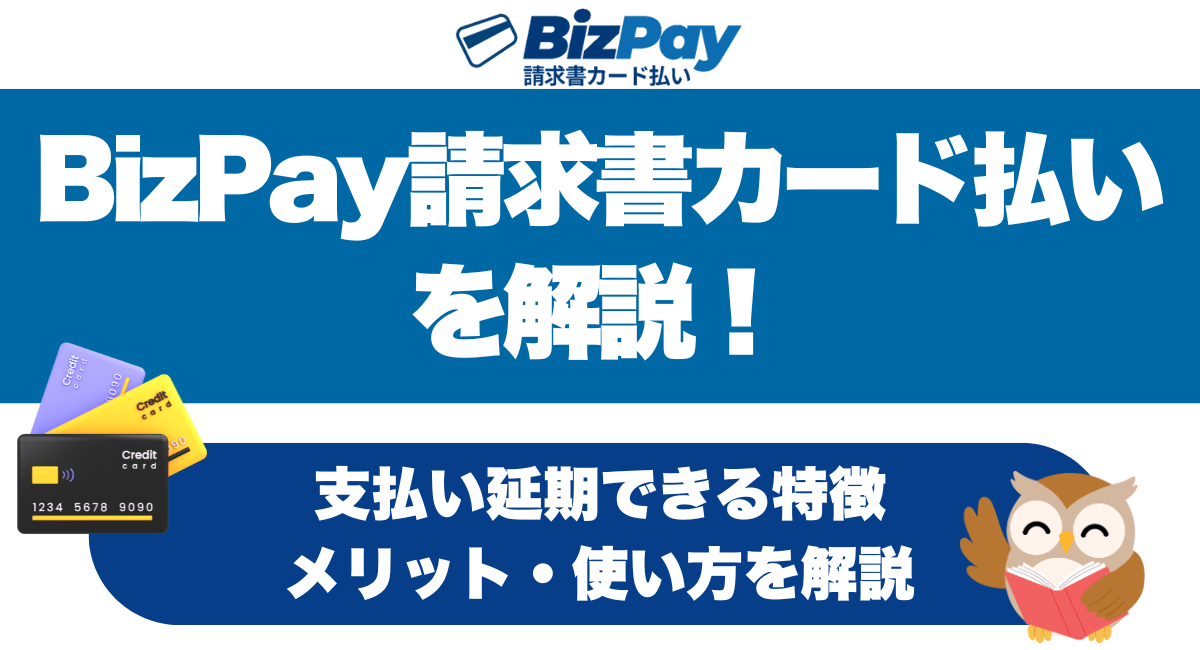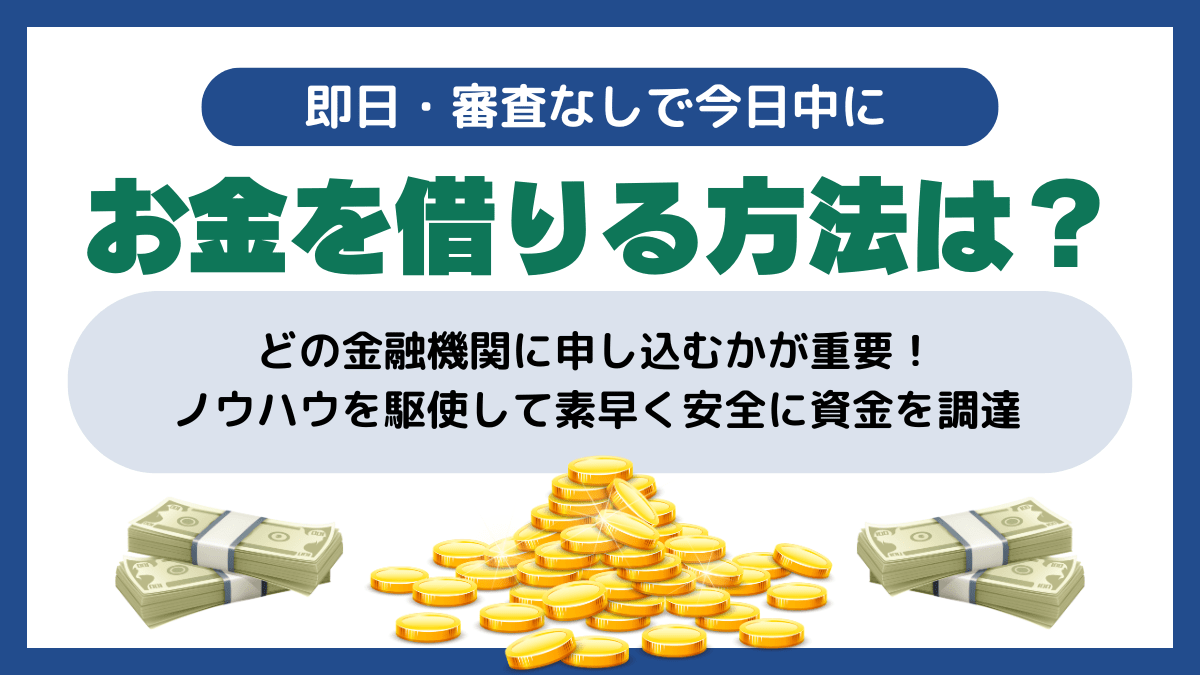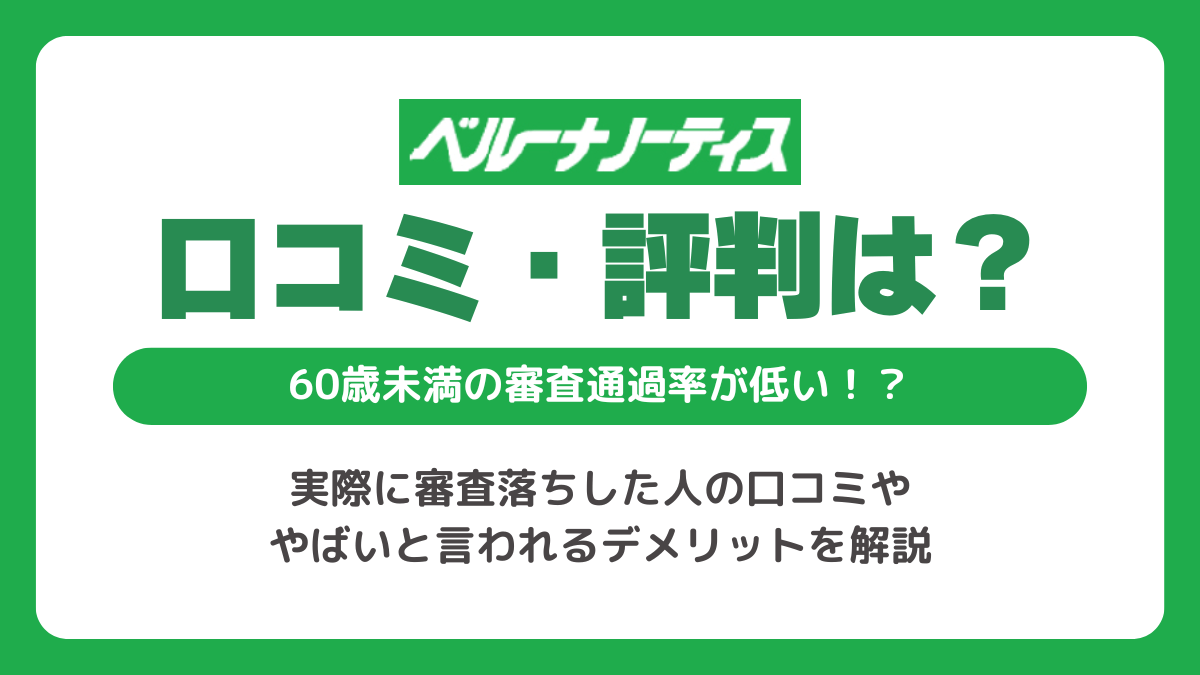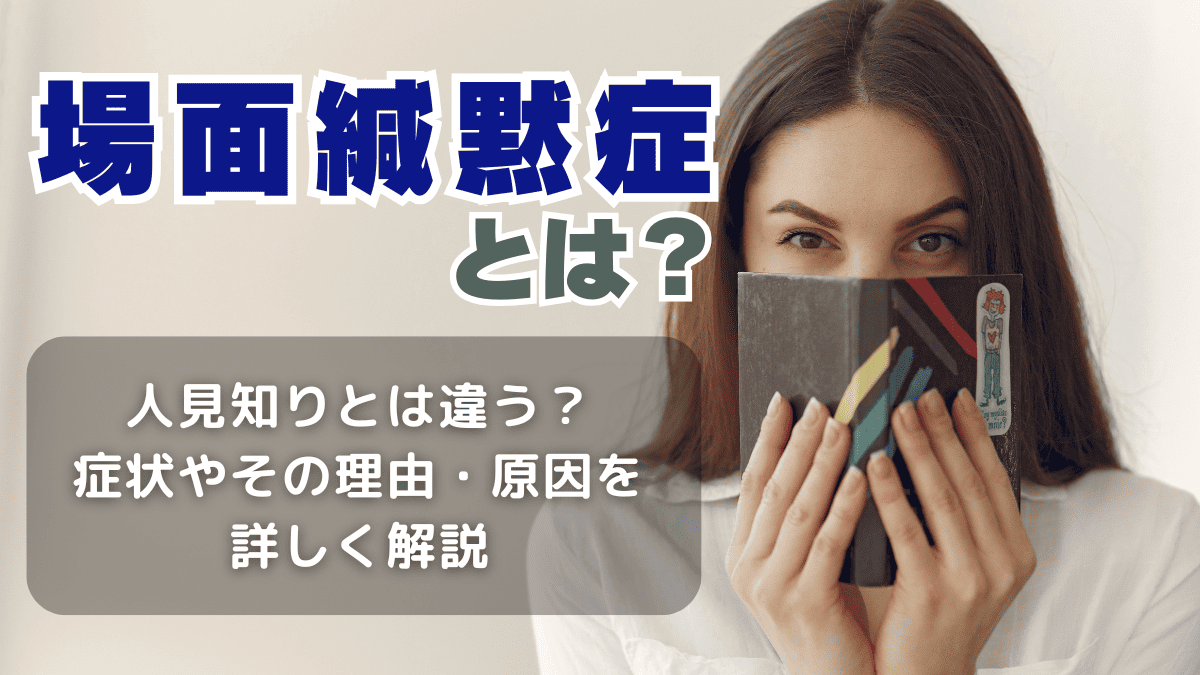山口県下関市にあった春帆楼は、日清戦争の講和会議が開かれた料亭です。1895年3月19日、清国全権の李鴻章ら講和使節団が関門海峡の沖合に停泊し、代表団が春帆楼にやってきました。
日本側の全権は総理大臣の伊藤博文、外務大臣の陸奥宗光らです。両国の話し合いの結果、4月17日に講和条約である下関条約に調印します。東アジアの大国である清が、なぜ、日本に敗北し、彼らにとって不本意な下関条約を結んだのでしょうか。
その理由は、日本が清を相手に次々と勝利を重ねたからに他なりません。日清戦争がなぜ勃発し、どのように日本が勝利したのでしょうか。今回は、日清戦争の背景や流れ、日清戦争が日本に与えた影響などについて解説します。
目次
日清戦争とは

日清戦争とは、1894年から1895年にかけて、日本と清国(現在の中国)が朝鮮半島の支配権をめぐって戦った戦争です。朝鮮で農民戦争が起きたことをきっかけに両国が出兵し、対立が深まりました。*1)
日本は朝鮮王宮を占領し、清国艦隊を攻撃して開戦に踏み切りました。近代的な装備と訓練を持つ日本軍は清国軍を圧倒し、陸海での戦いに勝利しました。
結果として下関条約が締結されましたが、その後のロシア・ドイツ・フランスによる三国干渉で、日本は獲得した遼東半島を返還することになりました。
日清戦争は、朝鮮半島をめぐる日清両国の争い
日清戦争のそもそもの原因は、朝鮮半島の支配権をめぐる両国の対立にありました。
当時の朝鮮は、清国に対して「属国」という立場にあり、外交や重要な政治決定において清国の影響を強く受けていました。一方、明治維新後の日本は近代化を進め、自国の安全を守るためには朝鮮半島が他の強国に支配されることを防ぐ必要があると考えていました。
1880年代から日本は朝鮮との関係強化を図り、朝鮮国内には日本の影響力を受けた改革派も現れるようになりました。しかし清国は従来の支配関係を維持しようとし、両国の対立が深まっていきました。
転機となったのは、1894年に朝鮮で起きた農民運動です。この混乱に対して朝鮮政府は清国に助けを求め、清国は兵を送りました。これに対抗して日本も軍隊を派遣します。両国の軍隊が朝鮮半島で向かい合う緊張状態が生まれました。
この時日本は、朝鮮の「独立」を主張し、清国の影響力を排除しようとしました。交渉は決裂し、ついに両国は戦争へと突入します。この戦争は単なる軍事衝突ではなく、東アジアの秩序をめぐる争いであり、朝鮮半島という地理的に重要な場所の支配権をめぐる競争が根本的な原因だったのです。*2)
日清戦争が起きた背景

日清戦争の根本原因は、朝鮮半島をめぐる両国の対立です。では、肝心の朝鮮半島はどのような状況だったのでしょうか。ここでは、朝鮮国内の対立や日清戦争前の国際情勢、戦争開始に大きな影響を与えた甲午農民戦争について解説します。
朝鮮国内の対立
日清戦争の背景には、朝鮮国内における保守派と改革派の対立がありました。当時の朝鮮は清国の影響下にあり、国内では伝統的な価値観を守ろうとする「事大党」と呼ばれる保守派と、近代化を進めようとする「独立党」と呼ばれる改革派が対立していました。事大党は清国との関係維持を重視し、独立党は日本をモデルにした改革を目指していました。
この対立は、1884年の甲申政変で表面化しました。独立党が一時的に政権を握りましたが、清国の介入で失敗に終わりました。その後も国内の混乱は続きます。*3)
事大党が政権を握る朝鮮政府は、清国に援助を求めました。それに対し、日本も朝鮮半島に介入を深めたため、両国の関係は悪化していきました。このように朝鮮国内の対立が国際的な問題へと発展し、最終的に日清戦争へとつながったのです。
日清戦争前の国際情勢
日清戦争直前の国際情勢は、東アジアを舞台にした欧米の強国と日本・清国の間の複雑な力関係が特徴でした。19世紀後半、清国はフランスとの戦争でベトナムの支配権を失い、ロシアとの間で現在の新疆地域をめぐる対立を抱えるなど、周辺地域での影響力が弱まっていました。
このような状況で、明治維新後に近代化を進めていた日本は、朝鮮半島への影響力拡大を目指すようになりました。
朝鮮半島では、伝統的に影響力を持っていた清国と、新たに勢力を伸ばそうとする日本が対立していました。1885年に両国は朝鮮からの軍隊撤退で一時的に合意(天津条約)しましたが、その後も緊張関係は続きました。*4)
同時に、ロシアは鉄道建設を進めながら南へ勢力を広げよう(南下政策)とし、朝鮮半島や満州(現在の中国東北部)に関心を示していました。イギリスはロシアの動きを警戒し、日本との関係を深めていました。日清戦争は、東アジアでの影響力をめぐる国際的な競争の中で起きた出来事だったのです。
甲午農民戦争の勃発:日清両国の出兵
甲午農民戦争は、1894年に朝鮮半島で発生した大規模な農民反乱であり、日清戦争の直接的なきっかけとなった重要な出来事です。
当時、朝鮮では封建体制を維持しつつ開国・近代化を進めるという矛盾が深刻化しており、地方役人の腐敗や不正、外国貿易による物価高騰が農民たちの生活を圧迫していました。こうした状況下で、「東学」の影響を受けた農民たちが立ち上がりました。
反乱は全羅道で地方役人の不正に抗議する形で始まり、指導者の全琫準(チョン・ボンジュン)のもと急速に拡大しました。農民軍は「西洋勢力と日本を排斥する」という主張を掲げ、全州府を占領するなど一時的に勢力を広げました。*5)
この事態に直面した朝鮮政府は自力での鎮圧を断念し、清国に援軍を要請しました。一方、日本も日本と清のどちらかが出兵した場合、他の国も朝鮮に出兵すると定めた天津条約に基づき出兵し、両国の軍事介入が始まりました。
反乱自体は、6月に朝鮮政府と農民軍との間で停戦協定が結ばれ終息しましたが、この介入を機に日清間の緊張が高まりました。
日本は清国に対し、共同で朝鮮内政改革を行うことを提案しましたが拒否されました。その結果、最終的に日本は清国軍への攻撃を行い、日清戦争へと発展しました。甲午農民戦争は単なる農民反乱ではなく、東アジアの国際関係の変化や外国の介入を招く契機となった歴史的事件でした。
日清戦争の流れ

甲午農民戦争をきっかけに、日本と清国の両軍は朝鮮半島でにらみ合い、やがて戦闘になります。ここでは、日清戦争の戦いの流れを解説します。
開戦
1894年7月25日、日本海軍は朝鮮半島西岸の豊島沖で清国艦隊と遭遇し、戦闘が勃発しました。この豊島沖海戦では日本側が圧勝し、清国軍の増援を阻止しました。同日、日本陸軍も朝鮮南部に進軍を開始し、牙山周辺の清国軍を攻撃する準備を整えました。
続いて7月29日、日本陸軍は朝鮮忠清道成歓で清国軍と衝突しました。この「成歓の戦い」は、日清戦争における最初の主要な陸戦であり、日本軍が勝利を収めました。これにより、清国軍は牙山から撤退を余儀なくされ、日本軍は朝鮮半島内で優位に立ちました。*2)
これらの戦闘の後、両国は8月1日に正式に宣戦布告を行いました。日本では明治天皇が詔勅を発し、清国でも光緒帝が同日に宣戦布告しました。こうして日清両国間の全面的な戦争が始まり、朝鮮半島を舞台とした激しい戦いへと発展していきました。
朝鮮半島での戦闘
豊島沖海戦や成歓の戦いで勝利した日本軍は、朝鮮半島南部での足がかりを得ました。9月には平壌で大規模な陸上戦が行われ、日本軍は近代的な武器と戦術を駆使して清国軍を撃退しました。
ほぼ同時期に黄海海戦が起こり、日本海軍は清国北洋艦隊に大打撃を与えて海の支配権を握りました。*2)
これにより日本軍は朝鮮半島を制圧し、さらに清国本土への侵攻路を確保することができました。この戦いの流れは、日本の近代化の成果を示すとともに、東アジアの勢力図を大きく変えるきっかけとなりました。
清国領土での戦争
朝鮮半島内での勝利を受けて、日本軍が本格的に清国本土へ侵攻する形で進展しました。1894年10月、日本軍第一軍は鴨緑江を渡り、清国領内に進軍しました。この際、九連城の戦いが行われ、日本軍は清国軍を撃破し、さらに鳳凰城や岫厳といった地域へ進攻を続けました。
一方、第二軍は海路を利用して遼東半島へ上陸し、旅順や大連といった重要拠点を次々と占領しました。旅順攻略では激しい戦闘が行われましたが、日本軍は勝利を収め、清国北洋艦隊の拠点を奪いました。その後、1895年2月には威海衛攻略が行われ、陸海共同作戦によって清国北洋艦隊が壊滅し、日本軍が制海権を完全に掌握しました。*3)
最終的に日本軍は遼河平原まで進出し、清国領内での主要な戦闘を終えました。この一連の戦いによって日本は清国本土での優位性を確立し、戦争終結に向けた講和交渉への道筋をつけることとなったのです。
日清戦争のその後

清国との戦争を優位に進めた日本は、下関で清国との講和会談を開きます。ここでは、日清戦争を終わらせた下関条約について解説します。
下関条約の締結
1895年4月17日、日本と清国の間で下関条約が結ばれました。講和条約の主な内容は、以下の通りです。
- 清国は朝鮮を独立国と認め、宗主権を放棄する
- 清国は遼東半島、台湾、澎湖諸島を日本に譲る
- 清国は日本に賠償金として2億両(3億円)を支払う
- 清国は、重慶など複数の港を外国に開放する
*6)
戦争を優位に進めた日本にとって、極めて有利な内容の講和条約となったのです。
日清戦争が日本に与えた影響

日清戦争は、日本が東アジアの大国である清国に勝利した戦いです。戦いの勝利は、いったい何を日本にもたらしたのでしょうか。戦争の勝利が日本に与えた3つの影響を紹介します。
三国干渉で遼東半島を返還した
日清戦争の勝利によって日本は1895年に下関条約を結び、遼東半島の割譲を獲得しました。しかし、ロシア、フランス、ドイツの三カ国は日本の大陸進出に危機感を抱き、遼東半島の返還を求める外交的圧力をかけました。これが三国干渉です。*7)
日本政府は当時、三国との軍事力の差を考慮し、やむなく遼東半島を清国に返還することを決断しました。しかし、この決断は日本に大きな影響を与えました。
まず国内では「勝った戦争の成果を西洋列強に奪われた」という屈辱感が広がり、軍備増強を求める声が高まりました。また、ロシアへの不信感と対抗意識が強まり、これが後の日露戦争につながる要因となりました。
さらに日本の外交政策にも変化をもたらし、西洋列強と対等に渡り合うための国力強化が国家目標となりました。
巨額の賠償金で軍備を拡張した
日清戦争で勝利した日本は、清国から巨額の賠償金を獲得しました。この賠償金は主に軍備拡張に使われることになります。
陸軍では、ロシアを将来の敵国と想定し、部隊数を6個師団から12個師団へと倍増させました。また、騎兵や砲兵部隊を増やし、砲台の建設や武器の改良も進められました。海軍では、大型の戦艦を中心とする主力艦隊と、巡洋艦や駆逐艦などの支援艦艇を増やす計画が立てられました。*2)
また、賠償金は八幡製鉄所(現在の新日鉄住金八幡製鉄所)の建設にも使われ、国内での鉄鋼生産が可能になりました。これにより武器製造や鉄道建設が進み、軍事力だけでなく産業基盤も強化されました。
朝鮮半島を日本の影響下に置いた
下関条約の結果、清国は朝鮮を独立国として認め、宗主国としての立場を失いました。
以後、清国は朝鮮の政治や軍事、外交に関して干渉できなくなったのです。
日清戦争とSDGs

日清戦争そのものは、SDGsとあまり深いかかわりはありません。しかし、戦争と平和という観点から見れば、日清戦争もSDGsに関連があるといえるでしょう。ここでは、日清戦争とSDGs目標16との関わりについて解説します。
日清戦争とSDGs目標16の関わり
SDGs目標16「平和と公正をすべての人に」の中に、あらゆる場所で、あらゆる形の暴力と暴力による死を大きく減らすというものがあります。
日清戦争は日本が勝利し、賠償金や領土を獲得した歴史的事実がありますが、その背後には大きな犠牲がありました。日本軍だけでも1万7,000人以上が戦死し、朝鮮半島や清国東北地方の犠牲者を含めると数万人もの命が失われました。
19世紀から20世紀初頭は世界的に戦争の時代でしたが、当時の戦闘は主に戦場やその周辺に限定されていました。しかし、現代では軍事技術が飛躍的に進歩したため、もし東アジアで大規模な紛争が起これば、被害は比較にならないほど甚大になるでしょう。
歴史から学ぶべきことは、戦争の勝敗や利益だけでなく、人命の尊さです。多くの命を守るためには、戦争を抑止し暴力による死を減らす継続的な努力が不可欠です。過去の戦争の真実を直視し、平和構築への決意を新たにすることが私たちの責務なのです。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
今回は、日清戦争について解説しました。日清戦争は1894年から1895年にかけて朝鮮半島の支配権をめぐって日本と当時の中国(清国)の間で行われた戦争です。きっかけは朝鮮での農民反乱でした。両国がそれぞれ軍隊を派遣したことで対立が深まり、ついに戦争へと発展しました。
日本は近代化された軍隊の力で、海では豊島沖海戦や黄海海戦、陸では成歓の戦いや平壌の戦いなどで次々と勝利を収めました。その結果、1895年に下関条約が結ばれ、日本は台湾の割譲や賠償金の獲得などの成果を得ました。
しかし、その後のロシア・ドイツ・フランスによる三国干渉で遼東半島を返還することになり、日本人の間に屈辱感が広がりました。
この戦争の勝利によって日本は国際的な地位を高め、東アジアでの影響力を拡大しましたが、同時に多くの人命が失われたことも忘れてはなりません。
参考
*1)山川 日本史小辞典 改定新版「日清戦争」
*2)改定新版 世界史大百科事典「日清戦争」
*3)日本大百科全書(ニッポニカ)「日清戦争」
*4)デジタル大辞泉「天津条約」
*5)日本大百科全書(ニッポニカ)「甲午農民戦争」
*6)精選版 日本国語大辞典「下関条約」
*7)改定新版 世界大百科事典「三国干渉」
*8)帝国書院「戦争別死傷者数」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。