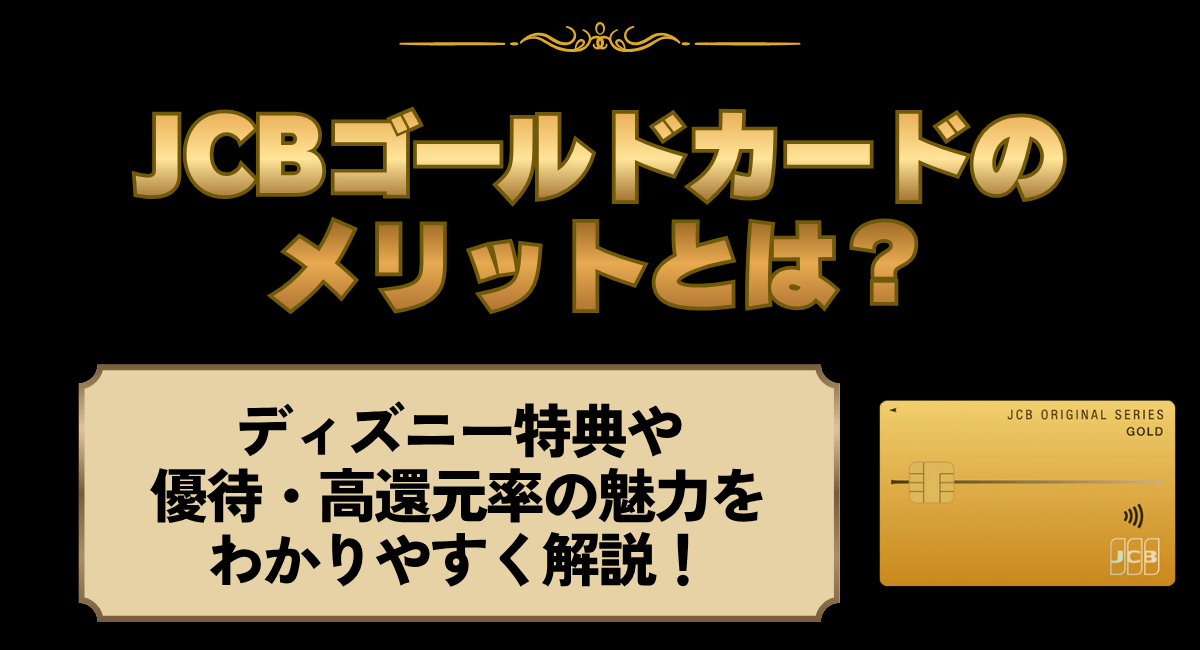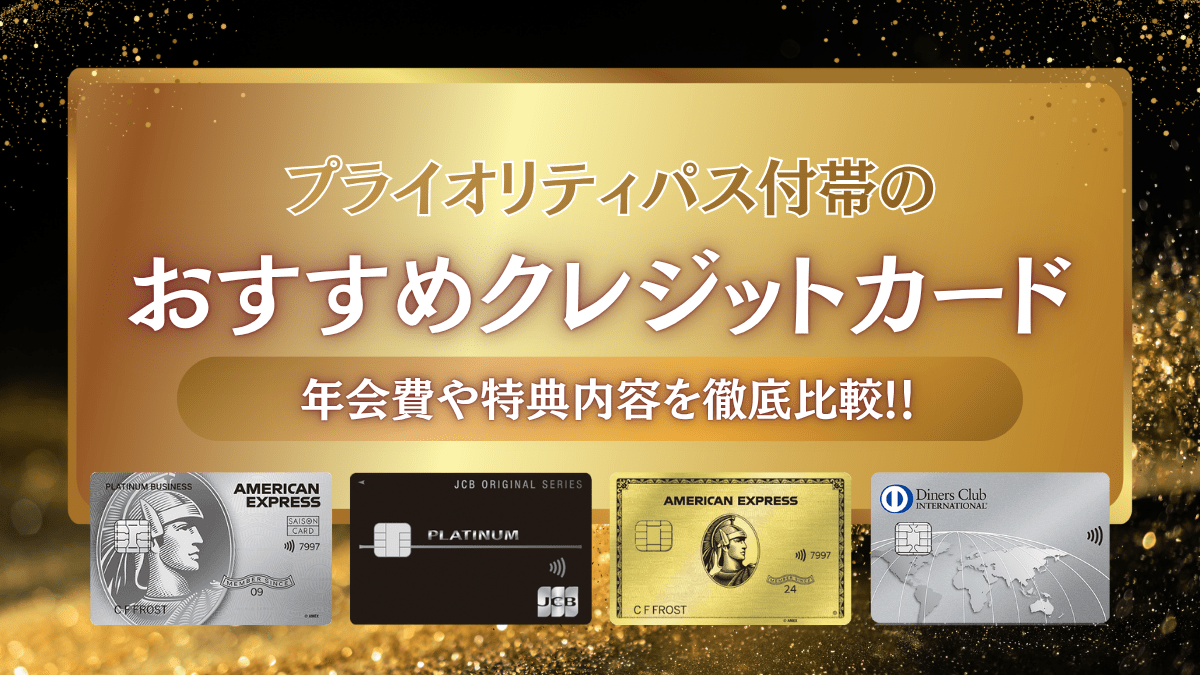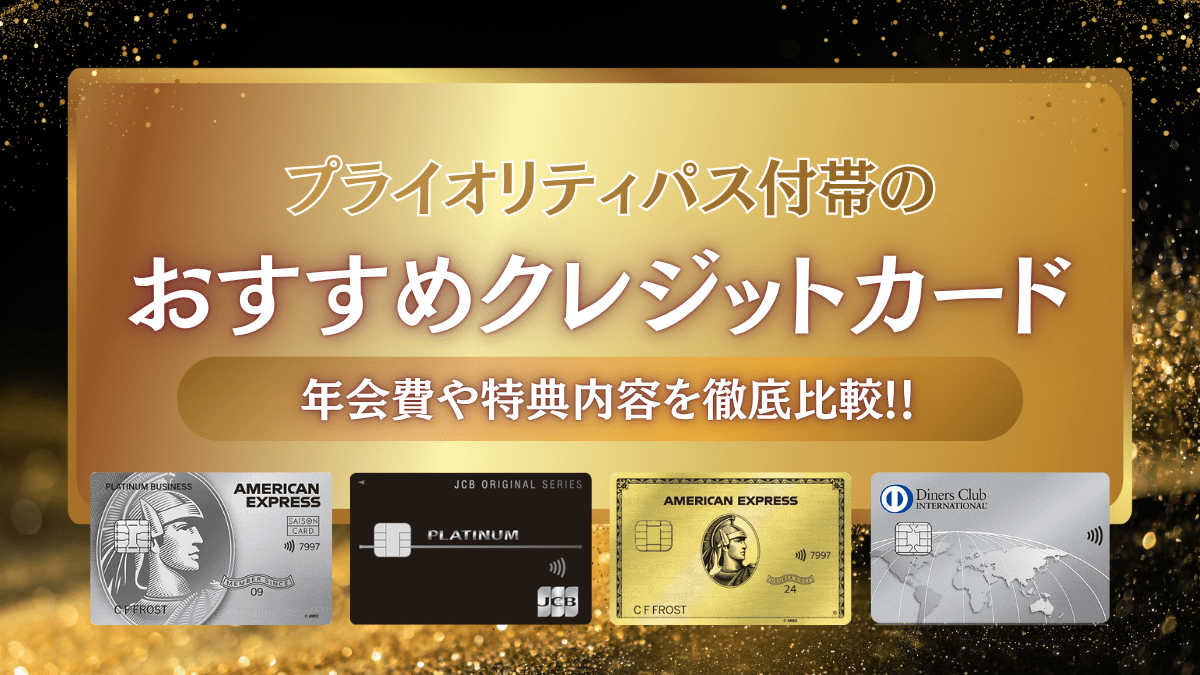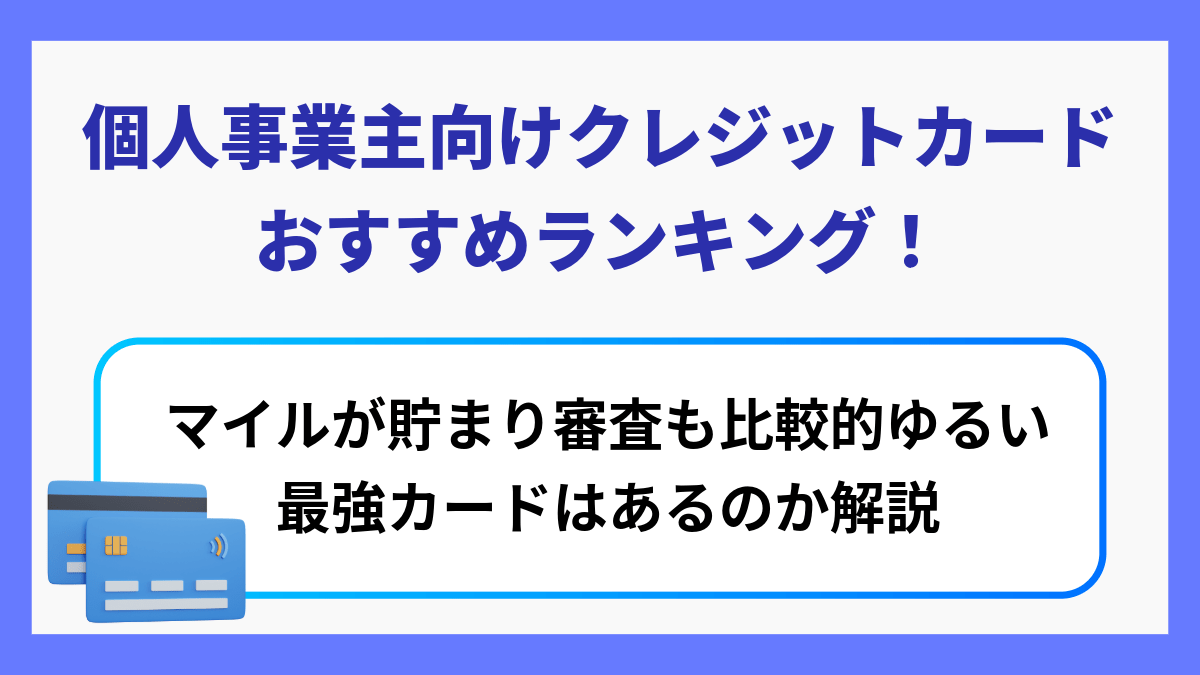名古屋市中村区の中村公園には、豊臣秀吉の生誕地と伝わる碑が建っています。今では静かな緑に囲まれたこの場所から、かつて天下を統一した英雄が生まれたとは信じがたいかもしれません。
貧しい農家の子として生まれた秀吉は、身分にとらわれず、努力と知恵で人生を切り開きました。やがて織田信長に仕え、仲間を惹きつける人柄と抜群の行動力で頭角を現します。天下を治めた後は、大坂城を築き、土地の調査や刀狩などの改革を進め、混乱の時代に安定をもたらしました。
しかし、栄光の陰には孤独や迷いもあり、辞世の句には人生の儚さがにじみます。豊臣秀吉は、ただの武将ではなく、平和と秩序を求めた時代の改革者でした。現代のSDGsにも通じるその生き方を通して、変化の時代を生き抜くヒントを探ってみましょう。
目次
豊臣秀吉とは

豊臣秀吉は、1537年に尾張(現在の愛知県)で足軽の子として生まれた戦国時代の武将です。幼名を日吉丸といい、貧しい家に生まれながらも努力と知恵で出世の道を歩みました。
織田信長に仕えて功績を重ね、やがて長浜城主となります。本能寺の変で信長が倒れると、明智光秀や柴田勝家を討ち、天下統一を果たしました。のちに大坂城を築き、関白や太政大臣に任じられて「豊臣」の姓を名乗り、政治の中心に立ちます。
太閤検地や刀狩を行い、農民と武士を分ける仕組みを整えて社会を安定させ、近世日本の基盤を築きました。一方で、朝鮮出兵では思うような成果を得られず、晩年は苦悩の中で62年の生涯を閉じました。
ここでは、豊臣秀吉の人生や彼の性格、エピソード、死因などについて解説します。
秀吉の生い立ち

豊臣秀吉は1537年ごろ、現在の名古屋市中村区に生まれました。父は足軽の弥右衛門、母は「なか」といい、のちに大政所と呼ばれます。裕福とは言えない農家の子でしたが、幼いころから人懐っこく、明るい性格で知られていました。
7歳で父を亡くしたのち、母が再婚し、秀吉は新しい家庭で育ちます。しかし、幼い心には武士として立身出世したいという強い思いが芽生えており、若くして家を出ました。
最初は遠江の城主・松平元綱に仕え、その後、18歳のときに織田信長の家臣となります。信長の草履を懐で温めたという逸話は、彼のまじめさと気配りの象徴です。
身分の低さをものともせず、人をよく観察し、誰からも愛されるその人柄が、のちに天下人へと押し上げる原動力となりました。貧しい少年が夢を信じて歩んだ道のりは、今も多くの人の心を動かしています。*2)
敵も味方も惹きつけた!人の心をつかむ「人たらし」
豊臣秀吉は、人の心をつかむ達人として知られています。その「人たらし」ぶりは、身分の高い者にも低い者にも分け隔てなく接する姿勢にありました。
1582年に書かれた直筆の手紙では、身分の低い家臣に「五人扶持(五人分の生活費)」を与えるよう命じています。末端の部下にまで気を配るその優しさは、信頼を集める大きな要因でした。*3)
また、織田信長の家臣となった際には、先輩の「丹羽長秀」と「柴田勝家」からそれぞれ一字をもらい、自らを「羽柴(はしば)」と名乗りました。上下関係を重んじ、周囲の尊敬を得るためにとったこの行動も、秀吉らしい気配りの現れです。*3)
さらに、敵であった毛利輝元を二カ月間も丁重にもてなし、豪華な茶会や観光に招いたことで完全に味方に引き入れました。戦で敗れた九鬼嘉隆にも「よく生きて戻った」と声をかけ、失敗を責めずに励ましたといいます。*4)
こうした温かさと柔らかい言葉が、秀吉の最大の武器であり、天下統一を支えた「人心掌握術」そのものでした。
金の茶室と花見好き――「天下人の美意識」を体現

豊臣秀吉は、ただの戦国武将ではありませんでした。彼は「見せる力」で天下を制した、華やかな演出家でもあったのです。
1587年、京都の北野天満宮で開かれた「北野大茶湯」では、なんと身分を問わず誰でも参加できるという前代未聞の茶会を開催しました。境内には千を超える茶席が並び、中央の拝殿には黄金で覆われた茶室が輝いていたと伝えられます。
天下人となった自分の威光を、茶の湯という文化の舞台で見せつけたこの催しは、まさに秀吉の派手好みの象徴といえるでしょう。*5)
そして晩年、彼が最後の宴として開いたのが「醍醐の花見」です。全国から桜を取り寄せ、豪華絢爛な衣装に身を包んだ女房衆が三度も衣装を替えて練り歩きました。*6)
まるで夢のような一日だったこの花見は、天下人としての栄華と、やがて訪れる終焉を象徴する場でもあります。金の茶室と桜の宴。そこには、権力を美で彩りたいという秀吉独自の“天下人の美意識”が息づいていました。
「露と落ち 露と消えにし」:辞世の句に込められた秀吉の思い
豊臣秀吉の辞世の句「露と落ち、露と消えにし我が身かな、浪速のことも、夢のまた夢」は、天下人としての彼の最期の心境を見事に映し出しています。
「露と落ち、露と消えにし我が身かな」とは、命の儚さを露にたとえ、自分の人生が一瞬の輝きにすぎなかったと悟る言葉です。「浪速のことも、夢のまた夢」は、栄華を誇った大阪(浪速)での日々すら、今は遠い夢のように感じるという意味です。
死期を悟った秀吉は、幼い秀頼の将来を徳川家康、前田利家ら五大老に託しながらも、すべてのものはいつか消えていくという世の移り変わりを、静かに受け入れました。戦国の乱れた時代をまとめあげた英雄が、最後に感じたのは、どんな力や富も永遠ではないという人生の儚さだったのです。
豊臣秀吉が行ったこと

豊臣秀吉は信長の家臣となってから頭角を現し、本能寺の変の頃には中国地方方面軍の司令官となっていました。本能寺の変後、秀吉は明智光秀を討伐して信長の後継者となります。ここでは、秀吉の行ってきたこと、とくに政権を握ってからの出来事を中心に解説します。
| 西暦 | 出来事 |
| 1537年 | 尾張国中村に生まれる |
| 1582年 | 本能寺の変 |
| 1582年ころ | 太閤検地が始める |
| 1585年 | 関白になる |
| 1587年 | 伴天連(バテレン)追放令を出す |
| 1588年 | 刀狩令を出す |
| 1590年 | 北条氏を滅ぼし天下を統一 |
| 1592年 | 朝鮮出兵①(文禄の役) |
| 1597年 | 朝鮮出兵②(慶長の役) |
| 1598年 | 秀吉死去 |
信長の後継者となって天下を統一

1582年、本能寺の変で織田信長が自害すると、豊臣秀吉はただちに毛利氏と和睦し、山崎の戦いで明智光秀を討ちました。翌年には柴田勝家を賤ヶ岳の戦いで破り、信長の後継者としての地位を確立します。
その後も徳川家康との小牧・長久手の戦いを経て和睦し、1585年には関白に任じられ、翌年には太政大臣となって「豊臣」の姓を賜りました。
さらに四国や九州を平定し、1590年には小田原攻めで北条氏を滅ぼして全国統一を完成させます。*7)
「豊臣政権」の樹立
豊臣政権とは、豊臣秀吉が全国を統一してつくりあげた政治体制を指します。1585年、秀吉は関白に就任し、「豊臣」という姓を授かることで政権を正式にスタートさせました。天下統一後は、土地の広さや収穫量を調べる「太閤検地」を実施し、税制を整えて公平な社会づくりを進めました。
1588年には「刀狩令」を出して農民の武器を取り上げ、戦のない国を目指すなど、平和への取り組みも行っています。さらに、キリスト教の宣教師を国外に追放する「バテレン追放令」や、海賊の取り締まりなど、国内の秩序を守る政策にも力を入れました。*8)
秀吉の死後、政権は五大老・五奉行の合議によって支えられましたが、朝鮮出兵の失敗や内部の争いが重なり、やがて徳川家康へと権力の座が移っていきました。
太閤検地と刀狩

太閤検地と刀狩は、豊臣秀吉が全国統一ののちに実施した代表的な政策であり、日本の社会の仕組みを大きく変えました。
まず太閤検地とは、全国の土地の広さや質、収穫量を正確に調べ、税の基準を統一するための調査です。秀吉は新たに支配した地域ごとに検地を行い、全国の土地を「石高」という単位で管理しました。これにより、土地ごとの生産量が明確になり、課税の不公平が減少しました。
また、田畑ごとに耕作者の名前を記録し、その人の耕作権を認めたことで、農民が安定して暮らせる仕組みが整いました。さらに、荘園制度が完全に終わり、武士と農民がはっきり分かれる社会の基礎が築かれたのです。*9)
一方、刀狩は1588年に出された命令で、農民が持つ刀や槍などの武器を取り上げる政策でした。秀吉は「没収した武具を大仏殿の建築に使う」と説明しましたが、実際には反乱を防ぐための措置でした。
この命令によって、武器を持てるのは武士だけとなり、農民は農業に専念するようになりました。太閤検地と刀狩は、平和で秩序のある社会を築くための基盤を作り出した重要な政策だったのです。*10)
バテレン追放令

バテレン追放令とは、1587年に豊臣秀吉が出したキリスト教の宣教師を国外に追放する命令です。秀吉は九州を平定した後、福岡県の筥崎でこの法令を発布しました。
内容は、日本は古くから神や仏を信仰する国であり、外国の宗教であるキリスト教はふさわしくないというものでした。そのため、宣教師に対し20日以内に日本から出るよう命じたのです。*11)
発令の背景には、宣教師たちが勢力を広げ、神社や寺を壊す行為があったこと、さらにキリシタン大名が増えて政治的な影響を強めていたことがあると考えられます。
しかし、秀吉は同時に外国との貿易を禁止しなかったため、宣教師たちは一時退去した後も各地に潜伏して活動を続けました。この法令は実際には徹底されませんでしたが、秀吉が国内の秩序を守り、宗教と政治のバランスを取ろうとした姿勢を示す出来事でした。*12)
朝鮮出兵

豊臣秀吉の朝鮮出兵は、1592年から1598年にかけて2度行われた戦争で、「文禄・慶長の役」と呼ばれます。全国統一を果たした秀吉は、国内の大名たちの力を外に向けるため、朝鮮を経由して中国(明)を征服しようと考えました。
しかし朝鮮がその要請を断ったため、1592年に出兵します。小西行長や加藤清正らが先陣を務め、平壌付近まで進みましたが、明の援軍と朝鮮の抵抗によって戦いは長期化し、いったん停戦しました(文禄の役)。*13)
ところが、講和交渉が決裂すると、秀吉は1597年に再び出兵を命じます(慶長の役)。しかし戦況は不利で、1598年に秀吉が亡くなると撤退しました。*13)
この戦争で朝鮮は大きな被害を受け、日本側も多くの兵を失いました。また、連行された朝鮮の陶工たちが、日本の陶磁器文化の発展に大きく貢献したことも知られています。
豊臣秀吉とSDGs
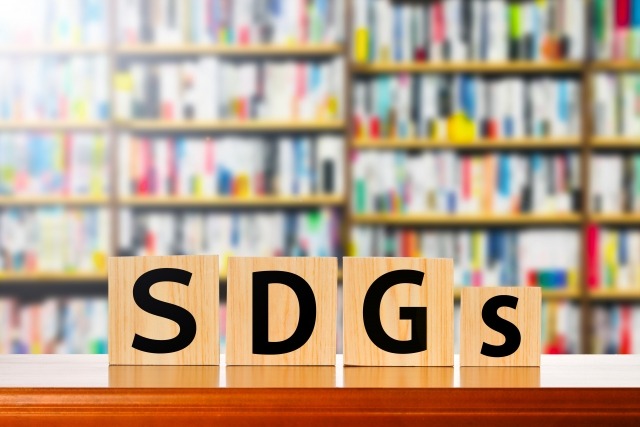
豊臣秀吉の政治や改革の中には、現代のSDGsにも通じる考え方が見られます。特に、争いのない社会を目指した政策は、SDGs目標16「平和と公正な社会の実現」と関わりがあります。
SDGs目標16「平和と公正な社会の実現」との関わり
豊臣秀吉の政治には、SDGs目標16「平和と公正な社会の実現」と重なる面が見られます。刀狩では、農民から刀や槍などの武器を取り上げることで、争いを減らし、平和な社会を築こうとしました。
また惣無事令を出して、大名同士の戦いを禁じ、力ではなく秩序によって国を治めようとした点も、この目標に通じています。これらの政策は、人々が安心して暮らせる社会を目指した取り組みでした。
しかし一方で、秀吉自身は朝鮮へ出兵し、多くの犠牲を生む戦争を行っています。国内の平和を維持しながらも、国外への侵略を進めたことは、平和の理念とは相反する行為でした。
つまり秀吉の政治には、「平和をつくる努力」と「武力による支配」の両面が存在していたのです。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
豊臣秀吉は、農民の子から天下人へと上りつめた戦国時代の立志者です。努力と知恵、そして人の心をつかむ才能によって、戦乱の世を統一し、安定した社会の基盤を築きました。太閤検地や刀狩によって公平な税の仕組みを整え、争いのない平和な国を目指した一方で、朝鮮出兵のように自ら戦を仕掛けた矛盾も抱えていました。
金の茶室や醍醐の花見に見られるように、文化や美を重んじる一面も持ち、政治と芸術の両方で日本の歴史に大きな足跡を残しています。
辞世の句に「夢のまた夢」と詠んだ秀吉は、栄華の中で人生の儚さを悟った人物でもありました。彼の生涯は、平和と秩序を求めた改革者としての理想と、権力を追い求めた人間らしさの両面を映し出しています。
参考
*1)デジタル版 日本人名大辞典+Plus「豊臣秀吉」
*2)日本大百科全書(ニッポニカ)「豊臣秀吉」
*3)東洋経済オンライン「豊臣秀吉の「接待」は、驚くほどスゴかった 「コスパ抜群!ハイリターン」その手法は? |
*4)東洋経済オンライン「「人たらし」豊臣秀吉のスゴすぎる人心掌握術 「上司、部下、敵を懐柔した」秘策はこれだ!」
*5)日本大百科全書(ニッポニカ)「北野大茶湯」
*6)日本大百科全書(ニッポニカ)「醍醐の花見」
*7)山川 日本史小辞典 改定新版「豊臣秀吉」
*8)日本大百科全書(ニッポニカ)「織豊政権」
*9)山川 日本史小辞典 改定新版「太閤検地」
*10)山川 日本史小辞典 改定新版「刀狩」
*11)改定新版 世界大百科事典「伴天連追放令」
*12)山川 日本史小辞典 改定新版「バテレン追放令」
*13)旺文社日本史事典 三訂版「文禄慶長の役」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。