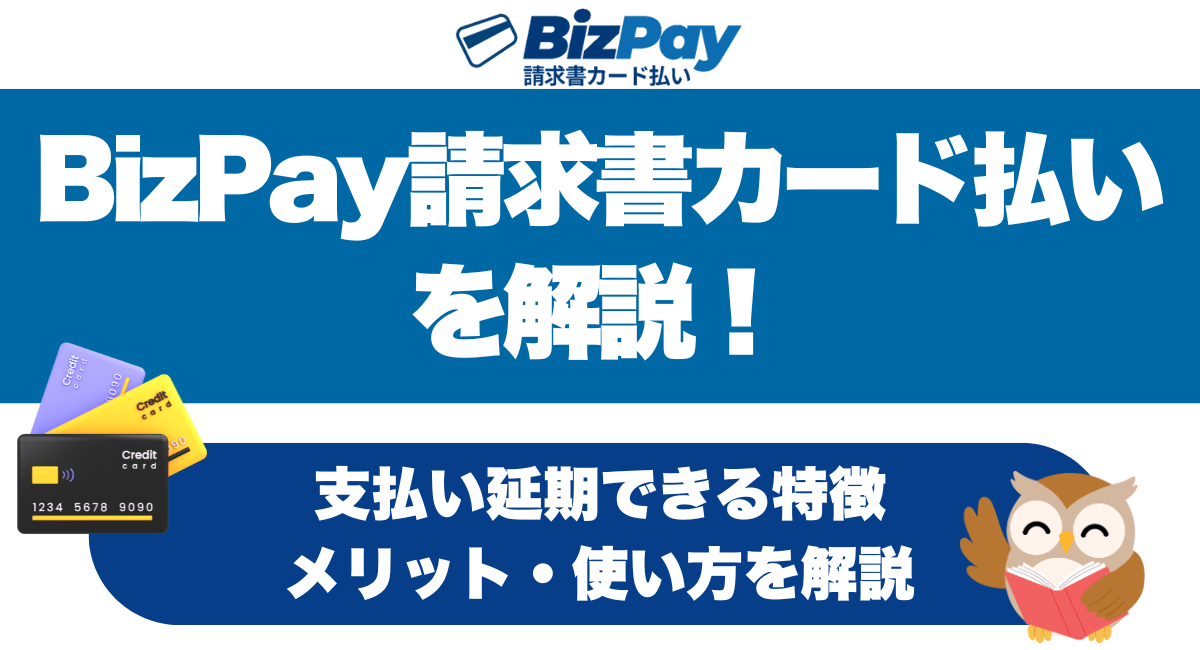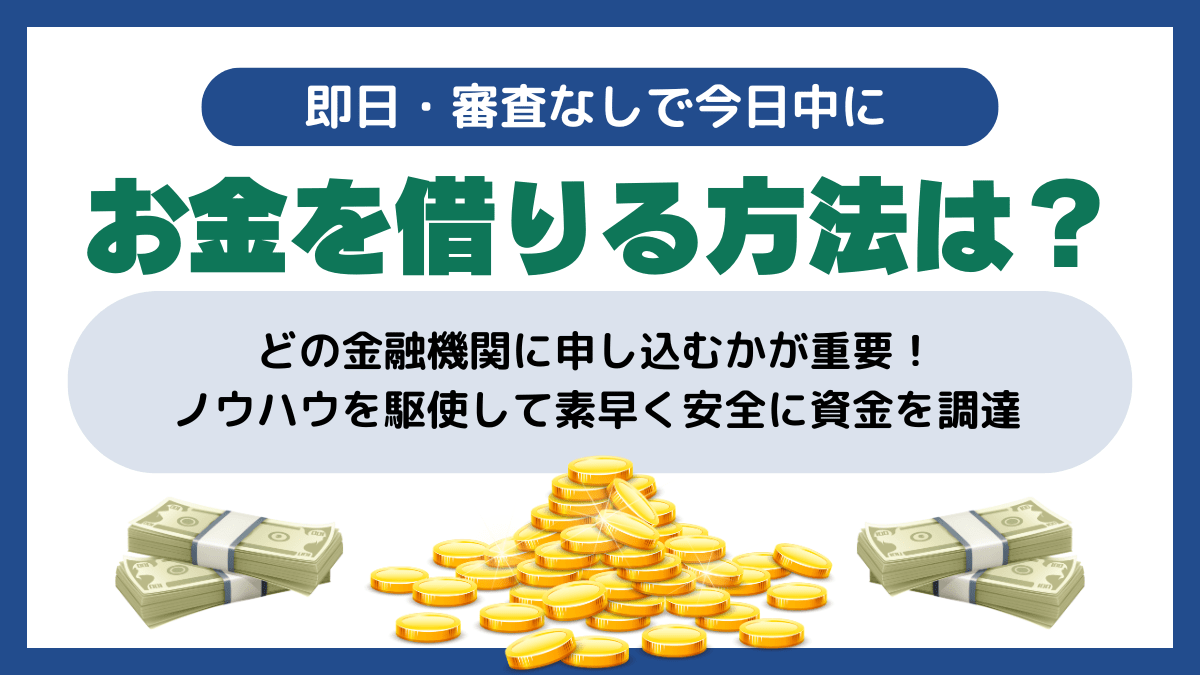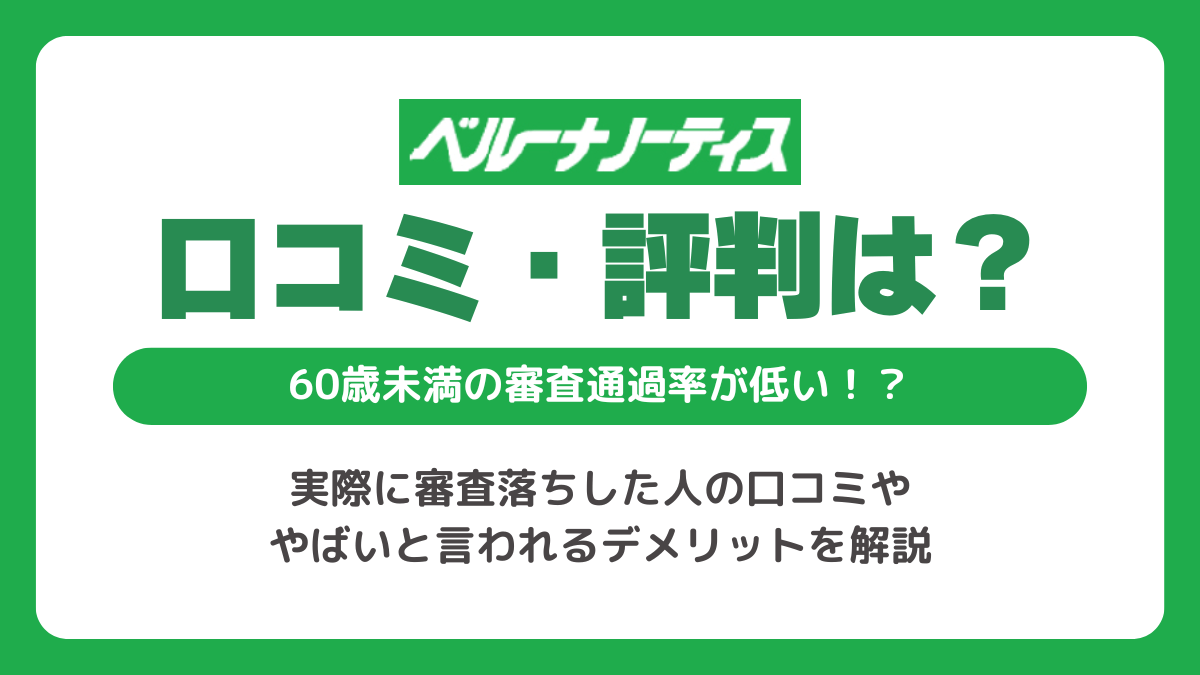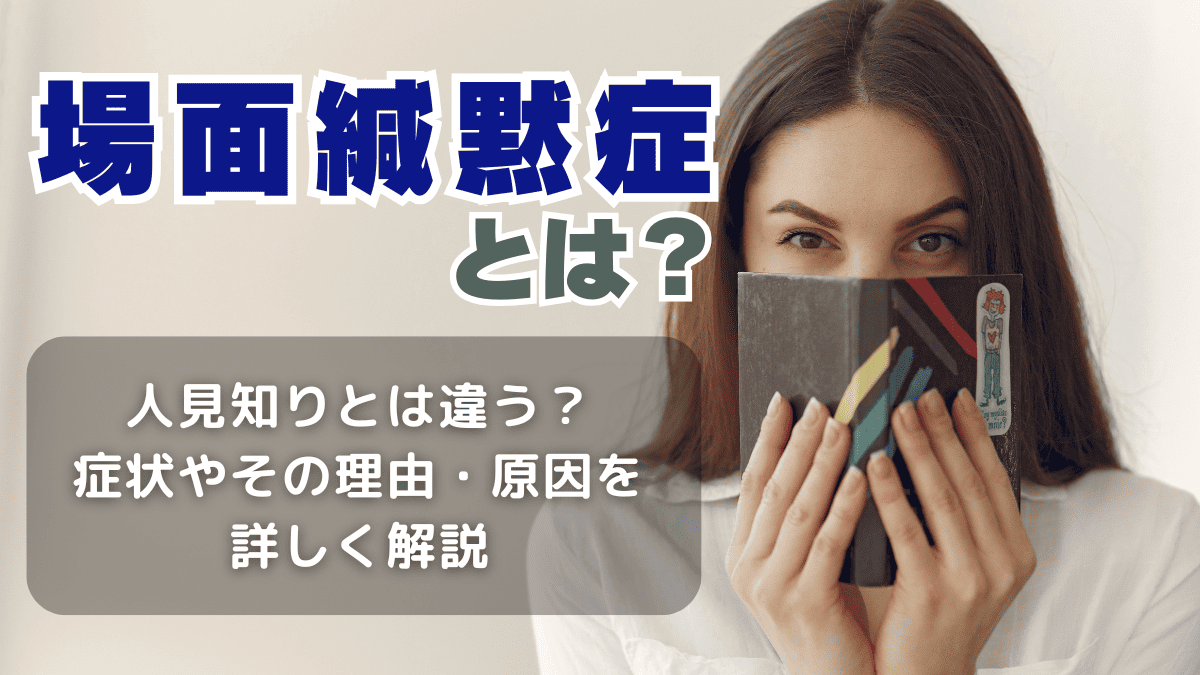近年、東京のような大都市でも、ファーマーズマーケットやマルシェなどで新鮮な地場野菜が販売されたり、学校で農業体験が行われたりする光景は珍しくなくなりました。このような都市と農の関わりが増えていく中、その中心的役割を担っているのが都市農業です。ではなぜ今、都市農業が注目されているのでしょうか。その特徴や実践例をもとに、都市農業の現状を探っていきましょう。
目次
都市農業とは
農林水産省では、都市農業を「市街地及びその周辺の地域において行われる農業」(都市農業振興基本法第2条)と定義しています。
日本では、古くから城の周囲に都市と農地が混在しており、さらにその周辺に農村が広がるのが普通でした。その後市街地エリアが拡大を続け、商業地や住宅地に取って代わられても、その中に点在する農地では引き続き農業が行われてきました。
現在都市農業は、こうした市街地区域内での事業としての農業の他に、
- 市民農園・農業体験
- 一般家庭での家庭菜園
- ビルの屋上を利用した農園
など、農家ではない人々による営利目的でない農業や、農地のない大都市中心部でも行われる農業も含めた、幅広い取り組みを指すようになっています。
近郊農業との違い
都市農業と似たような言葉として、近郊農業あるいは都市近郊農業があります。
両者は明確な区分もなく同じ意味で使われることも多いものの、農林水産政策研究所での分析研究を参考にすると
- 近郊農業:都市の「近郊部=DID(人口集中地区)の500m〜5kmの範囲」で行われる農業
- 都市農業:近郊に加え、DIDの内部+500mの範囲でも行われる農業
というのが都市農業と近郊農業の区分となり、都市からの距離によって分けられます。
例えば、渋谷や銀座などの都心でビルの屋上を利用した農園や養蜂は、都市農業のひとつといえますが近郊農業ではありません。都市農業は、近郊農業に加えてこうした農業も含めた、都市部全域での農業全般のことをいいます。
都市農業が進められてきた背景

都市農業は、最初から現在のように制度として確立され、推進されてきたわけではありません。むしろ都市化、商・工業化が進んできた高度経済成長期には、
- 1955年〜三大都市圏中心の大規模・無秩序な都市化の進行
- 1969年の新「都市計画法」による農地の大量編入
- 市街地区域内農地の宅地並み課税=高額の税負担で都市農地を排除
など、都市の農業・農地は市街地化を妨げるものとして縮小し、排除する動きが進められていきました。
都市農業を守る戦い
こうした国の動きに対し、都市農家は反対運動や一般市民へ向けた都市農業のPRなどの方法で抵抗を続けました。その後も宅地並み課税強化制度をめぐる攻防は続き、1991年の生産緑地法改正によって市街地化区域内農地の約7割が「宅地化する農地」とされます。
これによって都市農業は、残り3割の生産緑地で存続を余儀なくされてしまいました。
都市農業への追い風と政策転換
しかし、時代が進むにつれ、次第に都市農業が見直されるようになっていきます。
きっかけとなったのは1995年の阪神淡路大震災です。震災で都市機能が壊滅状態に陥る中、農業や農地が都市住民の近くにあることの大切さが見直されるようになりました。
また、この頃から食の安全や環境問題への関心が高まり始めたこともあり、都市農業を持続可能にする法整備の必要性が叫ばれるようになっていきました。
そして2015年にはついに都市農業振興基本法が制定され、都市農業の意義と方向性が明文化されるようになりました。都市農業は正反対の政策転換で排除される対象から、推進され振興される対象へと変わったのです。
都市農業の特徴・役割

都市農業は、それ以外の地域で行われている農業とは大きく異なります。
それぞれどのような特徴や役割があるのか、詳しく見ていきましょう。
都市農業の特徴
日本の都市農業が備えている特徴には、以下のようなものがあります。
特徴①生産緑地のほとんどが三大特定市
都市農業の特徴で顕著なのは、そこで農業が行われる生産緑地※のほとんどが、三大都市圏特定市(都の特別区、首都圏、近畿圏、中部圏内の政令指定都市など)にあることです。
生産緑地は市街化区域内農地の半分以上を占めていることから、都市農業は主に生産緑地を中心に行われてきたことがわかります。
特徴②零細農家が多い
都市農業の大きな特徴は、とても規模の小さな零細農家が多いことです。
これは、商業地や住宅地などに囲まれ、まとまった広さの農地がないため、農家個々の経営面積が小さくならざるを得ないという背景があります。
1経営体当たりの経営耕地面積を見ても、全国平均が305アールなのに対し、
- 東京都特別区=54アール
- 名古屋=102アール
- 大阪=52アール
と、いずれの都市でも小さな農地で営農を行っていることがわかります。
特徴③収益性の高い作物が中心
小さな農地にもかかわらず、収益が高い農家が多いのも都市農業の特徴です。
都市農業では稲作や畜産の割合が少ない一方、野菜や果実、花卉などの施設型作物が多く作られて、高い収益を上げています。これは温室などの施設を利用することで、年に数度もの野菜を生産できていることなどが理由です。
1経営体当たり農業産出額を見てみると、全国平均が452万円なのに対し東京都特別区は473万円、名古屋454万円、大阪481万円となっています。販売金額が500万円以上の農業者も約15%に上り、横浜市では平均産出額は682万円という高さです。
特徴④消費者への直接販売が多い

都市農業では消費者への直接販売が多いことも特徴です。
これは人口密度が大きくなるほど顕著になり、10,000人/㎢以上の地域の都市農家では36.8%が直接販売で、15.1%が卸売市場です。これは市場や小売店に近く、多くの顧客に農産物を届けやすいというメリットを生かすことができるためです。
特徴⑤有機農業の実施割合が高い
有機農業への取り組みに積極的なのも都市農業の特徴です。
有機農業を実施している経営体数は、人口集中地区から500m〜5kmでは6%半ばですが、人口集中地区では8.1%となり、人口密度5,000人/㎢以上の地域では9.2%、10,000人/㎢以上だと13.3%と、人口密度が高いほど有機農業への取り組みが多くなっています。
都市農業の6つの役割

また、都市農業には事業・産業としての農業だけではない、さまざまな役割をはたすことが期待されています。農林水産省では、都市農業の役割として以下の6つをあげています。
役割①新鮮な農産物の供給(地産地消機能)
都市農業の重要な役割のひとつが、都市の住民に新鮮な農産物を供給することです。
居住地・消費拠点の近くで農産物を生産できることで
- 地産地消の実現
- 災害など非常時に流通が遮断された場合の食料確保
- フードデザート問題(高齢者など交通弱者が生鮮食料品を入手できなくなる問題)
といった問題解決への貢献が期待されています。
こうした土地農業の役割は多くの住民も理解しており、約7割の都市住民が近くで生産された地場産の野菜を購入したいと考えています。
役割②身近な農業体験・交流活動の場の提供(交流創出機能)
都市農業では作物を育てて収穫する農業体験や市民農園も頻繁に行われています。
これらが果たす役割としては
- レクリエーションとしての市民の健康増進・維持機能
- 農業体験による世代・市民間の交流促進と地域コミュニティの形成・維持機能
などがあります。
都市農業が農業体験や交流活動の場を提供していると考える都市住民は約4割と決して多くはありません。しかし、都市農業に関心を持つ住民は多いため、市民農園や農業体験でこうした交流が促進されることが期待されます。
役割③災害時の防災空間の確保(防災機能)
都市農業を行う農地は、防災の役割も備えています。主な機能としては
- 一時避難場所として利用
- 火災の延焼を防ぐ空間
- 雨水の涵養による都市型水害の抑制
- 消防水としてのため池や水路・農業水利設備
などです。その他にも防災用農地は、生活用水の供給や地震に強い農業施設を活かした緊急避難場所、農作物の供給・貯蔵場所など様々な役割が期待されています。
地方自治体では現在、農家や関係団体の協力で防災協力農地の整備を進めています。
役割④やすらぎや潤いをもたらす緑地空間の提供(景観創出機能)

街の景観を創り出すという面でも、都市農業は重要な役割を果たします。
都市農地は市街地に貴重な緑地や水辺を提供することで、都市住民の生活に「やすらぎ」や「潤い」をもたらしています。
こうした効果に着目し、現在の住宅政策では地域の住宅需要とともに、実情に応じた都市農地の保全に留意するべきという考え方がとられています。
役割⑤国土・環境の保全(環境保全機能)
都市農業には、都市住民への緑の提供による都市環境の保全と改善の機能があります。
現代の大都市では、ヒートアイランド現象や大気汚染、水質汚濁など、生活環境の悪化が深刻な問題です。都市農業は、都市に緑地を増やすことでこれらの影響を緩和し、環境の改善や生物多様性の保全、雨水の保水や地下水の涵養など、国土・環境の保全に貢献します。
役割⑥都市住民の農業への理解の醸成(食育・教育機能)
近年は農業に関心のある人が増えていますが、実際に農業に接する機会がなければさらなる理解の促進にはつながりません。都市農業は、収穫体験や市民農園、学校での農業体験などを通して、市民が農業に触れ合い理解を深める機能を持っています。 さらに学校教育では、農業への理解だけでなく、食育や環境教育によって高い教育効果が期待できます。
都市農業のメリット

都市農業は、地域にとっても住民や都市を利用する人々にとってもさまざまなプラスの効果をもたらします。都市農業ならではのメリットをいくつか紹介します。
メリット①農産物の地産地消につながる
大きなメリットのひとつは、質の良い農産物を地産地消できることです。
都市農業で作られた作物は、消費者に直販される割合が高いため、近くの都市で消費される機会が多くなります。産地と消費地が近いことで輸送・流通にかかる時間や手間が大幅に削減されれば、消費者は新鮮で栄養価の高い農産物を購入できます。さらに、生産者は消費者のニーズに対応した効率的な生産や販売がしやすくなります。
メリット②信頼できる農産物を食べられる
都市農業のもうひとつのメリットは信頼できる農産物を手に入れることができる点です。
近年、世界的な食への関心の高まりによって、人々はより安全で、より信頼できる農産物を求めるようになっています。小規模な都市農家で作られた作物は、近場の直売所や小売店、ファーマーズマーケットなどに卸されるケースが多く、そこでは誰がどこでその作物を作ったかがわかるようになっています。
メリット③新規就農へのハードルが下がる
農業に興味がある人や新規就農を考えている非農家の人にとって、都市農業で行われる農業体験や市民農園はうってつけの予行演習です。
それまで農業の経験がない人が、一から始めるのは簡単なことではありません。
市民農園などで小規模な農地を間借りし、本格的な作物栽培を経験することは、農業を始めたいと考える人たちのハードルを下げ、新たな担い手を生み出すきっかけになります。
都市農業のデメリット・課題

一方、都市農業にもデメリットや解決すべき課題は残されています。
デメリット・課題①投資コストの高さ
都市農業は新規就農のハードルを下げる反面、実際の参入には困難が伴います。
その理由はいくつかありますが、最も大きいのは施設の投資コストの高さです。
都市農業では小規模でも経営が成り立つ営農方法が必要であり、狭い農地でも利益を出せる施設農業を始めるには、高い技術や大がかりな設備が必要です。
こうした設備は投資金額がかさむため、投資をためらう農家は規模の縮小や自給的農家へ転向し、規模の二極化を引き起こします。中には営農自体の断念にもつながってしまうため、JAなどが中心となって対策を立てることが求められます。
デメリット・課題②都市農地制度・税制の問題
多くの農家が都市農業を進める上で支障になると考えているのが、税負担の問題です。
都市農業についてはさまざまな制度改善がなされたとはいえ、現行の都市農地制度は都市農地の保全・活用の面では限界があると言わざるを得ません。
現在の法制度では、2022年以降、30年経過の生産緑地が特定生産緑地に指定され、指定されない場合は非特定生産緑地になります。その結果、
- 特定生産緑地は納税猶予が継続(終身営農が条件)
- 特定市の都市農地は生産緑地か特定生産緑地でないと固定資産税や相続税が高額に
- 生産緑地以外の市街化区域内農地は宅地並みの固定資産税(20年就農で猶予)
など、税制の特例措置が適用されない都市農地が増えることになります。
こうした固定資産税や相続税の高い税負担は、農業の廃業や農地減少の原因ともなっているため、宅地化農地や非特定生産緑地、(特定市以外の)一般市町村の市街化区域農地などへの税制特例措置の改善などが必要です。
デメリット・課題③後継者・担い手確保の問題
近年目立つようになっているのが、都市農業の後継者や担い手の減少です。
高齢化などに伴う後継者不足は農業全体の問題ですが、都市農業の場合は前述の農地の税負担によって農地を転用し、廃業してしまうケースも少なくありません。
都市農業は関心の高い新規就農希望者も少なくないため、農地の税負担の見直しに加え、
- 非農家=耕す市民による取り組みの推進
- 食品関連や周辺ビジネスを展開する企業
- 小規模農家の育成
など、労働者確保に向けた農業政策の多様化を進めていくことが必要になります。
都市農業の実践例

現在、全国の都市部では、都市農業の振興のために意欲的な取り組みを行っている農家がたくさんあります。ここではその中でも注目すべき実践例を、いくつか紹介していきたいと思います。
実践例①白石農園(東京都練馬区)
白石農園は、東京都練馬区で140アールの農地を有する農家です。同農園では2019年から、従来の多品種生産に加えて、都内ではほとんど栽培されていないアスパラガスの栽培に乗りだします。そこには、他農園との差別化を図るとともに、地場産野菜への関心を高めるという狙いがありました。
同農園は都市農業を支援する政策の追い風を受けて設備投資を進めながら、
- 野菜の選別や梱包を福祉作業所に委託する「農福連携」への取り組み
- 収穫体験イベントや援農ボランティアを通じて都市農業に親しめる活動を行う
など、都市農業振興のための積極的な経営を展開しています。
実践例②七彩ファーム(大阪府羽曳野市)
七彩(なないろ)ファームは、異業種から新たに農業を始めた女性2人が運営する農園です。ここでは130アールの畑で15種類の野菜を化学肥料を使わずに栽培し、低価格競争を避けるため主に個人経営の八百屋や高価格帯の直売所などへ出荷しています。
同時に、農業に興味のある消費者を募って援農ボランティア活動を開催。この他にもピザ焼きイベントやオリジナル商品の販売などさまざまな企画を展開し、農業を通じて人と人をつなぐ取り組みを進めています。
実践例③JA世田谷目黒(東京都世田谷区・目黒区)
JA世田谷目黒では、高齢化や後継者難などの理由で耕作できなくなった生産緑地を借り上げ、会員や近隣住民を対象にした体験農園事業を行っています。
これは2018年に制定された都市農地貸借法(体験農園を設置することで地権者が営農しなくても農地を維持できる法律)を活用したもので、地権者にとっては、JAが土地の貸借や相続の対応などをサポートしてくれるので安心です。
現在は世田谷区内に5か所の農園が開設されていますが、募集後はどこもすぐに定員が埋まってしまうなど、住民の都市農業に対する関心の高さがうかがえます。
実践例④アーバン・ファーマーズ・クラブ(東京都渋谷区)
アーバン・ファーマーズ・クラブは、渋谷区を中心に自分たちで食べる野菜を自分たちで作ろう、というプロジェクトを実現するために立ち上げられたNPO法人です。
同クラブでは「渋谷の畑」と銘打ち、遊歩道や恵比寿ガーデンプレイスの敷地内、ビルの屋上など渋谷区内の4カ所に畑やプランターを設け、プロジェクトの参加者たちが野菜やハーブ、オーガニックコットンなどさまざまな作物を栽培しています。
都市農業とSDGs

都市に農業生産拠点を獲得する都市農業には、SDGs(持続可能な開発目標)とも大きく関連のある取り組みが含まれています。直接関連のあるものだけでも
目標2「飢餓をゼロに」:地産地消による都市部への安定的な食料供給
目標6「安全な水とトイレを世界中に」:農業用水に適した水と水源を確保することで、都市部でも安全な水が得られる
目標11「住み続けられるまちづくりを」:防災機能の強化や地域コミュニティの促進により、包摂的で安全・強靭な都市環境を実現する
目標12「つくる責任つかう責任」:安全で質の高い食料を近隣に提供することで、適正で効率的な生産消費体制を確立する
目標13「気候変動に具体的な対策を」:過度な都市化に歯止めをかけ緑地を増やすことで、都市のヒートアイランド対策となる
目標15「陸の豊かさも守ろう」:生産緑地の増加によってグリーンインフラが整備され、都市環境の改善や生物多様性の保全につながる
といった複数の目標があげられ、都市農業が都市とそこに暮らす人々の生活をさまざまな方面から持続可能なものにできるということがわかります。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ

日本の都市でも古くから根付いていた都市農業は、紆余曲折を経て確固たる地位を確立しました。近年では新型コロナウイルスによるパンデミックによって、都市部での家庭菜園やベランダ菜園が注目されていたのは記憶に新しいところです。
たとえ都市がどれだけ大きくなろうとも、人は食と土、そして農業と無縁で生きていくことはできません。現在の都市農業への関心の高まりは、私たちが本来あるべき姿に気づき始めた第一歩と言えるのではないでしょうか。
参考文献・資料
都市農業の持続可能性:八木洋憲・吉田真悟編著/日本経済評論社,2023年
都市農業新時代 いのちとくらしを守り、まちをつくる:中塚華奈・榊田みどり・橋本卓爾編著/実生社,2023年
都市農業の時代 食料安全保障へ 反転攻勢始まる:青山佾 著/一般社団法人全国農業会議所,2023年
都市農業について:農林水産省
都市農業をめぐる情勢について:農林水産省
都市・都市近郊農業における構造変化と立地別の特徴 農林水産政策研究所 農業・農村領域研究員 吉田真悟:農林水産省
持続可能な都市農業の実現に向けて:日本学術会議 農学委員会 農業生産環境工学分科会
近郊農業とは?園芸農業との違いやメリット・デメリットを徹底解説 | コラム | イノチオグループ
都市の農業・農地の果たしている多面的役割|国土交通省
都市農業に関する実態調査 (農村振興局)
渋谷の街中で追求する農業の可能性 aff 2019年11月号:農林水産省
アーバンファーマーズクラブ
この記事を書いた人
shishido ライター
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。