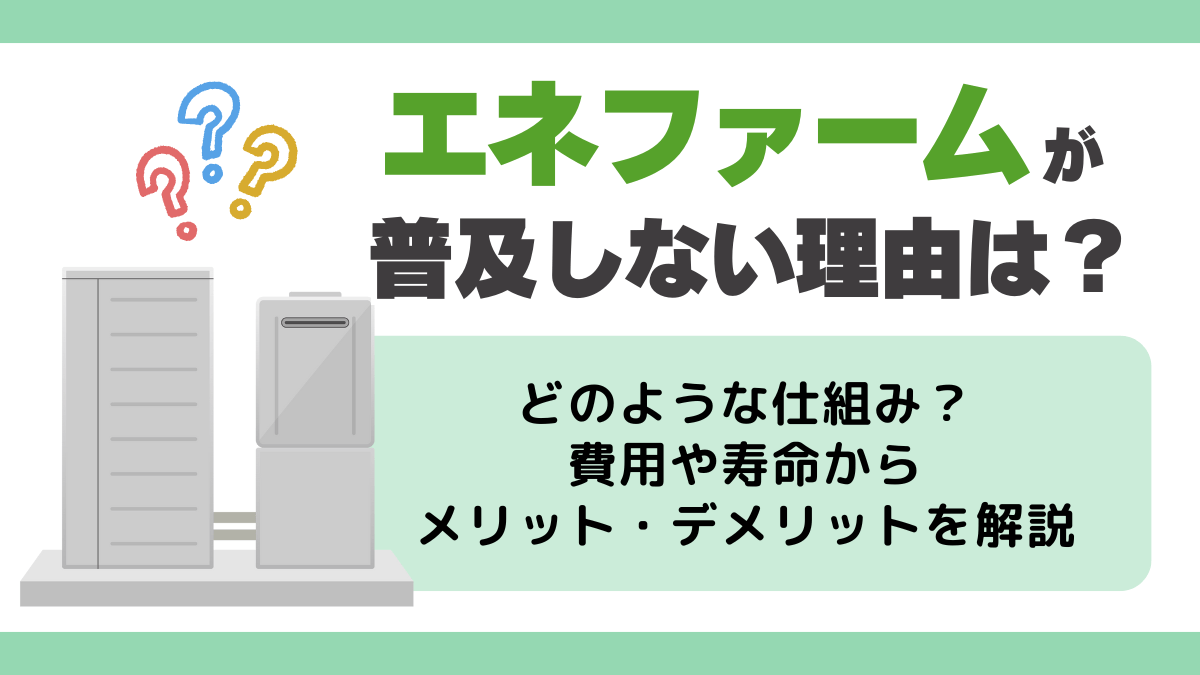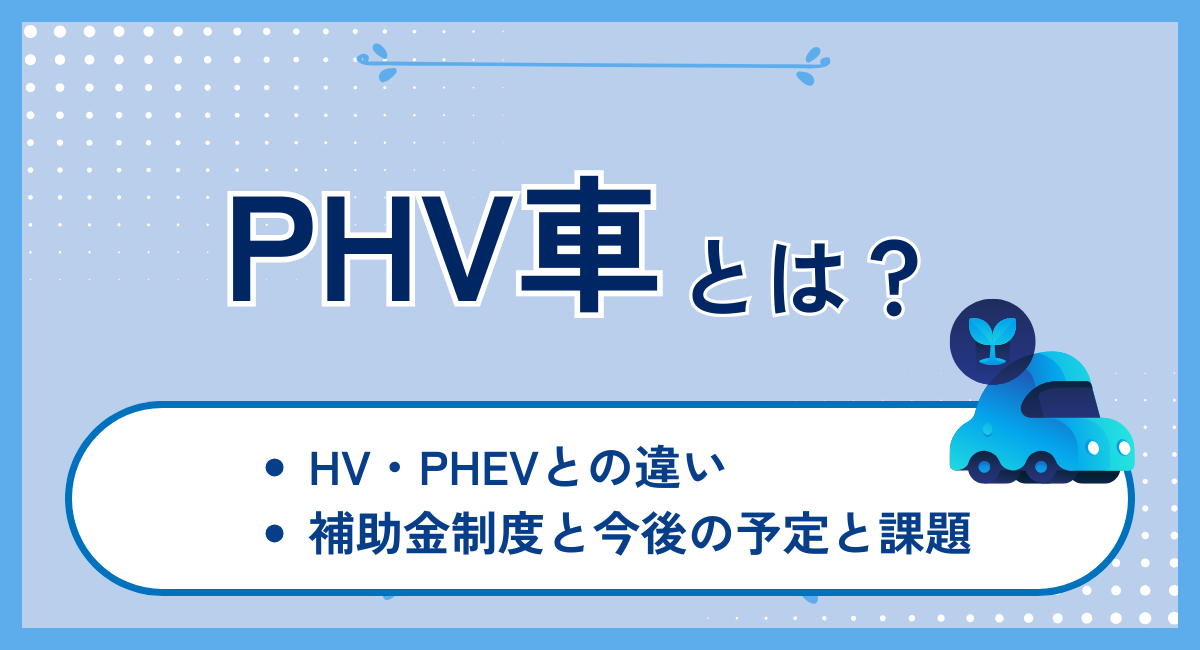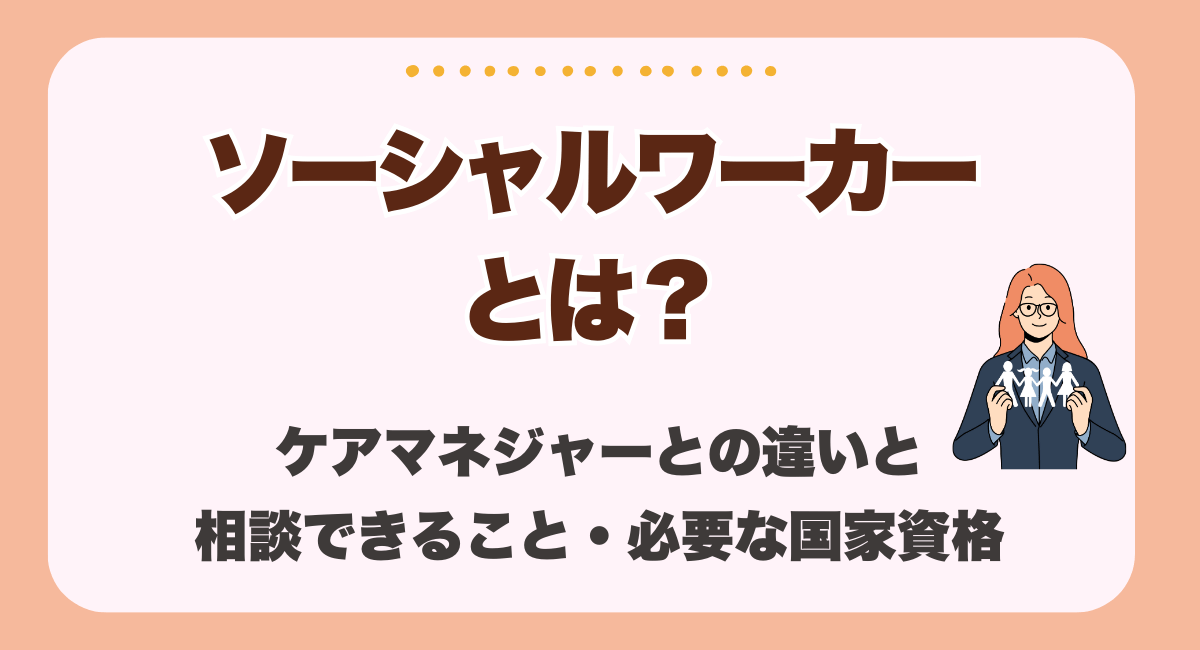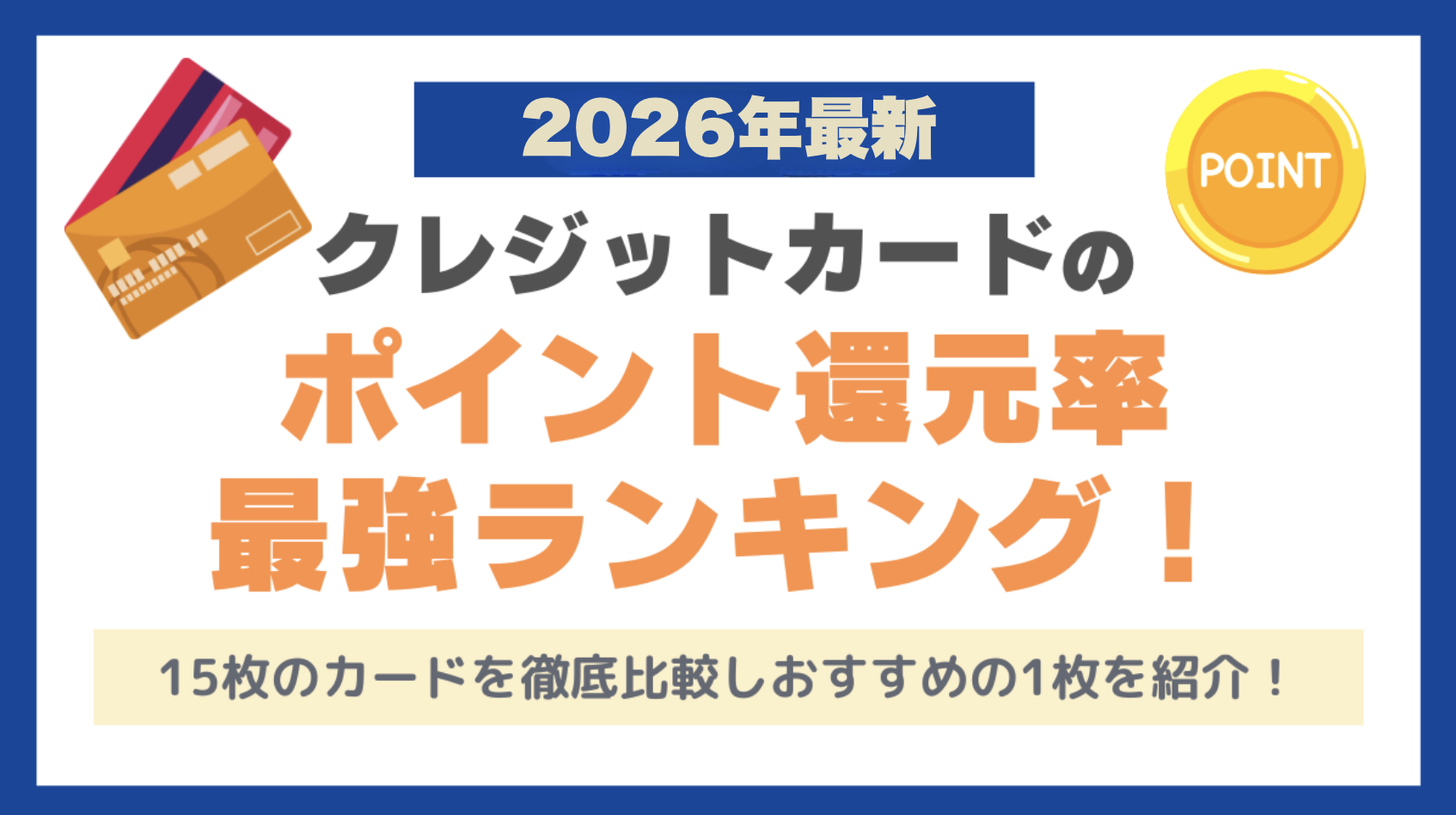私たちの社会には、様々な障害のある人々が暮らしています。目が見えにくい方、耳が聞こえにくい方、車椅子を使用する方など、障害の種類や程度は人それぞれです。しかし、どのような障害があっても、誰もが自分らしく生きる権利があります。
そんな思いを実現するために、日本には「障害福祉サービス」という制度があります。この制度は、障害のある方々の日常生活や社会参加を支援し、自立を促進することを目的としています。
では、具体的にどのようなサービスがあるのでしょうか?そして、どのように利用できるのでしょうか?ここでは、障害福祉サービスについて詳しく見ていきましょう。
目次
障害福祉サービスとは?わかりやすく解説
障害福祉サービスとは、障害者総合支援法に基づいて提供される支援制度です。この制度の目的は、障害のある方が自立した日常生活や社会生活を送るために必要な援助を受けられるようにすることです。
サービスの内容は大きく二つに分けられます。一つ目は「介護給付」で、これは居宅や施設などで介護の支援を受けるためのものです。二つ目は「訓練等給付」で、施設などで就労に向けた訓練等を受けるためのものです。
これらのサービスを通じて、障害のある方の生活の質の向上と社会参加の促進を図っています。
障害福祉サービスの基礎知識
障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づき、障害のある方が自立して地域で暮らすことを支援する制度です。支援内容は生活援助から就労支援まで多岐にわたり、利用には市区町村による認定が必要です。
本制度は原則として利用者に一定の費用負担が発生しますが、世帯の収入に応じて上限が設定されるなど、誰もが安心してサービスを受けられるよう工夫されています。
利用者負担の仕組み
障害福祉サービスの費用は、原則として1割の自己負担が発生します。ただし、負担額には世帯の所得に応じた月額の上限額が設けられており、過度な経済的負担を防ぐ仕組みになっています。
具体的な上限は以下のとおりです。
- 生活保護世帯:自己負担なし
- 市町村民税非課税世帯:月額上限額 0〜9,300円程度
- 一般世帯(課税):月額上限額 37,200円(所得により変動)
さらに、障害福祉サービスと介護保険制度の両方を利用している場合でも、二重に負担がかからないよう合算調整が適用される場合があります。利用開始後も、負担が重く感じる場合は、市町村に相談することで減免や補助制度が利用できることがあります。
障害福祉サービスの対象となる人
障害福祉サービスの対象となるのは、以下の人です。
- 身体障害のある人
- 知的障害のある人
- 精神障害のある人
- 難病等を有する人
障害には様々な種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。身体障害は、目や手足、内臓の機能などに問題があり、日常生活に支障がある状態を指します。知的障害は、知的な発達が遅れているために、日常生活や社会生活に適応することが難しい状態です。
精神障害は、心の病気によって感情や考え方、行動に問題が生じている状態を指します。また、政令で指定された難病による障害を持つ方も含まれます。
障害のある方が利用できるサービスは、障害の種類や程度によって異なることがあるので、事前に確認することが大切です。
障害福祉サービスの種類と内容を一覧で紹介
| 分類 | サービス名 | 内容の概要 |
|---|---|---|
| 介護給付 | 居宅介護 | 自宅での入浴・排泄・食事など日常生活の支援 |
| 介護給付 | 重度訪問介護 | 重度の障害がある方への、移動・生活支援を一体的に提供 |
| 介護給付 | 行動援護 | 知的・精神障害者の外出時に必要な援護 |
| 介護給付 | 同行援護 | 視覚障害者の外出時の支援 |
| 介護給付 | 短期入所 | 自宅で介護が困難なときの一時的な入所支援 |
| 介護給付 | 生活介護 | 日常生活の支援と創作・生産活動などの機会を提供 |
| 介護給付 | 施設入所支援 | 施設に入所しながら生活全般の支援を受けるサービス |
| 訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練) | 身体機能や生活能力の維持・向上を目指した訓練 |
| 訓練等給付 | 自立訓練(生活訓練) | 日常生活を営む能力を育む訓練 |
| 訓練等給付 | 就労移行支援 | 一般就労を目指す障害者への職業訓練や就労支援 |
| 訓練等給付 | 就労継続支援A型 | 雇用契約を結びつつ支援付きで働く場を提供 |
| 訓練等給付 | 就労継続支援B型 | 雇用契約はないが、継続的な作業活動を支援 |
| その他 | 共同生活援助(グループホーム) | 少人数での共同生活を行う施設での生活支援 |
| その他 | 自立生活援助 | 一人暮らしを希望する人のための生活支援 |
障害福祉サービスの内容は多岐にわたっています。
大きく分けると、介護給付と訓練等給付の2つに区分できます。それぞれの内容について詳しく見てみましょう。
介護給付
介護給付は、高齢者や障がいを持つ方が日常生活を円滑に送れるよう支援するための重要なサービスです。「訪問系」「日中活動系」「施設系」などが存在します。それぞれの内容について詳しく確認します。
訪問系
訪問系に区分されるのは、以下の5つのサービスです。
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 重度障害者等包括支援
居宅介護はホームヘルプサービスのことで、介護が必要な方の自宅をホームヘルパーが訪問して介護サービスを提供します。提供されるサービスは、排せつや入浴の介助、食事のサポート、洗濯・掃除などのサポートです*2)。
重度訪問介護とは、日常生活を送るうえで常に介護が必要なほど重い障害を持っている方を対象としたサービスです。居宅介護のサービスよりも包括的で、外出や入院の際の支援なども行います*2)。
視覚に障害のある方が安心して外出できるよう、サポートするサービスが同行援護です。移動の際には、付き添って必要な情報を伝えたり、安全を確認したりします。また、視覚的な情報が必要な場合は、代筆や代読なども行います。さらに、外出先でのトイレや食事のサポートも必要に応じて実施し、安心して過ごせるように支援します*2)。
行動援護は、知的障害や精神障害を持つ方の外出をサポートするサービスです。これらの障害により、一人で外出することが難しい方が対象となります。外出中に危険なことが起きないように、必要なサポートをおこないます*2)。
重度障害者等包括支援は、重い障害を持った方々が必要とする多様な支援を総合的に提供する取り組みです。自宅での介護や外出時の支援など、個々のニーズに合わせて様々なサービスを組み合わせて提供します*2)。
日中活動系
日中活動系に分類されるのは、以下の3つのサービスです。
- 短期入所(ショートステイ)
- 療養介護
- 生活介護
自宅で暮らす障害者の方が、家族の怪我や病気、冠婚葬祭への参加など、一時的に自宅での生活が難しい場合に、短期間だけ施設を利用できるサービスが短期入所です。主に障害者支援施設で行われていますが、一部のグループホームや宿泊施設を備えた通所施設なども提供しています*2)。
療養介護は、医療と常時介護の両方を必要とする障害のある方を対象としたサービスです。病院などの医療機関に長期間入院している方が対象で、機能訓練や療養上の管理、看護、日常生活の介助などを日中を中心に提供します。このサービスには、医療保険が適用される療養介護医療も含まれています*3)。
生活介護は、常に介護が必要な障害者の方々を対象としたサービスです。施設に通える方に、日常生活に欠かせない入浴、排せつ、食事などの基本的な支援を提供します。さらに、利用者の方々の生活をより豊かにするため、創作活動や生産活動の機会も設けています*2)。
施設系
施設系に区分されるのは、施設入所支援です。日中は自立訓練や就労移行支援、生活介護などを利用している方に向けて、夜間のサポートを提供します*2)。
訓練等給付
障害のある方が、日常生活や社会生活をスムーズに送れるよう、必要な訓練などを提供するのが訓練等給付です。この給付は、大きく分けて居住支援、就労支援、自立訓練の3つのカテゴリーに分けられます。それぞれのサービス内容の詳細については、以下で詳しく説明していきます。
居住支援系
居住支援系に含まれるのは、以下の2つです。
- 自立生活援助
- 共同生活援助(グループホーム)
自立生活援助は、自宅で自立した生活を送りたいと希望する障害のある方を対象としたサービスです。支援員が定期的にご自宅に伺い、生活に必要な手続きのフォローや、困りごとに関する助言などを行うことで、安心して暮らせるようにサポートします*2)。
共同生活援助は、障害のある方が集まって生活する場所で、専門のスタッフが生活全般をサポートするサービスです。主に夜間に行われ、食事や入浴、排せつなどの基本的な生活支援から、お金の管理や健康面のケア、緊急時の対応まで幅広い援助を受けられます。
就労支援系
就労支援は、以下の4つに区分されます。
- 就労移行支援
- 就労定着支援
- 就労継続支援A型(雇用型)
- 就労継続支援B型(非雇用型)
就労移行支援は、一般企業への就職を希望する障害のある方のうち、雇用されることが可能と見込まれる方を対象としたサービスです*2)。就労に必要な知識や能力を向上させるための訓練として、企業実習や個々の適性に合わせた職場探しなどを実施します。原則として、利用期間は最長2年間です*4)。
就労定着支援は、障害のある方が一般企業などで働き続けるためのサポートを行うサービスです。企業や医療機関などと連携し、日常生活や仕事上の課題に対して、環境調整や助言などを行います*2)。就労移行支援等を利用して就職した方を対象としており、就職後6ヶ月以降から最長3年間利用することができます*4)。
就労継続支援A型(雇用型)は、一般企業への就職が難しいけれど、サポートがあれば継続的に働くことができると期待される方々を対象としたサービスです。
このサービスでは、働く場と活動の機会を提供します。利用者は雇用契約を結ぶため、労働基準法に基づき最低賃金以上の給与が支払われます。原則として65歳未満の方なら、利用期限を気にすることなくサービスを利用できます*2)*4)。
就労継続支援B型(非雇用型)は、雇用契約を結ぶことが難しい障害のある方を対象に、働く場や活動の機会を提供するサービスです。就労継続支援A型とは異なり、雇用契約は結ばず、活動に見合った「工賃」が支払われます。利用期限はありません。通常の企業への就職が難しい方、就労移行支援を受けても就職に至らなかった方などが、生産活動などを通して、就労に必要な知識や能力を身につけられるよう支援を行います*2)*4)。
自立訓練
自立訓練に分類されるには、以下の2つのサービスです。
- 自立訓練(生活訓練)
- 宿泊型自立訓練
自立訓練(生活訓練)とは、障害のある方が自立した日常生活を送れるように支援するものです。障害者支援施設などに通ったり、自宅を訪問したりする形で、入浴、排泄、食事などに関する訓練や、生活相談、助言などを行います*2)。
宿泊型自立訓練とは、日中、一般就労や外部の障害福祉サービス、または同じ敷地内にある日中活動サービスを利用している方などを対象に、夜間の居住の場を一定期間提供するサービスです。帰宅後に生活能力などを維持・向上するための訓練を実施したり、昼夜を通して訓練を実施したりします*5)。
障害福祉サービスの利用の流れ
障害福祉サービスを受けるには、市町村への利用申請が必要です。ここでは、サービスを受けるための流れについて解説します。
障害福祉サービス受給者証とは
障害福祉サービス受給者証(受給者証)は、市区町村などの自治体が発行する証明書です。この受給者証を取得すると、障害福祉サービスを利用する際にかかる費用のうち、一部または全額を公費で負担してもらえます。
受給者証には、月に利用できるサービスの日数や、自己負担する必要がある金額が記載されていますが、障害者手帳とは異なるものなので、注意が必要です。
利用申請の流れ
利用の流れは以下の通りです。
- 市町村にサービスの利用を申請
- 認定調査の実施
- 一次判定
- 二次判定
- 市町村による認定と受給者証の発行
市町村は申請を受け付けると、認定調査員を派遣して訪問調査を実施します。調査内容は以下のとおりです。
| 概況調査 | 本人や家族、介護者の状況日中活動の状況居住環境など |
| 障害支援区分認定調査 | 80項目の調査(アセスメント) |
| 特記事項 | 障害支援区分認定調査だけではわかりにくい本人の状況 |
*6)
一次判定では、アセスメント結果や医師の意見書などにもとづいてコンピュータが判定します。これにより、障害者支援区分が決定します。二次判定は、障害保健福祉の専門家による審査で、一次判定の結果や特記事項、医師の診断書をもとに区分を審査します。これらの判定を経て、申請者の障害支援区分が決定し、申請者に通知します*6)。
市区町村で障害支援区分が決定すると、その区分に基づいて利用できるサービスの量が決まります。そして、市区町村から受給者証が交付されます。その後、障害福祉サービスを提供する事業者がサービス等利用計画を作成し、利用者と契約を結ぶことで、サービスの利用を開始することができます。
障害福祉サービスに関するよくある質問
ここでは、障害福祉サービスに関するよくある質問を紹介します。
2024年の障害福祉サービスの報酬改定とは?
2024年度の障害福祉サービスの報酬改定率は、全体で1.12%の引き上げとなります。これは、サービス提供の対価として国から事業者に支払われる報酬が、これまでより増加することを意味します*8)。
報酬改定によって、障害福祉の現場で働く人の給与が向上し、より質の高いサービス提供体制が整うことが期待されます。国は、今回の報酬改定や同時に実施される処遇改善加算の一本化を通じて、障害福祉に携わる人が安心して仕事に就き、安定したサービスが提供されることを目指しています*9)。
事業所一覧はどこでわかる?
障害福祉サービスを提供している事業者を探したい場合、便利な方法があります。「障害福祉サービス等情報検索」というウェブサイトを使うと簡単に探せます。
このサイトは、独立行政法人福祉医療機構が運営しています。
使い方は以下の通りです。
- サイトにアクセスする
- トップ画面に日本地図が表示される
- 探したい都道府県をクリックする
- 住んでいる市町村をクリックする
- その地域の障害福祉サービス事業者が表示される
このように、自分の地域の事業者を素早く見つけることができます。
障害福祉サービスの利用者負担は?
障害福祉サービスを利用する際、原則としてサービス費用の1割が自己負担となります。ただし、所得状況に応じて「月額上限額」が設けられており、それ以上の費用は支払う必要がありません。
たとえば、住民税非課税の世帯では月額上限が0〜4,600円に抑えられることが多く、生活保護世帯は無料です。負担軽減措置もあり、必要に応じて自治体に申請することで利用者負担をさらに減らせるケースもあります。
所得区分は世帯単位で判断され、制度の詳細は市区町村によって異なることがあります。
障害福祉サービスを受けるにはどうすればいい?
障害福祉サービスを受けるには、まず市区町村の障害福祉窓口に相談・申請を行う必要があります。その後、障害支援区分の認定調査が実施され、必要と認められた場合は「受給者証」が交付されます。
次に、サービス等利用計画を作成し、希望するサービス事業所と契約して利用が始まります。申請から利用開始までには一定の期間がかかるため、早めの相談がおすすめです。初めての申請では、相談支援専門員のサポートを受けるとスムーズです。計画相談支援が必要な場合もあるため、事前に自治体に確認しましょう。
介護給付と訓練等給付の違いは?
障害福祉サービスは「介護給付」と「訓練等給付」の2つに大別されます。介護給付は、主に日常生活を送るうえでの支援を行うもので、居宅介護(ホームヘルプ)や重度訪問介護、生活介護、短期入所などが含まれます。
一方、訓練等給付は、利用者の社会参加や就労に向けた力を育む支援で、就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)、自立訓練(生活訓練・機能訓練)などが該当します。目的の違いに応じて支援内容が異なるため、自分に合った支援を選ぶことが大切です。
障害福祉サービスとSDGs
持続可能な開発目標(SDGs)は、「誰一人取り残さない」という考え方にもとづいて作られた目標です。何らかの理由で障害を抱えている人も、SDGsでサポートする対象と考えられます。ここでは、障害福祉サービスとSDGs目標10との関わりについて解説します。
SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」との関わり
SDGs目標10.2では「2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。」と定められています*10)。
日本国内でも、政府が「障害を理由とする差別の解消」を掲げ、障害者差別解消法が制定されました。障害のある人もない人も共に生きる「共生社会」の実現を目指しているのです*11)。障害福祉サービスは、障害を持っている人とそうではない人が同じように生きるために必要なサービスではないでしょうか。
まとめ
障害福祉サービスは、障害のある方のニーズに合わせて、介護給付、訓練等給付など多岐にわたるサービスを提供しています。利用するには、市町村への申請が必要です。サービスを受けることで、障害のある方が住み慣れた地域で、自分らしく安心して生活できるよう支援します。
2024年には報酬改定も行われ、より質の高いサービス提供体制が期待されています。障害福祉サービスは、SDGsの目標である「誰一人取り残さない」社会の実現にも貢献する重要な取り組みと言えるでしょう。
参考文献
*1)デジタル大辞泉「障害者総合支援法」
*2)厚生労働省「障害福祉サービスについて」
*3)障害福祉情報サービスかながわ「療養介護」
*4)厚生労働省「就労移行支援」
*5)厚生労働省「宿泊型自立訓練」
*6)東京都福祉局「障害福祉サービス等の利用手続き」
*7)厚生労働省「障害者総合支援法における「障害支援区分」」
*8)厚生労働省「障害福祉サービス等の最近の動向について」
*9)厚生労働省「「処遇改善加算」の制度が一本化(福祉・介護職員等処遇改善 加算)され、加算率が引き」
*10)外務省「JAPAN SDGs Action Platform」
*11)内閣府「チラシ「障害者差別解消法が改正に事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました」
*12)
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。