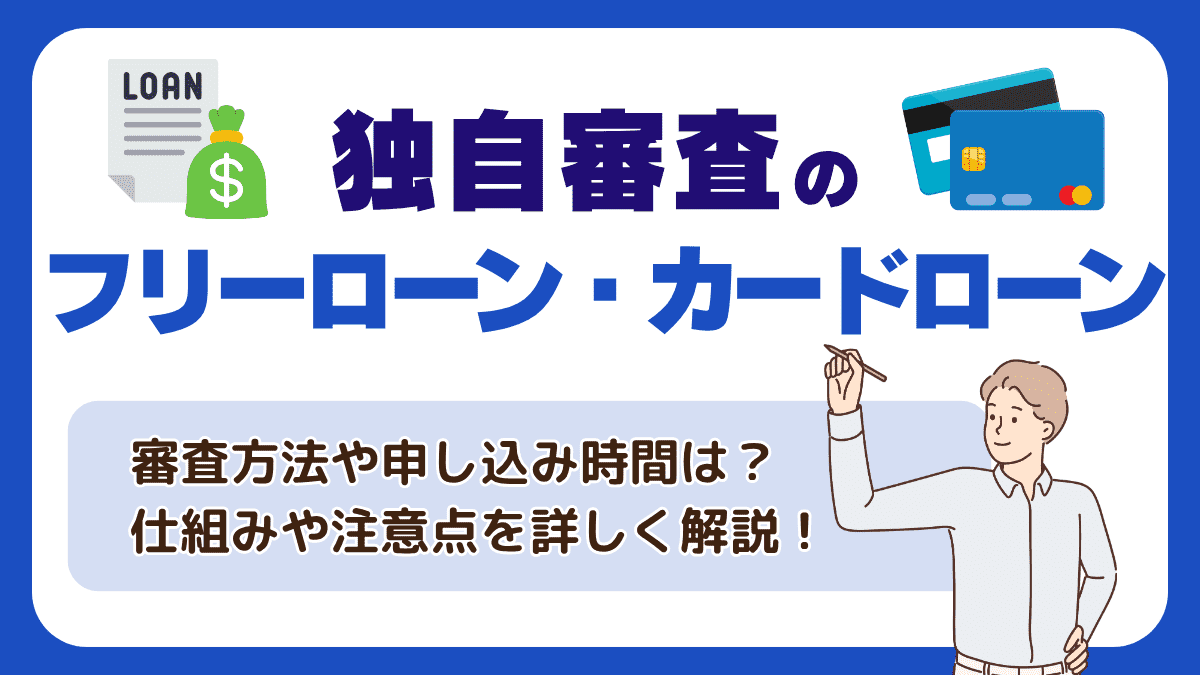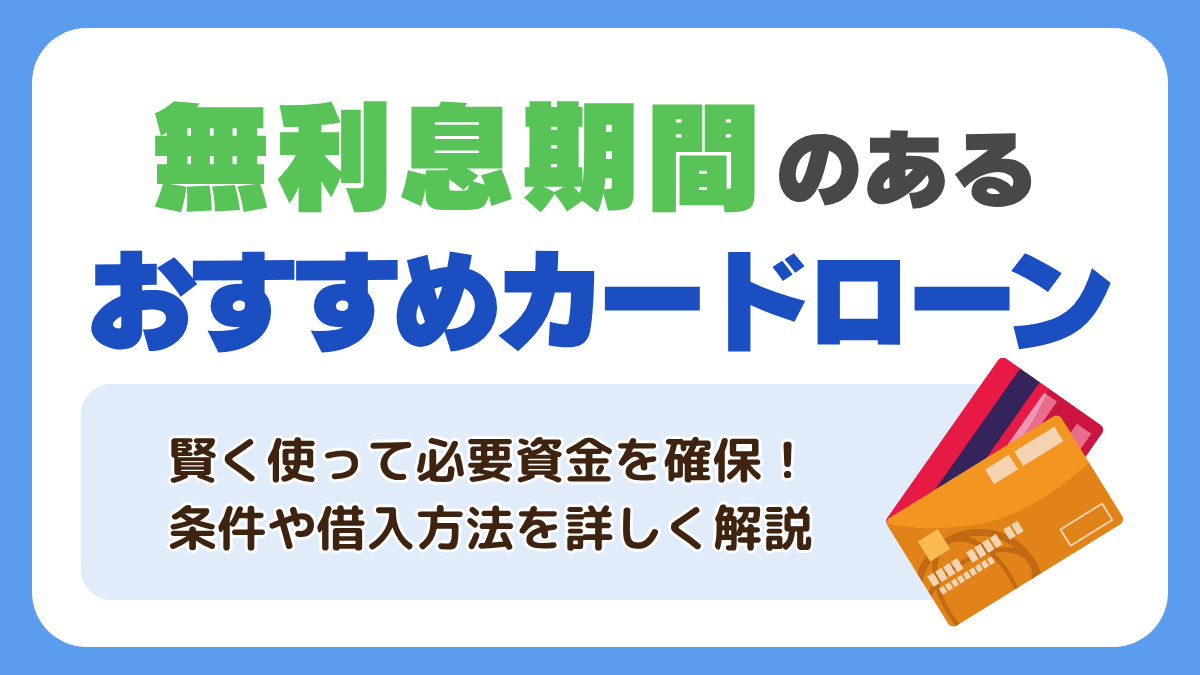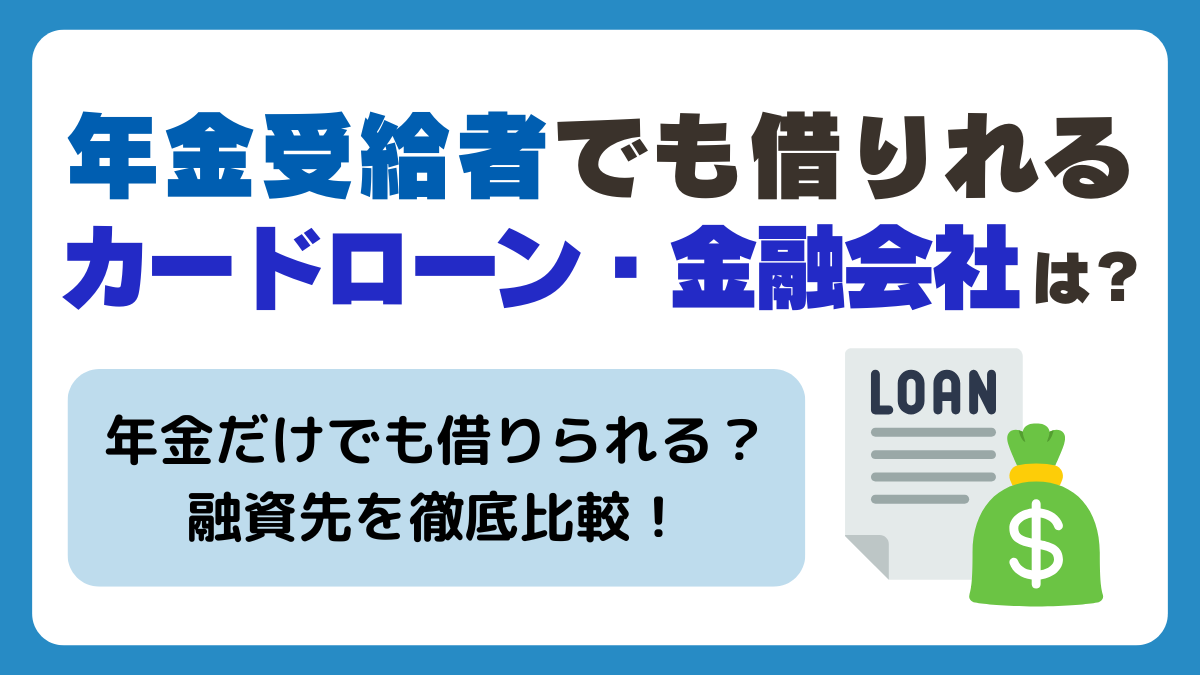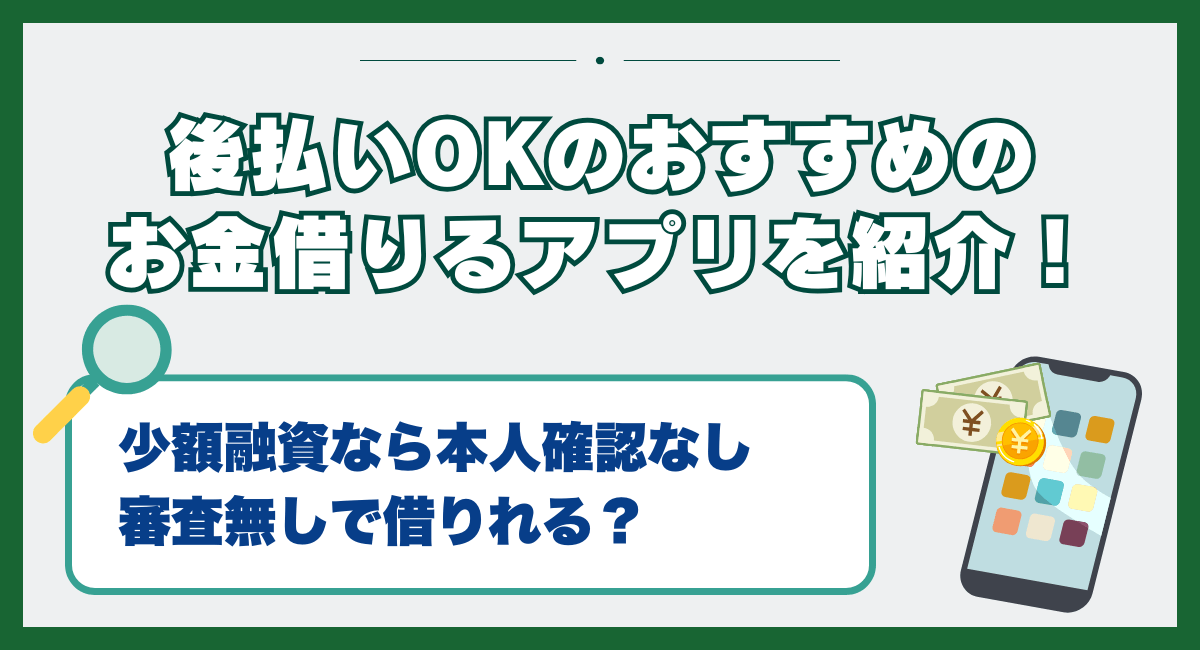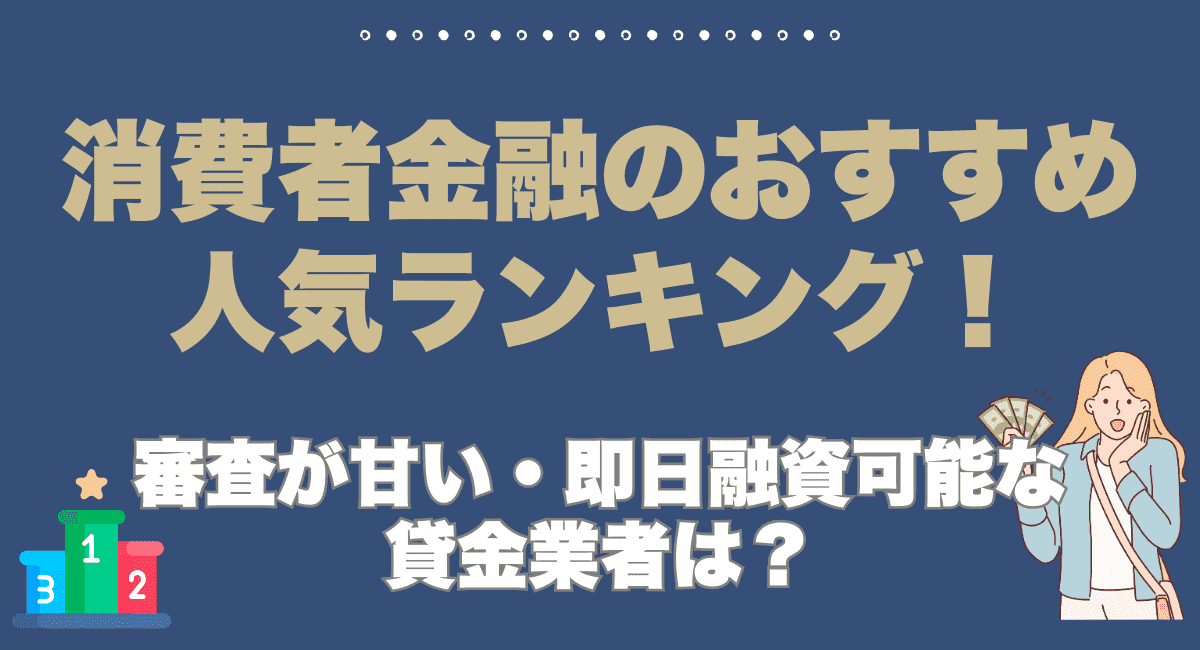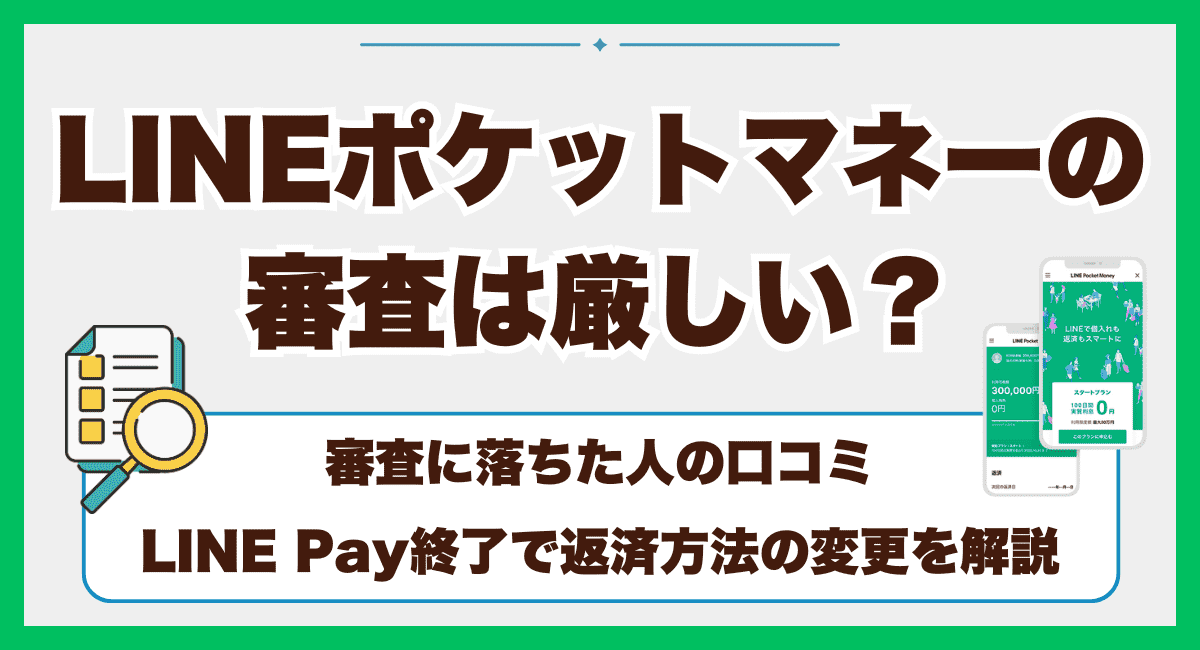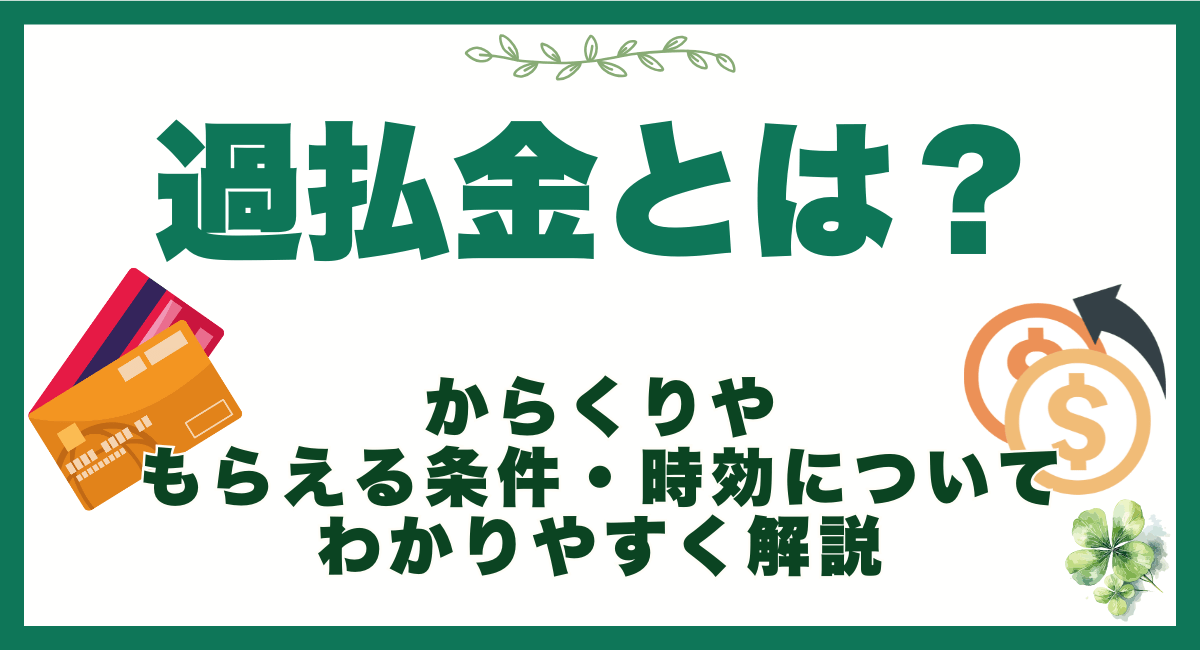
CMやネット広告などで「過払金請求」という文字を何気なく見たことがあるかもしれません。
これは過去に、当時の法律の抜け穴を利用した「グレーゾーン金利」により、貸金業者が提案した法外な金利でお金を借りてしまった人を救済するものです。
すべての人が対象ではないものの「もしかしたら自分も払いすぎているかも」と感じられた方は多いでしょう。
今回は、過払金の基本的な情報にくわえ、請求できる人や当てはまらない人の特徴、請求権が消滅する時効や、実際の過払金請求を行う流れについて、詳しく解説していきます。
目次
過払金とは?からくりが気になる方へ
過払金とは、貸金業者から借りたお金を返すときに、法律で決められている上限利率を超過した融資の契約をしたために、余分に支払ってしまった(返しすぎた)利息のことです。
過払い金の根拠となる法律とは「利息制限法」のことであり、貸金業者からお金を借りる際の利息について以下のような制限が設けられています。
- 元本が10万円未満:年率20%
- 元本が10万円以上100万円未満:年率18%
- 元本が100万円以上:年率15%
上記のとおり、利率の上限は貸金業者から借りるお金が高額であるほど高くなります。逆に言えば、貸金業者は100万円を超えていれば、たとえ500万円でも1000万円でも、20%以上の金利で貸し付けてはいけません。
借りる側はどれだけ多額のお金を借りていても、上記の利率を超えて支払われた利息分は法的に払い損、いわば無効となります。
そのため、すでに高い利息を過去に支払ってしまった人は「過払金請求」をすれば、貸金業者からお金を返してもらえる可能性があります。
実は、この利息制限法における金利上限は今も昔も変わりません。それにもかかわらず、なぜ「返済し過ぎる」人が発生したのか、それは利息制限法とは異なる、もう一つの法律が関係しています。
からくりのポイントは2つの法律の金利のズレ?
| 法律名 | 内容 | 上限金利 |
|---|---|---|
| 旧出資法 | 高金利を取り締まるための法律 | 年29.2% |
| 旧利息制限法 | 借主を保護するための上限利率規制 | 年20.0% |
大前提として、すべての消費者金融が対象となる現行法では、正規の貸金業者は利息制限法を遵守しないと国内で正規営業ができず、闇金と同格になってしまいます。
そのため、利用者が普通にお金を借りている分には、高い利息を支払わされることはまずありません。
しかし今から約50年前、1954年以降の日本における「旧出資法」と、利息制限法における上限金利には大きなずれがありました。それが多くの貸金業者による高金利での貸付を助長させ、過払金問題を発生させた大きな原因です。
まず上記の表に記載のとおり、出資法における貸金業者の上限金利は「29.2%」でした。
それに対して、利息制限法の上限は現在の上限と同じ「20%」であり、利息制限法の上限を超えているものの、事実上罰則はない「グレーゾーン金利」となっていました。
- 20%:正規の上限金利
- ~29.2%:グレーゾーン金利(罰則なし)
- ~109.5%:個人間融資の上限金利(業者は不可)
当時の貸金業者はこれを利用し、利用者に対して20%を超える高金利で貸付することが常態化していました。実際のところ業者は20%を超えて貸し付けても、ほぼリスクがなかったからです。
2006年のある調査では、全貸金業者のうち約46%がグレーゾーン金利での貸付を行っており、貸付残高が5,000万円を超える大手に関しては、ほぼすべての業者が該当していたと報告されています。
この背景には「みなし弁済」という、いくつかの条件を満たしたうえで、借主が任意で支払った利息は有効になる、という内容の規定があったことが影響しています。
のちの最高裁における判例により、このみなし弁済は実質的に廃止されました。
2010年6月に貸金業法が厳密に改正されたことで、グレーゾーン金利は法律上完全になくなりました。
グレーだった法外金利が完全なブラックになったため、正規の貸金業者として認められていない闇金業者を除けば、過払金が発生するリスクはほぼゼロになっています。

最大365日と無利息期間の長さが優れている消費者金融です!
原則勤務先への在籍確認も実施しておらず、書類で審査可能。
事前に返済額や総額をシミュレーションすることもできます。
レイクの詳細はこちら>>
過払金がもらえる条件は?確認すべきチェックポイント
次は過払金が貰える条件について、4つのチェックポイントをそれぞれ解説します。
2010年6月以前に借金をしていた
過払金の対象者は、現行の貸金業法が改正される前(2010年6月以前)に消費者金融からお金を借りていた人が対象です。
出資法が制定されたのは1954年のため、50年以上にわたって法外な利息が許容されていたことになります。
ちなみに2010年6月の改正以降、上限は20%ときっちり決められグレーゾーン金利は存在していません。
ただし、いくつかの業者が法改正後も20%を超えて貸し付けていた事例は存在するため、可否がわからない方は改めて借り入れ・返済記録を確認することをおすすめします。
時効の完済から10年がまだである
過払金請求を実施できる期間は、過払金の対象となる最後の取引から「10年」です。10年を過ぎると時効成立となり、過払金を請求する権利は消滅し、どれだけ金額が大きくても回収はできなくなります。
時効へのカウント(時効起算点)がスタートするタイミングは、最後の返済日です。たとえば1995年にお金を借りて2005年1月に返済した場合、借りた日にかかわらず、2015年1月が時効となります。
ただし過去の判例によると、同じ消費者金融で複数の取引を行っていた場合は、過払金の対象となる取引の最終返済日ではなく、他の借り入れを含む一連した取引終了時点が時効の起算点と認められる場合があります。
また完済日が2020年3月31日以降の場合は、10年が過ぎていても「過払金請求の権利を行使できると知った日」から5年が時効成立日となり、請求可能なボーダーラインが延びる可能性があります。
年20%以上の金利で借入をおこなっていた
過払金請求ができるのは、2010年6月より前に「20%を超えた利息を支払っていた人のみ」です。
すべての人が対象でないのは、貸金業法改正以前に消費者金融からお金を借りた場合でも、利用者全員が高金利で貸し付けられていたわけではないからです。
ちなみに、たとえ金利が20%を超えていても、相手が闇金である場合は「不法原因給付」となり、過払金の対象外です。その場合は利息だけでなく、元本も返済する必要はありません。
何年にもわたって返済していた
過払金の請求可否において、返済の有無や程度はとても重要です。具体的には、次の2点がポイントとなります。
- 上限を超えた利息の支払いを長期間行っているか?
- 完済または元本の大部分を完済しているか?
なぜ期間と金額が重要なのかというと、返済期間が長く返済金額が多い(完済に近い)人ほど、過払金請求の条件に当てはまる可能性が高いからです。
逆に返済期間が短い人は、元本の大半が残っており、余計な利息を支払うまでに至っていない可能性があります。
誤解されやすいのは、利息を払い過ぎている取引があっても、その取引自体が無効になるわけではないという点です。
借りたお金(元本)は返さなければならないため、過払金があっても、その分を元本返済分に充当する、ということが起こり得ます。
そのため、少ししか返済していない人が「お金に困ったので、とりあえず払いすぎた分だけ返してもらう」ようなことはできません。
過払金があるとしても元本と相殺され、返済金額が少し減るだけです。

利用限度額が最大800円であり、膨大な資金を調達できます!
融資も最短15分で完了するためすぐに借り入れが可能。
スピーディに多額の資金を調達する際におすすめです。
モビットの詳細・申込みページへ>>
過払金の対象外になりやすい人
次は過払金の対象外になりやすい人として、5つの特徴を解説します。
銀行カードローンを利用していた
過払金が発生し得るのはあくまで消費者金融を対象とした貸し借りなので、2010年6月以前に銀行カードローンを利用していた人は対象外です。
銀行にとって過去に「グレーゾーン金利」が存在したことはなく、法外な貸付も実質不可能であったためです。
同様の理由で、過去に借り入れしていた住宅ローンや自動車ローンも基本的に対象外となります。これらの商品は主に銀行が提供し、低金利で貸し付けられることが多いからです。
ただし、貸金業者と銀行が提携して発行されたクレジットカードでキャッシングを利用していた人に過払金が発生したケースは存在します。
あくまで貸しているのは銀行ではなく貸金業者ですが、銀行が全く無関係ではないケースがあるのも事実です。
クレジットカードのショッピング枠のみを利用していた
法外な金利での貸付が可能だったのは消費者金融が提供するカードローンであり、過去にクレジットカードのショッピング枠のみを利用していた人は過払金の対象外です。
ショッピング枠で発生するのはあくまで「分割手数料」であり、厳密には利息とは異なります。
クレジットカードの規制対象となるのは、利息制限法ではなく「割賦販売法」です。
ショッピング利用でトラブルが発生した場合でも専門家に相談するのは正しいですが、あくまで割賦販売法に則った手続きや法廷闘争を行うことになります。
ちなみにカードでもキャッシング利用なら、過払金の対象になる可能性があります。貸金業者が発行するクレジットカードのキャッシング枠に、グレーゾーン金利が適用されていたケースがあるからです。
2010年6月以降にキャッシングをはじめた
貸金業法が改正されたのは2010年6月であるため、それ以降に消費者金融からカードローンでお金を借りたり、クレジットカードのキャッシングを利用した人が過払金の対象になる可能性は低いです。
ただし、一部の業者が法改正後も法外な貸付を行っていた事例があり、レアケースではあるものの過払金の対象となる可能性はあります。
返済を早期に完了させた
2010年6月以前の借り入れにおいて、返済を早期に完了させた、または早めに一括返済したことで過払金請求自体ができなくなることはありません。
ただし、取引が連続していないとみなされる(取引の分断)場合は、請求できる過払金が減る可能性があります。
取引の分断があると判断される要素は、2つの取引における空白期間や、返済が行われていない期間の長さなどです。
取引の一連性を主張するために追加で資料を提出する必要なども生じるため、再借り入れの経験がある方は専門家に相談することをおすすめします。
返済がまだ続いている
過払金請求は完済が絶対条件ではないため、対象となり得る融資の返済を行っている最中でも過払金請求を行うことは可能です。
ただし返済中の人が過払金請求をする場合、返済は一時ストップとなり、信用情報が悪化する可能性があります。
信用情報が悪化すると、他のクレジットカードやローンの利用が制限される可能性があります。
過払金請求時には一時的な返済停止を要求することにはなりますが、信用悪化のリスクがあることは理解しておくべきです。

プロミスは最短3分で即日融資可能な消費者金融カードローンです!
上限金利が18.0%であり、他の消費者金融と比較して低めです。
今なら初回利用時から最大30日間の無利息期間が適用されるキャンペーンを実施中です!
プロミスの詳細・申込みページへ>>
過払金請求の仕方とは?流れについてわかりやすく解説
次は実際に過払金請求を行う流れについて、詳しく解説していきます。
①取引履歴の開示請求を行う
過払金請求を行う最初のステップは、過去に取引を行っていた貸金業者に「取引履歴開示請求書」を送付し、取引履歴の開示請求を行うことです。開示請求書には、主に以下の情報を正確に記載します。
- 請求日
- 宛先の社名・代表者名
- 請求者情報(名前・住所・電話番号・契約番号等)
- 開示対象となる取引の期間や種類
- 開示を行う理由
- 開示を行う根拠となる法令
- 開示の方法(書面・CDやUSBなどの記憶媒体等)
開示を求める情報には「何年何月に何円、どれくらいの利率で借りたか」とか「借りた金額のうちいくら返済したのか」といった、取引の詳細が含まれます。
取引履歴は、過払金額を正確に計算するために必須です。貸金業者は過払金請求に伴う情報開示を拒否することはできないため、相手方が倒産していたりしない限り「取引履歴をくれない」という事態には陥らないため安心してください。
基本的にはこの最初のステップから、弁護士などの専門家に依頼するのが一般的です。なぜなら開示請求に伴う手続きが煩雑ですし、開示請求を行う時点から貸金業者との交渉はスタートしているからです。
②引き直し計算を行う
履歴が取得できたら、次は専用のツールやExcel等を用いて利息の「引き直し計算」を行います。
要するに昔の法律ではなく現在の法律に則って、本来支払うべき税金と、実際に支払った税金にどれだけの差があるかを算出します。
当初の借入金額はすべて現在の法定上限金利(15〜20%)に直し、返済期間における借り入れ残高の推移を再計算します。
たとえば本来20%のものを年率29%で借りていた場合、その差9%分と実返済分の差額が、過払金として回収できる金額となります。
注意点として、返済期間が短い場合は引き直し計算の結果元本がマイナスにならないため、正式な元本が再計算され、総返済額が減ることになります。
この場合、現金として過払金を受け取ることはできません。
引き直し計算は対象の取引期間が長くなればなるほど複雑になり、計算を間違える可能性も高くなります。すべて弁護士などの専門家に依頼すれば金額を間違ったり、それにより請求の正当性を損なうリスクもなくなるため、おすすめです。
③過払金の請求手続きを行う
次は引き直し計算の結果に基づき「過払金返還請求通知書」を貸金業者に送付し、正式に過払金の請求手続きを行います。書類には、主に以下の情報を正確に記載します。
- 請求日
- 宛先の社名・代表者名
- 請求者情報(名前・住所・電話番号・契約番号等)
- 開示対象となる取引の詳細
- 引き直し計算で算出した金額
- 振込先の口座情報
- 支払いの期限・手数料の詳細
- 期限を超過した場合の法的措置について
書類を送付した後はすぐ支払われるのではなく、貸金業者と直接交渉を行うのが一般的です。交渉は借主が自分で行うこともできますが、多くの知識や経験がある弁護士などを通して行う方が、成功率(実際に支払われる過払金の金額)が高くなります。
貸金業者は引き直し計算で算出した金額の満額ではなく、8割程度の金額を提示してくることがあります。その金額で和解に応じれば過払金が受け取れるまでの期間も短くなりますが、納得いかない場合は過払金請求の訴訟を進めることになります。
過払金支払いが裁判に至った場合は、少なくとも数ヶ月から半年程度長引くことになります。多くの場合、業者側は和解として提示した金額よりも多くの過払金(満額+5%程度)を支払うことになるため、判決に至る前に和解が成立するケースが多いです。
④過払金が返金される
交渉段階で和解した場合は遅くても1〜2ヶ月程度で、裁判の場合は数ヶ月から半年を要する判決後に、過払金が口座に振り込まれます。口座は後から指定するのではなく、請求書類に記載するのが一般的です。
弁護士に依頼した場合、一旦弁護士事務所の専用口座や信託口座に入金され、そこから弁護士報酬を差し引いた金額が本人口座に振り込まれるのが一般的です。借主が業者に直接過払金の支払いを請求した場合は、本人の口座に振り込まれます。
一度和解が成立すれば、判決後に「和解金が支払われない」ことはまずありません。ただし過去には、貸金業者が無視して約束通りに支払わなかったため強制執行に進んだり、業者側が控訴して判決に時間がかかり、受け取りが遅くなるケースがありました。
現代では貸金業者にとっても社会的な信用を失うリスクがあるため、正式な決定後に支払われない事例に遭遇することは稀です。それでも期限内に指定した口座に振り込まれなかったり、何らかの脅しや嫌がらせを受けた場合は、すぐさま専門家に相談する必要があります。

最大365日と無利息期間の長さが優れている消費者金融です!
原則勤務先への在籍確認も実施しておらず、書類で審査可能。
事前に返済額や総額をシミュレーションすることもできます。
レイクの詳細はこちら>>
過払金に関するよくある質問まとめ
最後に、過払金に関するよくある6つの質問に回答していきます。
過払金請求によるデメリットはある?
過払金は現行法に則り「支払いすぎたお金を、正当な手続きを踏んで返してもらう」ことなので、基本的にデメリットはありません。ただし、返済中の取引に関して過払金請求を行う場合は注意が必要です。
本来、過払金の請求は債務整理とは異なり、すでに完済した取引における信用情報機関に信用事故が記録されることはありません。借主が自己都合で「返せなくなった」ケースには該当せず、不利益を被るには値しないからです。
しかし、返済が完了していない取引の場合は例外として任意整理と同じ扱いになり、信用情報機関に事故情報が記録される可能性があります。一度信用事故が記録されると、新しくクレジットカードが作れなくなったり、各種ローンが契約できなくなるため注意が必要です。
過払金は本当に戻ってくる?
過払金の請求は法律でも認められている正当な権利であるため、正式に手続きを行えば取り戻すことができます。もちろん、さきほど説明した「過払金がもらえる条件」をクリアしていることは大前提となります。
ただし例外として、次のようなケースではそもそも「過払金の請求自体ができない」可能性があります。
- 貸金業者がすでに倒産(破産)している
- 時効を過ぎている
- 貸金業者側が過払金の支払いを認めない
まず、借主が過去に取引していた貸金業者がすでに存在していない場合は、交渉したり、裁判を起こしたりできる余地がありません。過去には「武富士」や「クレディア」といった貸金業者が倒産し、破産手続きに伴う少額の分配しか受け取れないケースがありました。
次に時効を過ぎてしまった場合ですが、基本的には取引終了から10年を過ぎてしまったものは、金額にかかわらず返ってきません。ただし以下のケースに当てはまる場合は、10年が経過した後でも過払金の請求ができる可能性があります。
- 継続的な取引があると認められた場合
- 同一業者との借り入れがある場合
- すでに業者側に催告を行っている場合
過払金対象の業者との継続的な取引があり「過払金充当合意」が認められた場合は、その取引が終了するまでは時効が停止されないため、過払金請求が可能です。また新規借り入れの場合は、期限超過後でも債務との相殺を主張できる可能性があります。
くわえて、借主側から「催告」を行うと時効の進行が半年間だけストップします。要するに、現時点で期限を超過していても、超過前に催告していれば請求が可能です。もちろん請求手続きは催告してから6ヶ月以内に済ませる必要があります。
過払金の相談先はどこ?
過払金に関する相談は、弁護士に相談することをおすすめします。司法書士でも取り扱いは可能ですが、過払金の金額が140万円を超えると扱えないため、時間とお金を無駄にしたくなければ、最初から弁護士に相談するのが懸命です。
具体的に弁護士がやってくれることは、過払金の請求に伴う「ほぼすべての手続き」です。そのため、依頼主が自分自身で業者に対してコンタクトを取る必要がなくなりますし、相手方は知識と経験に長けた専門家を相手にすることになるため、成功率が上がります。
過払金請求を依頼した時の費用はいくらかかる?
過払金請求を弁護士に依頼する場合は、主に次の費用を支払うことになります。
- 相談料(初回は無料が多い)
- 着手金
- 成功報酬
- 裁判費用(該当する場合のみ)
まず初回の相談料に関しては、初回だけ無料にしているところは多いため、困っている方は気軽に相談してみましょう。多くの場合は正式に過払金請求の依頼を行った段階から費用が発生します。
着手金とは、その名の通り弁護士が過払金請求という事案に着手するための費用です。初回相談費用よりもばらつきは大きく、1〜3万円程度の費用を設定しているところもあれば、無料にしているところも増加しています。
次に成功報酬ですが、これは過払金の回収が成功した場合に支払うお金です。金額は実際に回収できた金額の15~20%程度ですが、訴訟まで発展した場合は訴訟費用も含め、数万円ほど高くなる可能性があります。
このとおり、過払金請求には少なくとも数万円の出費が発生します。特に回収できそうな金額が低い場合は、本当にお金をかけてでもやる価値があるのか、現実的に考える必要があるでしょう。
クレジットカードで過払金が発生するのはキャッシングのみ?
クレジットカード取引において過払金が発生するのは、原則的にキャッシング枠のみです。なぜならショッピング枠は、法律上「立て替え払い」であり、金銭(現金)の貸借には該当しないからです。
過去に行ったカードでの取引が、キャッシングなのかショッピングなのかはっきりしない場合は、各カード会社のマイページから過去の取引履歴を確認してみましょう。それでも分からない場合はカード会社に問い合わせたり、専門家に相談することをおすすめします。
ブラックリスト入りしていても過払金請求できますか?
ブラックリスト入りしていても、過払金請求は可能です。ブラックリストとは、信用情報機関に延滞や債務整理などの記録が残っている状態を指しますが、過払金請求は本来支払う必要のなかった利息を取り戻すための正当な手続きです。
そのため、信用情報の登録状況にかかわらず、請求する権利は失われません。ただし、過払金請求後に残債がある場合、その処理によって新たに事故情報が記録される可能性があるため注意が必要です。すでに完済していれば信用情報への影響は通常ありません。
過払金が発生しているかどうかの確認は、早めに専門家へ相談することが大切です。

利用限度額が最大800円であり、膨大な資金を調達できます!
融資も最短15分で完了するためすぐに借り入れが可能。
スピーディに多額の資金を調達する際におすすめです。
モビットの詳細・申込みページへ>>
まとめ
過払金請求は法的に認められた権利であり、特に2010年6月以前に行った、グレーゾーン金利での借り入れを完済済みの人にとっては、多額のお金が戻って来るチャンスでもあります。
もちろん交渉や裁判が一筋縄でいかないこともありますが、多くの過払金請求をこなしてきた弁護士などの専門家に頼るなら、成功率を大きく上げられます。該当する借り入れが過去にあると感じている方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

プロミスは最短3分で即日融資可能な消費者金融カードローンです!
上限金利が18.0%であり、他の消費者金融と比較して低めです。
今なら初回利用時から最大30日間の無利息期間が適用されるキャンペーンを実施中です!
プロミスの詳細・申込みページへ>>
参考文献
この記事を書いた人
エレビスタ ライター
エレビスタは「もっと"もっとも"を作る」をミッションに掲げ、太陽光発電投資売買サービス「SOLSEL」の運営をはじめとする「エネルギー×Tech」事業や、アドテクノロジー・メディアなどを駆使したwebマーケティング事業を展開しています。
エレビスタは「もっと"もっとも"を作る」をミッションに掲げ、太陽光発電投資売買サービス「SOLSEL」の運営をはじめとする「エネルギー×Tech」事業や、アドテクノロジー・メディアなどを駆使したwebマーケティング事業を展開しています。