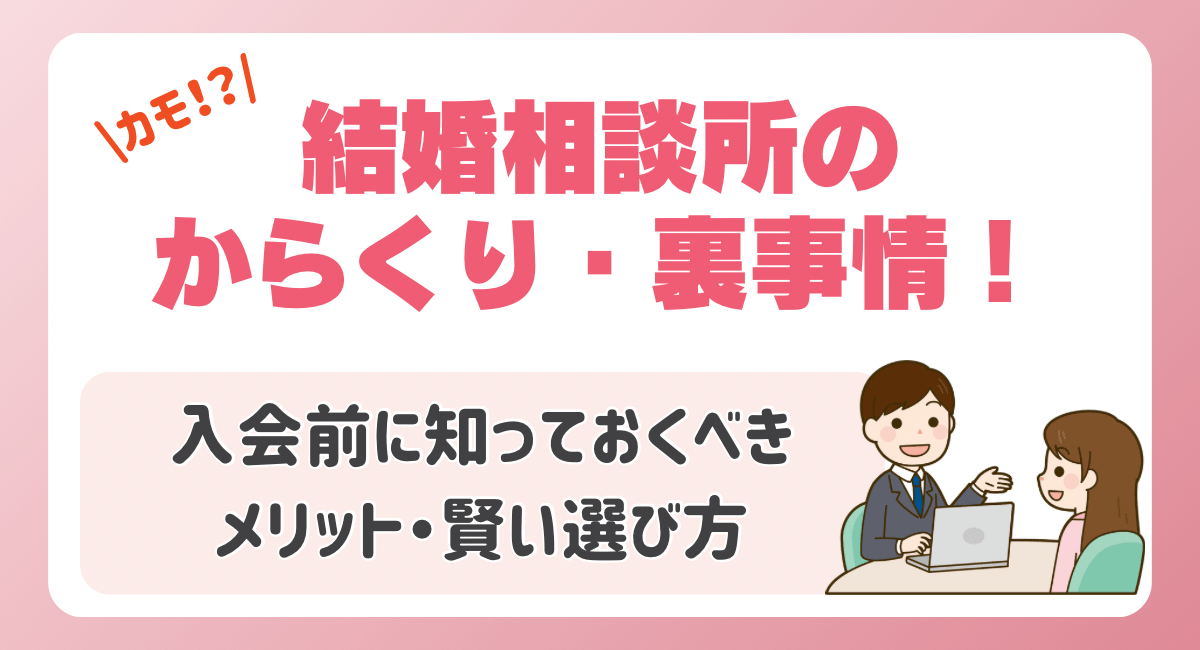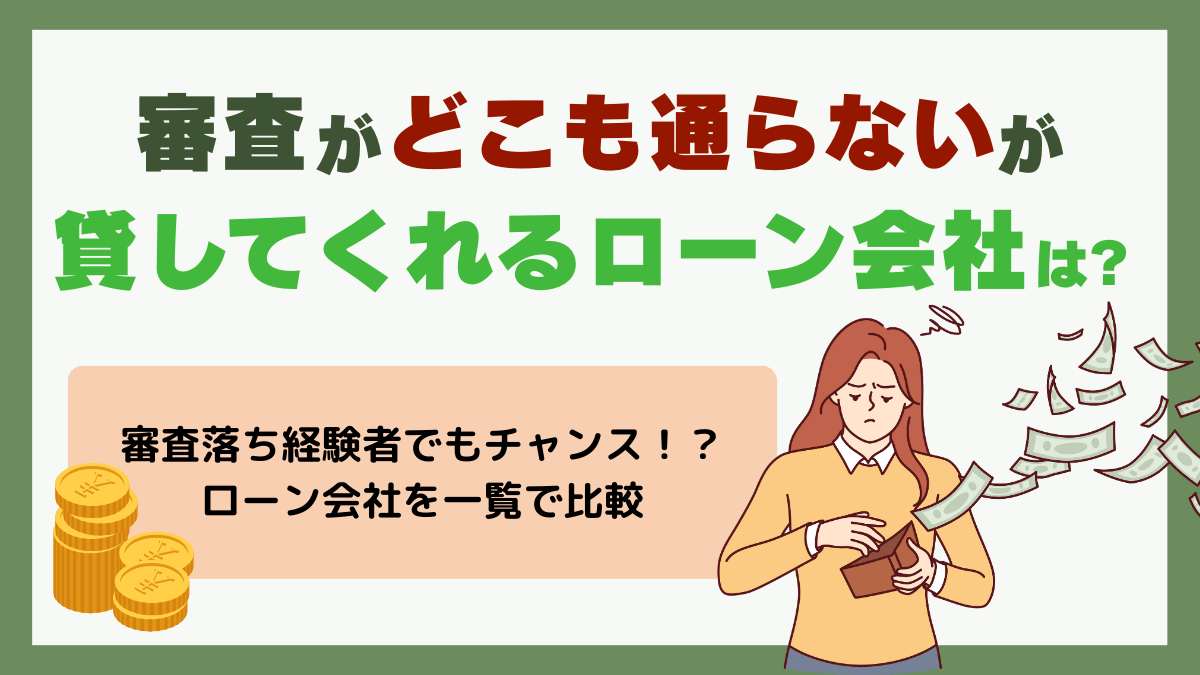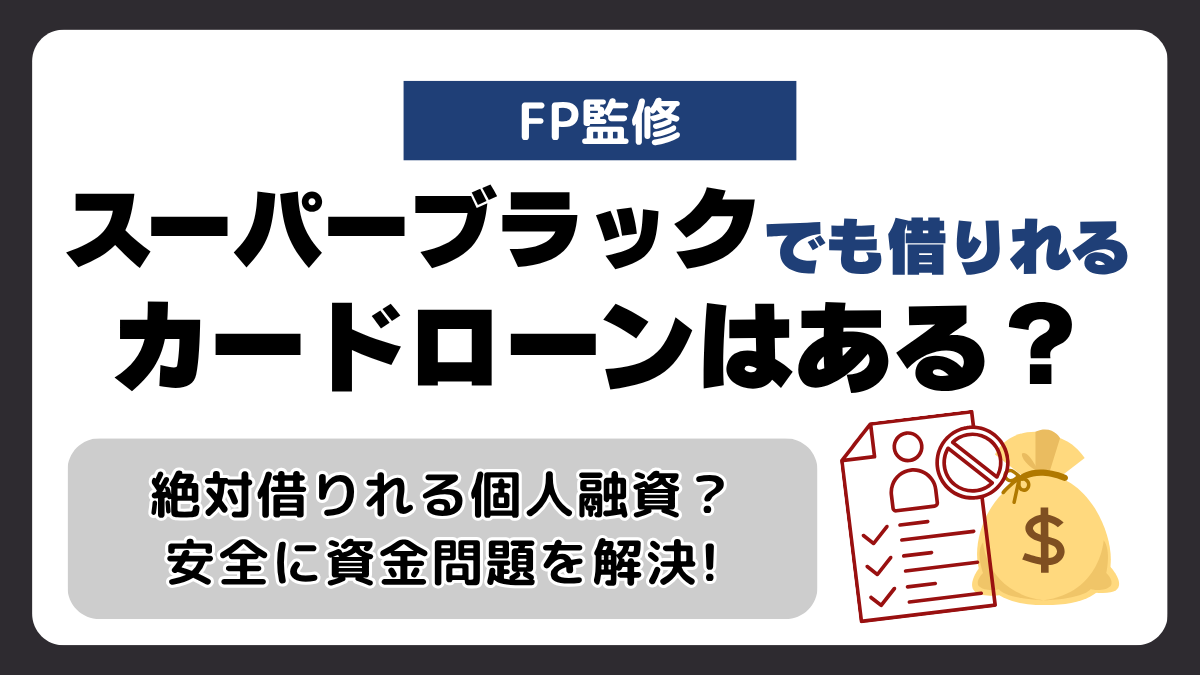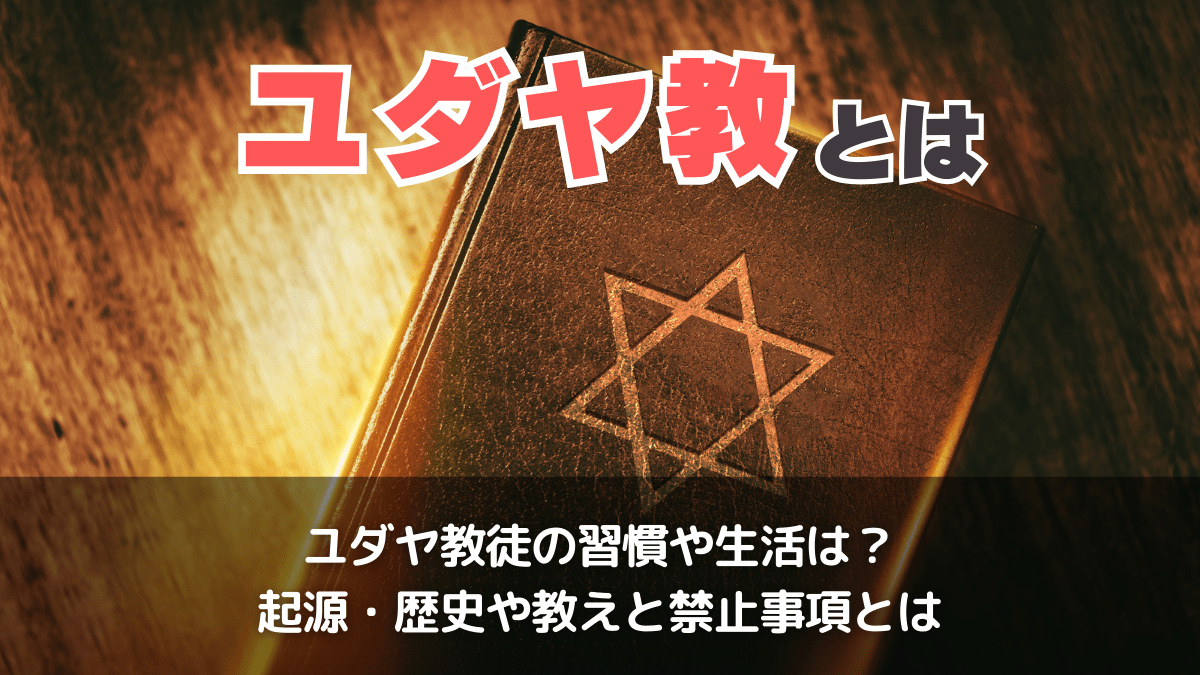日本の社会において、ほとんどの人が銀行を何らかの形で利用しています。しかし、当たり前に利用している銀行について、深く学んだことはあるでしょうか?
日本の銀行システムは、実は非常に多様な種類の銀行によって支えられています。都市銀行から地方銀行、信託銀行まで、それぞれの役割と仕組みを理解することで、経済ニュースの見方や社会の動きがより深く見えてきます。日本の銀行の種類をわかりやすく解説し、代表的な銀行を紹介します。
目次
日本の銀行の種類は?
【日本銀行本店】
私たちの日常生活を支える銀行には、法律や役割の異なる複数の種類が存在し、それぞれが金融システムの中で特定の機能を担っています。まずは全体像を確認してから、主な銀行の分類と特徴を見ていきましょう。
銀行システム全体の概要
日本の金融システムは中央銀行である日本銀行(日銀)を頂点に構成されています。日銀は
- 発券銀行
- 銀行の銀行
- 政府の銀行
の三役割を果たし、物価安定と金融システムの安定という二大使命を追求します。その下に、私たちが利用する預金取扱金融機関が位置するのです。
銀行法※に基づく「銀行」は、
- 預金
- 貸出
- 為替
の三大業務を通じて経済活動の血流を維持しています。また、万一の破綻時には預金保険制度(ペイオフ)※により、1金融機関あたり預金元本1,000万円までと利息が保護されます。
国内銀行
続いて、国内に拠点を置く銀行の種類を詳しく見ていきます。
都市銀行
全国に広範な支店網を持つ大規模銀行で、以下の5行が該当します。
- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- 埼玉りそな銀行
このうち、みずほ・三菱UFJ・三井住友は「メガバンク」と呼ばれ、国内外の大企業や政府系事業への融資・国際金融業務を得意とします。
地方銀行
都道府県や地方中心都市を営業基盤とし、地域の中小企業や個人を支える銀行です。全国地方銀行協会に加盟する第一地方銀行は、地元企業との信頼関係を武器に地域経済を支えます。
地方銀行II(第二地方銀行)
第二地方銀行協会に加盟し、1989年以降に相互銀行から普通銀行へ転換した銀行群です。相互銀行時代の中小企業向け金融のノウハウを生かし、小規模事業者や個人への融資に強みを発揮します。
信託銀行
銀行業務に加えて、信託業務と併営業務を営む特殊銀行です。信託業務では財産管理・運用を担い、併営業務には遺言の保管・執行、証券代行業務、不動産仲介業務などが含まれます。企業年金運用や不動産証券化など、専門性の高いサービスを提供しています。
外国銀行在日支店
海外本店を持つ銀行が金融庁の認可で設置した支店で、主に国際取引や外資系企業支援を行います。預金保険制度の対象外である点に留意が必要です。
外国銀行在日支店には、以下のような特徴があります。
- 海外本店の信用力を背景に、外国為替や国際送金など高度な国際金融サービスを提供
- 国内銀行が担わないクロスボーダー融資や本国基準の商品を扱う
これらの銀行はそれぞれ異なる設立根拠法や役割を持ち、私たちの資金ニーズに応じたサービスを提供しています。次の章からは、自分のライフステージやビジネスに最適な銀行を選ぶための第一歩として、各種類の特徴を押さえておきましょう。*1)
代表的な都市銀行

都市銀行は、大規模な支店網と豊富な資金力を背景に、全国および海外で幅広いサービスを提供しています。金融庁の定義では4行、日本銀行の統計では埼玉りそな銀行を含めた5行が該当しますが、ここでは主要4行の特徴を紹介します。
三菱UFJ銀行
三菱UFJ銀行は、1880年創業の三菱銀行と東京銀行を源流とする東京三菱銀行が、2006年に三和銀行・東海銀行を統合したUFJ銀行と合併し、現在の形となりました。資本金は約1兆7,000億円で国内最大手を誇り、アジア市場では現地銀行の買収を通じてネットワークを拡大しています。
一方で、組織が大きいために意思決定に時間を要する点が課題とされています。
三井住友銀行
三井住友銀行は、2001年にさくら銀行(三井系)と住友銀行が統合して発足しました。経費率の低さに象徴される効率的な経営が強みで、個人向けコンサルティングや中小企業向け融資で安定した高収益を維持しています。
また、米州やアジアでの法人取引を強化し、迅速な事業展開を実現している点も特長です。
みずほ銀行
みずほ銀行は、2002年に第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行の3行が統合して誕生しました。全国47都道府県に拠点を持ち、銀行・信託・証券が連携した総合金融サービスを提供しています。
グループ全体の総合力を活かした証券・信託連携が強みですが、過去のシステム統合トラブルによる組織的課題が残る点には注意が必要です。
りそな銀行
りそな銀行は、メガバンクと地方銀行の中間的ポジションを担い、リテール分野※に特化しています。埼玉りそな銀行と連携し、首都圏および関西圏を中心に地域密着型サービスを展開しています。
国内で唯一、信託併営商業銀行として遺言信託や不動産仲介などをワンストップで提供できる点が最大の特徴です。
以上のように、代表的な都市銀行はそれぞれ異なる統合の歴史と強みを背景に、規模、効率性、総合力、地域密着といった多様な価値を提供しながら、国内外での競争力を高めています。*2)
代表的な地方銀行

地方銀行は全国展開の都市銀行とは異なり、地域経済の血脈として独自の役割を果たしています。地域ごとの産業構造や社会課題に応じた戦略を展開し、地元企業や住民の信頼を獲得してきました。
特に影響力の大きい「三大地方銀行」と全国各地域を支える有力銀行に注目してみましょう。
三大地方銀行の個性
地方銀行の中でも、預金量や技術革新で先頭に立つ3行の戦略を押さえます。
横浜銀行
横浜銀行は、約17.9兆円の預金を抱え、地方銀行トップの座を守っています。コンコルディア・フィナンシャルグループ※の中核として、神奈川県内シェアは20%超。大学との連携や地域課題解決型ファンドの組成など、地場企業支援に力を入れています。
千葉銀行
千葉銀行は、成田空港や製造・農業など多彩な産業を背景に安定経営を続けています。TSUBASAアライアンス※参加で大手行並みのシステム基盤を活用し、「地域まるごとDX」を推進。
キャッシュレス化支援やIT導入コンサルティングを通じ、取引先の業務効率化を支援しています。
静岡銀行
静岡銀行は、製造業とIT企業が集積する地元を生かし、地方銀行初のAWS勘定系システム※を2027年中に本稼働予定です。生成AIチャットボット導入やクラウド基盤によるシステム最適化で、業務効率と顧客利便性を同時に高めています。
各地域を代表する有力行
三大地銀以外にも、地域経済を支える地方銀行があります。
福岡銀行
福岡銀行は、預金約13.7兆円を誇り、九州7県をまたいで行政資金運用や販路拡大支援を実施しています。地方銀行としては珍しい広域展開を展開し、県境を越えた地域活性化に貢献しています。
七十七銀行
七十七銀行は、預金約8.7兆円を集める東北最大手地方銀行です。1878年創業以来、「奉仕の精神の高揚」を行是に掲げ、震災復興支援や地域中小企業への伴走支援など、社会貢献型金融で地域に寄り添い続けています。
地方銀行は、地域の姿を映す「鏡」として、地域特性に即したサービスを提供し、地元の未来づくりをともに担う存在です。地方銀行の多様な戦略と役割を理解することは、地域経済の活力を実感し、よりよい金融選択へとつながります。*3)
代表的な地方銀行II(第二地方銀行)

第二地方銀行(以下、第二地銀)は、第二地方銀行協会に加盟する36行(2025年1月時点)を指します。1990年には68行存在していましたが、再編と合併を経て現在の規模に至っており、地域金融の要として進化を続けています。
代表的な第二地銀の戦略と特色を見ていきましょう。
北洋銀行
北洋銀行は、1997年11月17日に都市銀行として戦後初の経営破綻を起こした北海道拓殖銀行から営業を譲り受け、預金約7.2兆円・道内シェア約35%を実現しています。175店舗を展開し、農業・漁業など一次産業への深い理解に基づくサービスが強みです。
スルガ銀行
スルガ銀行は、静岡県東部・神奈川県西部を地盤としています。1989年の相互銀行転換※以降、リテール分野に特化。
ロードバイク購入ローンに代表されるサイクリスト向けローンやIT人材向け住宅ローンなど、顧客ニーズに沿った多彩な商品を提供しています。
静岡中央銀行
1926年設立の静岡中央銀行は、静岡・神奈川・東京に42店舗を展開し、「堅実で健全な経営」を掲げます。創業・新事業支援や中小企業向けコンサルティングなど、地域密着型サービスを重視しています。
佐賀共栄銀行
佐賀共栄銀行は、佐賀県を基盤に農業法人への対面相談を徹底し、地元農家の経営安定を支援しています。7行共同でSBKシステムバンキング九州共同センター※を運営し、効率化と地域密着の両立を図っています。
このように、第二地銀は相互銀行時代の中小企業金融の遺伝子を引き継ぎながら、地域に根ざした多様な戦略で地域経済を支えています。*4)
代表的な信託銀行

信託銀行は、預金や貸出などの銀行業務に加え、財産管理・運用を行う「信託業務」と、相続や不動産仲介などの「併営業務」を専門とする金融機関です。現在、主要な信託銀行は4社体制となっており、それぞれに特色を持つ代表的な各社を紹介します。
三菱UFJ信託銀行
三菱UFJ信託銀行は、グループの総合力を背景に、金融工学※の研究拠点「MTEC」を擁し、オルタナティブ商品※を含む高度な運用商品を開発しています。海外事業から約3割の利益を得るグローバル展開も大きな特徴です。
三井住友信託銀行
三井住友信託銀行は、国内最大の独立系専業信託銀行※として、不動産証券化受託残高業界1位を誇ります。法人・大口投資家向けにインフラファンドなど社会課題解決型プライベートアセット投資を推進しています。
みずほ信託銀行
みずほ信託銀行は、旧安田信託の流れを引き、不動産事業と企業事業承継コンサルティングに強みを持ちます。グループ内の知見を結集したコンサル部門が、オーナー企業の成長と資産承継を支援しています。
野村信託銀行
野村信託銀行は、野村グループの「金庫番」として、有価証券カストディ業務※やラップ信託※を提供しています。約70カ国を網羅するカストディアン・ネットワーク※により新興国市場への対応力を発揮しています。
信託銀行各社はそれぞれ異なる専門性を軸に、個人から法人まで多様なニーズに応える「財産管理のプロ」として重要な役割を担っています。*5)
代表的な外国銀行在日支店

東京のオフィス街を歩くと、世界中の銀行が日本とつながる「金融の玄関口」として立ち並んでいます。現在50行を超える外国銀行支店が認可を受け、日本企業の国際展開や外資系企業の日本進出を支えています。
地域別に代表的な銀行の特色を見てみましょう。
アメリカ系銀行
米国の銀行は、法人向けホールセール業務や投資銀行業務を中心に展開しています。
シティバンクは法人向け決済と送金業務に特化し、個人業務をSMBC信託銀行に譲渡後は大企業や機関投資家向けに集中しています。
J.P.モルガン・チェース銀行やバンク・オブ・アメリカは、カストディ業務や米国進出支援融資を提供しています。
ゴールドマン・サックス証券やモルガン・スタンレーMUFG証券は、M&A助言※や証券取引を専門とする投資銀行です。
ヨーロッパ系銀行
英国系を中心とするヨーロッパ系銀行は歴史とグローバルネットワークが強みです。
HSBC(香港上海銀行)は1866年横浜支店開設の日本最古の支店で、アジア太平洋の貿易金融を担います。
スタンダードチャータード銀行はアジア・アフリカ・中東59か国のネットワークを生かし、新興国市場支援と貿易金融に強みを持ち、ESG分野でも先駆的な役割を果たしています。
ドイツ銀行東京支店は外国為替、キャッシュマネジメント、不動産ファイナンスを展開し、グループ内証券部門と連携した総合金融サービスを提供しています。
アジア系銀行
中国の四大商業銀行(中国銀行、中国工商銀行、中国建設銀行、中国農業銀行)は、いずれも東京に拠点を置き、日中間の貿易金融や人民元決済を主軸としています。
シンガポール系ではDBS銀行が法人向け資金調達や東南アジア進出支援サービスを提供し、UOB東京支店は中小企業向け貿易信用状などを扱います。
インド系HDFC銀行東京支店はインド企業の日本進出と送金業務に強みを持ち、マレーシアのCIMB銀行はASEAN域内ネットワークを活かした複合金融サービス※を展開しています。
これらの支店は、それぞれ本国の経済圏との架け橋として、アジア各地域とのビジネスを円滑に進める役割を果たしています。
いずれも日本の預金保険制度の適用外である点に留意が必要ですが、本国の信用力とグローバルネットワークを武器に、日本と世界をつなぐ重要な役割を果たしています。*6)
銀行の選び方
日々のATMや振込手数料が年間で1万円を超えることもある現代、「銀行選び」は家計に直結する大切な節約術です。金融リテラシーを高め、自分に最適な銀行を選ぶことで、長期的な資産形成にも大きな差を生み出せます。
ここからは、賢く銀行を選ぶ3つのステップをご紹介します。
ステップ1:できれば「ネット銀行」を利用
ネット銀行は店舗運営コストを抑えているため、ATM手数料や振込手数料が大手銀行より格段に安く設定されています。
ただし、
- ID・パスワード管理
- フィッシング詐欺対策
などセキュリティ面の自己管理が重要です。日本の金融庁に登録された国内銀行の運営するネットバンキングであれば、預金保険制度も適用されます。
ステップ2:目的に合わせて銀行を使い分ける
やみくもに口座を増やすことは避けるべきですが、生活費の口座とは別に、貯蓄や副業の収入などを管理する口座を1~2つ持つと、お金の流れが明確になり管理が楽になります。その上で、以下のように銀行の得意分野に合わせて使い分けるのが現代の賢い戦略です。
- 日常:ATM手数料・振込手数料が安いネット銀行
- 貯蓄・投資:証券会社と連携し商品が豊富なネット銀行
- 住宅ローン:対面相談が可能な都市銀行・地方銀行
- 相続・資産承継:専門知識を持つ信託銀行
- 海外送金・外貨預金:手数料や為替レートが有利なソニー銀行など
複数の銀行口座を持つ際は、家計簿アプリと連携して収支管理を一元化しましょう。多くの家計簿アプリが金融機関との自動連携機能を持ち、全口座の残高や取引履歴を一画面で把握できます。
代表的な家計簿アプリには以下のようなものがあります。
- Zaim:レシート撮影で自動入力し、支出カテゴリをグラフで分かりやすく可視化
- MoneyForward ME:1000を超える金融機関と連携し、残高・入出金を自動で同期
- おカネレコ:シンプル操作で初心者にも使いやすく、スタンプ入力で楽に記録
- マネーツリー:リアルタイムで資産の推移を一目で確認できるダッシュボード機能
- Dr.Wallet:レシートを専任スタッフが手入力対応し、高い入力精度を実現
ステップ3:知識で自分を守り、選択肢を広げる
金融庁や信頼できる比較サイトで金利や手数料の仕組みを学びましょう。例えば、大手銀行で他行宛振込を月3回行うと年間約1,320円×12回=約1万5,840円かかりますが、多くのネット銀行なら月2〜3回まで無料で、年間1万円以上の節約が可能です。
まずは現在の銀行で先月どれだけ手数料を支払ったかを通帳や家計簿アプリで確認し、改善点を見つけることから始めましょう。
以上のステップを踏むことで、自分に本当に有利な銀行を選び、賢く資産形成を進める基盤を築けます。*7)
銀行とSDGs
銀行が支える経済の安定と、SDGsが目指す社会の持続可能性は、未来を豊かにするという共通の目的で結ばれています。銀行は経済の血液である「お金」の流れを通じ、SDGsの目標達成を後押しする重要な役割を担います。
特に関係の深いSDGs目標を確認していきましょう。
SDGs目標5:ジェンダー平等を実現しよう
近年では、多くの銀行が女性起業家向け融資制度や女性経営者への専門相談窓口を設置し、資金調達における性別格差の解消に取り組んでいます。銀行の組織内でも、女性管理職比率の数値目標を設定し、昇進機会の均等化を推進しています。
また、育児・介護と両立できる柔軟な働き方制度を導入し、性別に関係なく能力を発揮できる職場環境の構築を目指しています。
SDGs目標7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに
銀行は再生可能エネルギー事業への専門融資枠を設定し、太陽光・風力・水力発電プロジェクトに優遇金利で資金を供給しています。グリーンボンドの発行・引受を通じて、環境配慮型事業の資金調達を支援しています。
他方では、石炭火力発電など環境負荷の高い事業への新規融資を制限し、エネルギー転換を金融面から促進しています。
SDGs目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう
銀行はスタートアップ企業やベンチャーキャピタルへの出資・融資を通じて、革新的技術の事業化を資金面で後押ししています。地方銀行では地域の中小製造業に対する設備投資融資や事業承継支援により、技術継承と産業基盤の維持を図っています。
また、デジタル化推進のためのシステム導入資金や、産学連携プロジェクトへの資金提供により、技術革新のエコシステム構築に貢献しています。
SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を
銀行はESG投資基準を設定し、温室効果ガス排出量の多い企業への投融資を制限する一方、脱炭素技術開発企業への資金供給を拡大しています。近年では、TCFD提言に基づき、投融資先の気候リスクを定量評価し、経営判断に反映させています。
グリーンボンドの発行支援やカーボンニュートラル達成企業への優遇融資制度により、企業の脱炭素化を促進しています。
このように、銀行は金融機能を通じてSDGs達成への推進力となり、持続可能な社会実現に貢献し続けています。*8)
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ

銀行は多様な機能を通じて、私たちの日常生活や企業活動を支える存在です。2024年3月にマイナス金利政策が解除され、さらに2025年1月には政策金利が0.5%まで引き上げられたことで、預金やローンの金利環境が大きく変化し、どの銀行を選ぶかが家計や企業のコストに直結する重要な判断となっています。
日銀の利上げ後、メガバンクの普通預金金利は従来の0.001%から0.2%へと200倍に引き上げられました。さらに、一部ネット銀行では条件を満たすと最大0.5%を超える金利が適用されるため、手数料だけでなく金利差が家計に与える影響も、従来以上に大きくなっています。
今後の銀行では、AIやブロックチェーン技術の進展により、銀行の業務効率化やセキュリティ強化がさらに進むことが予想されます。また、中央銀行デジタル通貨(CBDC)※の導入検討が各国で本格化し、国際送金のコスト・時間短縮が実現すれば、私達の生活とグローバル経済との接続が一段と高まるでしょう。
企業にとっても個人にとっても、銀行選びは単なる口座開設ではなく、自分や社会の未来を形づくる重要な意思決定です。あなたは、どのような銀行に資金を預けることで、どのような未来を計画したいですか?
小さな一歩が、より良い金融システムと持続可能な社会の土台を築く原動力になります。ぜひ、金融知識を深め、自分に最適な選択を行ってください。*9)
<参考・引用文献>
*1)日本の銀行の種類は?
WIKIMEDIA COMMONS『Bank of Japan 2010』
金融庁『外国銀行代理業務に関するQ&A(改訂版)』(2019年6月)
金融庁『自己資本比率規制等(バーゼル規制)について』
金融庁『わが国における銀行・銀行グループの業務範囲規制について』(2020年11月)
金融庁『銀行法等の一部を改正する法律 (概要)』
金融庁『「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について』(2025年6月)
金融庁『銀行免許一覧(都市銀行・信託銀行・その他)』(2025年5月)
金融庁『外国銀行代理銀行認可・届出一覧』(2025年7月)
金融庁『金融機関等一覧(本法2条各号に規定)』
金融庁『預金保険制度(ペイオフとは?)
日本銀行『日本銀行の概要』
日本銀行『用語の定義』
日本銀行調査統計局『金融統計調査表の記入要領』(2024年8月)
日本銀行『日本銀行の目的は何ですか?』
MUFG『ペイオフ』
信託協会『信託銀行ってなに?』
信託協会『信託銀行とは?』
三井住友トラストグループ『信託銀行とは』
Bank of Americ『外国銀行代理業』
岸本 雄次郎『外国銀行代理業務にかかるコンプライアンス上の一考察――銀行法10条および47条の改正経緯を踏まえて――』(2013年)
金融広報中央委員会『各種金融機関の紹介』
NOMURA HOLDINGS『【3分で読める】日銀はなぜ「物価の安定」をめざすのか ~日本銀行の役割とその影響~』
*2)代表的な都市銀行
Wikipedia『メガバンク』
Wikipedia『都市銀行』
Wikipedia『三菱UFJ銀行』
Wikipedia『みずほ銀行』
Wikipedia『りそな銀行』
MUFG『会社概要』
三井住友フィナンシャルグループ『SMFG の強みとチャレンジ』
三井住友フィナンシャルグループ『SMBCグループの経営戦略』(2019年2月)
みずほ銀行『みずほ銀行について』
みずほ銀行『経営からのメッセージ』
みずほフィナンシャルグループ『企業理念・ブランド』
りそな銀行『会社概要』
りそなホールディングス『りそなグループのあゆみ』
法政大学『成立期日本信用機構の論理と構造(上)』(2025年8月)
歴史地理学会『明治・大正期における銀行立地と地域特性』
日本銀行金融研究所『金融機関の発達史について』
全国銀行協会『最近の銀行の合併を知るには』
東証マネ部!『渋沢栄一が調整役となり成立した「銀行制度」「株式会社制度」が明治以降の日本の発展を支えた』(2021年2月)
日本経済新聞『さらば「東京」 三菱UFJ銀行に行名変更』(2018年4月)
日本経済新聞『みずほ20年 再生への難路「メガ銀3位」定着、新興IT勢も台頭』(2019年8月)
日本経済新聞『メガバンクにのしかかる自重 総資産、GDPの1.5倍超え』(2022年4月)
*3)代表的な地方銀行
金融庁『中小・地域金融機関情報一覧』
金融庁『銀行免許一覧(都市銀行・信託銀行・その他)』(2025年5月)
Wikipedia『地方銀行』
Wikipedia『横浜銀行』
Wikipedia『千葉銀行』
Wikipedia『福岡銀行』
Wikipedia『七十七銀行』
横浜銀行『会社概要』(2025年4月)
Concordia Financial Group『組織図』
Concordia Financial Group『沿革』
千葉銀行『沿革』
千葉銀行『プロフィール』(22025年3月)
静岡銀行『基本理念』
静岡銀行『会社概要』
福岡銀行『ふくぎんについて』
福岡銀行『会社概要』
七十七銀行『会社概要』
七十七銀行『行是』
全国地方銀行協会『地方銀行一覧』
全国地方銀行協会『地方銀行を知ろう』
FinTech『ふくおかFGが地銀“初”の「ネット銀行」、それでも厳しすぎる現実が待ち受けるワケ』(2019年9月)
日経ビジネス『地銀再編 生き残りかけた地方銀行の合従連衡』(2025年7月)
福岡銀行『地方銀行 64行』
参議院『地域銀行の現状と課題―求められる経営基盤の確立―』(2018年7月)
日本経済新聞『地銀再編はまだ続く? 人口減少、不採算で集約必至』(2025年7月)
*4)代表的な地方銀行II(第二地方銀行)
金融庁『国内外の金融経済情勢の動向を踏まえた対応』(2025年1月)
中小企業庁『2 中小企業と金融機関との関係性』
日本銀行『国庫金電子収納事務取扱金融機関一覧』(2025年4月)
Wikipedia『第二地方銀行』
Wikipedia『北洋銀行』
Wikipedia『静岡中央銀行』
Wikipedia『佐賀共栄銀行』
スルガ銀行『スルガ銀行について』
静岡中央銀行『会社概要』
佐賀共栄銀行『当行の概要・経営理念』(2023年3月)
日本総研『数字を追う ~経営指標の特徴による金融機関の分類と合併・転換法の再考』(2015年9月)
大和総研『地方銀行の越境再編』(2025年7月)
日本経済新聞『1989年2月1日 全国の相互銀行52行、普通銀行に転換』(2021年2月)
新井 大輔『協同組織金融と地域 ―「コミュニティ・バンク論争」の再検討―』(2021年3月)
札幌大学『協同組織金融機関のあり方-信用組合の生き残りについての一考察-』(2013年2月)
*5)代表的な信託銀行
金融庁『3 信託銀行関係』
MUFG『信託銀行とは?』
MUFG『三菱UFJ信託銀行のビジョンとは?』
MUFG『会社概要』
三井住友信託銀行『三井住友信託銀行について 私たちの強み』
三井住友信託銀行『信託銀行のビジネスとは』
三井住友トラストグループ『信託銀行とは』
Wikipedia『三菱UFJ信託銀行』
Wikipedia『三井住友信託銀行』
Wikipedia『みずほ信託銀行』
Wikipedia『野村信託銀行』
みずほ信託銀行『社長メッセージ』
みずほ信託銀行『会社概要』
NOMURA『投資信託関連ビジネスについて』
NOMURA『事業内容』
NIKKEI COMPASS『信託銀行の会社』
日本経済新聞『信託4社の調査が示す「人的資本経営における金融経済教育の重要性」』
日本経済新聞『信託4社が人的資本に新たな方向性示す調査結果公表へ』
*6)代表的な外国銀行在日支店
金融庁『外国銀行代理銀行認可・届出一覧』
金融庁『外国金融サービス業者が我が国市場に参入するにあたって適用される法規制』
金融庁『1.外国銀行支店に対する規制について』(2012年8月)
金融庁『外国銀行代理業の認可制度について』
日本銀行『「国内銀行の資産・負債等」および「外国銀行在日支店の主要資産・負債」の変更について』(2002年7月)
Wikipedia『シティバンク、エヌ・エイ (在日支店)』
Wikipedia『シティバンク銀行』
Wikipedia『スタンダードチャータード銀行』
Wikipedia『香港上海銀行』
Wikipedia『バンク・オブ・アメリカ』
Wikipedia『四大銀行』
Wikipedia『DBS銀行』
Wikipedia『CIMB』
Bank of America『バンク・オブ・アメリカについて』
Standard Chartered『スタンダードチャータード銀行 東京支店 概要』
Standard Chartered『スタンダードチャータード銀行 東京支店の事業内容』
Standard Chartered『日本におけるビジネスのご案内』
JPMorgan Chase『日本におけるJ.P.モルガン』
Goldman Sachs『徹底したこだわりが最高の結果を生む』
HSBC『日本におけるHSBC』
Deutsche Bank『会社概要(日本)』
Deutsche Bank『ドイツ銀行グループについて』
IBA『活動』
citi『日本』
DBS『日本におけるDBSグループ』
三井住友銀行『外国業務』
三井住友フィナンシャルグループ『海外ビジネス』
りそな銀行『株式会社十六銀行との国際業務における連携について』(2025年8月)
SMBC『DXときめ細かな英語対応で、グローバルな顧客ニーズに応えるSMBC信託銀行』(2025年3月)
アジア経済交流センター『ここが違う!中国の「銀行」』
野村資本市場研究所『成功を収めた中国における国有商業銀行改革』(2009年)
八十二銀行『CIMB銀行(マレーシア)、インドステイト銀行(インド)との業務提携について』
*7)銀行の選び方
金融庁『高校生のための金融リテラシー講座』(2022年3月)
金融広報中央委員会『金融リテラシー・マップ』(2023年6月)
金融庁『基礎から学べる金融ガイド』
金融広報中央委員会『金融機関選びのポイント』
全国銀行協会『01 銀行口座の活用法と銀行の選び方』
全国銀行協会『将来のためにできること、それが資産形成』
りそな銀行『【失敗しない】銀行口座開設の際の選び方とおすすめの銀行を紹介』(2022年2月)
SMBC『ネット銀行とは?メリット・デメリットと選び方をわかりやすく解説』(2025年3月)
SMBC『預金(貯金)用の銀行口座は作るべき?メリットやおすすめの口座、選び方を解説』(2025年3月)
福岡銀行『知っておきたい銀行預金の種類とは?目的に合った口座を開設しよう』
日本経済新聞『銀行口座の選び方と使い方 無料送金、証券連携も活用』
*8)銀行とSDGs
Spaceship Earth『金融業界のSDGs取組事例を紹介!取り組むためのポイントも』(2025年3月)
金融庁『金融行政とSDGs』(2018年12月)
金融庁『金融行政とSDGs』(2019年2月)
金融庁『サステナブルファイナンスの取組み』(2025年7月)
金融庁『SDGsに貢献する金融商品に関するガイドブック』(2021年2月)
日本銀行『ESG投資の発展に向けた実務的な課題とその克服に向けた取り組み』(2021年11月)
日本銀行『SDGs/ESG金融に関する金融機関の取り組み』(2020年10月)
全国銀行協会『全銀協のSDGsに関する取組み』
全国銀行協会『SDGs に金融はどう向き合うか』(2019年3月)
日本政策投資銀行『DBJ環境格付融資』
MUFG『SDGs』
MUFG『今、注目のESG投資とは?』
立命館大学『ESG 投資と日本の NPO/NGO』(2024年12月)
みずほフィナンシャルグループ『持続可能な開発目標(SDGs)達成への取り組み』
*9)まとめ
金融庁『⾜元の預⾦動向の実態把握と⾦利上昇との関係にかかる分析』(2025年5月)
金融庁『今後の金融行政の方向性』(2025年1月)
政府広報オンライン『「金融リテラシー」って何? 最低限身に付けておきたいお金の知識と判断力』(2025年8月)
MUFG『円預金金利』(2025年8月)
NOMURA『日銀、政策金利は据え置きも 25年度の成長率見通しを0.5%に下方修正 野村證券・尾畑秀一』(2025年5月)
日本経済新聞『銀行のサイバー防御に次世代暗号要請 金融庁、量子技術悪用に備え』(2025年5月)
この記事を書いた人
松本 淳和 ライター
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。