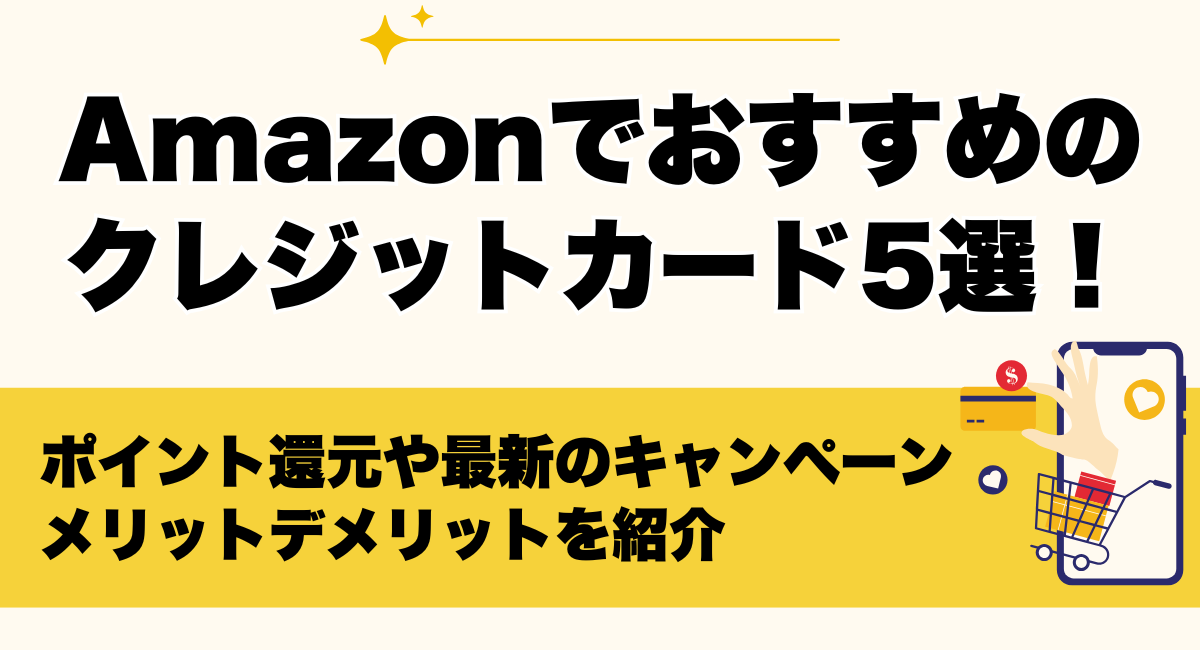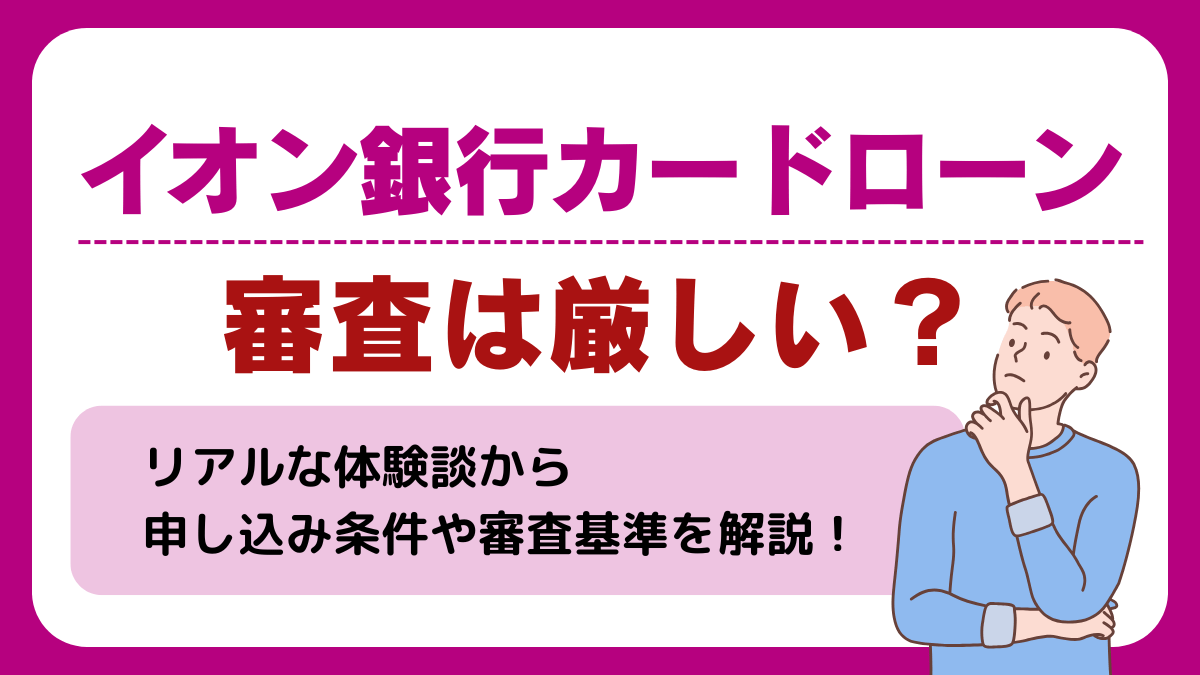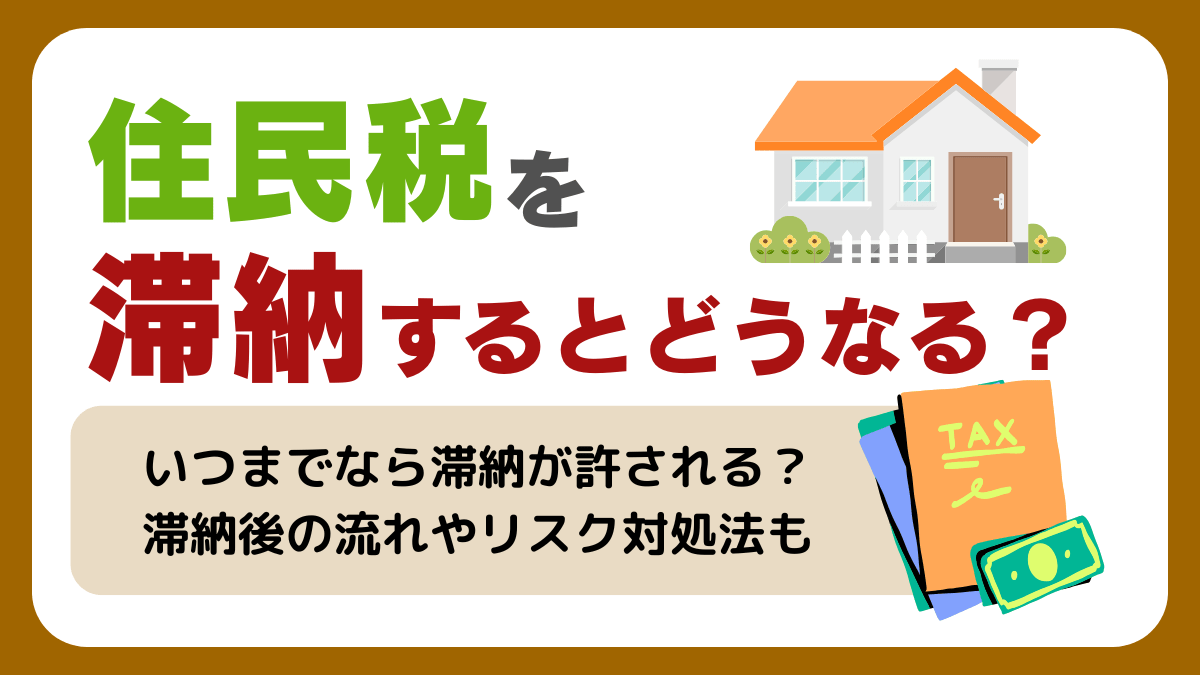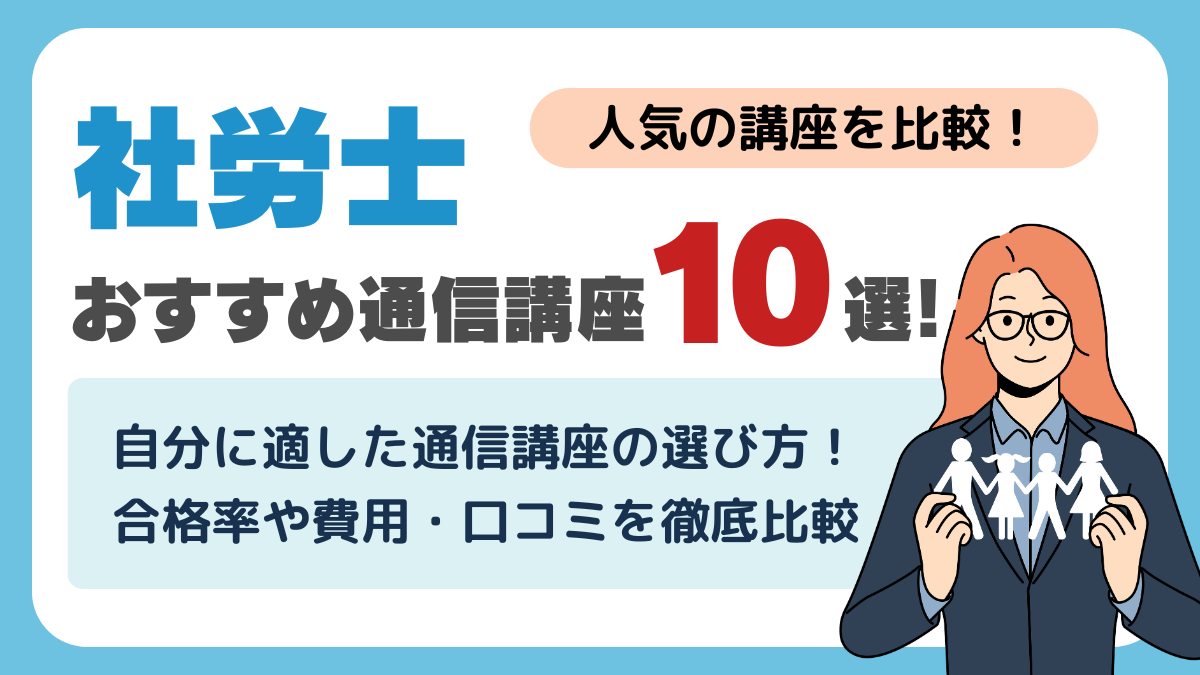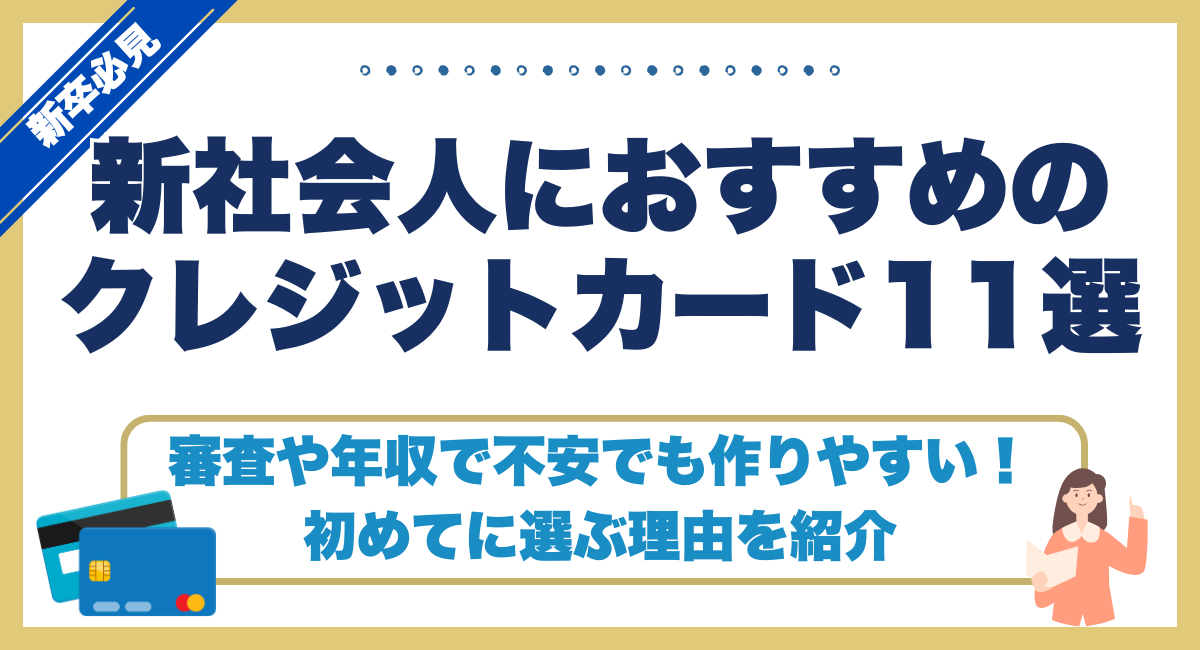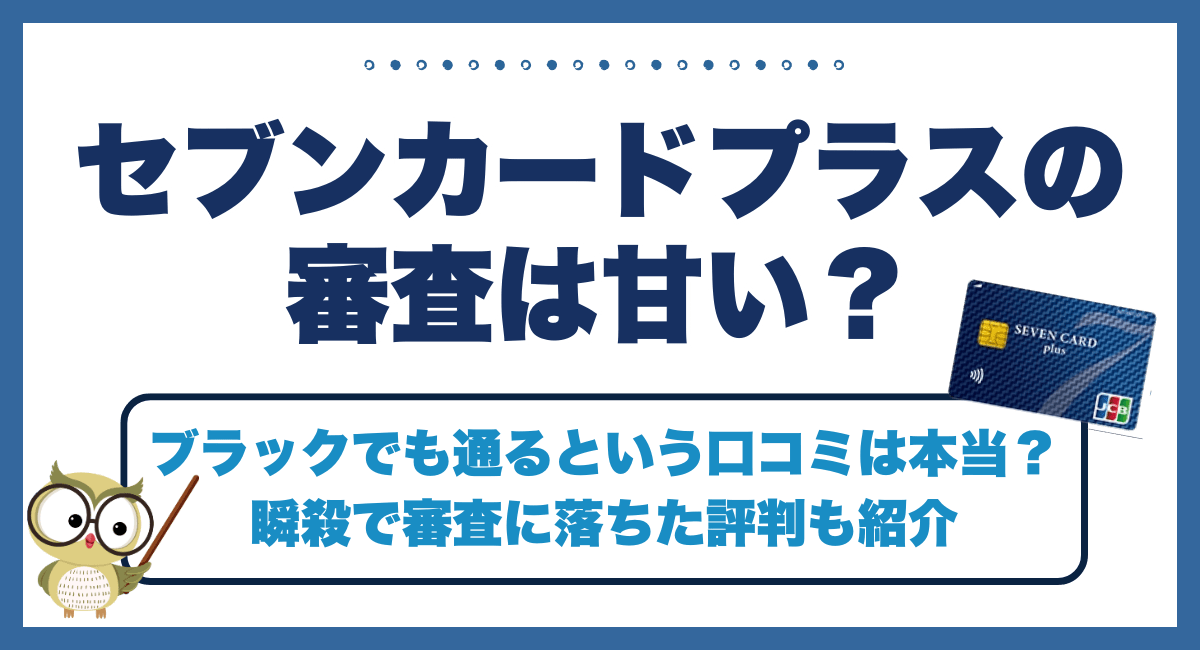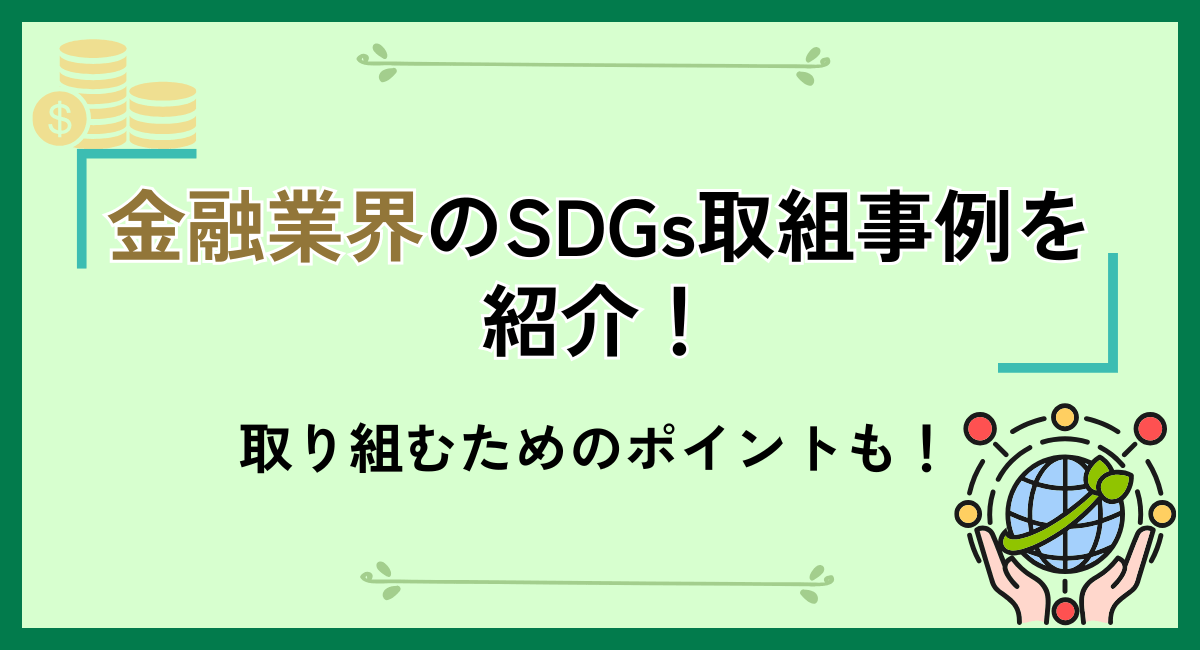
金融とSDGsの関係性をご存知ですか?実は、私たちの預金や投資は、金融リテラシーとエシカルな意識を持つことによって、持続可能な社会の実現に大きく貢献する可能性があるのです。
もはや日本では社会人の常識とも言えるSDGsの、海外・日本国内の金融業界による取r組事例を紹介し、金融によってSDGsの目標達成に取り組むためのポイントを解説します。あなたの金融行動は、世界を変える第一歩につながっています。
目次
金融業界がSDGsに取り組む必要性

金融は経済活動の血流であり、持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を果たします。SDGsの達成には莫大な資金が必要とされ、金融機関の積極的な取り組みが必要です。
国連の報告書によると、SDGs目標達成に必要な資金額は年間5〜7兆ドル(約760兆円~1,064兆円)※と推計されています。この巨額の資金を効果的に配分し、持続可能な開発を促進するためには、金融業界の力が重要な鍵となるのです。
※約152円/ドルとして計算
【金融とSDGs】
金融業界とSDGsの関係は、単なる資金提供以上に深いものがあります。金融業界がSDGsに取り組む必要がある理由を確認してみましょう。
①ESG金融(ESG投資)の重要性
ESG金融(ESG投資)とは、環境・社会・ガバナンスの要素を考慮した金融活動のことです。これは単なるトレンドではなく、金融業界の未来を左右する重要な概念です。
金融機関がこれらに取り組むことで、SDGsの目標達成に貢献しつつ、自らのビジネスリスクを軽減し、新たな成長機会を見出すことができます。
【ESG投資とSDGsの関係】
②資金配分の最適化
金融機関は、SDGsの達成に向けて資金を最適に配分する重要な役割を担っています。環境に配慮したプロジェクトや社会的課題の解決に取り組む企業への融資や投資を通じて、持続可能な開発を促進することができます。
国際通貨基金(IMF)は、SDGsの達成には金融システムの変革が不可欠であると指摘しています。
③リスク管理の進化
SDGsへの取り組みは、金融機関自身のリスク管理にもつながります。気候変動や社会的不平等などのグローバルな課題は、金融業界にとっても大きなリスク要因となります。
これらのリスクを適切に評価し、管理することで、長期的な安定性を確保することができます。
③ステークホルダーからの信頼獲得
金融機関がSDGsに積極的に取り組むことで、顧客、投資家、従業員などのステークホルダーからの信頼を獲得することができます。持続可能性を重視する姿勢は、企業価値の向上につながり、競争力を高める要因となります。
④地域経済の活性化
特に地域金融機関にとって、SDGsへの取り組みは地域経済の活性化につながります。地域の課題解決に資する事業への支援を通じて、持続可能な地域社会の構築に貢献することができます。
これは金融機関自身の経営基盤強化にもつながる重要な取り組みです。
金融業界がSDGsに取り組むことは、社会的責任を果たすだけでなく、自らの持続可能性を高め、新たなビジネス機会を創出する戦略的な選択肢となっています。今後、ESG投資はますます重要性を増し、金融業界の競争力を左右する要因となるでしょう。*1)
SDGsの達成に向けて金融業界ができること

金融業界は、持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を担っています。資金の流れを変え、環境や社会に配慮した事業を支援することで、SDGsの達成に大きく貢献できるのです。
【金融と社会問題の解決】

SDGsの達成に向けて金融業界ができることの具体的な例を見ていきましょう。
サステナブルファイナンスの推進
サステナブルファイナンスは、環境・社会・ガバナンス(ESG)の要素を考慮した、持続可能な社会の構築に資する金融活動を指します。金融機関は、ESG投資やグリーンファイナンス※、トランジションファイナンス※などを通じて、持続可能な事業や企業を支援することができます。
例えば、再生可能エネルギープロジェクトへの融資や、環境技術の開発を行う企業への投資などが挙げられます。
【国内企業等によるサステナビリティボンド※の発行実績】
【世界のグリーンボンド※発行体の地域別の発行実績】
気候変動リスクへの対応
金融機関は、気候変動がもたらすリスクを適切に評価し、管理する必要があります。TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)※の提言に基づく情報開示を行うことで、投資家や顧客に対して透明性を高めることができます。
また、気候変動リスクを考慮した融資や投資判断を行うことで、長期的な視点での資金配分が可能となります。
金融安定理事会(FSB)が2015年に設立した。ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の4項目の開示を推奨。日本では経済産業省や環境省が推進し、多くの上場企業が採用している。
金融リテラシーの向上
SDGsの達成には、個人の行動変容も重要です。金融機関は、金融経済教育を通じて、一般の人々のSDGsや持続可能性に関する理解を深める役割を果たすことができます。
具体的には、SDGs関連の投資商品や融資プログラムについて分かりやすく説明したり、持続可能な消費行動を促進するための情報提供を行ったりすることが例として挙げられます。
パートナーシップの構築
金融機関は、政府、企業、NGOなど、さまざまなステークホルダーとのパートナーシップを通じて、SDGsの達成に向けた取り組みを加速させることができます。国際的にも、新興国との技術協力や人材交流を通じて、持続可能な開発のための知識や経験を共有することが可能です。
【「社会の価値」の創出に関わるプレイヤー】
金融業界は、これらの取り組みを通じてSDGsの達成に貢献しつつ、不確実性の高い未来に備えることができます。サステナブルファイナンスの推進は、新たなビジネス機会の創出にもつながり、金融業界自体の持続可能性を高めることにもなるでしょう。*2)
金融業界のSDGs取組事例

金融機関のSDGsへの取り組みは、私たちの日常生活と密接に関わっています。預金や投資を通じて、個人も環境保護や社会問題の解決に貢献できる時代が到来しているのです。
世界と日本の金融機関の具体的な取り組みを見ていきましょう。
世界の金融機関の取り組み
国際的な金融機関は、SDGs達成に向けて先駆的な役割を果たしています。
世界銀行
世界銀行※は2008年に史上初のグリーンボンドを発行し、再生可能エネルギー事業に130億ドルを投資しました。この取り組みにより、600万人以上がクリーンエネルギーにアクセスできるようになりました。
2025年現在、世界銀行は120か国以上で1,500件を超える気候関連プロジェクトを展開し、年間約5,000万トンのCO2削減に貢献しています。
アメリカ:シティグループ
アメリカの大手銀行シティグループ※は、「1,000億ドル環境金融目標」を掲げ、風力発電所の建設や電気自動車充電インフラの整備に積極的に投資しています。2023年にはこの目標を2年前倒しで達成し、太陽光発電だけで500万世帯分の電力供給を実現しました。
日本の金融機関の取り組み
日本の金融機関もSDGsへの取り組みを加速させています。
三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)
三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は2021年、サステナブルファイナンス目標を35兆円に拡大しました。この目標には、再生可能エネルギーへの融資や、環境配慮型の住宅ローンなどが含まれています。
地方銀行
地域金融機関の取り組みも注目されています。滋賀銀行は2017年に「しがぎんSDGs宣言」を発表し、2018年には地方銀行として初めて「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しました。
滋賀銀行は「SDGsコンサルティング」サービスを提供し、地元企業のSDGs経営をサポートしています。また、「カーボンニュートラルローン 未来よし」という融資商品を通じて、企業の脱炭素化を支援しています。
【ESG地域金融】

日本取引所グループ(JPX)
日本取引所グループ(JPX)は、上場企業のESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みを促進しています。コーポレートガバナンス・コード※の改定により、上場企業に気候変動対応の情報開示を求めています。
2025年2月現在、東証プライム市場上場企業の95%以上がTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に沿った情報開示を実施しています。
これらの取り組みは、個人投資家にも影響を与えています。NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)を通じて、SDGsに貢献する企業に投資できるESG投資商品が増加しています。
2024年の調査では、20代の若年層におけるESG投資の比率が過去3年間で6倍に拡大したことが明らかになりました。
このように、金融機関のSDGsへの取り組みは、私たちの日々の金融行動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献する機会を提供しています。預金先の選択や投資判断を通じて、個人レベルでもSDGsに参加できる時代が到来しているのです。*3)
金融業界がSDGsに取り組むためのポイント

金融業界がSDGsに取り組む上で、いくつかの重要な課題があります。これらの課題を克服し、持続可能な社会の実現に向けて金融業界が取り組みを進めるにあたって何が重要かを確認します。
サステナビリティ人材の育成・充実
金融機関にとって、サステナビリティに関する専門知識を持つ人材の確保と育成が喫緊の課題となっています。環境問題や社会課題に精通し、それらを金融の観点から分析できる人材が不足しているのが現状です。
金融機関は、従業員に対してサステナビリティに関する研修プログラムを提供したり、外部専門家との連携を強化したりすることで、この課題に対応する必要があります。
情報・データ基盤の整備
サステナブルファイナンスを推進するためには、企業のESG情報やSDGsへの貢献度を正確に評価するためのデータが欠かせません。しかし、こうしたデータの収集や分析方法が標準化されていないのが現状です。
金融機関は、ESG評価・データ提供機関との協力や、TCFDなどのグローバルなフレームワークの活用を通じて、信頼性の高いデータ基盤を構築する必要があります。
グリーンウォッシュ対策の強化
サステナブルファイナンスの普及に伴い、グリーンウォッシュ※のリスクが高まっています。金融機関は、投資先企業の取り組みを厳密に精査し、効果的に持続可能な事業に資金を提供することが求められます。
そのためには、企業の情報開示の充実を促すとともに、自らの審査基準を明確化し、透明性を高めることが重要です。
個人レベルでも、金融機関のSDGsへの取り組みに注目し、自身の投資判断に活かすことができます。例えば、NISAやiDeCoを利用する際に、ESG投資やインパクト投資の商品を選択することで、間接的にSDGsの達成に貢献できます。
また、取引先の金融機関がどのようなサステナビリティ方針を持っているかを確認し、自身の価値観に合った機関を選ぶことも大切です。
金融業界がSDGsに取り組むことは、単なる社会貢献ではなく、企業価値の向上や新たなビジネス機会の創出につながります。私達一人ひとりにも、こうした動きに関心を持ち、自身の金融行動を通じて持続可能な社会の実現に参加することが求められています。*4)
まとめ

金融業界のSDGsへの取り組みは、持続可能な社会の実現に向けた重要な鍵となっています。
- 企業と投資家の対話
- 情報・データ基盤の整備
- 企業開示の充実
など、多岐にわたる課題に取り組むことで、金融業界は社会的責任を果たしつつ、新たな成長機会を見出すことができるでしょう。
国際情勢の不確実性は、金融業界に大きな影響を与えています。国連の報告書が世界経済の低迷を警告する中、IMFも金融安定性に関する懸念を表明しています。
こうした状況下で、金融機関には柔軟な対応と強靭な体制構築が求められています。金融業界がSDGsに取り組むことは、このような未来の予想が難しい状況下で、経済を安定的に維持するためのリスク対策にもなります。
あなたは、あなたのお金の使い方が世界にどのような影響を与えているか考えたことがありますか?これからの社会では個人レベルでの金融リテラシーの向上がますます重要となっていきます。
ESG投資やインパクト投資への理解を深め、自身の価値観に合った金融行動を取ることで、SDGsの達成に貢献してみてはいかがでしょうか。例えば、NISAやiDeCoを活用する際に、サステナブルな企業や事業に投資する商品を選択することも1つの方法です。
金融とSDGsの関係性を理解し、行動に移すことは、個人の経済的利益だけでなく、社会全体の持続可能性にも貢献します。より良い未来に向けて、無理なくできることから始めてみましょう。*5)
<参考・引用文献>
*1)金融業界がSDGsに取り組む必要性
金融庁『金融行政とSDGs』(2018年12月)
日本銀行『SDGs/ESG金融に関する金融機関の取り組み』(2020年10月)
国際連合広報センター『国連の新たな報告書、SDGsを救うための数兆ドルの開発投資の拡大を呼びかけ(2024年4月9日付プレスリリース・日本語訳)』(2024年4月)
国際通貨基金『IMFと持続可能な開発目標 (SDGs)』(2023年3月)
Reuters『最貧国SDGsに国際金融システムで取り組む必要=国連開発計画総裁』(2024年10月)
国際通貨基金『Sustainable Development Goals』
全国銀行協会『SDGs に金融はどう向き合うか』(2019年3月)
金融庁『金融行政とSDGs』(2020年1月)
全国銀行協会『第 1 章 SDGs に金融はどう向き合うか』(2018年12月)
日本銀行『SDGs/ESG金融を巡る最近の動向』(2021年1月)
経済産業省『サステナブルファイナンスの推進について』(2022年4月)
資源エネルギー庁『カーボンニュートラルに向けた産業政策“グリーン成長戦略”とは?』(2021年5月)
東証マネ部!『【ESG投資を知る】サステナビリティ経営のプロに聞く“ESG投資が目指す未来”』(2023年7月)
東証マネ部!『SDGsとの関係は?投資ビギナーが個人でも実践できるESG投資法とそのポイント』(2022年5月)
東証マネ部!『【日経記事でマネートレーニング20】投資ニュースを読む~なぜ「ESG」運用が大事なのですか?』(2021年10月)
東証マネ部!『(2)ESG投資の背景とSDGsとの関係』(2021年7月)
日本経済新聞『国連、SDGs実現へ「金融システムの見直し必要」』(2019年4月)
*2)SDGsの達成に向けて金融業界ができること
環境省『金融行政とSDGs』(2019年2月)
環境省『グリーンファイナンスポータル 国内におけるグリーンボンドの発行・投資への期待』(2024年1月)
環境省『グリーンファイナンスポータル 国内におけるグリーンボンドの発行・投資への期待』(2024年11月)
経済産業省『「SDGs 達成へ向けた企業が創出する『社会の価値』への期待」に関する調査研究報告書』(2020年3月)
生物多様性センター『ESG金融を通じた企業の生物多様性への配慮の促進』
Money Forward『SDGs融資とは?金融機関が取り組みを進める背景やESG・SDGs融資商品を紹介』(2024年7月)
日本証券業協会『SDGsに貢献する金融商品について』
全国銀行協会『全銀協SDGsレポート2021‒2022』(2022年6月)
全国銀行協会『全銀協SDGsレポート2023‒2024』(2024年6月)
JPX『サステナブルファイナンス環境整備検討会の設置要綱』(2021年10月)
JPX『JPX「サステナブルファイナンス環境整備検討会」中間報告書』(2022年1月)
*3)金融業界のSDGs取組事例
環境省『ESG地域金融実践ガイド 2.2』(2023年3月)
国際連合広報センター『安定のための融資』
IMF『IMF による国連の持続可能な開発目標への支援』(2017年)
世界銀行『持続可能な開発目標(SDGs)と世界銀行グループ:ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ』(2015年9月)
世界銀行『持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて:世界銀行グループの取り組み』(2018年10月)
IMF『持続可能な金融と金融安定性を結びつける』(2019年10月)
G20『2024 G20 Sustainable Finance Report』(2024年9月)
金融庁『外資系金融機関における持続可能な開発目標(SDGs)関連の取組みに関する調査報告書』(2018年3月)
財務局『金融庁によるサステナブルファイナンスの取組み』(2023年6月)
環境省『インパクトファイナンスの基本的考え方について』(2020年10月)
全国銀行協会『2023 年度活動の総括および 2024 年度の SDGs の主な取組項目について』(2024年3月)
全国銀行協会『気候変動問題への銀行界の取組みについて』(2022年6月)
日本証券業協会『日本証券業協会におけるサステナブルファイナンス推進に向けた取組み』(2024年2月)
MUFG『SDGs MUFGのサステナビリティ経営の現状』
JPX『SDGsへの取組み』(2024年12月)
JPX『ESG投資の普及に向けた取組み』
JPX『環境省のESG金融促進-開示と移行の観点から』(2021年4月)
JPX『環境に関する情報(TCFD開示/移行計画)』(2024年12月)
日本経済新聞『インパクト投資が拡大 昨年国内残高、6割増の17兆円』(2025年1月)
日本経済新聞『新NISA元年、「投資信託つみたて」定着 20代は比率5割に』(2025年2月)
日本経済新聞『環境や社会的責任を評価、KDDIなど上位 日経調査 日経サステナブル総合調査<SDGs経営編>』(2024年11月)
*4)金融業界がSDGsに取り組むためのポイント
IMF『持続可能な開発目標 達成に向けて総力結集を』(2021年4月)
金融庁『金融庁サステナブルファイナンス有識者会議 第四次報告書』(2024年7月)
金融庁『気候変動関連の日本銀行の取組―金融システム関連取組みを中心に』(2023年2月)
環境省『責任銀行原則(PRB)の署名・取組ガイド』(2021年3月)
野村総合研究所『金融機関の成長戦略としてのサステナブル経営』(2019年)
野村総合研究所『IMF世界経済見通し:各国間格差が大きな問題:米国利下げ期待後退で金融市場混乱のリスク』(2024年4月)
日本経済新聞『SDGs、日本の現在地 社会課題を投資の軸に』(2023年9月)
日本経済新聞『国連未来サミットでSDGs巻き返し 民間資金の動員探る』(2024年8月)
日経BizGate『グローバルサウスの未来、アナログとデジタルで創造 TOPPANホールディングス、エチオピア政府と合弁会社を設立』(2025年2月)
BBC『【COP26】 英財務省、金融機関などにネットゼロ計画を義務付け』(2021年11月)
東洋経済ONLINE『ウェルビーイングが導く、社会課題の解決法・前編 「ポストSDGs時代」の新たな指標をつくる意義』(2025年1月)
*5)まとめ
国際連合広報センター『長引く不確実性を背景に、世界成長は引き続き低迷する — 国連報告書が警告(2025年1月9日付 国連経済社会局プレスリリース・日本語訳)』(2025年1月)
Reuters『IMF金融安定報告、軟着陸への楽観論に警鐘 三重苦抱える銀行も』(2024年4月)
Reuters『今後、円安進行や金融の過熱回避の観点から政策調整必要=1月日銀主な意見』(2025年2月)
日本総研『サステナビリティ・2025万博』
大和総研『トランプ大統領が6ヵ月で本当に戦争を止めたら金融市場はどうなる』(2025年1月)
日本経済新聞『トランプ流「ドリル」政策 米国のESGファンドを直撃』(2023年2月)
日本経済新聞『トランプ時代、「ESG」は面従腹背で生き延びる』(2024年12月)
東洋経済ONLINE『投資の世界で普及「インパクト」が流行語になる日 事業や取り組みの社会や環境への影響度を評価』(2024年10月)
東証マネ部!『2025年の投資における注目点』(2025年1月)
この記事を書いた人
松本 淳和 ライター
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。