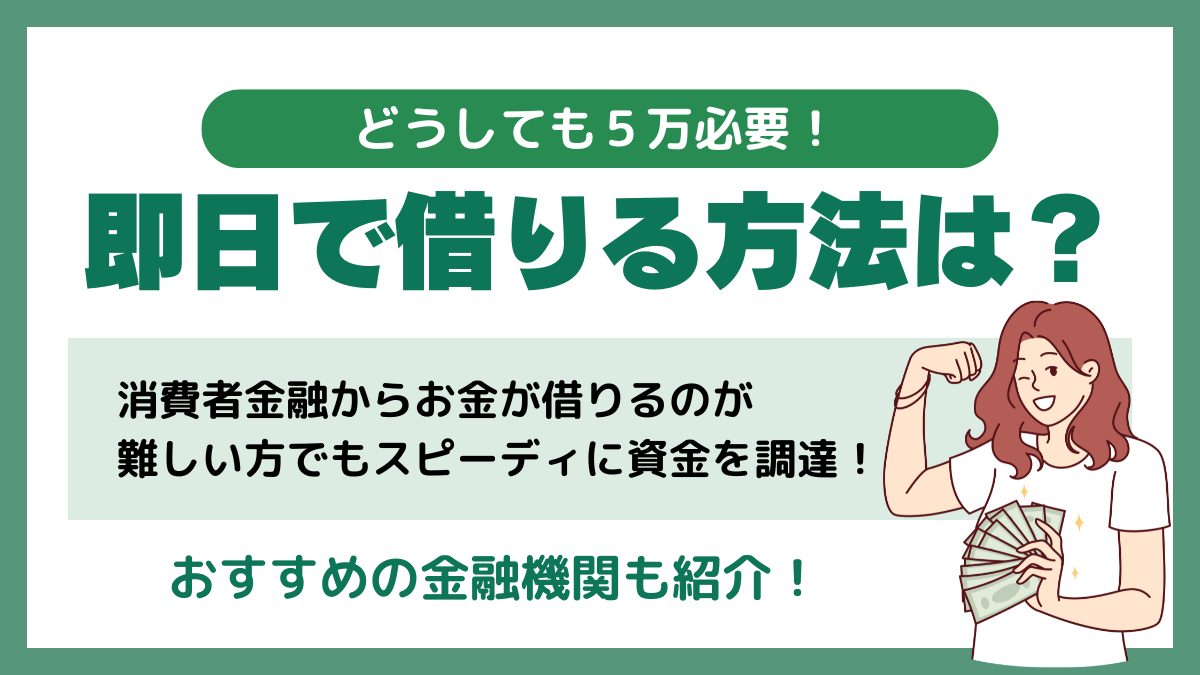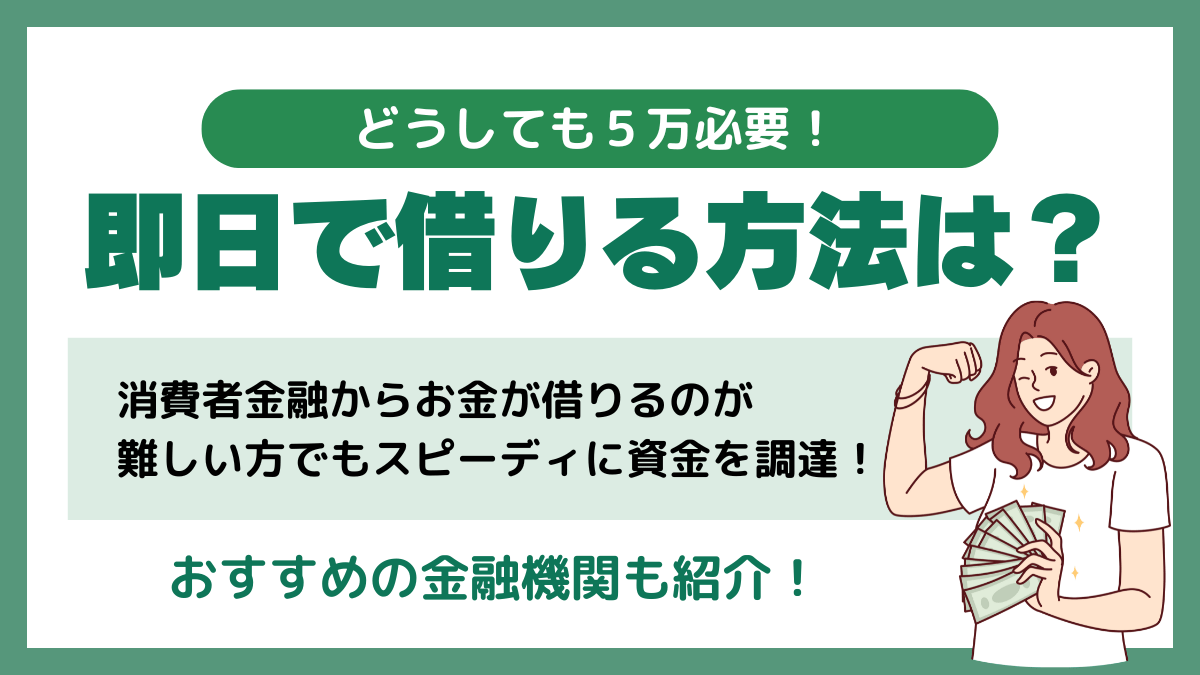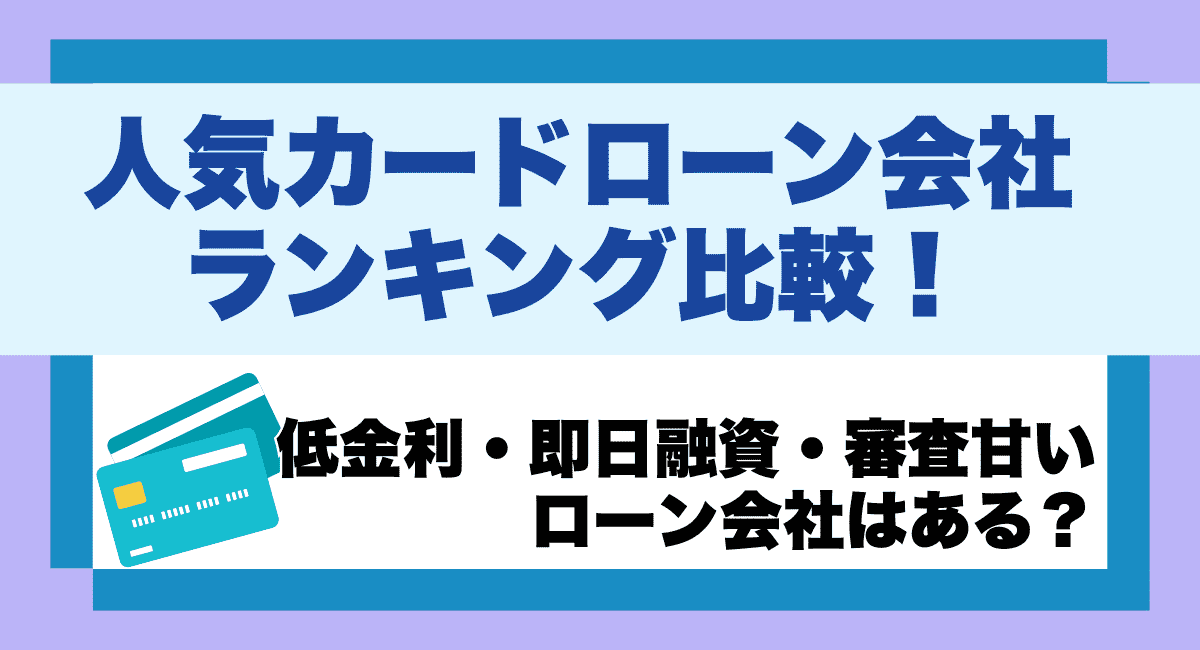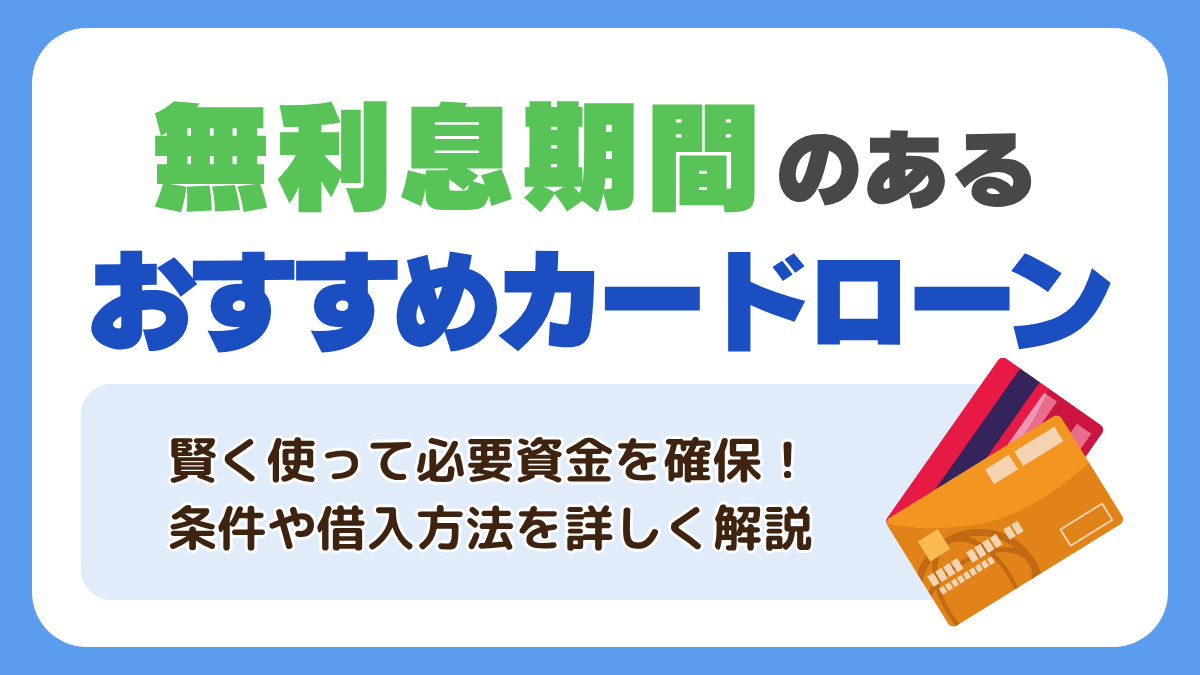カルチュラル・アプロプリエーションという言葉を耳にしたことはありますか?文化の盗用とも言われ、ある文化圏の要素が、別の文化圏によって無断で、あるいは不適切に利用されることを指します。
一見すると、異文化への憧憬や敬意の表れとも思えるこの行為が、なぜ批判の対象となるのでしょうか。カルチュラル・アプロプリエーションの代表的な事例や問題点を紐解き、その背景にある複雑な要因を多角的な視点から考察します。
目次
カルチュラル・アプロプリエーションとは

カルチュラル・アプロプリエーション(cultural appropriation)とは、日本語では一般的に「文化の盗用」と訳され、ある文化から生まれた視覚的・非視覚的なアイデア、シンボル、芸術作品などを、別の文化を持つ者が利用することを指します。この行為は、本来の文化的文脈を無視し、その価値を矮小化する形でなされることが多く、特にファッションの分野において議論を呼んでいます。
しかし、この問題はファッションに限ったことではありません。音楽、美術、映画、アニメ、食文化、宗教的シンボル、伝統的な儀式など、多岐にわたる分野で同様の現象が見られます。
カルチュラル・アプロプリエーションは、単に異文化の要素を取り入れることとは異なります。重要な問題となるのは、その行為が文化的背景への理解と敬意を欠いているかどうかです。
また、文化の盗用は「キャンセル・カルチャー」と混同されることがありますが、これらは別のものです。キャンセル・カルチャーは、特定の人物や団体の言動に対する社会的な制裁を指し、文化の盗用は、文化的な要素の不適切な利用を批判するものです。
文化の模倣から盗用への変遷

文化の模倣は、古くから人類の文化交流の中で行われてきました。しかし、それが「アプロプリエーション」「盗用」と批判されるようになった背景には、いくつかの歴史的な要因があります。
西洋による東洋文化の「観賞品的扱い」が批判される
1945年、アーサー・E・クリスティはオリエンタリズムを論じたエッセイを発表しました。これは、西洋が東洋をどのように認識し、表象してきたかを考察したもので、後のポストコロニアル理論※に大きな影響を与えました。
フランスのデザイナーによる着物をモチーフにしたシリーズの賛否
20世紀初頭には、ポール・ポワレがオリエンタルなデザインを発表しました。これは称賛を受ける一方で、文化的意味の軽視という問題を提起しました。
【ポール・ポワレによる花模様の着物風コート】
エスニックシック・ブームの到来
1990年代の「エスニックシック・ブーム」※では、ネイティブアメリカン模様の大量生産製品が登場します。ニューヨーク・タイムズが「神聖なシンボルがカジュアルシャツに変質した」と報じるなど、商業化と大量生産による文化的意味の喪失が指摘され始めました。
原宿のサブカルチャーを取り入れたファッションが議論の的に
2000年代初頭には、グウェン・ステファニーが原宿のサブカルチャーを自身のデザインに取り入れましたが、これが文化の盗用であるとの批判と、日本文化を西洋に紹介したという称賛の両方を受けました。
炎上するカルチュラル・アプロプリエーション
2012年のヴィクトリアズ・シークレットのファッションショーでは、モデルがネイティブアメリカン風のヘッドドレス※を着用し、物議を醸しました。この事例では、SNS上で「#NotYourCostume」のハッシュタグが24時間で50万回以上使用されました。

2019年には、ディオールがネイティブアメリカンのイメージを多用したフレグランスの広告キャンペーンで激しい非難を浴び、同年、キム・カーダシアンが自身のシェイプウェアのラインで「Kimono」という言葉を商標登録しようとして、大きな批判を浴びました。
これらの事例は、カルチュラル・アプロプリエーションが単に異文化の要素を利用するだけでなく、その背後にある歴史的、文化的背景を無視することによって生じる問題であることを示しています。
民族文化と模倣の自由
【ゴッホ「おいらん(栄泉を模して)ゴッホ美術館】
カルチュラル・アプロプリエーションは、「民族文化の保護」と「模倣の自由」という、相反する価値観の衝突でもあります。例えば、ある文化にとっては神聖なシンボルが、別の文化にとっては単なるデザインとして消費されることがあります。
このギャップは、近年しばしば「炎上」と呼ばれるソーシャルメディア上の論争を引き起こします。
しかし、特に芸術やデザインにおいては、「インスピレーション」や「オマージュ」と「アプロプリエーション(盗用)」の境界判断は、時に非常に困難な場合があります。また、文化庁は、「文化の盗用」には著作権法では対応できない、無形文化財保護という課題があることを指摘しています。
カルチュラル・アプロプリエーションは、単に異文化の要素を利用するだけでなく、その背後にある歴史的、文化的背景を無視することによって生じる問題です。私たちは、文化的な背景に目を向け、他者と文化の多様性を尊重しながらも、創造的な活動ができる社会を模索する必要があります。*1)
カルチュラル・アプロプリエーションの具体事例

カルチュラル・アプロプリエーションについては、ファッション界に留まらず食文化やテクノロジー分野まで議論が広がっています。ここでは国際的に議論を巻き起こした代表的事例から、その問題の多様な現れ方を見ていきましょう。
ファッション業界での例
衣服や装飾品をめぐるカルチュラル・アプロプリエーション問題は、歴史的に繰り返されてきました。先述した2012年ヴィクトリアズ・シークレットのショーで、モデルがネイティブアメリカンの戦闘用ヘッドドレス※を着用した件は、先住民団体から「神聖な象徴の冒涜」と抗議を受けました。
【伝統衣装をまとったスー族の戦士、ジトカラ・サ(19世紀の撮影)】
2013年には、セレーナ・ゴメスがコンサートでヒンドゥー教のビンディ※を着用した際、宗教指導者から「神聖な印の軽視」と指摘されました。彼女は「文化へのリスペクト」を主張しましたが、宗教的シンボルの商業利用の是非が問われました。
【ルンビニの巡礼者市場の若い女性(ネパール)】
また、2016年にはマーク・ジェイコブスが白人モデルにドレッドロック※を施し、「人種的感覚の欠如」と批判されています。
中でも、よく文化の盗用問題になっている「コーンロウ」は、アフリカ系の人々にとって文化的アイデンティティを表す重要な髪型とされる。奴隷制時代に文化を守る手段として用いられ、現代でも伝統や誇りの象徴として受け継がれている。ただし、髪型についての起源は諸説あるため、注意が必要。
【スーダン、ヌバ族の伝統的な編み込み】
食文化をめぐる衝突
2019年ニューヨークでは、中華料理店「ラッキー・リーズ」のユダヤ系アメリカ人経営者が「健康的な食材を使ったクリーンな中華料理を提供し、翌日に膨満感や不快感を感じさせない」と宣伝し、炎上しました。伝統的な中華料理を「不健康」と決めつけ、自分たちの料理を「衛生的」と表現し、中華料理に対する敬意を欠いている、移民系レストランの衛生面への偏見を助長する、などと批判され、3日間で閉店に追い込まれました。
別の例では、BBCが報じたマークス&スペンサーのビーガン・ビリヤニ巻きも、伝統料理の本質的価値が損なわれた例として議論を呼んでいます。
【カリフォルニアロール】

先住民文化とAIの新たな課題が浮上
2023年ニュージーランドでは、マオリ族がAIによる紋様生成ツールの開発を「デジタル植民地主義」と批判しました。伝統的な模様「マンガイア」が無断で使用される事態を受け、文化庁がデータ利用規制のガイドライン策定を開始しています。
近年、生成AIの学習データに先住民文化が無断収集されるケースが増加し、日本でも「デジタル時代の文化保護」の必要性が指摘されています。
このように、カルチュラル・アプロプリエーションの問題は実に多様な形で現れます。次の章では、この問題をさらに深く考えてみましょう。*2)
カルチュラル・アプロプリエーション問題の根底

カルチュラル・アプロプリエーションは、単に見た目の模倣にとどまらず、その背後にある文化的な意味や価値を奪い取る行為です。それは、時にオリジナルの文化や人々に対して失礼であったり、不快感を与えたりすることがあります。
ここでは、この問題を「搾取の連鎖」と「尊厳の侵害」という2つの軸から、深堀りしてみましょう。
搾取の連鎖:歴史的権力関係の再生産
【インドネシア、マレーシアのろうけつ染め布地バティック】

文化の盗用は、単に「見た目が似ているものを使う」という問題ではありません。その背後には、歴史的な権力関係が深く関わっています。
「ファッションの犠牲地帯」
人類学者サンドラ・ニーセンは、「ファッションの犠牲地帯」という言葉を使って、この問題を説明しています。これは、まるで一部の地域が「犠牲」になることで、他の地域が豊かになるような状態を指します。
この現象は、かつての西洋諸国による植民地支配と似ています。過去に、強い国が弱い国から資源を奪い、自分たちの国を豊かにしました。
現代でも、植民地支配の構造は形を変えながら残り、「文化」という形で行われていると指摘されているのです。

ディオールの事例:神聖なものが商品に
2019年のディオール「ソヴァージュ」香水キャンペーンが代表的です。ネイティブアメリカンの儀式用顔料を瓶のデザインに転用したことで、「神聖な文化を観光土産のように扱った」と批判されました。
歴史的権力関係の再生産

この背景には植民地時代からの構図が横たわっています。19世紀、西洋企業がアフリカやアジアの伝統文様を無断で製品化し富を築いた歴史が、現代の「インスピレーション借用」という形で継承されているのです。
また、デザイナーやブランドが多くの利益を得る一方で、文化の源である先住民コミュニティには利益が還元されないという矛盾も問題となっています。
ここで重要なのは、単なる「デザインの真似」ではなく「力関係の再生産」という点です。社会的弱者の文化が「自由に使える素材」と見なされる構造が、現代ビジネスにも根深く残っているのです。
尊厳の侵害:文化的アイデンティティの侵食
【ラオス、モン族の少女たち(1973年撮影)】
伝統的な模様や文様は、単なる装飾品ではありません。それらは、民族の歴史や価値観、自然との関わりを表現する「文化の言語」のようなものです。
マックス・マーラの事例:ラオスのオマ民族の伝統模様をコピー
例えば、ラオスのオマ民族の伝統模様は、彼らの祖先から受け継いだ物語や教えを織り込んでいます。2023年、イタリアのファッションブランド・マックス・マーラが、オマ民族の伝統模様を無断で使用した事件がありました。
オマ民族にとって、これは単なる「デザインの盗用」ではなく、自分たちのアイデンティティの一部が奪われたように感じられたのです。「模様は土地との契約書」と表現されることもあるように、これらの伝統的な模様は単なる見た目の美しさだけでなく、その土地で生きてきた人々の歴史や知恵、自然との約束を表しているのです。
模様は土地との契約書

「模様は土地との契約書」という表現は、先住民族の伝統的な模様や文様が単なる装飾ではなく、その土地や自然との深い結びつきを表していることを意味します。これらの模様は、世代を超えて受け継がれる文化的知識や精神性、自然との調和の象徴です。
つまり、伝統的な模様は、先祖から受け継いだ土地との関係性や責任を視覚的に表現し、文化的アイデンティティを維持する重要な役割を果たしているのです。
AIの発展による新たな問題
現代では、AIによる伝統模様の自動生成技術が発展しています。これは一見便利そうですが、模様に込められた深い意味や文化的背景を理解せずに大量生産することで、その文化の本質が失われてしまう危険性があります。
もし、AIが生成した模様が、本来の意味や背景を無視して使われたら、それはカルチュラル・アプロプリエーションにつながるかもしれません。さらに、デジタル空間では、文化的な情報が簡単にコピーされ、拡散されるため、より深刻な問題となる可能性が懸念されています。
このように、カルチュラル・アプロプリエーションは、単に経済的な問題だけでなく、文化的な尊厳やアイデンティティに関わる問題であることを忘れてはいけません。私たちは、文化の多様性を尊重し、文化的な搾取を防ぐために議論を深め、より意識的な行動を取る必要があるのです。*3)
カルチュラル・アプロプリエーションの線引きはどこなのか

文化の盗用を巡る議論は、時に感情的な対立を生み、明確な線引きを見出すことが困難です。しかし、急速にグローバル化が進み、文化的な交流が不可避になってきた現代において、私たちはどのように異文化と向き合えばよいのでしょうか。
文化的交流における倫理的な境界線
文化の盗用と文化的な交流の境界線は曖昧であり、状況や文脈によって判断が異なります。しかし、倫理的な観点から、いくつかの考慮すべき重要な原則があります。
「平等な交換の精神」
文化的な交流は、一方的な搾取ではなく、相互の尊重と利益に基づくべきです。ベルナルディン・エヴァリストが文化の盗用という概念を否定しているように、文化的な交流や創作活動において、文化的な境界線を引くことは現実的ではありません。
2025年3月、カシミールでのファッションショーをめぐる論争は、この原則の重要性を浮き彫りにしました。インドのファッションデザイナーのShivan & Narresh(シヴァン・アンド・ナレッシュ)は、地元の伝統衣装を現代的に解釈しましたが、一部の地域住民からは「文化の侵略」との批判が上がりました。
この事例は、文化的コラボレーションには共通のビジョンと相互理解が必要であることを示しています。
文化的知的財産権の保護
このような状況の中、文化知的財産権イニシアチブ(CIPRI)の取り組みは、伝統文化の保護と現代デザインの融合を両立させる新たな枠組みを提示しています。以下の、CIPRIが提唱する「3つのC」は、デザイナーと伝統的職人の協働における倫理的指針となっています。
- Consent (同意):職人、先住民、または地域コミュニティからの自由意思による事前の十分な情報に基づく同意を得る
- Credit (クレジット):ソースとなるコミュニティやインスピレーションの源を適切に認識し、謝辞を表す
- Compensation (補償):金銭的、非金銭的、またはその両方の形での適切な補償を行う
創造的対話の促進
Crafting Futures Community Coutureプロジェクトは、異文化間のデザイナー協働を通じて、文化的交流の新たな可能性を探っています。このプロジェクトでは、レンタル可能な共同制作衣服を通じて、文化の融合と継承を実現しています。
現代では、デジタル技術を使って、衣服のデザインや製作過程、着用方法の変化を詳しく記録できます。これにより、実際の衣服だけでなく、その背景にある文化や歴史、物語も一緒に共有することができるようになります。
カルチュラル・アプロプリエーションをめぐる議論は、社会の成長のための痛みの表れとも言えます。このような対話は時に不快や苦痛を伴いますが、多様性を尊重し、創造性を育む社会の実現には避けては通れないプロセスとも考えることができます。
文化的コラボレーションは、公正な社会と世界のバランスを取り戻すための源泉という側面も持っているのです。*4)
カルチュラル・アプロプリエーションとSDGs
【西アフリカのアフリカン・ワックス・プリント】
カルチュラル・アプロプリエーションは、一見するとSDGsとは無関係のように思えるかもしれません。しかし、どちらも「多様性の尊重」と「持続可能な社会の実現」という共通の目標を持っています。
文化の盗用は、特定の文化を軽視し、その価値を矮小化することで、社会の不平等を助長します。これは、SDGsが目指す「誰一人取り残さない」社会の実現を妨げるものです。
しかし、このような問題に関する議論は、SDGsの目標達成において重要な役割を果たします。それは、私たちが多様な文化を尊重し、持続可能な社会を築くための意識を高めるきっかけとなるからです。
SDGs目標4:質の高い教育をみんなに
文化の盗用は、特定の文化に対する誤った認識や偏見を広めることで、教育の質を低下させる可能性があります。例えば、ある文化のシンボルが誤って解釈され、教科書やメディアで広まると、子供たちはその文化に対する誤った知識を身につけてしまうかもしれません。
このことから、文化の盗用に関する議論は、教育現場における文化多様性への理解を深める上で重要です。教師や教育関係者が文化の盗用について学び、それを教育に取り入れることで、子供たちは多様な文化を尊重し、理解する力を養うことができます。
SDGs目標10:人や国の不平等をなくそう
文化の盗用は、歴史的な権力関係を背景に、マジョリティ文化がマイノリティ文化を搾取する構造を生み出すことがあります。これは、SDGs目標10が目指す「不平等の是正」に反するものです。
一方で、文化の盗用に関する議論は、社会における不平等の構造を明らかにし、その解決に向けた取り組みを促進します。企業やデザイナーが文化の盗用について学び、倫理的な配慮に基づいた活動を行うことで、文化的な不平等を是正し、多様な文化が尊重される社会を実現することができます。
SDGs目標12:つくる責任 つかう責任
文化の盗用は、大量生産・大量消費のファッション産業と深く結びついています。ファストファッションブランドが、安価な労働力と素材を用いて、異文化のデザインを模倣することは、倫理的な問題だけでなく、環境破壊にもつながります。
文化の盗用に関する議論は、このような状況を改善し、持続可能なファッションの実現に向けた取り組みを促進します。消費者が倫理的な消費を心がけ、企業が持続可能な生産を行うことで、環境負荷を低減し、文化的な多様性を尊重するファッション産業を築くことができます。
SDGs目標16:平和と公正をすべての人に
文化の盗用は、文化的な対立や紛争の原因となることがあります。特定の文化が軽視されたり、誤って解釈されたりすることで、その文化を持つ人々が不快感や怒りを感じ、社会的な緊張が高まることがあるからです。
つまり、文化の盗用に関する議論は、文化的な対立を解消し、平和な社会の実現につながります。文化的な多様性を尊重し、相互理解を深めることで、異なる文化を持つ人々が共に生きる社会を築くことに貢献するのです。
カルチュラル・アプロプリエーションは、SDGsの目標達成を妨げるだけでなく、解決に向けて取り組むことで、目標達成のための取り組みを促進します。私たちは、文化の盗用に関する議論を通じて、多様な文化を尊重し、持続可能な社会を築くための意識を高め、合意点を探り続ける必要があるのです。*5)
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
【髪を伝統的なジャータースタイルにした2人のサドゥー(ヒンドゥー教の修行僧)】
カルチュアル・アプロプリエーション(文化の盗用)は、異文化間の力の不均衡を背景に、ある文化の要素が別の文化によって無断で、あるいは不適切に利用される現象です。それは単なる模倣ではなく、文化的な搾取や軽視を伴う行為として、近年、グローバル化とSNSの普及により議論が活発化しています。
価値観が多様化し、環境問題や人権問題、サステナビリティへの配慮が求められる「地球管理の試行錯誤」の現代において、カルチュアル・アプロプリエーションは創作活動や契約交渉を複雑化させ、明確な基準のない諸問題への対応を困難にしています。
これは、線引きが非常に難しい問題です。しかし今後、誰かが不当に搾取されることなく、健全な発展を目指すために、法的論点等の整理や行動指針となるガイドラインの策定に取り組む必要があるでしょう。
あなたが今日手にした製品は、その文化の担い手の尊厳を守りながら生まれたものですか? 多様性が豊かさとなる世界の実現には、一人ひとりが「文化の翻訳者」となる意識改革が必要です。
過去の過ちを未来の創造力に変えることは可能です。よりよい未来のために、まずは学び、知識を深めることから始めてみましょう。*6)
<参考・引用文献>
*1)カルチュラル・アプロプリエーションとは?事例や問題点も
文化庁『著作権』
Museum of Fine Arts『Cultural Appreciation and Appropriation of Kimono in Western Fashion and Art』
Fashion Law Journal『Fashion and Cultural Appropriation : Legal and Ethical Considerations』(2024年9月)
BBC『ファッション業界は「文化の盗用」をしているのか?』(2018年11月)
BBC『Cultural appropriation: Why is food such a sensitive subject?』(2019年4月)
BBC『What high fashion is doing about cultural appropriation』(2020年1月)
Cambridge Dictionary『cultural appropriation』
HuffPost News『Valentino Accused Of Cultural Appropriation For Its ‘Africa-Inspired’ Fashion Show It featured less than 10 non-white models on the runway.』(2015年10月)
Te Aro Astanga Yoga『Yoga and Cultural Appropriation — Am I Guilty?』(2023年11月)
佐々木 優『文化盗用理論の検討』(2024年)
家田 崇『ファッションに関連する文化流用と差別表現』(2021年1月)
現代ビジネス『いまファッション業界を揺るがせている「文化の盗用」という大問題』(2022年7月)
日本経済新聞『問われる「文化の盗用」(上)「弱者からの収奪」と批判 創作との線引きが課題に』(2021年7月)
日本経済新聞『問われる「文化の盗用」(下)そこに尊敬と共感はあるか』(2021年7月)
日本経済新聞『炎上相次ぐ「文化の盗用」 リスク避けるためには』(2021年7月)
東洋経済ONLINE『「私は日本人」と語ったアメリカ人歌手が炎上の訳 日本人にはわかりにくい文化の盗用という問題』(2023年2月)
WWDJAPAN『「文化の盗用」問題に切り込む 異文化にインスピレーションを求めるのはタブーなのか?』(2021年2月)
WWDJAPAN『「文化の盗用」って何を盗んでいるの? 考えたい言葉 vol.7』(2021年10月)
*2)カルチュラル・アプロプリエーションの具体事例
法学館憲法研究所『リスペクトか盗用か 民族文化と模倣』(2021年10月)
BBC『コム デ ギャルソン: 白人ファッションモデルのコーンロウウィッグをめぐる論争』(2020年1月)
BBC『ドルチェ&ガッバーナ、人種差別の非難を受け上海ファッションショーを中止』(2018年11月)
BBC『バーガーキングが「人種差別的」な箸広告を削除』(2019年4月)
BBC『H&M、パーカーを着た黒人少年の「人種差別的」画像について謝罪』(2018年1月)
Reuters『アングル:NZのマオリ族、対話型AIによる「植民地化」警戒』(2023年4月)
WWDJAPAN『異文化を取り入れる難しさ』(2022年2月)
日本経済新聞『生成AI時代、マイノリティーが危惧する「文化盗用」』(2023年10月)
日本経済新聞『ハーバード大学長辞任、盗用疑惑や反ユダヤ発言対応で』(2024年1月)
AERA『KIMONO「文化の盗用」理解できない日本人 背景にある“名誉白人感”とは?』(2019年)
Newsweek『Mrs. GREEN APPLEのMV「コロンブス」炎上事件を再発させない方法』(2024年6月)
EATER NEW YORK『New NYC Chinese Restaurant Draws Swift Backlash to Racist Language [Updated]』(2019年4月)
*3)カルチュラル・アプロプリエーション問題の根底
BBC『What defines cultural appropriation?』(2022年5月)
BBC『Why black TikTok creators have gone on strike』(2021年7月)
BBC『Ralph Lauren apologises after Mexico indigenous ‘plagiarism’ claim』(2022年10月)
Sandra Niessen『Fashion, its Sacrifice Zone, and Sustainability』(2020年8月)
Laotiantimes『Max Mara vs Laos’ Oma Ethnic Group: Fashion Chain Facing Claims of Textile Plagiarism, Design Theft』(2019年4月)
HuffPost News『Dior Pulls Native American-Themed ‘Sauvage’ Ad After Backlash For Racism』(2019年8月)
*4)カルチュラル・アプロプリエーションの線引きはどこなのか
経済産業省『海外取引と多様な文化・価値観の尊重』(2022年12月)
BBC『エシカルビューティーブームの裏側』(2022年3月)
BBC『Creativity or cultural invasion? A fashion show sparks a row in Kashmir』(2025年3月)
THE VOICE OF FASHION『Shivan & Narresh in Gulmarg: Case Against Badgering Fashion』(2025年3月)
VOGUE『「文化の盗用(Cultural Appropriation)」、その不完全な用語が担うものとは。【コトバから考える社会とこれから】』(2020年8月)
小林 瑠音『英国コミュニティ・アートの変遷とアーツカウンシルの政策方針に関する研究— 1960年代から1980年代を中心に —』(2025年3月)
VOGUE『What Is Cultural Appropriation? Why It’s Problematic and How to Avoid It』(2024年1月)
VOGUE『Cultural Appropriation of Islam Is a Focus of ‘Stealing My Religion’』(2022年9月)
VOGUE『P1Harmony’s Keeho Speaks Up About Cultural Appropriation in K-pop』(2022年6月)
*5)カルチュラル・アプロプリエーションとSDGs
BBC『エシカルビューティーブームの裏側』(2022年3月)
Culture Action Europe『Things to follow: cultural policy in 2025』(2025年1月)
National History Day『Performing Perspectives: Cultural Appropriation』
OXFORD ACADEMIC『White Negroes: When Cornrows Were in Vogue … and Other Thoughts on Cultural Appropriation』(2020年12月)
*6)まとめ
日本経済新聞『[社説]ファッション界は法を強みに』(2024年7月)
VOGUE『Is Fashion Finally Turning the Page on Cultural Appropriation?』(2023年8月)
Fashion Law Journal『Fashion and Cultural Appropriation : Legal and Ethical Considerations』(2024年9月)
Fine Arts Museums of San Francisco『Appropriation, Appreciation + Commodification』(2024年2月)
NIKKEI Asia『No doubt, Gwen Stefani is not Japanese even if she says she is』(2023年1月)
Yahoo! JAPAN SDGs『日本文化が海外で盗用されたら? 文化の盗用の本質を小川さやかさんに聞く』(2024年3月)
この記事を書いた人
松本 淳和 ライター
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。