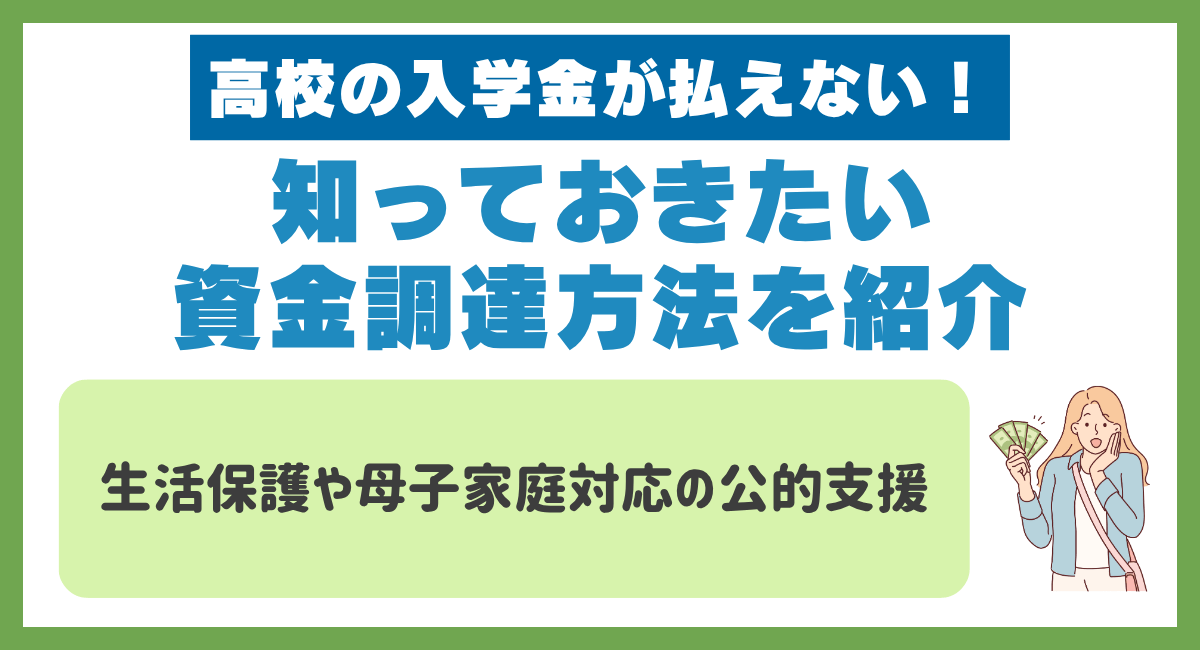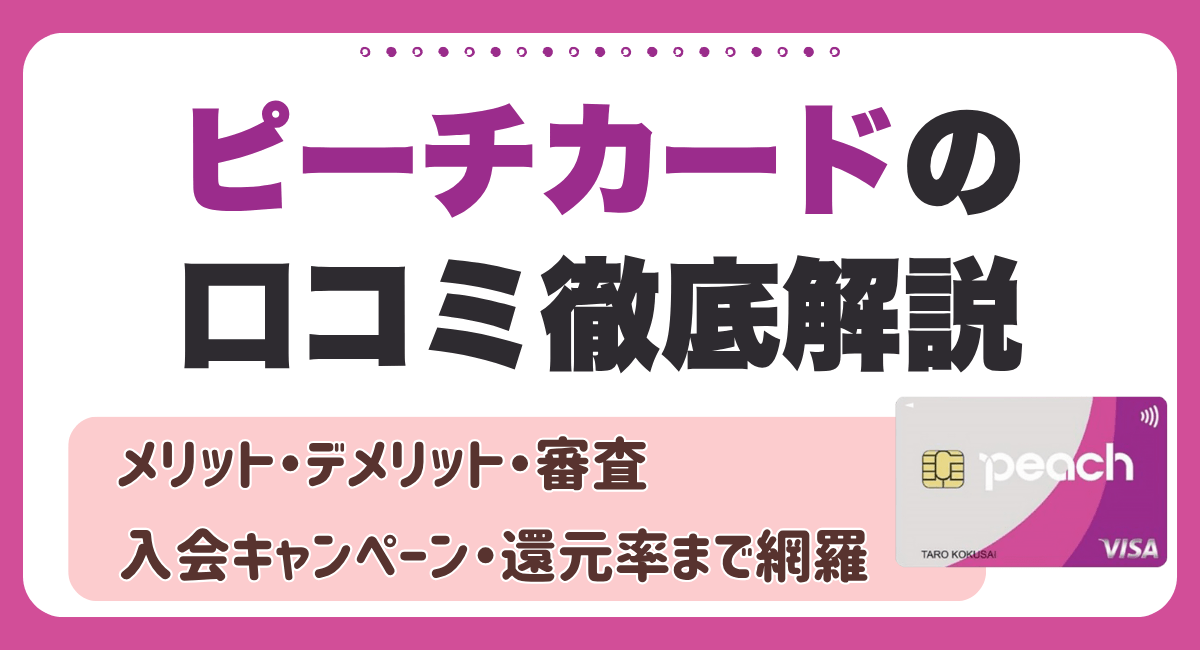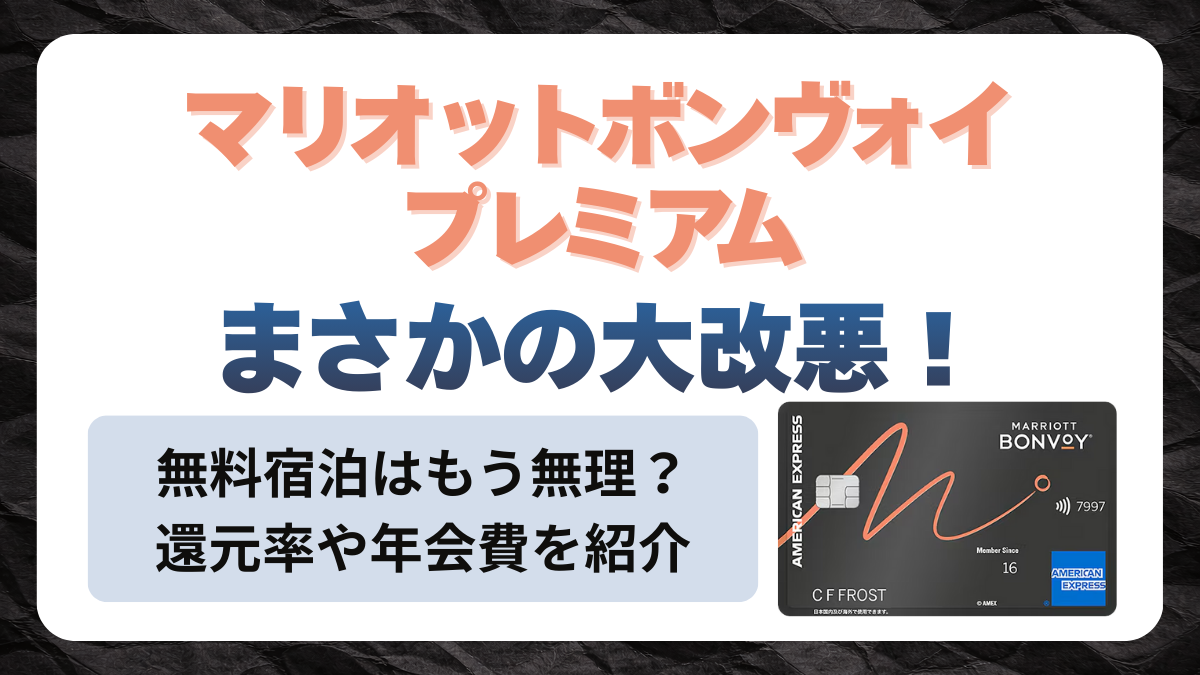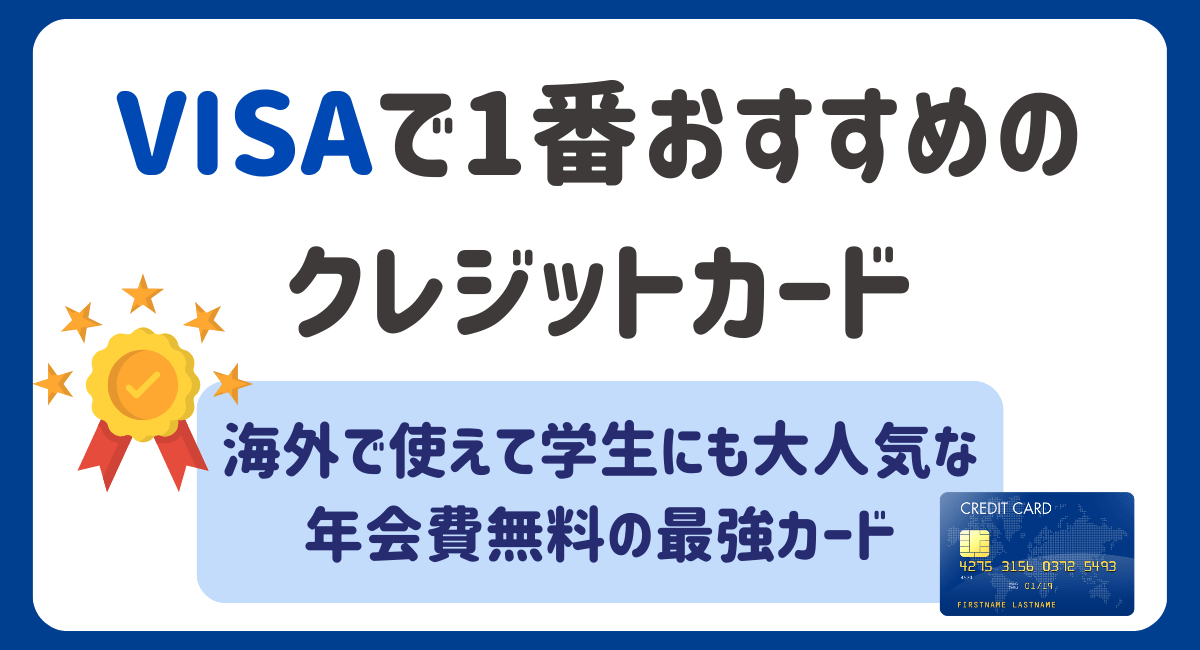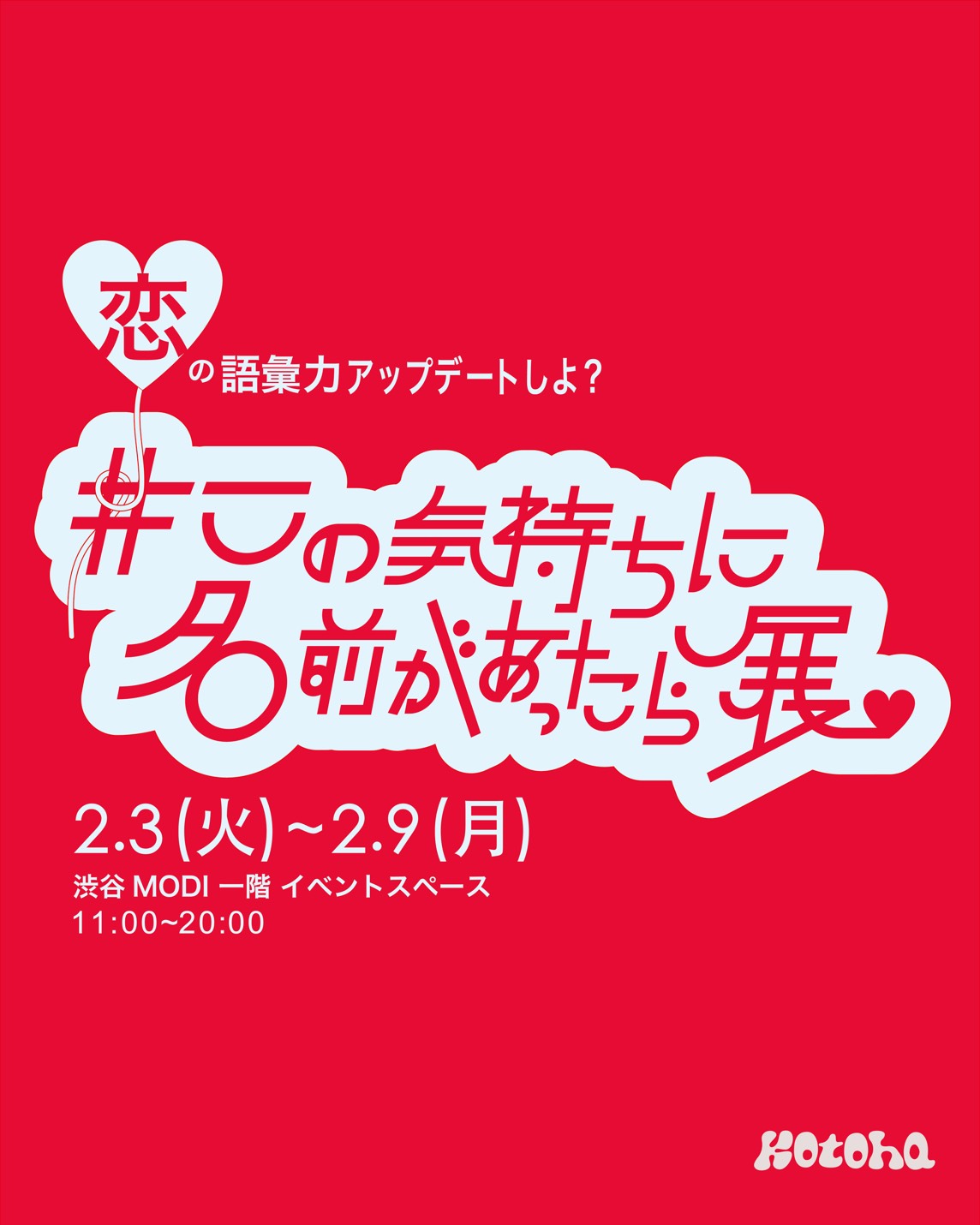現在、私たちの生活では現金を使わずに買い物をする機会が増えています。皆さんの中にも現金を持たず、キャッシュレスで買い物や支払いをしている人も多いでしょう。
そんな中、世界各国で現在活発に議論されているのが「デジタル通貨」です。従来のお金のあり方をも変えてしまうとも言われているデジタル通貨ですが、その実態はまだ一般的に広く知られてはいません。今後の経済を左右するかもしれないデジタル通貨とは、どのようなものなのでしょうか。
目次
デジタル通貨とは

デジタル通貨とは、紙幣や硬貨のような現金ではなく、デジタルデータとして発行され、使われるお金のことです。
デジタル通貨は、端末やオンライン上での数字データで物理的には存在しませんが、日常の決済や送金などで現金と同じ価値を持ち、実際の運用ではスマホアプリやICカード、その他端末などで利用されることが想定されています。
現在世界中で議論され、検証や実験が進められているデジタル通貨は、それぞれの国の中央銀行が正式な法定通貨として発行することを想定しているため、中央銀行デジタル通貨(Central Bank Digital Currency=CBDC)と呼ばれます。そのため本記事でも、この中央銀行デジタル通貨をデジタル通貨と呼称します。
デジタル通貨の条件

現在のところ、デジタル通貨に関する明確な定義は定まっていません。しかし、デジタル通貨が法定通貨としての役割を果たすためには、以下のような2つの条件と3つの機能が必要になります。
2つの条件
- 強制通用力=支払手段として法的に有効であると国が保証すること
- 一般受容性=支払手段が誰にでも受け取ってもらえることであり、通貨が広く流通するために重要
3つの機能
- 交換(支払)機能=通貨を媒介にして取引機能を節約し、経済取引を円滑にする
- 価値尺度機能=あらゆる物の価値を通貨の尺度で表すことができる
- 価値保存(貯蔵)機能=通貨を将来に備えて蓄えておける
他のキャッシュレス決済との違いは?

とはいえ、現金ではなくデータで買い物や送金をするのなら、すでに私たちが日常的に使っているキャッシュレス決済はデジタル通貨ではないのでしょうか。また、一時期世界中で話題になったビットコインなどの暗号通貨・暗号資産は、通貨の新たな形ではないのでしょうか。
そんなさまざまなキャッシュレス決済手段について、それぞれ特徴を見ていきましょう。
クレジットカード/デビットカード
現在最も多く使われている決済手段がクレジットカードです。
基本的には個人の支払能力への信用を担保し、紐付けされた銀行口座から後払いで引き落とされ、デビットカードは支払によって即座に銀行口座から引き落とされます。
いずれも銀行口座の預金は中央銀行から発行された法定通貨が元になっています。そのため、クレジットカードやデビットカードそれ自体は法定通貨そのものではなく、単なる代替手段に過ぎません。
電子マネー
今や私たちの生活にすっかり浸透した新しい決済手段が電子マネーです。
電子マネーは、
- ICカード系=SuicaやPASMO、WAONなど
- QRコード決済系=PayPayなど二次元コードを使って決済
の2種類に大別されていますが、どちらもあらかじめ現金や口座からチャージして使うことが前提であり、やはり通貨そのものではない代替手段としての位置付けとなります。
仮想通貨
仮想通貨は、ブロックチェーンなどの分散型台帳技術を基盤としてインターネット上で民間が発行する暗号資産です。
つまり、仮想通貨は法定通貨ですらなく、国や中央銀行の管理下にもありません。
またその時々の需給などによって価値の変動が大きく、支払いよりも投機目的で使われることが多いのが特徴です。
これらの特徴を踏まえて、それぞれの決済手段を通貨の条件と照らし合わせると、どれも強制通用力や一般受容性を備えているとは言えません。それぞれの支払い手段は、加盟店や導入店舗でなければ使えないためです。
機能面の条件にしても
- クレジットカード:決済手段自体は価値尺度ではない/価値保存機能はない
- 電子マネー:決済手段自体は価値尺度ではない(通貨の代替)
- 仮想通貨:価値変動が大きく、支払い・価値尺度・保存の3つの機能を満たすには不十分
として、やはりどれもデジタル通貨としての条件は満たしていません。
一方の中央銀行デジタル通貨は、国が法定通貨として発行するため、現金同様の無制限の強制通用力、決済サービスの種類に関係なくどこでも通用する一般受容性、3つの機能を満たす決済手段を備えるとされています。
デジタル通貨の種類

ひとくちにデジタル通貨と言ってもいくつかの方法があり、どのような形で発行するかについてはいまだ議論が続いています。一般的に、中央銀行デジタル通貨を発行する際に想定しているのは
- ホールセール型:金融機関など限られたユーザーの大口取引に使う
- リテール型:個人や一般企業を含む幅広い利用を想定するもの
の2つがあり、それぞれに口座型とトークン型/直接型と間接型という異なる発行形態に分かれるとされています。
口座型とトークン型
口座型とは、利用者がデジタル通貨専用の口座を開設してその口座にデジタル通貨を入金したり引き落としたりする形で、通常の銀行口座と同じような形態です。
口座の記録を書き換えることで価値が動くのでオンラインでの利用が前提となり、遠くの相手とも取引が可能になります。
対するトークン型は、トークンと呼ばれる権利や価値をデータ化したものを、スマホアプリやICカードなどの媒体に記録してデジタル通貨を発行するものです。SuicaやPASMOなどの鉄道系電子マネーと同じ仕組みと思えばいいでしょう。
オフラインでも利用することができ、やり取りには物理的な近さが前提となります。
実際の運用ではどちらか一方だけではなく、両方を併用するタイプもあります。
直接型と間接型
口座型とトークン型は、さらにそれぞれ直接型と間接型という2つの形態に分けられます。
直接型は利用者が中央銀行に直接口座を開設してデジタル通貨の発行を受ける方法です。
ただし
- 中央銀行が利用者個々のニーズに直接対応するのは困難なこと
- 中央銀行という公的機関が国民のお金の動きを直接把握できてしまうこと
という理由から、直接型は採用されにくいとされます。
一方間接型は、利用者が仲介機関(民間銀行・民間決済サービス業者など)にデジタル通貨口座を開設し、その口座で中央銀行が発行したデジタル通貨を受け取る方法です。
将来的にデジタル通貨が発行される場合は、日本を始めとする多くの国では口座型/間接型を採用すると想定されています。
デジタル通貨が注目されている背景
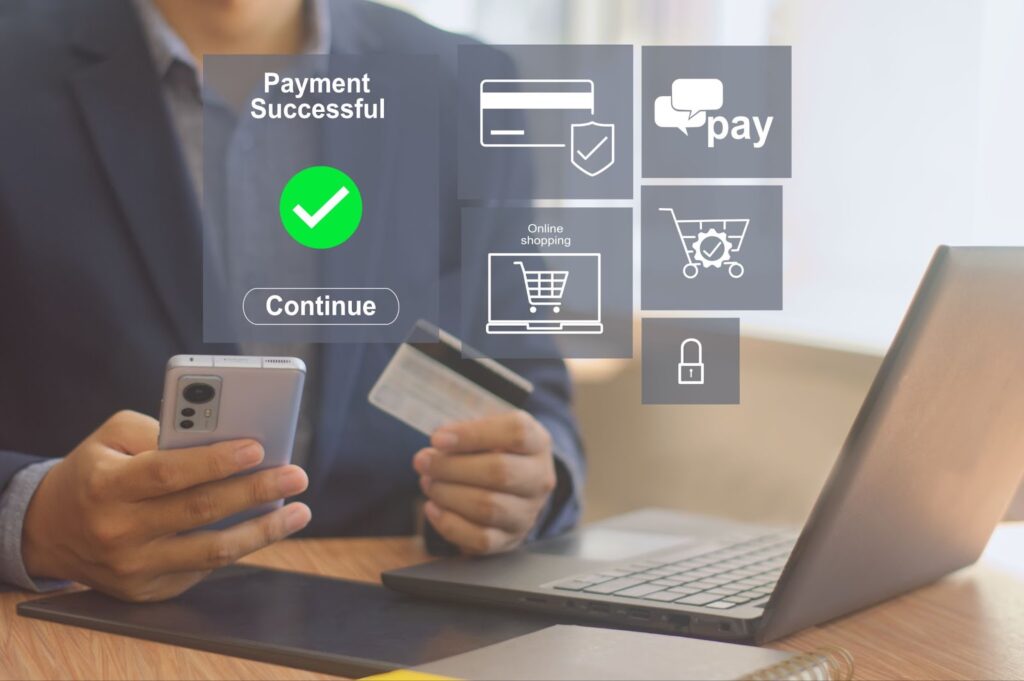
ではなぜ今、デジタル通貨が世界各国で導入を検討されるようになっているのでしょうか。そこには、現在社会におけるお金と情報技術をめぐるさまざまな出来事が関係しています。
背景①デジタル決済の浸透
最も大きいのが、目覚ましい情報・通信技術の発達を背景にしたキャッシュレス決済、特にデジタル決済手段の浸透です。
主なものだけでも
- ICカードの発明によるキャッシュレス決済の普及
- スマートフォンの爆発的普及によるモバイル決済の拡大
- ブロックチェーン・分散型台帳技術などの登場
などのさまざまな技術によって、従来のクレジットカードやデビットカード、プリペイドカード以外にも現金を必要としない決済方法が普及してきました。
こうした状況を踏まえ、世界各国の中央銀行でも、これらの新しい情報技術を活用した便利で効率的な通貨が必要なのではないか、という提言がなされるようになってきたのです。
背景②現金の減少への危機感
デジタル通貨の必要性が唱えられた背景には、一部の国での現金の減少も関連しています。
スウェーデンなど北欧諸国では、民間のモバイル決済が浸透するにつれ、現金を利用できる店舗が減っています。その結果、現金を必要とする一部の人々がお金を入手することが難しくなる可能性が指摘され始めました。
それに伴い、中央銀行による信用度の高い支払手段をより多くの人々に提供すべき、という議論が高まりました。その一環として検討されたのがデジタル通貨の導入です。
背景③金融包摂の推進

それ以外の要因としてあげられるのは、金融包摂を推進する手段としてデジタル通貨の役割が重要であるという考え方です。
金融包摂(financial inclusion)とは、すべての人々が経済的に不安定な状況を軽減するために必要な金融サービスを受けられることです。
世界では、いまだに約25億人もの人が銀行口座の保有などの基本的な金融サービスを受けられていません。しかし、国がデジタル通貨を発行すれば、たとえ銀行口座を持てなくても、トークンを利用した携帯電話でのモバイル決済や、ICカードでの通貨利用が可能になります。デジタル通貨は、すべての人々に平等な通貨をより簡単に提供するという意味でもその必要性が問われているといえます。
デジタル通貨のメリット

デジタル通貨が発行されることで、従来の現金にはないさまざまなメリットが期待されます。同時に、現在使われている民間のデジタル決済方法が抱える弱点も、デジタル通貨によって補うことができます。
メリット①利便性向上と決済効率の改善
デジタル通貨の一番のメリットは、お店や決済サービスの種類を問わずどこでも使えるため、利便性と効率が大きく向上することです。
キャッシュレス決済の便利さはもはや説明不要ですが、民間の決済方法は、そのサービスに加盟して決済システムを導入している所でしか使えません。〇〇Payで支払おうと思っていたのにお店側が対応しておらず、手持ちの現金も足りずに支払えなかった…という経験をした方も少なくないでしょう。
デジタル通貨は国が発行する法定通貨なので、法的位置づけは現金と同じです。利用環境が整っていることが前提ですが、民間サービスの違いに左右されることはありません。デジタル通貨の導入は、手軽さと効率性に現金の安心感がプラスされます。
メリット②現金発行・輸送・保管のコスト削減
デジタル通貨のもうひとつのメリットは、現金の運用コストを削減できることです。
現金には
- 紙幣・硬貨を製造する費用
- 運搬や輸送にかかる費用
- 保管とその警備にかかる費用
といった多くのコストがかかります。
しかし通貨がデジタルで発行されれば、これらの費用は必要ありません。
もちろんデジタル通貨にも新しい運用コストがかかる可能性がありますが、現物としてのお金の管理コスト削減は発行側にとっても大きなメリットとなるでしょう。
メリット③信頼性が高い
デジタル通貨は中央銀行つまり日本銀行が発行するので、民間事業者が行う決済サービスや仮想通貨などに比べリスクがなく、法定通貨として信頼性が高いことも大きなメリットになります。
民間の決済サービスを提供する発行事業者は経営状況によっては倒産・破綻のリスクがあります。対して、中央銀行は自ら金融システム全体のお金の流通量をコントロールできるため、日銀が破綻することはありません。こうした中央銀行の安全性の高さも、デジタル通貨の信頼性を裏付けるものになっています。
デジタル通貨のデメリット・課題

一方、デジタル通貨にはデジタル特有のデメリットや問題も指摘されています。各国がデジタル通貨の実用化に慎重なのも、これらの問題をどのようにして解決するかに頭を悩ませているからです。
デメリット・課題①セキュリティ対策
デジタルならではの課題としてあげられるのはセキュリティ対策です。デジタル通貨はデータとして取り扱われるため、常に
- サイバー攻撃/不正利用/偽造/二重利用
などのデータの改ざんへの脅威にさらされます。そして実際に運用システムがこれらの被害を被るようなことがあれば、デジタル通貨だけではなく、国そのものへの信用をも揺るがすことになります。デジタル通貨のシステムを盤石なものにするためには、暗号化や電子署名など最新の技術を駆使したセキュリティ対策が必要です。
デメリット・課題②「いつでも・どこでも」への壁
もうひとつの通貨として「いつでも・どこでも」使えることを目指すデジタル通貨ですが、その実現には多くのハードルが待ち構えています。
インフラ途絶
大きな懸念材料となるのが、災害や停電、回線トラブルなどのインフラ途絶によってデジタル通貨が使えなくなることです。こうした状況に対処するため、少額決済に限っては電力を使わないタッチ式ICカードの導入も視野に入れていますが、読み取り用の端末が利用できなくなる可能性もあります。
利用環境の整備
デジタル通貨を現金並みに利用できるようにするためには、対応する読取端末などの設備が必要となります。しかし、全国すべての店舗に対応機器を導入するのはとても困難です。
これらの店舗に対する設備費用を国がどこまで負担するのかという議論も、デジタル通貨普及にむけた課題となります。
デメリット・課題③プライバシー対策

デジタル通貨では、匿名性の確保とプライバシー対策が新たな課題となります。
完全な匿名性がある現金と違い、デジタル通貨はデータの流れを中央銀行が把握することが可能となり、個人の経済活動へのプライバシー侵害につながりかねません。
特に日本よりプライバシー対策への要望が強い欧州では、オンラインとオフラインの両方で利用でき、オフライン決済は現金と同レベルのプライバシー保護がなされる予定です。
ただし、デジタル通貨の匿名性が高すぎると、脱税やマネーロンダリングなどの犯罪を助長する危険もあるため、デジタル預金残高や決済額に上限を設ける方法も検討されています。
デメリット・課題④民間決済サービスとの棲み分け
デジタル通貨の導入は、すでに存在する民間デジタル決済サービスとの棲み分けも課題となります。
特にデジタル通貨は公共インフラなので、取扱店舗への手数料を課さない、あるいは極めて少なくすることが予想されており、民間決済サービスを駆逐し民業圧迫になってしまうのではないかと懸念されています。
安全で決済方法を問わないデジタル通貨と、利便性で勝負する民間決済サービスの両立は、実現に向けた非常に難しい問題となっていくでしょう。
デメリット・課題⑤経済への影響
デジタル通貨の流通による経済全体への影響も検討されている問題です。
特に銀行への信用不安が起きた場合、銀行預金からデジタル通貨へと大量の預金流出が起きることも想定されます。そうすると銀行が貸出に回せる資金が減ってしまうため、経済に悪影響を及ぼしかねません。これを避けるためには、デジタル通貨の保有に上限を設けるなどの措置も検討されています。
デジタル通貨の今後の見通し
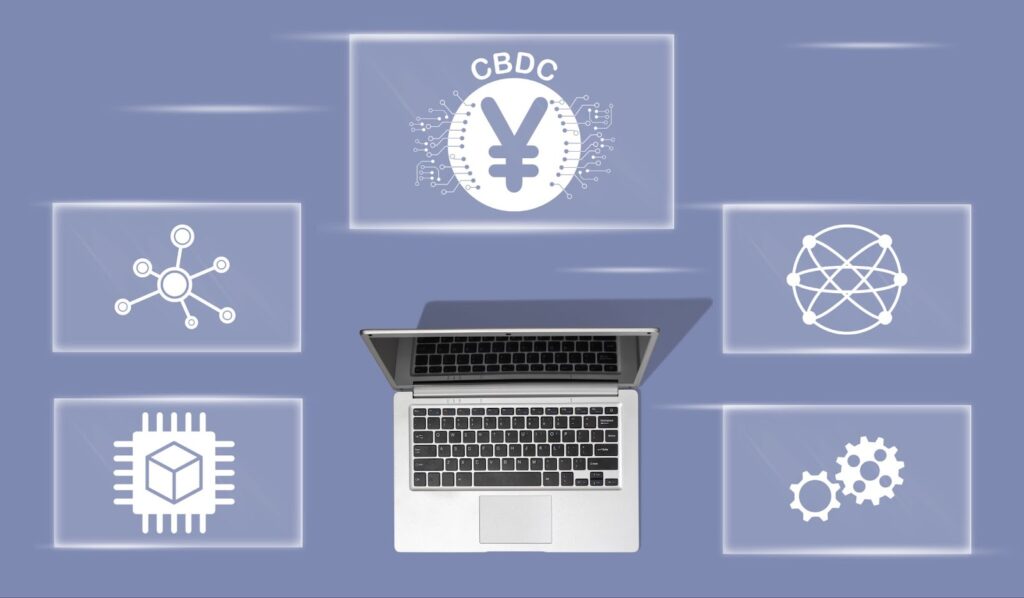
将来的な実用化が期待されるデジタル通貨は、各国で検証や実証実験が行われており、実用化に向けた動きは着実に進んでいます。
しかし、実際の発行に当たってはどの国も慎重な姿勢を崩しておらず、国際的な機運は低迷気味です。
EU(デジタルユーロ)
EUではECB(欧州中央銀行)が早くからデジタル通貨に関する研究を進めており、2023年11月からはデジタルユーロ導入に向けた2年間の準備段階に入っています。
2024年2月には欧州議会で審議が始まるなど政治的な合意形成プロセスに入っていますが、ECBの政策理事会が最終決定を下して実際に発行に至るのは早くとも2028年頃とも言われています。
アメリカ(デジタルドル)
アメリカでもデジタル通貨の研究は行われており、技術的には最も頑強なデジタルドルを構築できるとされています。ただし、ドルは基軸通貨であるため、導入の成否は世界中に大きな影響を及ぼします。そうした理由もあり、FRB(連邦制度理事会)はデジタルドルの導入には慎重な姿勢を取り続けてきました。
そして、かねてから中央銀行デジタル通貨に反対していたトランプ大統領は、就任直後の2025年1月に早速デジタル通貨の発行を禁止する大統領令に署名しました。アメリカにおけるデジタル通貨発行の動きは、現時点では完全に止められたと言っていいでしょう。
中国(デジタル人民元)
国によるデジタル通貨発行で最も先を進んでいるのは中国です。2022年の北京冬季五輪で行われたデジタル人民元の実証実験はその後全土へと広がり、17省26都市で累計7兆元(2024年6月まで)にも上る取引が行われています。
ただし、中国当局は正式な法定通貨としての導入時期を現時点でも公表していません。中国ではAlipayとWeChatPayの2大民間決済サービスが浸透しきっており、当局がこの2つとどう棲み分けていくのか、あるいは介入によって吸収するのかも注視されています。
日本(デジタル円?)
日本でも、現時点で日本銀行はデジタル通貨を発行する計画はないとしており、他の国と同様、中央銀行デジタル通貨、いわゆるデジタル円の導入には慎重です。
ただし、実際にはデジタル円の発行を視野に入れた、中央銀行デジタル通貨の研究や実証実験には積極的に取り組んでいます。
具体的には
- プロジェクト・ステラ=ECBと共同での分散型台帳技術に関する調査
- 民間事業者と議論・検討を行う場としてCBDCフォーラムを設置
などの技術的・制度的な検証や実験を行ってきました。
さらに今年(2025年)の夏には、民間企業主導による擬似デジタル円の店舗実験も予定されています。日銀は国際的な動向、特に中国のデジタル人民元の動きを警戒しながら、事態の急変に備えて民間の取り組みをサポートしながら導入に備える意向です。
デジタル通貨に関してよくある疑問

デジタル通貨についての世間の認知度はまだ高くないことから、さまざまな疑問や、事実に基づかない憶測も少なくありません。そのいくつかを見ていきましょう。
投資にも使える?
仮想通貨と違い、デジタル通貨は投資対象としての想定はされていません。
その理由としては、
- 政府と日本銀行は現時点でデジタル通貨の発行を予定していないこと
- 中央銀行デジタル通貨には利子をつけない方向であること
などが挙げられます。
にもかかわらず「中央銀行デジタル通貨の売買で利息がつく」など虚偽の投資話によるトラブルが複数報告されており、金融庁では冷静な対応や相談の呼びかけなどの注意喚起に努めています。
中央銀行デジタル通貨(CBDC)の売買に関する勧誘にご注意ください|金融庁
現金がなくなる?

中央銀行がデジタル通貨を発行するようになると、将来的に現金が廃止されてしまうのではないかという声も一部で聞かれます。
しかし、実際に現金がなくなる可能性は少ないと言っていいでしょう。日本は現金への信頼が高いこともありますが、それ以外にも
- 現金には完全な匿名性があり、利用履歴を把握されることがない
- 自然災害の多い日本では被災時でも現金が使える
- スマホなど新しい決済手段に不慣れな高齢者などへの配慮
といった理由があるため、将来デジタル通貨が発行されたとしても、政府は現金との相互補完としての位置付けが基本であるとしています。これは日本だけでなく、他の国でも同様の方針です。
DCJPYって何?
2024年8月に、DCJPYというデジタル通貨の商用サービスが始まったと報道されました。
このDCJPYとは、ディーカレットDCPという会社がプラットフォームを提供し、GMOあおぞらネット銀行が発行する民間デジタル通貨です。
DCJPYは法定通貨を裏付けに価格変動を抑えるよう設計され、ブロックチェーンを基盤に発行されるステープルコインと呼ばれるデジタル通貨の一種です。法定通貨ではないため強制通用力や一般受容性はありません。
DCJPYは中央銀行デジタル通貨が発行された場合には連動も視野に入れており、将来的な普及には複数の金融機関との連携や、参加する企業の増加がカギとなっています。
デジタル通貨を導入している国は?

主要各国がいまだデジタル通貨の導入に慎重である一方、すでにデジタル通貨が導入されている国もあります。2025年の時点でデジタル通貨を導入している国は以下の通りです。
- バハマ:2020年に導入/保有率は人口の3割、残高は現金流通高の1%未満
- ジャマイカ:2022年に導入/残高は現金流通高の約1%
- ナイジェリア:2021年に導入/民間決済手段の浸透で利用は低迷
と、いずれの国もあまり利用されているとは言えません。
またカンボジアは、2010年にバコンと呼ばれる中央銀行のデジタル通貨を発行していますが、実際は参加機関(民間銀行)の債務で成り立っています。したがってバコンは中央銀行デジタル通貨ではなく、決済システムとするのが妥当です。
これらの国々が主要先進国と異なるのは、デジタル通貨が
- 銀行口座を持たない国民への金融包摂を進めるため
- 米ドルへの依存から脱却し自国通貨の利用促進を図る
という目的で導入されている点です。したがって、日本がデジタル通貨を導入するにあたってあまり参考にすることはできません。
デジタル通貨とSDGs

デジタル通貨の導入は、金融サービスへのアクセスという面でSDGs(持続可能な開発目標)の達成とも関連してきます。
特に関連の強い目標としては、
- 目標1「貧困をなくそう」
- 目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」
の2つがあげられます。
中でも目標1の「貧困をなくそう」を実現するためには、世界中のすべての人への金融包摂が大事です。デジタル通貨による支払いサービスの提供は、銀行口座を持てず、経済的圧力に直面する人々にもビジネスや教育に投資できる機会をもたらし、貧困からの脱出にもつながります。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ

現在もさまざまな検証や実験が続き、実用化が目前とされるデジタル通貨。
しかし、ひとたび導入された時の影響も大きいことから、どの主要国も最初の一歩を踏み出せていないのが現状です。さまざまな可能性と不安を孕むデジタル通貨が、私たちの生活をどのように変えていくのか、その答えが見れるのはもう少し先のことになりそうです。
参考文献・資料
図解ポケット 中央銀行デジタル通貨(CBDC)がよくわかる本:下田知行 著/秀和システム,2024年.
情報技術革新・データ革命と中央銀行デジタル通貨 日本銀行ワーキングペーパーシリーズ
中央銀行デジタル通貨とは何ですか? : 日本銀行 Bank of Japan
中央銀行デジタル通貨(CBDC)のメリット:利用者コストから見た決済手段の比較 – wisdom|NEC
金融包摂の鍵となるFinTech|野村総合研究所
日本初のデジタル通貨が本格始動、その商用サービスが秘めた可能性 | WIRED.jp
日銀、デジタル円は黒子役 JCBなど「店舗実験案」|日本経済新聞:2025年3月15日
持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けて:金融包摂の役割 CGAP, 2016.
この記事を書いた人
shishido ライター
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。