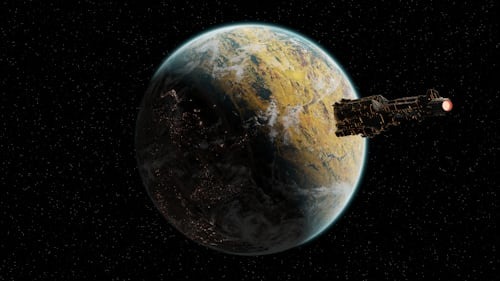1958年、東京タワーが真新しい姿を街に現した頃、日本は未曾有の経済発展期へと踏み出していました。戦後の混乱から立ち直りつつあった国民の目に映ったのは、変わりゆく都市の風景と次々と登場する新しい文化の数々です。
この時代、日本の財政は「神武」「岩戸」「いざなぎ」など複数の好景気に恵まれ、東京オリンピックや大阪万博の開催、東海道新幹線の開通といった大事業が実現しました。石炭から石油への転換、最新技術の積極導入、政府の経済政策などが成長を支え、国民の生活水準は飛躍的に向上しました。
家庭では冷蔵庫・カラーテレビ・自動車といった耐久消費財が広まり、食事や余暇の楽しみ方も多様化。しかし急成長の陰で公害問題も発生しました。
石油危機と国際通貨制度の変化により終わりを告げたこの高度経済成長について、わかりやすく解説します。
目次
高度経済成長とは
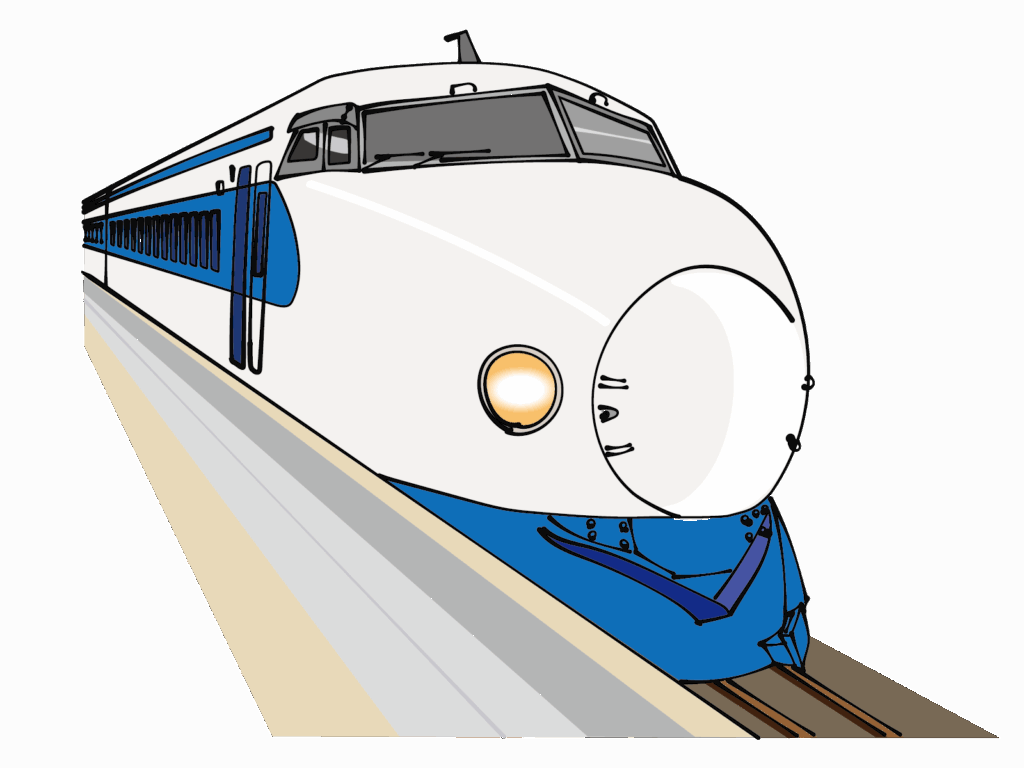
高度経済成長とは、日本が1950年代中盤から1970年代初頭にかけて、年平均約10%の実質経済成長率を記録し、急激に経済発展と国民生活の向上を達成した時代のことです。*1)この時期、経済は持続的に拡大し、国民生活の水準が大きく上昇しました。
オリンピックや大阪万博が開催された
高度経済成長期の日本において、1964年の東京オリンピックと1970年の大阪万博は国際的な重要行事として開催されました。東京オリンピックはアジア初の夏季競技会として、戦後の復興と先進国としての地位を世界に示す機会となりました。*1)
一方、大阪万博は、日本の技術や文化の先進性を世界に発信する場となり、「太陽の塔」などの象徴的な作品も登場しました。この催しは、産業発展と経済成長の到達点を示す出来事として、多くの来場者を集めました。*1)
これら二つの国際的イベントは、当時の日本人の誇りとなり、社会と経済の発展に大きな影響を与えました。
東海道新幹線が開通した
高度経済成長期(1955年頃~1973年頃)には、日本の経済発展を支えるために大規模なインフラ整備が進められました。特に1964年の東京オリンピックに向けて、首都圏を中心に高速道路、鉄道、空港などの基盤が急速に整備され、その後全国に波及しました。
具体的な整備例としては、世界初の高速鉄道である「東海道新幹線」が1964年10月に開業しました。これは東京と大阪を結び、移動時間を大幅に短縮、産業の活性化と経済の一体化を促進しました。*2)
また、東京モノレールや首都高速道路、東京国際空港の拡張も行われ、これらのインフラは「オリンピック景気」と呼ばれる経済の好循環を生み出す契機となりました。
高度経済成長の流れ

はじめに、高度経済成長全体の流れを年表形式で整理します。
| 年代 | できごと | 内容 |
| 1954~55年ごろ | 高度経済成長の始まり | - |
| 1955~57年 | 神武景気 | 戦前の水準を回復「もはや戦後ではない」 |
| 1958~61年 | 岩戸景気 | 輸出が好調 |
| 1960年 | 所得倍増計画 | 池田内閣のスローガン |
| 1963~64年 | オリンピック景気 | 東京オリンピックに伴う公共投資の増加 |
| 1966~70年 | いざなぎ景気 | 重工業の成長所得倍増の達成 |
| 1972年 | 沖縄返還 | 沖縄県が日本に復帰 |
| 1973年 | 第一次オイルショック | 高度経済成長の終わり |
このように、高度経済成長期には4度もの好景気があったことがわかります。以下で、神武景気・岩戸景気・オリンピック景気・いざなぎ景気について解説します。
神武景気
神武景気とは、1955年から始まった日本経済の好景気のことです。この名前は、有史以来最も良い経済状況という意味で、日本の初代天皇の名前から付けられました。
この好況は、世界的な経済回復を背景にした輸出増加や米の豊作などによる「数量景気」から始まり、やがて物価上昇を伴う「価格景気」へと変化しました。*3)
この時期の民間企業による設備投資は、戦後最大の伸び率を記録しました。また、テレビや洗濯機、冷蔵庫などの家電製品が一般家庭に普及し始める契機となり、大量消費社会への第一歩となりました。しかし、1957年後半からは「なべ底不況」と呼ばれる落ち込みへと転じていきました。
岩戸景気
岩戸景気は、1958年7月から1961年12月まで続いた日本の好況期で、第二次世界大戦後では「いざなぎ景気」や「平成景気」に次ぐ第3位の長さ(42ヶ月間)を記録しました。この名称は、それまでの「神武景気」を上回る規模だったことから、天照大神が隠れた「天の岩戸」の故事にちなんで付けられました。
この時期は技術の進歩が著しく、企業の設備投資が次の投資を促すという好循環が生まれました。1959年には皇太子(現上皇)の結婚を契機に白黒テレビの需要が急増し、「三種の神器」と呼ばれたテレビ、冷蔵庫、洗濯機といった家電製品が一般家庭に広く普及していきました。
さらに1960年12月には「国民所得倍増計画」が発表され、日本は本格的な経済成長の時代へと突入しました。この景気は、戦後日本の経済発展における重要な転換点となったのです。
オリンピック景気
オリンピック景気とは、1962年11月から1964年10月まで続いた日本の好況期で、東京オリンピック開催に向けた様々な準備活動が原動力となった経済現象です。*4)
この時期には、東海道新幹線や首都高速道路、東京モノレールといった交通網の整備が急速に進められました。また、国立競技場や日本武道館などの競技施設、多くの宿泊施設も新たに建設されました。これらの大規模な建設事業は、建設業界やその関連産業に大きな活気をもたらし、多くの雇用を生み出して国民の収入増加につながりました。*4)
さらに、大会をテレビで見るためのカラーテレビの普及が進み、クーラーなど家電製品の需要が拡大しました。観光や交通などのサービス分野も活性化し、経済全体が盛り上がりました。
いざなぎ景気
いざなぎ景気は、1965年11月から1970年7月まで続いた日本の長期的な好況期です。57ヶ月にわたる成長局面は、それまでの「岩戸景気」の42ヶ月を上回る記録となりました。この名称は、さらに古い日本神話の国づくりの神様から取られています。*5)
この時期、企業の設備投資が日本経済を大きく牽引し、約5年間で国全体の生産額(名目国民総生産)は2倍以上に膨らみました。1968年には西ドイツを追い抜き、資本主義圏では米国に次ぐ経済大国となりました。*5)
また、消費面でも大きな変化があり、「3C」と呼ばれた自動車、カラーテレビ、冷房機器が一般家庭に急速に広まりました。これらの耐久消費財の普及は、日本人の生活様式を大きく変え、豊かさを実感させるものとなりました。この好況期は、戦後日本の経済発展における黄金時代といってもいいでしょう。*5)
高度経済成長が起こった要因
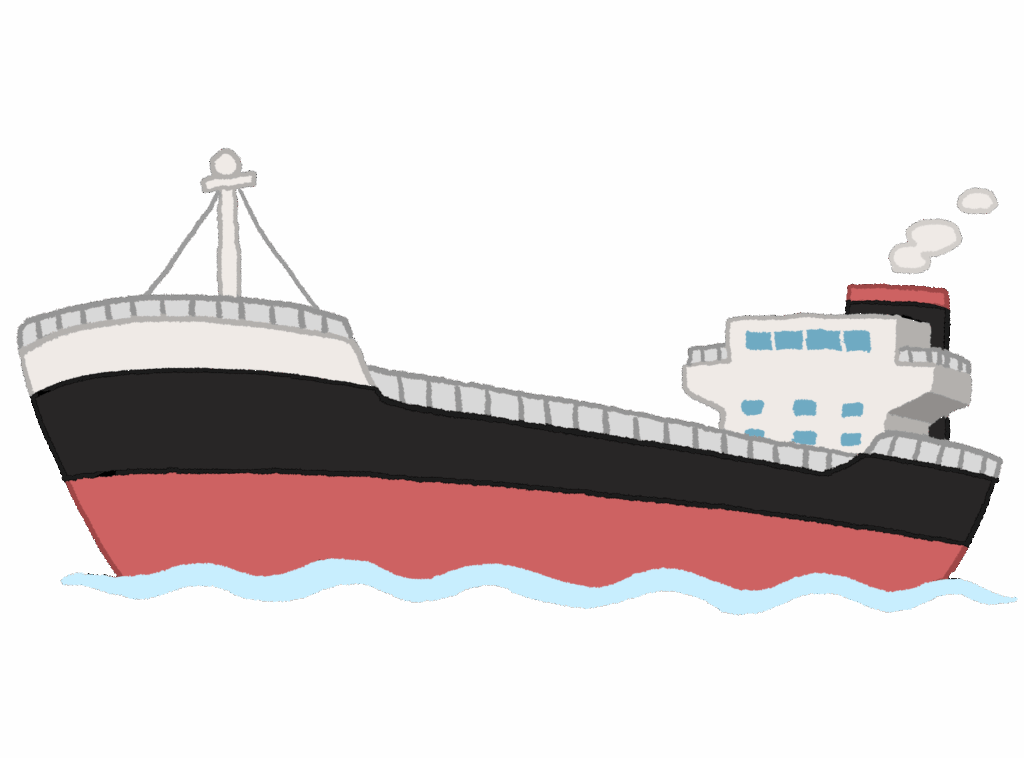
高度経済成長の要因は複数あります。
- エネルギー革命の進展
- 技術革新の急速な進展
- 所得倍増計画などの政府の後押し
それぞれの要因について解説します。
エネルギー革命の進展
高度経済成長期、日本経済の飛躍的発展を支えた重要な要因の一つに「エネルギー革命」があります。これは第二次世界大戦後に主要なエネルギー源が石炭から石油へと急激に移行した現象を指します。
この変化が進んだ背景には、石油の持つ様々な利点がありました。燃料としての発熱量が高く、燃焼効率に優れ、取り扱いや保管が容易という特徴を持っていたのです。さらに中東での大規模油田発見により供給量が増加し価格が下落しました。輸送技術も大型タンカーや長距離パイプラインの発達で効率化されました。
日本では1962年に石油が石炭の使用量を上回り、その後も急速に普及していきました。国内の石炭産業が品質や生産性の問題を抱える中、安価な石油の大量供給は製造業の技術革新を促進し、経済成長の原動力となったのです。*6)
技術革新の急速な進行
昭和30年代から40年代前半にかけて、海外ですでに実用化されていた様々な製造技術や製品が日本に一斉に導入され、産業構造や日常生活に大きな変化をもたらしました。
この時期の技術発展の特徴は、新しい商品の開発と生産コストの大幅な削減にありました。例えば鉄鋼業界では「高炉の大型化」という改革が進められました。
これにより製鉄所の生産能力が飛躍的に向上し、規模の拡大による効率化で製造費用を大きく抑えることに成功したのです。昭和30年頃には約941万トンだった粗鋼生産量が、昭和50年には1億トンを超えるまでに成長したのです。*7)
このような製造現場での革新は、自動車や家電製品など関連産業の発展も促進しました。各分野での設備投資が連鎖的に広がり、「投資が次の投資を生む」という好循環が形成されました。
所得倍増計画などの政府の後押し
高度経済成長期には、政府による積極的な経済政策が重要な役割を果たしました。その代表例が1960年12月に池田内閣によって決定された「国民所得倍増計画」です。この政策は、10年間で実質的な経済規模を2倍にするという野心的な目標を掲げたものでした。*8)
この計画では、道路・港湾・都市開発といった公共施設の整備拡充が重視されました。また産業構造の近代化や貿易の促進、人材育成と科学技術の発展支援なども主要な課題として位置づけられていました。さらに企業規模による格差の是正や地域間の発展バランスにも注目した点が特徴的でした。*9)
それまでの経済計画と比べて、日本の成長可能性を高く評価し、社会基盤の充実に力を入れた点が画期的だったのです。政府のこうした明確なビジョン提示と後押しが、民間企業の投資意欲を刺激し、結果として当初の予想を上回るスピードで経済成長が実現しました。
高度経済成長の暮らしの変化

1950年代後半から1970年代初頭にかけての経済発展は、日本人の日常生活を大きく変えました。カラーテレビ・クーラー・自家用車といった「3C」が各家庭に広まり、食卓にはインスタント食品が並ぶようになりました。また余暇を楽しむレジャー文化も定着し、戦後の質素な生活から豊かさを実感できる時代へと移り変わっていったのです。
3Cが普及した
高度経済成長期、日本人の暮らしは劇的に変化しました。特に注目されるのが「3C」と呼ばれた、自家用車(カー)・冷房機(クーラー)・カラーテレビの急速な普及です。これらは生活の質を大きく向上させる象徴的な製品となりました。
自動車については、1958年に発売されたスバル360が「てんとう虫」の愛称で親しまれ、手頃な価格で多くの家庭に普及しました。それまで遠かった場所も気軽に訪れられるようになり、レジャーの選択肢が広がりました。さらに1966年に登場したトヨタ・カローラは実用性と経済性を兼ね備え、「国民車」と呼ばれるほどの人気を博し、日本のモータリゼーションを加速させたのです。
一方、家庭内ではクーラーによって夏の暑さから解放され、カラーテレビの登場は娯楽の形を一変させました。「三種の神器」と呼ばれた白黒テレビ・洗濯機・冷蔵庫が普及した時代から、さらに豊かさが進んだ証でした。
これらの製品は単なる便利さだけでなく、人々の生活様式や価値観にも大きな変化をもたらし、現代の消費社会の基盤を形作ったといえます。
ライフスタイルが一変した
高度経済成長期には、日本人のライフスタイルが大きく変わり、インスタント食品の普及やレジャー(余暇活動)の拡大がその象徴となりました。
1958年(昭和33年)に発売された「チキンラーメン」は、日本初のインスタントラーメンであり、「お湯をかけて2分」でできるという手軽さが、当時の家庭に革命をもたらしました。*11)
高度経済成長期の後半から1970年代にかけて、国民の生活水準が向上するにつれて、余暇活動の大衆化が急速に進みました。この変化を後押ししたのは、労働環境の改善による自由時間の増加です。週休二日制が広まり、連続した休日を活用した新しい楽しみ方が生まれました。*12)
人々の関心も多様化し、健康増進や自然との触れ合い、スポーツ活動など様々な目的でレジャーを楽しむようになりました。特に自家用車の普及により移動範囲が広がり、遠方への観光旅行やアウトドア活動が身近になりました。*12)
高度経済成長が終了した理由とその後

1970年代初頭、日本の急速な経済発展は大きな転換点を迎えました。アメリカの金とドルの交換停止(ニクソンショック)や中東からの石油供給危機(オイルショック)という国際的な経済混乱により、高度成長期は幕を閉じることになります。その後の日本経済は、爆発的な発展から緩やかな伸びへと移行し、新たな時代へと歩みを進めていきました。
オイルショックとニクソンショックで高度経済成長が終了
1970年代初頭、日本の高度経済成長は二つの国際的な経済危機によって終わりを迎えました。まず、1971年に起きたのが「ニクソンショック」です。アメリカのニクソン大統領が金とドルの交換を停止する政策を発表したことで、円の価値が上昇し、日本の輸出産業が打撃を受けました。*13)
さらに1973年、中東で第四次中東戦争が勃発すると、アラブの産油国が石油価格を大幅に引き上げる「第一次オイルショック」が発生。エネルギー源を海外に依存していた日本経済は深刻な影響を受け、物価が急騰する「狂乱物価」と呼ばれる状況に陥りました。翌1974年には、戦後初めての経済的なマイナス成長を記録します。*13)
この後も1979年には「第二次オイルショック」が発生し、石油価格は約3倍に高騰しました。石油に頼る経済構造の脆さが露呈し、企業は省エネ対策を迫られました。これらの連続した危機により、日本経済は高い成長率を維持できなくなり、安定成長期へと移行していったのです。*13)
日本は安定成長に移行した
日本の高度経済成長期(1955~1973年頃)の後、経済は一定の成長率で安定的に成長する「安定成長期」(もしくは安定経済成長期)に移行しました。この時期はおおむね1973年12月から1991年5月まで続き、経済成長率は高度成長期ほどの急激な伸びは見られなかったものの、比較的安定して中程度の成長を維持しました。
高度経済成長とSDGs

日本の驚異的な経済発展は豊かさをもたらす一方で、深刻な環境問題も引き起こしました。今日のSDGs(持続可能な開発目標)の視点から振り返ると、四日市ぜんそくや水俣病といった公害は「経済成長と環境保全の両立」という現代的課題の原点といえます。過去の教訓から、持続可能な社会への道筋を考えてみましょう。
SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」との関わり
高度経済成長期、日本の急速な産業発展は豊かさをもたらす一方で、深刻な環境問題を引き起こしました。経済最優先の姿勢から環境対策が後回しにされ、四日市ぜん息や水俣病といった公害病が全国で発生したのです。工場排煙による大気汚染や工場排水による水質悪化は多くの人々の健康を損ない、社会問題として大きく取り上げられました。
SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」との観点から見ると、経済優先の開発が人々の健康を犠牲にしたという点で大きな教訓を残したといえるでしょう。
公害被害者の長期にわたる苦しみは、健康が経済発展の代償になってはならないという強いメッセージを残しています。1967年の公害対策基本法制定以降、日本は環境と健康を守る法整備を進め、企業の環境対策も強化されました。
歴史から学んだ「人間の健康を最優先する」という価値観は、SDGs目標3の根幹をなす考え方となっており、持続可能な社会の実現には経済成長と健康保障の両立が不可欠だと教えています。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
今回は、高度経済成長について解説しました。1950年代半ばから1970年代初頭にかけて、日本は年平均約10%という驚異的な経済発展を遂げました。この時代には神武・岩戸・オリンピック・いざなぎという4つの好景気が訪れ、国民生活は大きく変化しました。
成長の原動力となったのは、石炭から石油へのエネルギー転換、製造技術の急速な近代化、そして池田内閣の「所得倍増計画」に代表される政府の積極策でした。
家庭では「3C」と呼ばれる自動車・冷房機・カラーテレビが普及し、余暇活動も多様化。しかし、急速な発展の陰で公害問題も深刻化しました。
1971年のニクソンショックと1973年のオイルショックにより高度成長期は終わりを告げましたが、この時代の変化は現代日本の社会・経済構造の基盤を形作ったのです。とはいえ、経済発展と引き換えに、環境汚染が進んだという事実を忘れてはなりません。産業発展と環境保護の両立は、現代に生きる私たちにとって重要なテーマだといえるでしょう。
参考
*1)改定新版 世界大百科事典「高度経済成長」
*2)改定新版 世界大百科事典「東海道新幹線」
*3)日本大百科全書(ニッポニカ)「神武景気」
*4)三井住友信託銀行「オリンピックと景気」
*5)ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「いざなぎ景気」
*6)改定新版 世界大百科事典「エネルギー革命」
*7)経済企画庁「昭和52年 年次経済報告」
*8)ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「国民所得倍増計画」
*9)国立公文書館「国民所得倍増計画について」
*10)NHK for School「高度経済成長」
*11)日本即席食品工業協会「インスタントラーメンの誕生」
*12)岐阜経済大学「時代の変遷に伴うレジャー産業の系譜」
*13)弘前市「新編弘前市史」
*14)内閣府「平成元年度 年次経済報告」
*15)環境庁「昭和57年 環境白書」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。