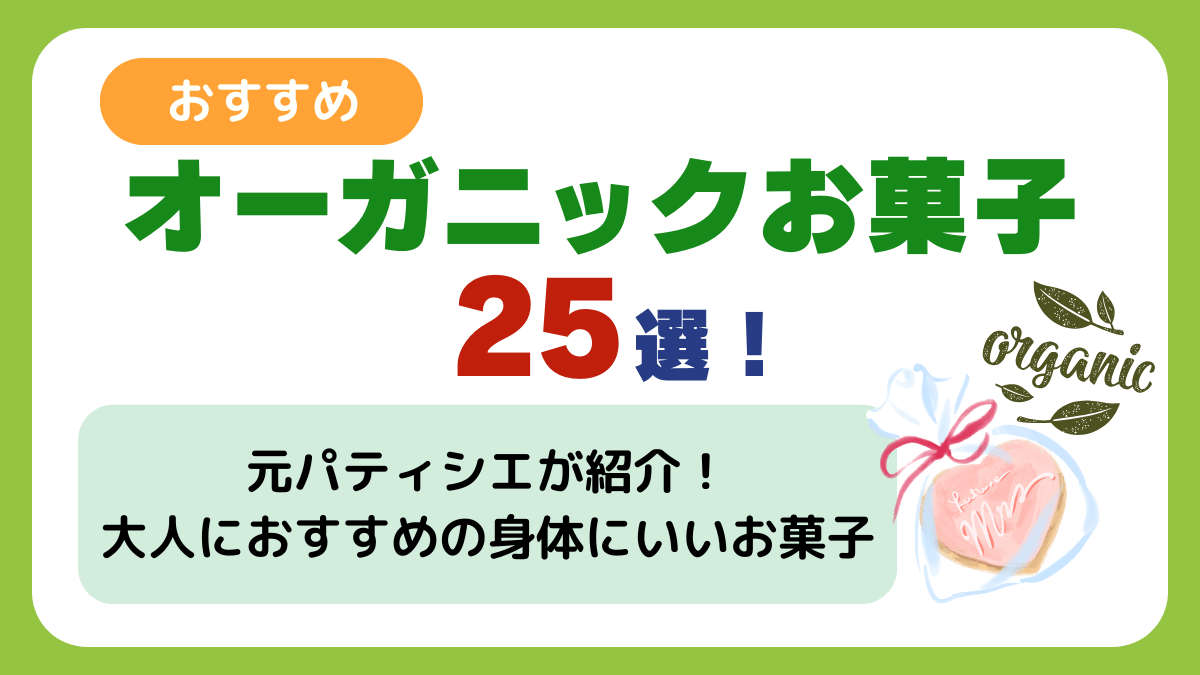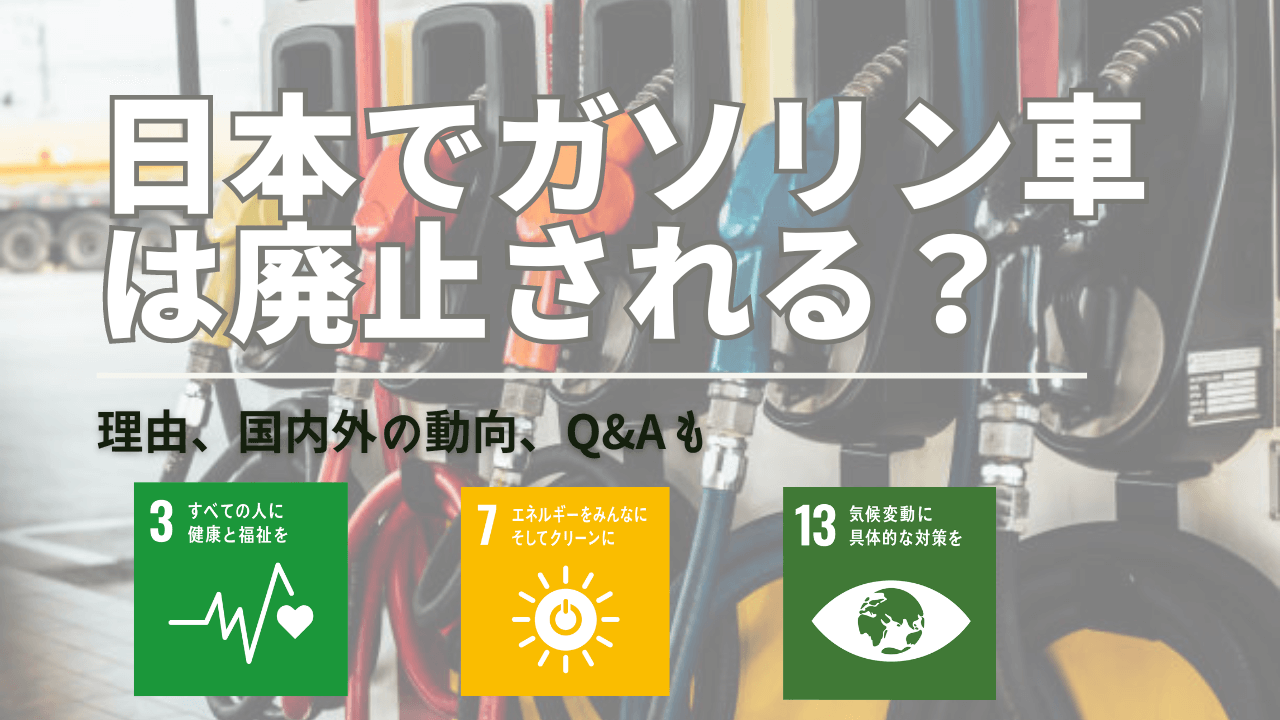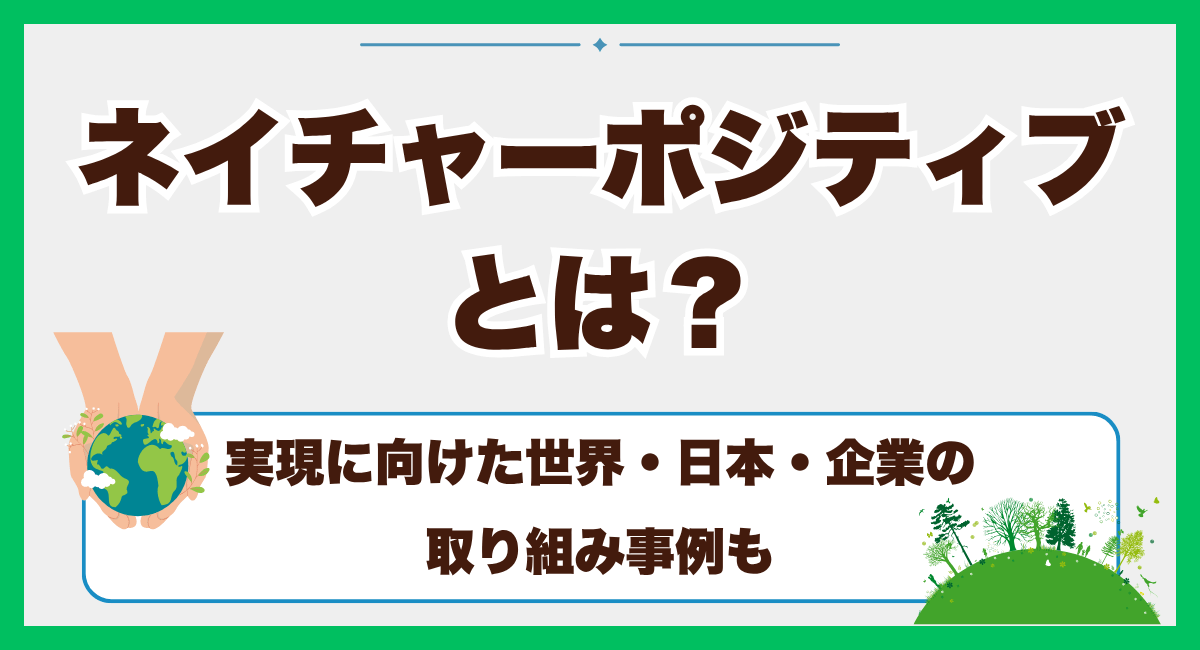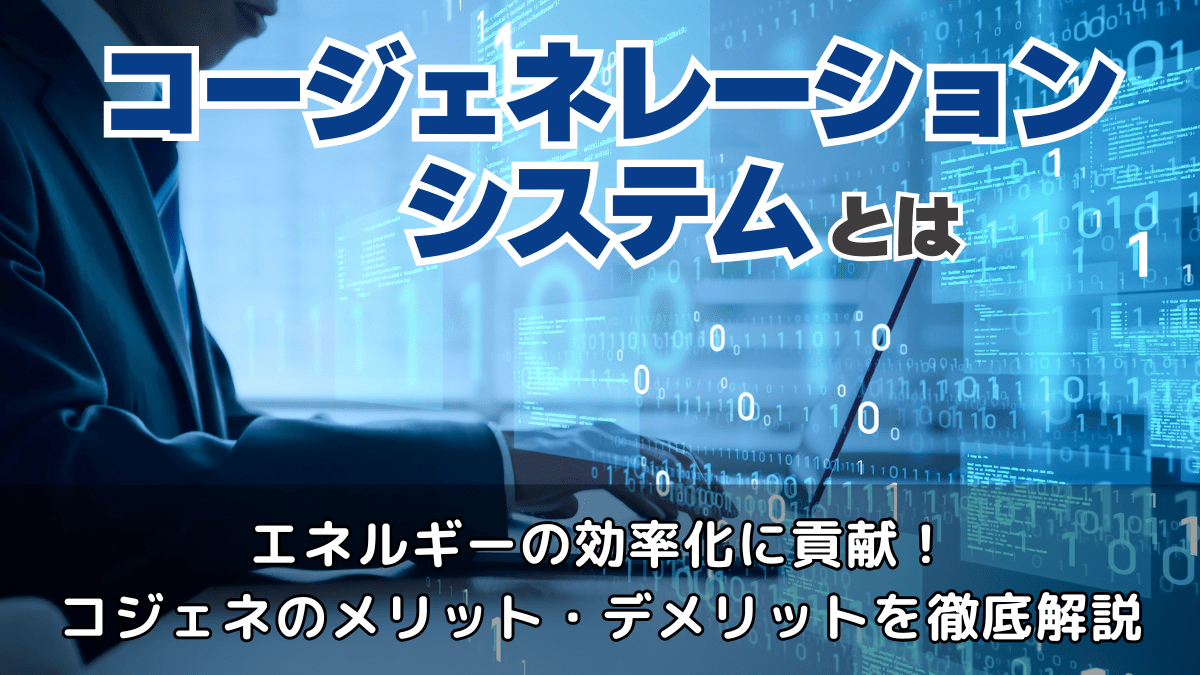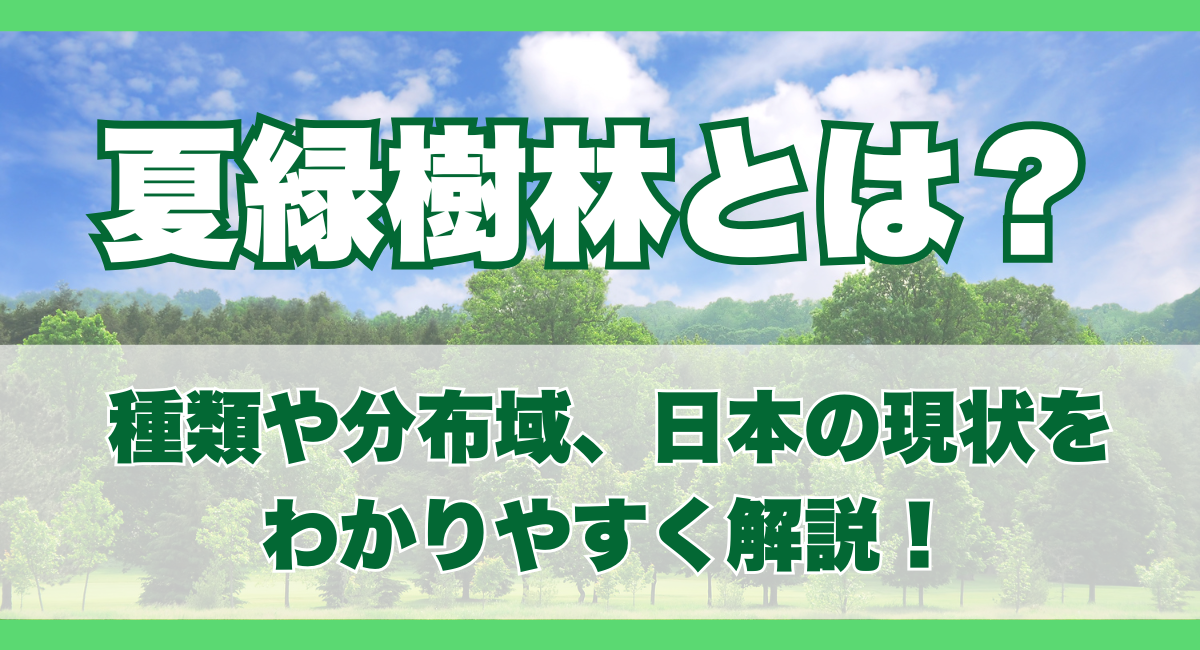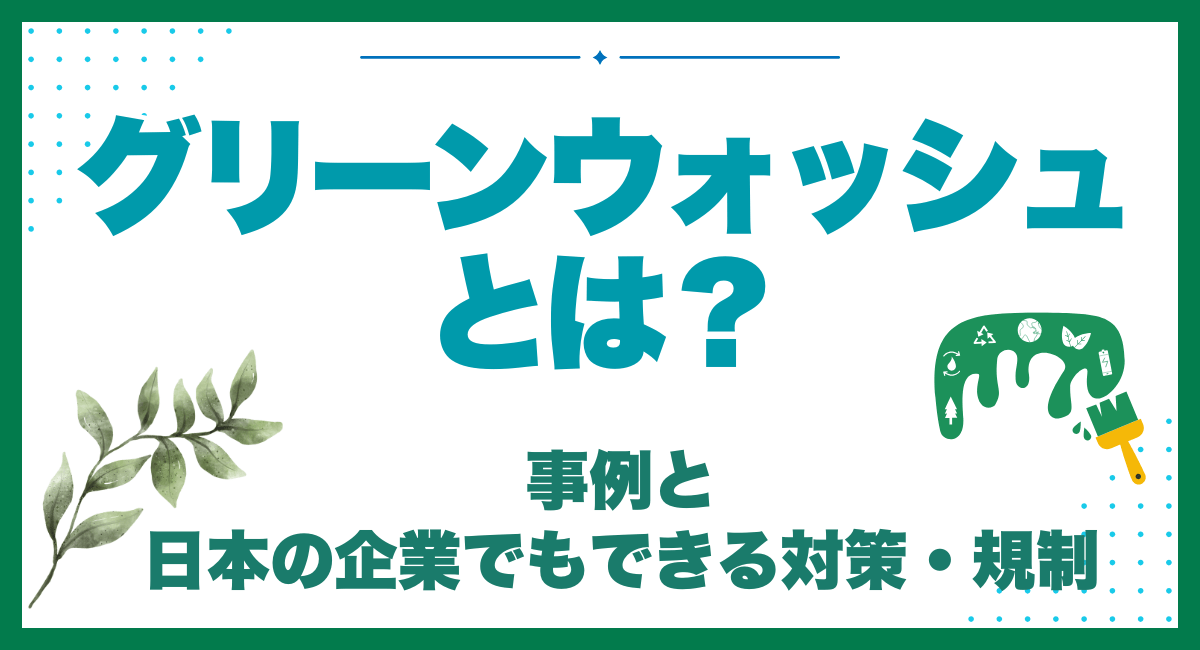
近年、人や環境に優しい製品やサービスを提供する企業が増えてきました。環境配慮を意識する企業が、増えること自体は良いことです。しかし、なかには自分たちの利益を優先して、環境に配慮していると見せかける企業も存在します。
このような企業のビジネス戦略を、「グリーンウォッシュ」と呼び、現在大きな問題となっています!
本記事では、グリーンウォッシュが問題視されている理由や、消費者がグリーンウォッシュに騙されないためのポイント、企業がグリーンウォッシュを行わないための対策などをまとめました。
まずは、グリーンウォッシュとは何かを見ていきましょう。
目次
グリーンウォッシュとは?簡単に解説
グリーンウォッシュとは、エコや環境に良いイメージとして使用される「グリーン」と、「うわべだけ」や「取り繕う」を意味する「ホワイトウォッシュ」を合わせた言葉です。本当は環境に配慮していないにもかかわらず、しているように見せかけて商品やサービスを提供することを指します!
例えば、
- 「環境に優しい商品です」とアピールし販売しているが、実は製造過程で大量の二酸化炭素を排出している
- 天然成分がたくさん入っているように見せかけているパッケージデザイン
- 環境悪化の恐れがある商品のパッケージデザインに、緑色や自然を連想させるものを採用する
など、このような場合はグリーンウォッシュに当てはまります。
グリーンウォッシュは1986年から使われ始めた言葉
グリーンウォッシュは、アメリカの環境活動家であるジェイ・ヴェステルフェルト氏が、1986年に書いたエッセイの中で誕生しました。その後、2022年9月にはイギリスで古い歴史をもつ辞書『メリアム=ウェブスター』に、グリーンウォッシュが動詞と名詞の2箇所に追加されました。
メリアム=ウェブスターが単語を辞書に追加する条件として、「一定期間に多くの人が、対象の単語を同じ意味で使用する」があります。つまり辞書に載るということは、グリーンウォッシュがそれだけ多くの企業で行われ、注目されたと言うことです。
【関連記事】SDGsウォッシュとは?企業事例や指摘されないためのポイントも
グリーンウォッシュに対する規制とは
グリーンウォッシュに対する規制とは、企業が環境に配慮しているように見せかけた虚偽・誇大な広告表示を防ぐための取り組みです。欧州では「グリーンクレーム指令案」などが検討され、科学的根拠のない環境主張の使用を禁止する方向に動いています。
日本では景品表示法が該当し、「優良誤認表示」として措置命令の対象になることがあります。ただし明確なルールが不足しており、今後の法整備やガイドラインの策定が課題です。
グリーンウォッシュの問題点
ここからは、なぜグリーンウォッシュが問題なのか。その理由を確認していきましょう!
グリーンウォッシュを行っている企業の利益を増やしてしまう
商品やサービスを購入する際に「環境に配慮したもの」を選択する消費者は増えていますが、何が環境に良くて何が悪いのかを把握している人はまだまだ少ないでしょう。商品に記載されている「天然由来の成分配合」といった文字や、自然をイメージしたパッケージデザインを見て「なんとなく環境に良さそう」と思い購入する人もいます。
そのため、グリーンウォッシュに気づかずに商品を購入してしまうケースもあるのです。グリーンウォッシュを行っている企業から消費者が商品を購入し続けると、企業側は利益を上げて成長してしまいます。このような事態を防ぐためにも、消費者はグリーンウォッシュに対する知識を身につけ、正しい選択ができるようになることが大切です!
投資家をだますことにつながる
グリーンウォッシュは、投資家にも影響を及ぼします。近年は、「ESG投資※」や「グリーンボンド※」などの投資市場が拡大しており、企業が環境に良い取り組みを行っているかが判断基準に含まれるようになりました。
細心の注意を払って投資先の選定をしているものの、巧妙な手口でグリーンウォッシュを行う企業に対しては、見抜けずに投資してしまう可能性もあります。この場合、投資家は「環境に良い取り組みをしているから応援したい」と出資したはずが、実際は真逆のことを行っている企業を支援していることになるのです。
企業のイメージダウンにつながる
意図的ではないものの、環境に良さそうなイメージのある言葉を使ってPRしていたサービスや商品が、グリーンウォッシュと指摘される場合もあります。これは、グリーンウォッシュに対する理解がなかった企業に起こる可能性が高く、注意が必要です。
消費者は「裏切られ」「騙された」と感じ、起こった出来事を周囲の人に話したり、SNSへ投稿したりするでしょう。噂は瞬く間に広がり、企業の大幅なイメージダウンにつながります。商品やサービスのアピール方法は、よく考え慎重に行いましょう!
日本企業が行っているグリーンウォッシュの具体例
ここでは、日本企業で実際に起こったグリーンウォッシュの事例を紹介します。
ユニクロ
ユニクロはリサイクル活動やサステナブル素材の使用を強調し、環境配慮企業としてのイメージを発信しています。しかし、実際には生産過程での大量のCO₂排出や、低価格・大量生産型のビジネスモデル自体が環境負荷を高めているとの指摘があります。また、衣類リサイクルの回収率が低く、再利用される割合も限定的なため、実質的な効果に疑問の声が上がっています。
トヨタ
トヨタは「エコカー」の先駆者としてハイブリッド車を広めた実績がありますが、近年はEV(電気自動車)への移行が他社より遅れていると批判されています。表向きは環境対応を進めているとしながら、実際には水素やハイブリッド車に重点を置き、純粋なEVへの本格対応を後回しにしている点が、グリーンウォッシュと見なされることがあります。
世界企業が行っているグリーンウォッシュの具体例
続いては、世界企業で実際に起こったグリーンウォッシュの事例を紹介します。
マクドナルド
イギリスとアイルランドのマクドナルドでは、プラスチック製ストローから紙ストローへの切り替えを2018年に実施。当初、この紙ストローに対してマクドナルドは「100%リサイクル可能」と言っていました。
しかし、マクドナルド内部の人が書いた「紙ストローの厚みがありすぎてリサイクルは困難」というメモが外部に流出し、リサイクルされずにごみ箱へ捨てられていることが発覚したのです。その結果、マクドナルドはグリーンウォッシュを疑われ、批判を浴びました。
ライアンエアー
アイルランドの航空会社ライアンエアーは、2019年9月に発表した広告で「ヨーロッパで、最も環境負荷の低い大手航空会社」という内容の主張をしました。しかし、何を根拠に最も環境負荷が低いと言っているのかが曖昧であったため、広告基準局は「広告を見た人が誤解を招く」と判断。2020年2月には、広告がグリーンウォッシュであるという理由から禁止処分を受けました。
スターバックスコーヒー
スターバックスは、紙ストローやリサイクル可能なカップ導入など「脱プラスチック」を強調していますが、その実態に批判もあります。たとえば2020年に発表した「プラスチックストロー全廃」では、代替として提供されたリッド(フタ)が従来より多くのプラスチックを使用していると指摘されました。
さらに、店舗全体での廃棄物削減やCO2削減への実効性ある対策が不透明であり、環境配慮の姿勢を強調する一方で実質が伴っていない点がグリーンウォッシュとされる要因です。
消費者目線からのグリーンウォッシュの見分け方
ここまで見てきたように、グリーンウォッシュは身近なところにも存在しています。とはいえ、消費者の私たちが、グリーンウォッシュかどうかを見分けるにはどうすればいいのでしょうか。ここからは、消費者がグリーンウォッシュを見分けるためのポイントを確認していきましょう。
目の前の情報だけで判断しない
まずは、商品購入の際、目の前の情報だけで判断しないようにしましょう。
例えば、パッケージや商品イメージ画像に植物や緑色を多く採用した「グリーン掃除機(架空の商品です)」があったとします。見た目は「環境に良さそうな電化製品」であるため、つい購入してしまう人もいるかもしれません。しかし、製造過程で二酸化炭素を大量に排出していた場合、グリーンウォッシュに該当した商品と言えます。
このように、消費者は外側からの情報だけでは判断できない部分があるため、購入前にその製品について詳しく調べることが大切です。どの部分が環境に優しいのかを公式サイトで確認し、グリーンウォッシュを疑う口コミがないか検索することをおすすめします。
根拠がない・曖昧な主張には気をつける
根拠がない効果が書かれていたり、具体的な数値が書かれていない場合も注意が必要です。
具体的には、「リサイクル素材を使用」や「環境に優しい成分を配合」のようなアピールをしている商品やサービスが挙げられます。
この表記では、
- どの程度リサイクル素材を使用しているのか
- どの程度環境に優しい成分が配合されているのか
がわかりません。「リサイクル素材を〇〇%使用」のように具体的な数字が表記されているものを選択しましょう。
また、「環境に優しい成分」と表示する場合は、何を根拠に「環境に優しい」と言っているのかも重要です。「しっかりと実験を行い証明されている」「専門機関でその成果を発表している」など、裏付けされた情報であるかも注目しましょう。
専門用語の多用にも注意
一般の人を対象とした商品にもかかわらず、理解することの難しい専門用語を多用している場合は、「商品の信頼度を高めること」や「なんだか環境に良さそう、という雰囲気で購入してくれる消費者」を狙っている可能性があります。
環境に優しく良いものと自信をもって販売できるのであれば、多くの人に手に取ってもらえるように企業側もPR方法を工夫するはずです。難しい専門用語も多用せず、簡単な言葉でわかりやすく商品やサービスの説明をしてくれるでしょう。
つまり、わかりにくい説明には注意が必要です。
主張がズレているものは疑う
環境に配慮していない商品やサービスを販売する際に、「地球環境の改善を目指し活動している企業が、立ちあげた商品やサービスです」と、販売する対象(商品)ではなく企業の話を目立たせるなど、ズレた主張を行っているケースがあります。
これにより、「環境に良い活動を行っている企業が販売している=商品やサービスも環境に良い」と思いこんでしまう消費者も多く、疑うことなく購入してしまうのです。また、本当はその活動を数年に一度しか実施していないのに、積極的に行っているように見せかけている企業も存在します。商品やサービスを利用する際は、その辺りのポイントも確認するようにしましょう。
日本企業もできるグリーンウォッシュ対策
続いては企業側の、グリーンウォッシュへの対策を見ていきます。
「グリーンウォッシュの7つの罪」を確認する
企業側の対策としては、アメリカの第三者安全科学機関「ULソリューションズ」のScot Case氏が提唱した、消費者がグリーンウォッシュを行っている商品やサービスを特定するためのツール「グリーンウォッシュの7つの罪」の活用が挙げられます。
「グリーンウォッシュの7つの罪」は、消費者がグリーンウォッシュを特定するためのツールではあるものの、企業も知ることによって意図的ではないグリーンウォッシュを防げます。
7項目は以下の通りです。
【グリーンウォッシュの7つの罪】
| 隠れたトレードオフの罪 | 製品の原材料が環境に優しいものであったとしても、製造過程で環境汚染や破壊が行われている可能性がある |
| 証明しないことの罪 | 信頼できる第三者認証によって立証(裏づけ)されていない、環境に良いという主張 |
| 曖昧さの罪 | 消費者が誤解する可能性の高い、定義が不十分で曖昧な表示や範囲 |
| 偽りのラベル崇拝の罪 | 第三者認証がないにもかかわらず、言葉や画像を使用して「認証されています」と表示している |
| 的外れの罪 | 環境に配慮した商品・サービスを求める消費者にとって、まったく役に立たない、意味のない主張をしている |
| 環境に悪いもののうち、かろうじてて良い方を「環境に良い」と宣伝する罪 | その商品のカテゴリーの中では環境に良い方に分類されるかもしれないが、カテゴリー自体が環境に良くないため悪影響を与える危険性がある。 例:オーガニックの煙草 |
| 嘘をつく罪 | 環境に配慮していないのに、「配慮している」と嘘をつく |
海外のガイドラインから学ぶ
他にも、グリーンウォッシュに該当しないためのガイドラインを読み込むことも大切です。
しかし、残念ながら日本には国が定めたグリーンウォッシュに対する明確な基準がありません。そのため、海外のガイドラインから学ぶと良いでしょう。例えばイギリスでは、「Green Claims Code(グリーン クレーム コード)」が制定されています。
内容は、下記の通りです。
- 自社の製品やサービス・ブランド・活動に誠実かつ明確であること
- 消費者がそのメッセージをどう受け取るかを考え、製品の情報と一致するようにする
- 重要な情報を省略しない・隠さない
- 製品の比較は、公平で意味のあるものだけを行う
- 製品のライフサイクル全体を考慮する
- 製品に関する主張には、必ず信頼できる最新の証拠(裏づけ)があること
その他にもフランスでは、2021年4月にグリーンウォッシュに関する「改正法5419」が成立。グリーンウォッシュと判断された広告には、記事の訂正や説明文章を自社サイトへ30日間掲載することに加え、該当する広告費の最大80%の罰金が課されます。
ぜひ一度、「グリーンウォッシュの7つの罪」や海外のガイドラインを使いながら自社製品を見直してみてはいかがでしょうか。
グリーンウォッシュに関するよくある質問
ここでは、グリーンウォッシュに関するよくある質問を5つ紹介します。
グリーンウォッシュとは何ですか?
グリーンウォッシュとは、企業が実際には十分な環境配慮を行っていないにもかかわらず、あたかも環境に優しい企業であるかのように見せかけるマーケティング手法です。1986年にアメリカで登場したこの言葉は、現在では世界中で使われるようになりました。
環境問題への意識が高まる中、消費者の関心を引くために「エコ」や「サステナブル」といった言葉を安易に使う企業が増え、注意が必要です。
どのような事例がグリーンウォッシュとされるのですか?
グリーンウォッシュの事例として、スターバックスの紙ストロー導入があります。表向きはプラスチック削減を掲げていましたが、フタは依然としてプラ製であり、全体としての環境負荷軽減には疑問が残ります。
ユニクロはリサイクル活動を強調する一方、大量生産・大量消費のビジネスモデルが変わっていないと指摘されます。トヨタもEVへの本格移行の遅れが、環境配慮に対する姿勢として批判されています。
グリーンウォッシュはなぜ問題なのですか?
グリーンウォッシュが問題視される理由は、消費者や投資家を誤解させることにあります。企業が実態とかけ離れたイメージを広めると、真に環境対策を行っている企業の信頼性が損なわれ、エシカル消費やESG投資の妨げになります。
また、環境改善への本質的な行動が遅れ、気候変動や資源問題の解決に逆行する恐れもあります。意図せず社会全体の環境意識を形骸化させてしまう点も深刻です。
グリーンウォッシュを見分ける方法はありますか?
グリーンウォッシュを見抜くには、企業の取り組みの「全体像」をチェックすることが重要です。広告やパッケージの一部だけが環境配慮されていても、実態が伴っていなければ疑うべきです。第三者機関の認証や報告書の有無、定量的な実績の開示なども判断材料になります。あいまいな表現(例:「エコに配慮」「自然由来」など)が使われていないかを確認することも効果的です。
グリーンウォッシュへの対策や規制は進んでいますか?
欧州ではグリーンウォッシュ対策が進んでおり、虚偽表示に対する法的制裁や広告規制が導入されています。日本でも、消費者庁や環境省が表示ガイドラインを整備し、事業者向けに注意喚起を行っています。一部では環境表示の国際基準化も進んでおり、企業に対する説明責任が強化されています。企業の透明性や実効性のある取り組みが今後ますます求められるでしょう。
グリーンウォッシュとSDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」との関係
最後に、グリーンウォッシュとSDGsの関係を見ていきます。
世界中で起きている環境・社会・経済の課題解決を目指し、2015年に誕生したSDGsは、17の目標と169のターゲットが設定されている国際目標です。そして、グリーンウォッシュを行う企業が減ることによって、さまざまなSDGsの目標達成につながると言われています。
今回は、その中の1つである目標13との関係性を見ていきましょう。
目標13は、気候変動とその影響によって起こる被害に対して、エネルギーや金融など、あらゆる方面から対策を行う内容となっています。そして気候変動の原因の1つが、大量の温室効果ガス排出によって起こる地球温暖化です。
グリーンウォッシュを行う企業は、表面上は環境に良いと大々的に宣伝し消費者の支持を得ています。しかし、実際は製造過程で大量の二酸化炭素を排出しているケースもあります。二酸化炭素は、地球温暖化の悪化につながる「温室効果ガス」の1つです。
そのため、この企業が製造方法を改め、本当に環境に優しいやり方に切り替える(グリーンウォッシュをやめる)ことで、二酸化炭素排出量の削減が期待されます。その結果、目標13の達成に近づけるのです。
まとめ
「エコ」や「サステナブル」な商品やサービスが増える一方で、そういった考え方を利益のためだけに利用する人・企業も一定数出てきました。グリーンウォッシュを見破ることは難しいものの、消費者は環境配慮に対する正しい知識を身につけ、違和感に気づき、自分で調べるようにならなければいけません。
企業も、「知らないうちにグリーンウォッシュを行っていた」とならないように、対策をする必要があります。企業と消費者の両方が気をつけることによって、グリーンウォッシュが減り、自然環境に優しい社会に近づいていくでしょう。その結果、SDGsの目標達成にもつながります。
〈参考文献〉
We Added 370NewWords to the Dictionary for September2022|Merriam-Webster.com
グリーンウォッシュとは?– エコを売りにしたSDGsマーケティングの問題点をひもとく3つの事例|国際環境NGOグリーンピース・ジャパン
ESG投資|経済産業省
グリーンボンドとは|環境省
知っておきたいエネルギーの基礎用語 ~CO2を集めて埋めて役立てる「CCUS」|資源エネルギー庁
マクドナルドの紙製ストローはリサイクルできず廃棄されていた|Newsweek日本版
「グリーンウォッシュ」の7つの罪と、それ以上の危機|Forbes JAPAN
グリーンウォッシングの罪|ULソリューション
Green Claims Code -Check your green claims right |HM Government
【RI特約記事】フランスがグリーンウォッシュ規制を導入|QUICK ESG研究所
気候変動とは?|国連広報センター
SDGs(持続可能な開発目標)|蟹江憲史 著
この記事を書いた人
スペースシップアース編集部 ライター
スペースシップアース編集部です!
スペースシップアース編集部です!