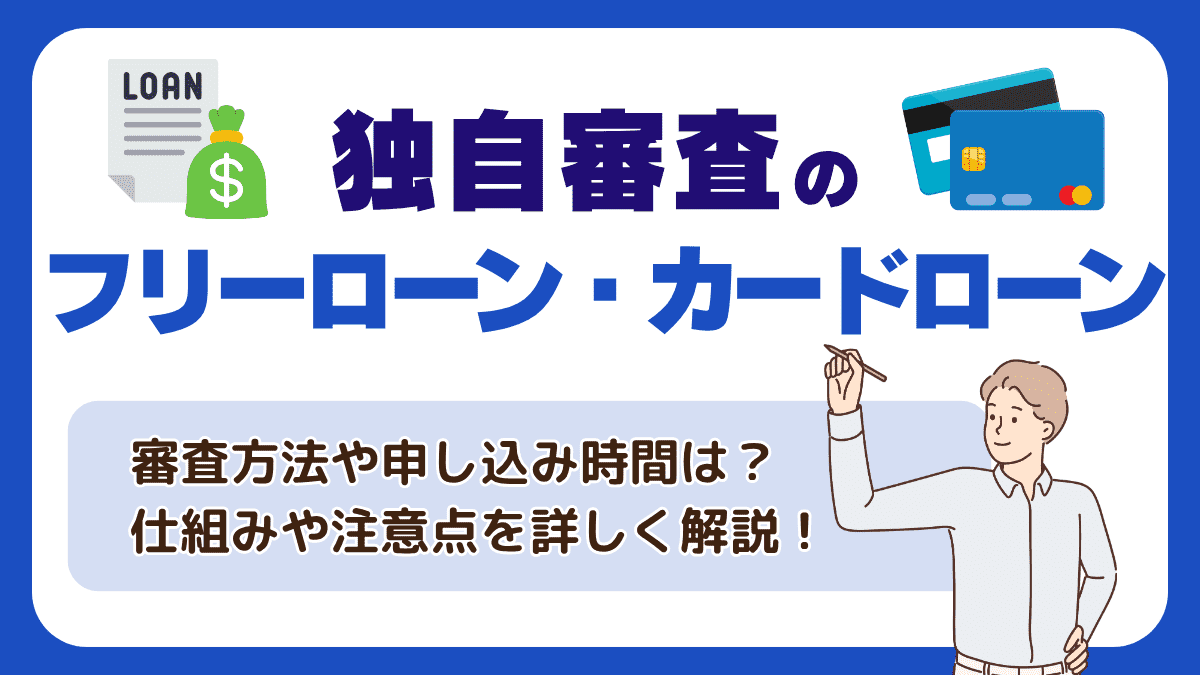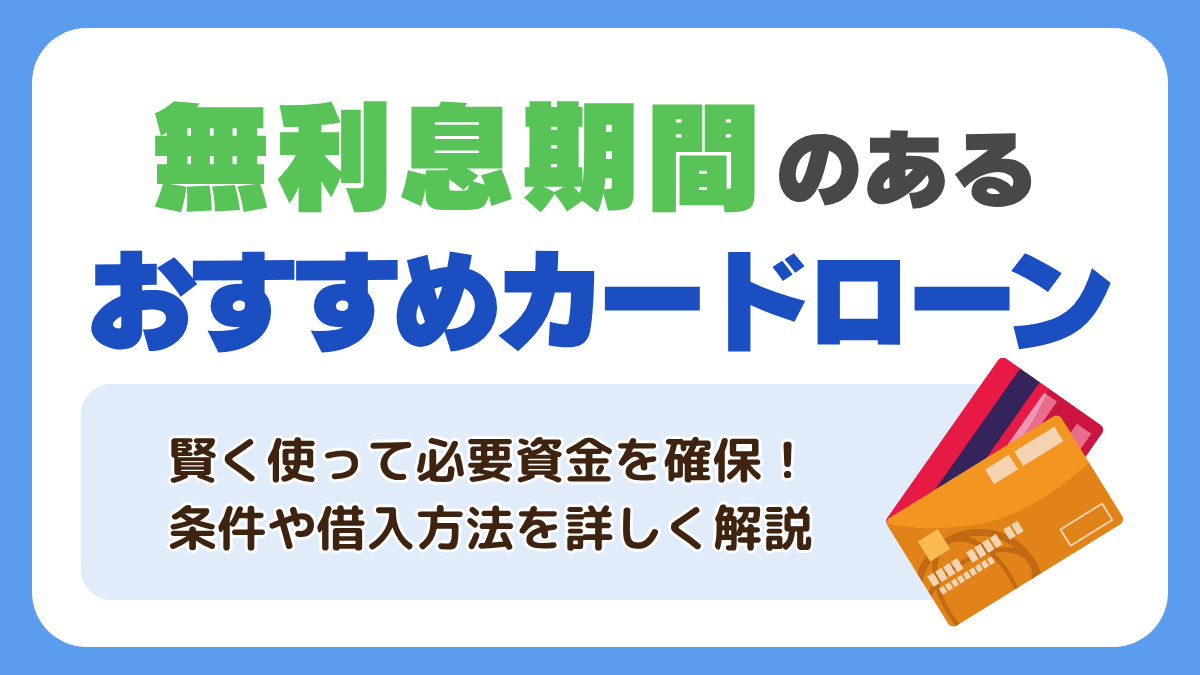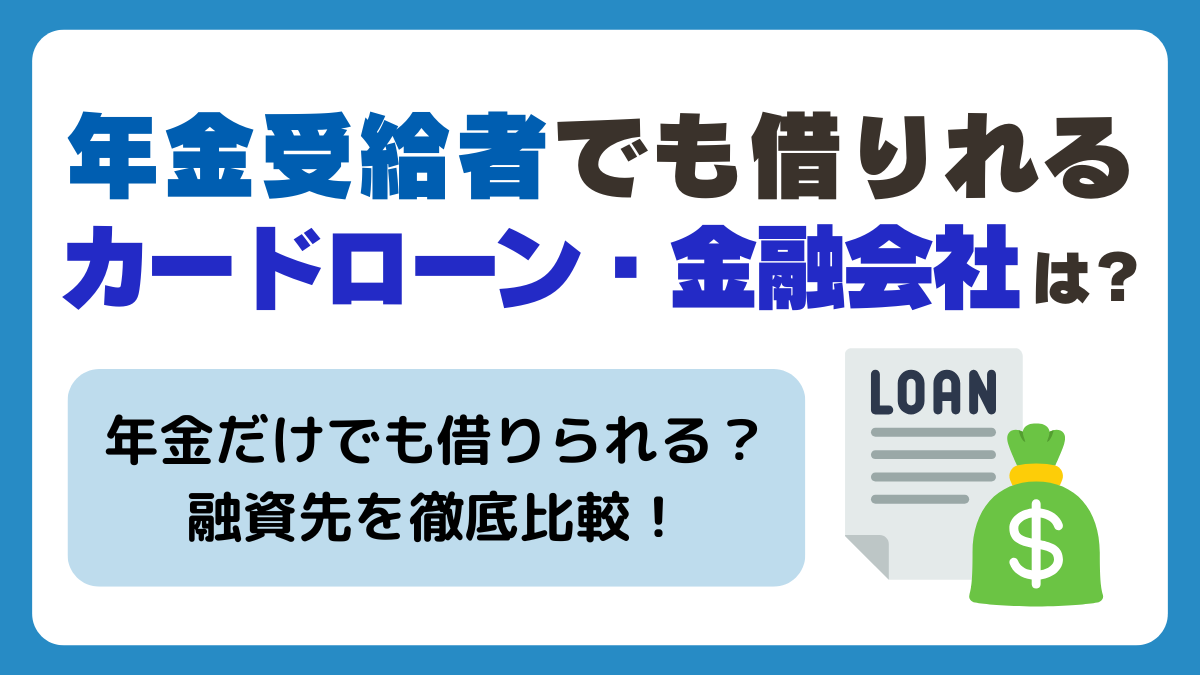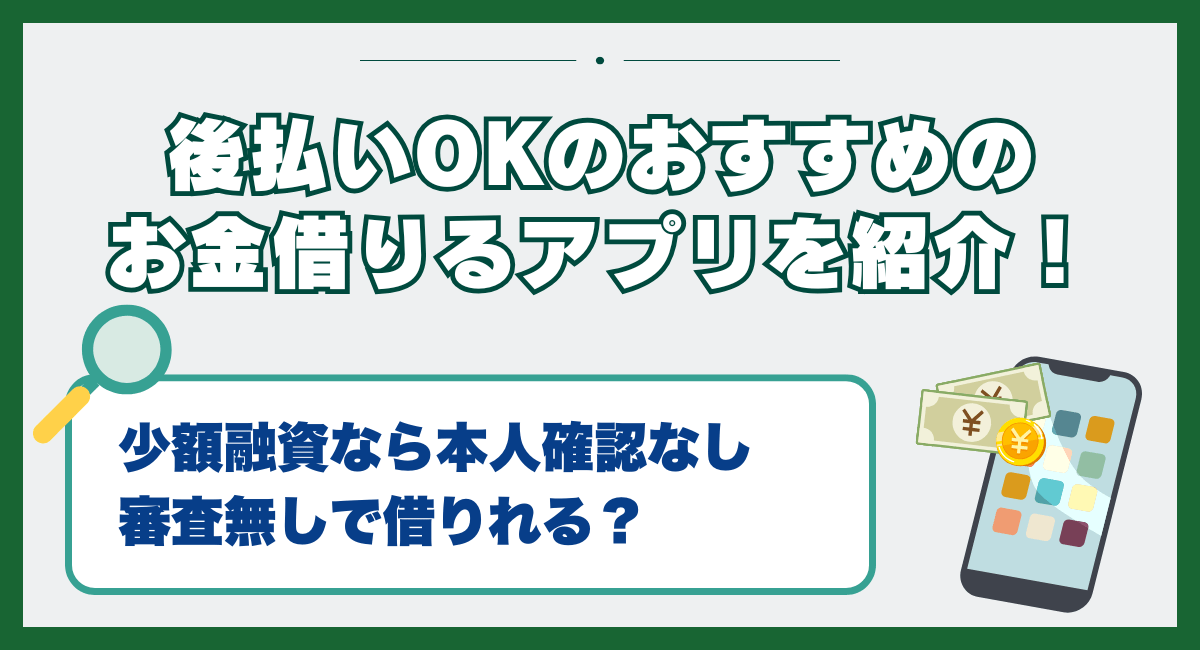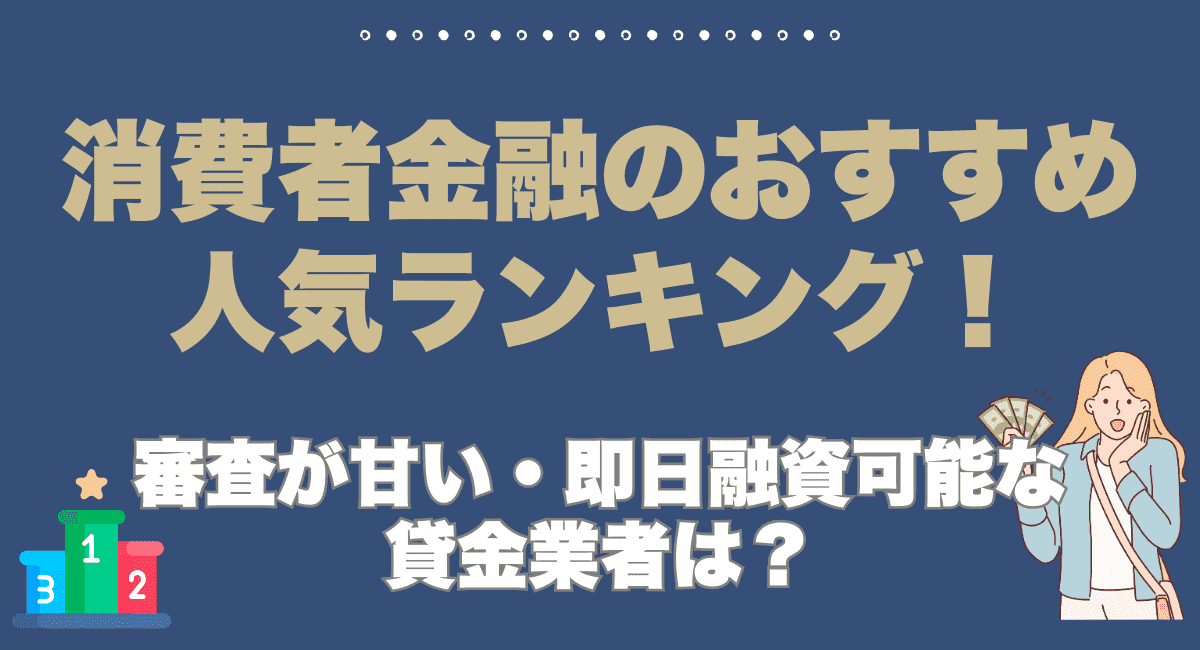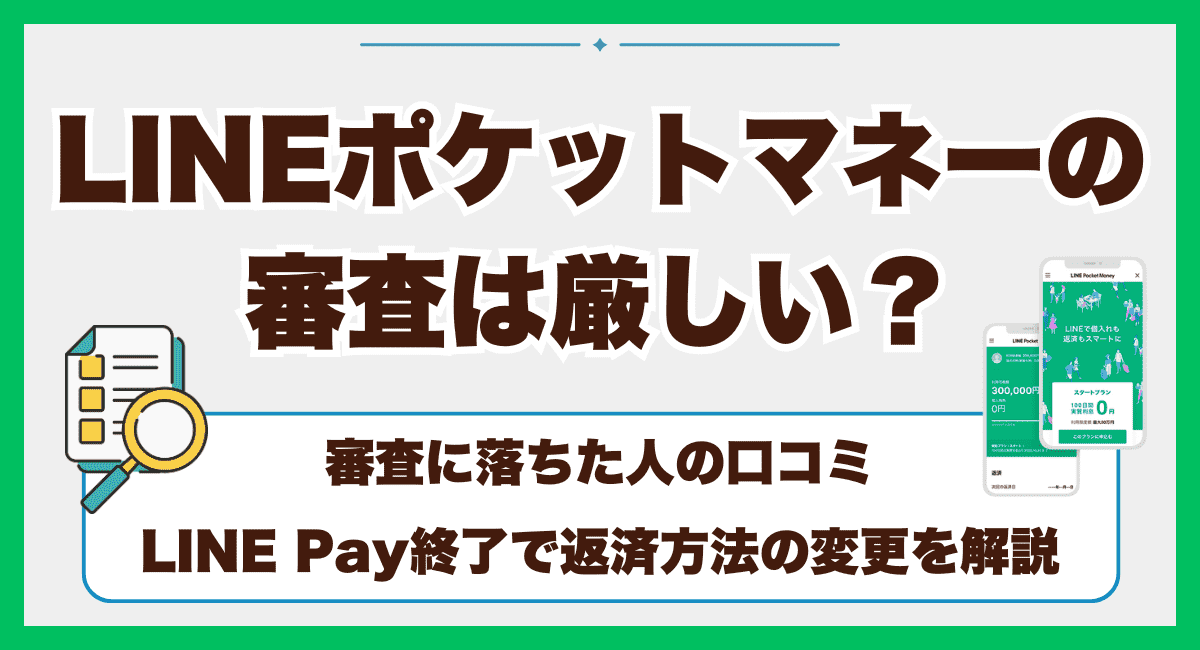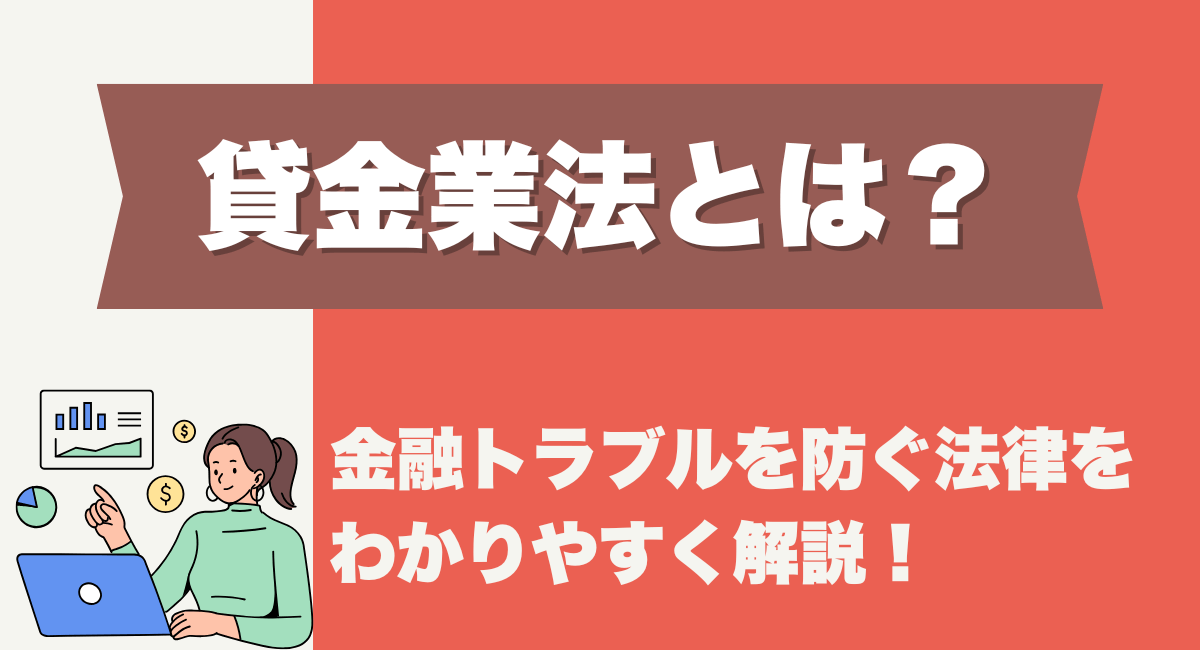
お金に困ったとき、すぐに貸してくれる消費者金融は便利なサービスですが、実際は厳格なルールのもと成り立っており、そのルールを貸金業者が遵守しているからこそ成立します。
そのルールというのが、今回取り上げる「貸金業法」です。
この法律は利用者を保護して金融トラブルを防ぎ、貸金市場の健全な発展を促す役割を果たしていますが、具体的にどのようなルールや禁止行為、違反時の罰則等が定められているのか、改正前と大きく変わった部分も含めて詳しく解説していきます。
目次
貸金業法とは?概要と目的について
貸金業法は、正式名称を「貸金業の規制等に関する法律」という、消費者金融や貸金業者からお金を借りる行為を法的に規制するため、1983年に制定された法律です。規制といっても貸金行為を禁止するのではなく、逆に消費者が健全にお金を借りられるようにルールを定めたものです。
この法律が何のために制定されたのか、そしてどのような内容なのかを、わかりやすく解説していきます。
貸金業法の目的は?何のために存在するのか
貸金業法が制定された目的は、お金を貸す側が適切に貸金業を運営すること、そして借りる側の消費者の利益を保護することです。もともと貸金業の市場はかなり大きかったのですが、その反面さまざまな問題が発生したため、国を挙げての対策が必要でした。
その問題の一つが「多重債務」です。貸金業者による高金利での貸付が可能だった時代は、顧客が必要とする以上の貸付が横行していました。結果的に多くの人が借りすぎて首が回らなくなり、「返すために借りる」悪循環で生活が破綻する事態が多発したのです。
そこで国は貸金業法を制定し、利用者を守ることと、貸金市場を健全に発展させることを両立させようとしました。
これにより、利用者は悪徳業者等による金融トラブルから守られますし、貸す側は融資先の信頼性や持続性が担保され、結果的に双方が保護されることになります。
貸金業法の概要
次は貸金業法の概要について、4つの点をそれぞれ解説します。
貸金業を営むには登録しなければならない
貸金業法の制定により、貸金業は完全登録制となりました。事業者が正規の貸金業を営むためには、国(財務局長)と都道府県知事から認可を受ける必要があります。また、認可されるには次の要件もクリアすることが求められます。
- 純資産額が5,000万円以上である(財産的基礎を有すること)
- 役員は貸付業務の経験が3年以上ある(業務経験を有すること)
- 事業所ごとに資格保有者を1名配置する(貸金業務取扱主任者の配置)
これらの要件をクリアすれば正規の貸金業者として登録され顧客にお金を貸すことができるようになりますが、登録は一度だけでなく3年ごとに更新される必要があります。
もし、これらの認可を受けずに貸金業を営んだ場合は無登録営業となり、罰金や懲役刑の対象となります。無登録営業の事業者は理由にかかわらず悪徳業者、いわゆる「闇金」と同じ扱いになってしまうのです。
年利20%を超える利息の禁止
貸金業法では、年利20%を超える金利で顧客にお金を貸すことを禁じています。猶予があるわけではなく完全な禁止なので、2010年以前には存在した「グレーゾーン金利」は存在できません。
グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法における金利上限の差が生んだ「罰則のないルール違反」が可能な金利帯のことです。具体的には、旧出資法で定められている「29.2%」以内であれば、20%超の金利で貸し付けても罰則がなかったのです。
しかし改定された現在の法律では、20%を超えた利息で貸し付けることは違法です。この改正によりボーダーラインが明確となり、弱かった「借りる側」の権利が大幅に向上し、貸金業の公平性と透明性が大幅に向上しました。
総量規制による制限
貸金業法の改正に伴い新たに導入されたのが、個人の年収に応じて借りられる金額を制限する「総量規制」です。文字通り一個人が借りられる総量が「年収の3分の1まで」に規制されるため、自由度は減りますが、多重債務に陥るリスクは大幅に軽減されます。
冒頭で解説したとおり、以前の日本では個人の返済能力を大幅に超える貸付が横行しており、生活や人生そのものが破綻する人が増加しました。自由に「いくらでも借りられる」のは良いことばかりではなく、リスクも大きいのです。
しかし総量規制ができたことで、貸金業者は個人の返済能力を調査(審査)し、一定の返済能力が担保されてから貸付額を決めるようになりました。要するに「借りすぎ」と「貸しすぎ」を同時に防ぐというリスクヘッジができるようになったのです。
ちなみに、住宅ローンやマイカーローンは総量規制から除外されます。また「おまとめローン」や緊急で必要な費用に関しては、例外で総量規制を超えた貸付が可能です。
不当な手段での取立ては違法
貸金業法では、貸金業者による違法な取り立てが禁止されています。これは返済が滞っている利用者への督促行為自体を禁止するものではありませんが、乱暴な言葉や脅迫めいた督促行為、夜中に自宅に複数人で押しかけドアを叩く、といった行為をしてはいけません。
それらの行為はフィクションではなく、貸金業法で明確化される以前は実在していました。たとえば職場に電話をかけて「借金の事実をいいふらすぞ」と脅したり、夜中でも執拗に電話したり自宅へ訪問してドアを何度も叩く、といったことが行われていました。
現行法では認可を取り消されたり、裁判に発展する可能性があるため、少なくとも正規の貸金業者で行われることはほぼなくなっています。

最大365日と無利息期間の長さが優れている消費者金融です!
原則勤務先への在籍確認も実施しておらず、書類で審査可能。
事前に返済額や総額をシミュレーションすることもできます。
レイクの詳細はこちら>>
貸金業法施行規則の内容を解説
貸金業が適正に発展していくために、貸金業者は貸金業法施行規則に従う必要があります。これは多重債務や闇金の排除、利用者を保護するために重要です。そこで次は、貸金業法施行規則の内容と重要性を、4つの点に分けて解説していきます。
登録申請に関する詳細
貸金業の登録申請を行う事業者は、貸金業法が正しく運用されるために作られた「貸金業法施行規則」に則って申請を行う必要があります。これには登録申請書や添付する所在地の登記事項証明書や写真・案内図、貸金業務取扱主任者や株主に関する書類の様式や提出方法などの、さまざまな規定が含まれます。
ここまで規則が厳格に定められているのは、行政手続きを曖昧にしないため、また貸金を行うのにふさわしくない事業者をフィルタリングするためです。これにより、貸金業業界の成長とクリーンさを両立できます。
書類や帳簿の整備と保存の義務
貸金業者は、取引を行ったすべての債務者情報を帳簿として記録し、いつでも開示請求に応じられるように準備しておく必要があります。帳簿には主に以下の情報を記録し、少なくとも10年間は保存する必要があります。
- 取引の契約日
- 貸付金額や利率、返済期間や返済方法
- 従業員の氏名や業務に従事じはじめた日付
- 返済能力に関して調査した情報
- 信用情報機関から照会した情報
これらの情報を記録した帳簿は電子的な形式でも保存可能ですが、それでも保存期間や即出力・開示ができる点など、紙面と同じ規則を遵守している必要があります。
返済能力調査の方法
貸金業者は新規顧客にお金を貸す前に必ず「貸付審査」を行い、当人に十分な返済能力があることを確認する必要があります。審査に伴い、貸金業者は「CIC」や「JICC」といったl指定信用情報機関に記録されている信用情報を参照できます。
具体的には、顧客が他社からいくら借りており、いくら返済しているか、どれだけの延滞が発生しているか、といった情報を参照できます。これらの情報を元に、最終的な融資の可否や融資額が決定されます。
くわえて、貸金業者は審査に伴って顧客から収入証明の提出を受ける必要があります。収入証明が必要となる要件は次のとおりです。
- 1社から50万円以上借り入れる
- 複数の貸金業者から100万円以上借り入れる
要するに、顧客の借り入れが自社のみで50万円以下なら収入証明はなくても可、ただし他社からの借り入れがあり、その合計額が100万円を超えている場合は必須、というルールになっています。
取立てに関する制限
貸金業法施行規則では、支払いの延滞に伴う取り立て(督促)に関して次のような行為が明確に制限されています。
- 正当な理由なく、午前9時から午後8時以外の時間帯に、債務者へ電話したり訪問すること
- 正当な理由なく、債務者の自宅以外の場所(職場等)に電話したり、メールやFAXを送信すること
- 保証人を除く第三者に対して、債務の返済を要求したり、情報を聞き出すこと
- 債務者に対して身体的・精神的に脅迫したり、困惑させるような形で取り立てを行うこと
- 債務者との融資内容や延滞の事実に関して、貼り紙や立て看板など、他者が見える形で公示すること
消費者金融などに支払い遅延の連絡を入れる際、夜8時以降は相談等の電話対応ができない、と言われた経験がある方もおられるかもしれませんが、その理由はここにあります。ただし本人の申し出がある場合(社会通念上適当である場合)は例外もあります。
規制されているのは電話だけでなく、メールやFAXも同様です。勤務先への電話連絡も原則禁止されているため、フィクション作品でありがちな「勤務先に押しかけて別室で返済するように脅す」といった行為は完全に違法であり、処罰対象となります。
第三者に対して「◯◯に返済するよう言ってくれ」というような弁済要求行為も違法です。また、本人がすでに司法書士や弁護士に相談しており受任通知が届いた場合は、貸金業者はすみやかに督促そのものを停止しなければなりません。

利用限度額が最大800円であり、膨大な資金を調達できます!
融資も最短15分で完了するためすぐに借り入れが可能。
スピーディに多額の資金を調達する際におすすめです。
モビットの詳細・申込みページへ>>
賃金業法違反に該当する禁止行為は?具体例を紹介
最後に、貸金業法違反に該当する禁止行為について、4つの具体例を解説します。
無登録で貸金業を営んだ
国と都道府県知事の認可を得ない無登録営業は闇金と同じであり、3000万円以下の罰金や10年以下の懲役の対象となります。すでに解説したとおり、貸金業法において貸金業という形態は完全登録制です。
過去にもいくつか大規模な貸金業法違反の事件は発生していますが、個人単位でも逮捕されるケースが発生しています。
- 大手銀行の元理事ら3人が無登録のまま融資を仲介し、計1.1億円を受け取り逮捕
- 三重県の女がSNSを通じて、無許可で79.5万円を貸付けて逮捕
これらが「友人にお金を貸す」のと異なる点は、継続性や反復性があること、また利息を取っていることなどです。
要するに、貸金を単なる貸し借りではなく一種のビジネスとしてやる場合は認可を受けなければならず、違反すると刑罰の対象となります。
上限金利を超過する貸付を行った
現行法においてグレーゾーン金利は存在していないため、20%を超えた貸付を行うと利息制限法違反または出資法違反となります。
とりわけ厳しいのが出資法違反であり、5年以下の懲役、法人の場合は3,000万円以下の罰金の対象となります。具体的には、以下のような事例があります。
- 東京都の貸金業者が中小企業経営者に対して法定金利の22倍で貸付を行い逮捕
- カードの現金化に伴い法外な金利での貸付を行った決済代行会社社長を逮捕
上記の1つ目のような事例は、とりわけ現代の貸金業法でも完全に規制しきれていないグレーゾーンに当たります。当該のケースではカードで高額な買い物をさせ、購入額から法外な利息を差し引いた分を現金で振り込むという手法が用いられていました。
ここまであからさまではないものの、今でも「先払い買取」などの現金化が前提のビジネスは完全に規制されておらず、業者だけでなく利用者側にとってもリスクがあるため、注意が必要です。
暴力などの違法な取立て行為を行った
すでに解説したとおり、不当な取り立て行為は明確な貸金業法違反となり、業務停止や登録の抹消、悪質なケースでは2年以下の懲役・300万円以下の罰金や、悪質な場合は強要や脅迫などのより重い罪に問われる可能性もあります。
- 大手消費者金融による暴行を伴う取り立てにより最長25日間の業務停止命令
- 沖縄県内の闇金グループ9人が悪質な職場への電話等による取り立てで逮捕
悪質な取り立てに関する事件のほとんどが悪徳業者によるものですが、そうでない場合もあります。多くの人にとって記憶に残っているのが、大手消費者金融における、暴行を伴う取り立てによる業務停止処分です。
事件からは約20年が経過していますし、同社は業務規程の抜本的な見直しを行ったため今も大手の消費者金融として知られていますが、まだ「サラ金」と呼ばれていた頃のイメージが抜けない、という方も多いでしょう。
年収200万円の人に100万円無担保で貸付を行った
貸金業者は、総量規制(年収の3分の1)を超えて貸し付けると貸金業法違反となり、業務停止・登録取り消しになる可能性があります。たとえば、年収200万円の人は総量規制により約66万円までしか融資できないため、仮に100万円を無担保で融資すると違法です。
過去には目立った事例はありませんが、新規で事業を始める業者が顧客を増やすために「敢えて融資基準を緩めた」ような事例では、このようなケースに当てはまり摘発される可能性があります。

プロミスは最短3分で即日融資可能な消費者金融カードローンです!
上限金利が18.0%であり、他の消費者金融と比較して低めです。
今なら初回利用時から最大30日間の無利息期間が適用されるキャンペーンを実施中です!
プロミスの詳細・申込みページへ>>
貸金業法の対象
貸金業法の対象となる金融機関、つまり貸金業者に該当するのは以下の金融機関です。
- 消費者金融
- クレジットカード会社
- ノンバンク
財務局または都道府県に貸金業者として登録した上でお金を貸す業務を行っている上記の金融機関は貸金業法の対象になります。
貸金業法対象外の金融機関
お金を貸す業務を実施していても貸金業法の対象外になるのは以下の金融機関です。
- 銀行
- 信用金庫
- 信用組合
- 労働金庫
上記の金融機関は銀行法の対象なので、貸金業法の対象になりません。

最大365日と無利息期間の長さが優れている消費者金融です!
原則勤務先への在籍確認も実施しておらず、書類で審査可能。
事前に返済額や総額をシミュレーションすることもできます。
レイクの詳細はこちら>>
まとめ
多重債務が社会問題になり大きく貸金業法が改正されたことで、お金を借りる側・貸す側の両方の安全性が担保され、多重債務に苦しむ人は一定数減少しました。
一方で未だに解決されていない課題やグレーゾーンは存在するため、サービスを利用する側として常に金銭的リテラシーを培い、返済能力を超えて借りすぎないように注意していきましょう。

利用限度額が最大800円であり、膨大な資金を調達できます!
融資も最短15分で完了するためすぐに借り入れが可能。
スピーディに多額の資金を調達する際におすすめです。
モビットの詳細・申込みページへ>>
参考文献
https://www.asahi.com/articles/ASS9L3RK2S9LUTIL037M.html
https://www.corporate-legal.jp/news/2782
https://sp.m.jiji.com/article/show/3491662
https://www.sp-network.co.jp/column-report/column/bouhi/candr0344.html
この記事を書いた人
エレビスタ ライター
エレビスタは「もっと"もっとも"を作る」をミッションに掲げ、太陽光発電投資売買サービス「SOLSEL」の運営をはじめとする「エネルギー×Tech」事業や、アドテクノロジー・メディアなどを駆使したwebマーケティング事業を展開しています。
エレビスタは「もっと"もっとも"を作る」をミッションに掲げ、太陽光発電投資売買サービス「SOLSEL」の運営をはじめとする「エネルギー×Tech」事業や、アドテクノロジー・メディアなどを駆使したwebマーケティング事業を展開しています。