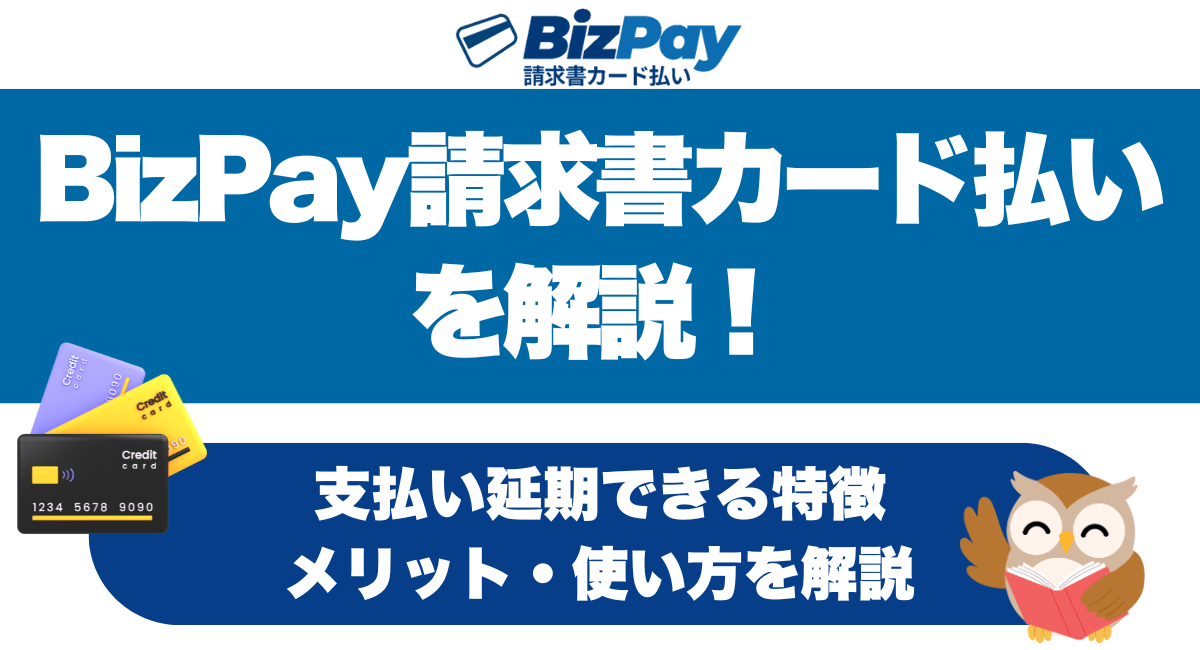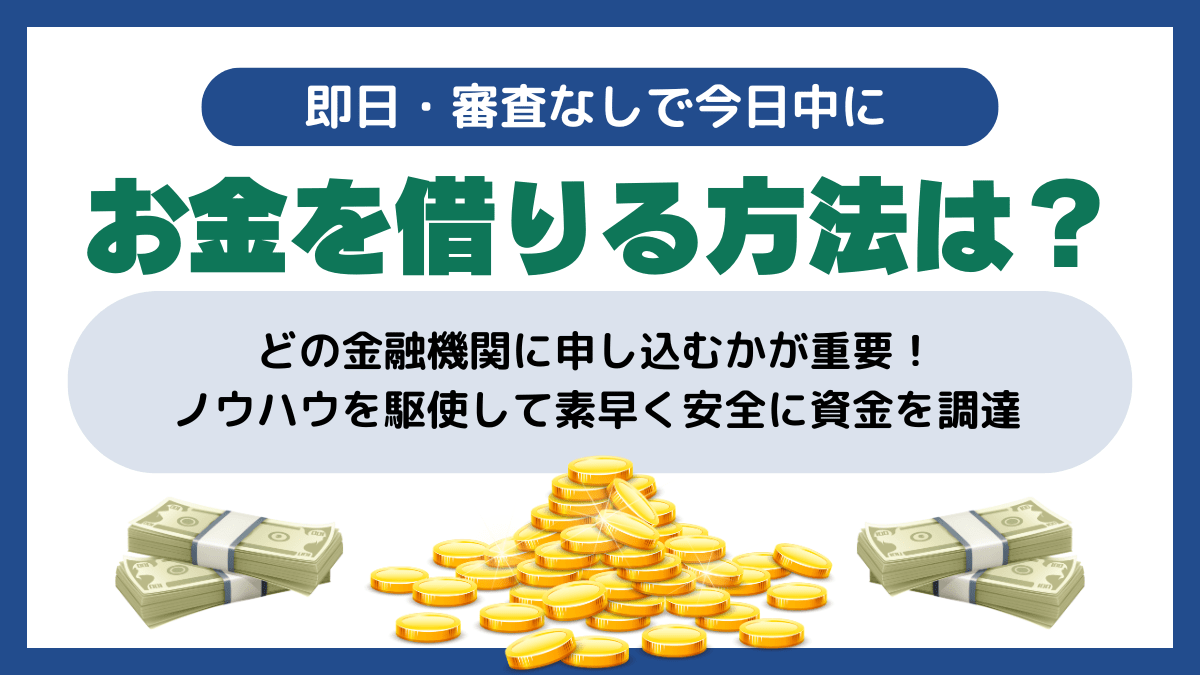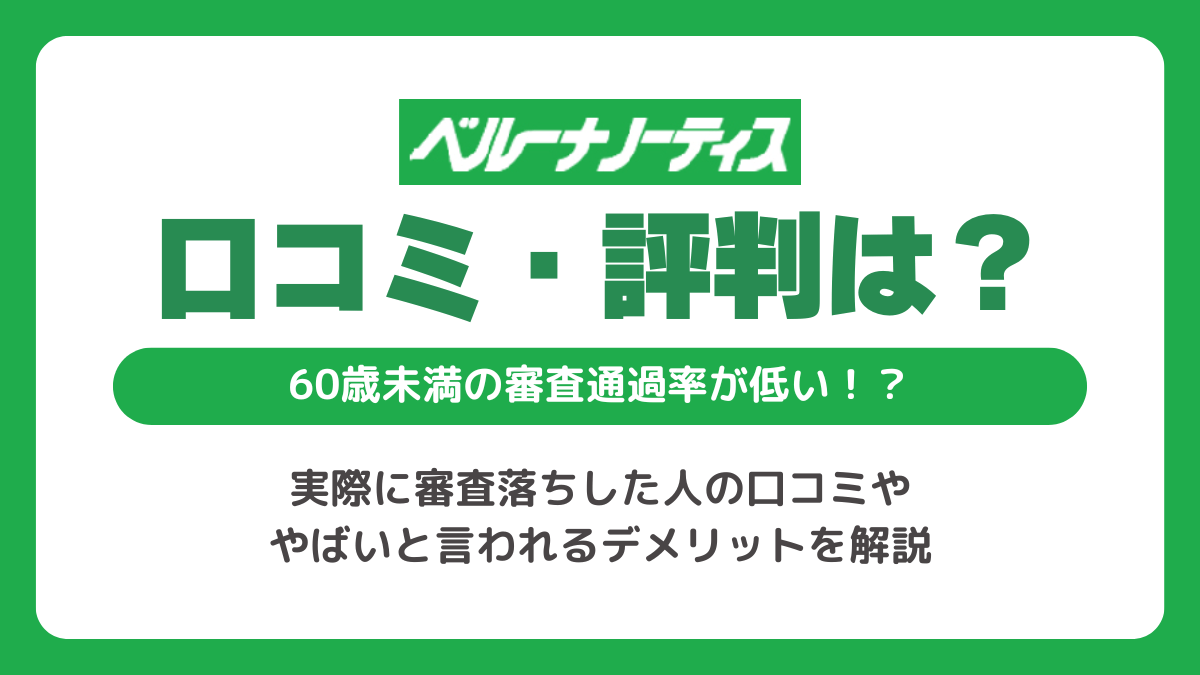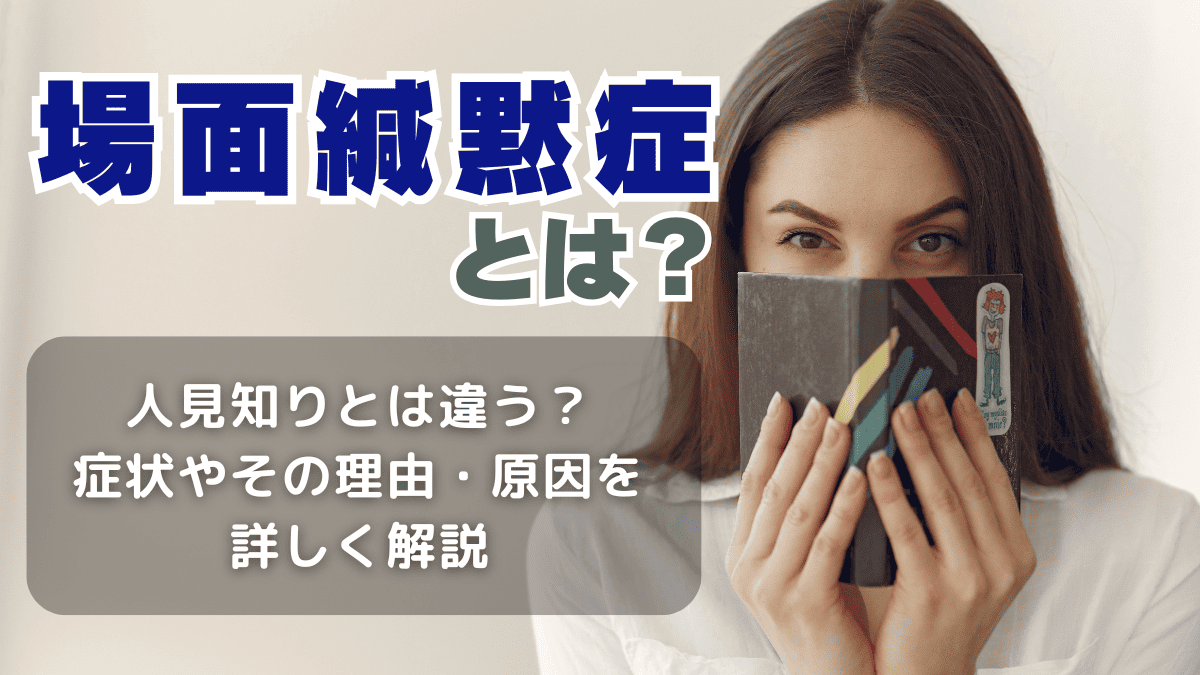江戸時代の商いから始まり、日本の近代化と共に歩んできた巨大企業があります。その中でも、呉服商の「現金掛け値なし」という革新的な商法で成功を収め、明治維新の激動を乗り越え、やがて日本最大の財閥へと成長したのが三井財閥です。
日本の経済史に燦然と輝くこの巨大財閥は、政商として明治政府との緊密な関係を築き、銀行・商社・鉱山・製造業に至るまで多角的に事業を展開しました。
第二次世界大戦後の解体を経ても、その遺伝子は三井グループとして脈々と受け継がれています。272年にわたる三井の歴史は、日本企業の挑戦と変革、そして持続的成長の物語そのものなのです。
今回は、三井財閥の歴史や現代の三井グループ、SDGsとの関わりについて解説します。
目次
三井財閥とは
三井財閥とは、三井家が支配した財閥です。江戸時代に両替商・呉服商として大きな成功を収めた三井家は、明治維新後の1876年に三井銀行と三井物産を設立し、さらに三池炭鉱の払い下げを受けて事業基盤を固めました。*1)
そして、1909年から1911年にかけて主要事業を株式会社化し、三井合名会社を設立してコンツェルン形態を整えました。この組織形態は他の財閥の模範となりました。
その後、三井信託や三井生命などの子会社、東洋レーヨンや小野田セメントなどの孫会社を次々と設立し、特に製造部門は三井物産と三井鉱山の子会社を中心に拡大しました。
1944年に三井本社へと改組されましたが、第二次世界大戦後の1946年、財閥解体政策により解散することとなり、以後は三井グループとして戦後経済の一翼を担いました。
財閥とは
そもそも財閥とは、持ち株会社を中核として多角的な経営を行った企業集団です。財閥の代表例として挙げられるのが三井・三菱・住友・安田で、これらは「四大財閥」とよびます。また、規模が比較的小さい安田を除いた三社を「三大財閥」と呼ぶこともありました。*3)
三井財閥の歴史:江戸期

三井は、江戸時代に創業した「老舗」の財閥です。ここでは、創業者の三井高利やその後の三井の事業拡大についてまとめます。
三井高利が日本橋で呉服屋を創業
三井財閥の基礎を築いたのが三井高利という人物です。伊勢(三重県)の松阪にあった商家の出身で、14歳のときに江戸にやってきました。先に店を開いていた兄の下で商売を手伝い、28歳で松阪に帰ります。その後、資金を蓄え52歳のときに江戸で自分の店を開きました。この時の店の名が「越後屋」です。*4)
高利は、それまで主流だった掛け売り(後払い)をやめ、商品の受け渡しと同時に代金を受け取るようにします。また、定価に上乗せした「掛け値」を廃止し、呉服の定価販売を始めました。この高利のやり方は「現金掛け値なし」と呼ばれました。*5)
三井の大成功
高利の「現金掛け値なし」は、江戸で急増する呉服の需要をとらえ、越後屋は急成長を遂げました。他にも、高利は様々な工夫を行っています。たとえば、仕入れを工夫し安いときに大量に仕入れて、その時々の相場に応じて売却して利益を上げる方法をとりました。
こうした商売の工夫により、江戸出店からわずか10年で売上高が5倍にまで成長しました。その活躍は、大ベストセラー作家の井原西鶴の目にもとまり、作中に高利をモデルとする人物まで現れました。*5)
そして、ついには金融部門にまで進出します。三井は、創業の地である日本橋から駿河町に移転していましたが、この時に両替店を併設したのです。
両替商は江戸時代に活躍した金融業者で、現代の銀行の先駆けです。主な仕事は金貨、銀貨、銅貨の交換や、預金、貸付、送金などのサービスを提供することでした。複雑な貨幣制度や地域による使用貨幣の違いから、両替商の存在が不可欠でした。
三井財閥の歴史:明治・大正期

江戸時代に着々と財力を蓄えた三井家でしたが、幕末から明治維新の時期に大きな危機を迎えます。その危機を乗り越えた三井家は、財閥として急成長していきました。ここでは、幕末の危機とその後の成長について解説します。
幕末の危機
江戸時代の終わりから明治時代の始めにかけて、三井家は何度も倒産しそうになりました。当時、日本が外国と貿易を始めたとき、三井家は横浜に店を開いて幕府のお金を扱う仕事をしていましたが、経営がうまくいかず、幕府から預かった資金に手を出してしまいました。さらに幕府から多額の御用金を要求され、ますます苦しくなりました。
そんなとき、三野村利左衛門という人物が三井家を助けました。彼は幕府の小栗忠順と親しく、要求されたお金を減らしてもらうことに成功し、三井家の重要な役職に就きました。
江戸幕府と新しい政府が戦った時期には、三井家は両方と関係を保ちながらも、最終的には新政府にお金を提供して支持しました。その後、明治時代になると、三井家は他の二つの商家と一緒に新政府の財政を支えました。
他の商家が倒産する中、三井家は外国の銀行からお金を借りたり、政府の保護を得たりして生き延びました。この生き残りが、後に三井が大きな財閥に成長する基礎となったのです。*7)
政商として地位を確立
明治維新後、三井家は政商としての地位を確立していきます。政商とは、政府や政治家と結びついて利益を得る商人のことです。*7)三井は、政府による「太政官札」発行をサポートすることで、政府の信用を得ます。さらに、1876年には三井銀行を創業するなど、金融部門を強化していきました。
また、1880年代には政府が行った官営工場の払い下げにおいても、政府から安く工場を売却してもらうといった便宜を図ってもらっています。
こうして、三井は政府との距離を縮めていったのです。
三井財閥の歴史:昭和期

三井財閥の拡大は、第一次世界大戦後も続きました。しかし、三井に対する反発も強まり、血盟団事件では三井のトップが暗殺されます。その後、三井も他の企業と同じように戦時体制に組み込まれ、終戦後のGHQによる統治の中で解体されてしまうのです。
三井財閥や他の財閥の拡大
昭和期に入ると、三井財閥は第一次世界大戦後から進めていた重化学工業への進出に加え、信託・保険などの金融事業にも多角化を図りました。昭和初期には、三井合名会社を頂点に、銀行・鉱山・貿易など多岐にわたる事業を傘下に収め、日本最大の財閥へと成長しました。
三菱や住友も同様に持株会社制を採用し、銀行・鉱山事業を基盤に重化学工業へと勢力を拡大しました。1920年代の不況下でも、これら三大財閥はむしろ力を強め、昭和4年には日本の主要100社の総資産の28%を占めるまでになっていたのです。
この時期の三井財閥の中心である三井合名会社は、株式配当を主な収入源として大正末から昭和初期にかけて毎年2,000万円以上の純益を上げ、その資産は昭和5年には約3億8,000万円に達し、日本最大の財閥としての地位を不動のものとしました。*9)
血盟団事件
血盟団事件は、1932年に井上日召を中心とする国家改造を目指した一団によるテロ事件です。同年2月9日に前大蔵大臣の井上準之助が殺害され、続いて3月5日には三井合名会社理事長の団琢磨が菱沼五郎によってピストルで射殺されました。
事件の背景には、支配階級への不満や農村の貧困、社会主義思想の広がりがありました。井上日召は茨城県の立正護国堂に籠もり、小学校教員や農村青年、さらに海軍将校や大学生まで取り込んで「一人一殺」という過激な行動計画を立てました。
団琢磨の殺害は財閥への攻撃という側面を持ち、その後の五・一五事件とともに政財界の右傾化を促進することになりました。犯人たちは裁判の結果、首謀者と実行犯に無期懲役などの刑が言い渡されましたが、1940年には全員が恩赦で釈放されています。
戦時経済と三井
満州事変から太平洋戦争に至る戦時経済の進行において、三井財閥は大きな変革を迫られました。軍需中心の重化学工業への事業拡大により、三井の総投資額は1937年に6億円を超える規模となりました。*10)
1943年には三井銀行と第一銀行が合併して帝国銀行が発足し、三井系列企業への融資体制が強化されました。
戦時中の三井は、一時期軍部や右翼からの批判を受けながらも、積極的に国策に協力し、石炭・金属鉱業などの軍需産業の基幹を担いました。さらに満州や中国、東南アジアの占領地域へも進出し、軍の要請に応じて各地の鉱山や精錬所の経営を担当したのです。
財閥解体
三井家にとって財閥解体は、272年続いた同族経営の終焉を意味しました。1945年、GHQによる占領政策の一環として財閥解体が進められると、三井家は同族会議で自主的な解散を決議します。これにより長い歴史を持つ三井財閥の組織的枠組みは崩壊しました。
1947年には三井十一家が「財閥家族」に指定され、資産が凍結されます。さらに財産税により資産の大部分が没収され、三井家は経済的基盤を大きく損なうことになりました。所有していた有価証券も不利な条件で売却処分を強いられました。*11)
三井物産をはじめとする主要企業の解散や分割も三井家にとって大きな痛手でした。また、「三井」という商号の使用制限も課されました。三井家の古参幹部たちは公職追放され、経営の場から退くことを余儀なくされました。
このように三井家は財閥解体によって経済的・社会的地位を大きく後退させましたが、後年には三井グループとして、緩やかな連携を保ちながら日本経済に影響力を持ち続けることになります。
三井グループの歴史:戦後〜現在

戦後、三井財閥は解散しましたが、旧三井財閥の企業は三井グループとして日本経済に影響を与え続けます。ここでは、戦後から現在の三井グループについて、簡単に説明します。
戦後の三井グループ
戦後に成立した三井グループは、戦前の財閥解体を経て新たな形で再結集した企業集団です。1950年代に旧三井財閥系企業の社長が集まる「月曜会」が発足し、これが後の「二木会」へと発展しました。
三井グループの中核を担ったのは、三井銀行(現・三井住友銀行)、三井物産、三井鉱山、東洋レーヨン(現・東レ)などです。これらの企業は株式持合いや融資関係を通じて緩やかな結びつきを維持しながらも、各社が独立した経営を行うという特徴がありました。
平成以降、業界再編の波により三井グループ企業も大きく変化しています。銀行や保険会社を中心に住友グループとの合併が進み、三井住友銀行や三井住友海上など「三井住友」の名を冠する企業が誕生しました。こうした再編を経ても、歴史ある「三井」の名と伝統は日本を代表する企業グループとして今日も受け継がれています。
三井グループとSDGsの関わり

江戸時代から現代まで、三井家や三井財閥、三井グループは日本経済に大きな影響を及ぼしてきました。その間、様々な変化に対応したからこそ、現代まで巨大企業グループとして存続しています。ここでは、現代の大きな流れであるSDGsに対して、同グループの企業である三井不動産がどのように対応しているのかを見ていきます。
SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」との関わり
三井不動産は、SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」に対して積極的な取り組みを展開しています。同社は北海道道北地方を中心に約5,000ヘクタールの森林を所有・管理し、「終わらない森」創りを実践しています。この森林は年間約2万1,315トンの二酸化炭素を吸収・固定し、約7,400世帯分の排出量に相当する環境貢献を果たしています。*12)
同社は「植える」「育てる」「使う」という持続可能な森林サイクルを通じて、気候変動対策に寄与しています。人工林と天然林をバランスよく保有し、適切な管理を行うことで生物多様性も保全しています。これらの取り組みが評価され、「森林管理認証(SGEC)」や「フォレストック認定」を取得しています。
また、環境教育にも力を入れており、社員や子どもたちに森の大切さを伝える活動や、社員参加型の環境研修を実施しています。このように三井不動産は、森林を通じた具体的な気候変動対策を推進しています。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
今回は、三井財閥について解説しました。三井財閥は、江戸時代に両替商・呉服商として財を成した三井家が、明治維新を経て設立した三井銀行や三井物産などを基盤に、巨大なコンツェルンへと発展した企業集団です。
三井家は、創業者の三井高利が打ち出した「現金掛け値なし」の商法で成長し、江戸時代には金融業にも進出しました。幕末から明治維新にかけては、政府との関係を巧みに築きながら政商として台頭し、官営工場の払い下げなどを通じて事業を拡大しました。
昭和に入ると、三井財閥は重化学工業や金融事業への多角化を進め、日本経済を牽引する存在となりました。しかし、その一方で血盟団事件のような反財閥感情の高まりにも直面しました。戦時体制下では軍需産業の中核を担いましたが、第二次世界大戦後、GHQの財閥解体政策により解散を余儀なくされました。
戦後、旧三井財閥系企業は三井グループとして再結集し、日本経済の復興と成長に貢献してきました。今日では、三井グループの企業は、三井不動産のようにSDGs目標達成に向けた積極的な取り組みを行っています。
参考
*1)山川 日本史小辞典 改定新版「三井財閥」
*2)山川 日本史小辞典 改定新版「コンツェルン」
*3)山川 日本史小辞典 改定新版「財閥」
*4)精選版 日本国語大辞典「三井高利」
*5)三井文庫「三井のあゆみ 現金掛け値なし」
*6)三井広報委員会「三井の苦難(後編)」
*7)デジタル大辞泉「政商」
*8)百科事典マイペディア「官業払下げ」
*9)三井文庫「三井の歩み 三井の規模」
*10)改定新版 世界大百科事典「三井財閥」
*11)三井広報委員会「三井財閥の解体(後編)」
*12)三井不動産「未来に続く終わらない森創り」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。