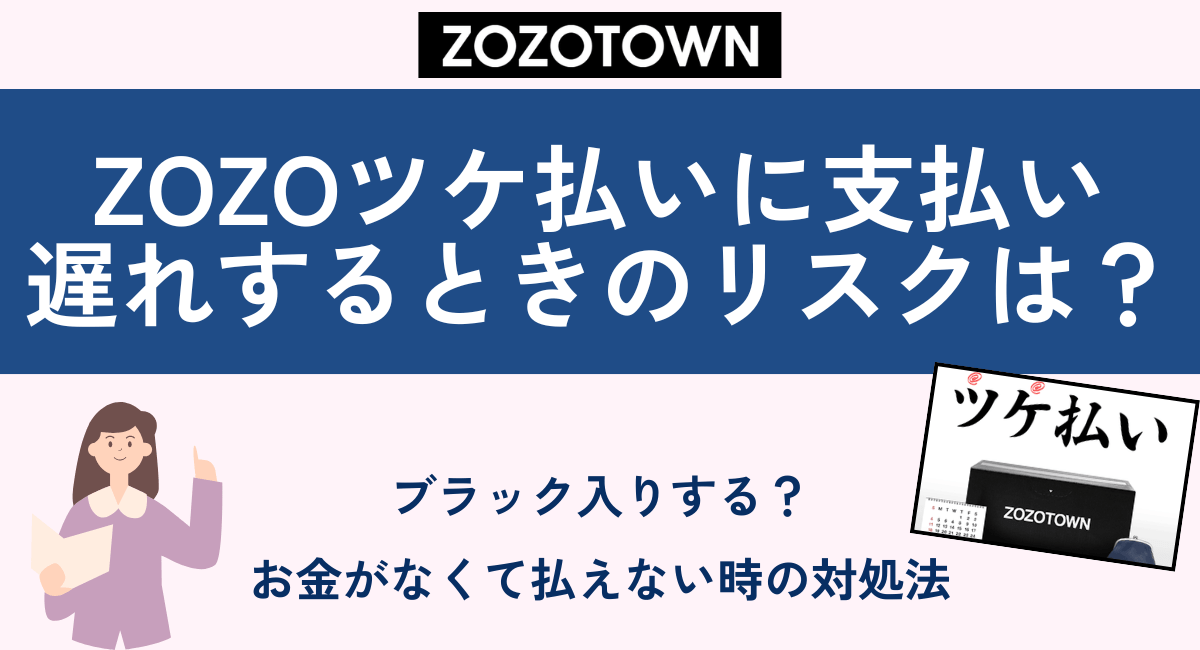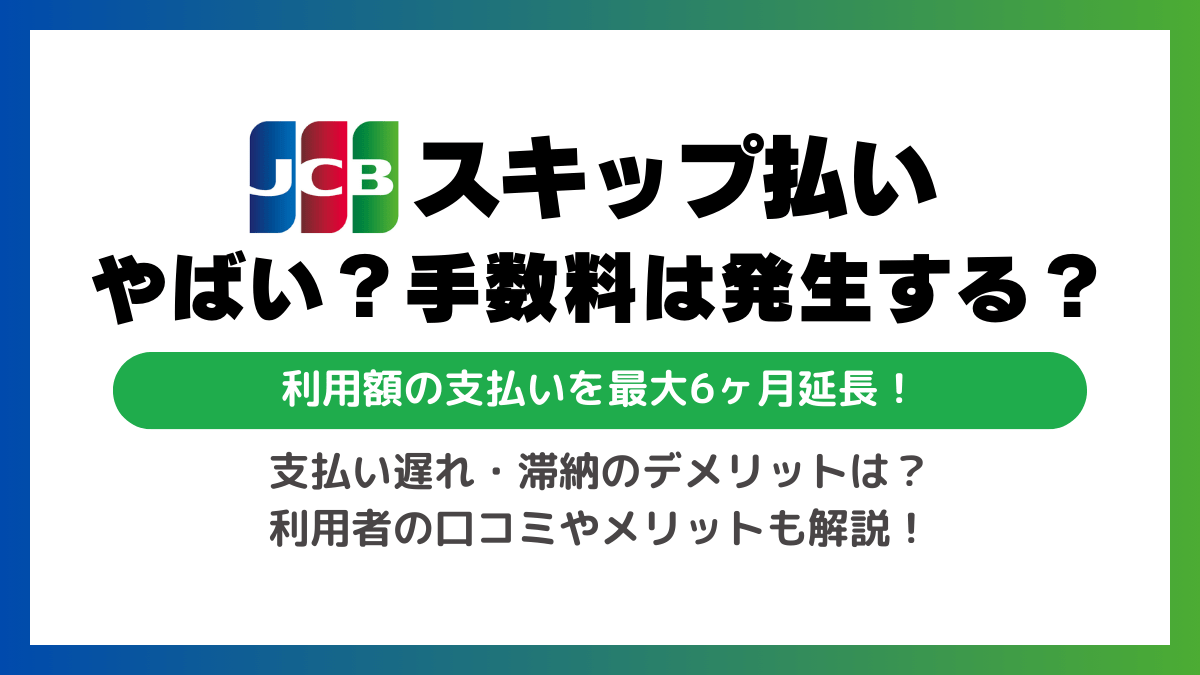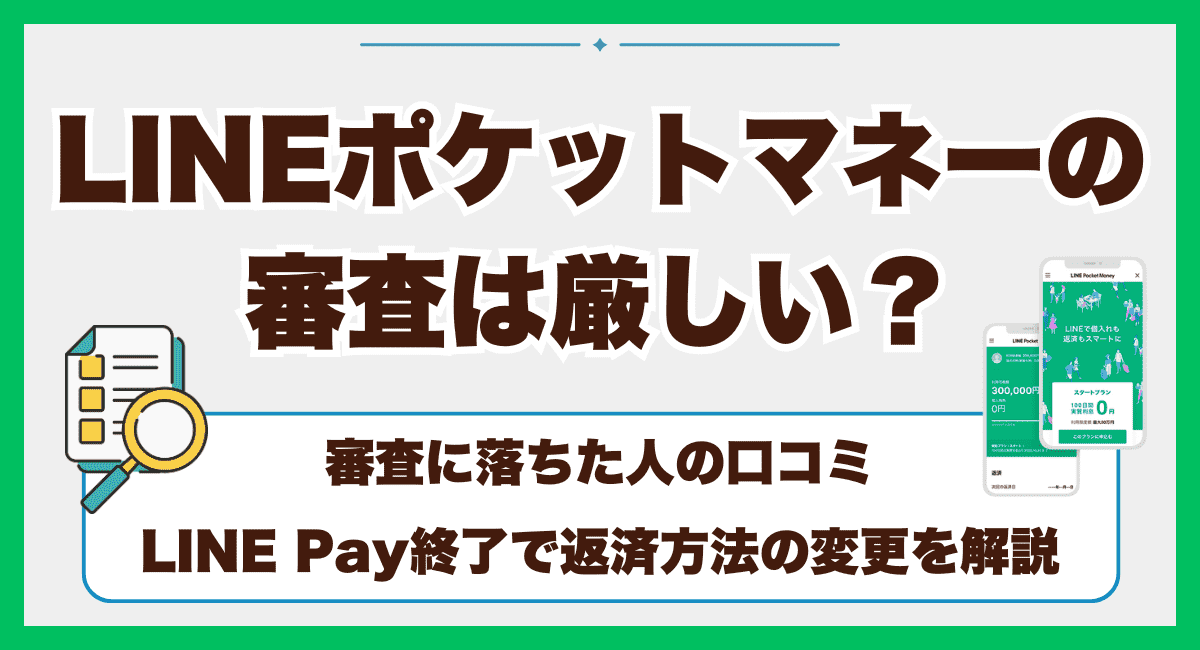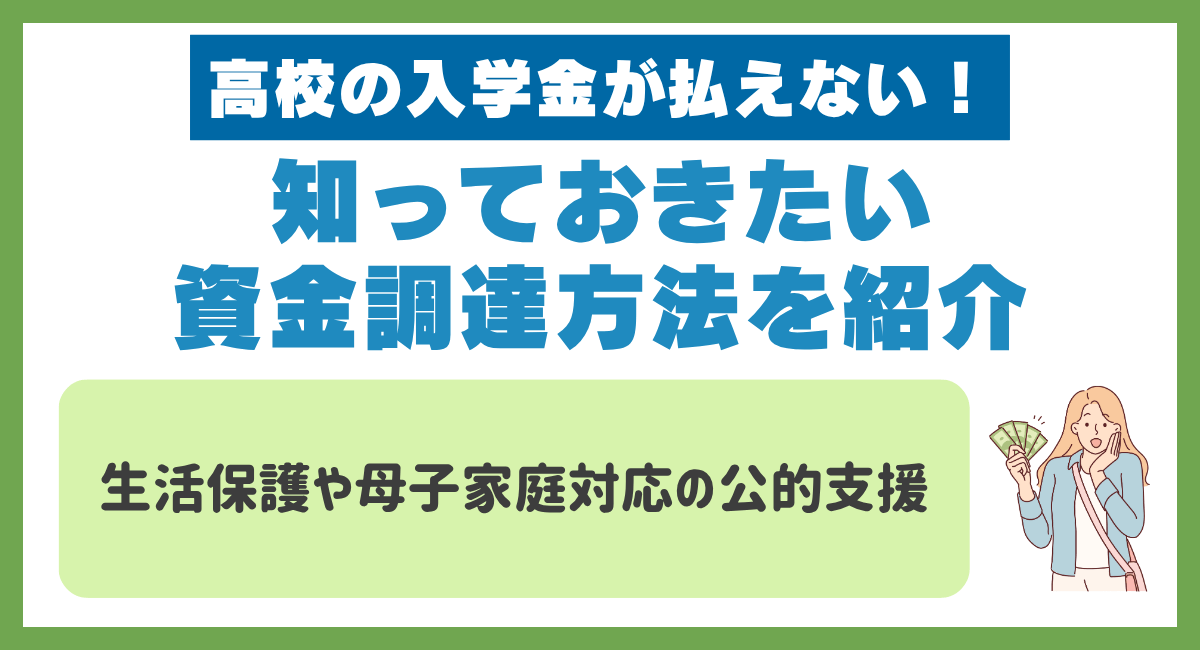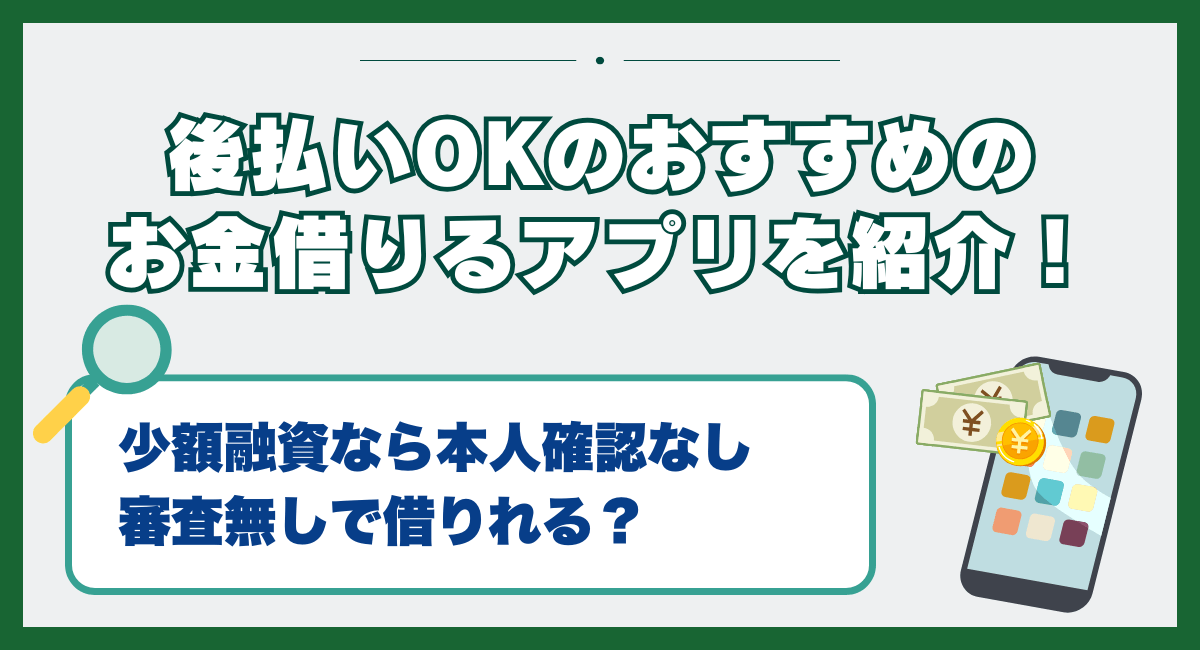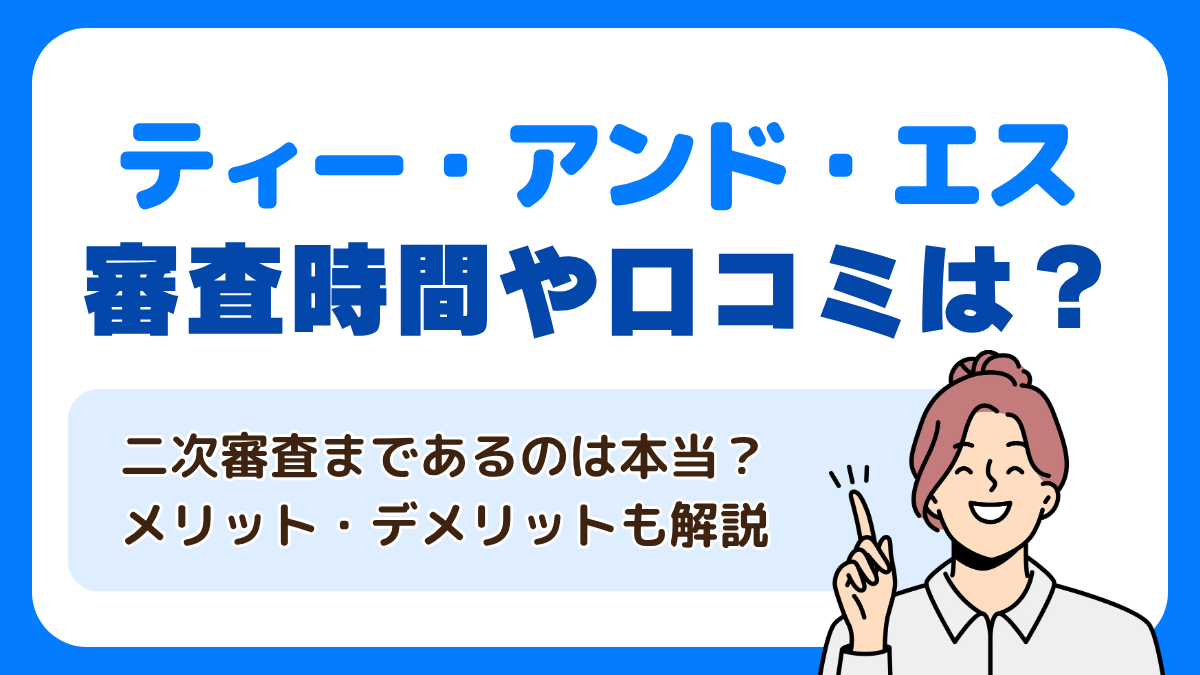NPO法人ぱれっと 南山さん インタビュー

南山
東京生まれ。明治学院大学社会学部卒。学生時代よりぱれっとでボランティアを始め、1991年に同会が開店した「スリランカレストランぱれっと」(障がい者、外国人、健常者がともに働く飲食店。株式会社が運営)では店長を務める。2013年より事務局長に就任。同会が手掛ける各事業の統括・広報・人材育成・資金調達など、対外的、対内的に広く担当している。
目次
introduction
NPO法人ぱれっとは、「余暇」「就労」「暮らし」「国際協力」を柱に、障がいのある人が生活や人生においてさまざまな選択肢を持てるよう支援してきました。
40年を超える歴史の中でさまざまな課題に直面するたびに「これは自分(健常者)の人生では当たり前のことと言えるのか」と問い続けてきた事務局長の南山さん。
今回は南山さんに、そんなNPO法人ぱれっとの変化の歴史や、現在向き合っている課題などについてお伺いしました。
変化の中で見出した4つの柱
–まずは事業内容のご紹介をお願いいたします。
南山さん:
「ぱれっと」は、今年で41年目を迎える認定NPO法人です。「ぱれっと」という名前の由来は「絵画の道具のぱれっとにたとえて、障がいの有無や人種などを越えて、さまざまな人たちが出会い交流し新たな色(可能性)を生み出すこと」を表しています。
特に「余暇」「就労」「暮らし」などの場面で、障がいのある人が直面する課題を解決し、すべての人が当たり前に暮らせる社会の実現を目指しています。
この「当たり前に暮らせる」という表現を少し噛み砕いて説明すると、私たちのような健常者が当たり前に選択できることが、彼らも選択可能な状態になっていることを指します。例えば、「将来はあの仕事に就いてみたい」「あそこに住んでみたい」と考えるのは当然のことですよね。
にもかかわらず、「そんな制度はない」「そんなサービスはない」などといった理由で自由な選択肢が持てずにいるのだとしたら、それは「当たり前」の状態ではありません。そんな状況を変えていくために活動しています。
–現在は「余暇」「就労」「暮らし」に加え、「国際協力」の分野でも活動をされていますよね。活動の4つの柱について、具体的な内容をお伺いできますでしょうか。
南山さん:
そうですね、40年の歴史の中でいろいろな変化があり、現在は「余暇」「就労」「暮らし」に加えて、「国際協力」4つの柱を掲げて活動しています。
まず「余暇」の取り組みにあたるのが「たまり場ぱれっと」です。これは公園に遊びに行ったり、ハロウィンパーティーなどの季節の行事を行ったりなど、月1回仲間が集まって交流するというものです。ヒップホップのダンスチームや劇団などのクラブ活動もあります。
ぱれっとのすべての活動に通じることですが、ここでのポイントは活動は「障がい者のために」ではなく「みんなで一緒に」行うことです。それが私たちの目指す当たり前に近い状態だと思っています。

「就労」の面での支援事業では、「おかし屋ぱれっと」「工房ぱれっと」を運営しています。「おかし屋ぱれっと」ではクッキーなどのお菓子を、「工房ぱれっと」ではオリジナルキャラクターの「らぶらび」というウサギのぬいぐるみや、ヘアゴムなどの製造販売を行っています。
こうしたお菓子や小物などの商品を扱うことで、相手に感謝してもらえる場面を作っているのがポイントなんです。「この間のクッキー、美味しかったからまた買いにきたよ」などと声をかけてもらえれば、働く喜びや世の中の役に立つ喜びが感じられます。私はこれこそが就労支援だと思っているんです。
ぱれっとが活動を始めた1993年頃の障がい者の就労というのは、企業から委託を受けてアパートの一室で箸を袋に入れるなどの単純な軽作業が中心の時代でした。ただ、そのような作業で自己有用感を見出すのは難しいことです。
近年ではこのような取り組みをする就労支援はかなり増えてきましたが、その広がりを生み出す役割の一部を果たしたのがぱれっとだと自負しています。
また、近年ではアート関連の就労支援も盛んになってきています。彼らの独特の感性を書体や模様、絵画で表現して、企業や公共団体の建物や印刷物などに取り込んでいく。私たちの地元渋谷区では全域を巻き込みながら官民が一体となった「シブヤフォント」という取り組みが始まっています。

【関連記事】一般社団法人シブヤフォント|多様性と包括をキーワードに、アートと福祉とビジネスを融合
–「暮らし」と「国際協力」はいかがでしょうか?
南山さん:
「暮らし」に関しては、1993年からの「えびす・ぱれっとホーム」と、2016年から始めた「しぶや・ぱれっとホーム」の2箇所のグループホームを運営しています。2つ合わせて15人程度の利用者が職員のサポートで生活しています。

また、「国際協力」は「ぱれっとインターナショナル・ジャパン」として、私たちの日本での取り組みを海外でも実践してもらえるよう、主にアジアの国々の現地団体と手を結んで、交換研修プログラムや現地でのワークショップなど、交流や直接的な支援を行っています。
目の前の課題に向き合い変化してきた40年
–そもそも、なぜこの4つが活動の柱となったのでしょうか?また、ぱれっとのこれまでの歩みについても教えてください。
南山さん:
最初から「この4つの柱でいこう」となったわけではありません。私たちの考える「当たり前」に近い社会を作るためにニーズに応えつつ目の前の課題に向き合ってきた結果、今の形になったというのが正確なところです。
ぱれっとの活動のもとになっているのは、渋谷区教育委員会が主催していた「えびす青年教室」でした。これは様々な社会教育プログラムを行って障がい者の仲間作りを支援する取り組みです。ところが開催は月1回、場所も社会教育館という閉ざされた建物の中で、その場に来る人のほとんどが障がいがある人というのでは活動の広がりに限界があります。これでは本当の意味の仲間作りではありません。
そこで「えびす青年教室」の有志が立ち上げたのが今のぱれっと、そして障がいの有無にかかわらず、あらゆる人が緩い繋がりを持てる場所である「たまり場ぱれっと」なのです。
現在はさまざまなところで居場所作りが行なわれていますが、まるでその先駆けのような形ではないでしょうか。
–「たまり場ぱれっと」が最初の取り組みだったのですね。
南山さん:
そうですね。ただ、そこからまた新たな問題に直面していくことになります。
「たまり場ぱれっと」にいる仲間に就労について聞いてみると、職場の人間関係がうまくいかない、そもそも仕事自体が上手くこなせない、やりがいを見出せない、という声が多く上がっていたのです。
そこで今度は「おかし屋ぱれっと」を作ったわけですが、関係者から話を聞くうちに、ここでも新たな問題に気がつくことになりました。障がいがある人は仕事を持つことが直接経済的な豊かさには繋がらないケースが多いということ、そして現状彼らを支えている親が亡くなったあと、彼らの暮らしをどのように支えていくのかという問題が解決されないままになっていることです。
そしてこのような「暮らし」に関する問題の解決を目指し、開設に至ったのがグループホームです。このように、私たちはその時直面した切実なニーズに対処しながら活動の幅を広げてきました。
これは国際協力に関しても同じことです。障がい者と外国人、健常者がともに働くというコンセプトの「スリランカレストランぱれっと」を1991年にオープンさせたことからスリランカとの交流が始まり、その中で海外にも障がい者支援への切実なニーズがあることを知りました。
そこから海外にも足を運ぶようになり、アジアなどの近隣の国では、ぱれっとが活動を始めた頃の日本以上に閉ざされた、劣悪な環境で障がいのある人が生活しているとも知るようになります。そのような各国の状況を変えたい、これまでの自分たちの取り組みを他の国にも伝えていきたいと願ったのが、国際協力の始まりです。
例えば最初に交流が始まったスリランカでは、現地の人たちのニーズに応える形で、クッキーを生産する作業所「Sri Lanka Palette(現在は閉所し現地の企業に委譲)」の運営に至っています。
助け合いの形を作りたい
–何度も課題に直面してきたぱれっとですが、現在課題に感じているのはどのようなことでしょうか?
南山さん:
「暮らし」に関する問題はいまだに多く、特に「8050問題」と「高齢者福祉への円滑な移行」の問題は深刻です。
まず8050問題とは、親が80歳、子どもが50歳ということを表していて、親が体力の続くギリギリまで子どもの面倒を看ざるを得ない現状を言います。
こうなると万が一親が倒れたり病気で入院したりすれば、子どもは自分で生活することなどできず、途方に暮れてしまいます。生活が上手く回らないだけでなく、亡くなってしまうようなこともあるほどです。
そこまでの事態にはならなくても、近隣のグループホームと条件が合わずに本人が望まない遠方への引越しを余儀なくされ、また新しい土地で一から生活を始めなければならないケースもあります。これは私たちの目指す「当たり前の選択が当たり前にできる社会」とは程遠いものです。
また、「高齢者福祉への円滑な移行」とは、障がい者福祉から高齢者福祉へ、いかにスムーズに移行させるかという課題です。近年は医療が進歩して、以前よりも障がいのある人が長く人生を歩めるようになりました。これは喜ばしいことである反面、障がい者に新たな困難を生んでいる側面もあります。
これまで障がい者福祉からサポートを受けてきた障がい者も、65歳になった際には原則として高齢者福祉にサポート体制を切り替えなければならないからです。この連携に課題があります。
障がい者福祉を担当するのは「相談支援員」、高齢者福祉を担当するのは「ケアマネジャー」ですが、この両者はまったくの別物で、現在はお互いの仕事がなかなか見えにくい状況にあります。
65歳以降、これまで受けてきたサービスが変容していってしまうような感覚です。
かといって、65歳以降も障がい者支援が続けられるような制度ができるとも期待できません。障がい者支援は税金が財源であるのに対し、高齢者支援は徴収した保険料が財源なので、国としては負担の少ない高齢者支援に移行したい考えがあるでしょう。
増え続ける高齢者を支えるのも日本の深刻な課題ですから、それはお互い様です。
–そのような課題に対して、現状ではどのようなアプローチをされているのでしょうか?
南山さん:
私たちのような小さな団体は、国のように制度を整えることはできません。ただ、ある程度の制度が整ったあと、その先にある豊かさを創造していくのは、私たちのような活動をしている者を含めた一人ひとりの課題だと思っています。
水を引く、橋を架けるのは行政の仕事でも、その橋を渡って人と交流したりコミュニティを作ったりするのは市民の役割ということです。
現状の課題に対する具体的なアプローチはまだ模索している段階というのが正直なところですが、社会の中でのつながりを作っていく取り組みというのが、私たちにまずできることだと思っています。
ぱれっとでは制度外の取り組みとして、シェアハウス事業も行っています。障がいのある人だけでなく、健常者と呼ばれる人も、同じ入居者として助け合いながら一緒に生活する形です。「障がいがあるから」と分断するのではなく、緩やかなつながりが保たれている状態が本来の形なのではないかとの思いから挑戦しました。
今後もその時々の課題に真摯に向き合い、誰もが当たり前に暮らせる社会を実現していきたいですね。
–今後の活動も楽しみです。本日は貴重なお話をありがとうございました。
この記事を書いた人
スペースシップアース編集部 ライター
スペースシップアース編集部です!
スペースシップアース編集部です!