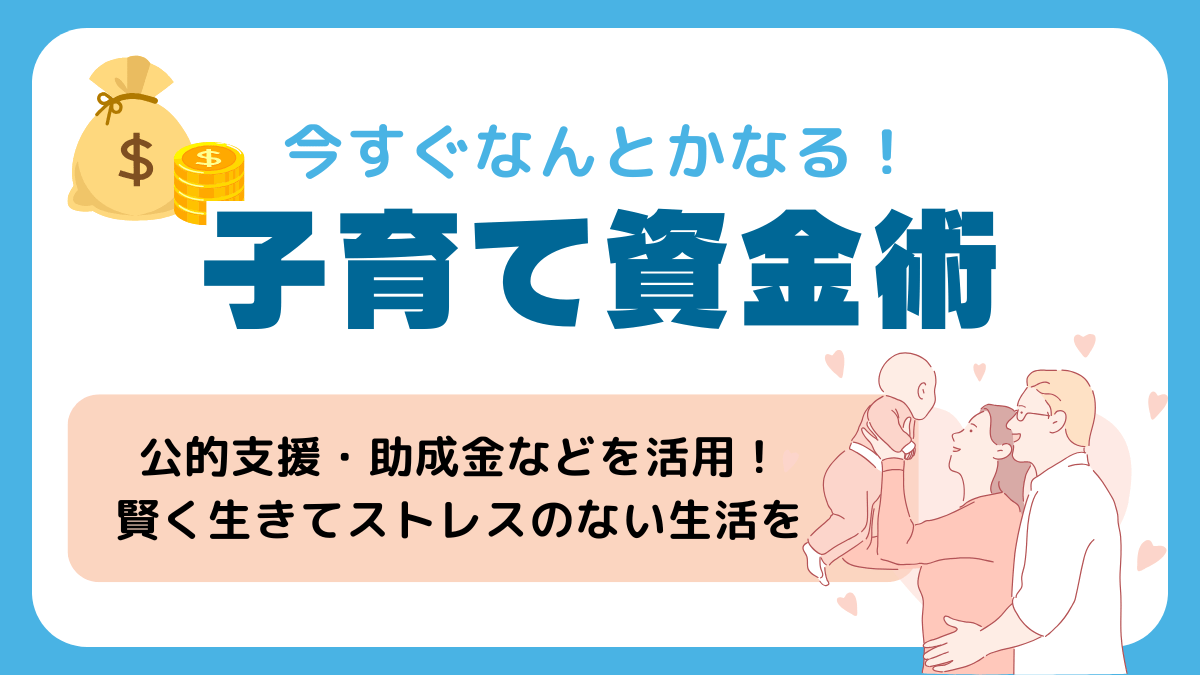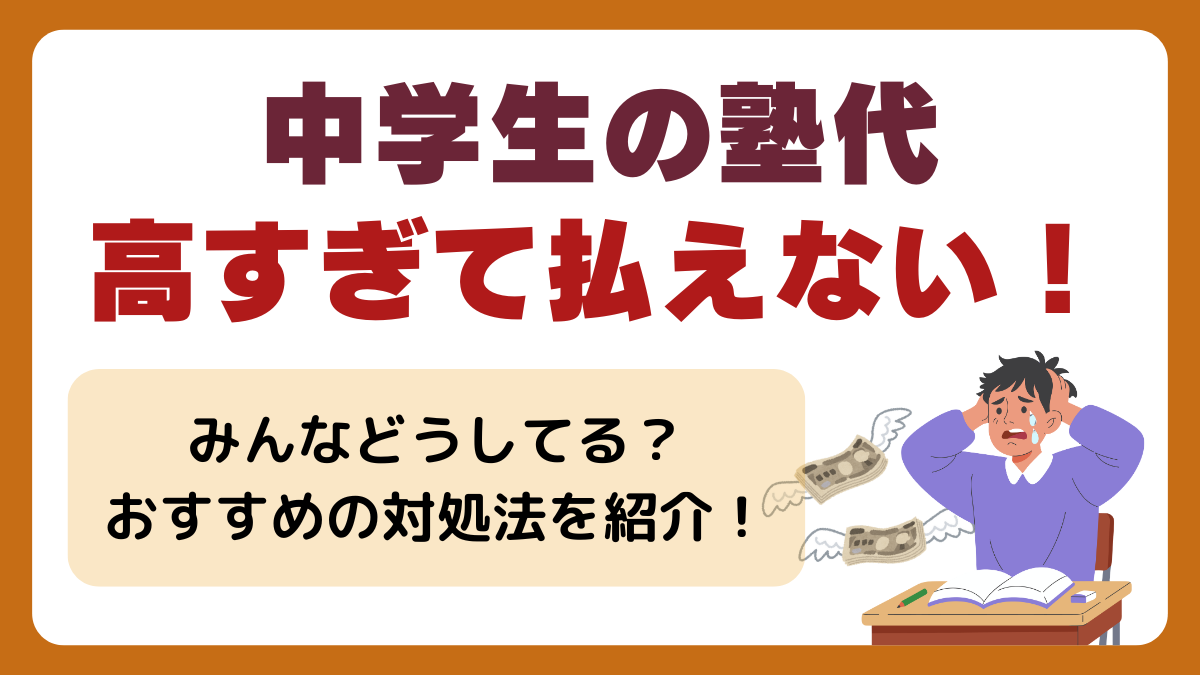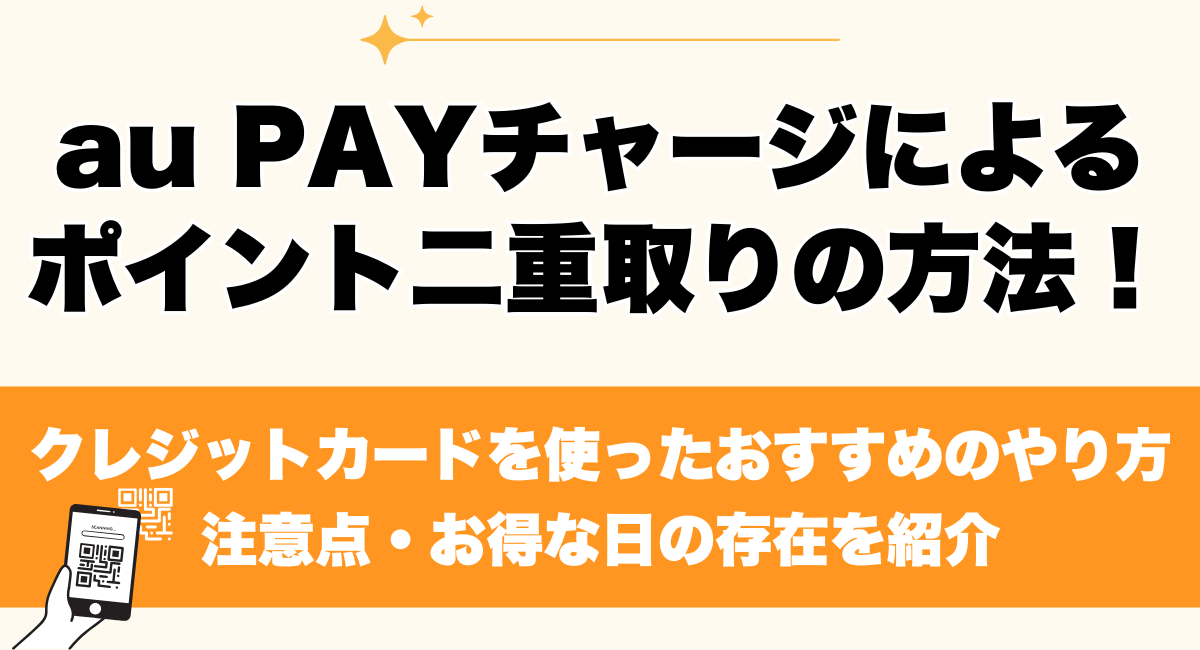1930年代、日本は「昭和恐慌」と呼ばれる未曾有の経済危機に見舞われました。企業が次々と倒産して多くの人が仕事を失い、街には失業者があふれたのです。特に農村地域では深刻な貧困問題が発生しました。
この危機は、世界恐慌の影響や当時の政府による金解禁政策など、複合的な要因によって引き起こされたものです。危機に直面した日本政府は、経済統制や財政政策の転換など、様々な対策を打ち出しました。
最終的に、大蔵大臣だった高橋是清の財政政策(高橋財政)によって、昭和恐慌の混乱に終止符が打たれます。昭和恐慌は、現代の私たちが経済問題を考える上でも、学ぶべき教訓は数多くあります。今回は、昭和恐慌の原因や影響、対策について詳しく見ていきます。
目次
昭和恐慌とは

昭和恐慌とは、1930年から翌年にかけて発生した恐慌で、戦前最大規模の深刻な経済的混乱です。*1)
恐慌とは何か
恐慌とは、景気が急激に悪化する現象です。通常、景気は良くなったり悪くなったりを繰り返しますが、恐慌は景気悪化の度合いが特に激しく、社会全体が混乱する状態です。
具体的には、企業の作った商品が売れなくなり、株価が急落します。多くの会社が経営難に陥り、倒産する企業も増えてしまいます。
それに伴い、働く場所がなくなって失業者が急増し、場合によっては、銀行にお金を預けている人々が不安になり、一斉に預金を引き出そうとする「取り付け騒ぎ」も起きます。日本では1927年の金融恐慌のときに、大規模な取り付け騒ぎが発生しています。
最も有名な恐慌の例は1929年にアメリカで始まった「大恐慌」で、その影響は全世界に広がりました。この大恐慌でも多くの人が仕事を失い、貧困に苦しみました。
現代では、このような大きな混乱を防ぐため、国が経済に関わり、景気が極端に悪化しないような対策を取っています。しかし、経済のバランスが大きく崩れると、今でも恐慌のような状況が起こる可能性があります。
金融恐慌との違い
昭和恐慌と金融恐慌の違いを表でまとめました。
| 項目 | 昭和恐慌 | 金融恐慌 |
| 発生時期 | 1930~31年 | 1927年 |
| 特徴 | 世界的な要因が絡む経済不況 | 国内金融システムの混乱 |
| 原因 | 世界恐慌金解禁による円高緊縮財政 | 震災手形の状況悪化大蔵大臣の失言銀行の不良債権問題 |
| 主な影響 | 輸出の不振企業倒産失業者の増大農村の困窮 | 中小銀行の取り付け騒ぎ震災手形の処理 |
| 政府の対応 | 高橋蔵相が財政出動(高橋財政)や円安誘導を主導 | 高橋蔵相が紙幣を大量に増発し、市場に現金を供給 |
金融恐慌は国内の金融システムの混乱にとどまりましたが、昭和恐慌はそれと異なり、世界経済の問題が日本に大きく波及したものでした。そのため、昭和恐慌は影響の範囲も深さも、より深刻なものだったと言えます。
昭和恐慌が発生した原因

昭和恐慌は、複数の要因が複雑に絡み合って発生した恐慌です。主な原因は以下の4つです。
- 世界恐慌の影響を受けたから
- 金解禁政策を実施したから
- 相次ぐ恐慌で日本経済が弱っていたから
- 緊縮財政政策を採用したから
それぞれの内容について詳しく見てみましょう。
世界恐慌の影響を受けたから
昭和恐慌は、1929年に始まった世界恐慌の波が日本に押し寄せたことで引き起こされました。発端となったのは、アメリカで起きた株価の大暴落です。株式市場の混乱により、アメリカ経済は急速に冷え込み、多くの人々が職を失いました。
当時の日本は、生糸を中心とする輸出品をアメリカで多く販売していました。生糸は高級衣料品の材料として重要で、日本の外貨獲得の柱となっていました。しかし、アメリカ人の購買力が低下すると、生糸への需要が急減し、日本の輸出は大打撃を受けてしまったのです。
この影響は農村部に特に深刻な打撃を与えました。生糸を生産する養蚕農家の収入が激減し、多くの農家が借金に苦しみました。輸出の柱だった繊維産業が打撃を受けたため、都市部でも工場の閉鎖や失業者の増加が進み、社会不安が高まりました。国際的な経済の結びつきが、日本社会に深刻な影響を及ぼしたのです。
金解禁を実施したから
昭和恐慌の主要因の一つに「金解禁」という政策があります。これは、日本円と金との交換を再開し、外国との自由な金の取引を許可する制度です。1929年に世界恐慌が発生した直後の1930年、浜口内閣は日本円の国際的信頼を高めるため、この政策を実施しました。
当時、世界各国は恐慌から自国経済を守るため、金の輸出を禁止する動きを見せていましたが、日本の井上蔵相は金解禁を継続しました。その結果、金と交換できる円の価値が上昇し、日本製品の輸出価格が高くなってしまいました。*3)
輸出が減少すると企業の収益は悪化し、工場の閉鎖や人員削減が相次ぎました。さらに問題だったのは、円と金の交換が自由になったため、多くの投資家が円を金に交換して海外に持ち出したことです。国内から金が流出し、日本経済の基盤が揺らいだのです。
このように金解禁は、円高による輸出不振と国内からの金流出という二重の打撃を日本経済に与え、昭和恐慌を深刻化させる要因となりました。
相次ぐ恐慌で日本経済が弱っていたから
日本は第一次世界大戦中に「大戦景気」に沸きましたが、戦後ヨーロッパの生産回復により輸出が減少し、1920年には戦後恐慌が発生しました。この恐慌では株価暴落や企業倒産が相次ぎ、経済基盤が揺らぎました。さらに、以下の出来事が続き、日本経済は慢性的な不況に陥りました。
| 年 | 出来事 | 影響 |
| 1920年 | 戦後恐慌 | 第一次世界大戦終結後の恐慌輸出が急減し、多くの企業が倒産 |
| 1923年 | 震災恐慌 | 震災による経済的混乱「震災手形」の発行 |
| 1927年 | 金融恐慌 | 震災手形の処理や銀行の取り付け騒ぎで混乱 |
このように、1920年代は相次ぐ恐慌により日本経済が疲弊していました。昭和恐慌が発生する前の段階で、すでに日本経済のシステムが大きなダメージを受けた状態だったのです。
緊縮財政政策を採用したから
1929年7月から1931年12月まで、民政党の浜口内閣・若槻内閣で大蔵大臣を務めた井上準之助は、経済の立て直しを図るため、政府支出を抑える方針を打ち出しました。これが「井上財政」と呼ばれる引き締め策です。
井上大臣は国の借金を減らし、経済の土台を強化するため、公共事業費の削減や国債整理に取り組みました。また、企業の合併や業界団体の形成を進め、産業の効率化も推進しました。*
しかし、この政策が実施されたのは、世界恐慌の影響で国際取引が急速に縮小していた時期でした。そのような状況下で国の支出まで減らしたため、市場全体の景気は急速に冷え込み、物価下落が加速したのです。
本来ならば、景気を回復させるために、政府が積極的にお金を使うべき時に、逆に支出を抑えたことで、不況は一層深刻化しました。これが井上財政が昭和恐慌を悪化させた主な理由です。
昭和恐慌による影響
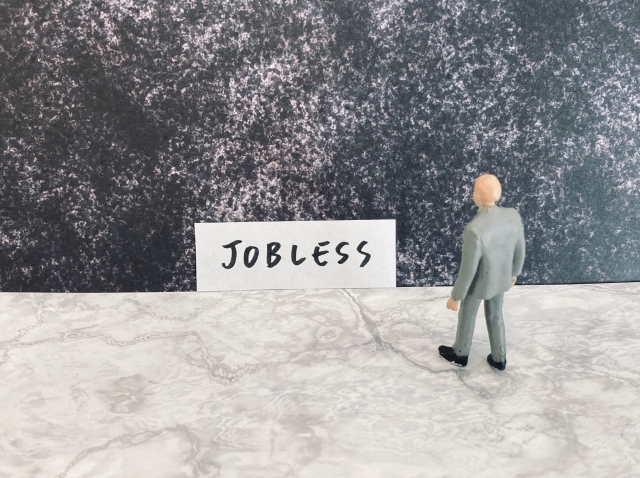
1930年に発生した昭和恐慌は、日本社会にどのような影響を与えたのでしょうか。主な影響は以下の2点です。
- 企業倒産と失業者の増大
- 農村恐慌の発生
詳しく見てみましょう。
企業倒産が増え、失業者が急増した
昭和恐慌は1929年に始まり、日本経済に深刻な打撃を与えました。この時期、大手から中小まで多くの企業が経営危機に陥りました。三井、三菱、住友といった当時の経済を支えていた大企業でさえ利益が大幅に減少し、多くの中小企業は事業継続が困難になりました。
倒産する会社が急増し、工場の閉鎖や経営者が夜逃げする事態も頻発しました。給料が支払われないケースも多発し、労働者の生活は一層厳しくなりました。失業者数は1930年に237万人、翌31年には250万人、32年も242万人と高い水準が続きました。失業率は8.3%から8.9%に達し、現代の感覚でも非常に深刻な状況でした。*5)
仕事を失った人々の中には、故郷に帰りたくても交通費すら払えない状況に追い込まれた人も少なくありませんでした。集団で道を歩き、夜は屋外で眠るしかない人々の姿が各地で見られました。昭和恐慌は単なる経済問題を超えて、日本社会の大きな転換点となったのです。
農業恐慌が発生した
昭和恐慌のただ中、日本の農村は未曾有の危機に直面していました。1929年に発生した世界恐慌の波は、やがて国内農業へと押し寄せました。特に日本の重要な輸出品だった生糸の価格が暴落し、養蚕農家の収入は激減しました。
1930年、浜口雄幸内閣による金本位制復帰政策は円高とデフレをもたらしました。特にデフレの影響により、農産物価格が下落します。皮肉にも同年は豊作となりましたが、米価は大暴落しました。供給過剰で農家の収入は減り、「豊作なのに貧しくなる」という逆説的状況が生まれました。
困窮した農村では現金収入を得るため、娘を女工や売春婦として送り出す家庭も増加しました。東北地方では「娘一人質に入れば、一家が冬を越せる」と言われるほど深刻な状況でした。
政府は農村救済のため、土木事業の拡大や低利融資制度を導入しましたが、効果は限定的でした。農家の借金は膨らみ、地主への小作料が払えないケースが続出しました。農村の疲弊は軍部の台頭を後押しし、やがて日本は対外膨張政策へと向かっていくことになります。
昭和恐慌に対して日本政府が行った対策

今まで経験したことがない深刻な不況にあえいでいる日本経済の状況に対し、政府は3つの対応策を試みました。ここでは、政府の対策を確認します。
経済統制を試みた
昭和恐慌が深刻化する中、浜口雄幸内閣は1931年4月に「重要産業統制法」を施行しました。この法律は、経済危機に直面した主要産業の立て直しを図るための対策でした。
当時の日本経済は世界恐慌の影響を受け、多くの企業が過剰生産や価格競争に苦しんでいました。この状況を改善するため、政府は企業同士が協力して生産量や価格を調整する「企業連合(カルテル)」の仕組みを法的に支援することにしたのです。
この法律の最大の特徴は、業界の大多数が合意した生産制限や価格設定などのルールを、同じ業界の全ての企業に強制できる点にありました。これにより、協力を拒む少数の企業によって価格が崩れるのを防ぎ、業界全体の安定を目指しました。
しかし、この制度は資金力のある大企業や財閥に有利に働き、中小企業には厳しい内容となりました。また、政府の経済への介入を強める契機ともなり、後の統制経済への布石となった点も見逃せません。
金輸出を再禁止した
昭和恐慌時、犬養毅内閣の高橋是清蔵相は1931年12月に金本位制からの離脱を決断しました。当時、日本は金と円の交換を自由に行う制度を維持していましたが、これにより大量の金が海外へ流出し、国内の景気悪化が深刻化していたからです。
高橋蔵相は金の輸出を再び禁止することで、円の価値を下げ、日本製品の海外での競争力を高めました。この政策転換によって輸出が増加し、また政府の積極的な財政出動も可能となりました。*6)
結果として日本経済は他国より早く恐慌から回復し、「高橋財政」として評価されています。この決断は世界的な不況からの脱出策として、後の経済政策にも大きな影響を与えました。
積極財政を行った
昭和恐慌に苦しむ日本経済を立て直すため、1932年に犬養毅内閣の高橋是清蔵相は、それまでの緊縮方針を大きく転換した積極的な経済政策を実施しました。高橋は政府支出を増やして景気を刺激する「積極財政」を推進したのです。
具体的には「時局匡救費」という特別予算を設け、道路や河川整備などの公共事業を全国で展開します。これにより失業者に仕事を提供し、都市部と農村の両方で収入機会を創出することで国内の消費を活性化させました。
同時に軍事費も拡大し、政府全体の支出を大幅に増加させました。これらの費用は国債発行によって調達され、日本銀行が積極的に国債を引き受ける仕組みを整えました。高橋財政によって日本経済は回復へと向かいました。*7)
当初は政府の支出拡大が景気を押し上げ、その後は輸出増加や民間の消費回復も加わって、日本は世界に先駆けて恐慌から脱出することができました。高橋財政は世界に先駆けたケインズ政策の実践と評価する声もあります。
昭和恐慌とSDGs

昭和恐慌は、それまでに日本が経験したどの恐慌よりも深刻なものでした。未曽有の大不況である昭和恐慌をSDGsの視点で見ると、どのようなことがわかるのでしょうか。ここでは、昭和恐慌とSDGs目標8「働き買いも経済成長も」との関わりを解説します。
SDGs目標8「働きがいも経済成長も」との関わり
昭和恐慌は1930年代に日本を襲った深刻な経済危機です。この時期、工場の閉鎖が相次ぎ、多くの人々が職を失いました。農村部では米価の大暴落により農家の収入が激減し、生活のために娘たちを女工として送り出す家庭も少なくありませんでした。
この社会不安は単なる経済問題にとどまらず、政治的混乱も引き起こしました。1930年に浜口首相が東京駅で銃撃され、1932年には井上前財務大臣や三井財閥の団琢磨氏が暗殺されるなど、経済政策への不満が暴力的な形で表れたのです。
SDGs目標8が掲げる「働きがいも経済成長も」という理念は、経済成長だけを追求するのではなく、すべての人に安定した仕事と公正な賃金を保障することを目指しています。昭和恐慌の苦い経験は、持続可能な経済発展と質の高い雇用創出が社会の平和と安定に不可欠であることを教えてくれます。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
今回は、昭和恐慌について解説しました。1930年代に日本を襲った昭和恐慌は、世界恐慌の波及と金解禁政策の影響を受け、日本経済に深刻な打撃を与えました。企業倒産や大量失業に加え、特に農村では米価下落による貧困が広がり、社会不安が高まりました。
この危機に対し、政府は経済統制や金輸出再禁止などの対策を実施します。特に高橋是清による積極財政政策が効果を上げ、日本は世界に先駆けて恐慌から回復しました。
昭和恐慌の経験は、経済政策の重要性と社会安定のためのバランスある成長の必要性を私たちに教えています。現代の経済危機を考える上でも、持続可能な経済発展と質の高い雇用創出の重要性を示す歴史的事例といえるでしょう。
参考
*1)山川 日本史小辞典 改定新版「昭和恐慌」
*2)山川 日本史小辞典 改定新版「恐慌」
*3)日本大百科全書(ニッポニカ)「金解禁」
*4)日本大百科全書(ニッポニカ)「井上財政」
*5)改定新版 世界大百科事典「昭和恐慌」
*6)ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「高橋財政」
*7)改定新版 世界大百科事典「高橋財政」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。