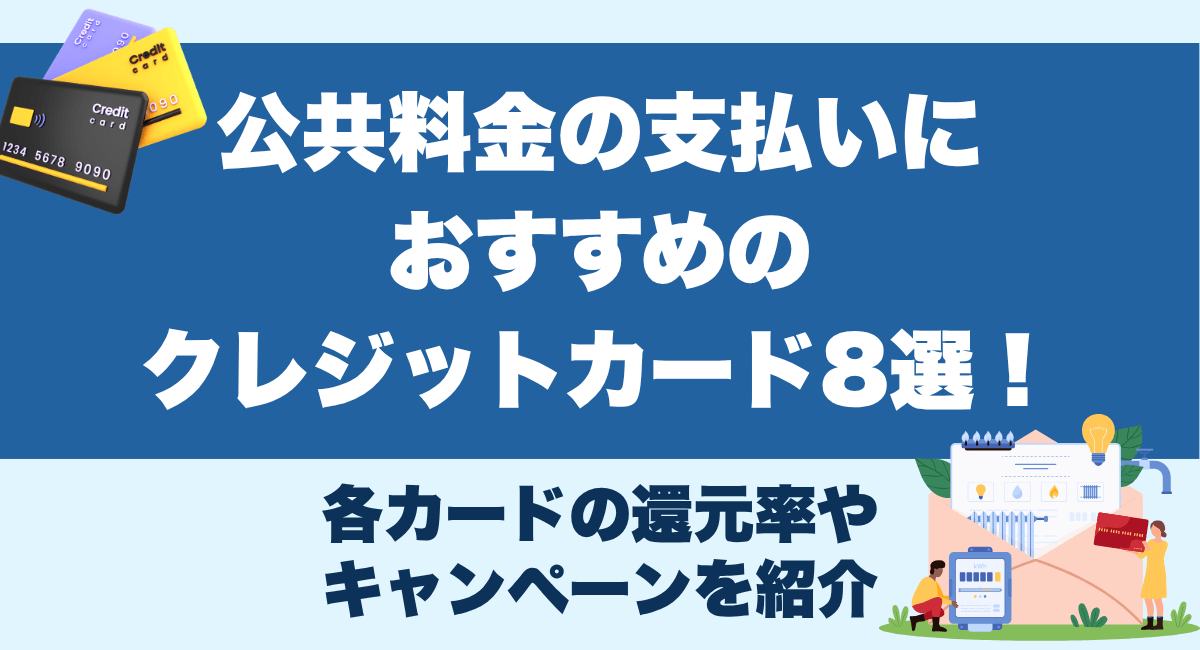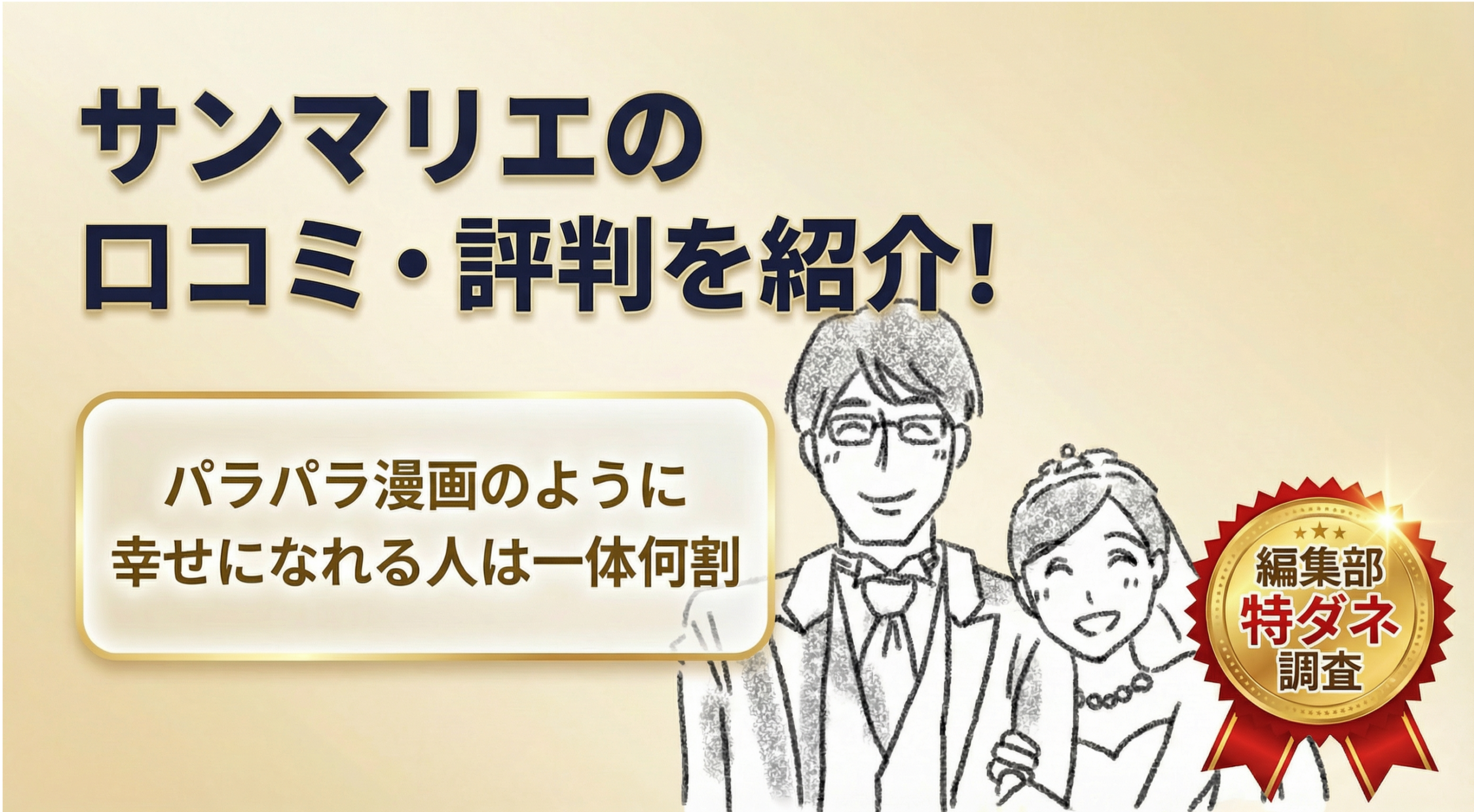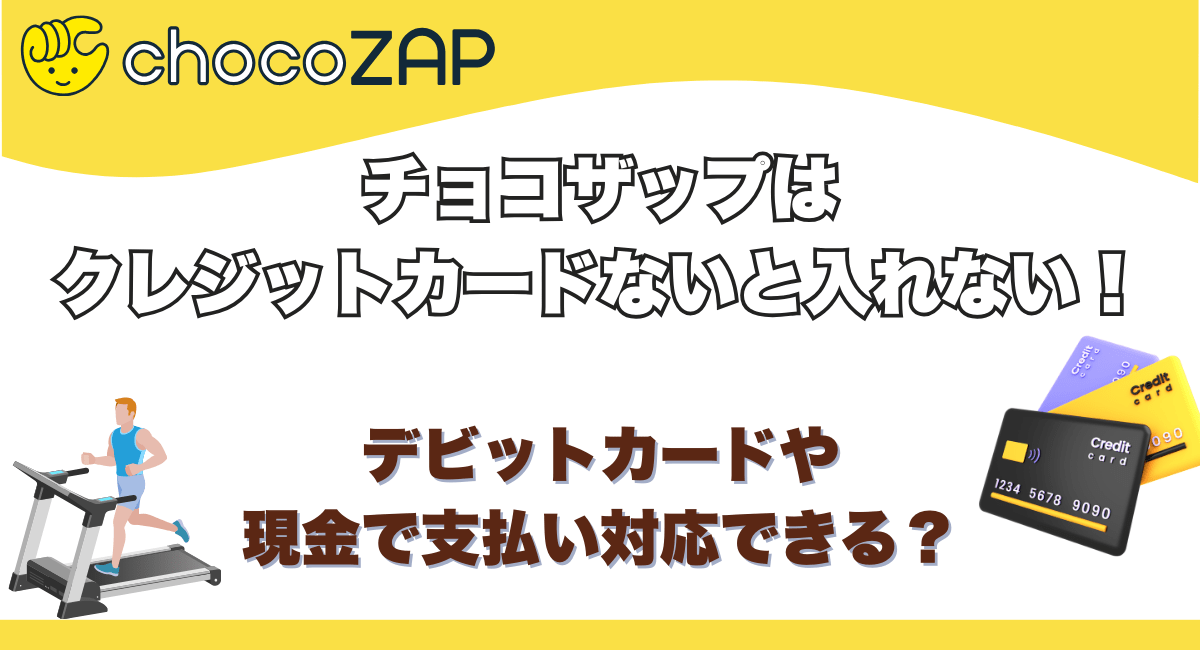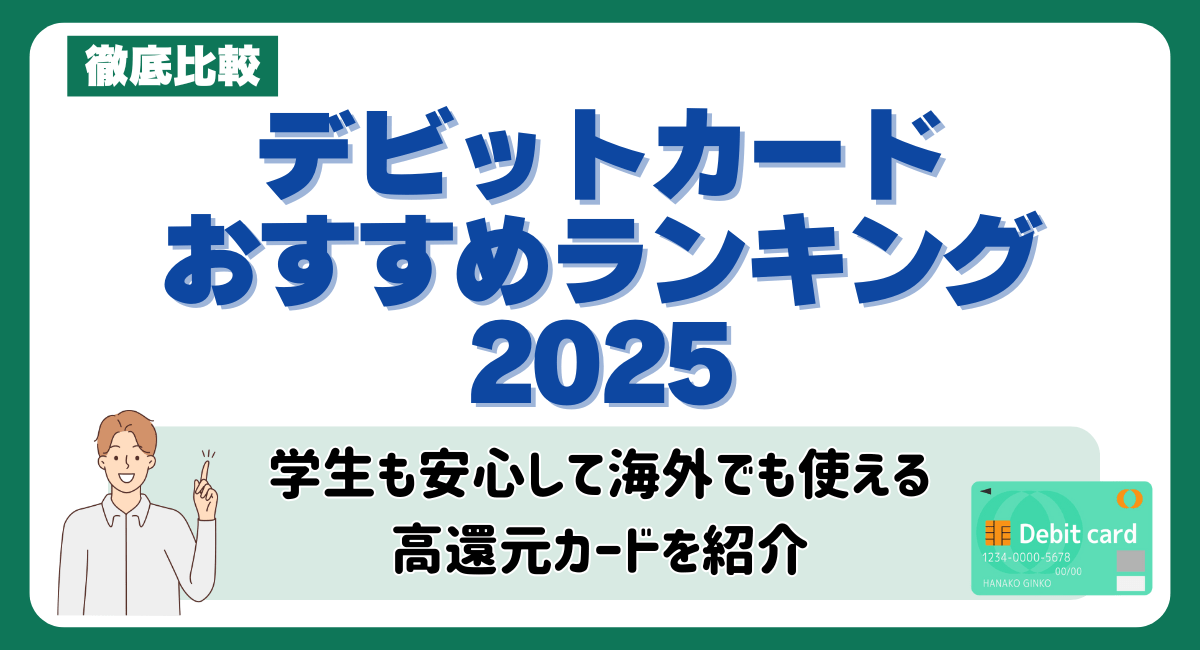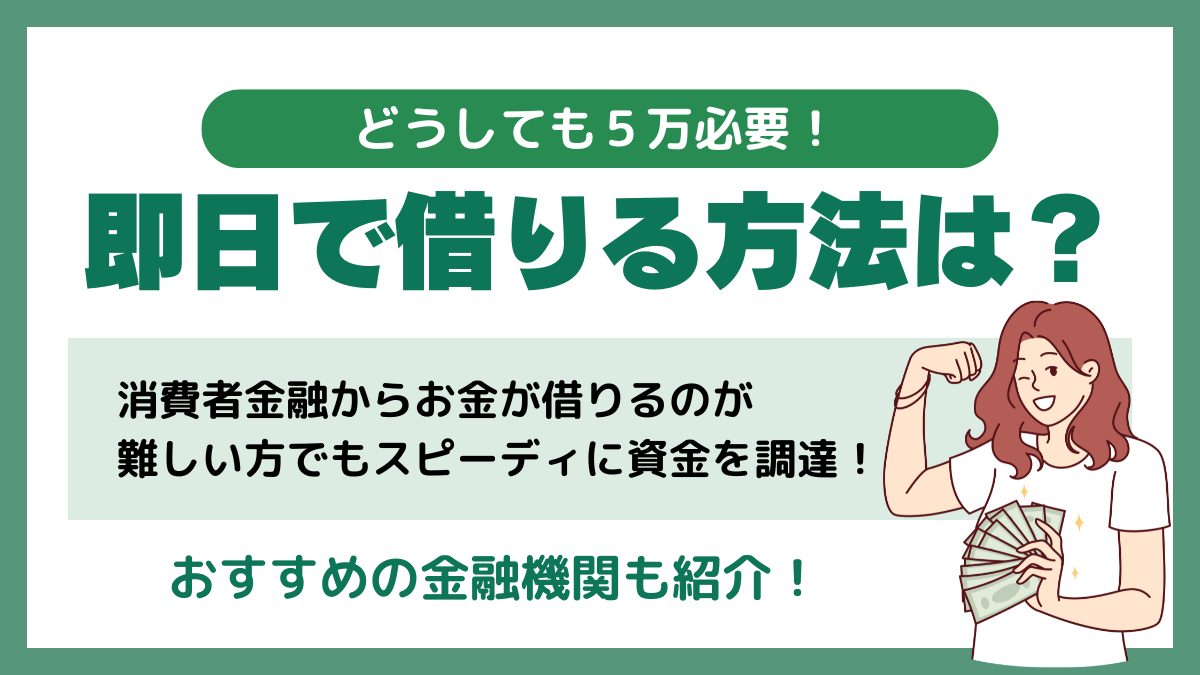特定非営利活動法人Silent Voice 日下友乃さん 大西啓人さん インタビュー

日下友乃
1998年11月25日、広島県広島市生まれ。2021年、国際教養大学を卒業後、大学在学中にサークルで学んだ手話を活かし、NPO法人Silent Voiceにて、ろう・難聴児向けのスポーツイベントのプロジェクトを担当する。2022年、幹部候補生として日本ヒルトン株式会社に新卒入社をし、ホテル経営を学び始めたが、10月にNPO法人Silent Voiceへ転職。ろう児・難聴児向けオンライン教育事業「サークルオー」にて、カスタマーサポート、サービスの企画運営、広報活動、システム管理、総務などの業務に加えて、新規プロジェクトの推進を行う。2023年6月から事業責任者に就任し、デフのスタッフと聴のスタッフが協働するチームのリーダーとして、ろう児・難聴児のオンライン教育の公的サービス化を目指している。

大西啓人
1997年、奈良県で生まれ。ろう者。第一言語は日本手話。0歳の時に病気がきっかけで耳が聞こえなくなり、幼稚部から高校までろう学校に通う。2016年に大学に入学し、初めて聴者に囲まれた環境で過ごす経験をする。ろう者に囲まれた環境、聴者に囲まれた環境の両方を経験する中で、「ろう者と聴者の間に架ける橋になりたい」という法人代表の尾中さんの活動に共感し、大学生の時にアルバイトとして法人の活動に従事。2020年からアメリカにあるギャローデット大学院にて、2年間ろう教育を学ぶ。帰国後、ろう学校で英語の非常勤講師を務めるが、更なる知識と経験を求め、現在、NPO法人Silent Voice「サークルオー」事業の運営スタッフとして携わり、全国各地に散らばるろう・難聴の子どもたちにオンラインで様々な機会を提供している。ろう・難聴の子どもたちがありのままの自分でいられる居場所をこれからも提供し続けたい。
目次
Introduction
NPO法人Silent Voiceでは、ろう者・難聴者と聴者が共存するコミュニティを増やすことをミッションに、ろう・難聴の大人と子どもに向けた活動を行っています。
普段生活を送る中で、ろう・難聴の子どもが、いつどのように手話や言語を習得するかを考える機会は少ないかもしれません。
今回は、サイレントボイスが行う、ろう児・難聴児向けのオンライン教育事業「サークルオー」の事業責任者である日下さんと、運営スタッフで、自身もろう者※である大西さんに、ろう・難聴の大人や子どもを取り巻く社会課題についてお聞きしました。
ろう・難聴者と聴者がともに協力して活動していくために

–始めにNPO法人Silent Voiceについて、ご紹介をお願いいたします。
日下さん:
私達は、ろう・難聴者と聴者がともに協力して活動している団体です。
主に、ろう・難聴者と聴者がともに働くための職場改善を目指す「デフビズ」と、ろう・難聴の子どもたちを対象にした教育事業「デフアカデミー」と「サークルオー」が活動の軸となります。
「デフビズ」は、ろう者と聴者がともに働いている企業様に対して、スムーズなコミュニケーションや、一緒に働く環境作りをコンサルティングさせていただく活動です。
「デフアカデミー」と「サークルオー」は、両方とも小学生〜高校生までのろう児・難聴児に対して、自ら「OOをやりたい!」と思う気持ち(内発的動機)を高めるためのプログラムを行います。
大きな違いとしては、デフアカデミーは大阪にある教室を用いた放課後等デイサービスとして福祉制度の中で運営していること、サークルオーは全国のろう・難聴の子どもに対して、オンラインで授業を行う私費事業であることです。
私たちの活動はデフビズからスタートしました。デフビズを通して感じたことは、チームワークやコミュニケーション能力などの力は、社会に出てから急に身につくわけではないことです。
そのため、子どものころから協働する力を養うプログラムを提供したく、教育事業にも注力するようになりました。

聴者とろう・難聴者が共存するコミュニティが、社会にほとんど存在しない
–聴覚障がい者/児が抱える課題について教えてください。
日下さん:
私たちが考えている課題感としては、ろう者と聴者が共存するための方法や経験が世の中に蓄積されていないということです。
社会全体で考えたときに、聴者のコミュニティの中にろう者がいる、という状態が一番多いと思います。
例えば家族。ろう児・難聴児の90%は、聞こえる親のもとに生まれてくると言われています。つまり、家族という最小単位のコミュニティでも、聴者のコミュニティの中にろう者が1人だけ存在することになります。
もう少し具体的な例として、ろう学校へ通う子どもが減っているという状況があります。
ろう学校の生徒数は少なく、集団行動を学ばせたいと考える両親が多くいます。その中で近年は、地域の一般的な学校に通わせる家庭が増えているんです。
そうした環境の場合、とくに影響が大きいのは学習の遅れです。
一般的な学校は、ろう児・難聴児者に合った方法で授業が行われるわけではありません。かつ、そもそも、ろう児・難聴児に適した授業方法が何なのかもわからないため、ろう・難聴の子どもはどんどん置いて行かれてしまいます。
そのため、小学校高学年や中学生になるタイミングで、ろう学校へ転向するケースも多く見られます。しかし、ろう学校においても、手話が必ず根付いている環境とは限りません。
ろう学校の先生も、全員が今まで手話を勉強されてきたわけではないので、できない方が多いんです。

これらを踏まえたときに、ろう児・難聴児が共存コミュニティで暮らす方法がわからない期間が長いこと、また、ろう者のコミュニティに触れる機会も限られている現状が想像できるかと思います。
大西さん:
私も含めてろう者は、周りが聴者ばかりの環境で生活することがほとんどです。
そのため、ろう者としてどんなふうに生きていけばいいのか、自分にとって良いコミュニケーション方法は何か知らないままで過ごしている人が多いのです。
また、聴者の方たちも、ろう者に対してどう配慮していいのかわからない、知らないことが多いと思います。
様々なろう者としての生き方があることを知らないまま学生時代を過ごすことで、子どもたちが自分自身で将来を選ぶことができない、内発的動機を持てないことが、大きな課題だと感じています。
共存コミュニティを形成するために、ろうコミュニティを広げる
–御団体のMISSIONについて教えてください。
日下さん:
私たちはミッションとして「共にできるを、ふやす。」を掲げていて、聴者とろう者の共存コミュニティをアップデートし、増やし続けたいと考えています。
そのための1つの方法が、先ほどお話しした教育事業「デフアカデミー」と「サークルオー」です。
「デフアカデミー」と「サークルオー」では、手話やイラストなどの視覚情報を組み合わせ、ろう・難聴の子どもが理解しやすいようなコミュニケーション方法で、学習を進めていきます。
また、子どもが学生の頃から、ろう・難聴のコミュニティに属することで、ろう・難聴の大人がどのように生きているのかを共有し合うことができます。これにより、聴者とろう者の共存コミュニティでの過ごし方を学びます。
なにより、自分と同じ聴覚障がいのある人と繋がること、また自分が属しているコミュニティを実感することが、子どもたちにとって重要だと考えています。
大西さん:
「デフアカデミー」と「サークルオー」を通して、様々な大人と出会うことで、自身のロールモデルを見つけたり、大人になった後のイメージをつかむことができます。
その結果、子どもたちは成長する過程で、社会の中で自分のことを表現する力をつけられるきっかけをつかめると思うんです。
また、私の経験からお話すると、ろう学校には通っていましたが、幼稚部年少の頃までは、私も両親も、ろう者のコミュニティに触れたことはなかったため、特に親は手話で生きる私がどのように成長していくのか想像できなかったと思います。
そんな時に同じ手話で生きるろう者の大人と出会うことで、親自身も学んでいくきっかけになったと感じています。
日下さん:
「デフアカデミー」と「サークルオー」は共存コミュニティを作る前段階として、質の高いろうコミュニティを形成していくことが重要だと考えています。
この事業を通して培ったノウハウや考え方を活かして、共存コミュニティの増加につなげていくビジョンです。
また、サイレントボイスでは、聴者とろう者・難聴者が共に働いているため、1つの共存コミュニティのロールモデルとして、あるべき姿を模索し続け、アップデートしていきたいと考えています。
オンライン教育事業として、全国のろう児・難聴児へサポートを
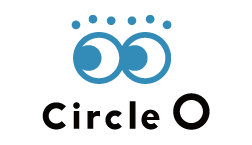
–全国のろう・難聴子どもに対してアプローチできる「サークルオー」について、もう少し詳しく教えていただけますか。
大西さん:
サークルオーの理念としては、子どもたちが、自分の得意なこと、好きなこと、大切なことといった内発的動機をもって、自分で選択し、行動ができることを最終目標としています。
具体的なプログラム内容としては、「ことば学習」と「教科学習サポート」をマンツーマンで行う個別学習と、生徒複数人と先生1人の体制で行う集団学習の2つがあります。
個別学習におけることば学習は、ことばの数を増やすための授業です。
手話を使って日本語を学ぶ子どももいれば、手話の勉強をしている子どももいます。
多くのろう児・難聴児が最初にぶつかる壁は日本語です。
家族や友達の会話の声が情報として入らない分、生活に関わる身近な単語も習得が難しい場合もあります。また、生活の中で簡単な単語は習得できても、抽象的な概念などは自然な習得は難しく、コミュニケーション能力や思考力の発達に影響を与えます。
そこで手話を第一言語とする子どもの場合、まず手話やイラストや図などの視覚情報で概念を獲得してから、日本語につなげていく方法が多く、私たちのプログラムも同じ方法で大人と一緒に言語習得を促していきます。
教科学習サポートでは、国語や算数などの学校で学んだ学習内容について、わからない部分に対して、手話を用いて学習しなおしていくプログラムです。
手話や口話、文字や図解など、その生徒の最もコミュニケーションを取りやすい方法を考えながら、学習理解のサポートをしていきます。
集団指導は、子どもたちのコミュニケーション力や思考力を深めるための様々なプログラムを行っています。
例えば小学生の場合、簡単なクイズを行って、子どもたちに話し合いながら答えを導きしてもらいます。他にも理科の実験や手話を用いた演劇など、楽しんで学習できるような講座を実施しています。
中高生には、ろう・難聴の大学生や社会人を呼んで、人生や考えを共有してもらうことで、生徒たちの視野が広がるようなプログラムを考えています。
サークルオーを通して、人生における成功体験、引き出し、自分の意思で行動する力を身につけられる

–「サークルオー」が果たす役割についてどのようにお考えでしょうか。
大西さん:
私も幼少期から大人になるまで、耳が聞こえないことで話についていけないこと、自分の考えを思うように伝えられないことに対してストレスを感じた部分はありました。
親戚で集まった時に感じた孤独感や、大学の友達同士のコミュニケーションにおいて、自分が発言するタイミングを逃したり、何で盛り上がっているのかの理解が遅れてしまったり…。
そういった経験を自分の中でどのように捉えるかが、人によって違うと考えています。
サークルオーという、ろうコミュニティに属することで、同じような経験を持つ大人と繋がることができます。
そして、普段の生活で困ったときの対策方法を学び、自身の引き出しを増やすことで困った時に自分で考えて決定できるようになることが、サークルオーの大きな意義だと考えています。
日下さん:
普段の生活の中で孤立しがちなろう児・難聴児たちは、聞こえる子どもたちのように成功体験やコミュニケーションを経験することが難しいんです。
サークルオーでは、コミュニケーションの基礎である手話や言語を身につけることが可能です。
また、ろう・難聴の子ども同士のコミュニケーションを通して、コミュニケーション力や思考力を育み、小さな成功体験を経験してほしいと考えています。
実際に参加いただいてる方からも、うちの子どもがこんなに話しているのを見たことがない、とおっしゃっていただくこともあります。
こうした経験や身についた力によって、ろう児・難聴児たちが、自分の中に強い意志を抱いてくれるようになってほしいという想いです。
サークルオーの活動を今後も持続させていくために
–現在活動を続けている上で、課題に感じていることを教えてください。
日下さん:
一番の課題としては、持続可能な運営を可能とするための、運営基盤を固める必要があると考えています。
他の企業様がサークルオーのようなろう児・難聴児に対する教育事業を行っていない1つの理由として、聴覚障がい児の絶対数が少ないことがあります。
また、サークルオーはオンライン教育事業のため、厚生労働省の福祉制度に含まれておらず、補助制度も対象外なんです。
そのため、ビジネスとして安定した運営資金を確保すること、つまり事業を持続させていくことが1つの大きな課題だと考えています。
現状、サークルオーはろう児・難聴児の1つの居場所として成功しましたが、あくまで継続していくことに意味があります。
既に参加してくれている子どもたちの居場所を奪ってしまう、喪失感を感じさせるようなことはあってはなりません。
そのためにも、私たちの活動の認知を広げ続けて、ステークホルダーを増やしていけるような活動を行っていきたいと考えています。

子どもたちにとって最良の方法を研究し続け、ろう・難聴者における社会進出の後押しをしたい
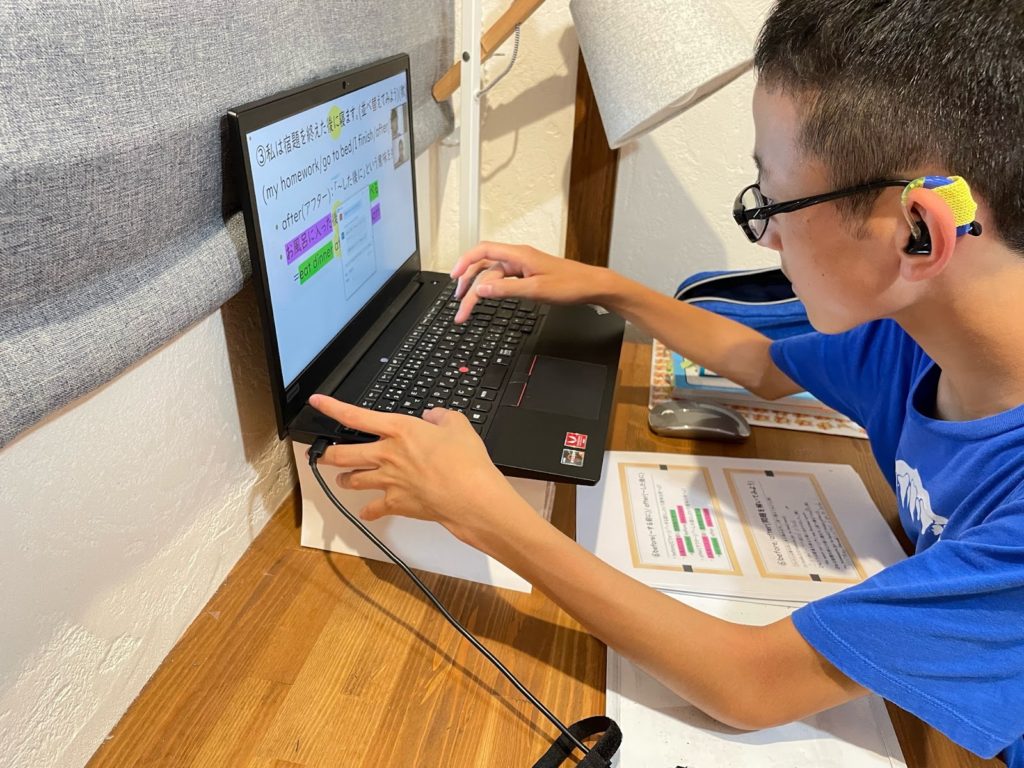
–今後の展望についてお聞かせください。
日下さん:
まず、持続可能な運営を実現することが一番大きな要素だと考えています。
それに加えて、事業の成果を出し続けることで、正式な国の制度としてサービスを提供したいという想いがあります。
現状だと、ろう児・難聴児に対する教育事業はサークルオーしかないような状況ですが、子どもたちの選択肢はもっとあっていいと思っているんです。
そのため、サークルオーがろう児・難聴児に対する教育事業のモデルケースとなることで、ろう児・難聴児の教育事業がもっと盛んになって欲しい。
そういった社会を実現して、ろう・難聴の子どもたちが社会に出たときに、人生の満足度が高められるようなことに繋がれば、ろう・難聴者における1つの社会進出の後押しができたと言えるんじゃないかと考えています。
大西さん:
サークルオーはこれから日本全国だけではなく国際交流など世界にも展開していきたいと考えています。。
ただ、ろう難聴の子どもたちへ向けたオンライン教育事業ということで、前例がなく、私たちも最良を探りながら、日々改善を続けている状況です。
子どもたちの内発的動機を高めるために、どのような授業内容、授業方法が適しているのか、革新的な方法はまだ見つかっていません。
今後もサークルオーに所属する講師や運営、そして子どもたちともともにコミュニケーションを取り、生徒たちにとって最良な方法を考えて続けていきます。
–聴覚障がい児における課題、また、NPO法人Silent Voiceとオンライン教育事業「サークルオー」が果たす役割についてお聞きできました。
貴重なお話をいただき誠にありがとうございました。
NPO法人Silent Voice:https://silentvoice.org
この記事を書いた人
スペースシップアース編集部 ライター
スペースシップアース編集部です!
スペースシップアース編集部です!