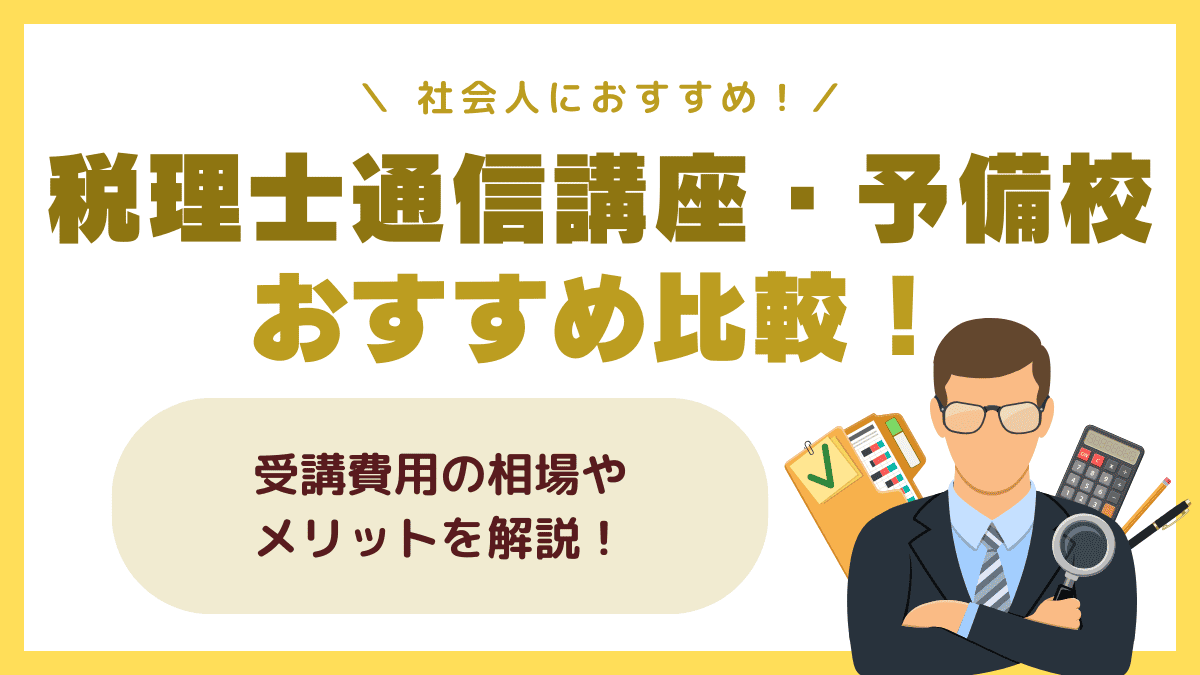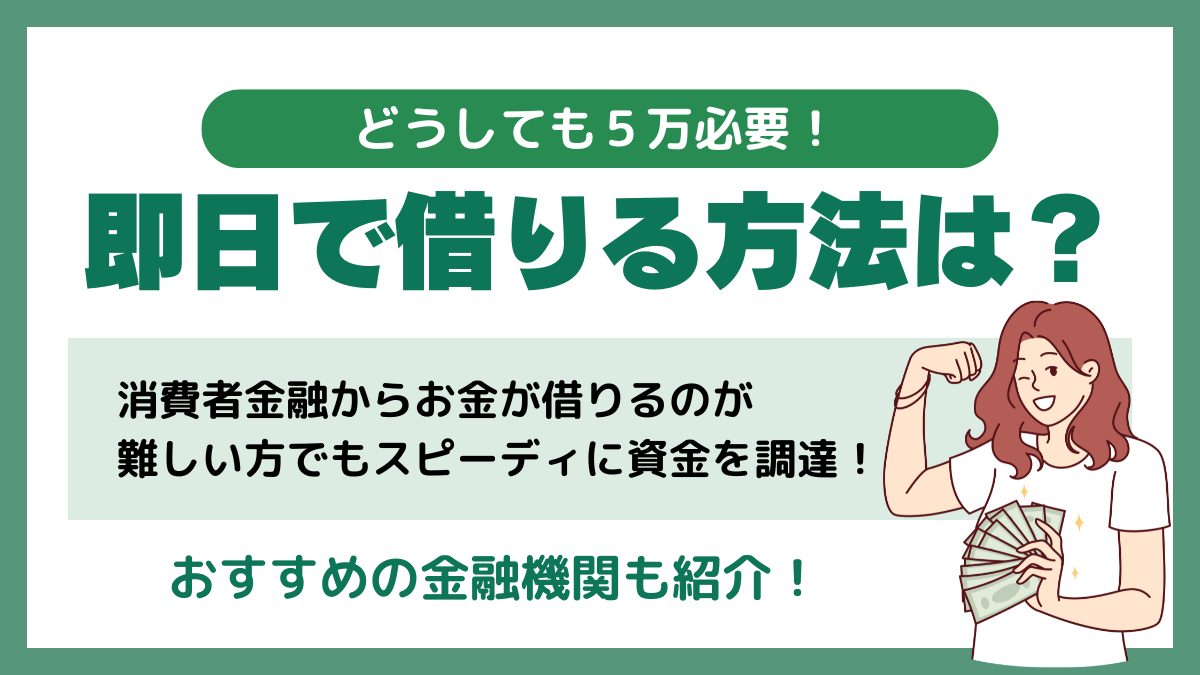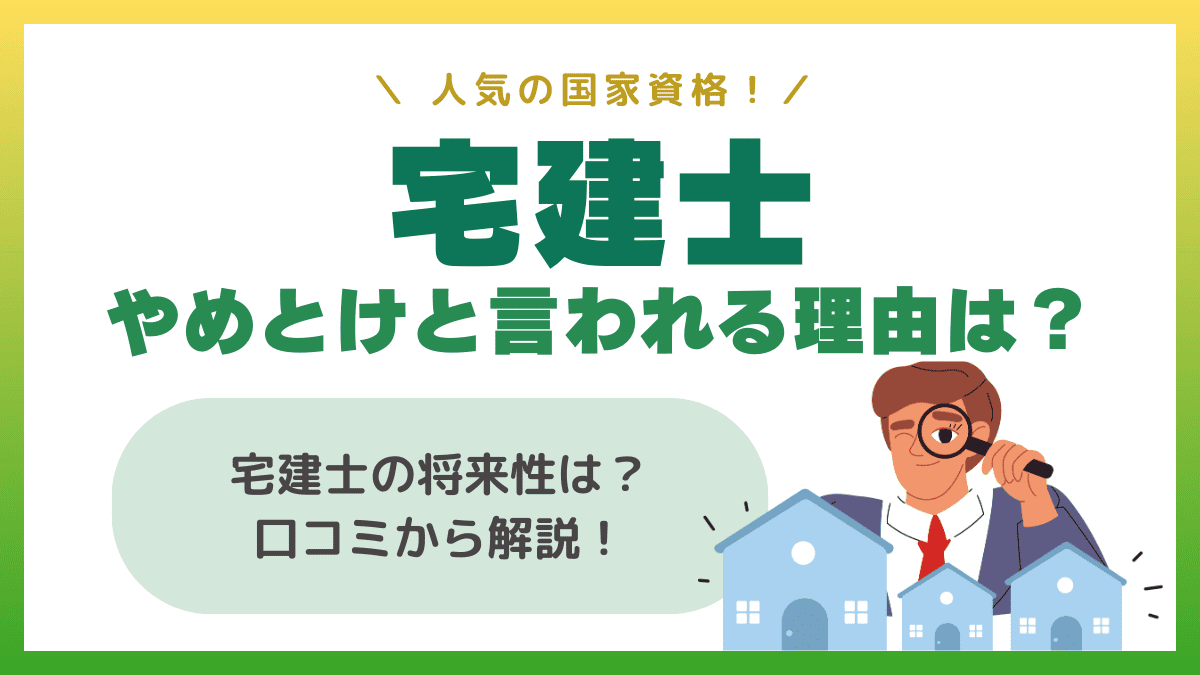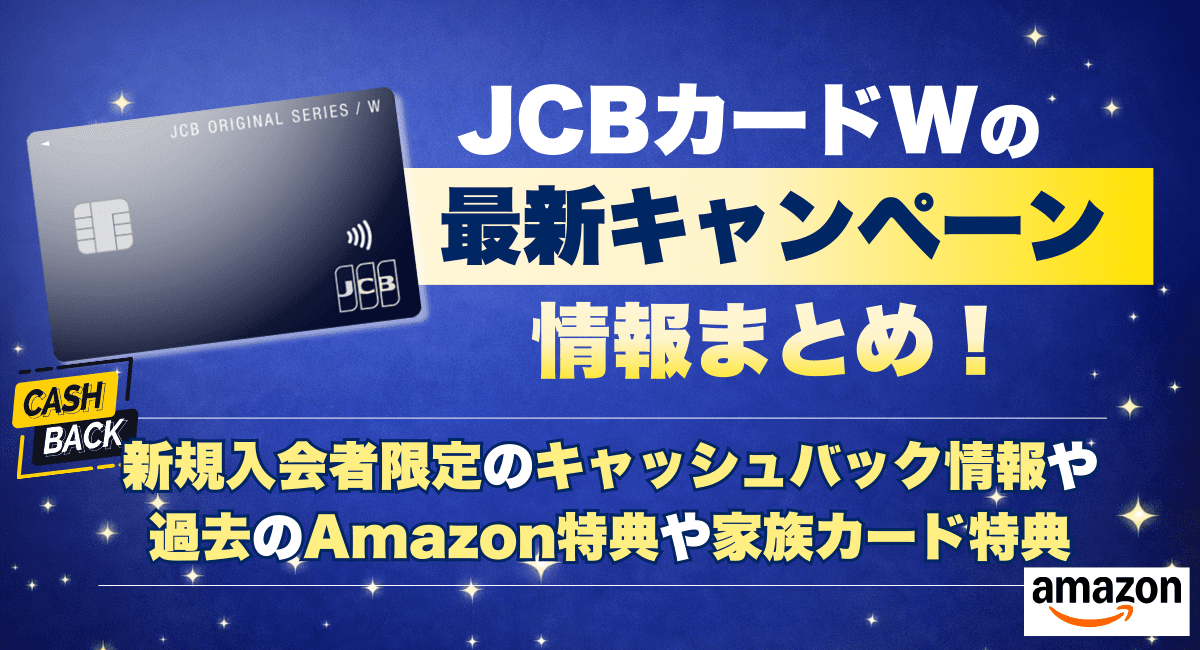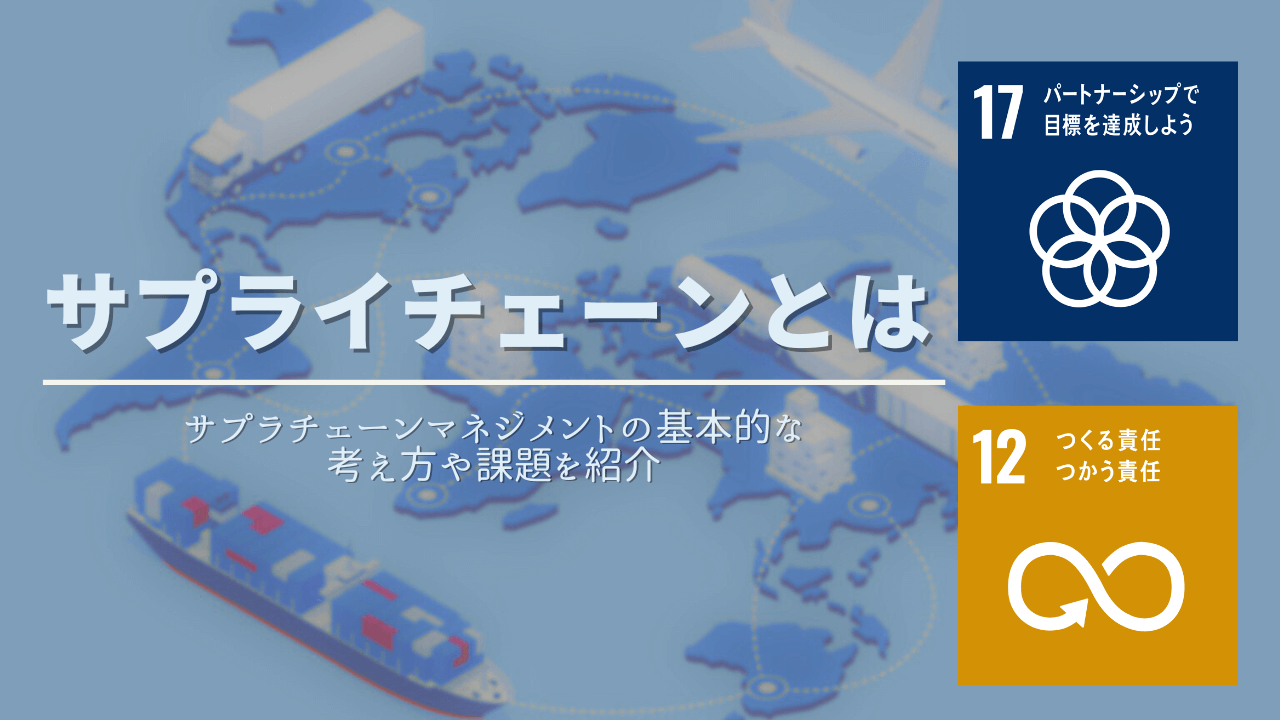
現在のビジネスでは、サプライチェーンをどう構築し、どう管理するかが最重要課題となっています。
この記事では、サプライチェーンとはどういうものか、サプライチェーンを管理することでビジネスがどのような効果をもたらすのかを紹介していきます!
目次
サプライチェーンとは?簡単に解説
サプライチェーン(Supply Chain)とは、日本語で「供給網」と呼ばれ、生産・流通における一連の流れのことを言います。
企業が製品を作り、市場に流通させるには
- 原材料の調達
- 部品や製品の製造
- 在庫管理
- 配送
- 販売
といった多くの工程があり、そこにはたくさんの企業が関わっています。このすべてのプロセスとその関係企業をまとめてサプライチェーンと呼びます。
物流を把握することでリスク低減につながる
サプライチェーンを理解し、物流の流れを把握することは、ビジネスで発生するリスクの低減につながります。
物流におけるリスクとして考えられるのは、災害・事故・情報セキュリティ・国際物流特有のリスク(関税や為替レート、商習慣など)があげられます。
サプライチェーンを構成するすべての組織が情報を管理し共有することで、何が、どこにどれだけあって、誰がどのように扱うかが明確になります。その結果、ビジネス上のリスクにもすばやく対応することができるのです。
サプライチェーンとバリューチェーンの違い
物流業界でよく使われる言葉として、「バリューチェーン」があります。
バリューチェーンとは「企業の事業内容やビジネスモデルを分析・改善し、付加価値を生み出す業務の流れ」を指します。
サプライチェーンが「製品流通のすべてのプロセスと関連企業を包括するもの」であるのに対し、バリューチェーンは主に「企業単体で価値を生み出す」ことに主眼を置いています。
サプライチェーンを言い換えると?
サプライチェーンを言い換えると「供給網」や「調達から販売までのつながり」と表現できます。原材料の調達、生産、流通、販売、そして消費者に届くまでの一連の流れを指し、企業活動の基盤となる仕組みです。
最近では英語のまま「サプライチェーン」と呼ばれることが多いですが、日本語では「物流網」「供給連鎖」「生産と販売の仕組み」といった言い方も可能です。
特にグローバル化が進む中で、その範囲は国境を越えて広がっており、単なる物流経路ではなく、取引先との関係性やリスク管理も含めた「企業の生命線」として理解されています。
サプライチェーンマネジメントとは
サプライチェーン・マネジメント(supply chain management)とは、サプライチェーン全体を、ITを駆使して統合的に管理し、経営効率を高める仕組みのことです。
サプライチェーン・マネジメントの概念は1980年代に提唱され、90年代に理論が確立されました。さらに2000年代以降、インターネットやIT技術を活用してサプライチェーン全体をつなぐことで、より効率的な一元管理ができるようになっています。
サプライチェーンリスクとは
サプライチェーンリスクとは、原材料の調達から生産、流通、販売までの一連の供給網において、想定外の事態が発生し、製品やサービスの供給に支障が出る可能性を指します。例えば、自然災害やパンデミックによる工場停止、国際紛争や地政学リスクによる輸送ルートの寸断、取引先企業の倒産や不祥事、人権侵害や環境問題などによる社会的批判も含まれます。
特にグローバル化が進む現代では、サプライチェーンが複雑かつ国際的に広がっているため、影響範囲が大きく、ひとつの障害が全体に波及しやすいという特徴があります。このリスクに対応するためには、取引先の多様化や在庫の適正確保、デジタル技術を活用した可視化など、事前の備えが欠かせません。
企業にとってサプライチェーンリスクの管理は、安定供給と社会的信頼を維持するための重要な課題です。
サプライチェーン・マネジメントの基本的な考え方
サプライチェーン・マネジメントは、単純にマネジメントの方法や技術だけを指すのではありません。サプライチェーン全体を「どのように捉え、どう動かすか」という考え方そのものが重要になってきます。その基本となる考え方は、次の3つです。
スループット重視
スループットとは「モノの移動スピードとそれにまつわるお金の流れ」です。スループットを重視することで、製造から販売に至るまでの時間短縮、在庫管理から需要予測までが可能になり、結果的にコスト削減にもつながります。
「在庫をもたない」という概念
かつての大量消費時代は、大量生産した製品をなるべく多くの人にすばやく売ることが良しとされており、「売り切れ」はあってはならないことでした。
その一方で、私たちの生活が豊かになるとモノは売れなくなります。さらに嗜好の多様化によって少量多品種の時代となり、だぶついた「余剰在庫」は経営を圧迫するようになりました。こうして「在庫を極力もたない」ことが重視されはじめ、「必要なものを」「必要な分だけ」効率よく生産するための管理手法が求められるようになったのです。
「全体最適」という考え方
サプライチェーン・マネジメントでは「部分最適」より「全体最適」が求められます。
部分最適とは「ある部門やプロセスで最善を求める」ことで、全体最適は「全体を見てその状態をベストにする」という考え方です。
例えば、ある部門だけが最善を尽くして生産量を上げても、他の部門では需要予測に基づいて出荷量を抑えたのでは、過剰在庫が生まれてしまいます。
無理やムダのないサプライチェーンを構築するには、すべての工程や企業に目配りし、全体のバランスを取ることが大事なのです。
サプライチェーン・マネジメントが注目されている理由
現在では多くの企業で、サプライチェーン・マネジメントを取り入れる必要性が叫ばれています。サプライチェーン・マネジメントがここまで注目されているのにはどのような理由があるのでしょうか。
少子高齢化による労働人口の減少
サプライチェーン・マネジメントが必要とされる背景には、少子高齢化による国内での労働人口の減少、すなわち人手不足があります。
現在の日本では、製造業やサービス業をはじめ、物流業や農林水産業にいたる多くの業界で人手不足が深刻です。さらに2025年頃には、こうした問題がより顕著になると予測されています。一方でモノやサービスを提供する業務はより多様化、高度化しているため、少ない人数で高い生産性を生み出すことが不可欠となります。産業全体でより効率的な生産管理手法が求められているのです。
企業のグローバル化
多くの企業で事業がグローバル化してきたことも重要な要因です。
かつては国内で作られた製品を国内で消費するビジネスモデルが主流でした。しかし現在では、どの企業も生産拠点を国外に多数展開し、原材料の調達から製造、流通も国際間で行われるようになりました。
当然そこにはさまざまな企業風土や文化的背景、経営方式を持つパートナー企業が存在します。グローバル化が進めば進むほど、世界中の顧客や取引先との意思疎通を図り、モノや人、データ、お金の流れを管理し、効率化することが重要になってくるのです。
テクノロジーの発達
インターネットに代表される情報技術(IT)の進化は、サプライチェーン・マネジメントの導入に大きな影響を与えました。
より大量の情報をすばやく、誰しもが扱えるようになったことで、生産や物流、販売などのあらゆるプロセスに専用の基幹業務システムが導入されました。
今後は、
- IoT(Internet of Things:モノのインターネット)による物流の管理
- AI(人工知能)を利用した需要予測や在庫管理
といった技術にも注目が集まっています。
【関連記事】IoTとは?Internet of Things(モノのインターネット)の意味や事例を簡単に
サプライチェーンの3つの区分
サプライチェーンの流れは、大まかに①購買物流・②製造・③出荷物流の3つに分けられます。
購買物流
購買物流とは、原材料を外部から仕入れる物流活動を指します。
一例としては、パンの材料となる小麦を農家から買い付け、保管したり各工場へ送ったりするといった流れが購買物流です。ここでは製パン業者のほか、小麦農家・製粉会社・配送業者などがサプライチェーンを構成しています。
さらに小麦農家から見れば、種もみや肥料、農薬や農機具を外部から仕入れているため、ここでもそれぞれの業者とのサプライチェーンによる購買物流活動が行われていることになります。
製造
製造は、仕入れた原材料を加工して、製品にしていく過程です。同じ会社内、同系列の企業だけで製造を行うだけではなく、各部品の製造を他社に外注するケースもあります。
出荷物流
出荷物流は一連の流れの川下にあたります。製造メーカーから出来上がった商品は物流業者によって卸売業者に渡り、そこから販売店や販売会社へ送られて、消費者へ販売されます。
サプライチェーン・マネジメント導入の課題・サプライチェーンの問題とは
現在、日本でもサプライチェーン・マネジメントの重要性が認知されてきているのにもかかわらず、その導入に苦労している企業が多い現実があります。いったいどのような課題があるのでしょうか。
企業間・部門間の意思統一
日本企業の多くで、サプライチェーン・マネジメントを導入するときに問題となるのが、組織内、企業間で意思統一が取りにくい点です。サプライチェーン・マネジメントは部門や企業、ときには業界の枠を超えて同じ目標や情報、問題意識を共有しなければうまく機能しません。
意思統一が困難な原因としては次のような理由があります。
- 企業間での利害対立
- サプライチェーン・マネジメントへの参画意識の薄さ
- 部門や組織ごとに目標や計画が違う
- 現場が強すぎてデータを残さない、残しても最適化されない
特に日本の大企業では、部門別・機能別の組織体制が強く「部分最適」の考え方から脱却するのが難しい傾向があります。関係する組織すべてに、どうやって「全体最適」という考え方やデータの最適化を浸透させるかがカギとなるでしょう。
組織としての透明性の低さ
日本の組織特有の、透明性の低さも問題になってきます。
多くの企業において、部門や部署単位で動くことが多く「ウチとソト」を分ける感覚が強い傾向があります。そのため「よそ者」と情報やデータを共有することへの抵抗感があり、これも「全体最適」を妨げる要因となっています。
ましてや他の企業を含めたサプライチェーンとなればなおさらです。関連企業の中には、同業他社とも取引のあるケースも少なくないため、情報の共有をどのように行うかは考えるべき問題と言えるでしょう。
DX化の遅れ
企業や官公庁など、国内の組織でDX(デジタルトランスフォーメーション)が進まないことも課題のひとつです。
国内の会社では多くの基幹業務システムが老朽化、ブラックボックス化しており、このレガシーシステムをどう刷新するかが問題となっています。ところが、予算や人員の不足、セキュリティへの不安から、新しいシステム構築や投資に消極的な実態があります。
加えて日本の組織の透明性の低さも「データ共有」や「オープン性」の大事さが認識されない一因となっています。「全体最適」の実現に不可欠なDXの進展は、早急な解決策になります。
【関連記事】デジタルトランスフォーメーション(DX)とは?SDGsとの関係・事例をわかりやすく解説
リスクへの柔軟性
サプライチェーンを構築する上で避けて通れないのが、各種リスクへの対応です。
近年、日本では毎年のように自然災害に見舞われ「サプライチェーンの途絶」が問題となってきました。さらに新型コロナウィルスの蔓延や世界各地の紛争や騒乱によって、関連企業が経営危機に陥ったり、グローバルな物流が脅威にさらされていたりするという現状があります。
こうした内外のリスクに対し、サプライチェーンの二重化や生産拠点の分散化、雇用の促進などの維持・強化を進める必要性も求められています。
費用や人材の問題
多くの企業にとって、サプライチェーン・マネジメント導入のハードルになるのが、適切な人材と相応の費用が必要になることです。
サプライチェーン全体と連携した管理体制を構築するには、大規模な基幹業務システムを入れることになります。そのため、こうしたシステムを導入しているのは、すべてのサプライチェーンを自社のコントロール下に置ける規模の大企業であるケースがほとんどです。
規模の面で不利な中小企業がサプライチェーン・マネジメントを取り入れるには、関連会社や取引先との協力体制を従来以上に強化することや、自分たちのビジネスに最適化されたシステムを絞り込むことが求められます。
セキュリティの脅威
近年増加しているサイバー攻撃に、サプライチェーン攻撃があります。サプライチェーンの中でセキュリティ対策が不十分なシステムへの攻撃を足がかりとしながら、関連企業や取引先といったサプライチェーン全体へ攻撃を広げるサイバー攻撃です。
海外に拠点を置く関連企業へサイバー攻撃され、そこから本社システムへの不正アクセスがあった事例があります。また人的要因によるリスクもあります。委託先従業員によるデータベースの不正利用によって、当該企業の信頼が失われてしまった事例もあります。
このように、自社のセキュリティのみでなく、サプライチェーン全体を意識したセキュリティ対策が必要となってきます。
サプライチェーンから見る人権問題
2011年に国連人権理事会にてビジネスと人権に関する指導原則が全会一致で支持され、ビジネスの場においても人権尊重を求める動きが国際的に加速しています。
サプライチェーンが世界中に広がっている現在、自社で行なっているビジネスが世界全体に影響を及ぼすということを意識していることが重要です。過去「人権」は政治と結び付けられてきましたが、企業活動の過程で生じる人権リスクにも注目が集まっています。
人権デュー・ディリジェンス
人権デュー・ディリジェンスとは、自社のみでなくグループ会社、取引先といったサプライヤーチェーン全体における人権侵害について、
①人権侵害等の特定・評価
②防止・軽減
③取組の実効性の評価
④情報開示
を行う一連のプロセスを指します。このプロセスは一度行えば完了といったものではなくて、継続的に実施していくことでサプライチェーン全体の人権が守られていきます。ステークホルダーとの継続的な対話が必要です。
日本企業のサプライチェーン・マネジメント導入事例
ここからはサプライチェーン・マネジメントを導入している企業の事例を紹介していきます。取り組みの内容のほか、サプライチェーン・マネジメントを環境対策の一環として行っている会社は、併せて例をあげました。
パナソニック
国内屈指の家電メーカーであるパナソニックでは、サプライチェーン・マネジメントの切り札として2021年より、現場最適化ソリューションを導入しました。
画像認識・センサー技術を使った「可視化アプリケーション群」と、蓄積したノウハウをデジタル化してAIに組み込む「最適化アプリケーション群」により、シフト・生産管理・庫内・輸配送のあらゆるプロセスで最適化が行われています。
公募式の環境配慮型サプライチェーン・マネジメント「ECO-VC活動」
パナソニックのサプライチェーン・マネジメントで特徴的なのは「ECO-VC活動」と呼ばれる活動を行っていることです。
ECO-VCとは、温室効果ガス削減や循環型モノづくりといった環境配慮活動と、コスト合理化とを両立させる取り組みで、サプライチェーンすべてのプロセスを対象として、世界中の購入先からアイデアを募っている点がユニークです。優れた取り組みは審査の上表彰し、グループ全体での活動に取り入れています。
花王
石鹸をはじめ、洗剤や化粧品などサニタリー製品を数多く展開している花王も、優れたサプライチェーン・マネジメントを行っている企業です。花王では、国内外1500アイテムにも及ぶすべての品目情報を統合し、在庫を管理するために、過去の様々な新製品の出荷挙動をモデル化、出荷実績に基づいて今後を予測しコントロールするシステムを導入しています。
輸送に関してもデータベースを構築し、製品アイテム毎にかかるコストを要因別に管理し、物流の最適化を図っています。
サプライチェーンを含む環境ガイドラインの設定
また花王では、独自の環境ガイドラインを設け、自社のみならずサプライチェーンを構成するパートナー企業にも、「社会的責任」と「環境」への配慮を求めています。取引先に対し、Sedex※1やCDPサプライチェーンプログラム※2への入会や活動を奨励しています。加えてサプライチェーン全体のトレーサビリティや、資源保護・環境保全や安全、人権など社会課題上のリスクを特定する、取引先への第三者監査等を実施するなどといった項目もガイドラインに設けられています。
※1:Supplier Ethical Data Exchange。倫理的かつ責任あるビジネス慣行の促進を目的に、労働基準、健康と安全、環境、ビジネス慣行に関する情報の共有と確認を行なう国際的協働プラットフォーム
※2:CDPはロンドンに本部がある非営利団体。気候変動、水、森林に関する情報開示を世界の主要企業に求める活動等を行なっている。サプライチェーンプログラムは、その情報開示をサプライチェ-ン全体を対象に行うプログラム
リコー
複合機やプリンターなどオフィス向け画像機器の製造販売やサービスを展開するリコーは、調達、生産から販売、回収・リサイクルまでの全工程でグローバルなサプライチェーン・マネジメントを行っています。
マネジメントのカギとなるのが
- Global Inventory Viewer(GIV/在庫可視化ツール):グローバルに在庫のモニタリング測定ができるシステム
- MB&R方式:モジュール(製品の共通コア部分)を作ってから世界各地の生産拠点へ送り、組み立てて仕上げる方法
です。これによって、生産性の向上や戦略機種へのシフト、購入原価の低減につながっています。
コストと環境負荷の両方を削減
リコーではサプライチェーン・マネジメントの導入により、コストダウンと環境負荷低減の両立を行っています。
例えば、
- 調達:環境面や行動規範の遵守をサプライヤー企業に求める
- 物流:環境負荷の低い梱包材や省エネな輸送手段の利用
- 回収・リサイクル:効率の良いリサイクルを実現するための製品回収ネットワーク
などがあります。サプライチェーンの効果的な管理が、同時に環境負荷の低減をもたらしているのです。
タビオ株式会社
タビオ株式会社は、「靴下屋」をはじめとする靴下ブランドを展開するアパレル企業です。
タビオが構築した「タビオネットワークシステム」は、大企業以外でもサプライチェーン・マネジメントを構築できる好例です。
物流面でのオンライン受注システムと、製造面でのオンライン生産管理システムからなります。これにより原料確保から製造、流通、小売までのすべての段階で商品の販売情報が共有されました。ここから売れ筋情報や必要な素材、生産量が把握でき、スピーディーな発注も可能にしています。
サプライチェーンのメリット
サプライチェーンを適切に構築・管理することで、企業はコスト削減や効率化だけでなく、安定した供給体制や顧客満足度の向上といった多くの利点を得られます。ここではサプライチェーンの主なメリットを整理して紹介します。
コスト削減や効率化
サプライチェーンを最適化することで、原材料の調達から生産、流通、販売に至るまでの無駄を減らし、コスト削減や業務効率化が可能になります。例えば、在庫管理を適切に行うことで過剰在庫や欠品を防ぎ、保管コストを削減できます。
また、生産計画を需要予測に基づいて調整することで、余分な生産を避けられます。さらに物流網の合理化や輸送手段の見直しによって、輸送コストの圧縮や配送リードタイムの短縮も期待できます。このようにサプライチェーンの効率化は、利益率の改善に直結する重要な施策といえます。
納期短縮や安定供給
サプライチェーンを適切に管理することで、需要の変化に素早く対応しやすくなり、納期の短縮や安定的な供給体制を築けます。例えば、リアルタイムで在庫状況や輸送経路を把握できるシステムを導入すれば、急な需要増にも迅速に対応可能です。
また、複数のサプライヤーと契約しておくことで、特定の供給元がトラブルに見舞われても代替調達ができ、供給の途絶を防げます。こうした仕組みは顧客への信頼性を高め、継続的な取引関係の強化につながります。安定供給を実現することは、企業競争力の維持に欠かせません。
品質向上や顧客満足度向上
サプライチェーンを統合的に管理することで、製品やサービスの品質を高め、顧客満足度の向上につなげられます。例えば、原材料の調達段階から品質基準を徹底し、製造や物流の各工程で情報を共有すれば、不良品の発生を減らすことができます。
また、配送の遅延や欠品といった顧客に不利益となる事態を防ぐことができれば、企業への信頼が強まります。さらに、サステナビリティや人権配慮を組み込むことで、社会的評価やブランド価値の向上にもつながります。結果としてリピーターの増加や市場での競争優位性を確保できるのです。
サプライチェーンのデメリット
一方で、サプライチェーンは多くの組織や工程が関わるため、効率化の裏で新たな課題やリスクも生じます。ここではサプライチェーンの代表的なデメリットについて解説します。
自然災害や地政学リスクの影響を受けやすい
サプライチェーンは国際的に広がるほど複雑化し、自然災害や感染症、戦争や国際的な緊張などの外部要因に大きな影響を受けやすくなります。例えば、地震や洪水による工場停止、パンデミックによる輸送網の寸断、または紛争や制裁による物流の停滞が発生すると、全体の供給が滞ります。
一部の地域や企業に依存している場合、その影響はさらに深刻です。このように、グローバル化したサプライチェーンは効率性を高める一方で、外的リスクへの脆弱性が高まるという課題を抱えています。
供給不足や柔軟性低下につながる
サプライチェーンの効率化を追求しすぎると、在庫削減や生産工程の最適化が行き過ぎ、需要変動に対応できないリスクが生じます。特に「ジャストインタイム方式」では在庫を最小限に抑えるため、突発的な需要増や供給元のトラブルに対応できず、欠品や納期遅延が発生しやすくなります。
また、生産や物流の選択肢を絞り込みすぎると、柔軟性が低下し、顧客ニーズの変化に対応しにくくなる点も課題です。効率性と柔軟性のバランスをどう取るかが、サプライチェーン設計における大きな難題です。
管理コストや中小企業への負担が大きい
サプライチェーンを高度に管理するには、在庫管理システムや需要予測ツール、物流追跡システムなどの導入が必要です。これには多額の投資や運用コストが伴い、大企業に比べて資金力に限りのある中小企業にとっては大きな負担となります。また、取引先との情報共有や調整のために人員や専門知識も必要であり、内部リソースを圧迫します。
さらに、ITシステムに依存する度合いが高まることで、サイバー攻撃やシステム障害によるリスクも増大します。効率化と同時に管理コストの抑制策をどう講じるかが課題です。
サプライチェーンに関するよくある質問
サプライチェーンは専門用語や範囲が広いため、意味や仕組み、リスク、企業での活用方法などについて疑問を持つ方も少なくありません。ここでは、サプライチェーンに関して多く寄せられる質問に答えていきます。
サプライチェーンとの定義と具体的な意味は?
サプライチェーンとは、原材料の調達から生産、流通、販売、そして消費者の手に届くまでの一連のつながりを指す概念です。単なる物流経路ではなく、メーカーや卸売業者、小売業者、物流会社など複数の企業や組織が関わるネットワーク全体を意味します。
英語では「supply chain」と呼ばれ、日本語では「供給網」や「供給連鎖」と言い換えられることもあります。現代のサプライチェーンは国境を越えて複雑化しており、効率的に管理することでコスト削減や顧客満足度向上につながる一方、リスク管理の重要性も高まっています。
サプライチェーンとバリューチェーンとの焦点の違いは何?
サプライチェーンとバリューチェーンは似た概念ですが、焦点が異なります。サプライチェーンは「モノがどのように流れるか」を重視し、調達から生産・流通・販売に至るまでの供給の流れを表します。
一方でバリューチェーンは「価値がどのように付加されるか」を分析するフレームワークです。マイケル・ポーターが提唱したもので、原材料が製品に変わる過程でどのように利益や差別化が生まれるかを示します。
つまり、サプライチェーンは供給網、バリューチェーンは付加価値を生む活動の連鎖と整理できます。企業戦略では両者を組み合わせて効率と競争力を高めることが重要です。
SCM(管理手法)による最適化の仕組みは?
サプライチェーンマネジメント(SCM)とは、原材料調達から消費者への販売までの供給網全体を効率的に管理・最適化する経営手法です。従来は各段階が個別に管理されていましたが、SCMでは流れを一体的に把握し、在庫削減やコストダウン、納期短縮を実現することを目的とします。
例えば需要予測に基づく生産調整や、物流の最適化、ITを活用したリアルタイムの情報共有などが含まれます。企業にとっては競争力向上や顧客満足度アップに直結しますが、同時に外部環境の変化に敏感でリスク対応力が問われる点も特徴です。
サプライチェーンを脅かす外部リスクの種類は?
サプライチェーンリスクとは、予期せぬ事態により供給に支障が出る可能性を指します。代表的なものには、自然災害や感染症による工場の停止、国際紛争や地政学的緊張による輸送の遮断、主要取引先の倒産などがあります。
近年はグローバル化によって供給網が広域化しているため、一部の地域で起きたトラブルが世界全体へ波及する危険性が高まっています。
サプライチェーンにおける人権・環境への責任とは?
現代のサプライチェーンでは、供給網全体での社会的責任(ESG)が厳しく問われています。自社だけでなく、委託先での強制労働や児童労働といった人権侵害、不適切な廃棄による環境破壊がないかを管理する「人権デュー・ディリジェンス」が求められます。
これらの問題が発覚した場合、企業のブランド価値や信頼を大きく損なうリスクがあるため、透明性の高い管理が不可欠です。
サプライチェーン・マネジメントとSDGsの関係
サプライチェーン・マネジメントの導入は、SDGsの目標達成にもつながります。
一見あまり関係なさそうにも思えますが、そこには私たちがこれから目指していくべき社会のあり方が、ビジネスの立場から提案されています。
SDGs(Sustainable Development Goals)は、「持続可能な開発目標」と呼ばれます。2030年までの解決を目指し、世界中の国や企業、個人で取り組むべき17の目標と169のターゲットを定めたものです。その17の目標のいくつかはサプライチェーンの考え方とも関連してきます。なかでも特に関係するのが、目標12と目標17です。
SDGs目標12「つくる責任 つかう責任」
大量生産による、製品のロスや資源の浪費を削減することは、今後あらゆる産業で欠かせない事業課題となってきます。特にモノを供給する製造業・メーカーにとってこの問題は避けて通れません。ムリ・ムダ・ムラをなくし、効率的なビジネスを行うことで、持続可能な消費と生産活動にもつながります。
社会に対する責任も果たす
サプライチェーン・マネジメントを適切に行うことで、生産過程における社会的責任をだれが、どのくらい果たせているかも明確になります。
「原料調達による強制労働や人権侵害の有無」「再生可能エネルギーの利用度合い」「温室効果ガスの排出量」といった、品質情報をサプライチェーン同士で共有し企業活動に反映させることで、SDGsの目標達成にも貢献します。
>>関連ターゲット
12.6 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。
SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」
サプライチェーン・マネジメントは、生産活動に関わるすべての企業が緊密に連携することで効果を発揮します。企業間で優劣をつけたり、特定の大企業が関連会社を「子会社」「下請け」と見なして厳しい条件を課したり、不利益を強いたりするようなビジネスは「全体最適」の仕組みを損ないます。
対等、公正なパートナーシップで皆がWin=Winになって初めて、目標達成に近づくのです。
>>関連ターゲット
17.16 全ての国々、特に開発途上国での持続可能な開発目標の達成を支援すべく、知識、専門的知見、技術及び資金源を動員、共有するマルチステークホルダー・パートナーシップによって補完しつつ、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを強化する。
まとめ
サプライチェーン・マネジメントは、グローバル化やIT化が進み、多種多様になっていく世界で、経済活動における共通認識となっています。
そのベースになる考え方は「みんなで協力して」「無理せず、でも手早く効率よく」「ムダをなくしていこう」というものです。
限りある資源を有効に活用し、持続可能な経済体制を作り上げるには、すべての企業やそこで働く私たちが、サプライチェーンという考え方を意識することが不可欠になってくるのです。
<参考文献>
トコトンやさしいSCMの本 第3版 鈴木邦成/日刊工業新聞社
日本企業がSCMの課題を乗り越えるための3つのポイント – GEMBA
デジタル技術の活用によるサプライチェーンの 強靱化 – 経済産業省
トピックス 物流連続講演会「花王におけるSCMへの取り組み」郵政研究所月報 2002.8
花王株式会社 – ABeam Consulting
サプライチェーンにおけるパフォーマンス測定システムの構築・運用
再導入・再構築が進むSCM(サプライチェーンマネジメント)とは?
この記事を書いた人
shishido ライター
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。