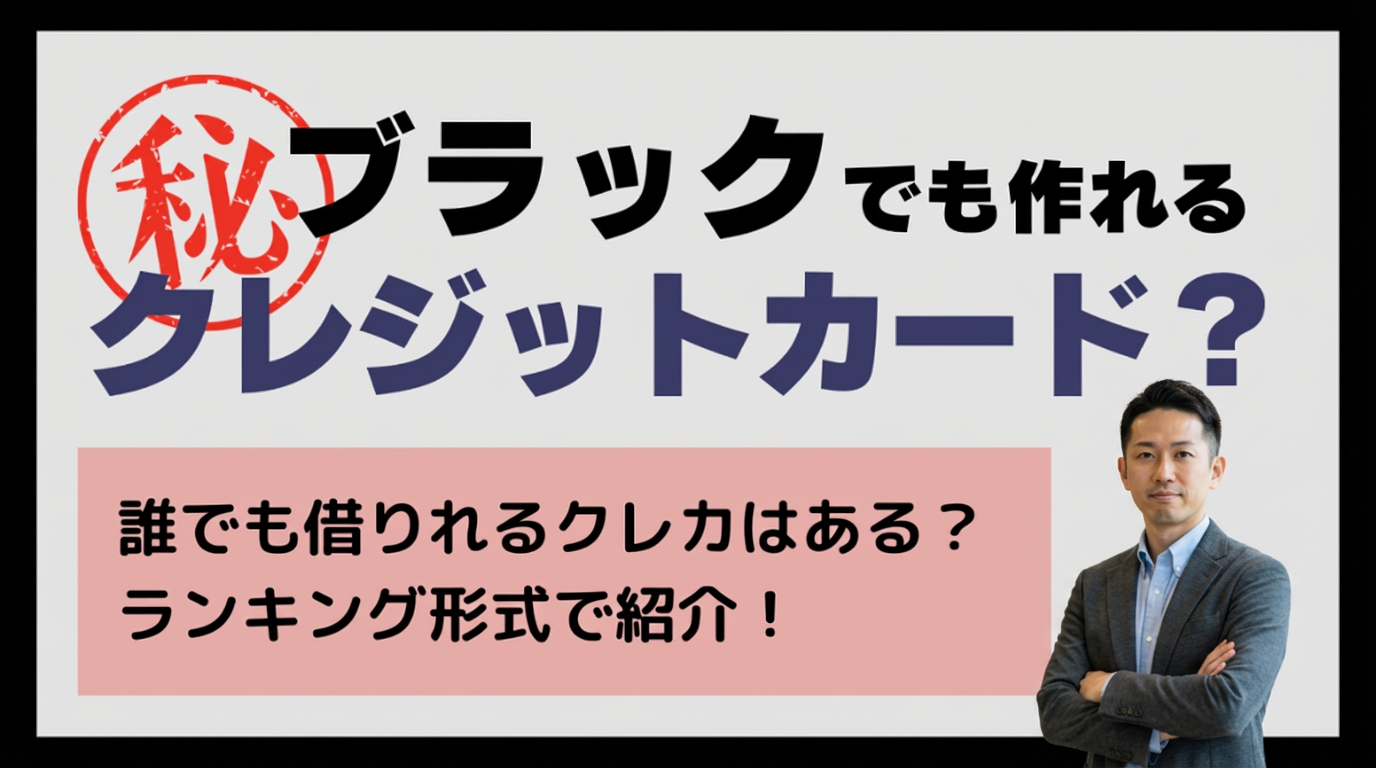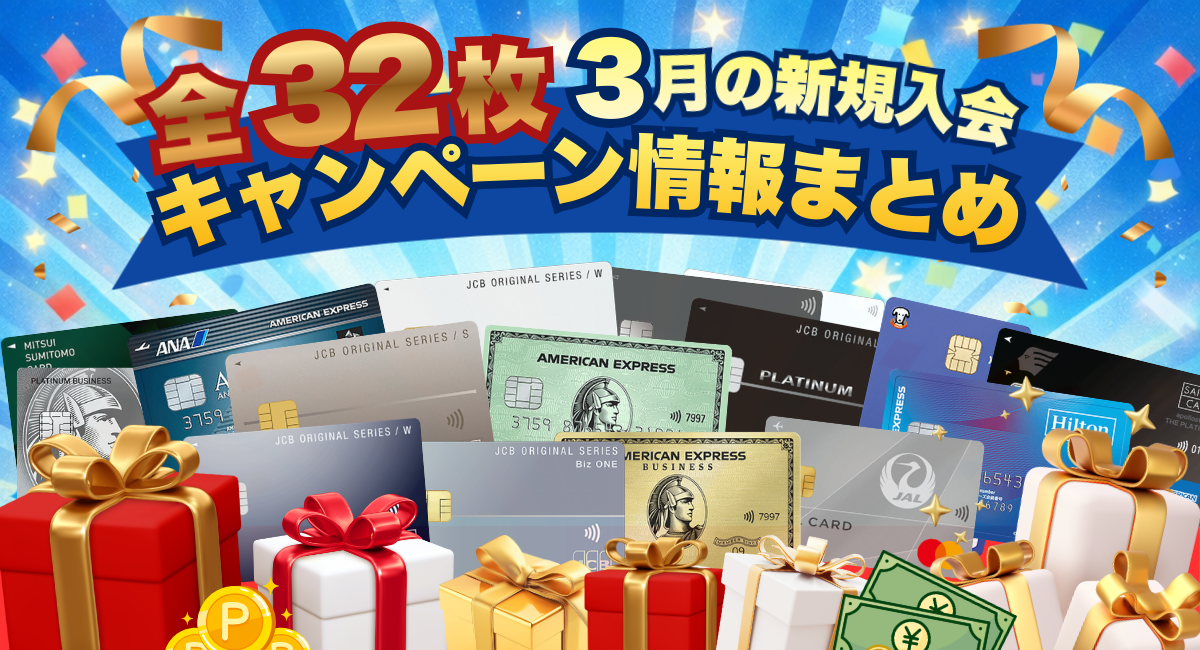株式会社土屋 高浜敏之さん インタビュー

高浜敏之
代表取締役 兼 CEO 最高経営責任者
慶応義塾大学文学部哲学科卒 美学美術史学専攻。 大学卒業後、介護福祉社会運動の世界へ。自立障がい者の介助者、障がい者運動、ホームレス支援活動を経て、介護系ベンチャー企業の立ち上げに参加。 デイサービスの管理者、事業統括、新規事業の企画立案、エリア開発などを経験。
2020年8月に株式会社土屋を起業。代表取締役CEOに就任。趣味はボクシング、文学、アート、海辺を散策。
目次
introduction
福祉業界で人手不足が取り上げられてから久しい中、創業からわずか4年弱で、数百人の職員を採用し、今では約2,700人が働く土屋グループ。福祉業界の採用の成功モデルといわれています。
事業においては、「重度訪問介護事業」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に注力し、経営が難しいといわれる業界を牽引しています。
今回は、代表取締役兼CEO最高責任者である高浜敏之さんに、企業理念や事業内容、課題への取り組みなどについてお聞きしました。
マイノリティーの小さな声を拾い、聴き、応えることが使命
–はじめに、株式会社土屋のご紹介をお願いします。
高浜さん:
2020年8月に創業した株式会社土屋は、9社のグループ会社からなる土屋グループの中核となる企業です。
現在、グループ全体で約2,700人の従業員が働いています。
すべての会社が、高齢者や障がいを持つ方々の支援・介護、教育や医療に関連する事業を展開しています。
メイン事業は、グループ会社のホームケア土屋が展開する「重度訪問介護事業」です。
さらに、高齢者向けのサービスとして、訪問看護・定期巡回型事業・デイサービスなど様々なサービスを提供しています。
その中でも現在は、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に注力しています。
また、企業理念として『「生き延びる」の肯定』を掲げ、今まで以上のサービスの充実を目指しています。
《訪問介護の様子》


–御社の企業理念『「生き延びる」の肯定』について、もう少し詳しくお聞かせいただけますか。
高浜さん:
これは、いわゆる「生存肯定」です。「生き延びる」は「生きる」とは違い、置かれている環境が厳しい時に使われる言葉だと思うんです。「戦場を生き延びる」などと使われますよね。
先週までベトナムに行っていましたが、貧富の格差が非常に大きく、生きていくのがやっとという人達を多く見かけました。彼らは、自然に生きているというよりも、「努力して生き延びている」という表現の方が合っているのではないかと感じました。
私達が事業を展開する中で出会う方々も、生きる努力が必要な方ばかりです。
そして、非常に残念なことに、生き延びることをあきらめざるを得ない方々も多くいらっしゃるんです。
弊社が注力していることの一つのに、ALS(筋萎縮性側索硬化症)という難病の方々の支援があります。手足・のど・舌の筋肉や呼吸に必要な筋肉がだんだん痩せていくのですが、 筋肉そのものではなく、筋肉を動かし、運動をつかさどる神経が主に障がいを受ける病気です。
病状が進むと、呼吸ができなくなり、人工呼吸器を使うか使わないかの選択を迫られるときが来ます。人工呼吸器を使わなければ延命は難しいのですが、現在、約70%のALSの患者さんが使わない選択をします。
これは本人の希望というよりは、十分なケアサービスを受けるのが難しいという現状によるものです。人工呼吸器をつけた後にケアサービスが受けられなければ、家族の負担が大きくなります。家族に迷惑をかけたくないという思いで、人工呼吸器を使わない選択をする方が多いんです。
私は、ケアサービスをインフラとして充実させることが、「生き延びる」を選択できる条件の一つと思っていますので、この『「生き延びる」の肯定』を弊社のフィロソフィーとして掲げています。


また、生き延びることを肯定するためには、人やいろいろなテクノロジーなどとのつながりが持てる環境が重要だと考えています。つながり合い、支え合う場を構築することが私達の存在意義だと思いますので、「つながりあいささえあう場の創造」をパーパスとして掲げています。
そして、このようなつながりの場から遮断されている社会的弱者、マイノリティーの方々からの声はとても小さくて、聞こえづらいんです。ですから、私達は『探し求める小さな声を』を弊社のミッションとし、こちらからその声が聞こえる場所まで出向き、声を聴き、応えていくことを使命と考えています。
自分のしていることに疑念を抱かなくてもよい仕事がしたかった
–次に、高浜さんがなぜ福祉事業に取り組むようになったのか、きっかけをお聞かせいただけますか。
高浜さん:
私が福祉事業を仕事にしたきっかけの一つは、大学を卒業するときに、世の中のためになる仕事をしたい、自分がしていることに疑念を抱かなくてもよい仕事をしたいと思ったことです。
私は、2つの大学に通ったので、2校目の卒業は30歳のころでした。その頃、哲学に傾倒していた私に、友人が哲学者鷲田清一さんの『「聴くこと」の力:臨床哲学試論』という本を紹介してくれました。
この本は、「ケア」に関するいろいろな状況を哲学的に分析した本です。そこに、精神科医が不眠症で苦しむ女性のカウンセリングをする中で、二人の脈拍が完全に一致したということが書かれていました。
それを読んだとき、ケアという現場だからこその相互浸透性があり、人と人の境界線はそれほど太くはないんじゃないかと感じ、ケアの現場に興味がわきました。
もう一つは、私は新聞配達をしながら大学に通っていたんですが、2002年1月1日の夕刊に韓国の映画監督イ・チャンドンのコメントが掲載されていたんです。そこには「真のグローバリゼーション、それはハリウッド的大音量のスピーカーによる支配ではなく、世界の小さな声にお互い耳を傾け合えることでしょう」とありました。
その頃はアメリカの同時多発テロや、アフガニスタンの空爆など、テレビでは連日暴力的な
映像が流れる毎日で、私は金儲けをして稼ぎ、楽しく過ごすみたいな発想が全く浮かばなかったんです。
そんな背景があり、ケアに関わる仕事をしたいと思うようになりました。弊社のミッション『探し求める小さな声を』はその時の記憶から来ているものですね。
「介護難民」をなくし地域全体で高齢者を看る社会環境を作るには
–では、福祉業界での深刻な人材不足に対し、御社はどのように取り組んでいるのでしょうか。
高浜さん:
ケアが必要だけれど受けられない方々を「介護難民」と呼んでいますが、現在日本では、日々増え続け深刻さを増しています。これは介護の必要な人を受け入れる事業所も人手も足りないことが大きな原因です。
昨今、福祉事業の運営は日増しに難しくなっていて、倒産件数も毎年過去最高を更新しています。利用者はたくさんいるのになぜと疑問に思うと思いますが、経営が難しいというのは、介護職員を採用できない、人手不足だからです。
そこで、弊社ではこの問題を解決するために様々な取り組みを進めています。
まず一つ目は、事業を高収入化することです。収入が上がれば、間接コストに投資できます。最大の間接コストは採用投資だと思うので、そこにお金が使えれば人も来てくれます。人が増えればもっと利益が上がります。この採用と事業拡大の好循環が生まれていることが事業の高収入化の要因の一つだと思います。
事業の高収入化と、企業の規模・企業体力はリンクしているので、企業規模を追求してきた結果です。
また、社内の制度を見直してガバナンス体制を整え、良質な運営を心がけ、国からの加算金が多くなるようにしています。
もう一つは、マーケティング・ブランディングにも力を入れて知名度を上げ、人材を採れるように努力しています。
その成果もあり、毎月のように100名以上の応募があり、今までに数百名の入社が実現していますので、福祉業界の採用の成功モデルといわれています。
こういった取り組みの結果として、採用に関しては競争優位性が確立されてきましたが、一方で、ケアワーカーさんの高齢化という問題も出てきています。
そこを解消するために、今後は外国人の方々の力も借りたいと思っています。
これから、ベトナム・インドネシア・ミャンマー・スリランカ・フィリピンなど様々な国から人材を採用していきます。しかし、労働力を搾取するようなことがあっては絶対にいけませんか。そのため、外国で生活するための環境整備や教育などのフォローをきちんと行い、日本人と同じ賃金で働いてもらいます。家庭が貧しく、家族のために海外に働きに出る人達も多いので、少しでもその問題解決にもなれば良いと考えています。
《海外からの研修生や職員の方》

–御社では、高齢者の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に注力されているとのことですが、このサービスについてお聞かせいただけますか。
高浜さん:
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を非常に簡単に、わかりやすく言うと、街全体を高齢者施設にしてしまうということです。
《定期巡回・随時対応型訪問介護看護の様子》

一般的に、老人ホームといわれる施設は、建物の中に利用者の居室があり、介護職員が各室を見回りながら介護をします。
しかし、多くの高齢者が施設への入居を拒む傾向にあります。理由は、社会や今までの人間の様子の画像で関係から切り離され、特殊な場所に閉じ込められるという思いからの心理的抵抗だと思います。社会的排除の象徴だと見られる場合もあるんです。
それならば、地域全体を施設のようにして介護しようと、モデル事業が立ち上がり、始まったサービスです。
利用者は各自宅でそれまでと同じように暮らし、介護職員が利用者の家に必要な時に必要なだけ訪問してサービスを提供するという取り組みです。現在は、国の制度に定められています。
デイケア・訪問介護・訪問看護・定期巡回サービス、この4つがあれば、90%くらいの方が、住み慣れた土地で、最期まで、つまりターミナルケアも含め生きていくことができるのではないでしょうか。高齢者を最後まで地域で看るという社会環境を作ることができるのではないかと思います。
そして、ここでの課題も人手不足です。訪問介護と比べて介護職の資格要件が高いので、人員を集めるのが大変です。その中で、弊社には研修機関がありますので、資格を取得してもらい働いてもらえるようにしています。



また、この制度は経済的な効率も高いと思います。
高齢者施設を始める際に、建物を新しく建てると、莫大な資金がかかりますが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護なら建物は必要ありません。介護保障費の増大を抑制することも可能なのではないかと思います。
現在、全国7箇所で運営していますが、5年以内に100箇所まで増やしたいと考えています。
このサービスを本気で全国に展開しようと考えている企業は限られていますので、弊社がパイオニアになりたいと思っています。
ケアが必要なすべての人達のためのトータルケアカンパニーを目指して
–サービスを利用している方や働いている方はどのように感じていらっしゃるのでしょうか。
高浜さん:
利用する金額は一般的な施設の利用とあまり変わりありませんので、利用者の方々の負担が増えることはありません。
年々増えている、老後をひとりで暮らす方の生活を支えるサービスとしても有効だと思います。
家族の方々からは「このサービスのおかげで亡くなるまで自宅で暮らせた」と多くの声を聴いています。
最後まで、自宅で家族や友人と交流し、切り離されたくないという思いは強い方が多く、自宅で過ごす時間はとても大切で、このサービスの有効性を非常に感じます。
また、職員の意見ですが、実は弊社のすべてのグループの中で、このサービスに携わっている方達の満足度が一番高いんです。賃金も、比較的高く保証できますし、一定数いるターミナルケアの利用者さんの最後を、自分が見届けるということにも、大きなやりがいを感じてくれているようです。

–では最後に、今後どのように事業を展開して行くのか、展望をお聞かせください。
高浜さん:
まずは、日本の若い方達に介護職についてもらうのが大事だと考えていて、そのための仕掛けをいろいろ作りたいと思います。
いまの若い方たちは、小さい時からSDGsの教育を受けていますよね。ですから、世の中に貢献したい、やりがいのある仕事をしたいという気持ちは強いと思うんです。しかしそれだけではなく、働き方や休日の使い方、社内環境などにも敏感です。
ですから、働きに見合った賃金がきちんともらえ、キャリアアップもできる環境が用意されていることを示せないと事業は成功しないと思います。今後はますます企業のイメージなどにもこだわって戦略を立てていきたいと考えています。
弊社は、社会問題を解決していくという事業内容から、SDGsすべてをビジネスのテーマとしてとらえています。
今後は、ケアサービスを高齢者・障がいを持つ方・児童を問わず、ケアが必要な方々すべてに広げ、トータルケアカンパニーとして、展開したいと考えています。
また、すでに農業法人を子会社化していますが、「ケア」という枠を超え、様々な事業にチャレンジできるように、ホールディングス化を進めようと思います。
その半面で、サステナブルに対しては鈍感だということにならないように、社内での意識啓発を大事にし、SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」を自分ごととしてしっかり取り組める企業風土を作り、多くの方にあの会社で働きたいと思ってもらえるような企業に進化させていきたいと考えています。
–本日は貴重なお話をありがとうございました。
株式会社土屋公式WEBサイト:https://tcy.co.jp/
この記事を書いた人
中島卯月 ライター
フリーランスのライターをしています。以前は、電機メーカーや飲食店での勤務、化粧品の卸、販売店の経営、エステティシャンなどいろいろな経歴があります。駐在員の家族として通算約10年、アメリカでの生活もしており、その間に出産や子育ても経験しています。皆様の“読みたい!”記事が書ければ嬉しく思います。
フリーランスのライターをしています。以前は、電機メーカーや飲食店での勤務、化粧品の卸、販売店の経営、エステティシャンなどいろいろな経歴があります。駐在員の家族として通算約10年、アメリカでの生活もしており、その間に出産や子育ても経験しています。皆様の“読みたい!”記事が書ければ嬉しく思います。