
2025年現在の日本は、いまだ経済的に裕福な先進国の地位を保っています。しかし国民の多くは、実際には家計に不安を抱え、決して楽とは言えない状況をどうにか乗り切っているというのが現状です。
こうした長引く不況は、元を正せば1990年代からの「失われた30年」に端を発しています。今回改めてその概要や原因を振り返ることで、今後の日本の取るべき道や、私たちの政治や社会、そして仕事への向き合い方を考えるきっかけになるのではないかと思います。
目次
失われた30年とは?

失われた30年とは、1990年代から始まった日本経済の長期低迷期を指す言葉です。
その始まりが具体的に何年からとは定義されていませんが、バブル経済が崩壊した1991年を契機とする見方が多いようです。
当初は「失われた10年」と言われていましたが、その後も経済の低迷は続き、景気回復も進まなかったことから、10年が20年となり、やがて30年を過ぎて現在に至ります。
失われた30年で起きたこと

1990年代からの30年と言っても、当時を知らない世代の方には実感しづらいかもしれません。このおよそ30年の間に、どのようなことが起きたのか。主な出来事を、時系列で見ていきましょう。
1991年:バブル経済の崩壊
日本でバブル経済と呼ばれる状態が崩壊したのがこの時期です。
直前の1980年代後半から90年代は、日本では株価や土地の価格が実体を伴わない異常な高値をつけ、国中が好景気に沸いていました。
しかし90年に日銀が公定歩合(中央銀行が市中銀行に貸付ける基準金利)を引き上げたことで、
- 株価:1989年12月29日の3万8,915円を最高値に、1990年10月には半分の2万円割れにまで下落
- 地価:翌91年に下落が始まり6大都市商業地価は87%下落。年間下落率は92年15%、93年には25%弱
という、株価と地価の大暴落に見舞われます。
地価の下落は2005年まで続き、不動産投資に関わっていた銀行やノンバンク、不動産業者に致命的な打撃を与えました。
企業倒産の増加

バブルの崩壊により、銀行から借りたお金を返せなくなった企業の倒産が相次ぎました。
この時期の倒産による負債総額は、1990年の2兆円余りから、翌91年には8兆円台、2000年には24兆円に達します。この結果、銀行も資金の貸し出しに慎重になり、倒産を免れた多くの企業は設備や人材への投資を控えるようになります。
1990年代後半①:橋本内閣による財政政策
バブル崩壊後に政府は公共投資の拡大などの対策をとり、デフレ対策が機能し始めたことで景気も回復の兆しを見せました。そんな中1996年から始まった橋本政権は公共投資拡大で増加した財政赤字を防ぐため、
- 財政健全化:財政支出の抑制と見直し
- 社会保障改革:民間活用や効率化
- 経済構造改革:規制緩和や環境整備による高コスト体質の是正
- 自由競争に基づく金融市場の改革
- 消費税率の3%から5%への引き上げ
などの構造改革を打ち出します。しかしこの改革は、後述する金融機関の破綻やアジア通貨危機の発生などで政策を転換せざるを得ず、かえって景気を後退させることになります。
1990年代後半②:金融再編の進行と公的資金の注入
この時期には、企業倒産の増加などで貸し付けたお金が回収できず、巨額の不良債権を抱えた金融機関の破綻が相次ぎました。
- 1997年11月:北海道拓殖銀行の破綻と山一証券の自主廃業
- 1998年:日本長期信用銀行、日本債券信用銀行が一時国有化
- 銀行の合併による統合
などは、その典型的な事例です。
膨れ上がった不良債権を処理するために、政府は公的資金を注入して救済に乗り出します。
この時期政府が投じた公的資金は、銀行の統合の後押しや不良債権の買い取りなどで合計38兆円にも上ります。
2002年から04年にかけて貸し出しの低下と貸出金利の下落に見舞われたこともあり、国内の金融機関は苦境に立たされることになりました。
2000年代:小泉政権の改革

2001〜2006年には、小泉純一郎首相による構造改革が進められます。
小泉政権の改革の柱は
- 官から民へ:公共部門の民営化
- 規制緩和:医療、介護、教育などの分野に競争原理を導入
- 多様な就労形態を選択できる労働市場の改革
- 年金や社会保障制度の負担引き上げ
など、「小さな政府」を志向した新自由主義政策とも呼べるものです。小泉政権下では、輸出の増加によって景気回復を見せるものの、不良債権処理の強行による失業率の上昇や内需の停滞によって実質的な経済改革の成果は見られませんでした。
2010年代:民主党政権からアベノミクスへ
2009年からは民主党が政権をとり、「コンクリートから人へ」を進めた鳩山内閣のもと、2010年にGDP実質成長率を4.2%に高めるなど、景気は一時回復を見せます。しかし、
- 菅内閣=成長重視、財政再建路線への回帰、財界寄りなど自民党のような政策
- 野田内閣=「社会保障と税の一体改革」に向け自民・公明党と政策合意
など、生活重視の政策を後回しにするような路線変更を行ったことで支持を失い、3年で政権を自民党に奪い返されます。
2012年から長期政権を担った第二次安倍政権では、アベノミクスと呼ばれる経済政策を打ち出し、
- 異次元の金融緩和政策
- 機動的な財政政策
- 民間投資を喚起する成長戦略
などの改革を進めます。その結果、2012年には景気が回復に転じ、2013年の実質GDP成長率も2%に達しました。
しかし、その間も民間の消費支出は伸び悩み、実質所得低下や社会保障制度改悪などによって、2014年からは再び景気が落ち込むことになります。
結果的に1990年代からの日本の経済低迷は、ことごとく失敗に終わりました。
2020年代に入った現在でも、新型コロナウイルスの蔓延による経済停滞や、ウクライナ侵攻による物価高騰の影響などによる不況を解決できないまま、現在に至っています。
失われた30年の原因

失われた30年を生み出した原因については、現在も経済学者やエコノミストらの間で議論が続いています。その中で最も一般的な要因として挙げられるのは以下のような理由です。
原因①不良債権処理の遅れ
失われた30年の最も大きな原因に挙げられるのは、不良債権処理の遅れです。
2008年のリーマン・ショックの際7000億ドルもの公的資金を一気に投入し、金融システムの回復や公的資金の回収を素早く進めたアメリカとは対照的に、日本の不良債権処理は実に15年もの時間を要しました。当時の不動産事業では、住宅金融専門会社(住専)が大蔵省の天下り機関になっていたなどさまざまな利権が絡んでおり、政治家も事業者も不良債権処理に手をつけることをタブー視する状況が続きました。
公的資金投入の是非については現在もさまざまな意見がありますが、こうした対応の遅さが問題を長引かせた要因であることは間違いないでしょう。
原因②少子高齢化
失われた30年の背景には、少子高齢化という要因も無視できません。
日本の生産年齢人口は1995年頃から減少し始め、働き手が減った分の所得税収は低下していきます。こうした傾向が高まることにより
- 税収の減少を補うため国債の発行を増やす
- 高齢者の増加により社会保障費が増大する
- 高齢化が進むと貨幣への需要が増え、物への需要が減少する
などにつながり、経済成長を阻害する要因となります。
実際にはこうした因果関係は立証されていませんが、生産年齢人口の減少が始まった1995年頃から国債の発行残高が急激に膨張し始めたことからも、その可能性は十分にあると言えます。
原因③企業の人的投資削減

長期的に日本経済の土台を切り崩すきっかけとなったのが、この時期から企業が雇用や賃金、教育などの人件費を削減してきたことです。
バブル崩壊のあおりを受けて体力が低下し、金融機関からの融資も得られない多くの企業は、投資を控えて資金をため込むことを優先するようになります。
社員への昇給は抑えられ、教育や人材育成も投資ではなくコストとして削減の対象となりました。そのため、この時期に社会人になった人の多くは不況の後始末に追われ、生産性向上のための経験やスキルを身につける機会を失うことになります。
原因④非正規雇用の拡大
そして日本経済に大きな打撃を与えたのは、1990年代から政府が進めてきた、労働市場の自由化に伴う非正規雇用の拡大と一般化です。
当初、制限されていた非正規雇用は、政権が変わるにつれ適用範囲が拡大され、現在ではほぼ全ての業種で認められるようになっています。
こうした、賃金を低く抑えられた非正規労働者の増加と正社員の昇給抑制は、失われた30年の大きな原因のひとつとして現在に至るまで続いています。
原因⑤相次ぐ構造改革の失敗

国の構造改革がことごとく不調に終わったことも、経済低迷が長く続いた原因です。
この30年の間、政府は落ち込んだ経済を立て直すべく、さまざまな金融・財政政策を打ち出してきました。にも関わらず、日本の経済成長率は現在に至るまでおおむね平均1%前後で低迷し続けています。その理由としては
- 政府の低金利政策が長引きデフレを引き起こした
- 段階的な消費税引き上げで家計消費が落ち込んだ
- 財界や企業、アメリカなどの利害を優先する政策が中心
- 賃金抑制や非正規雇用の促進、社会保障制度の改悪
などが挙げられ、多少の方針は違えど、国民の生活よりも企業の業績を優先する施策はどの政権においても共通しています。その結果、企業の年間経常利益は倍増したにも関わらず、働く人の年間給与額はおよそ30万円、約7%も落ち込みました。たとえ景気が良くなっても賃金は上がらない。そんな社会へと、日本経済の構造が変わっていったのです。
原因⑥社会のデジタル化への遅れ
失われた30年の間に、日本がデジタル化に遅れをとったことも手痛い失策でした。この時期には世界中でインターネットの普及が進み、アメリカを始めとする先進国はデジタル技術を活用したイノベーションを生み出し、経済を成長させてきました。
一方日本では
- 不良債権問題を優先しITへの投資や人材育成への関心が低かった
- まだ勢いがあった製造業は従来の技術に慢心しデジタル化に消極的だった
- 大企業が海外に拠点を移し、中小企業のスキル向上やデジタル化の必要性が低下
などの理由でデジタル化に後ろ向きなまま、社会全体で現状維持と思考停止の状態が続きました。その結果、日本はイノベーションの力を失い、経済が停滞していったのです。
失われた30年による影響

失われた30年による影響は、日本経済に計り知れないダメージを与え、私たちの生活にも暗い影を落とし続けてきました。
日本の国力低下
最も深刻な影響は、全体的な日本の国力の低下です。
まず経済面では株価の低迷があります。現在は大きく持ち直していますが、1989年末に3万8,915円87銭をつけた日経平均株価は、2019年末には2万3,656円62銭まで落ちるなど、株価の低迷が長期にわたって続いたことが痛手となりました。
もう一つの大きな要素は、日本の競争力の低下です。
さまざまな国際競争力ランキングでも、
- 日本の国際競争力:1992年の1位→2019年には30位
- グローバル企業収益ベスト500:1989年は日本企業が111社→2019年には52社に減少
- 名目GDP:中国、ドイツに抜かれ2023年には世界第4位に
- 自然科学分野の論文数:2022年までの20年間で4位から10位に
など、企業収益から科学技術力までさまざまな分野での凋落ぶりが際立っています。
人的資本の劣化
失われた30年の間に、日本企業は人材投資を減らして非正規雇用を増やしてきました。
その結果がもたらしたのは人的資本の劣化です。
世界競争力指数を見ても、日本の国際競争力の中では「ビジネス効率性」が著しく低く、その要因は現場の労働者の生産性の低さにあることが指摘されています。
その背景には
- 労働者、特に若年層の仕事への満足度が低下、専門性習得への意欲も低い
- 専門性を発揮でき評価される管理職以外のキャリア整備が弱い
- マネジメント業務の過度な負担で中間管理職が付加価値の高い業務ができない
- 男性中心の企業文化が固定化され女性のキャリアを活用できていない
などの要因があり、下落傾向にある日本のビジネス効率性は、直近の数年でさらに落ち込みが強くなっています。
低所得層の増加と経済格差の拡大

私たちの生活に直結する大きな影響は、低所得者層の増加と格差の拡大です。
かつては女性がほとんどだった非正規雇用は、その範囲が徐々に広げられた結果、現在では若者や現役世代の一部の男性、高齢者にまで及び、労働人口の4割を占めるまでになっています。
とりわけこの30年は、人口ボリュームが多い団塊ジュニア世代が社会に出るタイミングと重なってしまいました。社会の担い手の中心となるべきこの層が多数非正規化した結果、
- 経験もスキルも低いままキャリアを積む機会を奪われた
- 正規と非正規の賃金や待遇の格差が拡大し、貧困世帯が増加
- 増加した低所得者層は経済的な不安から結婚や家族形成ができず、少子化を助長
- 低所得で年金・医療など社会保険料を収められない層が増え、社会保障制度の持続可能性を揺るがす
といった結果を招き、いわゆる就職氷河期世代として苦しむ人々を多く生み出した社会問題へ発展していくことになります。
今後の日本の見通し

では、今後の見通しはどうなっていくのでしょう。
2025年現在、日経平均株価は4万5,000円を越え、地価もバブル期を上回る上げ幅を記録するなど、さまざまな経済指標が約30年ぶりの値を更新しています。同時に長く続いたデフレも収束し、インフレ傾向へと推移し始めています。
では、失われた30年は終わったのでしょうか?
いまだ見えぬ「失われた〇〇年」の出口
結論から言えば、まだ決して終わったとは言えません。確かにいくつかの指標では高い数字を出していますが、私たちの実質賃金は相変わらず伸び悩み、物価上昇には追い付かない厳しい生活状況が続いています。
また、1人当たりGDPも期待ほど伸びず、生産性もいまだ低いままです。
政府もこの現状には危機感を抱いており、これまでの考え方ややり方のままでは、
- 社会は当面安定するが、実質賃金やGDPの成長は横ばい
- 新興国に追いつかれて海外と比べ豊かではない状況に
- 中長期的に社会の安定性すら失われる可能性
という状況に陥ると想定しています。最悪の場合、2030年代には日本は恒常的なマイナス成長と経常赤字が続き、先進国ではなくなる日が来るかもしれないという懸念の声も上がっています。
失われた30年の解決策
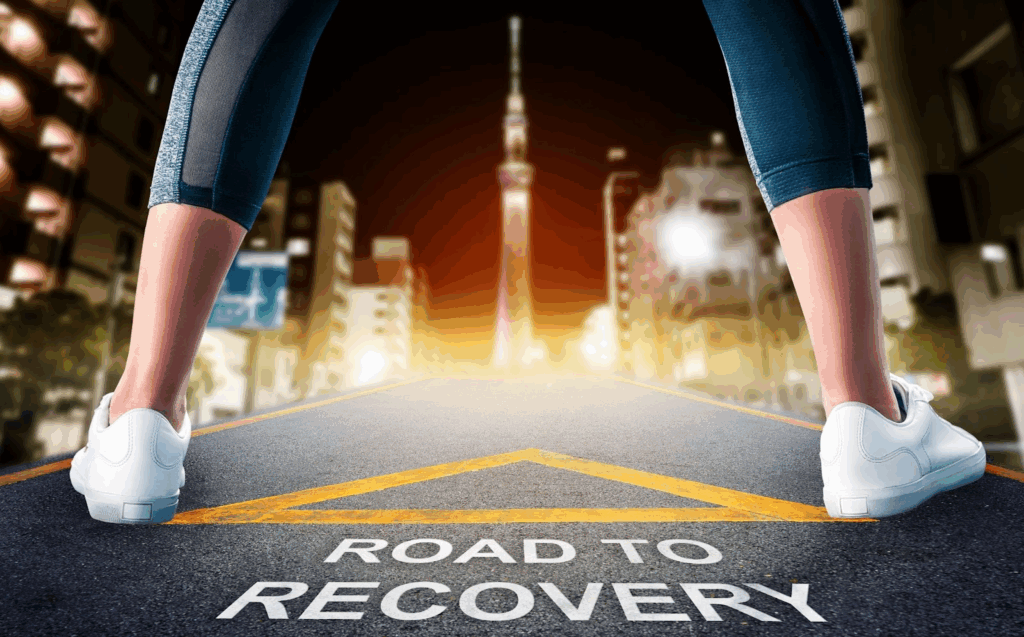
では、「失われた30年」が名実ともに終わりを迎え、私たちが本当の意味で景気回復を実感するためには、どのような解決策が必要になるのでしょうか。
方策①賃金の大幅引き上げ
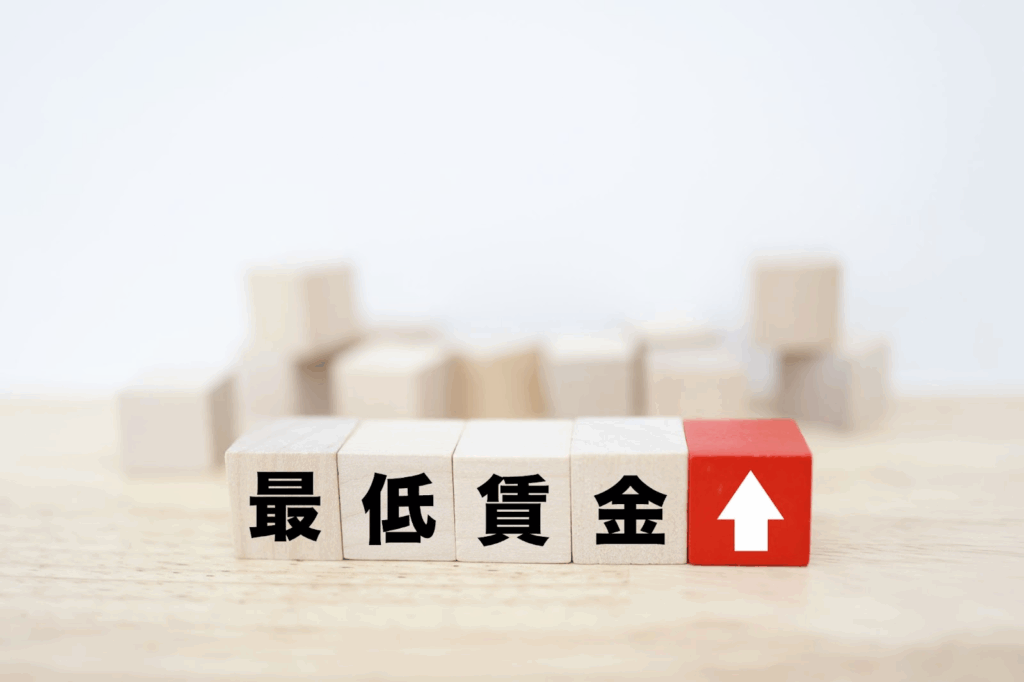
国民の生活を改善させ、消費を上向かせるのに必要なのは賃金の大幅な引き上げです。
欧米主要国の賃金はこの20年で50〜80%も上昇している反面、日本だけはトータルで10%も低下し、経済成長の足枷になっています。
2015年から現在まで賃金は上昇に向かっていますが、その上昇率は3%弱と低く、現在の物価上昇には全く追いついていないのが現状です。
政府は2030年代までに最低賃金1,500円を目標にしていますが、それではあまりにも遅いと言わざるを得ないでしょう。
方策②社会保障制度の改善
国民が上向いた所得を貯蓄に回さずに、安心して消費活動を行うためには、
- 不足ない額の年金を確実に受けられる
- 必要とする全ての人に生活保護費を支給できる
- 誰でも医療費の心配をせずに治療を受けられる
- 介護や医療で働く人の処遇を良くする
といった、将来の不安を解消するような社会保障制度の改善が必要です。
しかし日本の政府は、国の厳しい財政状況を理由に、上記とは真逆の社会保障制度改革(改悪)を行ってきました。
これを覆し、財政健全化と社会保障制度の拡充を両立させる方策のひとつとして、国民負担率引き上げが提案されています。仮に日本の国民負担率をフランスの67%並みに引き上げれば、100兆円の政府収入が得られるため、社会保障制度を改善できることが見込まれます。
方策③累進税率の引き上げ

ただし、国民負担率を上げるにしても、逆進性が高く低所得者層への負担が重い消費税増税は得策とは言えません。
賃金引き上げと社会保障改善という上記の2つの方策を実現させるには、法人税率や富裕層、実業家、会社役員などの所得への累進税率の引き上げを行い、負担能力のある者から所得に応じて負担を求める必要があります。
現在、多くの先進国では所得税の上限はだいたい40%前後まで下げられていますが、かつては70%〜90%もの負担が求められていました。税率を当時に近いくらいまで戻し、負担能力の高い者に負担してもらうことで、
- 国債の発行による累積債務で財政が破綻するのを防ぐ
- 収益を内部留保でため込まず、企業に設備投資や人材投資に回すインセンティブができる
などのメリットが期待されます。
方策④非正規雇用の縮小と労働条件の抜本的な改善
根本的に改善が求められているのは、非正規雇用制度の見直しと労働条件です。
具体的には、
- 非正規雇用適用の厳格化
- 「派遣法」改正と非正規雇用抑制策(業種制限26業種に戻す)
- 同一労働同一賃金の徹底
- 正規雇用促進(オンブズマン制度や正規雇用比率増加へのインセンティブ)
など、非正規雇用自体を減らし正規雇用に戻すこと、非正規のままでも賃金や待遇面で差をつけないなど、これまでの政策を180度転換させるような制度の改正が不可欠となるでしょう。
失われた30年とSDGs

失われた30年は、日本の経済成長率や生産性のある雇用を損ない、不公平で不平等な社会システムを温存し続けました。
その結果産業や技術革新の発展機会も失うなど、日本はSDGs(持続可能な開発目標)における
- 目標8「働きがいも経済成長も」
- 目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」
- 目標10「人や国の不平等をなくそう」
の各目標からはほど遠い、極めて持続可能性の低い経済政策を採り続けてきました。
今後日本が高い生産性や国際競争力を取り戻し、持続可能な開発目標を達成するためには、労働環境や賃金体系の改善、設備や人材への正しい投資などが十分になされることにかかっていると言えるでしょう。
まとめ

現在の日本の厳しい社会状況を生んだ失われた30年。それは、バブルに踊らされた挙句に正しい判断力を失い、時代の流れを見誤って後始末に失敗し続け、落ちぶれていった国の姿です。
今でこそ株価や地価は大幅に回復し、景気の上昇が期待されています。しかし、足元の私たちの暮らしは一向に回復の実感がなく、生活苦や格差の拡大は改善される兆しすらありません。政府や財界が上辺だけの景気回復に浮かれ、国民の生活を立て直す施策に本気で取り組まない限り、失われた30年が今後、40年、50年と続く可能性も決してあり得ないことではないのです。
参考文献・資料
日本の経済政策 : 「失われた30年」をいかに克服するか / 小林慶一郎著.中央公論新社, 2024.
日本経済30年史 バブルからアベノミクスまで 山家悠紀夫/著. 岩波書店, 2019年
公定歩合 読み – 証券用語解説集|野村証券
平成―バブル崩壊の後始末とデフレ対策に追われた金融界 | nippon.com
日本人は「失われた30年」の本質をわかってない 原因と責任を突き止め変えねば低迷はまだ続く | 国内経済 | 東洋経済オンライン
日本を「失われた三十年」に陥れた、財政支出を抑制した政府 | Web Voice|新しい日本を創るオピニオンサイト
大田, 英明, 2022, 日本の非正規雇用拡大に伴う経済低迷 : 「失われた30年」の背景: 立命館大学国際関係学会 , 107–135 p.
篠﨑, 彰彦 デジタル化と2040年の経済社会 : 技術環境と国際関 係の変化をてがかりに ;SBI金融経済研究所 所報 vol.7 pp.9-23, 2025-02-28.
人的資本の再建 第1回:失われた30年、人材の課題と対応の方向性日本企業の革新に向けて | 日本企業の革新に向けて | MRI 三菱総合研究所
縮減する日本社会の課題 原 俊彦 季刊個人金融 20 (1Spring), 2-, 2025
「科学技術力の低下」になぜ危機感が覚えないのか 日本の地位は20年あまりで4位から10位に陥落 | 先端科学・研究開発 | 東洋経済オンライン
日本はなぜデジタル化が遅れ、生産性が伸びなかったのか|機関誌Works 特集 リクルートワークス研究所
第3次中間整理で提示する 2040年頃に向けたシナリオについて 2024年3月 経済産業政策局
この記事を書いた人
shishido ライター
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。







