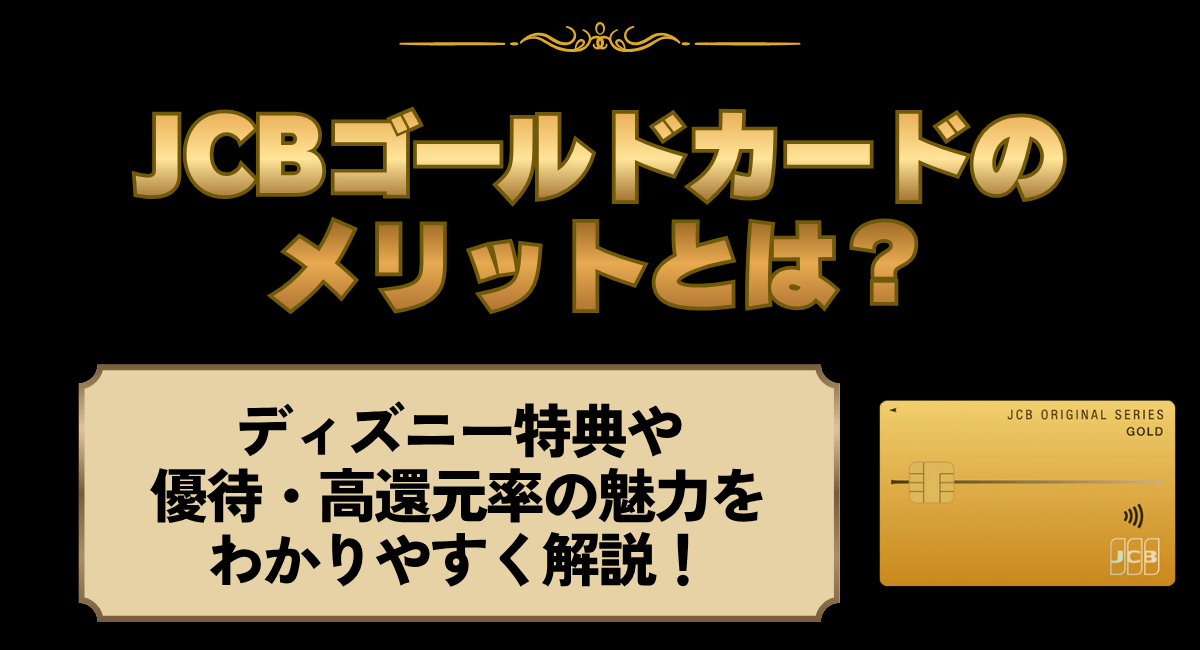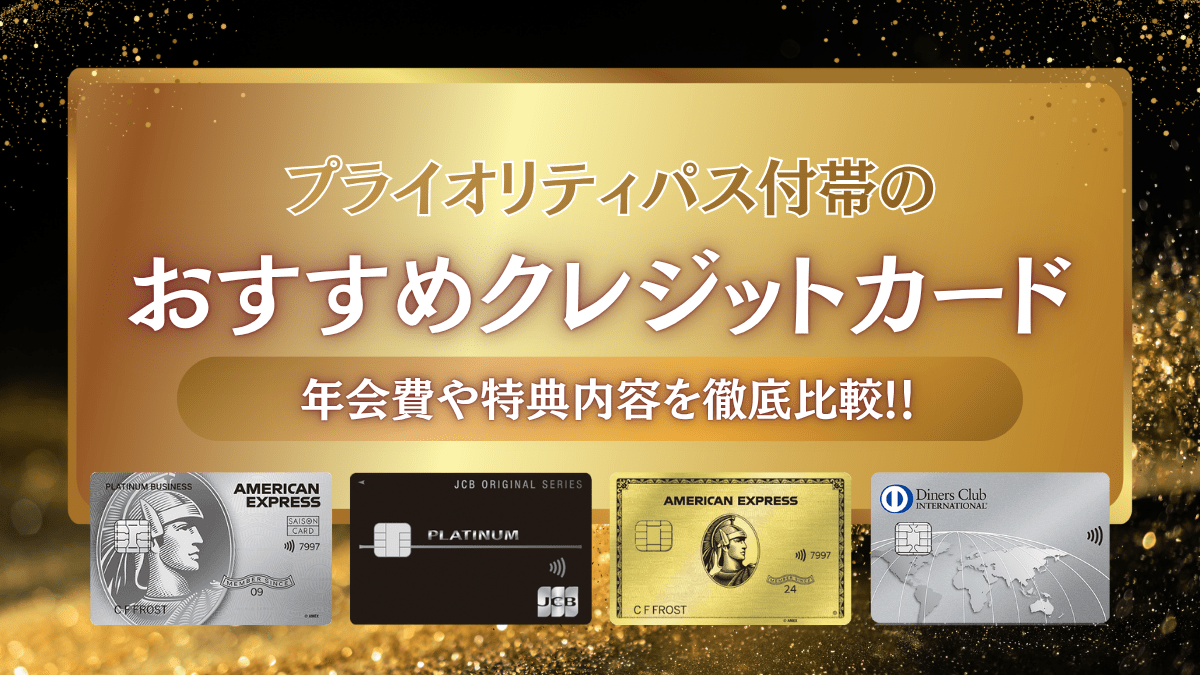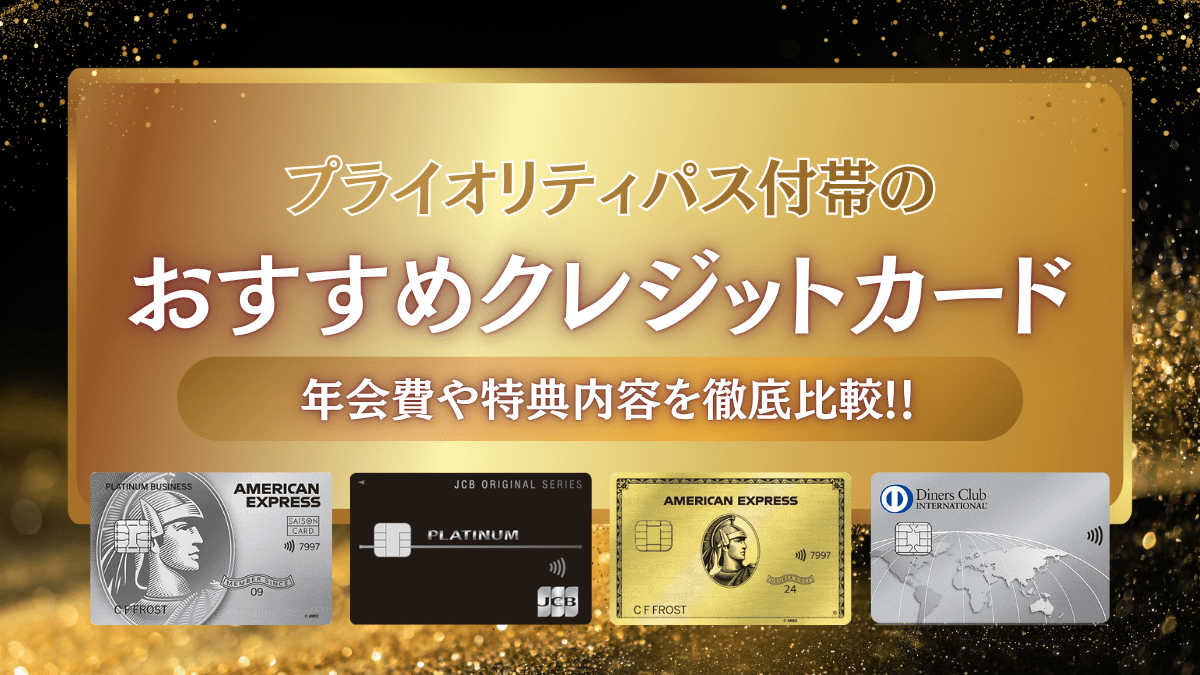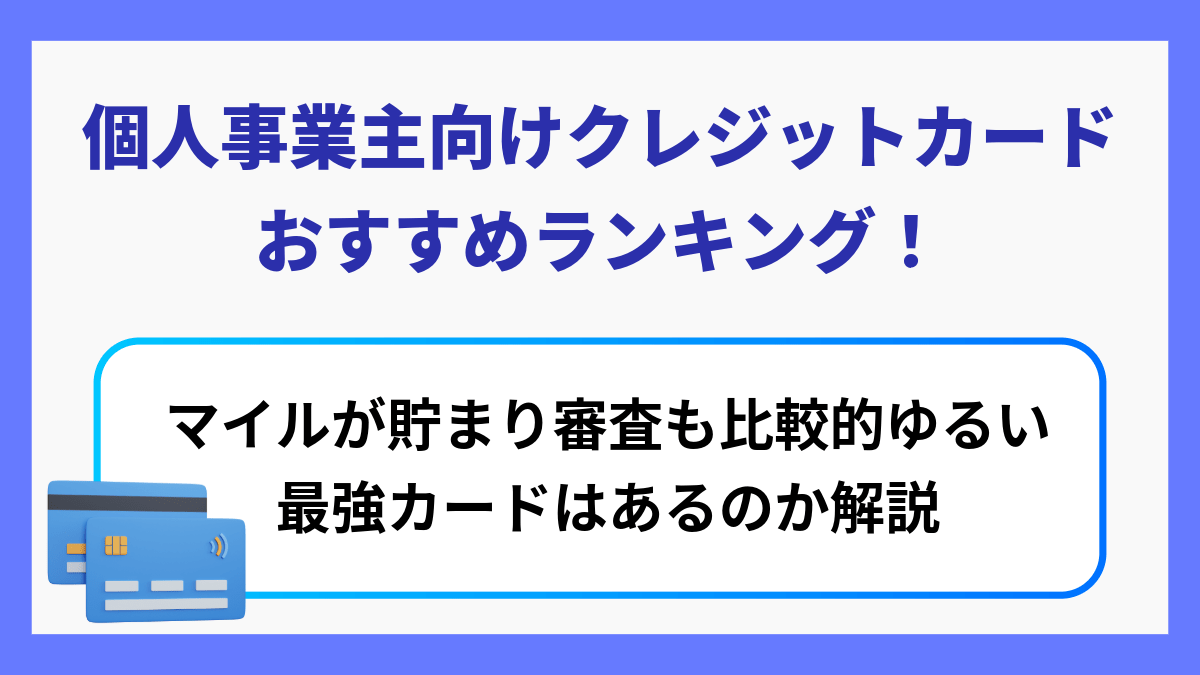環境基本法は、日本の環境保全に関する基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者、国民それぞれの責務を明らかにした、環境政策の根幹となる法律です。この法律の基本理念と具体的な施策を知ることは、環境問題への取り組みを単なる理想論から実践的な行動へと変える重要な第一歩となります。
持続可能な未来の実現に向けて、一人ひとりが環境保全に参加するための法的基盤として、環境基本法について確認しておきましょう。
目次
環境基本法とは

環境基本法は、日本における環境政策の最上位に位置づけられる基本的な法律です。この法律は、「環境の保全と持続可能な社会の実現」を国・企業・国民の共通責務として定めています。
- 公害対策
- 地球温暖化
- 生物多様性
など、地球規模の課題にも対応する包括的な枠組みを示しており、私たちの生活と未来の世代のために、社会全体で環境を守る理念を明確に打ち出した法律といえるでしょう。この法律を理解するための基礎的なことを確認しておきましょう。
環境基本法の目的
この法律が何を目指しているのか、その根本的な目的は第一条に記されています。それは、現在そして未来の国民が、健康で文化的な生活を送れるようにすること、さらには人類全体の福祉に貢献することです。この目的は、単に目の前の公害をなくすことだけを指しているのではありません。豊かな自然環境という恵みを将来の世代も変わらずに享受できるよう、社会全体で環境保全に取り組んでいくという、長期的かつ広い視野に立った理念が込められているのです。
法律の構造と重要な定義
環境基本法は、全3章46条から成り立っています。法律を正しく理解するためには、まず法律の中で使われている言葉の定義を知ることが大切です。特に重要となる3つの用語が第二条で定められています。
- 環境への負荷:人の活動によって環境に加えられる影響のうち、環境保全上の支障の原因となるおそれがあるもの。
- 地球環境保全:地球温暖化、オゾン層の破壊、海洋汚染、生物多様性の減少など、国境を越えて広範囲に影響を及ぼす問題に対する環境保全活動。
- 公害:事業活動など人の活動によって生じる、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭(典型七公害)により、人の健康や生活環境に被害が生じること。
これらの言葉が明確に定義されることで、法律が対象とする問題の範囲が具体的に示されています。
制定された歴史的背景
環境基本法が1993年に制定された背景には、国内外の環境問題に対する意識の高まりがあります。それ以前は、1967年に制定された公害対策基本法が日本の公害対策の中心でした。
しかし、この法律は主に工場などから排出される産業公害を対象としており、都市・生活型の公害や、地球温暖化といった地球規模の環境問題には十分に対応できないという課題がありました。1992年にブラジルのリオデジャネイロで開催された「地球サミット(国連環境開発会議)」は、国際社会が持続可能な開発に向けて協力する大きな転換点となり、日本国内でもより包括的な環境法制の必要性が叫ばれるようになりました。
このような流れを受け、従来の公害対策基本法を発展的に解消し、自然環境保全の考え方も取り入れた新たな基本法として、環境基本法が制定されたのです。
責務を負う4つの主体
環境保全は、特定の人々だけが取り組むものではなく、「社会を構成するすべての者がそれぞれの立場で役割を果たすべきである」と、この法律は示しています。具体的には、以下の4つの主体それぞれに、果たすべき責務があることが明記されています。
- 国:環境保全に関する、基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する責務を有します。
- 地方公共団体:国の施策に準じつつ、それぞれの地域の自然的・社会的条件に応じた独自の施策を策定し、実施する責務を負います。
- 事業者:事業活動に伴う公害を防止し、自然環境を適正に保全する責務があります。また、製品が廃棄物となった場合の適正処理への配慮や、再生資源の利用に努めることも求められます。
- 国民:日常生活に伴う環境への負荷を減らすよう努めるとともに、国や地方公共団体が実施する環境保全施策に協力する責務を有します。
このように、環境基本法は、国から国民一人ひとりに至るまで、それぞれの役割と責任を具体的に定めることで、持続可能な社会を実現していくための法的基盤を築いています。*1)
環境基本法の基本理念と4つの柱

環境基本法は、日本の環境政策の最上位に立つ法律です。その根幹を成す「基本理念」は、国や事業者から私たち国民一人ひとりに至るまで、すべての主体が環境問題に取り組む際の、いわば不動の指針として機能します。
ここでは、法律の第3条から第5条に定められた3つの基本理念と、その理念を具体的な行動へと導く「4つの柱」について見ていきましょう。
環境の恵沢の享受と継承(第3条)
この理念は、清浄な空気や安全な水といった「環境の恵沢」※が、私たちの健康で文化的な生活に不可欠であるという大前提を示しています。
その上で、この恵沢を現代に生きる私たちだけのものとせず、「将来の世代へ継承していく責任」があることを明確にしました。これは、世代間の公平性を重視する画期的な視点であり、後のSDGs(持続可能な開発目標)にも通じる考え方です。
環境負荷の少ない持続可能な社会の構築(第4条)
第4条は、環境と社会経済活動のあるべき関係性を示した、特に重要な理念です。これは、主に4つの要素から成り立っています。
- 環境負荷の低減:大量生産・大量消費型の社会から転換すること。
- すべての主体の参加:国民、事業者、行政が、それぞれの立場で自主的に協力し、役割を担うこと。
- 持続可能な発展:環境保護と経済発展を対立するものと捉えず、両立させること。
- 未然防止(予防原則):科学的知見に基づき、問題が発生する前に予防的に対策を講じること。
これらの考え方が一体となることで、持続可能な社会の実現を目指しています。
国際的協調による地球環境保全(第5条)
地球温暖化などの環境問題は、一国だけの努力では解決できない「人類共通の課題」であるとの認識を示しています。この理念に基づき、日本が持つ技術力や経験を活かして、国際社会における地位と責任に応じた貢献をしていく姿勢を明確にしました。
これは、地球規模の課題解決に向けた、先進国としての決意表明でもあります。
基本理念を具体化する「4つの柱」
法律で示されたこれらの理念を、実際の政策として推進するために、国の「環境基本計画」では、以下の「4つの柱」が長期目標として掲げられました。
- 循環:資源を大切に使い、ごみを減らす「循環型社会」を築く。
- 共生:生物多様性を守り、人と自然が豊かに共存する社会を目指す。
- 参加:社会のあらゆる人々や組織が、主体的に環境保全活動に参加する。
- 国際的取組:地球全体の環境を守るため、国際的な協力を進める。
これらの柱は、理念という設計図を、社会を動かすための具体的な行動計画に落とし込んだものです。
環境基本法が定める3つの基本理念と、それを具現化する4つの柱は、単なるスローガンではありません。これらは、社会がどうあるべきかという哲学を示し、現在に至るまで日本のあらゆる環境政策の根幹を成す、揺るぎない指針となっているのです。*2)
なぜ環境基本法が制定されたのか

1993年の環境基本法制定は、単なる法律の改正ではありませんでした。それは、日本の環境政策が、深刻な公害問題への対処という段階から、地球全体の未来を見据える新たなステージへと移行した、歴史的な転換点だったのです。
この大きな変革はなぜ必要だったのでしょうか。
従来の法律の限界と、変化する環境問題
日本の環境政策の原点は、1967年に制定された「公害対策基本法」にあります。この法律は、四大公害病※に代表される、工場などから排出される深刻な産業公害を克服する上で、絶大な成果を上げました。
しかし、時代が進むにつれ、環境問題はその姿を変えていきます。自動車の排気ガスや家庭からの生活排水が引き起こす「都市・生活型公害」が深刻化し、特定の発生源を規制するだけでは解決が難しくなりました。
さらに、地球温暖化やオゾン層の破壊といった、国境を越える地球規模の課題が明らかになり、一国の努力だけでは対応できない、新たな局面を迎えていたのです。
世界を動かした「地球サミット」という転換点
国内で新たな枠組みが模索される中、世界を大きく動かす出来事が起こります。1992年にブラジルで開催された「国連環境開発会議(通称:地球サミット)」です。
この会議は、環境保全と開発を両立させる「持続可能な開発」という新しい理念を、世界の共通目標として確立しました。特に、「将来の世代の必要性を損なうことなく、現代の世代の必要性を満たす」という考え方は、環境基本法の根幹を成す理念に直接的な影響を与えています。
国際社会の一員として、日本もこの新しい理念に沿った国内制度を整備する責任を負うことになりました。地球サミットで示した国際公約を果たすためにも、従来の公害対策の枠を超え、持続可能な発展を基本理念に据えた、新しい法律の制定が必要となったのです。
このように環境基本法は、国内の環境問題の質の変化と、地球環境保全という国際社会からの大きな要請という、二つの歴史的な潮流が交わったことで誕生しました。それは、従来の「事後対応型」の公害対策から、社会のすべての主体が参加して「持続可能な社会の実現」を目指すという、日本の環境政策の新たな出発を告げる、画期的な法的基盤となったのです。*3)
環境基本法の具体的な施策

環境基本法が掲げる大きな理念は、それを現実社会で動かすための具体的な仕組みがあってこそ意味を持ちます。この法律は、理念を政策として実行するための、多岐にわたる制度や手法を体系的に定めています。
これらは、現在の日本の環境政策の基盤そのものとなっています。
ここでは、その中でも特に重要となる4つの柱、「計画」「基準」「評価」「国際協力」について、具体的な内容を見ていきましょう。
国の羅針盤となる「環境基本計画」(第15条)
環境基本計画は、日本の環境政策全体の方向性を定める、政府の最重要マスタープランです 。法律に基づき、政府はこの計画を策定することが義務付けられています 。専門家で構成される中央環境審議会の意見を聞き、最終的に内閣の決定(閣議決定)を経て定められる、非常に重要な計画です 。
1994年に策定された第1次計画では「循環」「共生」「参加」「国際的取組」という4つの長期目標が掲げられました。その後、社会情勢の変化に応じて見直され、2018年の第5次計画ではSDGsの考え方が全面的に取り入れられるなど、常に進化を続けています。
この計画があることで、国や自治体、事業者が一体となって、計画的に環境保全を進めることが可能になります。
健康を守る目標値「環境基準」(第16条)
環境基準は、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で「維持されることが望ましい」として国が定める、科学的根拠に基づく具体的な目標値です。
例えば、大気汚染物質である微小粒子状物質(PM2.5)や、河川の汚れの指標となる化学物質の濃度などについて、具体的な数値が設定されています。ここで重要なのは、この基準が事業者に直接課される罰則付きの「規制値」ではなく、国や地方公共団体が達成を目指すべき「行政上の目標」であるという点です。
国や自治体は、この環境基準を達成するために、工場への規制や下水道の整備といった様々な施策を講じる責任を負っています。
未来への配慮を形にする「環境影響評価」(第20条)
環境影響評価(環境アセスメント)は、発電所や道路といった大規模な開発事業を行う際に、事業者が事前にその事業が環境に与える影響を調査・予測・評価し、適切な配慮を行うことを法的に求める制度です。この制度の導入により、日本の環境政策は、問題が起きてから対処する「事後対応」から、問題が起きる前に防ぐ「予防的取組」へと大きく転換しました 。
計画段階で住民や専門家の意見を取り入れる仕組みも設けられており、開発と環境保全の両立を図る「予防原則」を具体化した重要な制度といえます。
地球全体の未来に貢献する「国際協力」(第32条~)
環境基本法は、地球温暖化などの国境を越える問題に対し、日本が国際社会の一員として積極的に貢献することを国の責務として定めています。具体的には、
- 日本の持つ優れた環境技術や経験を活かした開発途上国への支援
- 地球環境の監視・観測における国際的な連携
- NGOや民間企業による国際協力活動の促進
などが定められています。これにより、日本は気候変動対策や生物多様性の保全といった分野で、世界の取り組みをリードする役割を果たしています。
このように、環境基本法が定める具体的な施策は、「計画」で大きな方向を示し、「基準」で具体的な目標を定め、「評価」で未来への影響を配慮し、「国際協力」で地球全体に貢献するという、それぞれが相互に補完し合うことで、理念から実行までを一貫した体系として機能させているのです。*4)
環境基本法とSDGs
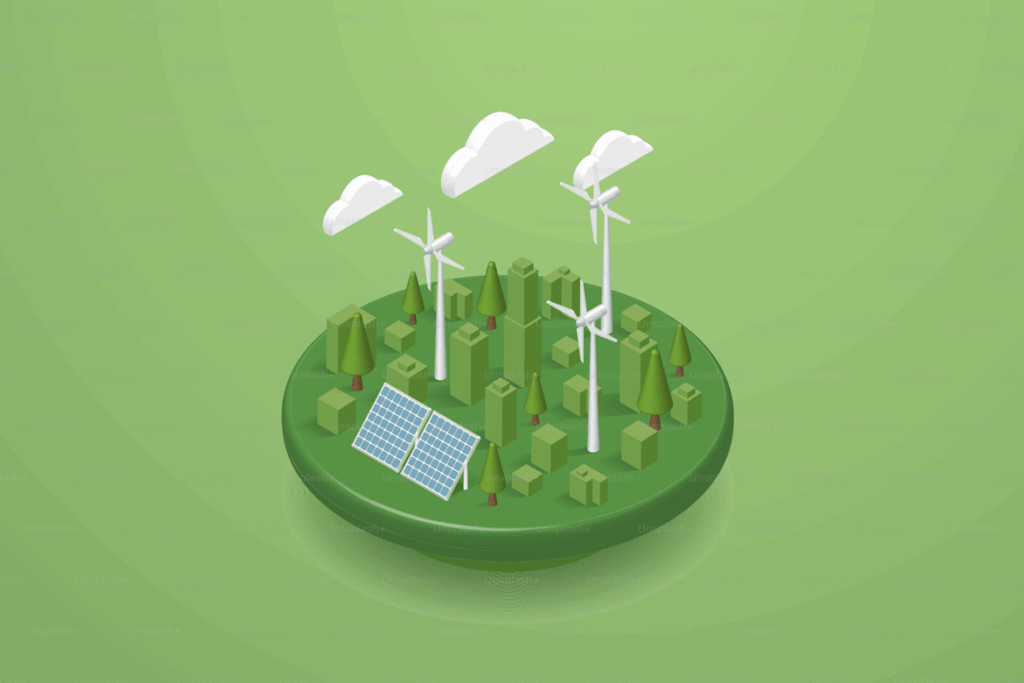
環境基本法が目指す「持続可能な社会」は、環境・経済・社会の統合的な向上を掲げるSDGs(持続可能な開発目標)の理念と、その根底で深く結びついています。この法律は、SDGsという世界共通の目標を日本国内で達成していくための、法的・政策的な土台そのものとして機能しています。
SDGs目標6:安全な水とトイレを世界中に
環境基本法は、水環境の保全を通じてこの目標達成に直接貢献しています。法律に基づいて国が定める環境基準では、河川や湖、地下水などの水質について、人の健康を守り、生活環境を保全するための具体的な基準値が設定されています。
この科学的根拠に基づく水質管理によって、安全な水の安定的な確保が支えられており、私たちの暮らしの根幹を守っています。
SDGs目標11:住み続けられるまちづくりを
SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」の実現において、環境基本法は包括的な政策の枠組みを提供します。大気の清浄さや騒音の静けさに関する環境基準は、人々が健康で文化的な生活を送るための都市環境の質を保証します。
また、特に公害が深刻な地域で策定される「公害防止計画」は、地域の環境を集中的に改善し、誰もが安心して住み続けられるまちづくりを支える重要な仕組みです。
SDGs目標12:つくる責任 つかう責任
SDGs目標12は、環境基本法の核心理念である「環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築」と完全に一致します。国の「環境基本計画」では、長期目標の一つに「循環」が掲げられており、廃棄物の発生抑制やリサイクルを推進しています。
これにより、大量生産・大量消費からの脱却を促し、持続可能な生産と消費のパターンを社会に根付かせることを目指しています。*5)
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ

環境基本法は、日本の環境保全に関する基本理念や国・国民の責務を定め、現在と未来の国民の健康で文化的な生活を守るための政策の根幹となる法律です。これは、日本の環境政策の揺るぎない羅針盤であり、その核心は「現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保」という未来志向の理念にあります。
2024年5月に閣議決定された第6次環境基本計画では、「ウェルビーイング(質の高い暮らし)」を最上位の目標に据え、環境の許容量を守りながら経済社会が成長する「循環共生型社会」の構築が明確に示されました。これは、気候危機という待ったなしの現実に対し、法の理念をより具体的に社会へ実装しようとする強い意志の表れです。
また、環境基本法が制定当初から掲げてきた「予防的取組」や「国際協調」といった原則は、現代においてこそ、その先見性が際立ちます。将来世代への責任を明記したこの法律の精神は、国境を越えて協力し、地球規模の課題に立ち向かうための、私たちにとって最も重要な指針です。
しかし、法律や政策だけでは、この壮大なビジョンは完成しません。私たち一人ひとりが、自らの生活を振り返り、問いを持つことが重要です。
「自分の消費行動は、未来の環境にどのような影響を与えるのか」
「地球のために、今日から何ができるだろうか」
このような問いに真摯に向き合い、日々の選択を変えていくこと、その一人ひとりの意識と行動の積み重ねこそが、環境基本法が目指す社会を実現し、次世代により良い地球を託すための、最も確かな力となるのです。*6)
<参考・引用文献>
*1)環境基本法とは
e-GOV『環境基本法(平成五年法律第九十一号)』
環境省『環境基本法の概要』
*2)環境基本法の基本理念と4つの柱
環境省『環境基本法の制定(1993年)』(2021年4月)
環境省『循環型社会形成推進基本計画』
UNEP『Breadcrumb Home Explore Topics Environmental law and governance Environmental Rule of Law』
*3)なぜ環境基本法が制定されたのか
環境省『平成5年版 環境白書 2 地球サミットの成果』
環境省『平成6年版 環境白書 1 持続可能な開発−対立から統合へ』
資源エネルギー庁『第1節 2030年のエネルギーミックスの進捗と課題』(2018年)
*4)環境基本法の具体的な施策
環境省『環境基本計画とは』
東京都環境局『大気汚染環境基準』(2023年12月5日)
出典元環境省『2.環境影響評価法の概要』
環境省『大気汚染に係る環境基準』(2019年11月)
環境省『第4節 国際的取組に係る施策』
*5)環境基本法とSDGs
国際連合『Sustainable Development Goals(SDGs)』
外務省『持続可能な開発目標(SDGs)外務省仮訳』
国立環境研究所『環境基準等の設定に関する資料集』(2010年6月)
環境省『環境基本法とSDGs統合報告』
環境省『第2節 第五次環境基本計画が目指すもの』
*6)まとめ
環境省『第六次環境基本計画の概要』(2024年5月)
UNEP『Making Peace With Nature』(2021年2月)
OECD『環境保全成果レビュー 日本 ハイライト 2025年』(2025年3月)
経済産業省『成長志向型の資源自律経済戦略の今後のアクションについて』(2023年10月)
この記事を書いた人
松本 淳和 ライター
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。