
インド国会議事堂に入ると、まず目に飛び込んでくるのが、ガンジー、ネルー、チャンドラ・ボースの肖像画です。この3人の指導者が率いたインド独立への道のりは、現代世界の形成に大きく関わっています。
イギリスの200年以上にわたる支配からの解放を目指した独立運動は、非暴力を貫いたガンジーの「真理の力」、政治的手腕を発揮したネルー、そして武力解放も辞さなかったボースという異なるアプローチで進められました。
塩の行進や不服従運動など、さまざまな抵抗を経て、1947年についに自由を獲得しましたが、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒の対立により二つの国に分かれる結果となりました。
この歴史は日本とも深い関わりがあり、第二次大戦中には日本軍がインド国民軍を支援していました。さらに、ガンジーの非暴力思想は世界中の人権運動に影響を与え、現代のSDGsにも通じる平等への希求を象徴しています。知られざるこの壮大な物語を紐解いていきましょう。
目次
インド独立運動とは

インド独立運動とは、19世紀後半から1947年の独立まで、イギリスの植民地支配からの解放と民族自決を目指してインド各地で展開された一連の運動です。*1)
1857年のインド大反乱を機に、教養ある層が中心となり民族意識が芽生え始めました。当初の外国製品不買や自治要求は、第一次大戦後に約束が守られなかったことで本格的な独立志向へと変化しました。
この闘いの特徴は、ガンジーが提唱した「力に頼らない不服従」の考え方です。特に「塩の行進」などの平和的抵抗が国民の心をつかみました。最終的に第二次大戦後、宗教の違いにより二つの国家に分かれて独立を実現しています。
イギリスはインドを巧妙に分割統治した

イギリスのインド統治(イギリス領インド帝国)は、現地社会の多様性を巧みに利用した「分断支配(分割統治)」が特徴です。宗教の違いを強調し、ヒンドゥー教とイスラム教の対立を深めるため、別々に代表者を選ぶ制度を設けました。
また、インド全土を直接治める地域と550以上の地方王国(藩王国)に分け、それぞれの王と個別に約束を交わすことで連携を防ぎました。さらに身分制度や部族間の区別を強調し、社会内部の分断を促進しました。*2)
この政策によって、少数の英国人による広大な土地の長期支配が可能になりましたが、同時に独立後の混乱や対立の種をまくことにもなりました。現在のインドとパキスタンの緊張関係も、この分断統治の名残といえるでしょう。
インド独立運動の歴史
はじめに、インド独立運動の流れを年表形式で整理します。
| 年 | 出来事 |
| 1857年 | インド大反乱がおこる |
| 1858年 | イギリス領インド帝国の成立 |
| 1885年 | インド国民会議の設立 |
| 1905年 | ベンガル分割令 |
| 1919年 | ローラット法の制定アムリットサル事件 |
| 1920年 | 非暴力・不服従運動が始まる |
| 1930年 | 塩の行進 |
| 1942年 | ガンジーらがイギリスに即時独立を要求 |
| 1947年 | インド独立パキスタン独立 |
| 1948年 | ガンジーの暗殺 |
インド大反乱から90年を経て、インドはイギリスからの独立を達成したのです。
独立運動のきっかけとなったインド大反乱

1857年から1859年にかけて起きたインド大反乱は、独立への意識を芽生えさせた重要な出来事です。当初はイギリスの雇い兵(シパーヒー)たちの反抗から始まりましたが、次第に農民や地方の王族など様々な立場の人々が参加し、全国的な抵抗へと発展しました。
特に注目すべきは、宗教の壁を越えて人々が団結したことです。高い税金や伝統産業の衰退、地方王国の併合など、イギリス支配への不満が一気に噴出した結果でした。
この反乱は最終的に鎮圧されましたが、「外国の支配に抵抗する」という考え方がインド社会に根付くきっかけとなりました。*3)
インド人の反感を買ったイギリスの政策

イギリスの強権的な統治政策は、インドの人々の反発を強め、独立への願いを燃え上がらせました。1905年に実施されたベンガル分割令は、行政効率化を名目にしながら、実際には宗教対立を利用して民族運動を弱めようとした策略でした。これに対して国産品愛用運動など全国的な抗議が巻き起こりました。
第一次大戦後に制定されたローラット法は、裁判なしで市民を拘束できる厳しい法律で、自由を求める声をさらに高めました。*5)
特に1919年のアムリットサル事件では、平和的な集会に対してイギリス軍が発砲し、多くの命が失われました。この悲劇的な出来事は全土に衝撃を与え、支配への不信感を決定的にしました。*6)
これらの弾圧政策が、皮肉にもインド人の団結と独立への決意を強める結果となったのです。
非暴力・不服従運動

ガンジーが指導した非暴力・不服従は、不当な支配に対して暴力を使わずに抵抗する革新的な運動方法でした。南アフリカでのインド人差別体験から生まれたこの考え方は、「サティヤーグラハ(真理の力)」と呼ばれ、不正な法律には従わず、逮捕されても構わないという姿勢を貫くものです。*7)
ガンジーはインドに帰国後、この理念を全国的な反英運動に広げました。ローラット法への抗議活動、イギリス製品の不買運動、そして有名な「塩の行進」など、様々な場面で実践されました。塩の行進では、イギリスの塩税に抗議して自ら海水から塩を作り、法律に従わない意思を示しました。
インド独立
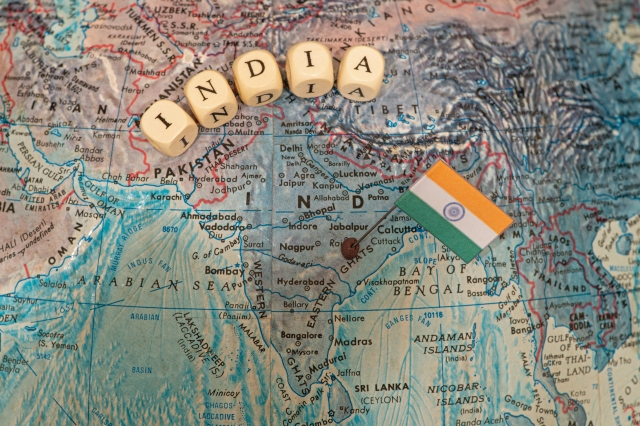
第一次世界大戦後のインド独立運動は、ガンジーの非暴力理念を軸に全国的な広がりを見せました。彼の指導のもと、塩の行進など様々な抵抗活動が展開され、若きネルーも運動の中心として台頭しました。
イギリスは時に厳しい弾圧を行い、時に譲歩しながら支配を維持しようとしましたが、第二次大戦を機に独立への流れは決定的となりました。しかし、独立の形態をめぐって深刻な対立が生じます。ガンジーとネルーは統一インドを望みましたが、ムスリム連盟のジンナーは宗教の違いを理由に別の国家を求めました。
この溝は埋まらず、1947年8月、インドは宗教に基づいて二つの国家に分かれて独立します。ヒンドゥー教徒中心のインド連邦とイスラム教徒中心のパキスタンの誕生は、喜びとともに大規模な混乱ももたらしました。こうして200年に及ぶイギリス支配に終止符が打たれたのです。*1)
インド独立運動の結果

インドが自由を手に入れた時、イギリスが支配していた地域がそのままひとつの国になったわけではありません。この広大な地域は、いくつかの国々に分かれて独立しました。具体的には、インド、パキスタン(後に東側の地域がバングラデシュとして独立)、そしてスリランカという別々の国家が誕生しました。
ここでは、特にインドとパキスタンがどのように分かれて独立国となり、その後すぐに起こった両国間の最初の戦争について説明していきます。
インドとパキスタンの分離独立

1947年、イギリス議会でインド独立法が成立し、それによってイギリスの植民地だった地域がヒンドゥー教中心の国とイスラム教中心の国に分かれることになりました。
この法律は1947年7月3日に承認され、8月14日にパキスタンが、翌日15日にはインドが正式に自由な国として歩み始めました。
インドとパキスタンの分離独立は宗教の違いによる対立が背景にあり、独立後すぐに多くの人々が住む場所を移動せざるを得なくなり、争いや社会の混乱が起こりました。
この法令の実施により、200年以上続いたイギリスの支配が終わり、南アジアに新しい二つの国家が誕生したことになります。
第一次印パ戦争

1947年、「インド独立法」に基づき、イギリスの支配下にあった南アジアの地域がヒンドゥー教中心のインドとイスラム教中心のパキスタンに分かれました。この時、両国の境界近くにあったカシミール地方では複雑な状況が生まれました。
この地域の支配者はヒンドゥー教徒でしたが、住民の多くはイスラム教を信仰していました。地元の人々の間で所属先について意見が分かれ、争いが起こり始めました。
この混乱から武力衝突へと発展し、後に「第一次印パ戦争」と呼ばれる対立の原因となりました。現在も続くこの地域の問題は、分離独立の際の取り決めに端を発しているのです。
インド独立運動の影響

インド独立運動は、世界に大きな影響を与えました。ここでは、非暴力・不服従運動の世界的な広がりについて解説します。
非暴力・不服従運動が世界に影響を与えた
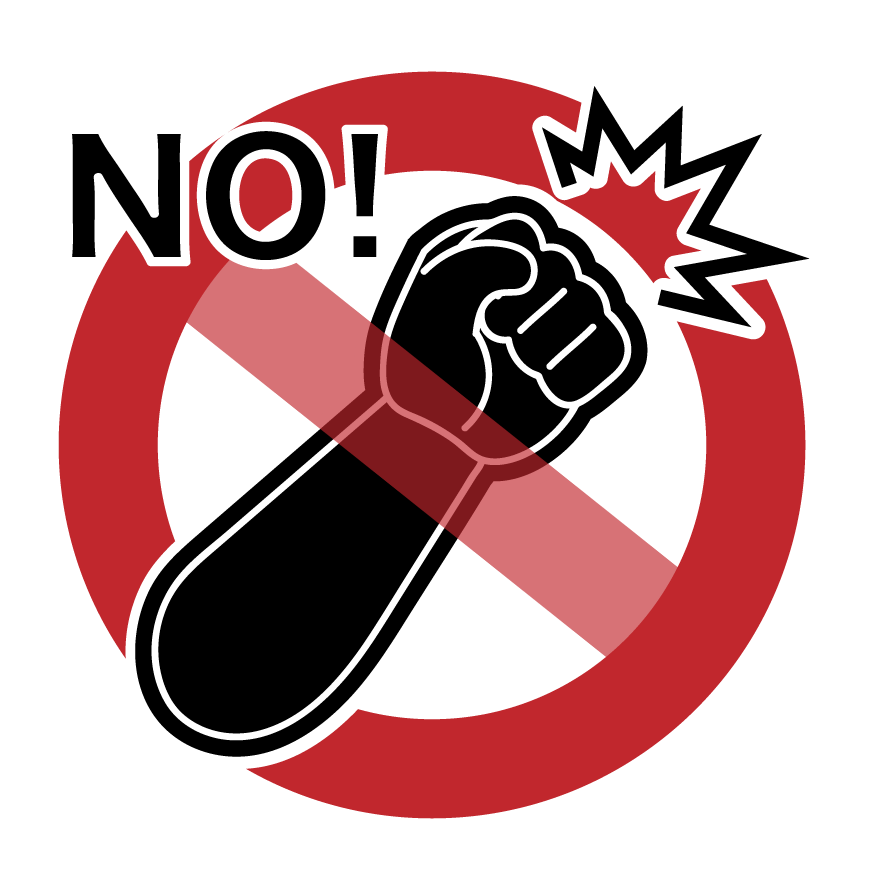
ガンジーが提唱した非暴力・不服従運動は、世界各地の社会正義や自由を求める活動に大きな影響を与えました。この理念は、力に頼らず対話と平和的手段によって変革を成し遂げる方法として、さまざまな国の民主化活動に受け継がれています。
国連はガンジーの生誕を記念し、2007年に10月2日を「国際非暴力デー」として制定しました。この記念日は、紛争解決や社会変革における平和的手段の重要性を世界中に広める機会となっています。ガンジーの思想は、現代社会においても対立を乗り越え、共存の道を模索するための貴重な指針となっているのです。
インド独立運動が日本に与えた影響
日本は、インドの独立運動に深く関与していました。ここでは、インド独立運動と日本の関わりについて解説します。
第二次世界大戦中に日本がインド独立運動を支援

第二次世界大戦のころ、日本はチャンドラ・ボースを中心とするインド独立運動を支援していました。
日本の支援は、イギリスの植民地支配を弱体化させる戦略的意図もありましたが、ボースの指導のもとインド人兵士や民衆の独立への意識を高める効果をもたらしました。戦後、ボースが作ったインド国民軍の幹部がイギリスの裁判で終身刑の判決を下されたものの、民衆が激高し、かえってインド独立の機運を高めました。*14)
インド独立運動とSDGs

インド独立運動は、単にインドがイギリスから独立したというだけにとどまりません。ここでは、インド独立運動とSDGs目標10との関わりについて解説します。
SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」との関わり
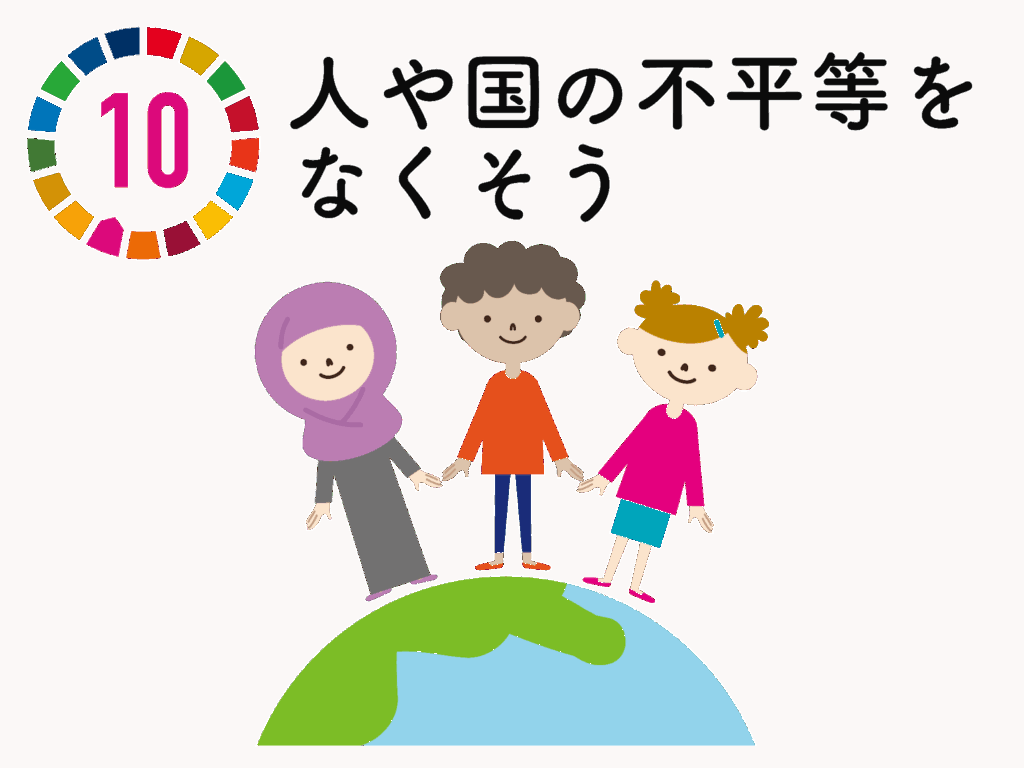
インド独立運動は、現代のSDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」の理念につながる歴史的な取り組みといえます。イギリス植民地支配下のインドでは、現地住民は政治参加の制限や経済的搾取など様々な差別に直面していました。この状況に対し、ガンジーをはじめとする指導者たちは自由と公正を求める運動を展開しました。
彼らの闘いは単なる統治権の移行だけでなく、すべての民族や宗教集団が平等に尊重される社会の実現を目指すものでした。この精神は今日、国連が提唱する「誰一人取り残さない」という理念と深く共鳴しています。
植民地からの解放を勝ち取った歴史的経験は、現代における格差是正や社会的公正の追求に重要な示唆を与えているのです。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
今回は、インド独立運動について解説しました。19世紀後半から1947年までの間、イギリスの植民地支配からの解放を目指した歴史的な闘いです。ガンジーの「真理の力」に基づく平和的抵抗を中心に、ネルーの政治手腕やボースの別アプローチも加わり多様な戦略で進められました。
「塩の行進」などの不服従活動が全国民の心をつかみ、第二次大戦後、民族自決への機運が高まりました。しかし宗教対立により、ヒンドゥー教中心の国とイスラム教中心の国に分かれて自由を獲得することになりました。
この歴史は、現代のSDGsにおける平等の理念にも通じる重要な事例であり、世界各地の民主化運動にも大きな影響を与えています。
参考
*1)ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「インド独立運動」
*2)改定新版 世界大百科事典「インド帝国」
*3)ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「インド大反乱」
*4)デジタル大辞泉「ベンガル分割令」
*5)改定新版 世界大百科事典「ローラット法」
*6)旺文社世界史事典 三訂版「アムリットサル事件」
*7)山川 世界史小辞典 改定新版「非暴力・不服従」
*8)デジタル大辞泉「ガンジー」
*9)デジタル大辞泉「ネルー」
*10)日本大百科全書ニッポニカ「インド独立法」
*11)ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「第1次印パ戦争」
*12)国際連合広報センター「国際非暴力デー」
*13)旺文社世界史事典 三訂版「チャンドラ・ボース」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。







