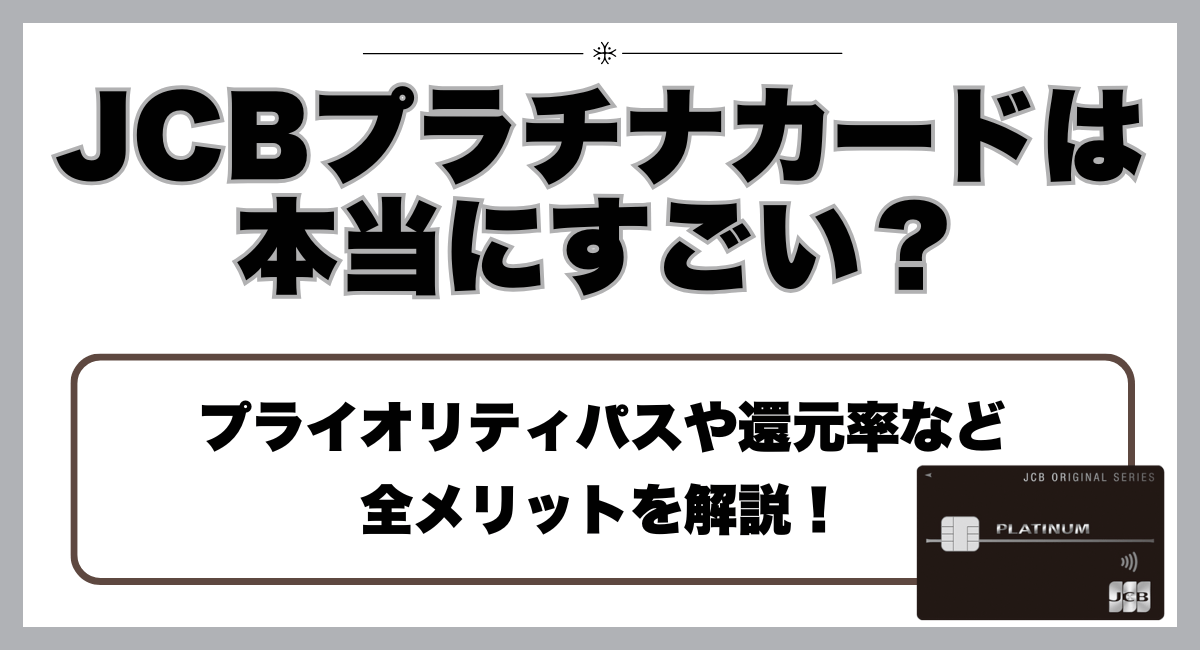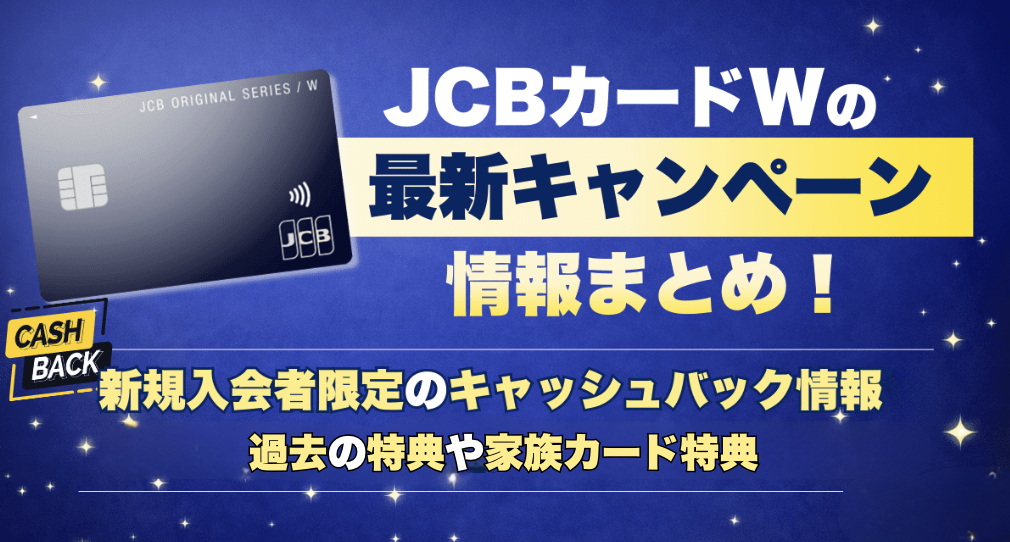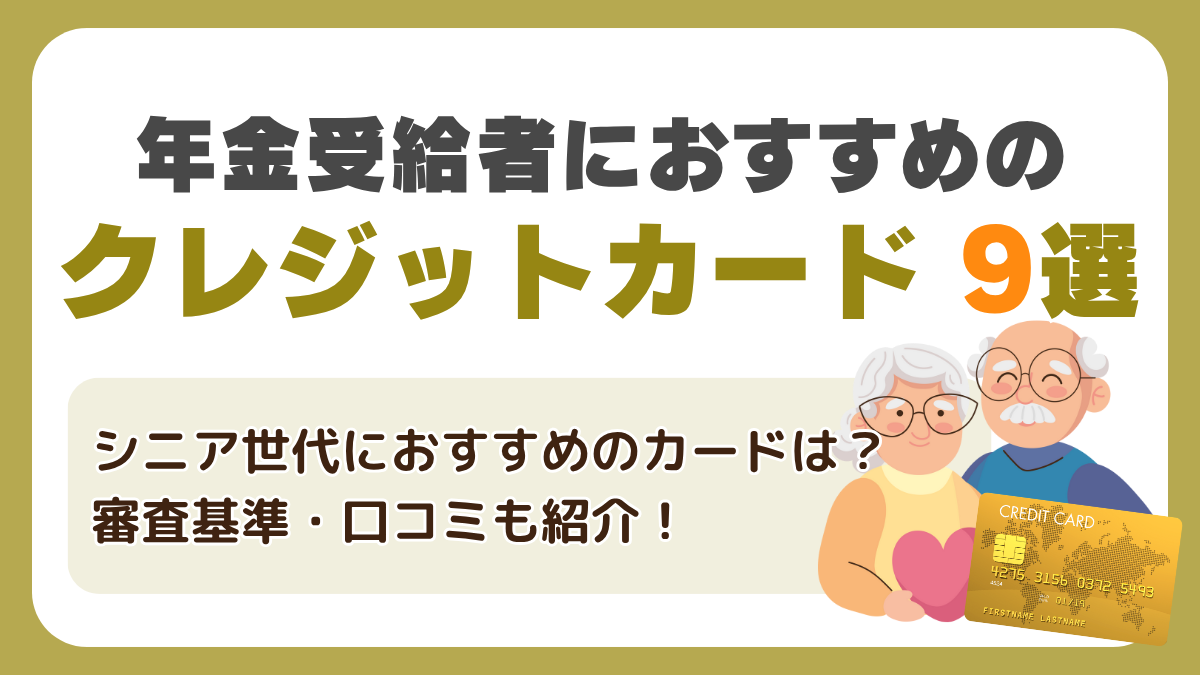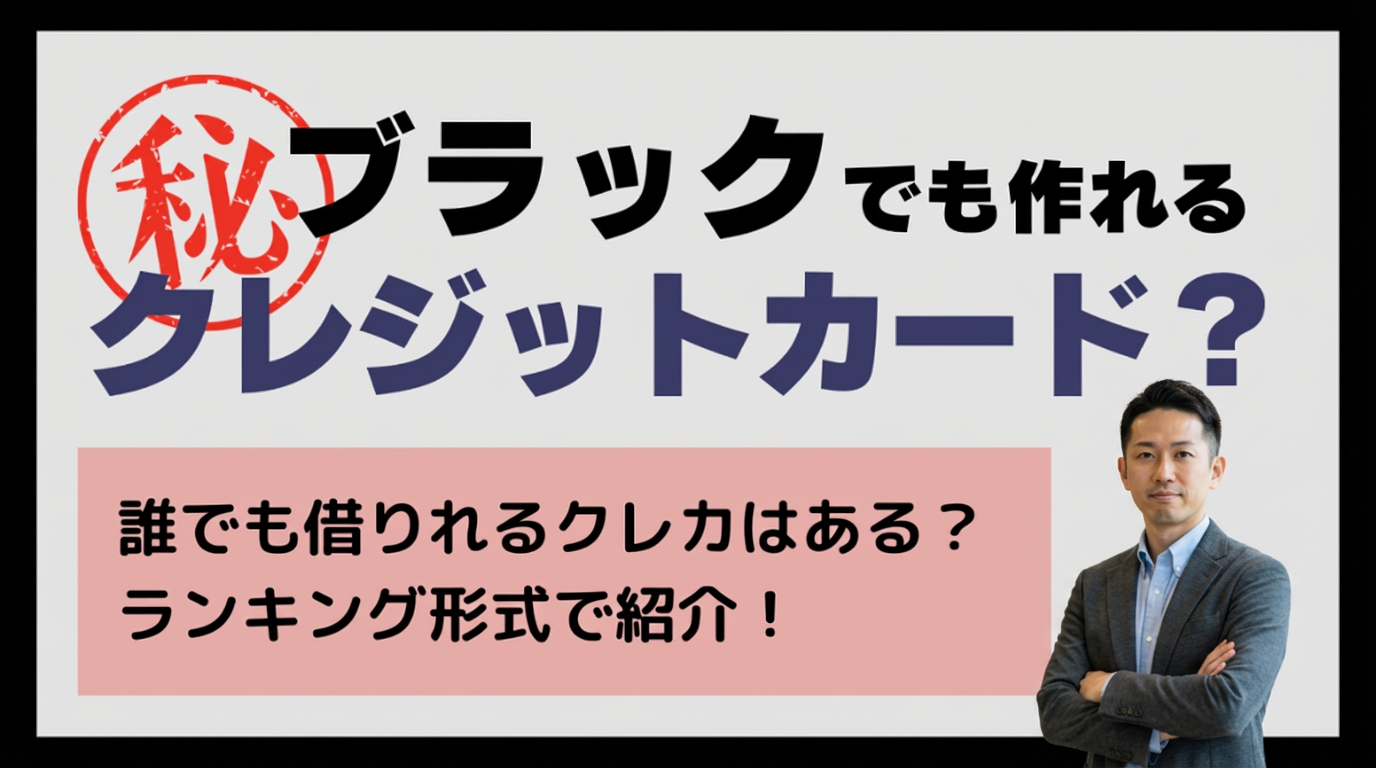かつて日本は、天皇を元首とする立憲君主制国家「大日本帝国」として、アジアで唯一の列強国として名を馳せていました。1889年に大日本帝国憲法が制定されてから1947年の日本国憲法施行まで、約60年にわたって存続したこの国家体制は、近代日本の歩みそのものでした。
軍事大国として台頭し、アジアの広大な地域を支配下に置きながらも、最終的には第二次世界大戦での敗北により崩壊してしまいます。本記事では、大日本帝国の成立から滅亡までを、様々な角度から詳しく見ていきましょう。
目次
大日本帝国とは

大日本帝国とは、明治時代から第二次世界大戦直後まで存在していた日本の国家体制のことです。天皇を中心とした国づくりを目指し、憲法(大日本帝国憲法)に基づいて国が運営されていました。
この時代の日本は、欧米の進んだ技術や制度を取り入れて急速に近代化を進め、アジアでは早い段階で列強の仲間入りを果たしました。その一方で軍事力を重視し、台湾や朝鮮半島などを植民地として支配するようになりました。
特に1930年代以降は、軍の力が強くなりすぎて、最終的には第二次世界大戦へと突き進んでいきました。1945年の敗戦後、日本は民主主義国家として生まれ変わることになり、1947年の新しい憲法(日本国憲法)の施行により、大日本帝国は正式に終わりを迎えました。
領土
大日本帝国の領土は、現在の日本本土である本州、北海道、九州、四国を中心に形成されていました。日清戦争後の1895年に台湾を獲得し、日露戦争の結果として1905年には南樺太と関東州を手に入れました。
その後、1910年には朝鮮を併合し、第一次世界大戦後の1919年にはドイツから南洋群島(マリアナ諸島、カロリン諸島、マーシャル諸島)を国際連盟の委任統治領として獲得しました。これらの領土は第二次世界大戦での敗戦により失われ、現在の日本の国土となりました。
大日本帝国の国号が使われるようになった背景

「大日本帝国」の呼称は、明治時代に突如として生まれたものではなく、幕末期からの歴史的な変遷を経て確立されました。なぜ「大日本帝国」という国号が選ばれ、定着していったのか、その背景を探ってみましょう。
「大日本」と「帝国」の意味
日本という国号は、701年に制定された大宝令の時代までさかのぼります。それまで、中国大陸の政権から「倭」と呼ばれていた我が国は、遣唐使を通じて中国の唐王朝に倭を日本に改めるように求め、それが認められました。日本に「大」の字をつけて「大日本」と記すことも、古代から行われてきました。*1)
「帝国」とは、皇帝の支配する国、広域的な支配をする国を意味する語で、近代以降では植民地を領有する国家を意味していました。*2)
幕末から使われ始めた
国号として「大日本」や「帝国」が使われるのは、幕末になってからです。たとえば、日米修好通商条約では、江戸幕府の将軍のことを「帝國大日本大君」と表記しています。*3)
また、国の正式文書に用いられる国璽には「大日本國璽」と刻まれていますが、国璽が作られたのは1871年のことでした。このことから、対外的に「大日本帝国」や「大日本国」という国号を用いたのは、幕末から明治の初めころと考えてよいでしょう。
国号が大日本帝国に統一されたのは1935年
明治時代以降も日本の正式な国号は未確定のままでした。1927年には政府が、各国での呼び方は実用性を重視し、一般的な呼称やジャパンの使用を容認する立場を示しました。
ところが、ジャパンという表記は帝国の威厳を損なうとの批判を受け、1935年に外務省が外交文書における国号を「大日本帝国」に定めました。*4)
それまでは「日本国」「日本帝国」「大日本国」など、複数の表記が併存していましたが、これによって「大日本帝国」への統一が図られたのです。
大日本帝国の統治機構について

大日本帝国の政治の仕組みはどのようなものだったのでしょうか。ここでは、大日本帝国の政治体制を天皇の地位、天皇の下での役割分担、統帥権、枢密院について解説します。
天皇が国政を「総攬(そうらん)」する
1889年に公布された大日本帝国憲法では、天皇は神聖で侵すことのできない存在として、国の統治権を全て掌握する元首と定められ、天皇主権が憲法上で明確に示されることとなりました。
その権限は多岐にわたり、陸海軍を含む全ての国家公務員の任命や罷免をはじめ、国防における基本方針の策定、さらには戦争開始や講和条約締結の決定権なども天皇に付与されました。
天皇の下での三権分立
大日本帝国憲法でも、現代のように三権分立体制が採用されましたが、現在と異なる点もたくさんあります。三権は、以下の機関が司っていました。
- 行政権:内閣
- 立法権:帝国議会
- 司法権:大審院
戦前の日本では、内閣は内閣総理大臣が率いる組織でしたが、現代とは大きく違う仕組みになっていました。現代では総理大臣が大臣を自由に選べますが、戦前は天皇が大臣を選ぶ権利を持っていました。そのため、総理大臣は思い通りに大臣を替えることができませんでした。
このような制度の問題点を示す、有名な例があります。昭和時代に総理大臣を務めた近衛文麿は、外務大臣の松岡洋右と外交政策について意見が合わず対立していました。近衛総理大臣は松岡外相に辞めてほしいと頼みましたが、断ったため、自分が総理大臣を辞めることを選びました。*5)
その後、もう一度内閣を作り直すことで、ようやく松岡外相を外すことができたのです。このような複雑な手続きが必要だったのは、当時の制度では総理大臣に大臣を直接解任する権限がなかったからです。
帝国議会は、衆議院と貴族院という2つの院から成り立っていました。選挙で選ばれる衆議院と、華族や天皇が任命した議員からなる貴族院が同じ権限を持っていたため、両者が対立すると立法機能が止まってしまうという不便な点がありました。
これらのことからわかるように、大日本帝国では天皇の存在感が大きく、現代とは違った三権分立となっていたのです。
軍隊を指揮する統帥権は天皇に直属
戦前の日本では、軍隊を動かす最高の権限である「統帥権」が天皇にあり、これは内閣から完全に独立していました。
簡単に言うと、軍隊の重要な決定は、内閣の許可がなくても、天皇の承認さえあれば実行できる仕組みだったのです。ただし、実際には天皇が直接指示を出すわけではありません。陸軍と海軍のトップである参謀総長や軍令部総長が天皇の名前を借りて命令を出していました。*6)
たとえば、中国との戦争を始めるかどうかといった重大な決定も、内閣が反対しても、軍部が天皇の承認を得れば実行できてしまいました。これは、まるで国の中に「政府」と「軍隊」という二つの権力が存在しているようなものでした。
このような制度があったため、軍部が暴走しても政府が止めることができず、日本は戦争への道をまっしぐらに進んでしまいました。今の日本では、このような反省から、軍事力(自衛隊)は政府の完全な管理下に置かれています。
枢密院が天皇の諮問に答える
枢密院は、戦前に存在していた天皇の諮問機関です。もともとは、大日本帝国憲法を審議する際に設置された組織でしたが、憲法制定後も存在し続けました。
憲法や皇室に関する重要事項、外国との条約締結などについて、天皇に助言する役割を担っていました。当初は天皇の諮問機関として設立されましたが、次第に政治的な影響力を持つようになり、特に政党内閣との対立が目立つようになりました。
1947年の日本国憲法施行とともに廃止されるまで、近代日本の政治において重要な役割を果たした機関でした。
大日本帝国の住民について

大日本帝国は、現在よりも広い範囲を支配していました。そのため、日本人以外にも多数の民族が「臣民」として存在していました。ここでは、日本人以外の住民や「臣民」の地位について解説します。
日本人以外の人々も住んでいた
大日本帝国の領域内には、さまざまな民族が住んでいました。主な民族は以下の通りです。
- 日本人
- 朝鮮人
- 台湾人
- アイヌ民族
- 樺太の先住民族
1910年の韓国併合により、朝鮮は大日本帝国の植民地となりました。韓国併合後、朝鮮人は朝鮮総督府の支配を受けました。*7)台湾が日本の植民地となったのは1895年の下関条約後です。日清戦争後の講和条約である下関条約後に、台湾が日本の植民地となったからです。
アイヌ民族は、主に北海道や樺太(サハリン)、千島列島に居住していた先住民族です。江戸時代、北海道は蝦夷地と呼ばれ、アイヌの土地と考えられてきました。
しかし、明治維新後、政府は北海道に開拓使を置いて北海道開拓を進め、同化政策を推し進めました。その過程で、アイヌ民族の数は急速に減少し、独自の言語や文化が急速に失われました。現在は、アイヌ文化を継承する取り組みが行われています。*8)
明治維新後、樺太は日本とロシアの「雑居地」と定められ、明確な国境は引かれませんでした。その後、1875年の樺太千島交換条約により、日本は樺太を放棄します。しかし、日露戦争勝利後に、樺太南部が日本領となりました。そのとき、樺太に住んでいた先住民が大日本帝国の住民となっています。
「臣民」としての権利が認められた
大日本帝国憲法では、天皇と皇族を除く全ての日本人が「臣民」として位置づけられていました。臣民には居住・移転の自由や言論の自由などの権利が認められていましたが、これらは「法律の範囲内」という制限付きでした。つまり、法律によってこれらの権利を制限することができたのです。
一方で臣民には、兵役の義務や納税の義務が課されており、天皇への絶対的な服従が求められていました。これは現在の日本国憲法における「国民」とは大きく異なり、より制限された立場であったと言えます。臣民は天皇の支配対象として位置づけられ、天皇に従う存在として扱われていたのです。
大日本帝国が終わった理由とその後

1945年8月15日、大日本帝国は連合国に無条件降伏し、アジア・太平洋戦争に敗れました。これにより33年間続いた大日本帝国体制は崩壊し、日本は戦後の民主主義国家として新たな一歩を踏み出すことになりました。ここでは、大日本帝国終焉の原因となった敗戦とその後の日本について解説します。
第二次世界大戦の敗戦で大日本帝国が終わった
大日本帝国は、1945年8月、広島と長崎への原子爆弾投下という未曾有の惨禍を経験した後、連合国のポツダム宣言を受諾することを決定しました。そして8月15日、昭和天皇は玉音放送を通じて国民に終戦を告げ、この放送により大日本帝国は事実上の終焉を迎えることとなりました。*9)
その後、9月2日に東京湾の戦艦ミズーリ号上で降伏文書の調印が行われ、正式に第二次世界大戦は終結しました。これにより、日本は連合国軍の占領下に置かれ、明治維新以来続いた天皇を元首とする帝国体制から、主権在民の民主主義国家へと大きく転換することとなりました。
日本は、GHQの支配のもと、軍国主義的な諸制度は解体され、新憲法の制定をはじめとする様々な民主化改革が実施されました。こうして大日本帝国は歴史の幕を閉じ、現在の日本国へと生まれ変わることとなったのです。
日本国憲法の公布
日本国憲法は、1946年11月3日に公布され、翌1947年5月3日に施行されました。この憲法は、第二次世界大戦後の日本の民主化における重要な転換点となりました。
この日本国憲法は、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の指導のもと作成され、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」という三大原則を基本理念としています。特に第9条における戦争放棄の明記は、平和国家としての日本の基盤を確立する重要な条項となりました。*10)
大日本帝国憲法から日本国憲法への移行は、天皇主権から国民主権への転換を象徴する歴史的な出来事であり、現代の日本の民主主義と平和国家としての在り方を規定する基本法として、今日まで重要な役割を果たしています。
戦後の民主化
戦後の日本における民主化は、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の指導のもと、急速に進められました。特に重要だったのは、1945年10月に出された五大改革指令です。これにより、女性参政権の付与、労働組合の育成、教育の民主化、特高警察の廃止、経済の民主化などが実施されました。
新憲法の制定により、天皇は象徴となり、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義が基本原則として確立されました。また、農地改革により地主制度が解体され、多くの小作農が自作農となりました。教育面では、教育基本法が制定され、6・3・3制の導入や男女共学が実現しました。
経済面では財閥解体が行われ、経済力の過度な集中が排除されました。労働環境も大きく改善され、労働基準法の制定により、労働者の権利が保護されるようになりました。
しかし、冷戦の激化とともに、GHQの占領政策は徐々に転換し、日本の自立化や経済復興が重視されるようになっていきました。これらの改革は、現代の日本社会の基礎となっています。
大日本帝国とSDGs

大日本帝国は、日本国憲法の制定とともに消滅しました。明治以降、日本は経済力と軍事力を高めて列強の一員となりましたが、第二次世界大戦の敗戦により、それまで獲得した植民地を失ってしまったのです。
かつての日本の歩みは、中国や周辺国への積極的進出により、かえって国際的な対立を引き起こしたという点で再検討の余地があります。ここでは、戦前の外構の問題点とSDGs目標17との関連について考えます。
SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」との関わり
大日本帝国の歴史は、国際協調の重要性を示す教訓として、現代のSDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」と深い関連性を持っています。
1933年の国際連盟脱退に至るまで、日本は実際には「協調外交」の時代を経験していました。1920年代の幣原外交では、国際協調主義に基づく外交政策を展開し、国際社会との良好な関係構築を目指していました。
しかし、国際連盟脱退後、日本は国際的な対話や協力の機会を失い、軍国主義化が加速し、最終的に無謀な戦争への道を歩むことになりました。この歴史的教訓は、SDGs目標17が提唱する国際パートナーシップの重要性を強く示唆しています。
現代社会が直面する環境問題や貧困などのグローバルな課題は、一国では解決できません。SDGs目標17は、政府間の協力だけでなく、市民社会や民間セクターを含めた包括的なパートナーシップの構築を提唱しています。大日本帝国の孤立による失敗から、国際協調と多様な主体の参加が、持続可能な発展には不可欠であることを学ぶことができます。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
今回は、大日本帝国について解説しました。大日本帝国は1889年の大日本帝国憲法制定から1947年の日本国憲法施行まで、約60年にわたって存続した天皇を元首とする立憲君主制国家でした。
欧米の先進技術や制度を取り入れて急速に近代化を進め、アジア唯一の列強国となりましたが、同時に軍事力を重視して台湾や朝鮮半島などを植民地として支配しました。国家体制としては、天皇が国政を「総攬」。三権分立が採用されるも天皇の権限が強い状態でした。また、統帥権が天皇に直属していたため軍部が暴走する要因となりました。
大日本帝国には日本人のほか、朝鮮人、台湾人、アイヌ民族など多様な民族が「臣民」として存在していました。
1945年の第二次世界大戦敗戦により連合国に無条件降伏し、GHQの占領下で民主化改革が進められ、1947年に日本国憲法が施行されたことで大日本帝国は正式に終わりを迎えました。
参考
*1)名古屋大学学術機関リポジトリー「国号に見る「日本」の自己意識」
*2)山川 世界史小辞典 改定新版「帝国」
*3)データベース「世界と日本」「日本國米利堅合衆國修好通商條約(日米修好通商条約)」
*4)外務省「外務省: 外交史料 Q&A その他」
*5)百科事典マイペディア「近衛文麿内閣」
*6)改定新版 世界大百科事典「統帥権」
*7)山川 日本史小辞典 改定新版「韓国併合」
*8)知恵蔵mini「アイヌ民族」
*9)改定新版 世界大百科事典「玉音放送」
*10)デジタル大辞泉「日本国憲法」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。