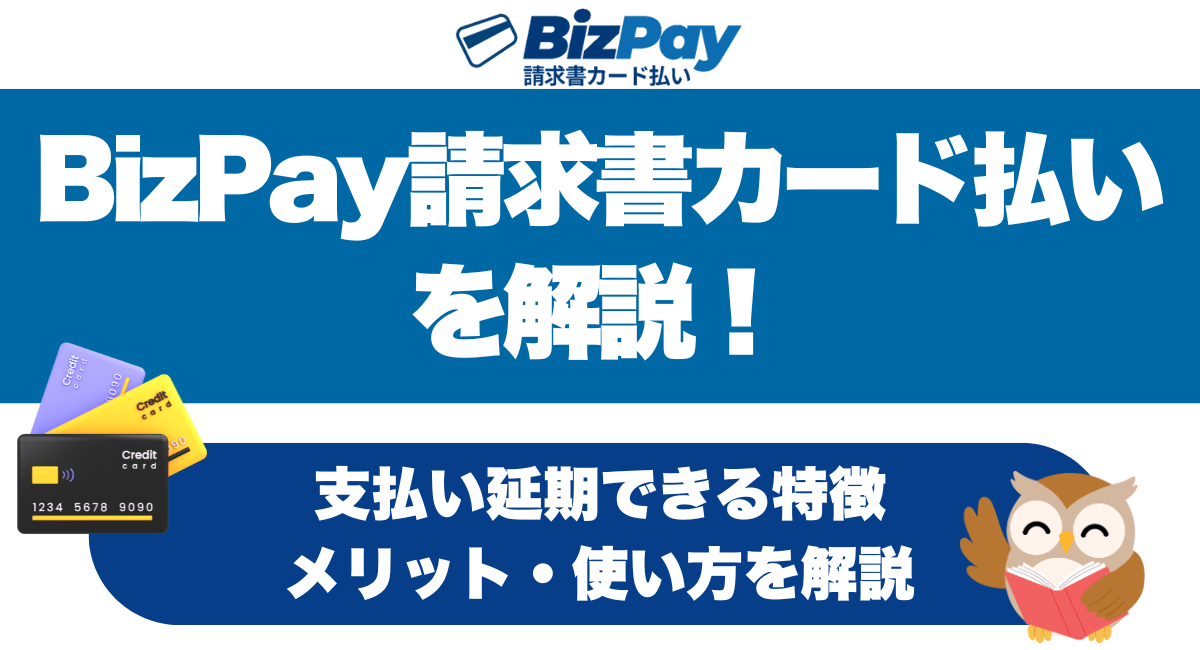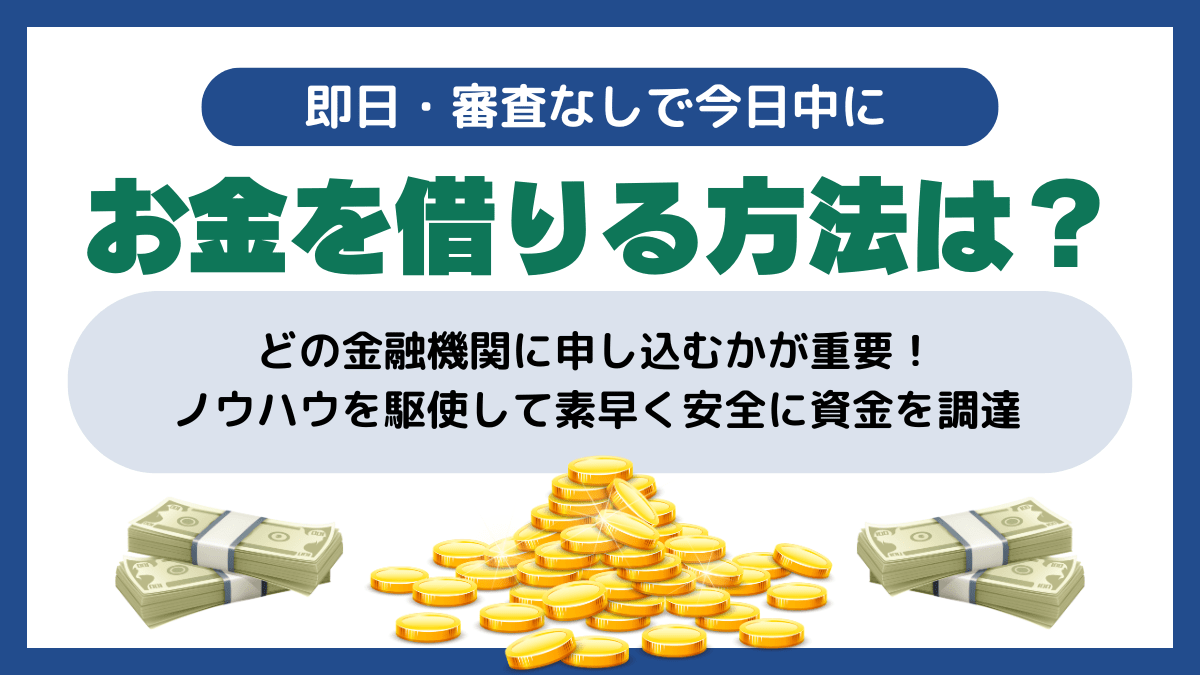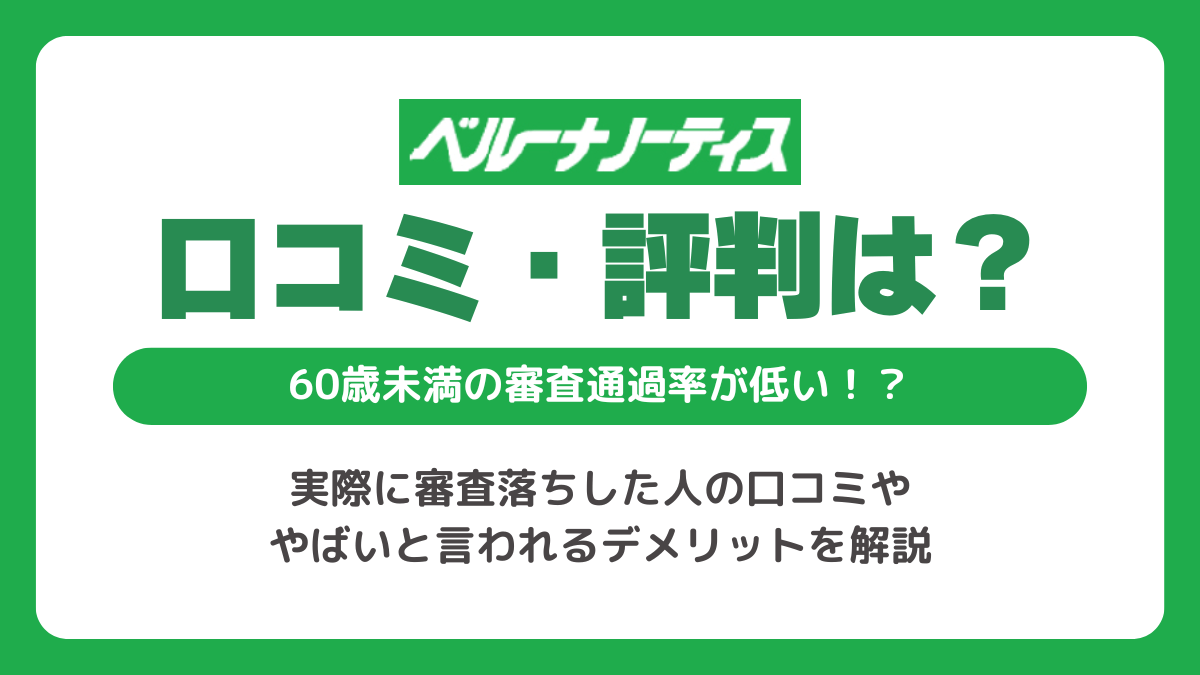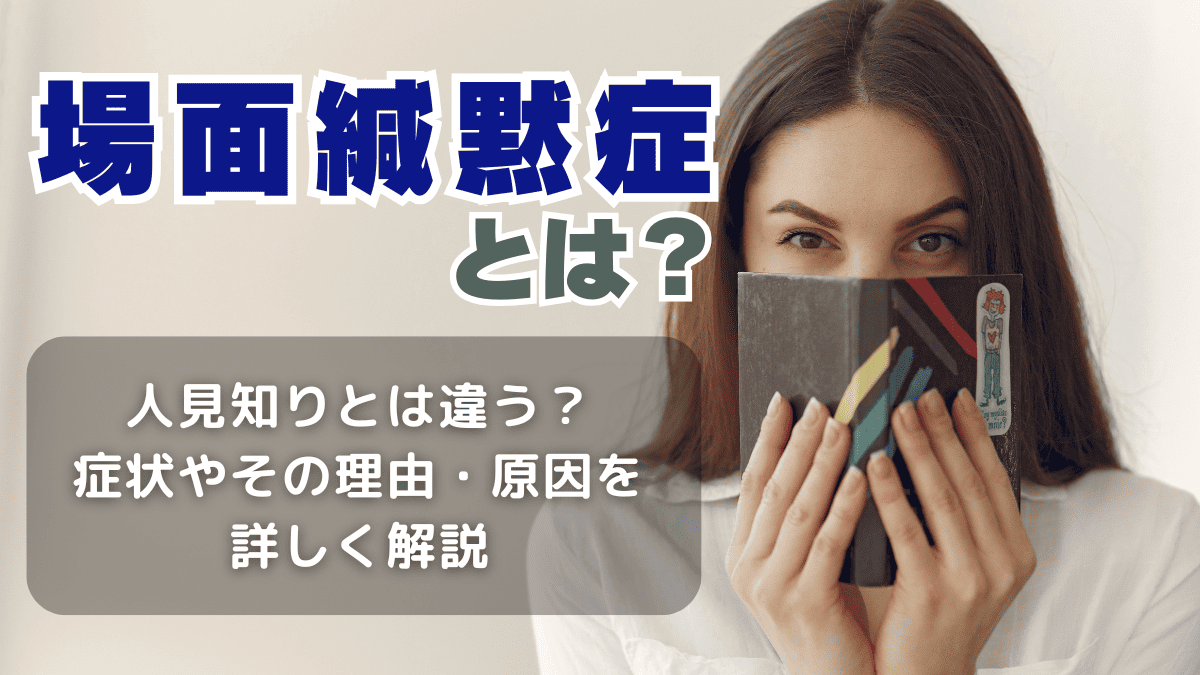オイテル株式会社 飯﨑俊彦さん インタビュー

飯﨑俊彦
オイテル株式会社 取締役。
「あなたによくて、社会にいいこと」をビジョンに掲げ、ビジネスを通じた社会課題の解決を目指し、OiTrをスタート。日本初となる、女性個室トイレに生理用ナプキンを常備・無料提供するサービス「OiTr(オイテル)」の企画立案・商品開発を手がける。OiTrを単なるプロダクトにとどめず、持続可能なエコシステムとして発展させることに注力し、社会インフラとしての普及を推進している。
目次
introduction
ビジョンに「あなたによくて、社会にいいこと」を掲げ、社会問題の解決と経済活動の両立を目指すオイテル株式会社。
社会課題をビジネスで解決することをミッションに、当初、男性のみのメンバーで起業したこともあり、従来の性別役割意識が生む格差について、男性自らが解決に取り組むべきだという思いで、「ジェンダーギャップ」という社会問題に真摯に向き合っています。
今回は、オイテル株式会社が提供する生理用ナプキン無料提供ディスペンサー「OiTr(オイテル)」の開発や導入について、飯﨑さんにお話を伺いました。
「生理の貧困」は、女性だけの問題ではない
―まずは会社概要について教えてください。
飯﨑さん:
弊社は「あなたによくて、社会にいいこと」というビジョンを掲げ、IoT事業を軸に、全国の商業施設、交通機関、公共施設、学校やオフィスなどの個室トイレに生理用ナプキンを常備・無料提供する日本初のサービス「OiTr(オイテル)」を展開しています。
OiTrが設置された個室トイレを利用された方は、無料で生理用ナプキンを受け取ることができます。また、無料提供するためにOiTrのディスペンサーにデジタルサイネージを搭載し、そこに企業の広告動画を流しています。広告出稿してくださる企業から広告協賛費をいただき、その収益などで生理用品代を賄う仕組みになっています。
―利用の流れを詳しく教えてください。
飯﨑さん:
OiTrが設置された女性個室トイレに入ると、ディスペンサーに搭載されたセンサーが人を感知し、デジタルサイネージに企業の広告動画が再生されます。
実際にトイレ内に設置されている「OiTr」のサービスを利用するためには、専用アプリ(無料)のダウンロードが必要です。
アカウントは無料で作成でき、作成していただくと25日ごとに最大7枚まで生理用ナプキンの無料で受けることができます。使い方はとてもシンプルで、アプリを起動し画面を表示したままスマートフォンをディスペンサー(OiTrのロゴ付近)に近づけ、「取り出しボタン」をタップすると、ディスペンサーと通信が行われ、生理用ナプキンが取り出し口から出てきます。
ディスペンサー内の生理用ナプキンの補充は、各施設のご担当者の方にお願いしています。在庫が切れている場合は、デジタルサイネージの画面にその旨が表示され、一目で確認できるようになっています。これは利用者への通知機能でもあり、清掃員の方の補充漏れを防ぐための機能でもあります。さらに、弊社では各施設の在庫状況をWEB上で管理し、在庫の欠品が起こらないように細心の注意を払ってサポートをしています。

―生理用ナプキンの無料提供サービスに至った経緯を教えてください。
飯﨑さん:
「生理の貧困」という言葉をご存知でしょうか。OiTrを開発していた2020年頃は、まだ日本では広く認識されていなかったものの、実際にこの現象は存在しており、海外では既に注目されていました。「生理の貧困」とは、生理用品はもちろん、清潔な水や衛生的な環境、生物学と生殖に関する教育など、生理に最低限必要なものにアクセスできない状態を指します。
厚生労働省の調査によると、新型コロナウイルス発生後(2020年2月以降)、生理用品の購入や入手に苦労した経験がある人は8.1%に上り、その影響で「プライベートなイベントや娯楽の予定を諦める」が40.1%、「家事・育児・介護に手がつかない」が35.7%、「学業や仕事に集中できない」が34.1%という結果が出ています。このように、生理用品へのアクセス不足は基本的な生活に大きな負担を与え、社会での活躍の機会を奪っているのです。
さらに問題なのは、日本ではこの現象が経済的側面だけで捉えられている点です。つまり、「お金がないために生理用品が買えない」という金銭的な理由に限定された狭義な意味で認識されているということです。そもそも、生理を女性だけの問題とみなす風潮自体が問題であり、生理は生命誕生に関わる重要な役割を担っていることから、単に女性だけの問題と限定すべきではありません。ライフステージの約40年間にわたり、生理用品を購入し、それに伴う消費税を支払い続けるのが女性のみであるという状況は、依然として男女間の賃金格差が存在する社会において、極めて不条理だと感じています。
男女の違いを認識しつつ、お互いの特性を補完し合うことが、より豊かな社会活動に繋がっていくのではないでしょうか。すべてを一律に平等とするのではなく、それぞれの違いを尊重するジェンダー平等のあり方こそが必要だと、私自身は理解しています。
このような背景から、「トイレットペーパーと同じように、個室トイレに生理用品が行き届く社会」を目指して、私たちのサービスは誕生しました。

開発を通して初めて見えた、女性の生理の実情
―事業を進める上で大変だったことはありますか。
飯﨑さん:
ディスペンサーの開発は非常に大変でした。起業当時、メンバーは全員男性で生理に関する知識も乏しく、さらにソフトウェアもハードウェアの開発経験もなかったんです。そんな中、私の知人の紹介でエンジニアに出会いました。技術力はもちろん、卓越したコミュニケーション能力で丁寧にヒアリングを行いながら製品設計を進めてくださり、OiTrの実現に大きく貢献してくれました。
また、その後の施設への設置営業も苦労がたくさんありました。2020年頃、様々な企業や施設を訪問した際、口を揃えて言われたのが「それって必要ですか?」です。営業時に対応してくださる方のほとんどが男性であったため、男女ともに利用するトイレットペーパーと異なり、女性専用の生理用品の提供の必要性が十分に理解されにくかったのです。現在でも多くの場合、生理用品の設置は不要と考えられていますよね。当時は「ジェンダーギャップ」や「生理の貧困」が広く認識されていなかったため、余計に問題意識が低かったのだと思います。
このような状況を実感した私たちは、まずはOiTrを実際に設置し、利用してもらうことが何より重要だと判断しました。従来のビジネスモデルにとらわれず、施設側の導入負担をできるだけ軽減する方法を考案しました。それが、デジタルサイネージ広告事業だったのです。その効果もあり、埼玉県にある大手企業の商業施設「ららぽーと富士見」で実証テストの機会をいただきました。利用者がSNSで体験を発信してくださったことで話題となり、メディアにも取り上げられるようになり、徐々に認知が広がっていったのです。

実証テストで寄せられた利用者の体験談をもとに、サービスの最適化に向けてさまざまな工夫を行いました。例えば、ディスペンサーの作動音です。実証テストで設置した施設からは、生理用ナプキンが出てくる際の音が静かであることに対し、好意的な反応をいただきました。この時初めて、女性トイレの個室でもナプキンを取り出す際に他の人に知られたくないという心理が働いていることを知りました。男性である私たちの想像以上に、生理という問題は当事者にとって繊細なものであると改めて実感する出来事でした。
また、急な生理時に慌ててコンビニで生理用品を購入しようとした際、店員が男性だったために購入が難しかったという話も耳にしました。こういった声から、たとえ周囲が気にしていなくても、当事者が不快に感じる以上、その人が安心して過ごせる環境を整えなければ解決しないと改めて思ったんです。そこで、メンバーに女性を加えて意見を取り入れるとともに、アンケートやヒアリングを通じて、さまざまな利用シーンを想定しながらディスペンサーの機能や仕組みを検討しました。
社会を変化させていくために今できること
―今感じている課題はありますか。
飯﨑さん:
スマートフォンを使用しなければOiTrのサービスを利用できない点は、課題の一つだと考えています。生理用品は医薬部外品として扱われるため、製造や販売に関して法律で定められており、弊社としても生理用品を取り扱い、問題なくサービスを提供するためにスマートフォンのアプリでの管理が必要だったのです。しかし、小中高校ではスマートフォンの持ち込みが制限されている学校もあり、また保護者が子どもにスマートフォンを持たせない場合もあるため、現在は大学や専門学校の設置に限定しています。今後は、アプリ以外の方法でもサービスを提供できるよう検討していきたいと考えています。正直なところ、スマートフォンを持ち歩く世代が広がるのが先か、弊社のサービスアップデートが先かはまだ不透明ですが、より良い方向へ向かって常に変革を続ける必要があると考えています。
―今後の展望を教えてください。
飯﨑さん:
OiTrは、全国28都道府県の292施設に3,300台を設置(2025年3月時点)を設置しています。日本全国の個室トイレにOiTrを導入することで、「ジェンダーギャップ」や「生理の貧困」に対する問題意識を高め、「トイレットペーパーと同じように、個室トイレに生理用品が行き届く社会」の実現へと推進していきたいと思っています。OiTrは、社会のインフラとして持続可能なサービスでなければなりません。そのためにもOiTrのプロジェクトに賛同・参画していただける企業を増やすため、OiTrのプラットフォームを企業に幅広く活用いただけるよう成長させたいと考えています。
皆様の応援よろしくお願いいたします。
―貴重なお話をありがとうございました。
関連リンク
オイテル株式会社:https://www.oitr.jp/
この記事を書いた人
鈴木愛美 ライター