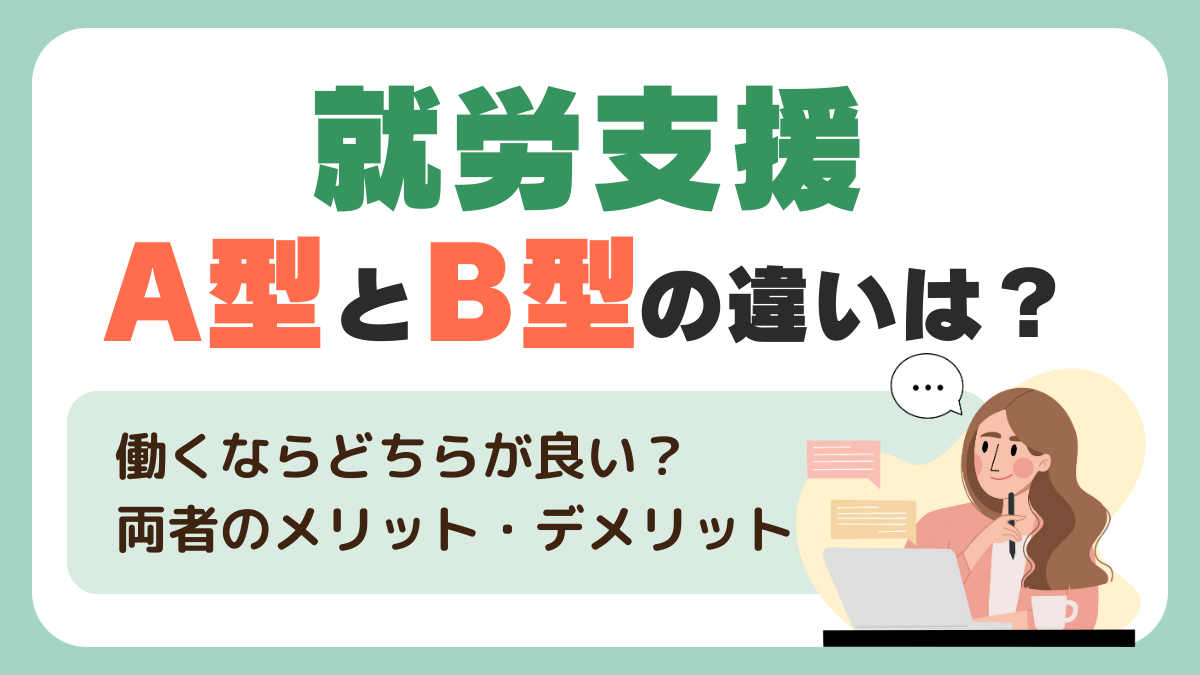
「自分らしく働きたい」というのは、多くの人が思うことかもしれません。それは、年齢や男女に関わるものではなく、一般的な想いなのではないでしょうか。しかし、障がいや病気など、何らかの理由で働くのが難しくなってしまった場合、どのように「自分らしい」働き方や社会の接し方をすればよいのでしょうか。
そのような場合の選択肢の一つが、就労支援施設を利用して働くことです。就労支援施設は、A型とB型に分かれていますが、両者の違いについてあまり詳しくご存じないかもしれません。
本記事では、就労支援A型とB型の特徴や利用する際のメリット・デメリット、どのような方が対象となっているかについてまとめます。また、就労支援施設で働く際の給与や職員の悩みなどについても紹介しますので、ぜひ、参考にしてください。
目次
就労支援とは
詳しい説明に入る前に、まずは就労支援について内容を確認しておきましょう。就労支援とは、障害者総合支援法によって定められた福祉サービスです。障がいや疾患などが理由で働けない人を対象とし、就労の手助けをします。
4種類の就労支援
就労支援には4つの種類があります。
| 就労移行支援 | 65歳未満の障がい者が対象一般就労に必要なスキルを身につける標準利用期間は2年 |
| 就労支援A型 | 障がいのある方に働く場を提供65歳未満が対象雇用契約あり |
| 就労支援B型 | 障がいのある方に働く場を提供年齢制限なし雇用契約なし |
| 就労定着支援 | 就労移行支援や就労支援で就職した方を対象に、面談や職場訪問でサポート就労6ヶ月以降の方が対象利用期間は3年 |
*1)
今回は、就労支援にスポットを当て、A型とB型の内容やメリット・デメリットについて解説します。
就労支援A型とは
【事業所数の推移】
就労支援A型の正式名称は「就労継続支援A型」で、就労機会の提供や生産活動の機会の提供などを目的*2)としています。就労支援A型の特徴は、就労を希望する障がい者と事業所が雇用契約を結ぶことであるため、雇用型とも呼ばれます。
事業所で労働者として働きながら、就職のための知識・能力を身につけ、最終的には一般企業に就職できるよう支援します。
令和元年度の就労支援A型の利用者は72,197人で、事業所数は3,842か所となっています。
就労支援A型の事業所は増加傾向を示していましたが、2017年4月に指定基準の見直しなどが行われたことにより、事業所数の増加が鈍化しました。
対象となる人
就労支援A型の対象となるのは、65歳未満の人で就労機会が提供されれば雇用契約を結べる可能性がある人です。具体的には、
- 就労移行支援事業を利用したものの雇用に結びつかなかった方
- 盲・ろう学校や特別支援学校卒業後に雇用に結びつかなかった方
- 就労経験はあるものの今は雇用されていない方
などが該当します。
厚生労働省は、具体的なイメージとして以下の例を挙げています。
- 特別支援学校を卒業して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している
- 一般就労していたが、体力や能力などの理由で離職した。再度、就労の機会を通して、能力等を高めたい
- 施設を退所して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している
出典:厚生労働省*2)
A型を利用する方は、労働者として働きつつ同時に訓練も受けることで、一般就労のための知識・能力を身につけます。その後、就労移行訓練を経て一般企業に就職することを目指します。
就労支援A型に向いている人
就労支援A型に向いているのは、一般企業での勤務が難しいものの、雇用契約を結んで働くことが可能な障がいのある方です。具体的には、一定の作業能力や出勤の安定性があり、支援を受けながら就労経験を積みたいと考える人が対象となります。
また、将来的に一般就労を目指している方にも適しています。A型就労では最低賃金が保証され、社会保険に加入できるため、収入面や社会的自立を重視したい人にも向いています。
体調や精神面で配慮を受けつつ、働く意欲がある方にとって、安心して職業訓練に取り組める環境です。
就労支援A型のメリット
就労支援A型のメリットは、一般就労が困難でも福祉的就労の範囲で労働できることです。ここでは、A型のメリットである福祉的就労について解説します。
福祉的就労が可能
障がいのある方の働き方は、一般就労と福祉的就労の2つに分けられます。
| 一般就労 | 企業や官公庁で働くこと |
| 福祉的就労 | 障がい者就労施設(就労支援施設A型・B型)で働くこと |
一般就労は、一般企業や官公庁で、障がいのない人と同じ場所で勤務します。一方、福祉的就労は、障がいのある人が障がい者就労施設で働くことであり、厳密には勤務ではなく「就労系の障がい福祉サービス」の利用となります。*3)
そのため、勤務である一般就労に比べると融通が利きます。障がいによる困りごとや体調に合わせて働けるのは、就労支援A型のメリットといってよいでしょう。
雇用契約に基づき最低賃金が保障される
就労支援A型事業所では、利用者と正式に雇用契約を結ぶため、法律に基づいて最低賃金が支払われます。これはB型と大きく異なる点で、働いた時間に応じて安定した収入を得ることが可能です。
賃金が保証されることで、経済的な自立の第一歩を踏み出すことができ、生活の安定やモチベーションの向上にもつながります。また、労働基準法が適用されるため、労働時間や休憩などもきちんと管理され、一般就労に近い環境で働く経験が得られます。将来的に企業での勤務を目指す際の準備としても有効です。
体調や特性に配慮した働き方ができる
A型事業所では、障がいのある方の体調や特性に応じて、勤務日数・時間・作業内容を柔軟に調整してもらえる点が大きな魅力です。例えば、体調に波がある人には短時間勤務や軽作業を中心とした業務が用意されることが多く、無理なく継続して働けるよう配慮されます。
さらに、精神的な不安を抱えている方には、専門スタッフによる声かけや相談支援も行われ、安心して職場に通える体制が整っています。このような環境があることで、就労への不安を和らげながら、社会参加や自己肯定感の回復にもつながります。
一般就労へのステップアップを支援してくれる
A型事業所では、将来的な一般就労を視野に入れたサポートが充実しています。職場での基本的なマナーやルールの習得、報連相(報告・連絡・相談)の訓練などを通じて、企業就労に必要なスキルを身につけることが可能です。
また、面接対策や履歴書作成の支援、企業見学や実習の機会を提供する事業所も多く、段階的に一般就労への準備が進められます。障がい特性に配慮した支援体制が整っているため、初めて働く人やブランクのある人でも安心です。
就労移行支援など他サービスとも連携し、着実なキャリア形成を目指せます。
就労支援A型のデメリット
就労支援A型のデメリットとして、以下の点があげられます。
- 一般就労よりも給与が少ない
- 労働契約を守らなければならない
- 事業所の面接が必要
上記のデメリットについて詳しく見てみましょう。
一般就労よりも給与が少ない
1つ目のデメリットは、一般就労よりも給与が少ないことです。令和5年度の「賃金構造基本統計調査」によると、一般労働者の年間賃金の平均(男女計)は318万.3000円で月額にすれば、26万5,250円となります。*4)
それに対し、就労支援A型の平均工賃(賃金)は、月額83,551円となっており、一般労働者の賃金の3分の1程度にとどまっています。*5)
労働契約を守らなければならない
2つ目のデメリットは、事務所と結んだ労働契約を遵守しなければならないことです。契約により決められた勤務日数や勤務時間に従って働くことが求められるため、就労支援B型に比べると自由度が低いことに注意が必要です。
事業所の面接が必要
3つ目のデメリットは、採用面接が必要であることです。自治体の窓口に利用申請を出すだけではなく、雇用する企業の書類選考や面接を受けなければならず、そのための準備も必要です。
就労支援B型とは
【事業所数の推移】
就労支援B型の正式名称は「就労継続支援B型」であり、A型と同じく就労機会の提供や生産活動の機会の提供*2)などを目的としています。雇用契約を結ばないことから、非雇用型とも呼ばれます。令和元年度の就労支援B型の利用者は269,339人で、事業所数は13,117か所となっています。
就労支援B型の利用者数や事業所数は、毎年増加しています。
【設置主体別割合の推移】
対象となる人
事業所数が増えているのは、営利法人による設置が急増したからです。
就労支援B型の対象となるのは、就労移行支援で一般企業での雇用に結びつかなかった方や、一定年齢(50歳)に達している方です。*2)
厚生労働省があげた具体的なイメージは、以下のとおりです。
- 就労移行支援事業を利用したが、必要な体力や職業能力の不足等により、就労に結びつかなかった
- 一般就労していて、年齢や体力などの理由で離職したが、生産活動を続けたい
- 施設を退所するが、50歳に達しており就労は困難
出典:厚生労働省*2)
B型を利用する方は、作業訓練などを通じて生産活動を行い、生産したものに対して賃金が支払われる仕組みです。訓練や経験を積むことで、A型や就労移行支援の段階に移ります。
就労支援B型に向いている人
就労支援B型に向いているのは、一般就労やA型での勤務が難しく、雇用契約に基づく働き方に不安がある方です。具体的には、体力や精神面に不安があって継続的な勤務が難しい人や、日によって体調の変動が大きい方などが対象になります。
B型では雇用契約を結ばず、自分のペースで通所や作業ができるため、プレッシャーを感じずに働く習慣を身につけることが可能です。福祉的な支援を受けながら、体調を整えたり生活リズムを整えたりする段階としても適しています。障がいの状態やライフスタイルに合わせた無理のない働き方を希望する方に向いています。
就労支援B型のメリット
就労支援B型のメリットは、雇用契約を結ばなくても働くことができることです。雇用契約を結ぶ必要がない利点について、解説します。
無理のないペースで働ける
就労支援B型のメリットは、障がいの程度や困りごと、症状などに応じて負荷がかかりすぎない程度に働けることです。
事業所ごとのルールはありますが、勤務日数・勤務時間などについては相談することができるため、雇用契約があるA型に比べるとプレッシャーを感じることなく仕事に取り組めます。
雇用契約がないため、出勤や作業の柔軟性が高い
B型事業所では雇用契約を結ばないため、働き方の自由度が非常に高い点が特徴です。出勤の義務や決まった労働時間に縛られず、自分の体調や都合に合わせて通所や作業時間を調整できます。
そのため、体力や精神面に不安がある方、通院や家庭の事情などで定期的な出勤が難しい方でも無理なく続けやすい環境です。就労のプレッシャーが少なく、失敗を恐れず挑戦できることも、B型ならではのメリットです。
柔軟な働き方ができることで、心身への負担が軽減され、継続的な通所や作業習慣の形成にもつながります。
生活リズムや社会性を整える訓練になる
就労支援B型は、収入を得るだけでなく、生活面を安定させるための訓練の場としても機能します。定期的な通所を通じて、日中の活動習慣が身につき、昼夜逆転の改善や生活リズムの安定に役立ちます。
また、スタッフや他の利用者との関わりの中で、あいさつや報告・相談といった社会性・コミュニケーション力も自然と養われます。いきなり一般就労を目指すのが難しい方でも、まずはB型で「外に出て人と関わる」ことに慣れることで、将来の自立やステップアップへの土台を築くことができます。
就労に不安がある人でも安心して作業に取り組める
就労支援B型事業所では、専門の支援スタッフが常にそばで見守りながら作業をサポートしてくれます。失敗しても責められることがなく、自分のペースで作業に取り組める環境が整っているため、「働くことに自信がない」「過去に職場でうまくいかなかった」といった不安を抱える人にも安心です。作
業内容も個人の特性や希望に応じて調整されることが多く、成功体験を積みながら、徐々に「働くことが楽しい」と感じられるようになります。自己肯定感の回復や意欲の向上にもつながる支援体制が魅力です。
就労支援B型のデメリット
就労支援B型のデメリットは、A型以上に賃金が低いことです。詳しく見てみましょう。
生活を支えるだけの収入が得られない
B型は、雇用ではなく訓練が中心となっているため、障がい者が生計を立てられるほどの収入を得ることは困難です。B型の主な仕事内容は、以下のとおりです。
- 農作業
- 部品などの加工
- パンやお菓子の製造
- パソコンのデータ入力
- 手作業
- 調理
これらの作業を行いながら、就職するための能力を養います。工賃の規定は事務所ごとで異なりますが、
- 作業内容や生産した品物の量などで支払うケース
- 日額で支払うケース
などがあります。
しかし、どの場合であっても工賃は低い金額に抑えられています。令和4年度の平均工賃(賃金)月額を見ると、月額で17,031円、時間額で243円となっています。*5)
一般就労へのステップアップが難しい場合がある
就労支援B型は、無理のない作業内容や自由な通所スタイルが特徴ですが、その反面、一般企業で働くために必要なスキルやビジネスマナーを身につける機会が限られる場合があります。例えば、決まった時間に出勤する習慣や、一定の生産性を求められる作業環境に慣れることが難しく、結果として一般就労への移行がスムーズに進まないケースもあります。
また、長期間B型にとどまることで現状に満足し、次のステップへ進む意欲を持ちにくくなる可能性も指摘されています。就労を最終目標とせず、生活支援に重点を置く形になりがちです。
社会保障や労働者としての権利が得られない
就労支援B型では雇用契約を結ばないため、法律上「労働者」とはみなされません。そのため、最低賃金や労働時間、休憩などに関する労働基準法の適用を受けることができず、給与や待遇面での保障が限定されます。
また、社会保険(厚生年金や健康保険)への加入も原則として行われないため、将来の年金受給や医療保障といった面でも不安が残る可能性があります。安定した生活基盤を築きたいと考えている方にとっては、B型の働き方は制度上の制約が多く、長期的な自立にはつながりにくいという課題があります。
就労支援A型とB型の違い
就労支援A型とB型にはどのような違いがあるのでしょうか。両者の違いを表形式で整理します。
就労支援A型とB型の違い
両者の違いは以下のとおりです。
| 就労支援A型 | 就労支援B型 | |
| 目的 | 就労機会の提供生産活動の機会の提供 | 就労機会の提供生産活動の機会の提供 |
| 対象者 | 一般的な事業所での雇用が困難な方 | 一般的な事業所での雇用が困難な方 |
| 雇用契約 | あり | なし |
| 賃金 | 給与 | 工賃 |
| 年齢制限 | 65歳未満 | なし |
| 利用期間 | なし | なし |
A型・B型に共通しているのは目的と対象者、利用期間の3点です。一方、大きな相違点は雇用契約の有無や賃金、年齢制限の3点です。障がいの状況にあわせ、A型かB型かを選択するとよいでしょう。
就労支援A型・B型に就職する際の注意点
就労支援施設に就職する際、いくつか気になる点があるのではないでしょうか。ここでは、給与面、職員が抱える悩み、向いている人などについて解説します。
給料は?
令和4年度障害者福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果によると、就労支援A型の令和4年12月の平均給与は264,520円、B型の平均給与は285,970円でした。*6)
【福祉・介護職員の平均給与額の状況(常勤)】
| 月収 | 年収 | |
| 全体 | 315,290円 | 3,783,480円 |
| 就労支援A型 | 264,520円 | 3,174,240円 |
| 就労支援B型 | 285,970円 | 3,431,640円 |
| 児童発達支援 | 281,740円 | 3,380,880円 |
| 放課後等デイサービス | 260,090円 | 3,121,080円 |
| 生活介護 | 313,710円 | 3,764,520円 |
| 施設入所支援 | 365,750円 | 4,389,000円 |
一般企業の平均年収である318万3,000円と比較しても、常勤の就労支援施設職員の給与は、安いわけではありません。
職員が抱える悩みは?
就労支援で働く職員は、どのような悩みを抱えているのでしょうか。主な悩みは以下の3点です。
- 精神的な負担が大きい
- 業務量が多い
- 給与が少ない
就労支援施設の利用者は、何らかの形で障がいや疾病を抱えています。そのため、どのように接するべきか、判断に迷うケースがあるようです。また、利用者の症状によっては情緒が突然乱れるケースもあり、フォローするのに神経を使うといった悩みがあるようです。
施設によっては十分な数の職員が確保できず、業務を消化しきれないといったケースも見られます。利用者の支援以外の業務によって、疲弊してしまう事例もあるようです。
また、他の障がい福祉サービスと比較すると給与が低い点も悩みの一つです。全体平均が月額315,290円であるのに対し、A型は264,520円、B型は285,970円と格差がみられるからです。
事業所ごとに支援体制や雰囲気が大きく異なる
就労支援A型・B型事業所は、運営する法人や施設によって支援の手厚さや職場の雰囲気が大きく異なります。たとえば、スタッフが親身に相談に乗ってくれるところもあれば、最低限の支援にとどまる事業所も存在します。
また、同じ障がい福祉サービスでも、利用者の年齢層や障がい特性、作業内容などが異なり、自分に合わない環境ではストレスを感じやすくなることも。就職前に見学や体験利用を通して、支援の質や職場の雰囲気、自分との相性を確認することが非常に重要です。ミスマッチを防ぐには、事前の情報収集がカギとなります。
仕事内容が希望と異なる場合がある
A型・B型事業所で提供される仕事は、施設によって大きく異なります。主な作業内容としては、清掃、軽作業、農作業、データ入力、製品の袋詰めや組立、飲食補助などがありますが、希望していた職種に必ずしも就けるとは限りません。
求人票やパンフレットに記載された仕事内容が実際と異なることもあるため、就職前に見学や実習を行い、実際の業務内容や一日の流れを確認することが大切です。特に「パソコンを使いたい」「体をあまり動かせない」など明確な希望がある場合は、事前確認を怠ると後悔につながる可能性があります。
将来のステップアップの支援内容に差がある
A型・B型事業所では、一般就労への移行を支援する目的を持つところもあれば、日中活動の場として安定的に利用することを重視しているところもあります。そのため、「将来は一般企業で働きたい」「段階的にスキルを身につけたい」と考えている方にとっては、事業所選びが非常に重要になります。
施設によっては、面接練習や履歴書の作成支援、企業実習などを積極的に行っている一方で、就労移行支援との連携が弱く、ステップアップ支援が形だけになっている場合もあります。将来像に合った支援内容や実績があるか、事前にしっかり確認しておくことが必要です。
就労支援A型・B型に関するよくある質問
就労支援A型・B型について初めて知る方や利用を検討している方からは、制度の違いや働き方、収入面などさまざまな疑問が寄せられます。ここでは、特に多い質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。
A型とB型って、最初にどっちを選べばいいの?
A型とB型には「どっちが上」とか「どっちが偉い」という順番はありません。どちらを選ぶかは、今の自分の体調・働けるペース・目標によって決まります。
たとえば、
- 「決まった時間に働ける」「毎日通える自信がある」
→ A型が合っているかもしれません。 - 「体調に波がある」「まずは少しずつ外に出たい」
→ B型から始める人が多いです。
実際には、B型で生活リズムを整えてからA型にステップアップする人もいれば、最初からA型で働く人もいます。
自治体の福祉窓口や相談支援員に相談すると、今の状態に合った選び方を一緒に考えてくれます。
A型とB型って、どっちが就職に有利なの?
一般企業への就職につながりやすいのはA型です。
A型は雇用契約があり、最低賃金が支払われるので、社会人としての働き方に近い経験が積めます。出勤のリズム、報連相(報告・連絡・相談)などのビジネスマナーも、企業就労の準備になります。
一方のB型は、体調を整えたり、生活リズムを作ったりするための訓練の場です。「すぐに就職」というより、「働く準備を整える場所」という位置づけです。
つまり、A型:実践・ステップアップ段階・B型:リハビリ・準備段階と考えると分かりやすいです。
自分の状態や目標にあわせて、どちらを選ぶかを考えるのがポイントです。
A型やB型って、自分で選べるの?どうやって利用を始めるの?
自分で選べますが、どちらも「福祉サービス」なので、手続きが必要です。
まず、お住まいの自治体(市区町村)の福祉窓口や相談支援センターで相談します。利用には「障害福祉サービス受給者証」が必要で、申請には障害者手帳や医師の診断書などを提出する場合があります。
その後、希望する事業所を見学・体験して、自分に合うか確認します。A型の場合は事業所と雇用契約を結ぶので、面接や選考があることが多いです。B型の場合は雇用契約がない分、利用までのハードルは低めです。
いずれも、「自分に合った働き方を見つける」という目的で選べる仕組みになっています。ハローワークや相談支援事業所に相談すると、スムーズに進められます。
A型やB型で働いたことって、履歴書や職歴に書けるの?
勤務日数や仕事内容が明確に記録されているため、一般企業の面接でも「就労経験」として説明しやすいです。
一方でB型は、法律上は「雇用」ではなく「福祉サービスの利用」という扱いです。そのため、形式上は職歴として書かない人もいます。
ただし、面接などで「B型事業所で○○の作業に取り組み、生活リズムを整えました」「協調性や集中力を身につけました」と話すのは大きなプラスになります。
B型の経験は立派な努力の証なので、伝え方を工夫すれば十分に評価されます。
A型・B型の事業所って、どこも同じ?どうやって選べばいいの?
事業所ごとに支援の手厚さ・雰囲気・仕事内容が大きく違います。同じA型でも、軽作業中心のところもあれば、飲食・農業・パソコン作業など得意分野が異なります。
選ぶときは、次のポイントをチェックしてみてください。
- スタッフの対応(優しく声かけしてくれるか)
- 作業の内容(自分に合う負担か)
- 雰囲気(静か・にぎやか・人間関係の印象)
- 将来の支援(一般就労へ進みたい人向けか、長期通所重視か)
パンフレットやネット情報だけで判断せず、必ず見学や体験をするのが大切です。1〜2回通ってみると、作業内容や雰囲気が自分に合うかどうか、すぐに分かります。
就労支援A型・B型とSDGs
「誰一人取り残さない」というSDGsの目標を達成するには、障がい者の就労についても支援していく必要があります。ここでは、就労支援と目標8との関わりについて解説します。
SDGs目標8「働きがいも経済成長も」との関わり
SDGs目標8は、障がい者を含むすべての人が「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)」で生計を立てることを目指しています。ディーセント・ワークは、1999年のILO(国際労働機関)総会ではじめて使用された言葉です。
また、SDGs目標8のターゲット8.5は、「2030年までに、若者や障がい者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、ならびに同一労働同一賃金を達成する」です。*8)
障がい者も含めたすべての人が、働き買いを持って働くためのサポートの一つが就労支援だといえるでしょう。
まとめ
今回は、就労支援A型・B型について取り上げました。一般企業での就労が難しい人を対象とした就労支援施設は、障がい者の社会参加という点でも非常に重要な施設です。SDGsの観点から見ても、就労支援を含む障がい者雇用はとても重要なテーマといえるでしょう。
就労支援には、賃金の低さという大きな問題点があります。しかし、働く意欲を持ち社会との接点を維持したい障がい者にとって、就労支援は非常に重要です。
障がいを持った方を社会から隔離するという考えは、現代では難しくなりつつあります。なぜなら、ストレスが多い現代社会において、障がいはより身近なものとなっているからです。実際、国民の約9.2%に相当する約1,160万人が何らかの障害を抱えています。*9)
障がいのある方が社会復帰するためのきっかけの一つとして、就労支援A型やB型の施設はとても重要だといえるでしょう。就労支援は、障がい者と社会をつなぐ重要な架け橋となっているのです。
参考文献
*1)厚生労働省「障害者の就労支援について」
*2)厚生労働省「障害者福祉施設における就労支援の概要」
*3)和歌山県「障害のある人の「働く」(就労)について」
*4)厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」
*5)厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」
*6)厚生労働省「令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果の概要」
*7)職業情報提供サイト「障害者福祉施設指導専門員(生活支援員、就労支援員等)」
*8)スペースシップアース「SDGs8「働きがいも経済成長も」現状と日本企業の取り組み事例、私たちにできるこ
*9)内閣府「令和4年度障害者施策の概況」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。







