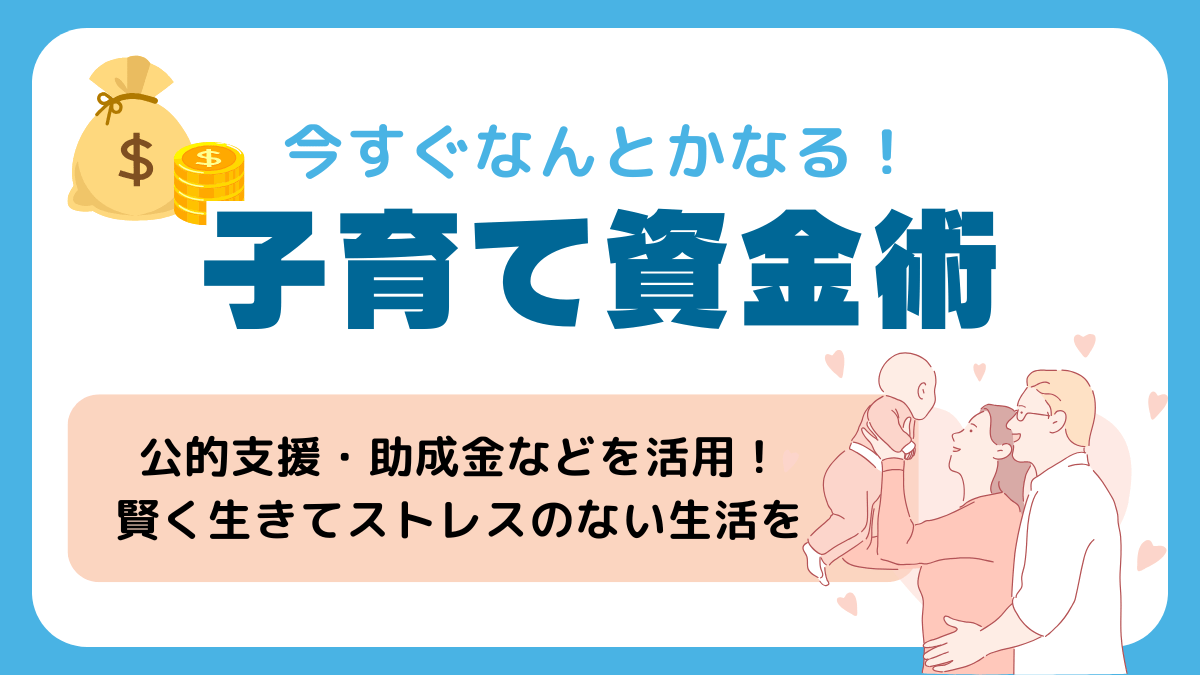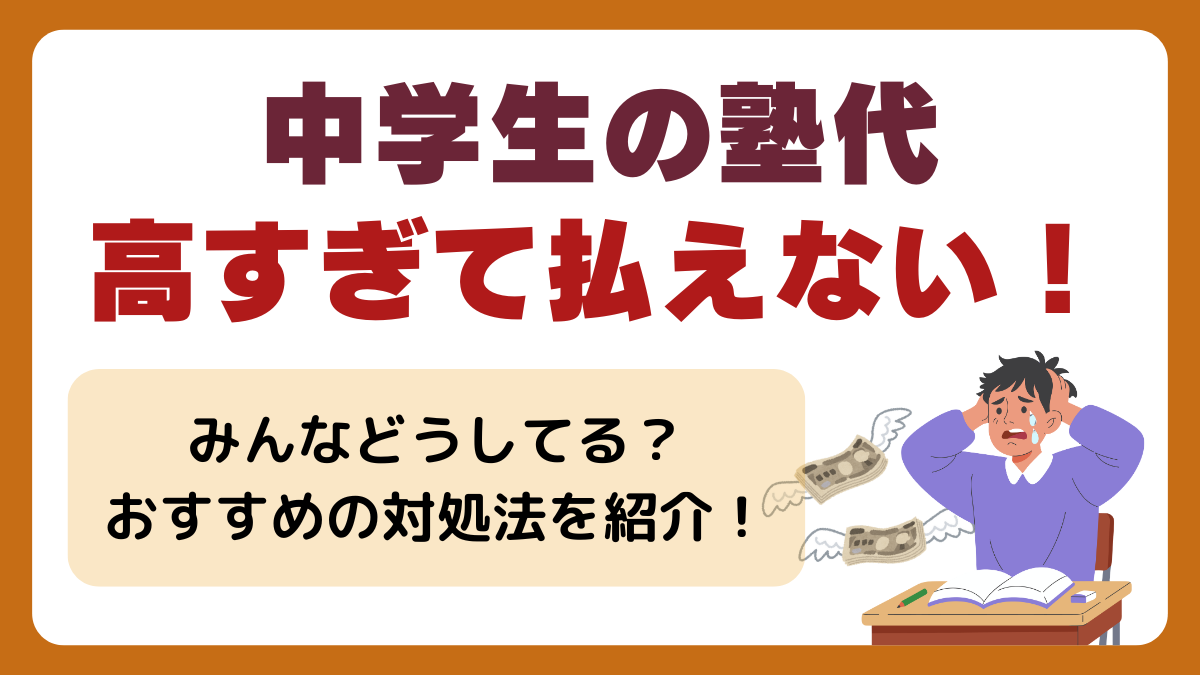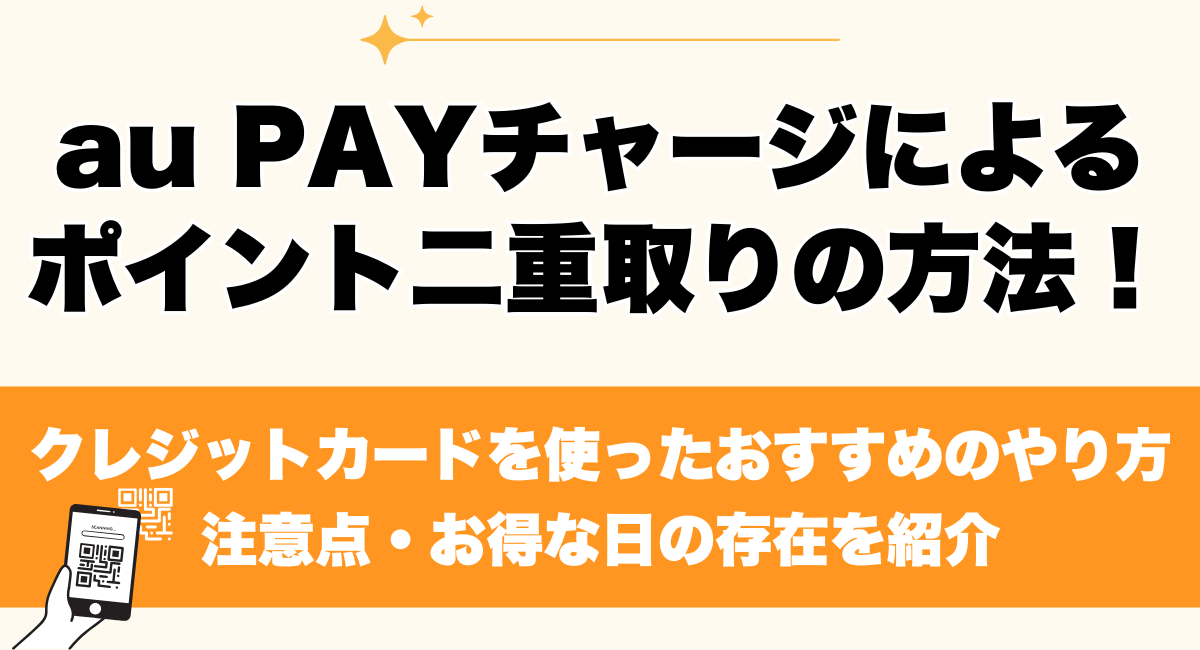物価が上がる一方で賃金はなかなか上がらない昨今、どのご家庭でも家計はますます厳しくなっています。そんな中、少しでも持続可能な暮らしを送るために効率的な節約術への関心はますます高まっています。この記事では、筆者の家庭(夫婦二人、子どもなし)で行っている工夫もあわせて、今日から実践しやすい節約方法をご紹介していきましょう。
目次
節約に取り組む際の心得
「なかなかうまく節約ができない」という方のために、まず節約に取り組む上で、心得ておいてほしいことがあります。
心得①無理をしない
最初に心得ておくのは、決して無理をせず、お金を使ってはいけないという固定観念を持たないことです。過度な我慢や忍耐によってストレスをためると節約は長続きしません。
無理せず節約するためには、以下のことを念頭に入れておきましょう。
- 自分なりに続けられる方法を考える
- お金は必要に応じて積極的に使う
- お金をかけたい部分は上限を設定し、それ以外は節約の対象にする
人生で一番大事にすべきことは自分や家族とその生き方であり、お金はあくまでもそのための手段に過ぎません。節約を生活の目的にして無理をしないようにしてください。
心得②簡単・便利の逆を行く

節約で大事なのは多少の不便を厭わず「簡単・便利」の逆を行くことです。具体的な取り組みとしては以下のような例があります。
- 原則定価のコンビニより、値引きが多いスーパーを
- 有料のコンビニATMより手数料無料のメインバンクを
- クレジットカードは持たないか1枚だけに
大事なのは、日々の何気ない便利さに流されて余計な出費をしない心構えを持つことです。特に、コンビニには不用意に立ち寄らない、近づかないことを習慣づけましょう。
心得③周囲に流されない
自分の軸や価値観を持ち、周囲に流されないことも節約には必要です。
「みんなが持っているから」「周りがやっているから」というだけで物やサービスに安易に飛びつかず、それが本当に自分にとって必要なのかを見極めましょう。そうすれば
- 最新型のスマホを購入する
- テレビで紹介しているイベント・催事に目的もなく行ってしまう
- 行く必要のない飲み会に行ってしまう
- 家にストックがあるのに特売だからといって何となく買ってしまう
などといった、不要な出費を避けることができます。
今日からできる節約術の準備

では、本格的な節約に取りかかる前に始めるべき準備について説明していきましょう。
家計を把握する
まず最初に家計の把握を行います。1か月にどのくらいの出費があるか、食費、光熱費、住宅費、通信費などを項目別にノートに書き出してください。
市販の家計簿や書き込み式の目録ノートなどを使う人もいますが、自分が書きやすく使いやすい、自由に書けるノートのほうが長続きしやすいと思います。
家計簿アプリやエクセルなどで収支管理をしている人も、数字や金銭感覚をよりリアルに感じるようにするために、できるだけ手書きノートとの併用をおすすめします。
口座は入金/支払い用の2つを用意する
次に、入金と支払い用の2つの銀行口座を用意します。それぞれ
- 使ってはいけないお金=入金専用口座
- 使っても良いお金=支払い専用口座
を決めて明確に分け、支払い専用口座からは家賃・住宅費/光熱費/通信費/保険などの固定費を支払うようにしておきましょう。
筆者の家の場合、上の2つとは別に、衣料品や日用品、外出など不定期な出費に使う口座、旅行・外食用など複数の口座を設け、それぞれに一定額を積み立てています。
入金専用口座は、身近に支店や提携ATMがない地方銀行や証券会社にあえて口座を作ることもひとつの手です。わざと不便にすることで、安易にお金を引き出せる機会を減らせます。
給与や入金の分配を行う

次に給料・収入の分配を行います。まず最初に貯金する金額を決めて入金専用口座に入れてしまいましょう。ただしここでも無理な貯蓄額の設定はしないでください。
そのあとで残りのお金を用途ごとに振り分け、支払い専用口座に移します。
一例として筆者の家で行っている分配方法をご紹介しましょう。
- 給料の全額(千円単位以下は下ろさず貯金)を一度現金で引き出す
- 家賃/固定費/食費/医療・衛生費/携帯電話料金/日用品費/緊急費/おこづかいに分配
- それぞれ封筒に入れて管理する
- 家賃、固定費や携帯電話料金、日用品費は支払い専用口座に入金する
一見不便で面倒ですが、お金を単なる数字ではなく、現物として量的に把握することは有効なやり方と言えます。
ここまで準備ができたら、いよいよ各項目ごとに節約に取り組んでいきましょう。
今日からできる節約術!食費編

毎日の生活で最も重要なのは食事です。食費を節約するには自炊を基本として、外食やコンビニ弁当などを極力減らしましょう。
食費はまず月ごとの予算を割り振って、米や調味料などに使うお金を差し引き、残りを週ごとに分配します。分配した週ごとの予算だけを財布に入れておけば、無駄な買い物を防げます。
食費①まとめ買いと作り置きをする
節約が上手な方の多くが実践しているのが、まとめ買いと作り置きです。
肉類や野菜は小分けやバラ売りの方が便利ですが、トータルで見ると高くつきます。キロ単位で売られている徳用の肉や、まとめて袋詰めされている野菜の方が、単価やグラム換算では安くなります。こうした点を踏まえて
- 安売りになっている肉や野菜をまとめ買いし冷凍して保管
- 米はまとめて炊き、冷めたら冷凍する
- 1週間、1か月で使い切れるように冷蔵庫や冷凍庫の中を整頓する
- 買い置きのストック食材を使いこなす
- 缶詰や乾物など常温で保存が効く食材を活用する
などの工夫を行うことで、4人家族でも1か月分の食費を2万円台に収めている方も少なくありません。
食費②使い切ることを習慣づける

ただ、①の方法には高い計画性と整理整頓スキルが求められ、ハードルが高いと感じる方もいるでしょう。そうしたやり方が苦手な人は無理にまとめ買いをしようとせず、食材を使い切ることを最優先にしてください。
そのためには
- 定番レシピを代替品で作れるようにする
- 重宝する丼レシピを増やす
など、今ある食材を活用できるメニューを増やすことを考えましょう。
たくさんの食材を管理できる自信がない人は、たとえ割引や特売でまとめ買いをしても食材を無駄にしてしまい、結局損をすることになります。決して無理をせず、必要なものを必要な分だけ買う方が、多少割高にはなっても長い目で見れば節約につながります。
食費③自宅居酒屋や家庭菜園でお得に
外食を控えることも重要な節約術ですが、やり過ぎるとストレスにもなります。
そうしたストレスを軽減するために、自宅居酒屋や自宅寿司屋などをやってみるのもいいでしょう。例えば
- 普段のおかずをおつまみ風にして小皿で何品も出す
- 刺身をサクで買い、酢飯を作って握り寿司に挑戦する
- ホームベーカリーで自作のパンを作ってみる
など、楽しみながら食費を節約できる方法はいくらでもあります。
コロナ禍で注目された家庭菜園もおすすめです。ベランダでトマトやハーブを栽培する、カイワレや豆苗の根を水に浸けて育てる、市民農園に申し込んで野菜作りに挑戦するなど、自分で食材を増やすことを楽しむのも立派な節約術です。
今日からできる節約術!固定費編

家計の中で占める割合が大きい固定費は削るのが難しい分野ですが、その分思い切って見直せば効果が大きく、毎月固定的に出て行くため管理しなくても大丈夫な費目でもあります。
住居費
固定費の中で最も金額が多いのが住宅費です。
月収20万円前後の単身者(子どもなし)を想定した場合、収入の総額に占める住居費の適正割合は28%、子供が2人いる場合でも25%程度が目安とされています。
このように実家暮らしや高収入なケースを除き、多くの人は住居費に最もお金を使っていますが、面倒な手続きや交渉、不便さを厭わなければ住居費も大幅に削減することが可能です。
持ち家の場合
戸建や分譲マンションなどすでに持ち家がある方、あるいは購入を考えている方は、
- ローン開始5年以内に住宅ローンの繰り上げ返済を始める
- 月々の返済金額を引き下げることも考慮
- 15年以上前の固定金利型住宅ローンは借り換えを要検討
など、さまざまな制度を利用することを考えましょう。
⒈の場合、同じ額を繰り上げ返済するのでも、開始から3年後と7年後とでは、前者の方が大幅に返済総額を減らせる可能性があります。
逆に、給与が上がらない、手取りが減るなど家計が厳しくなり、住居費が適正割合を上回る場合は、⒉の返済金額引き下げを選ばざるを得ないでしょう。
⒊の固定金利型住宅ローンの借り換えの場合、発生する手数料に注意しましょう。完済間近や借り換え前後の金利差が0.8%以下になる場合はおすすめできません。
住宅ローンは政策や市場の動向が影響してきます。最新の情報を常にチェックして検討していくようにしましょう。
賃貸の場合
賃貸の場合も、以下のように条件や住む地域・エリアを見直すことで大きく支出を減らすことができます。
- 住民に優しい地域を選んで引っ越す
- 家賃相場の安い地域を選ぶ
- 独身の場合はルームシェアという選択肢も
- 公営住宅・公団などを利用する
自治体によっては、健康保険や子育て政策への補助金が出ることも少なくありません。直接住宅費を減らさなくても、諸手当による収入増や医療費の削減につながります。
また、都心から離れた街、急行が止まらない駅や駅から少し離れた物件などは、一般的に家賃相場が安くなります。
水道光熱費

水道光熱費も工夫次第で効果的に節約できます。ただしこれも人によって向き不向きがありますので、できる範囲で無理のないやり方を心がけましょう。
まず一度だけの頑張りで済む方法としては、
- 契約のアンペア数を下げる
- 太陽光発電を導入する
- 電力会社・ガス会社の契約を変えてみる
- シャワーに節水シャワーヘッドをつける
- エコ家電に買い換える
などがあります。
日常の細かな気配りが苦にならない方であれば、
- 長時間使用しない家電は電源を切る、コンセントを抜く
- 水道の蛇口をこまめに閉める
- 浴槽のお湯を上手に使う:髪や身体を洗う、洗濯に使うなど
- 追い炊きの回数を減らす:家族ができるだけ同じ時間帯で入浴する
などの方法も有効です。
また、エアコンを使う時には断熱や空気の流れを意識し、温度を下げ過ぎ/上げ過ぎずに節電につながる方法も意識しましょう。
保険料
まさかの時に備えて加入する保険も、不安からつい高い保険料を払ってしまいがちです。
医療保険や生命保険は自分や家族のために必要な場合もありますが、現在の日本では高額療養費制度があるため、高額な医療保険は必ずしも必要とは限りません。割安な都民共済・県民共済でカバーするなど、掛金が高い保険については慎重に検討することが大事です。
通信費
インターネットが生活インフラとして欠かせない現代では、通信費、特にスマートフォンの料金について敏感になっている方も多いでしょう。携帯電話料金の節約方法としては
- 家庭や職場・公共のフリーWi-Fiを活用する(セキュリティには注意)
- 料金プラン、特に不要なデータプランは見直す
- 格安SIMに切り替える
- 子供のおこづかいに必要最低限の携帯代を上乗せし、自分で管理させる
などのような、ちょっとした工夫で大幅な削減が可能になります。
今日からできる節約術!趣味・娯楽費編

節約といっても、趣味や娯楽をあきらめる必要はありません。むしろ生活の満足度を上げ、生きがいを持つために趣味や娯楽は欠かせないものです。とはいえ使えるお金も有限なので、満足度を高めるための工夫もまた必要です。
趣味にかける予算を決める
節約しながら趣味を楽しむには、使う予算の上限を設けましょう。欲しい物はリスト化して必要かどうか定期的に検討する、最も安く買える所を探す、ネットオークションや中古で購入できるかどうかを調べるなど、節約の余地は十分にあります。
とはいえ、あまり削り過ぎては楽しめるものも楽しくありません。物・事の数や回数を増やすより、数を絞って十分お金をかけることも、満足度を上げる有効なやり方です。
お金のかからない娯楽を探す
節約が上手な人は、お金をかけずに楽しむ方法をよく知っています。
特に最近では、技術の進化によってコストをかけずに始められる趣味が増えています。
- 読書…図書館を活用
- ウォーキング・ジョギング
- 写真…デジタルカメラ1台で始められ、スマホでも綺麗な写真が手軽に撮れる
- 囲碁・将棋…アプリでオンライン対戦もできる
- 絵画…紙と鉛筆、スマホやタブレットのアプリなどでも始められる
- 映画鑑賞…動画配信サービスが充実
などは、今日から始められて初期投資の少ない趣味と言えるでしょう。
この他、フリーライブや無料のイベントも全国各地で盛んに行われています。こうした催しものに足を運ぶことも、お金をかけずに楽しめる秘訣です。
今日からできる節約術!その他

その他にも、日常生活で出費を見直すことができる余地はまだまだあります。
車の維持費を考え直す
日常的に車を使っている人にとって、車と維持費は馬鹿にできない出費です。
特に都市部に住んでいる人は、車を所有することが本当に必要か考えてもいいかもしれません。もし生活に支障がないのならば、
- 徒歩・自転車や公共交通機関を使うなど、できるだけ車を使わない
- レンタカーやカーリースなどを利用する
などの方法を検討してみるのもひとつの方法です。
ただし、車がないと生活に困る地方ではそうはいきません。車をフルに活用しながら維持費を節約するためには
- 会員割引やセルフ式スタンドを使ってガソリン代を節約
- 近所の整備工場やカー用品店などを利用してメンテナンス費用を抑える
- 燃費の良い車や電気自動車(EV)などに買い替えて税負担を抑える
などの方法があります。特にEVは、自治体の補助だけでなく年間の維持費の面でもガソリン車に比べ相当有利です。環境面でも経済面でも有望な選択肢と言えるでしょう。
中古・アウトレットを活用する
ネットオークションやフリマアプリ、リサイクルショップなどを活用し、中古品を上手に手に入れるのも有効な手段です。
最近は中古品を扱う店のレベルも上がり、出費額の大きいパソコンやスマートフォン、家電、家具などはもとより、状態の良い衣料品やバッグなども手に入りやすくなっています。
物の状態をしっかり見極め、賢い買い物をしていきましょう。
やってはいけない節約術
節約をする上でやってはいけない方法もあります。そこを間違えると、生活にも、健康にもさまざまなデメリットとなってしまいます。
安い物ばかりを買う
昔から「安物買いの銭失い」というように、ただ安いだけの物を買うのは、かえって無駄づかいとなります。値段の安い物は品質が低くて耐久性にも劣る物が多いため、短期間ですぐダメになり、無駄な出費となるからです。
買い物は値段だけでなく、
- 長く使える品質の良い物か
- 修理やメンテナンスができる商品か
- 本当に必要なものか
という視点から選びましょう。買った時は高くても、長く大切に使うことで結果的にコストを抑えられることになります。
健康を疎かにしてしまう
一番やってはならないことは、節約を最優先にするあまり自分の健康を損なうことです。
食費や光熱費を削り過ぎるがあまりやってしまいがちなのが、
- 安く手に入りがちな炭水化物に偏った食生活
- 冷暖房を我慢して使わない
など、栄養不足や体の不調につながるような生活を送ってしまうことです。
偏食による必須栄養素の偏りや不足は、免疫力の低下や生活習慣病のリスクを高めます。冷暖房費を削り過ぎれば、冬なら冷えを、夏なら熱中症を引き起こし、体調不良の原因となりかねません。結果的に将来的な医療費負担が増え、身体を壊した上にかえって損をすることになってしまうのです。
節約とSDGs

無駄を減らし、適切にお金を使う正しい節約術は、SDGs(持続可能な開発目標)を目指す上で多くの気づきを与えてくれます。具体的に関係する目標としては
- 目標1.貧困をなくそう
- 目標3.すべての人に健康と福祉を
- 目標12.つくる責任 使う責任
の3つがあります。
節約の目的は将来に備えて安定した資産を形作ること、健康な心身と充実した生活を送ることにあります。持続可能な生産消費のサイクルを自分の生活の中に確立することで、安全で自然や開発と調和したライフスタイルをすべての人が送れるようになるのです。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ

節約は、多くの家庭における重要な関心事です。しっかりした考え方に基づき、自分に合った適切な節約をすることで、生活や健康に支障をきたすことなく、大きな成果をあげることができます。最後に改めて強調すると、人生において主役となるべきなのは、お金ではなく自分自身の生き方です。これからも持続可能な生活を楽しむために、お金に振り回されない知恵と工夫を身につけ、上手な節約を始めましょう。
参考文献・資料
心も生活も整理されて輝く!貯金・節約のすすめ / 横山光昭著. — ぱる出版, 2011.
正しい家計管理 : 将来への不安が消える、自動的にお金が貯まる / 林総著. – 新版. – すみれ書房, 2022.
無理しない【節約】のきほん!お金が貯まる21の習慣 | キナリノ
毎日できる節約術15選!楽しんで節約するコツやメリットも解説|マネーキャリア
一番節約できるものとは?やってはいけない節約もあわせて紹介! – コツコツCD | 株式会社CDエナジーダイレクト
一番節約できるもの8選!やってはいけない節約やすぐできる節約方法も紹介|マネーキャリア
電気自動車(EV)の維持費は年間いくら? ガソリン車と比較して安いの?|東京電力エナジーパートナー
車の維持費が馬鹿らしい!高すぎる!年間月々のコスト削減方法|クルカ
中古スマホ販売台数は272.8万台で、5年連続過去最高 ≪ プレスリリース | 株式会社MM総研
大人がハマる!お金のかからない趣味20選と人生を豊かにするアイデアアイデア|しゃべりおbase
この記事を書いた人
shishido ライター
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。