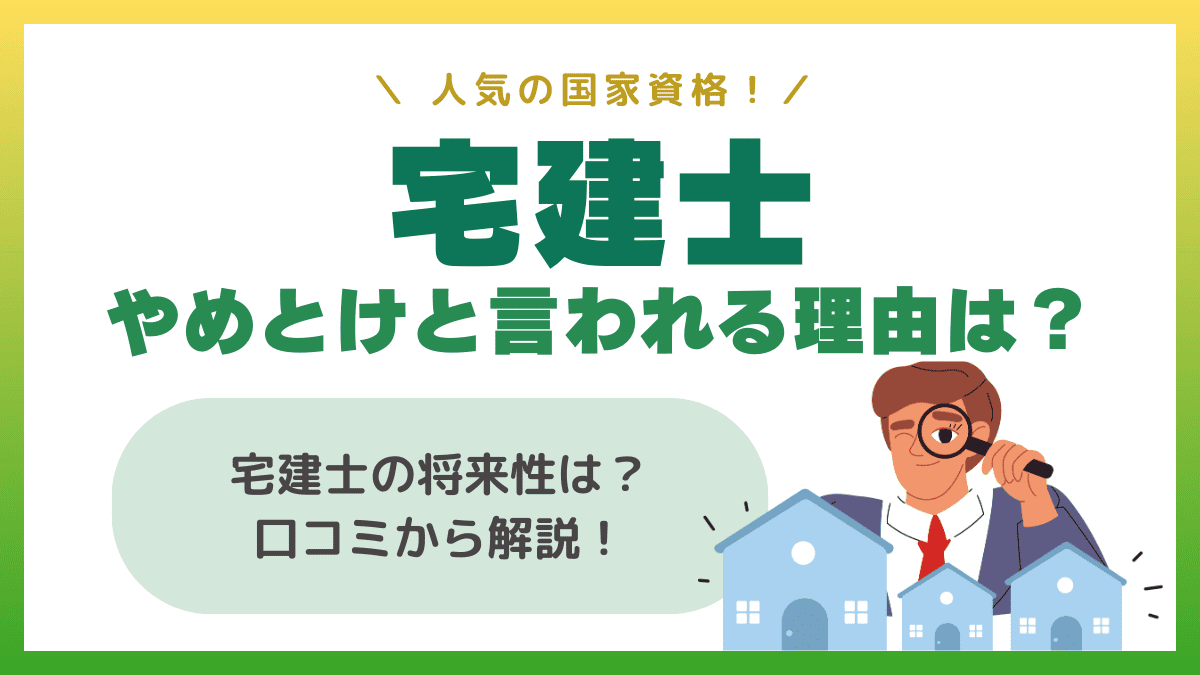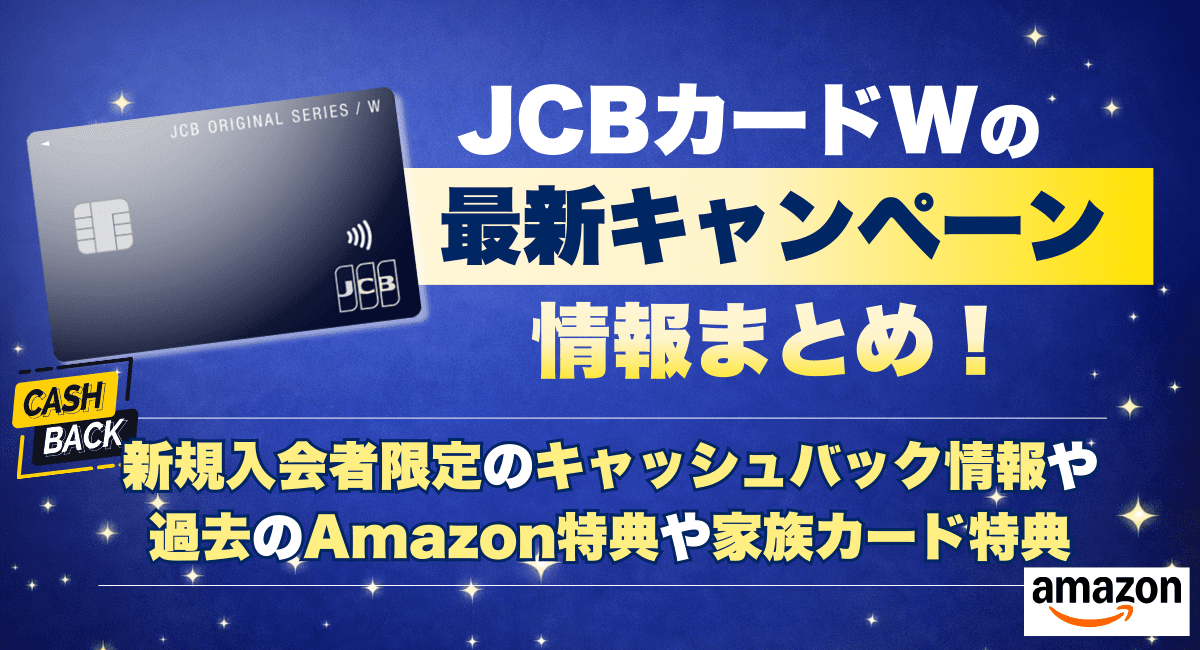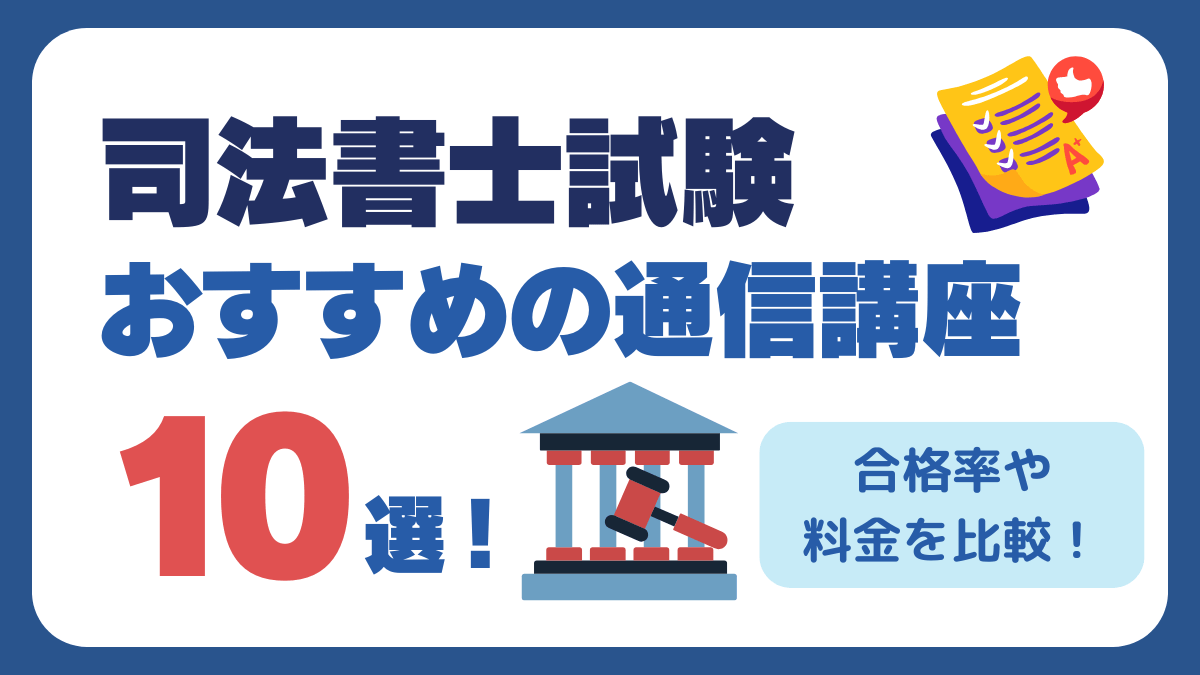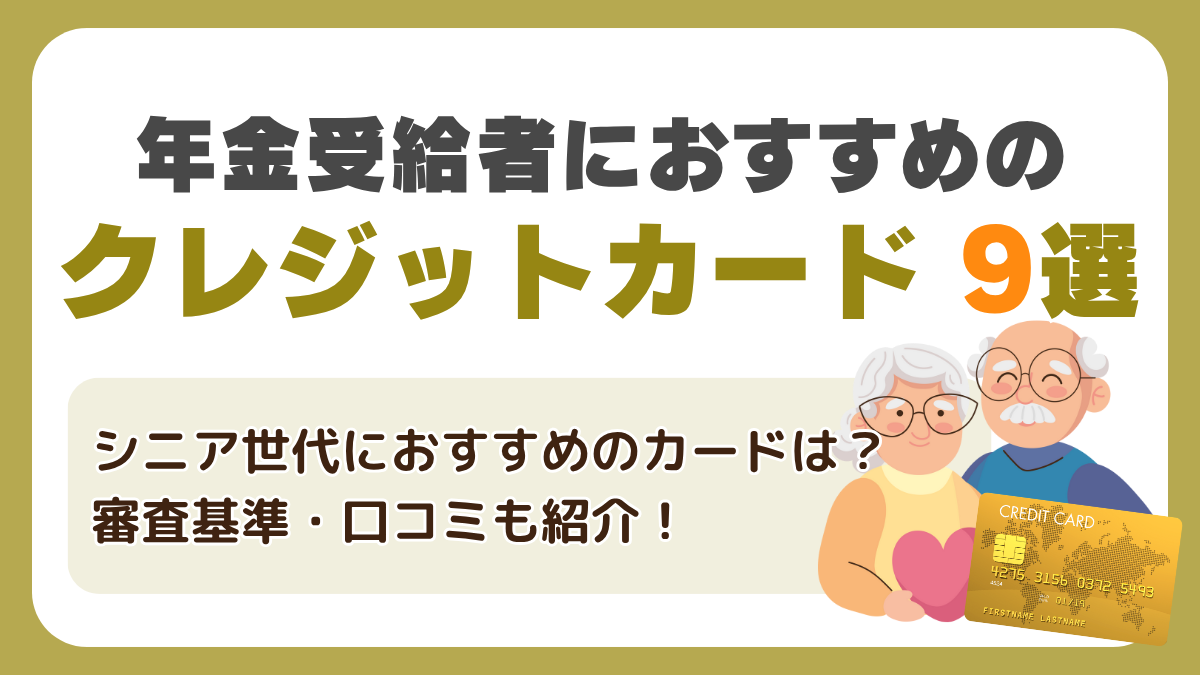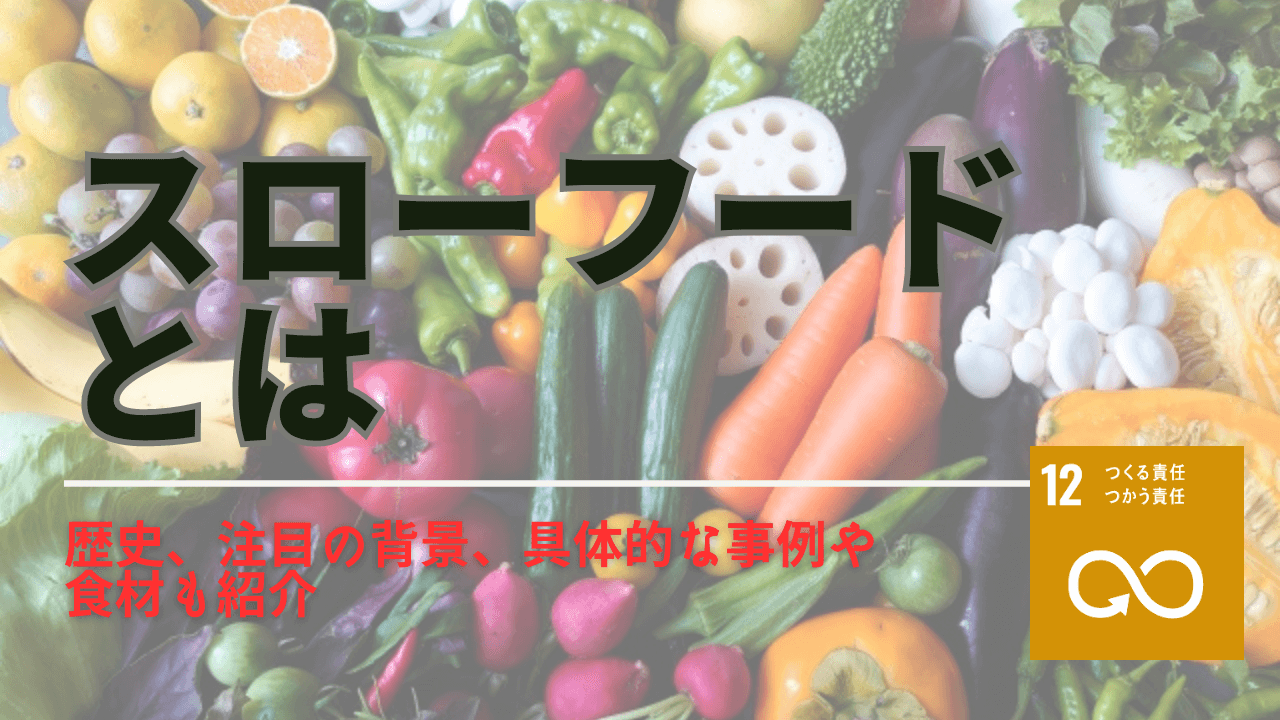
イタリアで誕生し、近年世界的に注目を集めるようになった「スローフード」。食に対する考え方のひとつですが、なんとなく聞いたことはあるけどよく分からない、そう思っている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、スローフードとは何か?ということから、スローフードの歴史、取り組みについて説明します。具体的な食品やメリット・デメリットについても紹介しますので、生活に取り入れるヒントにしてみてください。
目次
スローフードとは
スローフードとは、食べる人、作る人、環境、生態系、すべてを大切にする食生活を目指した活動です。現在、様々なテーマのもと160か国以上で活動の輪が広がっており、世界的な草の根運動となっています。
場合によっては、この活動と関係する食品を指すこともありますが、一般的には「食に向き合う活動」がスローフードであるため、本記事では主に取り組みにスポットを当てて説明していきます。
スローガンのスローガン「おいしい・きれい・ただしい」
スローフードの活動は、
- GOOD(おいしい):食べておいしく、健康的であること
- CLEAN(きれい):生態系・環境に負荷を与えないこと
- FAIR(ただしい):生産から販売・消費まですべての関係者の社会的公正を尊重すること
の3つをスローガンに掲げています。
おいしく健康的であることに加えて、その料理が出来上がって食べ終わるまでの背景にも考えを巡らせることがスローフードの考え方です。
スローライフのなかの一部
スローフードは、スローライフの概念のなかのひとつです。スローライフとは、時間に追われずにゆっくりと人生を楽しもうというライフスタイルのことです。例えば、効率重視の忙しい都会生活から離れ、田舎に移住してゆったり自分らしく生活することなどが挙げられます。
近年では個々のライフスタイルにとどまらず、まちづくりや教育、市町村の経営まで、地域活性化のひとつの選択肢としても注目されているのがスローライフで、スローフードもその中のひとつと言えるでしょう。
食のサステナビリティへの関心が高まったことで、より盛り上がりを見せる
スローフードが盛り上がりを見せる背景には、サステナビリティへの関心の高まりがあります。サステナビリティとは日本語で「持続可能性」を指し、これまでの地球に負荷をかける生活からの脱却を目指しています。
現在、食が抱える課題として、例えば
- 魚の乱獲による漁獲量減少
- 農薬の大量消費による土壌・水質汚染
- これらに伴う生態系の破壊
などが挙げられます。また、食べることに関してはフードロス問題もあります。多くの人がこれらの問題の解決を目指すようになり、スローフードへの注目も高まっているのです。
スローフードの歴史
続いては、スローフードがいつ誕生し、どのように広がったのか、歴史をみてみましょう。
1986年カルロ・ペトリーニによって提唱されたのが始まり
1986年、ローマのスペイン階段にマクドナルドがオープンしました。大量生産されるファストフードは伝統的な食を脅かすものとし、大きな反対運動が起こります。この反対運動に加わっていたカルロ・ペトリーニにより、地域食材を用いた伝統的で多様な料理を楽しむスローフードが提唱されました。1989年にはスローフードマニュフェストが調印され、国際的な運動として認められています。
ファストフードの代表格ともいえるマクドナルドは、1940年にマクドナルド兄弟によって創設され、その手軽さから第二次世界大戦後に急速に広がっていきました。画一的な味付けは先進的で魅力的な一方、土着の食生活を脅かすものとして、日本進出時にも反対運動が起こっています。
「早い・安い・便利」なファストフードは大量生産により作られ、原材料や加工において不自然・不明瞭な部分が多く、人体に悪影響があるのではないかと現在でも議論されています。また、高カロリーで脂質が多く、食べ続けると健康を害するとの指摘もあります。
ヨーロッパでの「スローチーズ」キャンペーン
その後、スローフードの考えはヨーロッパに広まりました。1997年にはヨーロッパの食生活に欠かせないチーズに特化したイベントがブラで開催されました。2001年には、生乳から作られるチーズを守るためのマニフェストが作成され、「スローチーズ」キャンペーンが始動。(このイベントは以後も隔年で行われ、最近では2019年にも開催されています。)
チーズ職人による伝統的な製法を学ぶワークショップや、ディナーイベントなどが行なわれ、ブラの街全体が賑わいました。
テーマとしている「生乳から作られるチーズ」は現在、生産数が少なくなっています。市場の多くを占めるのが、高温殺菌したミルクに大手企業が培養した菌を加えて作るチーズです。本来、ミルクをとる動物の種類、育った環境、えさ、などの違いによってチーズに多様性が生まれます。しかし、上記理由により画一的になってきていることを憂慮しています。
テッラ・マードレ開催
2004年、130の国から5,000人のスローフード会員、小規模生産者、食分野の学者や活動家が一堂に会し、会議を行う「テッラ・マードレ」がトリノで開催されました。(以後も定期的に開催。)
「サローネ・デル・グスト」(味の見本市)も同時に開催され、世界各地の食品を実際に食べてみることができます。
日本には2000年頃から考え方が広まる
日本では、2000年に「スローフードな人生!―イタリアの食卓から始まる」(島村菜津著、新潮社、2000)という書籍でイタリアのスローフードが紹介されたことから関心が集まるようになりました。
2004年には仙台でスローフードジャパン(スローフード日本の前身)が発足。同年、横浜にて初のスローフードフェアも開催され、日本においてもその考え方が盛り上がりを見せています。
2016年にSlow Food Nipponが設立

そして2016年に、スローフードジャパンがSlow Food Nippon(日本スローフード協会)と名前を変え設立されました。以後、この運動は日本各地に広がり、現在は日本国内に約20のネットワーク団体があります。
スローフードの主なテーマ
ここまで読んで、スローフードの考え方は分かったものの、結局何をすればいいのかわからない方もいると思います。
結論から言うと、食に関する様々なテーマに沿って、自分には何ができるかを考え、食べ物をよく選び、それを多くの人に広めることが主な活動と言えるでしょう。これを実践するためにも、まずはスローフードが掲げるテーマを知る必要があります。
ここでは、スローフード日本にて取り上げられている主なテーマを紹介します。
気候変動
1つ目が気候変動への対応です。気候変動は、地球温暖化によって引き起こされると指摘されており、主な原因が温室効果ガスです。現在、世界中で排出されている温室効果ガスの4分の1近くが、
- 集約的な畜産業(家畜の腸内発酵によるメタンガス)
- 作物への広範囲にわたる農薬、化学肥料の使用
- 旬に関係なく作付される作物
- 必要以上に距離のある輸送
などの、食糧生産由来のものとなっているのです。
また、気候変動によって影響を受けやすいのは生産者(特に小規模の生産者)です。干ばつや洪水などの異常気象により作物がうまく育たなくなったり、海の酸性化により魚の生態系が変わったりと、思うように収穫が見込めなくなってしまいます。
生物多様性
スローフードは、活動当初から生物多様性を軸に据えています。
現在の農業・畜産業は品種を絞って効率化されています。世界の食品生産の60%は小麦・米・トウモロコシの3つの穀物からなっていますが、特定の品種に集中しています。また、かつては数千種類もの米の品種があった中国やインドでも画一化が進行するなど、多様性が失われつつあります。品種の多様性が失われると、将来、気候変動や疫病などによってその種類が生産できなくなった際に、食糧危機を招く可能性があるのです。
加えて、スローフードには地域に根ざした食材を食文化とともに継承する、文化の多様性を守る側面もあります。伝統野菜や在来種を守ることで、
- それらを使った伝統的な料理も継承される
- 地産地消になり街の活性化にも役立つ
とされています。
フードロス
FAO(国連食糧農業機関)によると、生産された食品のうち年間およそ3分の1(約13億トン)が廃棄されている一方で、約8憶4千万人(世界の人口の12%)が飢餓に苦しんでいるとしています。
フードロス(食品ロス)は、途上国では収穫時や保管において多く発生し、先進国ではスーパーやレストラン、家庭などで発生しており、持続可能な食を実現するためには、解決しなければならない問題のひとつです。
種とGMO(遺伝子組み換え食品)
スローフードは、遺伝子組み換え作物(GMO)の商業的作付けに反対の立場を示しており、遺伝子組み換えでない食品・飼料の作付けの促進に取り組んでいます。
- 遺伝子組み換え作物は少数の企業の特許商品であるため、生産者と消費者の権利を奪う危険性を持っている
- 遺伝子組み換え作物に関して環境面・健康面においてどのような影響があるか明らかになっていない
など、社会的な影響も大きく、小規模農家や伝統的な食文化を脅かす可能性があります。
スローフードトラベル
スローフードでは、スローフードに触れ合う旅も提案しています。具体的には、旅行者は地域の文化に触れ、食についてより深く考えるためのきっかけとなり、地域の人がホストとなるような旅行形態です。
民泊のマッチングサービスAirbnbや体験のプラットフォームサービスainiと連携し、日本国内だけでなく世界各地での体験が企画されています。
ユースネットワーク
ユースネットワークは、大学生などの若年層によるネットワークです。日本でも「World Disco Soup Day」(ディスコ・スープ)というイベントが開催されています。これは、規格外野菜を使ったスープを提供し、音楽とともに楽しくおいしく食べることを目的としたプロジェクトで、若年層への啓発が期待されています。
先住民族と食
スローフードでは、生態系バランスを崩さずに持続可能な暮らしを続けている先住民族に着目し、「先住民族テッラマードレ」というネットワークを形成しました。定期的に国際会議を開催し、先住民族の叡智を広く紹介することを目的としています。
日本からは、アイヌ民族と琉球民族が参加。食をきっかけに先住民族を知ることで、良い変化をもたらすことが期待されています。
アフリカ10,000の菜園
アフリカに菜園を作るプロジェクトで、当初は1,000を目標としていましたが達成したため、10,000に設定し直して再スタートしました。現在はアフリカの36カ国で約2,600の菜園を作っています。
菜園を作ることには、以下のような役割があります。
- 地元の種や生物多様性を守ること
- 教育の場
- 自給率の向上
- 次世代リーダーの育成
家族農業
スローフードは家族経営による小規模農業も推進しています。家族農業には以下のような役割があります。
- 多種多様な種を育てることによる生物多様性の保存
- 食料安全保障の確保
- 飢餓撲滅
- 農業知識の維持
- 自然資源の管理・維持
- 雇用の創出
国連においても、2019年〜2028年は「家族農業の10年」とされ、食料安全保障確保と貧困・飢餓撲滅に大きな役割を果たす家族農業を推進する動きとなっています。
スローフィッシュ
FAO(国連食糧農業機関)の統計によると、人口が増えるに伴って魚類の消費量も増え、90年と比べて、
- 天然の魚類の漁獲高は14%増加
- 養殖の生産量は528%増加
となっています。その一方で、生物学的にみた持続可能な漁業資源割合は、1974年は90%から2017年は65.8%と減少しています。また、総生産量の35%は廃棄されています。
スローフードでは、漁業においても、小規模漁業が海洋生態系を守っていると考えています。この取り組みをスローフィッシュと呼び、
- 職人の技術や軽視されている魚種を守る
- 廃棄される魚を減らす
など、持続可能な漁業を目標としています。
ここまでスローフードのテーマについて見てきました。スローフードは、これらのテーマに沿って、食について見つめ直す活動となります。では、具体的にどのような取り組みがあるのかを次では見ていきましょう。
スローフードの取り組み事例
ここでは、世界と日本のスローフードの取り組み事例を紹介します。
【世界】味の箱舟
味の箱舟(ARK OF TASTE 、通称アルカ)は、地域の伝統的な加工食品や在来品種など、このままでは消滅してしまう可能性のある食材を世界共通のガイドラインに沿って選定し、生産・消費を守ろうとする取り組みです。現在、全世界で6,000件近く、日本からは約70の食品が登録されています。
登録基準は以下のようになっており、フォームから誰でも推薦することができます。
- 地域の自然や人々の生活と深く結びついている。
- 小さな作り手による限られた生産量である。
- 現在、あるいは将来的に、消滅の危機に瀕している。
- 遺伝子組み換えが、生産段階において一切関与していない。
- トレードマークや商業的ブランド名がついてない。 *ただし、商標の取得については、特別なパテントを得ていたりしなければ、問題はない。
味の箱舟の中で、特に消滅の危機にある食品をサポートする「プレシディオ」という取り組みもあります。これは食材を保護するために、生産して食べていくというサイクルを積極的に回していこうというプロジェクトです。世界ではコーヒー、チョコレート、オリーブオイルなどが対象となり、スローフード・プレシディオのラベルをつけて販売されています。
※2022年12月時点では、日本にプレシディオ対象の食材はありません。
【日本】かたつむりの会
日本では、かたつむりの会というコミュニティがあり、以下のような活動があります。
- オンライン講座の開催(かたつむりアカデミー)
- ニュース配信
- 会員限定オンライングループでの交流
- スローフード詰め合わせBOXのプレゼント
オンライン講座は月に1度行なわれており、日本や世界の食に関する最新情報、課題解決の先端事例などをテーマとしています。11月に行なわれた講座では「秋田のいぶりがっこはどうやって守っていけるのか?」をテーマに、改正された食品衛生法にも触れています。
身近なテーマからスローフードへの理解がより深まり、他のメンバーとの交流では無理のない実践方法を学ぶことができるでしょう。
日本におけるスローフード食材
スローフードに取り組みたいとなった際、どのような食材を使えばいいのかわからない人も多いと思います。そこで、ここでは味の箱舟に登録されている食材をいくつか紹介します。
ニホンミツバチとそのハチミツ

ニホンミツバチとそのハチミツは、本州と周辺諸島の標高1,000m以下の森や里山、都市部の公園などが生産地として登録されています。ニホンミツバチによる養蜂の最古の記録は「日本書紀」とされ、江戸時代には本格的に養蜂が行なわれるようになったとされています。
明治期にセイヨウミツバチが導入され絶滅が危惧されるものの、したたかに生き残ってきました。しかし、高度経済成長期にはニホンミツバチのすみかや蜜源となる森が切り開かれ、畑で使われる農薬の影響もあり、数が減っています。
近年では、ニホンミツバチの減少を危惧し「銀座ミツバチプロジェクト」のような高層ビルの屋上で養蜂をするという新たな取り組みも行なわれるようになりました。
味に関しては、セイヨウミツバチのハチミツは花の香りを残し甘みが後を引くのに対し、ニホンミツバチのハチミツは熟成香とコクがあり、切れの良いまろやかな味わいがあります。
阿波晩茶(あわばんちゃ)
阿波晩茶は、徳島県の上勝町・那賀町にて作られている、乳酸菌で発酵させた伝統的なお茶で、空海が伝えたと言われています。
自生しているヤマチャの葉を夏に収穫し、釜茹でして揉み、樽で10日〜3週間ほど漬け込みます。その後、天日干しで乾燥させて完成です。最近の研究によると、阿波晩茶には30種類近くの乳酸菌が含まれており、
- 血糖値を抑える
- 整腸作用
- 抗アレルギー・花粉症対策
ような効果があると、徳島大学福井教授や他の研究者により紹介されています。
ほのかな酸味と甘みがありフルーティーで、他のお茶とは全く異なる味わいです。漬け込み期間の差で生産者ごとに味が変わるのも魅力のひとつです。
生産者の高齢化が進んでおり、若い世代への継承が期待されています。
雪菜
雪菜は、山形県米沢市(旧上長井地区)、遠山町、古志田町、 笹野町で作られている野菜です。8月下旬から9月上旬にかけて種をまき、11月下旬に一旦根がついた状態で抜き取り、別の場所に寄せて(床寄せ)雪を待ちます。雪の中で成長し花茎(とう)立ちしたものを収穫し、湯通しして塩だけで漬け込むと「ふすべ漬け」になります。
米沢地方の方言で湯通しすることを「ふすべる」と言います。雪菜は「ふすべる」と辛味がありシャキシャキとした歯触りになります。
収穫には雪を掘り起こす必要があり、床寄せした雪菜は収穫時には3分の1から4分の1に減ってしまい、労力がかかる一方で収量の少ない効率の悪い野菜です。地区内では自家用として栽培する家庭が多くありますが、作業の大変さや「ふすべ漬け」のレシピを習得できないなどから、若年層には敬遠されています。こういった背景により、販売用の作付面積も年々減っています。
スローフードの活動の一環として、このような食材を口にしたり、これらの食文化を残すためには何をすれば良いかを考えてみてはいかがでしょうか。
スローフードに取り組むメリット
では、スローフードに取り組むことによって私たちはどのようなメリットが得られるのでしょうか。
健康によい
伝統的で質の良い食生活を取り入れることは、余分な化学物質や添加物を使用していないとも言えます。そのため、私たちの体にとって無理がなく、健康面で大きなメリットがあります。また、生産者の様子が想像でき、精神面でも豊かな気持ちで食に向き合うことができるでしょう。
環境にやさしい
スローフードは、持続可能な方法で作られている食材であることが重要です。
具体的には、
- 化学肥料を大量に使用していない
- 生態系を破壊するような大規模な土地開発を行わない
などが挙げられ、環境にも無理がなく、小規模生産者を守ることにも繋がります。
スローフードに取り組むデメリット
メリットが多くあるスローフードですが、デメリットもあります。
時間がかかる
ファストフードの対極に位置するスローフードですが、その名の通り、時間をかけて作られるものが多いことが特徴です。機械に頼らずに人の手で作物を生産する傾向があるため、手間がかかります。また、調理する際にも伝統的な調理法を採用すれば、時間と手間がかかることは覚悟しなければなりません。
また、季節に沿って作られるので、手に入る時期が決まっているものもあります。食べたい時にすぐ食べられるファストフードとは異なり、季節の移り変わりを楽しめると考えてみてはいかがでしょうか。
コストがかかる
時間と手間がかかるということは、大量生産には向いていないこということを意味し、購入する場合は必然的に価格も高くなります。すべての食生活をスロ-フードにするにはかなりの金額がかかってしまうため、無理のない範囲で少しずつ始めてみるのが良いでしょう。
スローフードとSDGsの関係
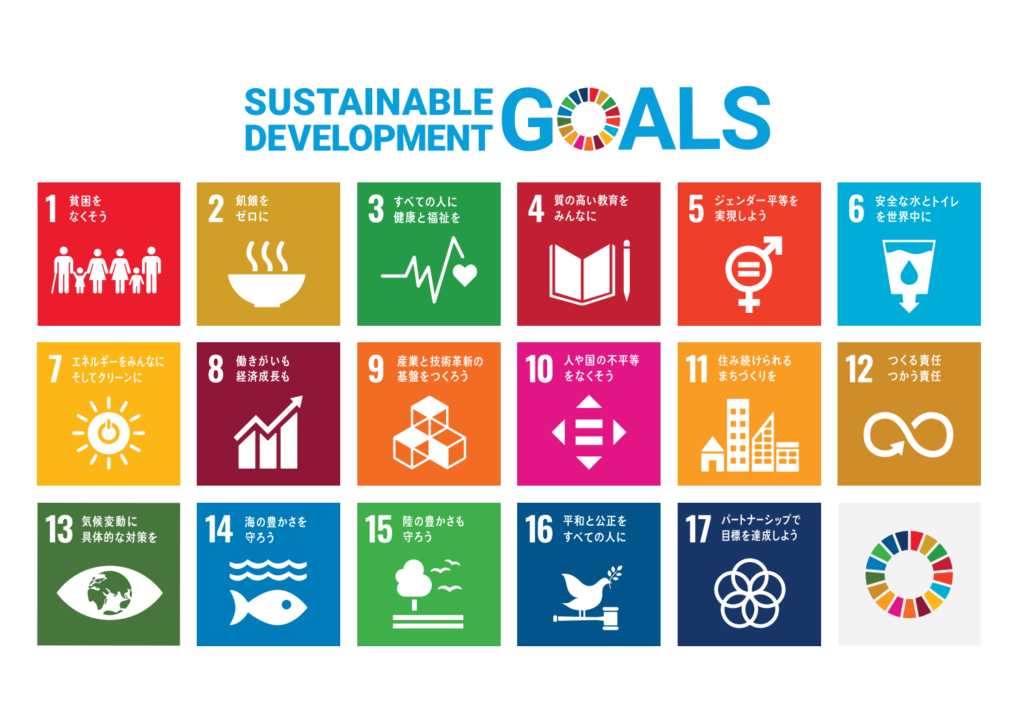
最後に、スローフードとSDGsとの関係について確認します。スローフードを生活に取り入れることは、SDGsの達成にも繋がります。
特にSDGs目標12「つくる責任つかう責任」と関係
目標12「つくる責任つかう責任」は、これまでの経済・消費体系を見直し、循環型社会の実現を目指した内容です。
- フードロスの削減
- 環境・生産者・消費者に配慮した食のサイクルの確立
- 気候変動への対応
など、「スローフードが目指す社会」と「目標12が目指す社会」はほとんど一致していると言えるでしょう。
まとめ
この記事では、スローフードについて詳しく見てきました。
スローフードは、近年注目を集めるサステナビリティにもつながる大事な活動です。メリット・デメリットを見極め、自身の気になるテーマから、無理のない範囲で取り組んでみてはいかがでしょうか。
参考文献
日本スローフード協会
2019年のCheese@イタリア、ブラの開催概要が公開されました
変革へのレシピ 〜より良い未来を食卓へ〜 | 日本スローフード協会
https://www.slowfood.com/about_us/jap/03.html
NPO スローライフ・ジャパン
#生物多様性 | 日本スローフード協会
スローフード、30周年 | Q&A 生物多様性と私たち | The MIDORI Press
飢餓の撲滅 | World Food Programme
食料の無駄は、気候、水、土地や生物多様性に危害を与える | FAO駐日連絡事務所
#食料廃棄問題 | 日本スローフード協会
#種とGMO | 日本スローフード協会
スローフード・トラベル
スローフードユースネットワーク東京 (@SFYN_Tokyo) / Twitter
#ユースネットワーク | 日本スローフード協会
先住民族と食 | 日本スローフード協会
アフリカ10,000の菜園 | 日本スローフード協会
#家族農業 | 日本スローフード協会
国連「家族農業の10年」(2019-2028):農林水産省
#スローフィッシュ | 日本スローフード協会
SEAFOODLEGACY TIMES » Blog Archive FAO『世界漁業・養殖業白書2020』にみる世界の水産動向
プレシディオ | 日本スローフード協会
かたつむりの会(個人会員) | 日本スローフード協会
特定非営利活動法人銀座ミツバチプロジェクト | GINZA OFFICIAL
ニホンミツバチとそのハチミツ | 日本スローフード協会
阿波晩茶 | 日本スローフード協会
上勝町の阿波晩茶 〜「我が家の味」は重要無形民族文化財〜|Slow Food Nippon|note
雪菜 | 日本スローフード協会
SDGsってなんだろう?
この記事を書いた人
スペースシップアース編集部 ライター
スペースシップアース編集部です!
スペースシップアース編集部です!