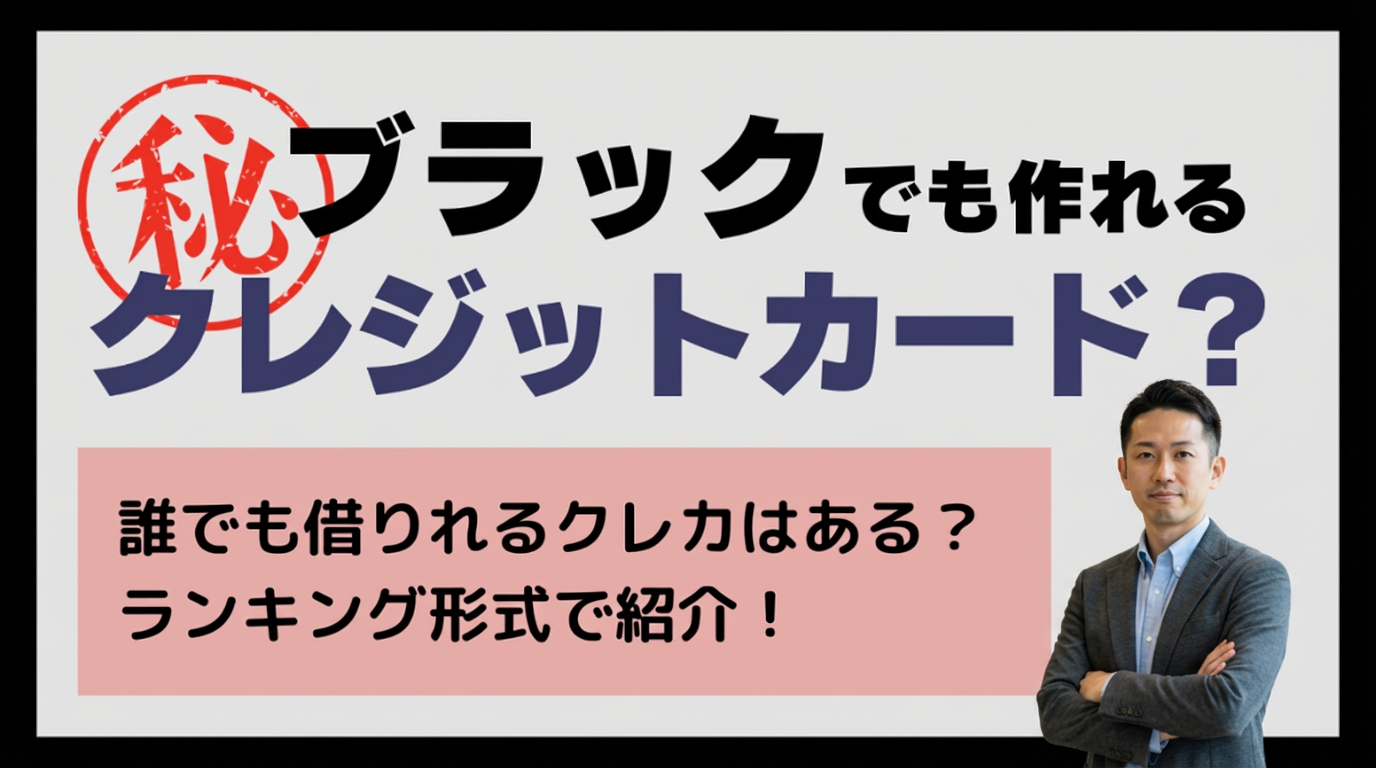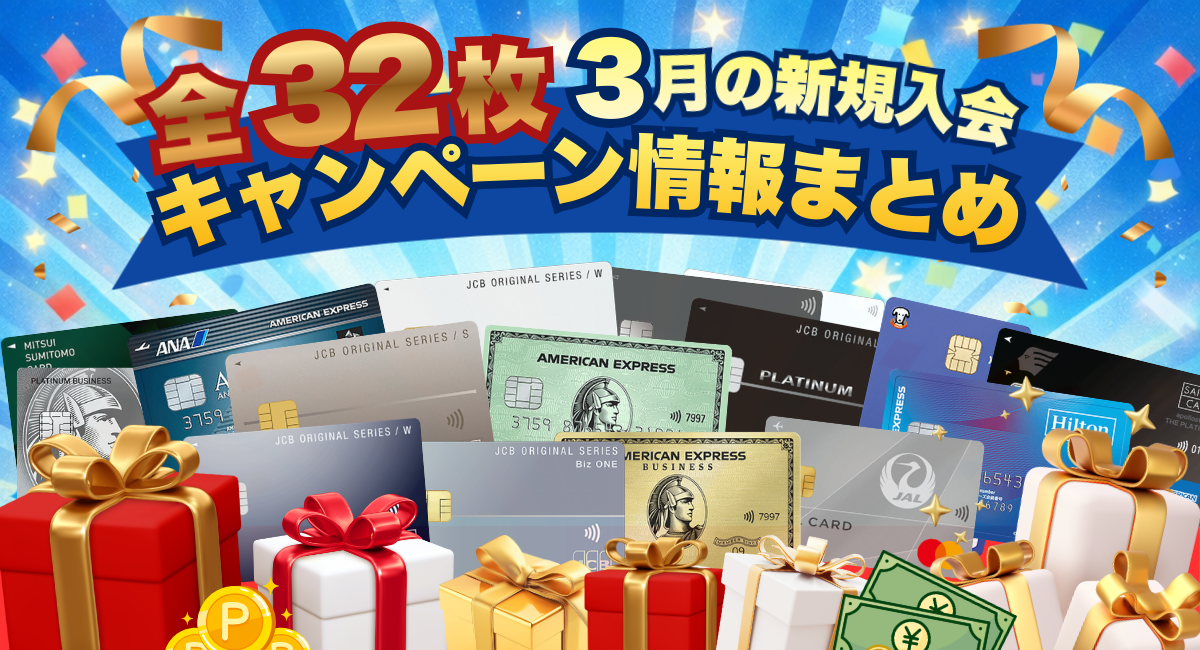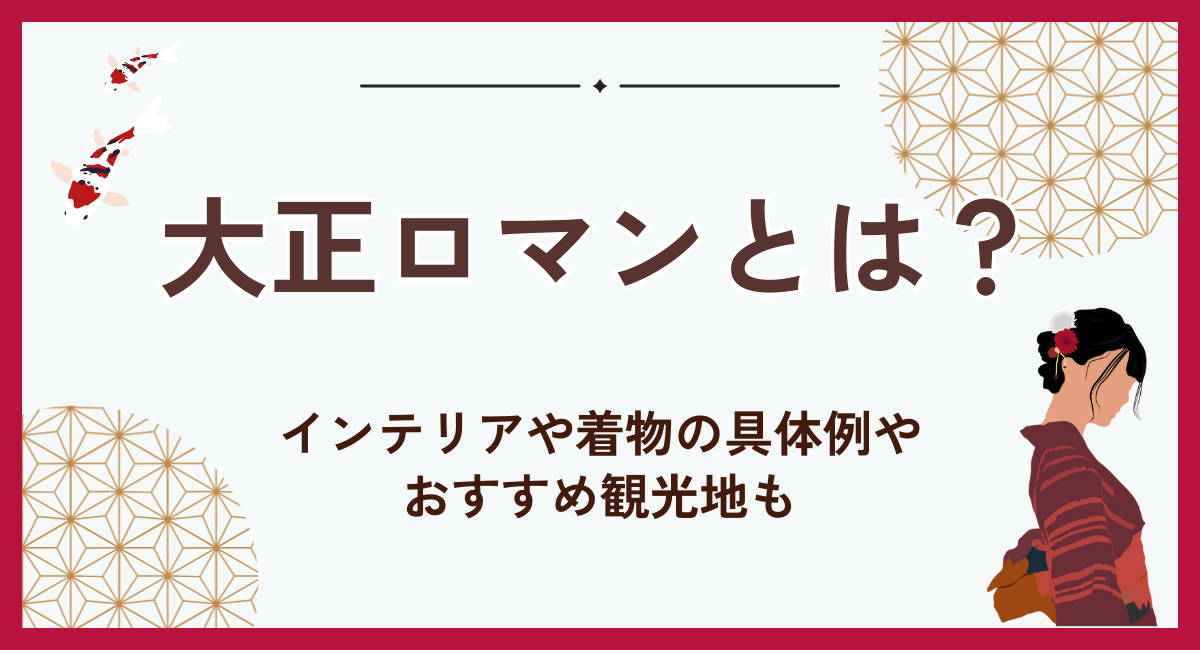
「大正ロマン」という言葉から、どのようなことを連想するでしょうか。大正ロマンは、西洋文化の影響を受けながらも、日本の伝統的な美意識と融合した、独特の美意識によって生み出されたものです。
和洋折衷ともいえる大正ロマンは、現代に生きる私たちから見ても、懐かしさを感じつつ斬新さも味わえるという点で非常に貴重なものです。
今回は、大正時代の世相に触れつつ、建築やインテリア、ファッション、芸術作品などを通じて、大正ロマンの魅力をわかりやすく解説します。さらに、大正ロマンを肌で感じることができる観光スポットも紹介します。
目次
大正ロマンとは

大正ロマンとは、大正時代(1912年~1926年)に花開いた独特の文化や社会現象を指す言葉で、「大正浪漫」と表記されることもあります。西洋文化の流入が加速する一方で、日本の伝統的な美意識も見直され、和洋折衷の文化が花開きました。
文学や芸術、建築など様々な分野で、西洋の様式を取り入れながらも日本独自の感性を生かした表現が生まれました。
自由で華やかな雰囲気を持つ大正ロマンは、モダンガールに代表される新しい女性像や、大正デモクラシーと呼ばれる自由主義的な社会運動など、時代を象徴するキーワードとともに語られます。
ノスタルジックでロマンチックなその魅力は、現代の文化や芸術にも影響を与え続けています。
大正モダンとの違い
大正ロマンと大正モダンは、どちらも大正時代のキーワードですが、そのニュアンスは異なります。大正ロマンは、西洋文化が流入する中で生まれた、日本の伝統的な美意識と西洋の文化が融合したロマンチックで感傷的な雰囲気を指すことが多く見られます。
一方、大正モダンは、西洋の新しい思想や文化を取り入れ、都市を中心に生まれた先進的で革新的なライフスタイルや文化を指します。
しかし、両者は完全に区別できるものではなく、互いに影響し合い、大正時代という時代を形作る上で重要な役割を果たしました。大正ロマンは、古き良き時代の情緒的な美しさを、大正モダンは新しい時代の洗練されたスタイルをそれぞれ表していると言えるでしょう。
大正時代はどのような時代だったのか

大正時代(1912-1926)は、日本が近代化を遂げ、民主主義的な動きが活発化した時代でした。第一次世界大戦後の好景気により経済が発展し、都市化が進むとともに、新しい文化や生活様式が生まれました。ここでは、大正時代の特徴を紹介します。
大正デモクラシーが活発化した
大正デモクラシーは、大正時代(1912年~1926年)に広がった民主主義的な動きのことです。それまでの日本は、一部の有力者だけが政治を動かす藩閥政治でした。しかし、この時期になると、一般の人々も政治に参加したいという声が大きくなってきました。*1)
きっかけとなったのは、日本国内で会社員などの中間層が増えてきたことです。特に都市部で教育を受けた人々を中心に、「政治は国民のためにあるべきだ」という考えが広まりました。
東京帝国大学の先生だった吉野作造は、「民本主義」という考え方を提唱しました。これは、天皇を国家の元首として認めながらも、実際の政治は国民の意見を大切にすべきだという考え方です。*2)
この運動の成果として、1925年には25歳以上の男性全員に選挙権が与えられる普通選挙法が実現しました。*3)また、政党が政治の中心となる政党内閣制も進みました。ただし、同年に制定された治安維持法によって自由な思想が制限され、次第に軍国主義の時代へと向かっていきました。*4)
「成金」が登場した
第一次世界大戦期の大正時代において、「成金」と呼ばれる新興富裕層が社会現象として出現しました。これは主に、戦争による特需で急激に富を築いた人々を指します。第一次世界大戦により、日本からヨーロッパへの物資供給が急増し、特に軍需産業や海運業が空前の好景気を迎えました。*5)
その結果、株式投資や商品投機によって短期間で莫大な富を得る人々が現れ、「株成金」「鉄成金」などと呼ばれました。この呼称は、将棋で歩が相手陣地に入ると金に成ることに由来するとされています。
成金たちは派手な消費生活で注目を集め、社会の話題となりましたが、その富は必ずしも永続的なものではありませんでした。1920年の戦後恐慌により、多くの成金が没落し、彼らの華やかな生活も一時の夢と消えていきました。
関東大震災が起きた
1923年(大正12年)9月1日、相模湾北西部を震源とするマグニチュード7.9の地震である関東大震災が発生しました。これにより、東京や横浜を中心とする関東一帯に甚大な被害を受けました。
地震による直接的な被害に加え、各地で発生した火災により、被害は更に拡大しました。死者・行方不明者は14万人以上に達し、全被災者は約340万人とされています。特に東京・横浜では、地震後の火災により市街地の大部分が焼失しました。
この災害の際、「朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだ」などの根拠のない流言が広まり、多くの在日朝鮮人が虐殺される痛ましい事件も発生しました。そして、この震災を契機として、都市計画や防災対策の見直しが進められることとなりました。
社会の変化により大衆文化が発達した
大正時代には、工業化の進展により都市部で会社勤めのサラリーマンが増加し、新たな消費者層として注目されるようになりました。また、電話やラジオなどの近代的な通信手段が普及し、情報伝達が迅速化したことで、人々の生活様式が大きく変化しました。
さらに、三越をはじめとする百貨店が次々と登場し、ショーウィンドウでの商品展示や季節ごとのセールなど、新しい商業文化を生み出しました。このような社会の変化により、都市部を中心に映画や演劇、カフェなどの娯楽が発展し、大衆文化が花開いていったのです。
女性の社会進出が進んだ
大正時代は、日本の女性の社会進出が本格的に始まった時期として重要な意味を持っています。第一次世界大戦による好景気を背景に、都市部を中心として女性の職業の選択肢が大きく広がりました。
教員、看護婦、女医といった専門職に加えて、事務員、タイピスト、電話交換手、美容師、デパートの店員など、新しい職種に女性が進出していきました。特に、都市部のオフィスで働く職業婦人は「モダンガール」*6)と呼ばれ、新しい時代の象徴となりました。
また、第一次世界大戦による産業の発展に伴い、工場労働者としての女性の需要も増加しました。しかし、大正時代に制定された普通選挙法で選挙権が与えられたのは25歳以上の男性であり、女性には与えられませんでした。
このように、依然として多くの制約や差別は残されており、完全な男女平等までの道のりはまだ遠い状況だったのです。
大正ロマンの具体例

大正時代は、明治時代の近代化の流れを受け継ぎながらも、より自由で華やかな文化が花開いた時代でした。西洋文化と日本の伝統が融合し、独特の美意識「大正ロマン」が生まれ、インテリアやファッション、食文化、芸術など、暮らしのあらゆる場面に表れました。
ここからは、それらの例を紹介していきます。
インテリア

大正ロマンの特徴の一つは、和洋折衷の独特のスタイルです。大正ロマンインテリアが見られる場所として有名なのが、鳩山会館です。鳩山会館は、総理大臣を務めた鳩山一郎が1924年に建てた私邸です。*7)
ダークブラウンを基調とし、ステンドグラスなどを用いた内装は大正ロマンを代表するインテリアといってよいでしょう。
ファッション
大正時代は、和装と洋装が混在していた時代であり、こちらも和洋折衷の時代でした。特徴的なこととしては、女性の洋装が目立つようになったことです。

男性もスーツが一般化するなど、現代に近い服装になってきました。
食生活の変化
大正時代に入ると、洋食が普及し始めました。主なものは以下の通りです。
- とんかつ
- コロッケ
- カレーライス
- オムライス

とんかつは、明治時代に日本に伝わったフランス料理の「コートレッツ」を起源とする料理です。日本人の舌に合うように、調理法を工夫して現在に至ります。*8)コロッケもフランス料理のクロケットをルーツとする料理で、大正時代に本格的に流行しました。*9)
また、カレーライスが家庭の味として普及したのもこのころです。*10)加えて、オムライスが本格的に提供されるようになったのも大正時代で、大正14年(1925年)に現在の北極星のメニューとして登場しました。
大正時代の洋食は、外国の料理をそのまま取り入れるのではなく、日本人の好みに合わせて改良したもので、今日の日本料理の形成に大きな影響を与えました。
絵画
大正ロマンを代表する画家として知られているのが竹久夢二です。夢二の美人画は非常に特徴的で「夢二式美人」とよばれ一世を風靡しました。
竹久夢二「饗宴」

大正ロマンを感じられる観光地3選

現代でも、大正ロマンを感じられる観光地がいくつかあります。今回は、日本大正村、鳩山会館、銀山温泉の3つを紹介します。
日本大正村
日本大正村は、岐阜県恵那市明智町に位置する文化テーマパークです。大正時代の雰囲気を今に伝える街並みが、旧明智町全体に広がっています。明智町の元町役場を活用した「大正村役場」や、当時の路地を忠実に再現した「大正路地」、さらに旧校舎を改装した「絵画館」など、往時の建築物を巧みに活用した施設が点在しています。*12)
大正時代の建物や生活様式を保存・展示することで、その時代の文化や風情を体験できる貴重な観光スポットとなっています。着物レンタルや昔懐かしい駄菓子屋など、大正ロマンを五感で味わえる様々な体験メニューも人気を集めています。
鳩山会館
インテリアの章でも紹介しましたが、東京都文京区にある鳩山会館は、第52~54代内閣総理大臣を務めた鳩山一郎が1924年に建てた私邸です。建築家の岡田信一郎が設計を手掛けた鉄筋コンクリート造りの洋館で、アダムスタイルの応接室やイギリス風の外観が特徴です。
館内各所には小川三知による鳩をモチーフにしたステンドグラスが装飾され、現存する貴重な作品として高く評価されています。庭園は英国風に整備され、90種160株もの薔薇が植えられており、開花時期には幻想的な景観を演出しています。*7)
銀山温泉
山形県尾花沢市に位置する銀山温泉は、江戸時代に銀鉱脈が発見されたことをきっかけに発展した歴史ある温泉地です。大正時代の洪水後に再建された木造3〜4階建ての旅館群が、銀山川の両岸に立ち並ぶ独特な景観が特徴です。
建物には屋根付き玄関や塔屋、鏝絵などの装飾が施され、大正ロマンの雰囲気を今に伝えています。夜になると街路のガス灯が情緒豊かな光を放ち、特に冬季は雪景色と温泉情緒が見事に調和し、多くの観光客を魅了しています。
映画やドラマのロケ地としても使用され、日本の伝統的な温泉街の雰囲気を色濃く残す観光地として国内外から注目を集めています。
大正ロマンとSDGs
大正時代には、伝統的な日本文化と西洋文化が融合した独特の和洋折衷文化が花開きました。明るく開放的な社会の雰囲気を背景に、それまで家庭内での役割が中心だった女性たちが、積極的に社会へ進出していったことは、この時代を象徴する大きな変化でした。
このような女性の社会進出という観点から、大正ロマンとSDGsの結びつきについて見ていきましょう。
SDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」との関わり
大正時代には、伝統的な日本文化と西洋文化が融合した独特の和洋折衷文化が花開き、女性の社会進出が進展しました。「職業婦人」という言葉が生まれ、教師や看護師、事務員として働く女性が増加し、平塚らいてうなど、女性解放運動の先駆者たちが活躍しました。
この時代の女性の社会進出は、現代のSDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」の理念と部分的に重なります。
大正時代の進歩的で開放的な社会の雰囲気は、ジェンダー平等という現代的な課題に通じる先進性を持っていたと言えるでしょう。
まとめ
今回は、大正ロマンについて解説しました。大正時代(1912年~1926年)は、西洋文化の影響を受けながらも日本の伝統的な美意識と融合した独特の文化が花開いた時期でした。
大正デモクラシーの高まりや、第一次世界大戦後の好景気による「成金」の出現、女性の社会進出など、社会の大きな変革期でもありました。
この時代を象徴する大正ロマンは、インテリアや着物、建築、食文化など様々な分野で和洋折衷の特徴を見せ、現代でも日本大正村や鳩山会館、銀山温泉などの観光地で、その雰囲気を体験することができます。
さらに、女性の社会進出という観点では、現代のSDGsにも通じる先進性を持っていたといえます。
参考
*1)デジタル大辞泉「大正デモクラシー」
*2)デジタル大辞泉「民本主義」
*3)日本大百科全書(ニッポニカ)「普通選挙法」
*4)デジタル大辞泉「治安維持法」
*5)日本大百科全書(ニッポニカ)「成金」
*6)デジタル大辞泉「モダンガール」
*7)鳩山会館「鳩山会館を知る」
*8)政府広報オンライン「和製洋食「とんかつ」のルーツを探る」
*9)日本コロッケ協会「コロッケの歴史」
*10)ハウス食品「日本のカレー カレーが国民食になるまでの歩み」
*11)北極星「オムライスの誕生までの由来」
*12)日本大正村「日本大正村」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。