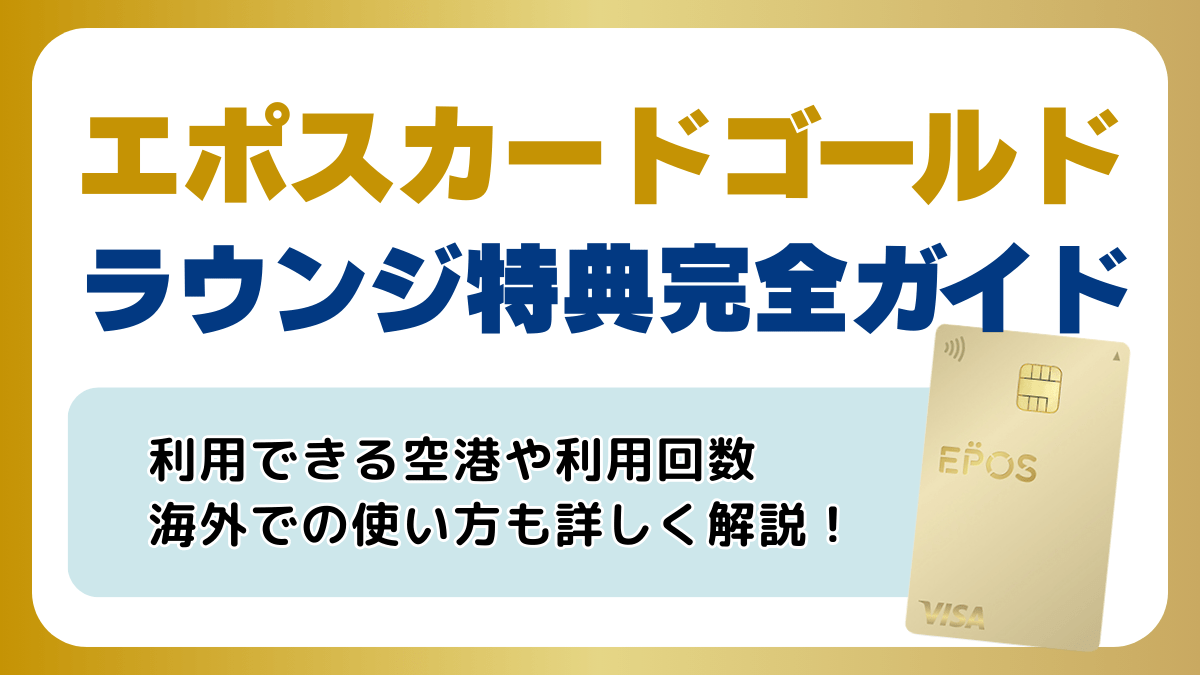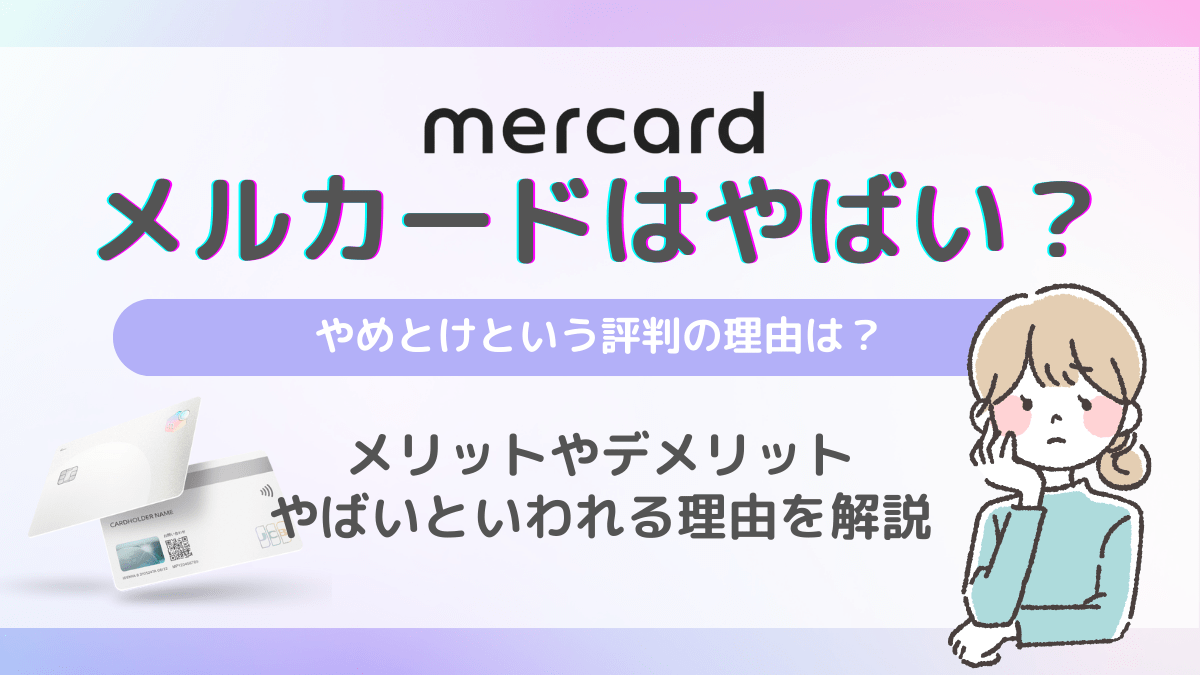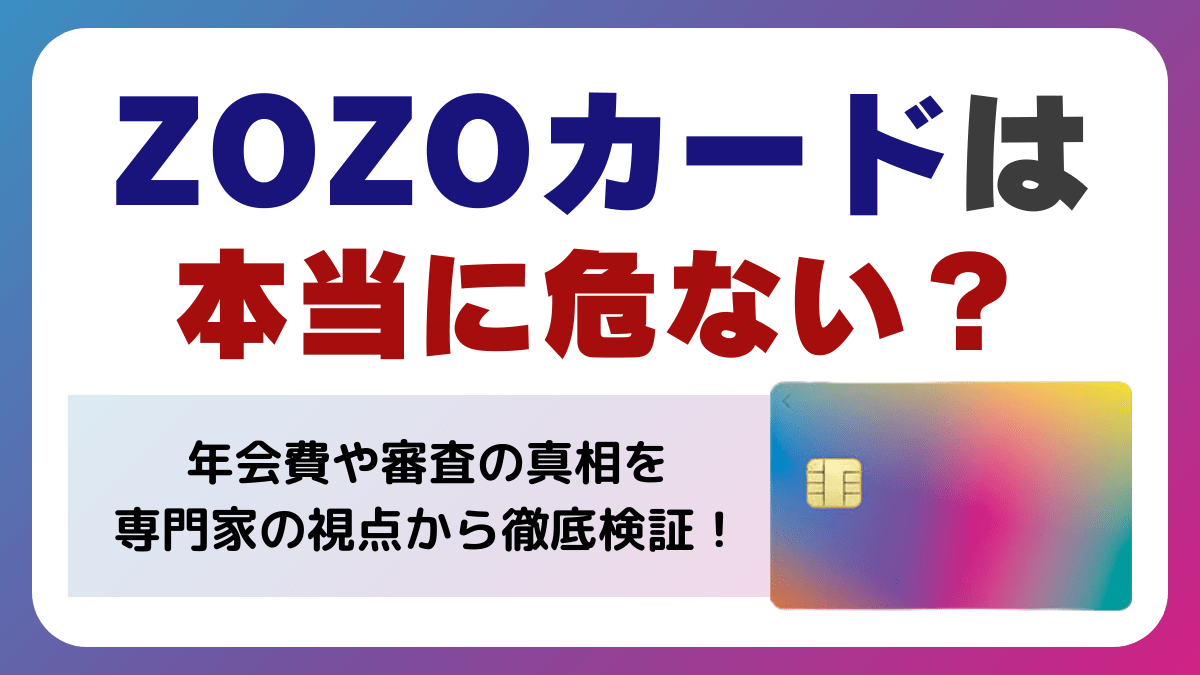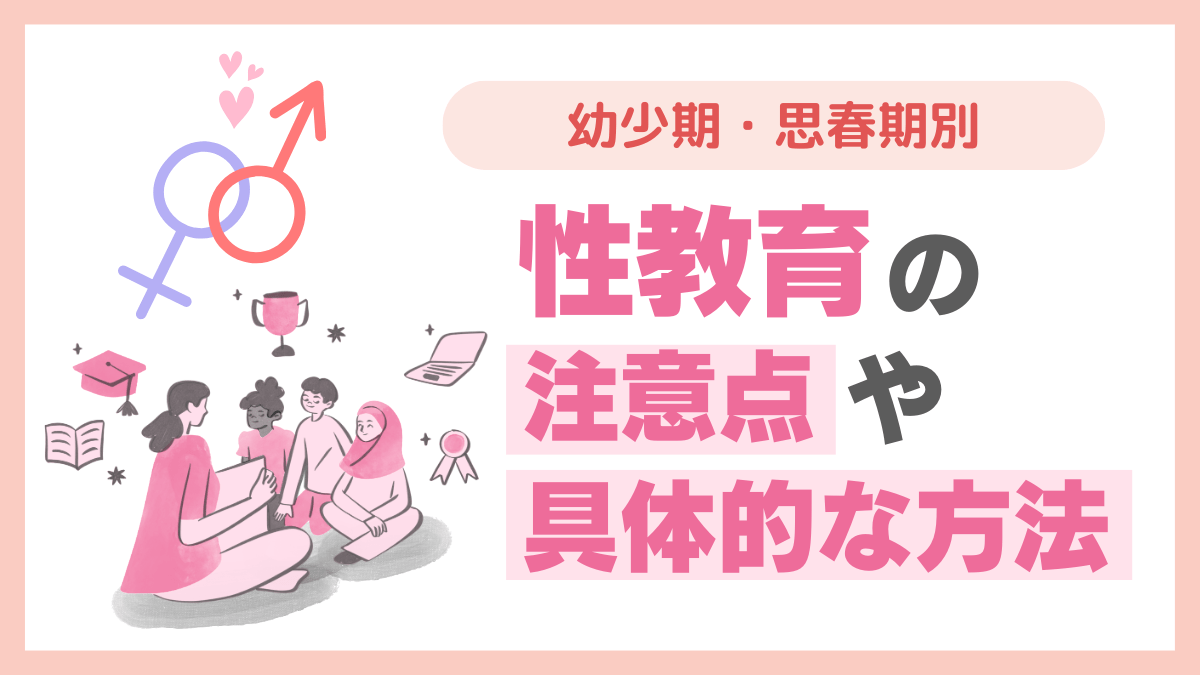
皆さんが子どもの頃、保健体育や道徳の授業で性に関する教育を受けたと思います。男女の身体には違いや特徴があることや、身体の仕組み、性犯罪といった内容を教えられたはずです。
近年は、そうした基本的な内容に加え、学校でもプライベートゾーンや性的同意など、より踏み込んだ内容を教えるところも出てきました。
しかし、まだまだ説明不足な部分が多く、家庭でも性教育の必要性が高まっています。
そこで今回は、子どもの成長時期にあわせた性教育のタイミングや、どんなことを教えたらよいのかについてご紹介します。
目次
性教育とは?大人にも必要?簡単に解説
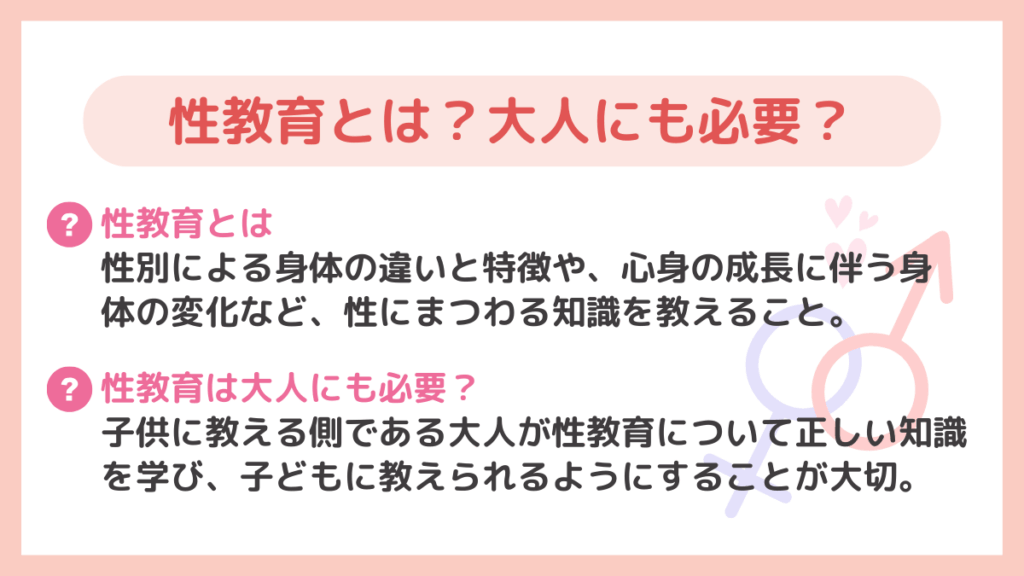
性教育とは、性別による身体の違いと特徴や、心身の成長に伴う身体の変化など、性にまつわる知識を教えることです。
純粋に身体の仕組みを教えるだけでなく、性に関するさまざまな問題やトラブルから身を守るためのトピックといった幅広い範囲が含まれます。
性教育によって得られる正しい知識を通して、自分自身はもちろん、大切なパートナーや家族・社会のコミュニティとの関わり方を学ぶことで、個人の健康や尊厳を守ることにつながります。
性教育は、学校だけでなく家庭やさまざまな機関によって行われ、子どもの成育過程によってアプローチ方法が異なります。
性教育の必要性
性教育は、子どもから大人まで全ての人にとって必要不可欠な学びです。性に関する正しい知識を持つことは、自分自身や他人の心と身体を大切にすることにつながります。
インターネットやSNSが普及する現代では、誤った情報に触れる機会も多く、子どもたちが混乱するリスクも高まっています。だからこそ、家庭や学校で信頼できる情報を段階的に伝えることが大切です。
また、性教育は「避妊」や「妊娠・出産」だけでなく、「人間関係」や「自己決定権」など、人生全体に関わるテーマでもあります。大人自身が正しい知識を持ち、偏見なく子どもと向き合う姿勢も、性教育を進める上で非常に重要です。
性教育は幼いころから行うことが重要!
性教育は思春期から始めるものと思われがちですが、実は幼児期から段階的に行うことがとても重要です。
幼いころから「体の名前」や「プライベートゾーン」といった基本的な知識を教えることで、子ども自身が自分の身体を守る力を身につけることができます。
また、早期から性に関する正しい価値観を育むことで、将来的なトラブルや誤解を防ぐことにもつながります。たとえば、「嫌なことは嫌と言っていい」「他人の体も大切にする」といった基本的な人間関係のマナーも性教育の一環です。
無理に難しい言葉を使う必要はなく、日常会話の中で自然に伝えていくことが大切です。親子でオープンに話せる雰囲気をつくることが、将来の健全な性意識にもつながります。
幼少期から性教育を行うメリット
幼い時期から性教育を始めることで、子どもは自己肯定感や他者への尊重を自然に学べます。ここでは、幼少期からの性教育によるメリットを紹介します。
自分の体を大切にする意識が育つ
幼少期から性教育を受けることで、子どもは自分の体が大切なものであると理解しやすくなります。
たとえば、「人に触れてほしくない場所は自分で守ってよい」と教えることで、プライベートゾーンの意識が育ち、性被害の予防にもつながります。また、「体の部位には正しい名前がある」と教えることで、子どもが不安や異変を伝えやすくなります。
こうした基本的な知識が、自己肯定感や安心感の土台になります。無理に話す必要はありませんが、絵本や遊びの中で自然に伝えることで、子どもも抵抗感なく受け入れられます。
他人の体や気持ちを尊重できるようになる
性教育は「自分を守る」だけでなく、「他人を尊重する」意識を育てる大切な機会でもあります。たとえば、「相手が嫌がることはしない」「触れる前に確認する」といった基本的な思いやりの姿勢を教えることができます。
これにより、友達との関わり方やコミュニケーションにも良い影響を与え、将来的な人間関係づくりの土台になります。また、性の話題に偏見を持たずに接することで、多様性への理解も深まりやすくなります。
幼いうちから「性=恥ずかしい、悪いこと」という誤ったイメージを与えないよう、日常の中で丁寧に伝えていくことが大切です。
思春期の性への戸惑いや不安を減らせる
性教育を幼少期から行っておくことで、思春期に急に性に関する変化が訪れても、子どもは戸惑いにくくなります。
身体の変化や性的な感情に対しても、恥や不安を抱かずに受け止めやすくなり、親や周囲に相談しやすい雰囲気づくりにもつながります。また、事前に知識を得ておくことで、インターネットや友人からの誤った情報に惑わされるリスクも減少します。
思春期は心も体も大きく変化する時期だからこそ、土台となる性教育を早い段階から始めることが、子どもの安心と自立を支える力になります。
幼少期から性教育を行うデメリット
性教育は大切な取り組みですが、伝え方やタイミングを誤ると逆効果になる可能性もあります。ここでは、幼少期から性教育を行うデメリットを3つ紹介します。
子どもが内容を誤解して受け取る可能性がある
幼い子どもは抽象的な内容を理解する力がまだ発展途上のため、性教育の内容を正しく理解できず、誤解することがあります。
例えば、「赤ちゃんはどうやって生まれるの?」という質問に対し、大人が科学的な説明をそのまま伝えると、かえって混乱を招く可能性があります。
誤った解釈が残ってしまうと、その後の成長に伴って正しい情報を受け入れる妨げになることもあるため、年齢や理解力に応じた言葉選びが重要です。親の価値観を押し付けず、子どものペースに合わせて少しずつ段階的に伝える工夫が必要です。
性に対して過度に意識させてしまうことがある
あまりに早く性に関する情報を与えると、子どもが性そのものに対して過度な関心を持ったり、興味を持ちすぎてしまう可能性があります。
これは、年齢に見合わない情報を与えることで起こる自然な反応ですが、過剰に意識することで恥ずかしさや不安が増し、性に対して否定的な感情を抱いてしまうこともあります。
性教育は「伝えること」自体が目的ではなく、子どもの健やかな心身の発達を促すためのものです。内容やタイミング、伝え方には十分な配慮が求められます。
親自身が戸惑いを感じ、適切に伝えられない場合がある
性教育を始める際、親自身が性について話すことに抵抗を感じたり、「どこまで話していいのか分からない」と悩むケースも少なくありません。
その結果、曖昧な説明や避けた言い回しをしてしまい、子どもが不安になったり、誤解を招く可能性があります。また、親が緊張しながら話す様子を見て、子どもが「性はタブーなもの」と捉えてしまうことも。
まずは親が性についての正しい知識を持ち、自分なりの考え方を整理することが大切です。子どもと対話する準備が整っていない場合は、無理に始めず専門書や教材の力を借りるのも良い方法です。
【幼少期】性教育を行うタイミング
次に、幼少期の子どもに性教育を行うタイミングについて見ていきましょう。
文部科学省が作成した「学校における性に関する指導について」に基づくと、日本では小学校4年生になって、はじめて性に関する教育がはじまります。
しかし子どもは、もっと前から自分や他人の身体に興味を持っています。
それまでは、家庭やほかのコミュニティで時間を過ごす中で、タイミングを見て教える必要がありそうです。
トイレやお風呂で行う
自分の身体を見たり触ったりする機会がもっとも多いのが、トイレやお風呂での時間です。
特に親と一緒に過ごすことの多い幼少期の子どもにとって、トイレ・お風呂での時間は自分や他人の身体の一部に興味を持ちやすく、さまざまな疑問が生まれる瞬間でもあります。
性器や身体の部位を指して「これは何?」と聞かれることもあるでしょう。その時は、大人が恥ずかしがらず、性教育を行う良いタイミングだと思ってたくさん話してあげましょう。
友達などとふれあいがあった
家庭や外で、同年代の子どもや家族以外の大人との交流があった時も、性教育のよいチャンスだといえます。
異性とのかかわりを通して身体の特徴の違いを感じたり、同性同士でも異なる部分があることを知ったりする機会になります。
また、身体の特徴以外にも、「男の子は青、女の子はピンク」のような、周りや世間によるステレオタイプに縛られない考え方を育むなど、周りとの交流を通して性に関する学びを得られるチャンスにもつながります。
性や赤ちゃんの作り方を聞かれた
日常生活の中で、子どもたちは常にさまざまな疑問を持ち、まわりの大人に質問します。
性や身体の仕組みに関する疑問もまた同様に、突然「なんで?」「どうして?」と聞いてくることがあるでしょう。
そのようなタイミングでも、まずは子どもがどのようなことを知りたいのかを汲み取り、できるだけ分かりやすく答えてあげられるとよいですね。
【幼少期】性教育の注意点
まずは、幼少期(1~8歳ごろ)の子どもに性教育を行う際に注意したいことを知っておきましょう。
シンプルな言葉で、具体的に教える
幼少期の子どもの場合、まだ身体の仕組みを詳しく知っているわけではなく、また、深く理解していないかもしれません。それでも、興味のあることは何だって知りたいものです。
そこで、子どもの疑問や興味をキャッチしたら、できるだけシンプルに、かつ具体的な言葉で説明してあげましょう。
たとえば「赤ちゃんはどこから来るの?」という質問に対しては、
- 「赤ちゃんは、お母さんのお腹の中で育って、お母さんの膣から出てくる」のように、複雑にならないよう簡潔に、やさしい言葉を選ぶ
- 「コウノトリが運んできた」のように嘘をついたり、「まだ知らなくてもよい」と子どもの好奇心・興味を否定するような発言は、子どもにとって信頼できない大人であることを印象づけてしまうため避ける
幼少期の段階では、精子と卵子の話や性交の話まで踏み込む必要はないかもしれません。ただし、子どもの興味に応じて答えることもあるでしょう。
その場合は、出来るだけ簡潔に「女の人が持っている卵(卵子)と、男の人が持っている種(精子)が出会ってひとつ(受精卵)になると、赤ちゃんに成長するんだよ」のように話してあげると、ほとんどの子どもは納得してくれるはずです。
シンプルさを意識しつつも、赤ちゃん言葉や曖昧な表現は避け、名称なども大人と同じ呼び方を使うようにしましょう。
話す相手を限定するように理解してもらう
性にまつわる話は、誰にでもしてよいわけではありません。とてもプライベートな話題であり、相手によっては不快な思いをすることもあるでしょう。
特に幼い子どもの場合、よく理解しないまま言葉を発し、相手の反応をうかがっているかもしれません。
そこで幼少期の子どもに性教育を行う際は、「こういう話は、とてもプライベートに感じる人もいるかもしれない。もし相手がその話をするのを嫌がっていたら、話すのをやめよう」などと伝え、性に関する話題は一方的にするものではない、プライベートなものである、といったポイントを理解してもらえるように努めましょう。
【幼少期】具体的な性教育方法
では、幼少期の子どもにはどのような性教育を行えばよいのでしょうか。
「自分の身体は自分のもの」をはっきりと伝える
まず性の話をするにあたり、自分の身体の中でも特に大切な「プライベートゾーン」から教えると始めやすいでしょう。
プライベートゾーンとは、水着で隠れる部位と口を含めた身体のパーツのことで、性器やおしり、胸(主に女性)が当てはまります。
プライベートゾーンは自分だけが見たり触ったりしてよい部位であり、親や医者などのケアが必要になる場合を除き、ほかの人には触らせてはいけないことを伝えましょう。
もし誰か(初対面の人はもちろん、知っている人でも)触ろうとしてくる人がいれば、はっきりとNOと伝え、その場から逃げ、親や先生など信頼できる大人に話すようにしてもらいます。
そうすることで、自分や他人の身体の大切さを学べ、また性犯罪の防止にも繋がるため、近年は世界や日本でも積極的に教えられるようになってきました。
性に関する話は、学ぶのに遅すぎるということはありませんし、プライベートゾーンについては性教育において最も大切な知識のひとつです。
特にプライベートゾーンを見たり触ったりするチャンスの多いトイレやお風呂などで、幼少期の頃から子どもと一緒に確認しながら教えてあげると理解が深まります。
自分と相手の身体・意思も大切!
プライベートゾーンの話でもいえることですが、自分の身体は自分だけの大切なものです。
自分自身を大切にするのと同様に、相手の身体や意思を大切にすることも、子どもが小さいうちから伝えておきましょう。
例えば、「お友だちが嫌だと言ったらやめようね」「お友だちとはお互いに親切にし合って、話したり聞いたりしようね」のように、相手へのリスペクトが大切であることを理解してもらうようにします。
【思春期】性教育の注意点
次に、思春期(8歳~18歳ごろ)に性教育を行う際、注意したいことをまとめてみました。
羞恥心を捨てて真剣に話す
まずは、大人が恥ずかしがらずに真剣に話をしてあげるように努めましょう。
親として、先生として、大人の側も性の話をするときにはどうしても「恥ずかしい」「言いづらい」と思ってしまいがちなのではないでしょうか。
しかし大人が恥ずかしがっていると、教わる側の子どもも「恥ずかしいこと」「話しづらいこと」として認識してしまい、何か悩みや相談があっても話せないままになってしまうかもしれません。
場合によっては、心身の健康や命の危険に関わることもある性の話だからこそ、普段から性教育を行う際は、羞恥心を捨てて子どもと対等な目線で話せるようにしましょう。
さりげなく伝わりやすい言葉で話す
思春期の子どもは、幼少期に比べて身体と心の発達が顕著になり、コミュニケーションを避けたがることもあります。
変化の大きい時期だからこそ、「教育のため」と気張らず、タイミングをうかがってさりげなく話を始められるとよいでしょう。かつ、伝わりやすい言葉を使って話すことも大切です。
例えば「この前、本で読んだんだけど」「知り合いの○○さんから聞いたんだけど」のように、自然に話を始められる流れを作ると、お互いに話しやすくなります。
「性の話=人権・人としての尊厳に関わる話」を理解してもらう
性教育を通して学べるのは、心身の仕組みだけではありません。性の知識を通して、人権や人としての尊厳にも関わるのだという点を理解してもらえるように努めましょう。
子どもたちの中には、さまざまな出会いを通して恋愛やセックスといった、これまでにはなかった深い関係に踏み込む機会も増えるでしょう。
近年は、学校やバイト先だけでなく、SNS(ソーシャルメディア)などのように、より幅広い交流の場が生まれます。
特にオンライン上でのやりとりが主流となってきた現代において、ヌード写真を含む自身や他人の写真をシェアすることや、間違った知識を広めてしまうといった問題が起きています。
これまでになかった複雑な環境に生きる子どもたちに、わたしたち大人はまず「誰にでも人権・尊厳があること」を前提に、性にまつわる問題を取り扱う必要があります。
本やニュースを参考にしながら、「こんな話があるけど、どう思う?」というように、家庭や学校で、大人と子どもが意見を交わしながら性について考える機会を設けてみるとよいでしょう。
【思春期】性教育を行うタイミング
次に、思春期の子どもに性教育を行うタイミングについて見ていきましょう。
学校での出来事などを話してくれたとき
最も話しやすいタイミングは、子どもから学校での出来事や話題をしてくれた時です。
こちらからも「その時、あなたはどう思った?」と気持ちや意見を聞いてみたり、問題があれば解決策を話し合ったりと、子どもと一緒に考えることで信頼関係を築けます。
性の話に関わらず、普段からさまざまな話をすることで、子どものほうからも何かあった際に話しやすくなるため、些細な話題でも面倒だと思わずに耳を傾けてあげましょう。
身体の変化や悩みを相談されたとき
子どもの成長に伴い、心身に変化を感じたり、悩みを抱いたりした際は、話を聞いてあげましょう。同時に、性教育のよいタイミングでもあります。
特に思春期になると、自分と他人を比べたがる傾向が高くなります。そんな時は「あなたはかけがえのない存在」「自分の身体に自信を持ってよい」と話してあげて、ボディ・ポジティビティを持たせてあげて下さい。
性自認や性嗜好といった場合も同様です。まずは「話してくれてありがとう」と、子どもの気持ちを尊重したうえで、誰にも自分の心身を大切にする権利があることを教えましょう。
生理や射精といった身体のセンシティブな悩みにも、まずは耳を傾け、必要であれば医療機関の受診を勧めるのも手です。
日常生活の中で性的な疑問を持ったとき
幼少期の性教育は、子どもが自然に性に関する疑問を持ったタイミングがチャンスです。
たとえば、「赤ちゃんはどこからくるの?」「なぜ男の子と女の子は違うの?」といった素朴な質問は、子どもなりに世界を理解しようとする健全な好奇心から生まれます。
この時に丁寧かつ年齢に合った言葉で答えることで、性に対するポジティブなイメージや正しい知識を育めます。無理に話題を避けたり、恥ずかしがってごまかすのではなく、質問に誠実に向き合うことが大切です。
絵本や図鑑などを活用して一緒に学ぶのも効果的で、親子の信頼関係を深める良い機会にもなります。タイミングを逃さず、自然な対話から始めることが、幼少期の性教育では何より重要です。
【思春期】具体的な性教育方法
では、思春期の子どもにはどのような方法で性教育をしたらよいのでしょうか。
相手と自分の意思について伝える
幼少期の子どもにも、相手へのリスペクトを持つよう教えることは大切ですが、思春期はそろそろ「お友達」のみならず、より複雑な感情が芽生える時期でもあります。
そのうえで、もし自分が嫌だと思うことを相手にされたら、ちゃんとNOの意思を伝えることを、改めて確認しておきましょう。
相手がたとえ自分と意見の合わない人だとしても、常にリスペクトを持って接することを忘れずに接することで、円滑な人間関係を築きやすくなると学べば、学校や社会で少し生きやすくなるかもしれません。
友人やパートナー関係においても、お互いに心地よい関係、もしくは逆に違和感のある関係とは何か?を一緒に考え、生活の中で実践できるようにしたいものです。
もし相手が、自分の望まないことを押し付けてきたら応じないこと、相手に「やめて」と言われたら一度で止めるように教えることも、基本的な性教育のひとつです。
また、万が一相手がいじめ・悪意のある言動を向けてきても、被害者側のあなたは決して悪くないこと、親や先生など信頼できる大人に話すこと、を併せて伝えましょう。
いざという時に、一人で抱え込まず誰かに相談できる環境づくりを整えてあげることも大切です。
性的同意を知っておく
性的同意とは、セックスをする前に両者が確認事項に同意することをいいます。
セックスをする時は、まず互いが本当にしたいかどうかの確認をとることが、何よりも大切です。
性的同意には、大きく分けて5つのポイントがあります。
1.対等な関係で、相手によるプレッシャーや操作がなく、お酒などで酔っていない健全な状態で同意が行われること。
2.誰でも、途中でしたくなくなったらやめてよい。
3.避妊方法など、お互いに必要な事項の確認が取れたうえで行うこと。
4.性交中は自分がしたいと思うことをすべきであり、過度な期待に応えようとする必要はない。
5.「部屋に入ったからセックスしてよい」「キスしたらセックスしてよい」と勝手に決めつけるのではなく、性交前は必ず、お互いにYESかどうかを確かめること。
酔っている時や気分が高揚している時は、相手の気持ちを読み取るのは非常に困難です。そのような場合は、性的同意を得るのが難しいため、しないほうがよいことも知ってもらいましょう。
どんなに親しい間柄でも、きちんと性的同意を取ること!
たとえ長い間一緒にいるパートナー同士でも、性交前には毎回きちんと性的同意を取る必要があります。
そうでなければ、「不同意性交罪」や「不同意わいせつ罪」といった犯罪になりうるからです。
内閣府による2020年の調査「男女間における暴力に関する調査報告書」によると、無理やりに性交などをされた経験のある人の割合は約24人に1人、うち女性は14人に1人でした。
加害者の内訳を見ると、「全く知らない人」は1割程度で、女性のおよそ3割が「交際相手・元交際相手」、男性は「通っていた(いる)学校・大学の関係者」による被害が2割となっています。
さらに、「配偶者」による被害も1割以上を占めており、たとえ親密な相手でも性的同意が取れていない場合、相手の体や心を傷つけることになり、犯罪にもなりえます。
現在、日本の法律では性的同意年齢が13歳から16歳未満に引き上げられ、それ以上の年齢であれば性行為を自ら判断できるとされています。
思春期の子どもを性犯罪に巻き込まないためにも、性的同意については基本的な知識として教えることが大切です。
SNSの扱い方を確認する
思春期の多くの子どもにとって、SNSはコミュニケーションのツールとして不可欠なものになっています。
そこで、SNSはお互いが繋がるための便利で大切な手段であると同時に、ちょっとしたきっかけでミスコミュニケーションが生まれやすく、誤情報が拡散しやすいことを確認しておきましょう。
場合によっては、ストーカーなど深刻な被害に遭う可能性もあるため、安易にプライベートな情報や写真をシェアしないようにするなど、必要最低限のルールやマナーを知ってもらうだけで、さまざまな危険から身を守れます。
性犯罪に遭った時の対処法を知っておく
思春期は心身の発達が著しく、性への関心も高まる時期です。同時に、SNSや外出先で性犯罪に巻き込まれるリスクも高まるため、万が一の対処法を事前に教えておくことが重要です。
まずは「嫌なことは嫌と言ってよい」という自己防衛の意識を持たせることが基本です。そのうえで、被害にあった場合にはすぐに安全な場所へ避難し、信頼できる大人や警察に助けを求めるよう伝えましょう。
また、証拠となる衣服や体をすぐに洗わないことや、相談窓口の存在を教えておくことも大切です。性犯罪に関する知識を与えることで、自分を責めずに正しく対応できる力を育てることができます。
性教育は、加害・被害の予防だけでなく、「自分を守る術を知ること」も重要なテーマのひとつです。
性教育に悩んだ時の相談先
もし性教育について、どのように伝えたらよいのか分からないといった悩みを持つ場合、オンラインサイトを当たってみることがおすすめです。
近年は、さまざまな団体が分かりやすくまとめたサイトが充実しています。たとえば意思専門家が監修している命育では、家庭で教えられるように分かりやすく説明したコンテンツが充実しています。
また、直接誰かに悩みを相談したいという場合は、チャットで相談できるcaran-coron カラダと性の相談室や、助産師や保健師・看護学生などがメールで相談に答えてくれるピルコンU30のためのメール相談があります。
その他にも、地域の助産師のように、性に関する知識が豊富な人が周りにいるかもしれません。お住まいの地域で活躍する助産師を見つけてみるのもよいでしょう。
性教育に関するよくある質問
ここでは、性教育に関するよくある質問に回答します。
性教育は何歳から始めるべき?
性教育は、特定の年齢から始めるものではなく、子どもの発達段階に応じて自然に始めるのが理想です。一般的には、3歳頃から「プライベートゾーン」や「体の名前」を教えることがスタートになります。
その後、成長に応じて「他人との距離感」や「妊娠・避妊」「性の多様性」など内容を段階的に深めていくことが大切です。
思春期になってから突然始めるのではなく、日常の中で自然な形で話すことで、子どもは性に対する健全な知識や価値観を育てることができます。大切なのは、子どもの疑問に誠実に向き合い、安心して質問できる環境を整えることです。
性教育は親がするべき?学校に任せてよい?
性教育は家庭と学校が連携して行うことが理想です。学校ではカリキュラムに基づいた基本的な知識が提供されますが、限られた時間や内容では子どものすべての疑問に対応しきれないこともあります。
家庭での性教育は、親子の信頼関係を土台にして、子どもが安心して性について話せる場をつくることが目的です。親が性の話題を避けず、自然に受け止める姿勢を見せることで、子どもは偏見や不安を持たずに学ぶことができます。
特に幼少期は親の役割が大きいため、学校任せではなく、家庭でも意識的に取り組むことが求められます。
性教育をすると逆に性に興味を持ちすぎない?
性教育をすることで、子どもが性に過剰に興味を持つのではと心配する声もありますが、実際には逆の効果があることが多いです。正しい性教育を受けた子どもは、性に対して健全で冷静な態度を持つ傾向があります。
知識が曖昧なままだと、誤った情報や興味本位の行動につながるリスクが高まりますが、性の仕組みやリスク、責任について理解していれば、不適切な行動を避ける力が育ちます。
性教育は「性を楽しむこと=悪いこと」ではなく、「自分や他者を大切にするための学び」として伝えることが大切です。正しい知識は、無知からくる問題を防ぐ最善の手段です。
性教育とSDGs
最後に、性教育とSDGsの関係性について確認しておきましょう。
持続可能な社会を目指すため、2015年に国連で採択されたSDGs(Sustinable Development Goals)には、人権や社会に関する取り組みも掲げられています。
性教育に関わるSDGs目標は?
SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」では、性別や住んでいる地域に関わらず、誰もが平等に適切な健康・福祉サービスを受けられるような社会の仕組みを勧める目標です。
その中のターゲット項目3.7では以下のように述べられています。
3.7 2030年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスを全ての人々が利用できるようにする
また、SDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」の中では、
5.6 国際人口・開発会議(ICPD)の行動計画及び北京行動綱領、並びにこれらの検証会議の成果文書に従い、性と生殖に関する健康及び権利への普遍的アクセスを確保する。
それぞれの国や地域で、適切な性教育を行えば、国民の性への関心・知識が深まり、もし身体に異変があったり、性トラブルに巻き込まれたりした際は、すぐ医療サービスへ利用しようと思いやすくなります。
そのためにも、教育カリキュラムの整備や、実際に医療サービスへアクセスしやすいようにシステムを築く必要が求められます。
まとめ
今回は「性教育」について、幼少期と思春期の子どもに向けた教育のタイミングやヒントを中心にお伝えしました。
わたしたち大人にとっても、性の話をすることはまだ社会の中でタブー視されることが多く、なかなか家庭やコミュニティの中で話題にしづらいかもしれません。
しかし子どもの人権や健康・安全面などを考えれば、必ず教えるべき内容であり、性の知識を身に付ければ社会全体がよりよい方向へ向かうはずです。
普段の暮らしの中で、周りの人との付き合い方や心身の健康を大切にできるよう願いを込めて、ぜひ子どもたちに性教育を実践してみて下さいね。
<参考リスト>
【国際基準の性教育】幼児期の子どもに妊娠と生殖(「赤ちゃんはどこからくるの?」)について何を教えたらいいですか? | 家庭ではじめる性教育サイト命育
各種法令による児童等の年齢区分|厚生労働省
What is Sex Education? | Sex Ed Definition and QA
【国際基準の性教育】幼児期の子どもに妊娠と生殖(「赤ちゃんはどこからくるの?」)について何を教えたらいいですか? | 家庭ではじめる性教育サイト命育
学校における性に関する指導について|文部科学省
Talking About Consent and Healthy Relationships at Every Age|Planned Parenthood
【助産師監修】 「プライベートゾーン」を教えて自分や相手を大切にする・自分を守る土台づくりを(イラスト解説・おすすめ絵本紹介)| 家庭ではじめる性教育サイト命育
思春期とはいつからですか? – 日本産婦人科医会
Parents’ Checklist to Support their Children’s Sex Education|Planned Parenthood
What Is Sexual Consent? | Facts About Rape & Sexual Assault
男女間における暴力に関する調査報告書|内閣府男女共同参画局
この記事を書いた人
のり ライター
東京生まれ&育ちのリトアニア在住ライター。森と畑に出会い「自然と人とが寄り添う暮らし方」を探求するように。現地で暮らし学んだ北欧の文化と植物、日本で体験したマクロビ&パーマカルチャーを糧に、食・暮らし関連を中心に執筆中。普段はほぼベジ。
東京生まれ&育ちのリトアニア在住ライター。森と畑に出会い「自然と人とが寄り添う暮らし方」を探求するように。現地で暮らし学んだ北欧の文化と植物、日本で体験したマクロビ&パーマカルチャーを糧に、食・暮らし関連を中心に執筆中。普段はほぼベジ。