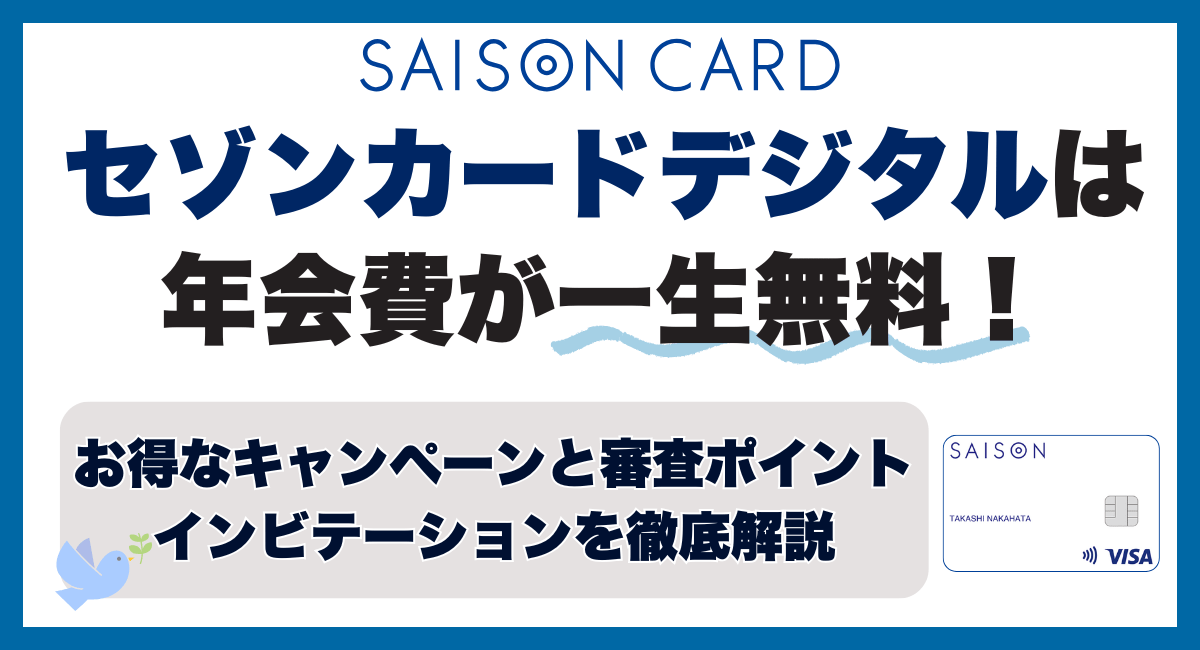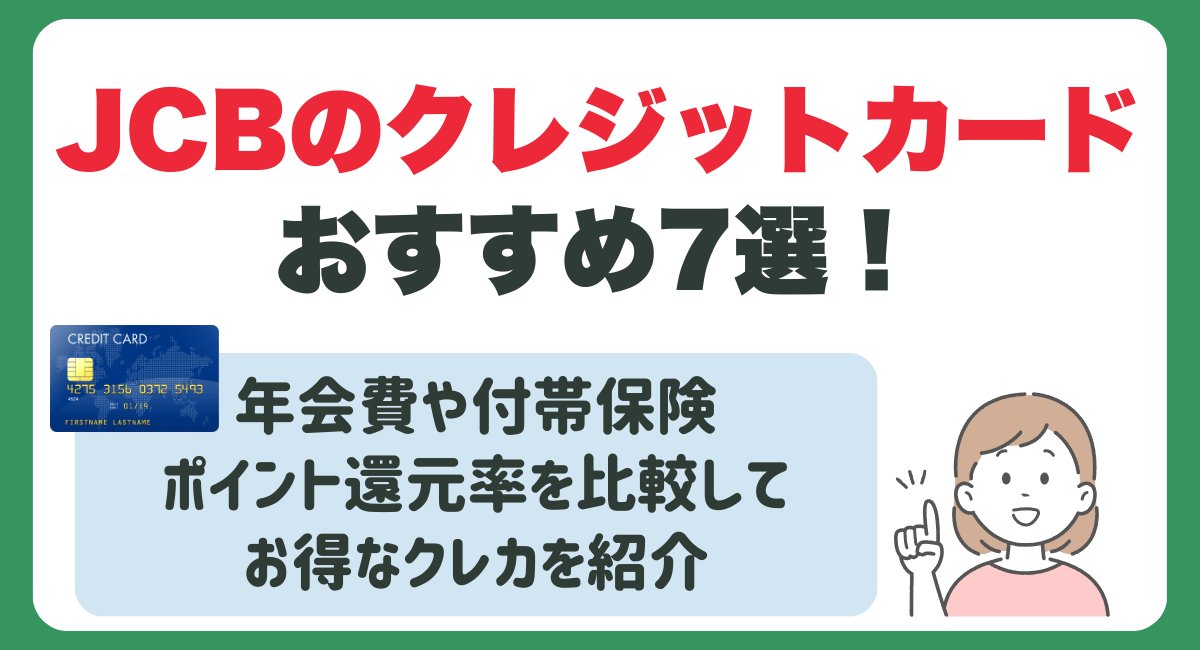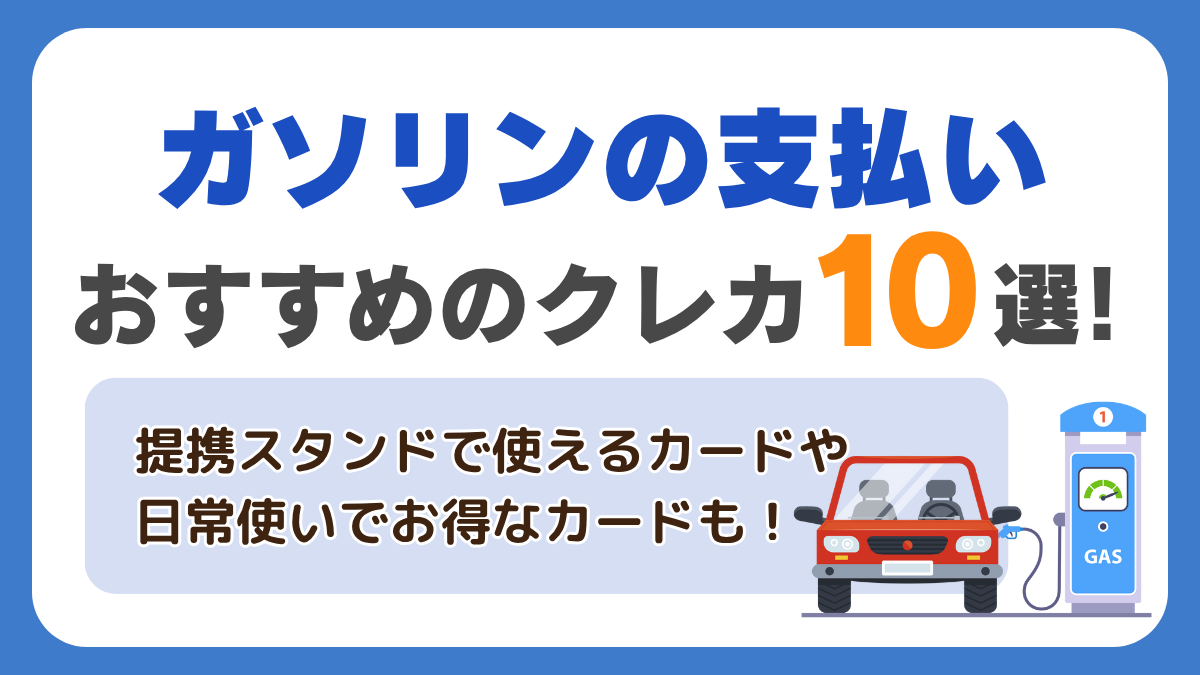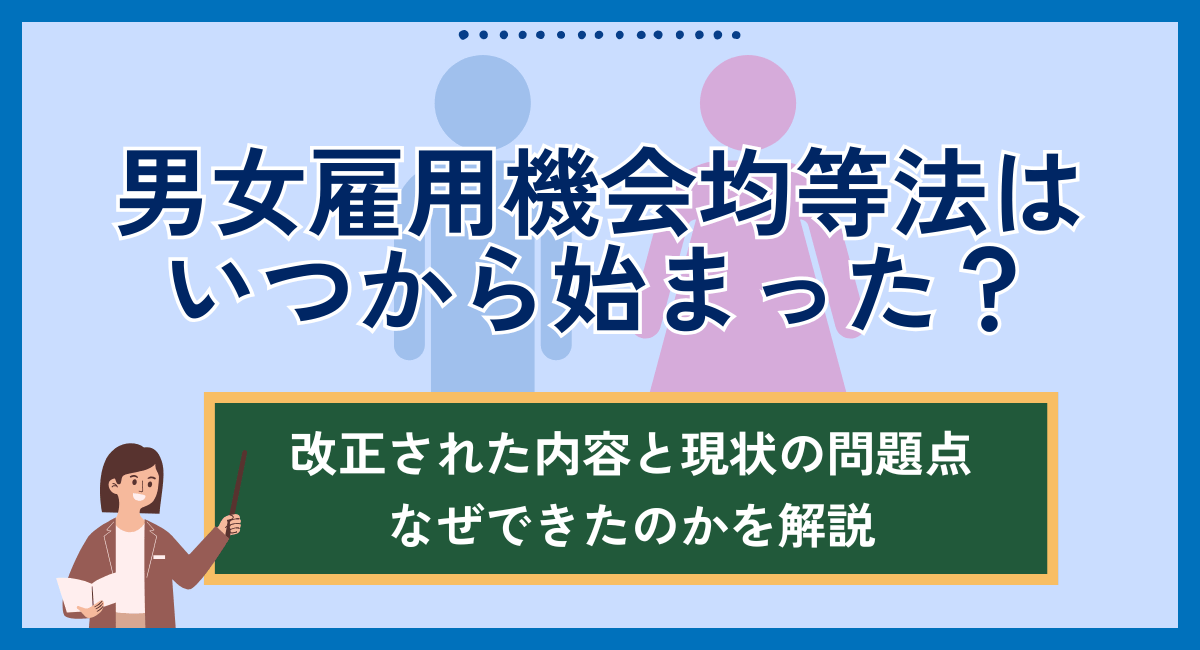
あなたの職場ではこのような対応をしていませんか?
「女性が応募してきた場合は、正社員ではなく期間契約社員として採用する」
「小さい会社なので、セクシュアルハラスメントの相談窓口を設けていない」
実はこれらは、男女雇用機会均等法に反する行為です。募集・採用は男女均等に取り扱うこと、またどんなに小さな会社でも、社内もしくは社外に担当者を決めて相談窓口を定める必要があります。
この記事では、事業主が守らなければならない男女雇用機会均等法について、歴史や具体的な内容、罰則、問題点、注意すべきポイント、SDGsとの関係について解説します。
目次
男女雇用機会均等法とは
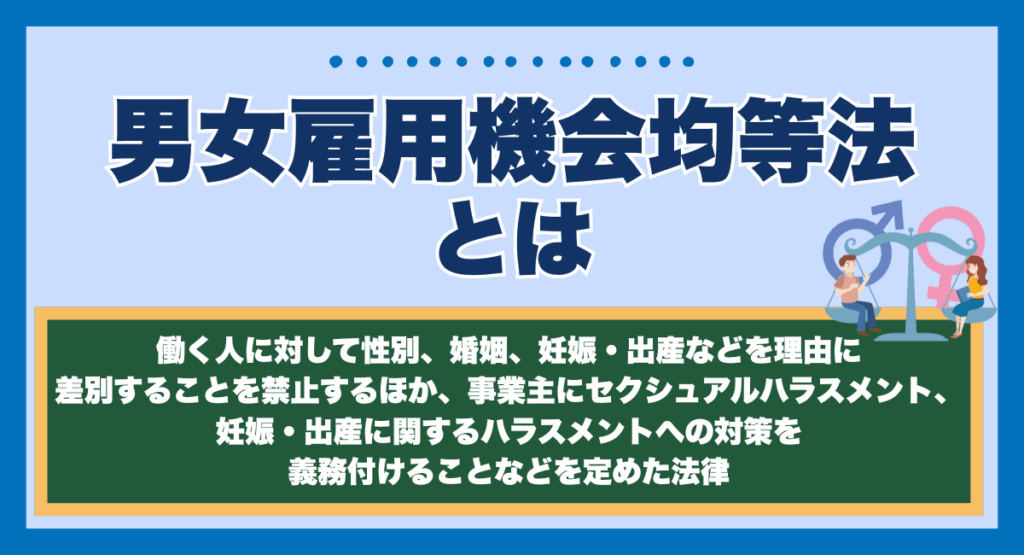
男女雇用機会均等法とは、働く人に対して性別、婚姻、妊娠・出産などを理由に差別することを禁止するほか、事業主にセクシュアルハラスメント、妊娠・出産に関するハラスメントへの対策を義務付けることなどを定めた法律です。
正式名称は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」です。
この法律は、雇用の場面で男女に均等な機会や待遇を与えるとともに、働く女性が仕事をしていても、妊娠中や出産後の健康を維持できる環境をつくることを目的に制定されました。
事業主は、同法に従って、募集・採用、配置、昇進・降格・教育訓練、健康管理、福利厚生などを行い、またこれらを実施するための体制を整える必要があります。
男女雇用機会均等法を理解することは、事業運営を行う上で不可欠です。事業者は雇用管理のさまざまな場面で、働く男女が能力を十分に発揮できる職場づくりに取り組むことが求められています。
男女雇用機会均等法に例外はある?なぜできた?わかりやすく解説
男女雇用機会均等法は、募集・採用から配置、昇進、退職まで性別を理由とする差別を禁じる法律です。例外として、妊娠・出産や母性健康管理に関する措置など、女性の身体的特性に配慮した取り扱いは差別に当たりません。
格差是正のための積極的改善措置や、業務の性質上どうしても同性対応が必要な職務に限った性別要件も、合理的範囲で認められます。
法律ができた背景には、女性の就業拡大にもかかわらず、採用での男女別枠や昇進差が残っていた現実があります。日本は国連の女子差別撤廃条約を批准するにあたり、国際基準に合わせる必要がありました。
こうした経緯から、職場での機会と待遇の平等を進めるために制定されたのが均等法です。
男女雇用機会均等法はいつから施行された?男女雇用機会均等法の歴史
男女雇用機会均等法は1985年に制定されました。制定に至るまでには、女性が置かれた国内の社会的な状況や、国際的な男女平等の流れが関わっています。
勤労婦人福祉法の制定(1972年)
男女雇用機会均等法が成立する以前から働く女性は増え続け、1970年代には雇用者総数の3分の1を占めるようになりました。その半数は既婚者でした。
こうした状況を受け、仕事と家庭の生活を調和させることや、性別により差別されることなく能力を発揮できるように配慮されるべきという理念を掲げた法律が制定されます。これが1972年に施行された「勤労婦人福祉法」です。
勤労婦人福祉法は、国・地方公共団体、事業主の責務として、職業指導や生活相談、健康診断、育児休業などの女性の福祉を促進することを定めています。[1]男女雇用機会均等法は、この法を全面的に改正して制定されたともいわれています。
男女雇用機会均等法と女子差別撤廃条約の関係(1985年)
男女雇用機会均等法を制定した背景には、国際的な流れもありました。具体的には、国連が1981年に「女子差別撤廃条約」を発効します。
これは、男女の平等を基礎として、女子に対する差別をなくすための必要な措置をとることを宣言した条約です。この中には、男女平等の原則を自国の憲法や法令に組み入れ、これを実現する手段を確保することとあります。
日本は、1985年に男女雇用機会均等法を制定したほか、国籍法や戸籍法を改正して法制度を整備しました。[2]そして同年の1985年、女子差別撤廃条約を批准しました。男女雇用機会均等法の制定には、女子差別撤廃条約を批准する目的もあったと言えるでしょう。
男女雇用機会均等法の制定(1985年)
男女雇用機会均等法は1985年に制定され、1986年4月1日に施行されました。
この法律は、1972年に制定された「勤労婦人福祉法」を全面改正する形で成立し、国際的な動きである「女性差別撤廃条約」(1979年採択)の批准に向けた国内法整備の一環として整備されました。
1960年代の高度経済成長期に女性の労働市場進出が進んだものの、単純作業や補助業務への限定など差別的扱いが常態化していた背景があり、男女の機会均等を求める労働組合や女性団体の声が法制定を後押ししました。
男女雇用機会均等法改正(1997年・1999年~)
男女雇用機会均等法が施行された後、当初の法律では、募集・採用・配置・昇進における男女均等扱いが「努力義務」とされ、教育訓練や福利厚生の差別は禁止されましたが、1997年に改正法が成立し、1999年4月に施行された改正法では、「努力義務」は「義務」になります。また、セクシュアルハラスメントの防止も義務化されました。
2006年(2007年施行)には、差別禁止の対象を女性ではなく男女双方にすることや、妊娠や出産、産前産後休業の取得を利用とする解雇の禁止などが追加されました。
2016年(2017年施行)と2019年(2020年施行)は、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産などに対するハラスメントの防止対策などが強化されています。
男女雇用機会均等法は、国内の状況や国際的な流れの影響を受けて現在まで運用されています。事業主は、同法が改正される際には、その内容を理解しておく必要があるでしょう。
男女雇用機会均等法の具体的な内容
男女雇用機会均等法の具体的な内容を、厚生労働省発行の「男女雇用機会均等法のあらまし」を参考に簡単に紹介します。
| 項目 | 主な内容(要点) |
|---|---|
| 性別を理由とする差別の禁止 | 募集・採用、配置(業務内容や権限の付与を含む)、賃金・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇などの場面で、性別を理由とする不利益取扱いを禁じます。男女の格差を解消するための合理的な積極的改善措置は例外として認められます。 |
| 婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止 | 妊娠・出産・育児休業の取得等を理由に、解雇や雇止め、降格、契約更新拒否、評価の引下げなどをしてはいけません。妊娠中および出産後1年以内の解雇は、事業主がそれ以外の正当な理由を証明しない限り無効です。 |
| セクシュアルハラスメント・妊娠出産等に関するハラスメント対策 | 相談窓口の設置、事実関係の迅速な確認、被害者の就業上の配慮、行為者への措置、再発防止の研修などの体制整備を事業主に求めます。ハラスメントで就業環境が害されないようにするのは事業主の義務です。 |
| 母性健康管理の実施 | 妊娠・出産後の女性労働者が保健指導・健康診査を受けられる時間の確保や、医師等の指導に基づく就業上の措置(業務の軽減、通勤への配慮など)を講じます。これらは事業主の義務です。 |
| 男女雇用機会均等推進者の選任 | 企業は、職場の男女の均等な機会・待遇を確保するための業務を担う推進者を選任するよう努めます。規程の整備や実態把握、社員への周知などの中心役になります。 |
| 派遣先にも均等法を適用 | 派遣先事業主にも、不利益取扱いの禁止、ハラスメント防止、母性健康管理措置などの規定が適用されます。派遣元・派遣先が連携して対応することが求められます。 |
| 深夜業務に従事する女性への措置 | 女性を深夜業務に従事させる場合、通勤や業務の安全確保に配慮します。健康への影響に注意し、必要に応じて勤務の見直し等の措置を検討します。 |
| 国から事業主への援助 | 国は、相談・情報提供、実態分析、計画作成の助言、研修や事例集の提供などを通じて、企業の取組を支援します。 |
| 紛争が生じた場合の救済措置 | 企業内の苦情処理や相談体制の活用を促し、解決しない場合は都道府県労働局のあっせん、機会均等調停会による調停などの行政的手続で解決を図ります。 |
| 厚生労働大臣の指導・監督 | 必要に応じて報告を求め、助言・指導・勧告を行います。命令や企業名公表、所定の過料などの規定があり、法の実効性を確保します。 |
| コース別雇用管理の指針 | 「総合職・一般職」等のコース別雇用管理を行う場合、募集・採用・配置・昇進等の各場面で指針に従います。コース新設・変更・廃止時の取扱いも示され、国や自治体のガイドやQ&A・事例集を参照しながら運用します。 |
男女雇用機会均等法の現状
男女雇用機会均等法の現状はどのような状況なのでしょうか。
制度と実態の乖離が残る職場環境
法律上は募集・採用から退職まであらゆる段階での性差別が禁止されていますが、間接差別の実態が問題視されています。
例えば総合職の全国転勤要件や昇進時の転勤経験要件が、結果的に女性のキャリア形成を阻害するケースが指摘されています。
2015年の裁判では昇進率の男女差が認められながら「適正評価」と判断され、差別認定のハードルが高い実情が浮き彫りになり、企業の意識改革が進まず、特に管理職比率の男女格差が課題です。
妊娠・出産に伴う不利益扱いの潜在化
2006年改正で「妊娠・出産を理由とした解雇の無効推定」が明文化されましたが、産休復帰後の不利益配置や評価ダウンの事例が後を絶ちません。
産後1年以内の解雇は原則無効とされるものの、退職勧奨や契約更新拒否など間接的な手法で不利益が行われるケースが報告されているのも事実です。
企業側が「業務効率低下」を理由に正当化する傾向があり、立証の難しさが課題となっています。
セクハラ防止とポジティブ・アクションの課題
セクハラ防止措置義務化後も相談件数は増加傾向にあり、特に「環境型セクハラ」(性的な環境醸成)への対応が不十分です。
他方、ポジティブ・アクション(積極的改善措置)は企業の自主努力に依存しており、2023年時点で実施企業は主要企業の約60%に留まります。
数値目標を掲げない「形骸化した取り組み」が多く、効果的な女性活躍推進が求められています。
現在では、AI採用ツールの性別バイアスや非正規労働者の格差など新たな課題が顕在化しています。
特に「同一労働同一賃金」との連動強化が必要とされ、間接差別の判定基準明確化が急務です。企業にはハラスメント防止だけでなく、働きやすい環境整備を通じた真の男女共同参画が求められています。
男女雇用機会均等法に反した場合の罰則
男女雇用機会均等法には、罰則が設けられています。適用されるのは、先の「男女雇用機会均等法の具体的な内容:ポイント10」のケースです。
「報告をしない」「虚偽の報告をする」と20万円以下の過料
男女雇用機会均等法では、厚生労働大臣の求めがあった場合、事業主はこの法に関わる事項を報告しなければなりません(第二十九条第一項)。
しかし、報告をしない、もしくは虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料(かりょう)に処されます。
| 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。(第5章第三十三条) |
過料とは、行政上の秩序を維持するために違反者に課す制裁金です。刑事事件の罰金とは異なり、前科にはなりません。
また、罰則ではありませんが、勧告に従わない場合には企業名が公表されます。これも企業にとっては大きなダメージになるので、注意が必要です。
男女雇用機会均等法の問題点
男女雇用機会均等法にはいくつかの問題点があります。そのうち2つのポイントに注目してみましょう。
差別を証明するルールが確立されていない
1つ目は、性別を理由とする差別があったかどうかを証明しようとする際に、証拠からそれを導き出すルールがないことです。
女性に対する昇進差別が問われた裁判(2015年)では、男女間で昇進状況に大きな差があったことは認められましたが、適正な人事評価の結果であり女性差別とは言えないと判断されました。[3]
何が男女雇用機会均等法で言う差別であり、何がそうでないのか。これを証明するルールが確立されていないため、事業主が取り組む際には難しい面も出てくるでしょう。
働く女性の母性のみが尊重されている
もう1つは、男女雇用機会均等法の基本的理念として、働く女性がその母性は尊重されつつ、充実した職業生活を送ることができるようすることが掲げられていることです。
| (基本的理念)第二条 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従って、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。 |
基本的理念では、働く男性の父性や充実した職業生活については触れられていません。そうしたこともあってか、仕事をしながら育児を担う男性が困難な状況に陥るケースもあります。
例えば、企業が育休復帰後に常に残業ができると考えているのは、男性(17.1%)、女性(2.4%)であり、男性が大きく上回っています。こうした意識により業務量が育休前と変わらず、仕事と育児で心身共に疲れ果てる男性もいるのが現状です。[4]
企業は、こうした背景を踏まえながら、今後の法律の改正にも注視し、企業経営を組み立てていく必要があるでしょう。
男女雇用機会均等法に違反しないために企業が注意すべきポイント
企業は、雇用管理のさまざまな場面について、男女雇用機会均等法に適用するよう細かく対応していかなければなりません。
しかし、伝統や慣例、個人の常識や思い込みなどは、法に適しているかを考える機会さえないこともあります。このことを十分に注意して、雇用管理の一つ一つを明確にしていくことが重要です。
そのためには、具体的にイメージできる実例や先に紹介したQ&A、チェックリストを活用するのも手です。これらは、国や自治体などのサイトなどで入手できます。
<参考>
- 「均等法Q&A」(厚生労働省)
- 「どんなハラスメントかチェック」あかるい職場応援団(厚生労働省)
- 「職場におけるハラスメント対策マニュアル」(厚生労働省)
- 「令和4年度雇用平等ガイドブック」(東京都)
男女雇用機会均等法に関するよくある質問
男女雇用機会均等法に関するよくある質問を集めましたので、ぜひ、参考にしてください。
男女雇用機会均等法の主な目的は?
男女の均等な機会と待遇の確保が目的です。1985年制定時は「努力義務」中心でしたが、1997年改正で募集・採用・配置・昇進における女性差別が禁止され、実質的な平等へ転換しました。
特に、女性保護から平等主義への方針転換が明確化され、深夜労働規制の男女共通化も進みました。
1997年改正の具体的な変更点は?
1997年改正の具体的な変更点は以下のとおりです。
- 差別禁止の義務化:従来の努力義務を廃止し、法的拘束力のある禁止規定に強化
- セクシュアルハラスメント防止措置:事業主に相談体制整備・再発防止策の実施を義務化
- ポジティブ・アクション支援:男女格差解消に向けた企業の自主的取組を国が支援
これにより、「女子」から「女性」への用語統一も実施され、法文から性別役割分業の意識改革が進みました。
内閣が推進する男女雇用機会均等法関連施策は?
政府はポジティブ・アクション促進を重点施策とし、厚生労働省を通じた企業への助言・指導を強化しています
2020年代には賃金格差解消に向けたガイドライン策定や、ハラスメント防止法整備との連動を進めています。特に、勧告違反企業の公表制度(1997年改正で導入)により、実効性確保に注力しています。
男女雇用機会均等法とSDGs
最後に、男女雇用機会均等法とSDGsの関係について確認していきます。男女雇用機会均等法は、SDGsの目標5「ジェンダー平等を実現しよう」に該当します。
目標5「ジェンダー平等を実現しよう」
目標5「ジェンダー平等を実現しよう」は、女性に対する差別をなくすことや、ジェンダー平等を促進するために政策や法律を導入することなどが掲げられています。
男女雇用機会均等法は、雇用管理の場面で男女の均等を実現するための法律です。女性に対する差別をなくすことで、ジェンダーの平等を図ります。この法律により、目標の達成に貢献することができます。
まとめ
男女雇用機会均等法は、働く人に対して性別、婚姻、妊娠・出産などを理由に差別することを禁止するほか、事業主にセクシュアルハラスメント、妊娠・出産に関するハラスメントへの対策を義務付けることなどを定めた法律です。
この中には、厚生大臣の求めに対して報告をしなかったり虚偽の報告をしたりする場合、20万円の過料に処される罰則が規定されています。また、男女雇用機会均等法は、ジェンダー平等を掲げたSDGsの目標5「ジェンダー平等を実現しよう」に貢献します。
女性に対して何が差別に当たるのかという問題は、事例などを参考に一つ一つ学んでいくほかありません。企業の伝統や慣例、個人の常識や思い込みなどに注意して進めていく必要があるでしょう。
<参考>
雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために |厚生労働省
「男女雇用機会均等法のあらまし」厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・ 均等部(室)
[1] 「勤労婦人福祉法のあらまし」労働省婦人青年局 1972.8 リーフレット№126
[2] 女子差別撤廃条約|日本女性学習財団|キーワード・用語解説
[3] 日本労働研究雑誌 括テーマ●〈平等〉の視点からみた女性労働男女の雇用平等──法制の現状と課題 中窪裕也
[4] 退職 転職のケースも…育休後 仕事と育児の両立 苦悩する父親たち | NHK | WEB特集 | 子育て
この記事を書いた人
池田 さくら ライター
ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。
ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。