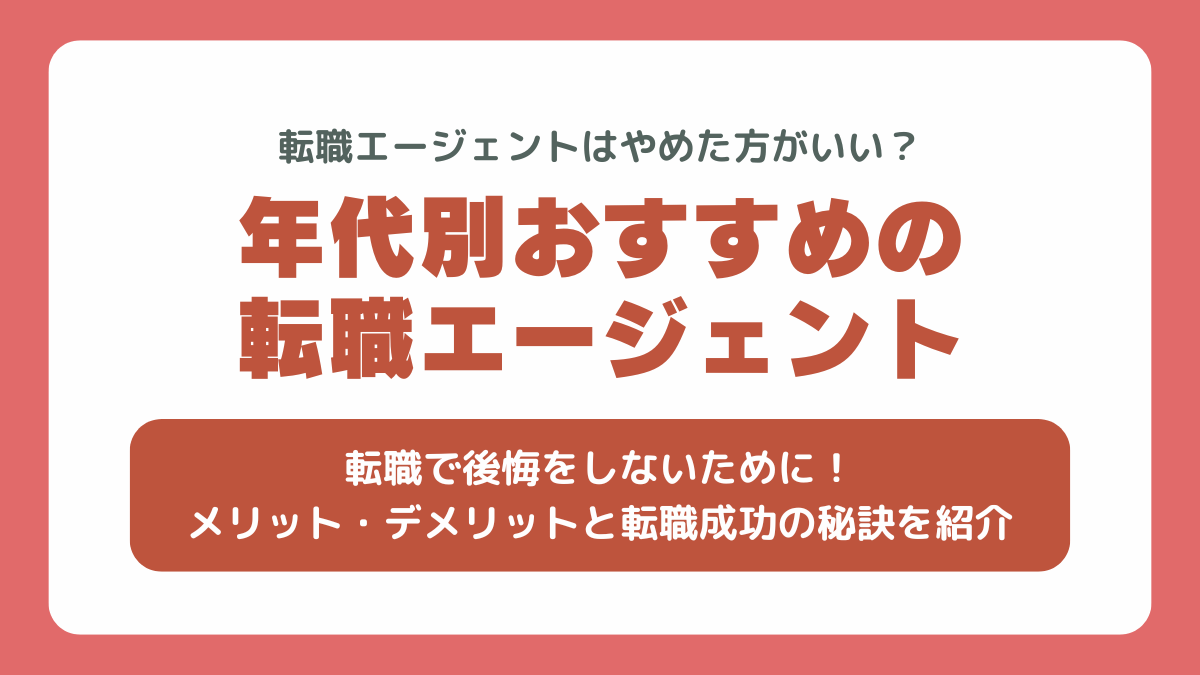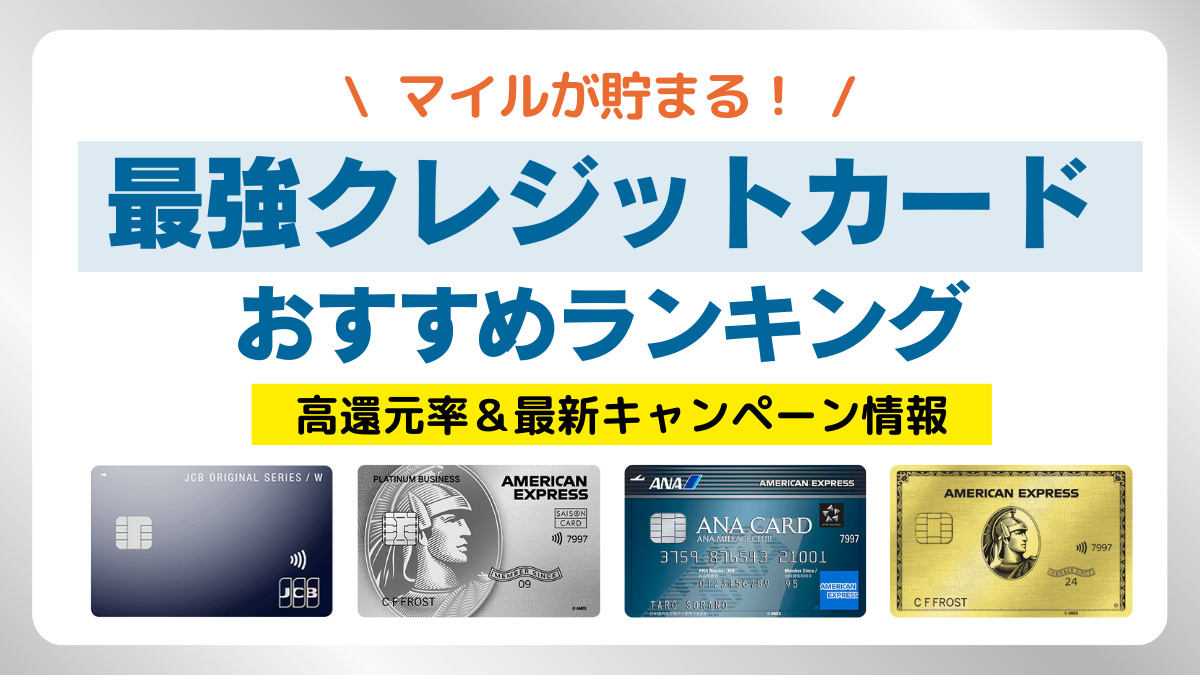データコム株式会社 取締役 小野寺裕貴さん インタビュー

小野寺裕貴
データコム株式会社 取締役兼経営推進部部長
株式会社みずほ銀行での法人営業、株式会社インテージでの事業開発・アライアンスを経て、データコム株式会社へ入社。取締役として財務会計、人事、マーケティングなど経営全般を管掌。また、米国・欧州等のビジネスイベントや店舗に出向きながら海外リテールトレンドを研究。「宣伝会議」や「販促会議」への寄稿や「販売革新」での連載を担当するなど、業界への発信活動を続ける。
目次
introduction
1994年の創業以来、スーパーやドラッグストアなどの小売業に特化したデータ分析システムで、数々の企業戦略を支えてきたデータコム株式会社。約2年前に大手マーケティング企業から入社した取締役の小野寺裕貴さんに、データコム株式会社の事業内容や、社会課題に向けた活動などについてお話を伺いました。

データ分析システムで全ての人の挑戦を支えたい
–まずは御社のご紹介をお願いします。事業内容や社風を教えてください。
小野寺さん:
データコム株式会社は、宮城県仙台市で創業した31期目の会社で、スーパーマーケットやドラッグストアのデータ分析をするシステムを提供しています。私たちの主なターゲットは複数の店舗を持つチェーン企業で、これまで150社以上の稼働実績があります。
例えば1人あたり10商品を買うとして、1店舗あたり1日に2,000人来客するとすれば、それだけでかなりの量のデータがとれます。当社はそのデータを分析するシステムを提供することによって、商品需要の予測や課題を発見したり、業務効率を改善したりすることで企業の成長を後押ししています。
仙台本社と東京支社があり、合わせて90名以上が在籍しています。時差出勤や1時間単位で休みをとったり、在宅ワークや時短勤務を選択したりもできるので、比較的フレキシブルに社員が働くことができる会社でもあります。
また、近年は外国籍人材の入社が続いています。当社の更なる成長に向けて、高度な技能や多様なバックグラウンドを持つ外国籍の方と一緒に働くことは非常に有益です。これからも歓迎していきたいと思います。
当社は父が創業した会社で、私は約2年前に入社しました。それ以前は金融機関や、マーケティング会社で働いていました。どちらの会社も数万、数千人の社員が所属する大きな組織でしたので、当社の有り様とは大きく異なりました。
当社の規模ですと、一人ひとりの個性が見えやすく、活きやすい一方で、個人に紐づく業務が多いと感じます。今後発展していくためには、業務や知識を棚卸ししながら形式知化していくことが必要だと考えています。
–御社はどのようなことを目指している会社ですか?
小野寺さん:
当社はお客様にしっかり向き合い、ビジネスへの新たな価値を創造し、確かな感動を生み出すということを目指しています。また昨年、「すべての人の挑戦をデータで支える」というミッションをつくりました。スーパーマーケットやドラッグストアへのサービス提供ももちろん大切ですが、ターゲットを狭めてしまうと成長には限りがあります。抽象度を上げて考えると、我々の強みであるデータハンドリングやシステム構築の技能は他業界にも活かせるのではないかと考えました。例えば地方の水産加工メーカーや建築メーカーなど色々な会社の状況を聞いてみると、今でもFAXを使って受発注をしてデータ化の機会を損ねていたり、同じ商品なのに入力の仕方が統一されていなかったりと、データ分析の視点をまだ持っていない、もしくはデータの持ち方に問題がある、そういった会社はまだ多いと感じています。今後はそういった新しい分野の会社にも、好事例を示すことなどでデータ分析をする価値を知っていただきたいと思います。

–データを分析することの意義についてもう少し詳しく教えて下さい。
小野寺さん:
経験や勘も、一定のスペシャリストがいる現場では有効だと思います。例えば個人商店の八百屋さんがきゅうりを20本仕入れて、自分の掛け声でなんとか売る。このような場面では感覚に頼った方が有効かもしれません。ただし、当社が対象としているチェーン店では、複数の現場で多くの従業員が販売をするわけですから、効率的な指示が必要です。その際に、経験や勘というものを売り上げデータの分析によって数値化することで、無駄のない発注や現場での作業効率を上げることが期待できます。
20年以上続く主力商品、「d3」で効率的な業務をサポート
–御社の主力商品、小売業特化型商品分析システム「d3」について教えてください。
小野寺さん:
まずはデータの流れについて説明します。お店で買い物をするとレシートが発行されますよね。それと同時に同じ情報がシステム上に送られます。そのデータが大きな基幹システムに入り、蓄積されたものをd3で抽出して分析をします。分析の結果、ある一つの商品がその日そのお店でいくつ何円で売れたかを集計し、いくつ仕入れているから残りはいくつあって、いくつ仕入れなければいけないという状況を可視化します。
マーケティングの意味合いもありますが、明日どれだけ発注するかという店舗担当者の意思決定の根拠になるという点では、業務サポートとしての役割が強い商品です。
このシステムは20年以上前から販売していますから、我々はスーパーなどの経営会議、商品部門の会議で注目される指標を把握しており、そのような項目をシステムにパッケージ化しているので、ある程度汎用的に使えるのが強みです。また、商品購入者の全ての行動をデータ化するとコストがかかってしまいます。そのため、データ利用者にとって効率的なデータの持ち方を調整している点も特徴です。
ひと昔前まではデータを抽出するだけでも数時間かかることもありました。その中で当社は、短時間でデータを抽出できるようにしたことで、お客様がより付加価値の高い仕事に専念できるようになりました。

–お客様からの反響などから、今後さらに改善していきたい点などはありますか?
小野寺さん:
今の世の中には安くて使いやすいクラウド型のサービスがたくさんあります。需要予測システムなどそのような外部サービスと我々のサービスがもっとうまく結合していく必要があると思います。そうしないと当社のサービスだけがガラパゴス化してしまいます。サービス単体としては素晴らしいものであったとしても、他社の便利なサービスと連携がとりにくいということになると、お客様にとって利便性が落ちてしまいますから、そこは課題として捉えています。データを分析した上でお客様ができることを視野に入れ、他のツールとの連携性を高めることを今後強化していきたいと思っています。
フードロス問題への貢献。データ分析会社としての使命
–ここからは話が変わりますが、御社は社会的課題解決のためにも活動をされていると伺いました。どのような活動をされているのか教えてください。
小野寺さん:
昨年、フードロスの削減を目的としたフードドライブプロジェクトを初めて行いました。このプロジェクトでは、期間内に集めた食品を回収し、社会福祉協議会を通じて仙台市内の食品を必要としている方々にお届けしました。
フードドライブを始めた背景についてお話します。我々は主にスーパーマーケットと取引があるわけですが、クリスマスケーキや鰻など、スーパーではイベント商品を大量に発注します。ところが値引きをしても、最終的には大量に売れ残ってしまうことがあります。我々のサービスを通してデータ分析が有効に作用すれば、結果的にフードロスを抑制することができます。
ただし、フードロスには色々な要因が作用しますから、データ分析だけが解決策ではありません。データ分析でフードロスを削減することが理想ではありますが、今できることとしてフードドライブなら、必要としている方に対して、食べ物を直接的に届けることができると考え取り組みを始めました。
社員としても、黙々と目の前の仕事に取り組むのではなく、そのような社会課題の解決を意識することで、自分の仕事は世の中にとってどのような意味があるのかを考えることはとても大切です。ゆくゆくは、それができる社員が増えていって欲しいと思います。
一方、対外的にも、データ分析サービスをしている会社がこのような活動をすることによって、社会のフードロスを減らすことの大切さに気づくきっかけを、データを見る側の立場の方や小売業者に与えていきたいですね。


–フードドライブ以外にもどのような活動をされていますか?
小野寺さん:
仙台市の中学校を訪問して、我々が関連している小売業について授業をさせていただきました。まだ難しいのでデータ分析の話はしませんでしたが、商品が売れるまでの流れや売場づくりに関する科学などを伝えました。これは中学生がこれからのキャリアを考えたり、視野を広げたりする上でのパーツになればいいなと思い、始めた取り組みです。また会社としても個人としても、伝えられることはまだたくさんあります。就業体験を含め、教育分野に対してできることについて、これからも仙台市と積極的に協力していきたいですね。

より良い仕事ができる風潮を広めて会社と社員をリードしたい。
–会社として成長を続ける上での課題や、今後取り組みたいことについても教えてください。
小野寺さん:
我々は小売業特化型のサービスを展開してきたわけですが、それが強みでもありながら課題でもあります。一つの業界しか見ていないと他の業界に疎くなります。「知らないから学ぶ」という姿勢があればいいのですが、「知らないから怖い」という気持ちでは余力がなくなってしまいます。いい意味での危機感と、周りの世界を見る楽しさを感じながら社員には仕事をして欲しいと思います。そのためには社長や私が半歩先を見ている状態を保つことによって、会社を伸ばしていく姿が理想ですね。
また、当社は創業社長が31期率いてきた会社ですから、一定のトップダウンがあったからこそ上手くやれてきた部分があります。一方で営業担当やエンジニアが切磋琢磨して育ち、その次の世代を育てるという循環が少し弱かったという部分が見てとれます。そこで、一定の裁量権を期待される社員に与えて運用してもらい、良いものがどんどん社内でエスカレーションするような仕組みを整えたいですね。その仕組みのひとつとして、時差出勤の許可などもそうですが、私は全ての行動を部下が上司に事前に伝えて許可を得る必要はないと思っています。お互いの信頼関係が成立し、管理できていることが前提ではありますが、全ての許可を得るコストを省略することで効率的に、信頼関係を深めてより良い仕事をすることができると考えています。今後このような風潮を全社的に広めていきたいですね。
小売業の枠を超え、東北地方を盛り上げる企業へ
–最後に御社の展望について、今後社会にどのような貢献をしていきたいとお考えですか?
小野寺さん:
フードロスなどの社会課題解決や、データ分析による適正価格導出など、小売企業の成長への貢献はこれからも続けていかないといけないと考えています。
その他には仙台市のベンチャー企業と連携したり、ベンチャー企業の創出を手助けしたりすることで、小売業だけではなく東北地方の地域経済全体をもっと盛り上げることに貢献していきたいです。

データ分析サービスの提供にとどまらず、自社が世の中の課題に対してできることを、他社経験が豊富な取締役として冷静に分析されている姿勢が印象的でした。この度はありがとうございました。
この記事を書いた人
あきもと なおみ ライター
元公務員。苔の魅力のとりこになり、農業(苔培養)で起業。プライベートでは読むことと書くことに幸せを感じる3児の母。ライターの仕事を通した出会いに敬意を示して、大好きな文章を紡ぎます。
元公務員。苔の魅力のとりこになり、農業(苔培養)で起業。プライベートでは読むことと書くことに幸せを感じる3児の母。ライターの仕事を通した出会いに敬意を示して、大好きな文章を紡ぎます。