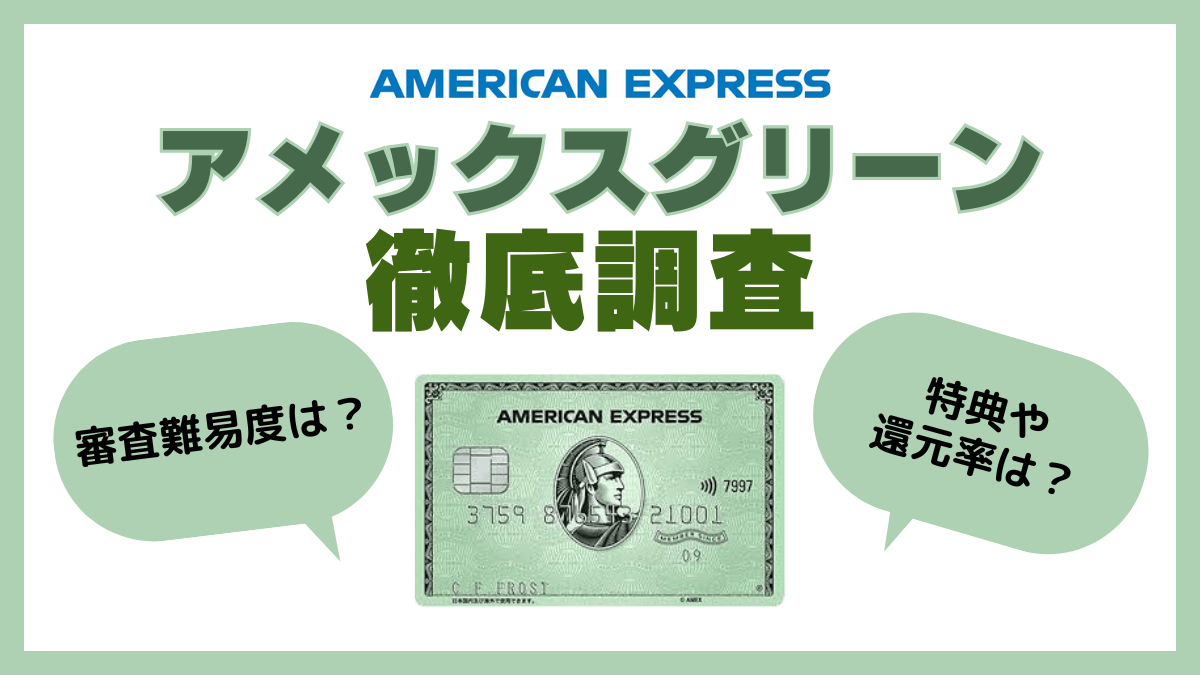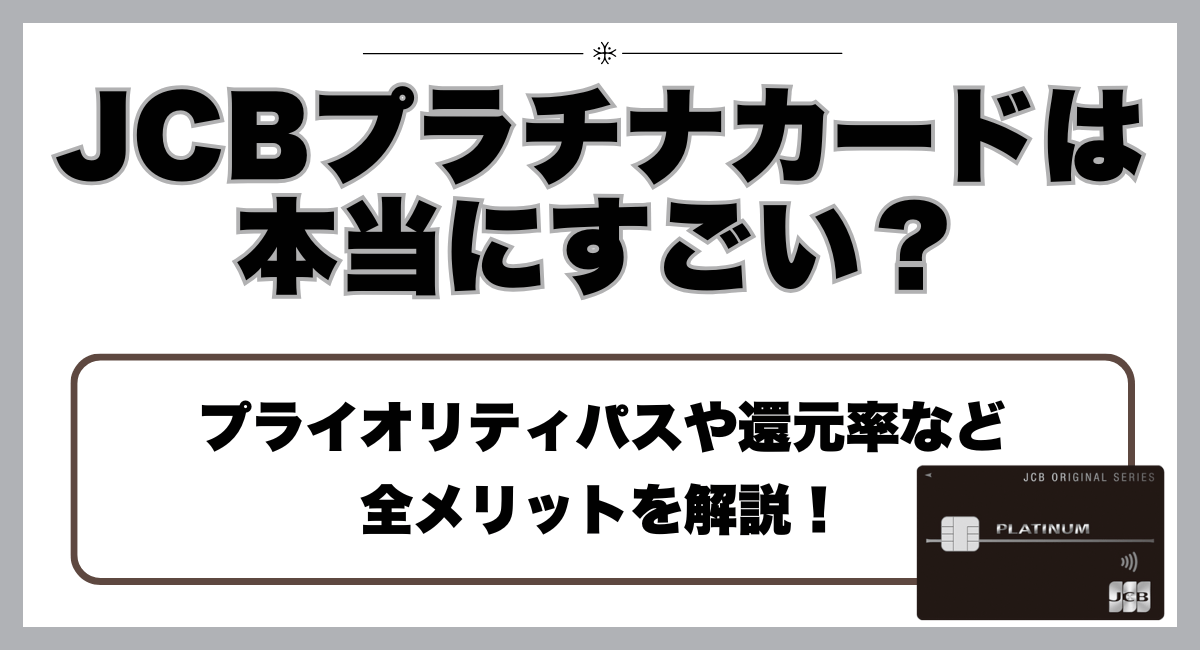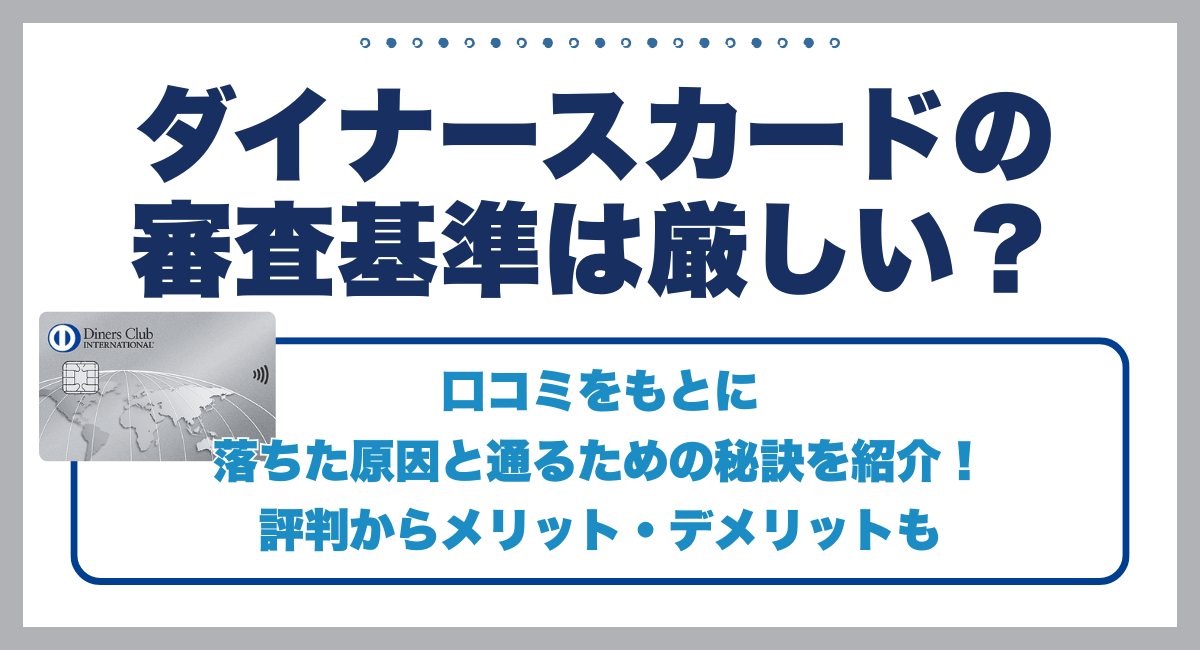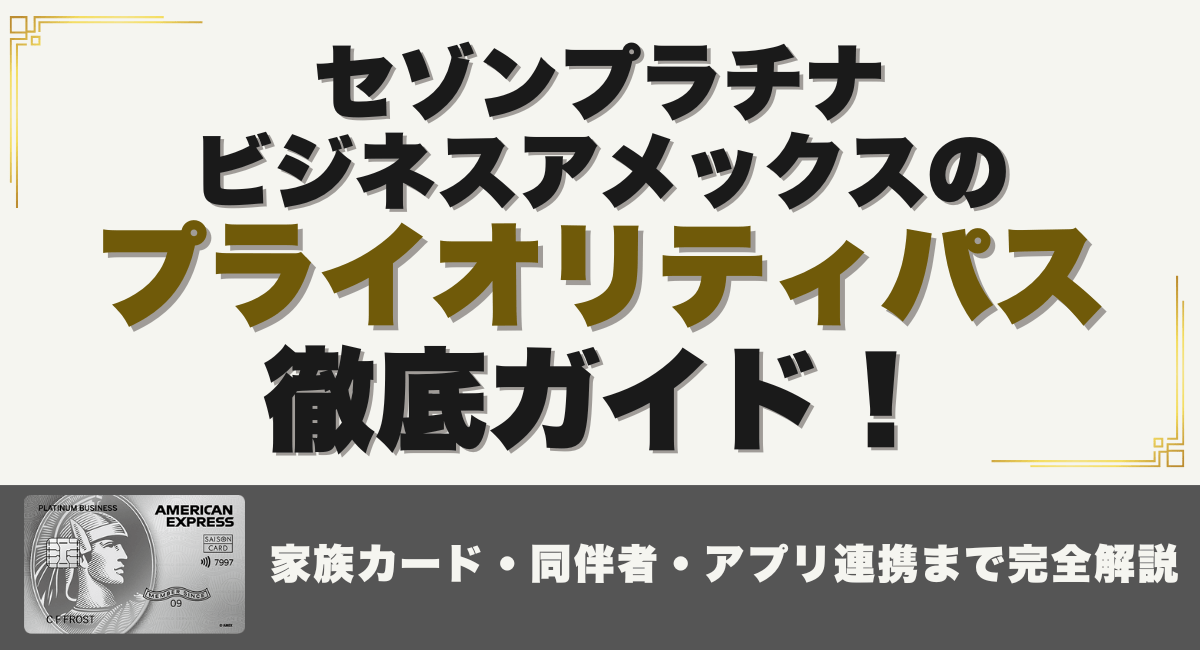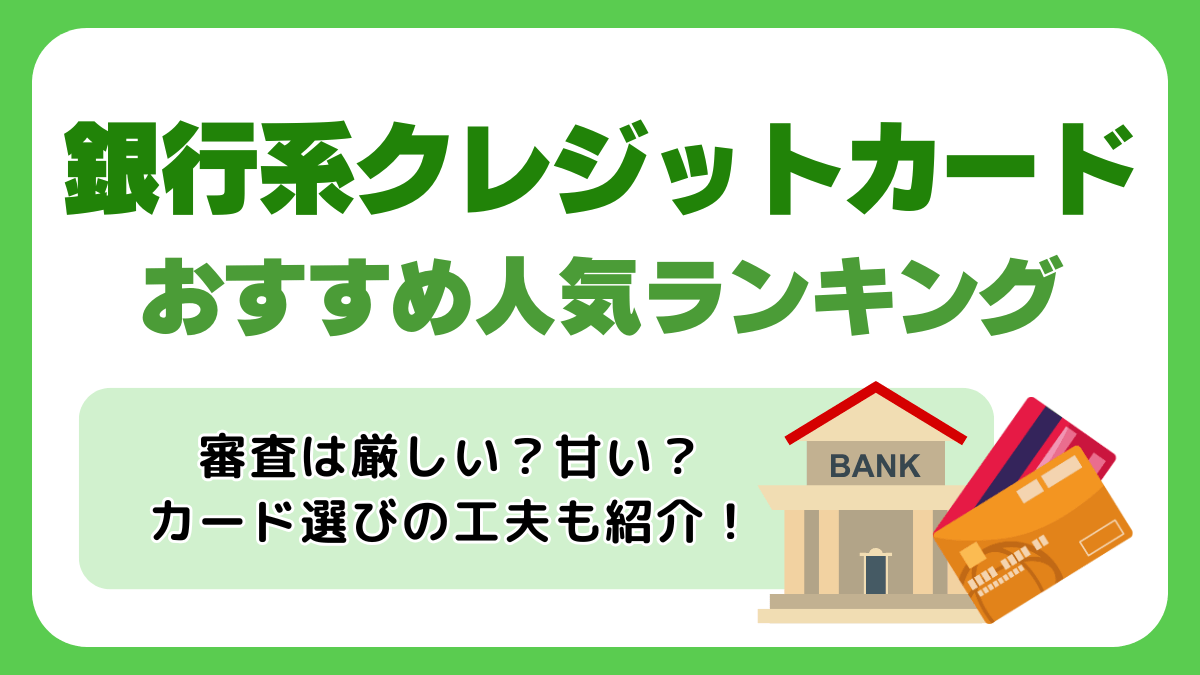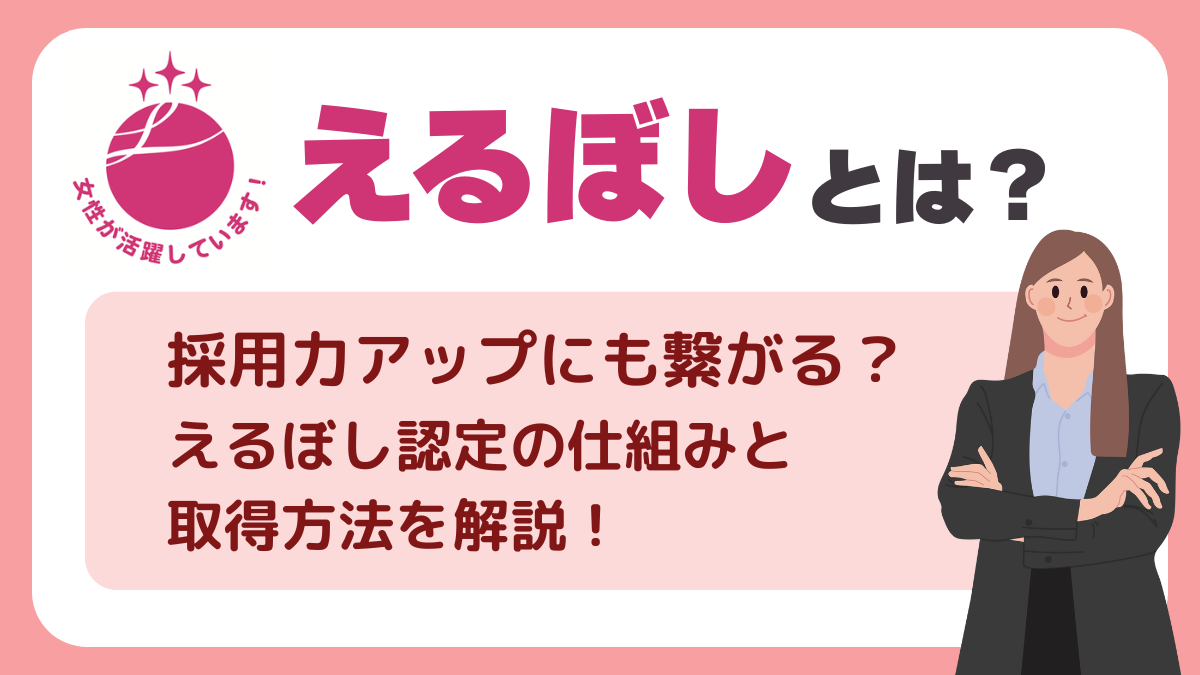
女性の活躍を推進する企業を認定する「えるぼし」を取得している数は、2023年8月末時点で2,000社を超えています。そのうち常時雇用する労働者300人以下の企業は、全体の約45%と半数近くであり、企業規模にかかわらず、認定取得に積極的に挑戦していることが分かります。
この背景には、人口減少に伴う人材不足など、中小企業が抱える課題があります。
この記事では、えるぼし認定・プラチナえるぼし認定とは何か、くるみんとの違い、認定基準について、メリット、取得する方法、取組事例、取得している企業一覧、SDGsとの関係を解説します。
目次
えるぼしとは
えるぼしとは、女性の活躍を推進する取り組み状況が優良である事業主を認定する制度です。もう少し踏み込んで説明すると、事業主は、女性活躍推進法に基づき、女性の職業生活での活躍を推進する取り組みを計画します。
そしてその内容を「一般事業主行動計画」にまとめ、都道府県労働局に届け出ます(常時雇用する労働者が101人以上の事業主は「義務」。100人以下は「努力義務」)。
そのうち、厚生労働省の定める基準に適合する事業主は、自ら申請することにより厚生労働大臣から「えるぼし認定」を受けられるのがこの制度です。
認定された事業主は、5つの基準のうち適合する項目数に応じて、認定マークを使用できます。
認定マーク「えるぼし」について※[i]
| 3段階目5つの基準をすべて満たす | |
| 2段階目5つの基準のうち3つまたは4つの基準を満たす | |
| 1段階目5つの基準のうち1つまたは2つの基準を満たす |
※いずれの段階も、一般事業主行動計画を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表する必要があります。
※1段階目、2段階目のえるぼし認定を受けた事業主は、満たさない項目に対して改善するための取り組みを行い、実施状況を毎年1回以上、「女性の活躍推進企業データベース」に公表しなければなりません。
えるぼしの「L(える)」には、Lady(女性)、Labour(働く、取り組む)、Lead(お手本)などの意味があります。また円の形が表現しているのは、企業や社会です。えるぼしのマークは、企業や社会で力強く活躍する女性をイメージしてデザインされています。※[ii]
認定マーク「えるぼし」の使用例
また、認定マークは次に挙げるものに表示できます。
- 商品
- 公告
- 取引に用いる書類
- ハローワークなどの求人票
- 自社のホームページや営業所・事業所など
えるぼしが創設された背景
えるぼしは、2016年に施行された「女性活躍推進法」(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)に基づいて創設されました。この法律の制定の背景には、人口減少に伴う労働力不足や人材の多様性の確保などが不可欠になっている日本の現状があります。
また企業にとっても、人材の確保や定着、社員のモチベーションの向上は重要な課題です。えるぼしは、国や企業の抱える課題への1つの対策と言えるでしょう。
女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)とは
女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図ることを目的とした法律。
次の3つを基本原則とする。
- 女性の採用・昇進などの機会を積極的に提供・活用すること。また、性別による固定的役割分担などが職場に及ぼす影響に配慮すること
- 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境を整備し、円滑で継続的な両立を可能にすること
- 女性の職業生活と家庭生活との両立について、本人の意思が尊重されること
プラチナえるぼしとは

プラチナえるぼし認定マーク
プラチナえるぼしとは、えるぼし認定を受けた事業主のうち、一定の要件を満たした上で特に優良であると認められた事業主に与えられる認定です。
えるぼし認定で求められる基準のほかに、3つの要件を満たすことで取得でき、えるぼしより多くのメリットを受けられることが特長です。
詳細は後述の「プラチナえるぼし認定基準について」「えるぼし認定・プラチナえるぼし認定を受けるメリット」にて解説しています。
くるみんとの違い
| 「トライくるみん」 | 「くるみん」 | 「プラチナくるみん」 |
※くるみんマークには、認定基準のレベルにより3つの種類があります。(「くるみん」という愛称は、赤ちゃんが大事に包まれる「おくるみ」や「職場ぐるみ・会社ぐるみ」で子どもの育成に取り組む、子どもが優しく「くるまれている」という意味が込められています。)
「えるぼし」とよく混同される制度に「くるみん」があります。くるみんは、「子育てサポート企業」を厚生労働大臣が認定する制度です。えるぼしと同様に、「一般事業主行動計画」を都道府県労働局に届け出た上で一定の基準を満たした企業は、自ら申請することにより認定を受けられます。
そして、商品や求人広告などに「くるみんマーク」を表示できます。「えるぼし」と「くるみん」の違いを次の表にまとめました。※[iii]
■「えるぼし」と「くるみん」
| 認定の種類 | えるぼし | くるみん |
|---|---|---|
| 認定対象企業 | 女性の活躍を推進する取り組みを実施している企業 | 子育てをサポートしている企業 |
| 根拠となる法律 | 女性活躍推進法 | 次世代育成支援対策推進法 |
| 目的 | 女性の職業生活における活躍を推進することに加え、少子高齢化をはじめとした社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現すること | 次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会を形成すること |
| 認定基準の一例 | 「男女別の採用における競争倍率が同程度であること」ほか | 「男性労働者の育児休業取得率の基準を満たしていること」ほか |
| 一般事業主行動計画の公表媒体 | 女性の活躍推進企業データベース | 両立支援のひろば |
えるぼしは「女性の活躍」、くるみんは「子育てサポート」を推進する企業を認定する制度です。いずれの認定も職場での働きやすさをアピールできるため、両方を取得している企業も少なくありません。
【関連記事】くるみん認定企業とは?メリットや認定条件、取り組み事例も
えるぼし認定基準について
えるぼしの認定基準には、5つの評価項目が設けられています。
- 採用
- 継続就業
- 労働時間等の働き⽅
- 管理職⽐率
- 多様なキャリアコース
これらのうちの最低1項目を満たせば、1段階目のえるぼし認定を受けることができます。各項目の概要を見ていきましょう。(参照元:厚生労働省「女性活躍推進法に基づく『えるぼし認定』『プラチナえるぼし認定』のご案内」)
採用
男⼥別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること
(※)直近3事業年度の平均した「採用における⼥性の競争倍率×0.8」が、直近3事業年度の平均した「採用における男性の競争倍率」よりも雇用管理区分*ごとにそれぞれ低いこと。
| *雇用管理区分の例:総合職(事務系)、総合職(技術系)、一般職(事務系)、契約社員、パートタイム労働者/総合職、エリア総合職、一般職 / 事務職、技術職、専門職、現業職 など) |
または、直近の事業年度において、次の①と②の両⽅に該当すること
- 正社員に占める⼥性労働者の割合が、産業ごとの平均値(平均値が4割を超える合は4割)以上※であること。
- 正社員の基幹的な雇用管理区分における⼥性労働者の割合が、産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること。
※産業ごとの平均値は、厚生労働省が公表している「女性活躍推進法に基づく認定制度に係る基準における平均値(適用:令和5年7月1日~令和6年6月30日)」で確認できます。
(※)正社員に雇用管理区分を設定していない場合は、①のみに該当すれば良い。
継続就業
直近の事業年度において、次の①と②のいずれかに該当すること
①「⼥性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること。
(※)期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。
②「⼥性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること。
(※)新規学卒採用者などとして雇い入れた労働者であって、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。
(※)新規学卒採用者などとして雇い入れた労働者であって、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。
①②を算出することができない場合は、直近の事業年度において、正社員の⼥性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上※であること
※「女性活躍推進法に基づく認定制度に係る基準における平均値(適用:令和5年7月1日~令和6年6月30日)」
労働時間等の働き⽅
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働、および法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各⽉ごとにすべて45時間未満であること
- 「各⽉の対象労働者の(法定時間外労働+法定休日労働)の総時間数の合計」÷「対象労働者数」 < 45 時間
これが難しい場合は、
- [「各⽉の対象労働者の総労働時間数の合計」-「各⽉の法定労働時間の合計=(40×各⽉の日数÷7)×対象労働者数」] ÷「対象労働者数」< 45 時間
管理職⽐率
直近の事業年度において、管理職に占める⼥性労働者の割合が産業ごと※の平均値以上であること
または、「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課⻑級に昇進した⼥性労働者の割合」÷「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課⻑級に昇進した男性労働者の割合」が8割以上であること
※「女性活躍推進法に基づく認定制度に係る基準における平均値(適用:令和5年7月1日~令和6年6月30日)」
多様なキャリアコース
直近の3事業年度のうち、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は2項目以上(非正社員がいる場合は必ずアを含むこと)、300人以下は1項目以上の実績を有すること
- ア ⼥性の非正社員から正社員への転換
- イ ⼥性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
- ウ 過去に在籍した⼥性の正社員としての再雇用
- エ おおむね30歳以上の⼥性の正社員としての採用
これら5つの評価項目のほかにも、
- 事業主⾏動計画策定指針に即して適切な一般事業主⾏動計画を定める
- 策定した一般事業主⾏動計画について、適切に労働者への周知および外部公表する
などの基準があります。
プラチナえるぼし認定基準について
プラチナえるぼしの認定基準は、えるぼしの評価項目と同じですが、「2.継続就業」「4.管理職比率」のみ内容が異なります。詳しく見ていきましょう。
採用
⼥別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること
(※)直近3事業年度の平均した「採用における⼥性の競争倍率×0.8」が、直近3事業年度の平均した「採用における男性の競争倍率」よりも雇用管理区分*ごとにそれぞれ低いこと。
| *雇用管理区分の例:総合職(事務系)、総合職(技術系)、一般職(事務系)、契約社員、パートタイム労働者/総合職、エリア総合職、一般職 / 事務職、技術職、専門職、現業職 など) |
または、直近の事業年度において、次の①と②の両⽅に該当すること
- 正社員に占める⼥性労働者の割合が、産業ごとの平均値(平均値が4割を超える合は4割)以上※であること。
- 正社員の基幹的な雇用管理区分における⼥性労働者の割合が、産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること。
※産業ごとの平均値は、厚生労働省が公表している「女性活躍推進法に基づく認定制度に係る基準における平均値(適用:令和5年7月1日~令和6年6月30日)」で確認できます。
(※)正社員に雇用管理区分を設定していない場合は、①のみに該当すれば良い。
継続就業
直近の事業年度において、次の①と②のいずれかに該当すること
①「⼥性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること
(※)期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。
②「⼥性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ9割以上であること
(※)新規学卒採用者などとして雇い入れた労働者であって、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。
① ②を算出できない場合は、直近の事業年度において、正社員の⼥性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上※であること
※「女性活躍推進法に基づく認定制度に係る基準における平均値(適用:令和5年7月1日~令和6年6月30日)」
労働時間等の働き⽅
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働、および法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各⽉ごとにすべて45時間未満であること
- 「各⽉の対象労働者の(法定時間外労働+法定休日労働)の総時間数の合計」÷「対象労働者数」 < 45 時間
これが難しい場合は、
- [「各⽉の対象労働者の総労働時間数の合計」-「各⽉の法定労働時間の合計=(40×各⽉の日数÷7)×対象労働者数」] ÷「対象労働者数」< 45 時間
管理職比率
直近の事業年度において、管理職に占める⼥性労働者の割合が産業ごとの平均値の1.5倍以上であること
ただし、1.5倍後の数字が15%以下の場合は、管理職に占める⼥性労働者の割合が15%以上(※)であること
(※)「直近3事業年度の平均した1つ下位の職域から課⻑級に昇進した⼥性労働者の割合」が「直近3事業年度の平均した1つ下位の職域から課⻑級に昇進した男性労働者の割合」以上である場合は、産業計の平均値以上で可。
40%以上の場合は、
- 正社員に占める⼥性⽐率の8割の値
- 40%のいずれか大きい値以上
であること
多様なキャリアコース
えるぼし認定と同じ
これらの評価項目のほかにも、次のような基準があります。
- 策定した一般事業主行動計画に基づく取り組みを実施し、当該行動計画に定めた目標を達成する
- 男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任する
- 女性活躍推進法に基づく情報公表項目のうち、8項目以上を公表する
- 雇用管理区分ごとの労働者について男⼥の賃⾦差異の状況について把握するなど
えるぼし・プラチナえるぼしは、女性が企業で活躍するためのさまざまな基準が設定されています。企業がこれらの基準を満たすには、新しい取り組みが必要になることもあるでしょう。
それでは、企業にとってえるぼし・プラチナえるぼし認定を受けるメリットにはどのようなものがあるかを次に見ていきましょう。
えるぼし認定・プラチナえるぼし認定を受けるメリット
えるぼし認定・プラチナえるぼし認定を受けるメリットは、主に4つあります。
優秀な人材の確保につながる
1つ目のメリットは、優秀な人材の確保につながることです。えるぼし認定・プラチナえるぼし認定を受けると、商品や求人広告などに認定マークを使用できるほか、厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」に認定企業として情報が掲載されます。
これらの情報は、求職者が企業を選択する際の有効な判断材料になるでしょう。また、女性が活躍できる働きやすい企業として魅力を発信することで、応募者の増加も期待できます。
公共調達において加点評価を受けられる
2つ目のメリットは、総合評価落札方式や企画競争による公共調達において加点評価を受けられることです。具体的な加点数については各調達によって異なるので、問い合わせる必要があります。
配点は、「プラチナえるぼし>えるぼし(3段階目)>えるぼし(2段階目)>えるぼし(1段階目)」と、段階が上がるごとに高くなる傾向にあるようです。公共調達の案件が多い企業には、魅力的なメリットと言えるでしょう。
日本政策金融公庫による融資を低金利で受けられる
3つ目のメリットは、日本政策金融公庫の「働き⽅改⾰推進⽀援資⾦(企業活⼒強貸付)」を通常よりも低金利で受けられることです。働き方改革推進支援資金は、非正規雇用の処遇改善などに取り組む中小企業者を支援する目的で創設されました。
取り組む内容によって融資の金額や利率が異なります(詳しくは、日本政策金融公庫のサイトで確認できます)。
※えるぼし認定・プラチナえるぼし認定を受けた事業主の具体的な金利の利率は、問い合わせが必要です。
企業イメージが向上する
4つ目のメリットは、企業イメージが向上することです。えるぼし認定・プラチナえるぼし認定を受けることで、ダイバーシティ(多様性)や働き方改革を推進している企業であることを表明できます。
企業が社会的な責任を果たすことで、ステークホルダーなど外部からの信頼を獲得できます。さらに、企業の社会的な取り組みを評価されることで、ESG投資の呼び込みにつながる可能性もあるでしょう。
えるぼし認定・プラチナえるぼし認定を受けるデメリット
えるぼし認定やプラチナえるぼし認定は多くのメリットがありますが、一方で企業にとっての負担や課題もあります。ここでは、取得に伴う主なデメリットについて解説します。
申請準備に時間とコストがかかる
えるぼし認定を受けるには、女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定・届出に加え、取り組み内容を証明する各種書類の整備・提出が必要です。
これには担当者の配置や全社的な情報収集、評価体制の整備などが伴い、特に中小企業では大きな負担となることもあります。
また、申請プロセスに不慣れな場合は、外部コンサルタントの活用や書類作成のための追加費用も発生しがちです。結果的に、時間的・人的・経済的コストが予想以上にかかる点は、取得を検討するうえでの懸念材料となります。
基準達成のハードルが高い
えるぼし認定には5つの評価項目があり、プラチナえるぼしでは全ての基準を高い水準で満たす必要があります。たとえば、女性管理職の割合や採用比率、働き方改革の実績などは、業界特性や企業規模によって達成が難しい場合もあります。
特に歴史ある企業や男性社員比率が高い業界では、短期間で数値目標を達成するのが困難であり、制度そのものに不公平感を感じるケースもあります。
認定を目指すために無理な数値目標を掲げてしまうと、現場の負担や形骸化した取り組みを生むリスクも否定できません。
取得後の継続的な対応が必要
えるぼしやプラチナえるぼしの認定は一度取得して終わりではなく、その後も定期的な評価や改善が求められます。
特にプラチナ認定の場合、より高いレベルでの継続的な実績維持が必要とされるため、制度の更新・改善、職場環境の整備、人事評価や研修制度の強化など多岐にわたる対応が求められます。
また、認定を受けたことにより社外からの期待や監視の目が強まることもあり、取り組みの停滞がブランドイメージの低下につながる恐れもあります。継続的な体制づくりができないと、企業にとって大きな負担となる場合があります。
えるぼし認定を取得する方法
えるぼし認定を取得するための申請方法について解説します。取得後の更新についても確認していきましょう。
申請方法
申請には、⑴~⑶までを順に進めていきます。
⑴ 一般事業主⾏動計画の策定・届出
はじめに、3つのステップにより一般事業主⾏動計画の策定・届出を行います。
ステップ1:状況の把握と課題分析
【現状の把握】⾃社の⼥性の活躍に関する以下の状況を把握します。
- 雇用管理区分ごとの女性比率( %)または採用者に占める女性比率( %)
- 雇用管理区分ごとの勤続年数の男女差( 年)
- 男女の平均残業時間数(毎月 時間)
- 管理職(課長相当職)に占める女性割合( %)
- 男女の賃金の差異( %)※301人以上の企業のみ
【課題分析】把握した状況から⾃社の課題を分析します。
| 例えば「管理職の女性が少ない」など |
ステップ2:一般事業主⾏動計画の策定、社内周知、外部公表
【行動計画の策定】ステップ1を踏まえて、次の項目を盛り込んだ一般事業主⾏動計画を策定します。
| (a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期 |
※常時雇用する労働者数(301人以上か)により内容が異なるので、詳しくは厚生労働省「女性活躍推進法に基づく『えるぼし認定』『プラチナえるぼし認定』のご案内」を参照してください。
【社内周知・公表】策定した一般事業主⾏動計画を社内の労働者に周知し、厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページなどの外部に公表します。
ステップ3:一般事業主⾏動計画を策定した旨の届出
【届出】一般事業主⾏動計画を策定した旨を、定められた書式により都道府県労働局へ届け出ます。
⑵ ⼥性の活躍に関する情報公表
次に、⼥性の活躍に関する情報をまとめて、厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページに公表します。
⼥性の活躍に関する情報は、あらかじめ決められている①⼥性労働者に対する職業⽣活に関する機会の提供、②職業⽣活と家庭⽣活との両⽴に資する雇用環境の整備、の2区分に含まれる複数の項目の中から選択します。
常時雇用する労働者数により公表する項目数が異なるので、詳しくは厚生労働省「女性活躍推進法に基づく『えるぼし認定』『プラチナえるぼし認定』のご案内」を参照してください。
⑶ えるぼし認定申請
最後に、えるぼし認定の申請をします。申請に必要な書類は、次の通りです。
- えるぼし認定の申請書類
- 基準適合一般事業主認定申請書
- 認定申請関係書類(実績を明らかにする書類)
- 関係法令遵守状況報告書
- その他、上記の書類に記載された添付書類
申請書類のデータは、厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」から入手できます。
更新について
えるぼしを取得したら、毎年1回以上、「女性の活躍推進企業データベース」に掲載された実績や取り組みの状況を更新しなければなりません。これを行うことで、えるぼし認定を継続することができます。
もし、認定取得時以降2年にわたり公表をしなかったり、基準に適合しなくなったと認められたりした場合には、認定を取り消されるので注意が必要です。取り消された後の3年間は、認定の申請ができません。
えるぼし認定までの流れ
えるぼし認定までの流れは、以下のようなステップで進みます。
女性活躍推進法に基づき、「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局に届け出ます。計画には、女性の採用・登用・継続就業などに関する数値目標や取り組み内容を盛り込みます。
行動計画に基づいた社内での取り組みを実施し、一定期間の実績を積み上げます。えるぼし認定の申請には、各評価項目(採用・継続就業・労働時間・管理職比率・多様なキャリア)の要件を満たす必要があります。
必要な書類(申請書、実績報告書、添付資料など)を準備し、管轄の労働局に提出します。内容が認定基準を満たしているかが審査されます。
労働局による書類審査が行われ、不備があれば修正対応を求められる場合があります。必要に応じて、ヒアリングや追加資料の提出も求められます。
審査を通過すると、厚生労働大臣から「えるぼし」または「プラチナえるぼし」の認定を受けます。認定企業は厚労省のHPに一覧として掲載され、認定マークの使用が可能になります。
認定を目指す企業は、事前準備から申請後の対応までを計画的に行うことが重要です。
えるぼし認定までの期間
えるぼし認定までの期間は、企業の準備状況や審査内容によって異なりますが、一般的には半年から1年程度かかるとされています。
まず、女性活躍推進法に基づいた「一般事業主行動計画」の策定と届出を行い、その後、一定期間の実績を積み上げたうえで申請書類を提出します。
書類審査や必要に応じたヒアリングを経て、基準を満たしていれば認定が付与されます。スムーズに進めるには、事前準備と計画的な取り組みが重要です。
えるぼし認定を取得している企業の取組事例
この章では、えるぼし認定を取得している企業の事例を紹介します。厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」では、女性活躍・両立支援に積極的に取り組む企業の事例集を公開しています。
えるぼし認定を取得した企業を業種や従業員規模から検索することが可能です。ここでは、その中から2社の取り組みを取り上げます。
株式会社シニアライフアシスト(医療、福祉)
香川県高松市の株式会社シニアライフアシストは、介護付有料老人ホーム・デイサービスを運営する従業員数99名の会社です。「えるぼし(3段階)」のほか、「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」も取得しています。(2022年度取材時)
女性活躍・両立支援に取り組むきっかけは、介護スタッフの不足です。良い人材を確保するために、働く環境を整えることが課題でした。そこでさまざまな制度を整えてきた結果、設立当初は30~40%だった離職率は、10%前後に改善していると言います。
また育児短時間勤務制度においても、出勤時刻と退勤時刻を30分刻みで組み合わせ合計15種類の勤務パターンを用意しています。365日24時間営業している老人ホームはなかなか取得が難しい長期休暇も、毎月1人ずつ1週間の連続休暇を実施。
女性のキャリアサポートを積極的に行っています。
名古屋眼鏡株式会社(卸売業、小売業)

愛知県名古屋市の名古屋眼鏡株式会社は、正社員59人(うち女性32人)、パート社員52人(うち女性37人)が在籍する眼鏡卸売業者です。
「えるぼし(3段階)」、「プラチナえるぼし」のほか、「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」も取得しています。(2020年度執筆時)
女性活躍・両立支援に取り組むきっかけは、女性社員が結婚や出産と同時に退職する人が多い現状でした。2006年に初めて産休・育休後も働きたいという女性が現れたため、環境づくりに着手することになったと言います。
具体的には、小チーム制を導入してチームリーダーというポジションをつくることにより女性管理職を増やしました。また、短時間勤務者に不利にならない評価基準を制定するなど、制度の整備を行っています。
その結果、係長級に占める女性の割合は55.6%に達しています。
えるぼし認定・プラチナえるぼし認定企業一覧
えるぼし認定・プラチナえるぼし認定を取得している企業一覧は、厚生労働省の「女性活躍推進法への取組状況(一般事業主行動計画策定届出・「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定状況)」に公開されています。
| 認定区分 | 企業名 | 業種 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| プラチナえるぼし | 株式会社三井住友銀行 | 金融 | 長時間労働の是正や女性管理職育成に注力 |
| プラチナえるぼし | 味の素株式会社 | 食品 | 育児・介護と両立できる柔軟な制度が充実 |
| プラチナえるぼし | パナソニック株式会社 | 電機 | テレワーク・時短勤務制度を積極活用 |
| プラチナえるぼし | 花王株式会社 | 化学 | 性別を問わず多様なキャリア形成を支援 |
| えるぼし(3段階目) | 株式会社資生堂 | 化粧品 | 女性管理職比率向上や柔軟な働き方を推進 |
| えるぼし(3段階目) | 日本航空株式会社(JAL) | 航空 | 女性パイロット登用・ダイバーシティ推進 |
| えるぼし(2段階目) | 株式会社NTTドコモ | 通信 | 女性活躍推進研修や在宅勤務制度を導入 |
| えるぼし(1段階目) | 東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本) | 鉄道 | 女性の採用拡大や職場環境整備を推進 |
2023年8月末時点で、えるぼし認定を取得している企業数は2,360社、プラチナえるぼし認定は41社です(企業の意向により公表していない企業は除く)。
そのうち、300人以下の企業は約45%と半数近くに上っています。従業員規模の小さい企業においても、認定取得に挑戦しているのです。
えるぼし認定に関するよくある質問
えるぼし認定を目指す企業や関心を持つ方からは、「認定基準は?」「くるみんとの違いは?」など多くの疑問が寄せられます。ここでは、よくある質問にわかりやすく答えます。
えるぼし認定は誰が申請できるの?
えるぼし認定は、女性活躍推進法に基づき行動計画を策定し、労働局に届け出ている企業であれば申請できます。大企業だけでなく中小企業も対象で、規模に関わらず取り組みが評価されれば認定される仕組みです。
例えば、女性の採用比率や管理職登用、働きやすさを改善してきた実績が評価されます。つまり「社会的に影響力のある大企業しか取れない」というものではなく、多様な企業に門戸が開かれている制度です。
えるぼし認定を取得するまでにどのくらい時間がかかる?
認定までの期間は企業の準備状況によって異なります。行動計画を立てただけでは認定されず、実際に施策を実行し成果を示す必要があるため、数か月から1年程度かかるケースが多いです。
例えば、在宅勤務制度や育児休暇の利用率改善といった取り組みを実行し、その結果をデータで示すことが求められます。計画・実行・検証という流れを経るため、短期間での取得は難しいですが、準備が整っていればスムーズに進められます。
えるぼし認定を受けたら更新は必要?
えるぼし認定は一度取れば終わりではなく、継続的に基準を満たし続ける必要があります。一定期間ごとに企業の取り組み状況が確認され、改善が止まっていると更新が難しくなる場合もあります。
そのため、女性の活躍推進に関するデータを定期的に見直し、労働環境の改善を続けることが重要です。更新を重ねることで、単なる「取得企業」ではなく「持続的に改善している企業」として社会的な信頼を高める効果があります。
えるぼし認定とプラチナえるぼしの違いは?
えるぼし認定には1段階目から3段階目まであり、満たした基準の数に応じて評価されます。一方で、プラチナえるぼしは3段階を超える取り組みや成果を示し、最高水準の条件を満たした企業に与えられる認定です。
つまり、えるぼしが「段階的な評価」であるのに対し、プラチナは「持続的に高いレベルで実践している証」といえます。採用活動や企業ブランドの強化においては、プラチナを取得することでより高い評価を得やすいといった効果もあります。
認定を受けた企業はどこで確認できるの?
えるぼし認定やプラチナえるぼしを取得した企業は、厚生労働省の公式サイトに一覧として掲載されています。業種や所在地ごとに検索できるため、就職活動をする学生や転職希望者にとって有益な情報源となります。
また、企業にとっても「えるぼし認定企業」として公的に公表されることで、社会的な信頼を獲得できるメリットがあります。消費者や投資家にとっても企業選びの参考になるため、一覧の存在は重要な役割を果たしています。
えるぼし認定とSDGs
最後に、えるぼし認定とSDGsの関係について確認していきます。えるぼし認定は、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」、目標8「働きがいも経済成長も」、目標10「人や国の不平等をなくそう」に関係があります。
目標5「ジェンダー平等を実現しよう」目標10「人や国の不平等をなくそう」
目標5「ジェンダー平等を実現しよう」は、女性への差別をなくし、平等なリーダーシップの機会を確保することを目指しています。
また、目標10「人や国の不平等をなくそう」は、年齢や性別、人種、出自、経済的地位などにかかわらず、すべての人に社会的・経済的・政治的に参加できる力を与えることを掲げています。
えるぼし認定は、企業の中での女性の活躍を後押しする制度です。採用や昇進において平等な機会を提供することや、職場の働きやすさなどを実現することで、女性の活躍する場を作ることができます。
その結果、目標5や目標10のテーマである平等を実現できるでしょう。
目標8「働きがいも経済成長も」
目標8「働きがいも経済成長も」は、働きがいのある仕事を創出し、持続可能な経済成長を促進することを目標にしています。
えるぼし認定を取得することにより、働きやすさが改善したり、キャリアの形成を支援したりすることができれば、従業員のモチベーションも向上します。それは生産性の向上にもつながり、企業としての成長も期待できます。
まとめ
えるぼしは、女性の活躍を推進する取り組み状況が優良である事業主を認定する制度です。厚生労働省の定める基準を満たした事業主は、自ら申請することにより「えるぼし認定」を受けることができます。
認定を受けることで企業の積極的な取り組みを示すことができるため、優秀な人材の呼び込みができるほか、公共調達において加点評価をもらえたり、日本政策金融公庫による融資を低金利で受けられたりするなどのメリットがあります。
えるぼし認定を取得している企業は2,000社を超え、そのうち300人以下は約45%と半数近くに上ります。中小企業にとって、優秀な人材の確保は大きな課題です。
将来にわたり安定した企業活動を行う上で、えるぼし認定は、人材確保を有利に進めていく1つの手段になるでしょう。
※[i] 厚生労働省「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定の概要」
※[ii] 厚生労働省「女性活躍推進法認定マークの愛称を決定しました『えるぼし』」
※[iii] 厚生労働省「くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されました!新しい認定制度もスタートしました!」
この記事を書いた人
池田 さくら ライター
ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。
ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。