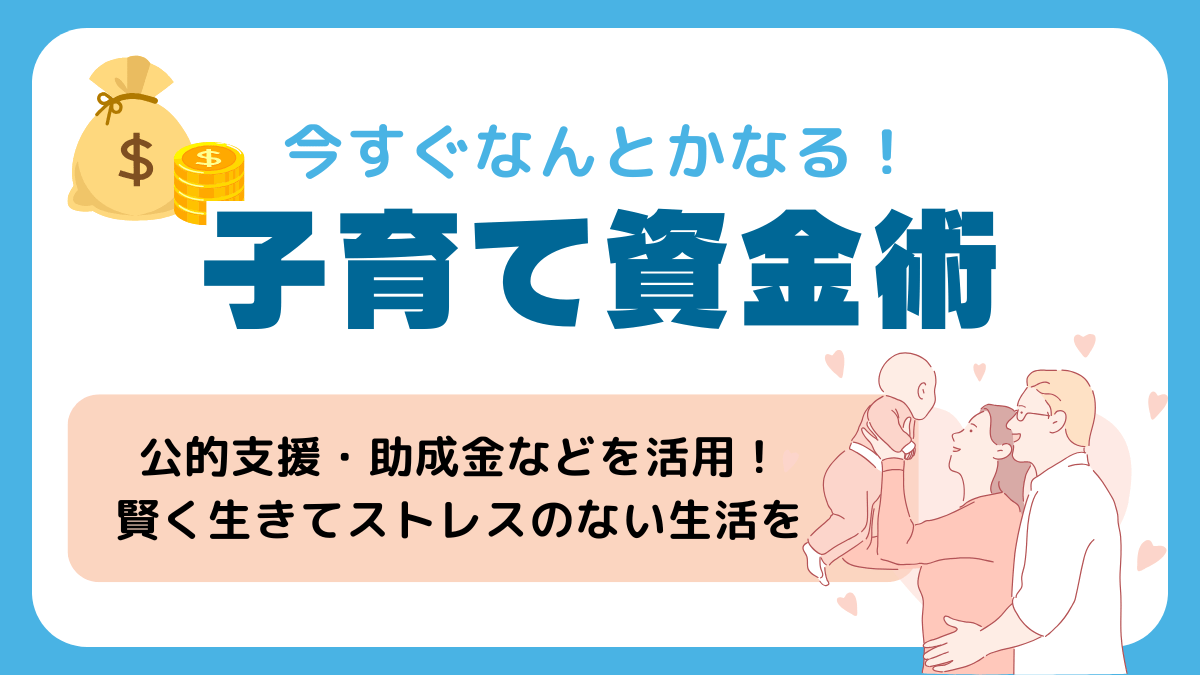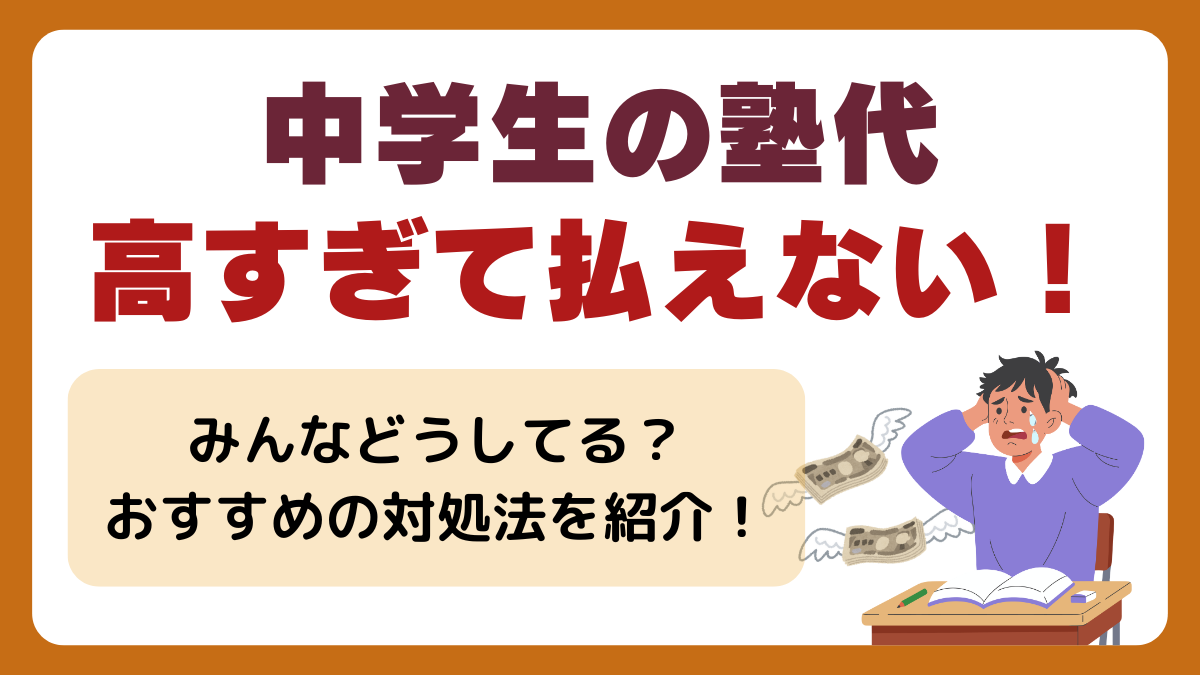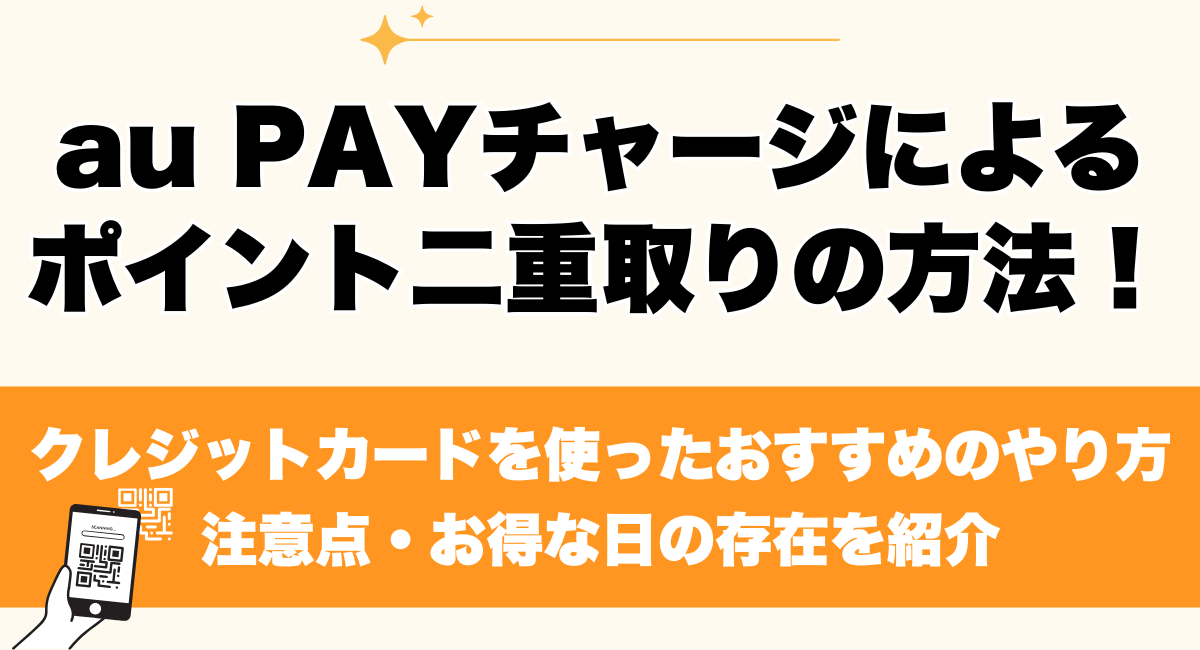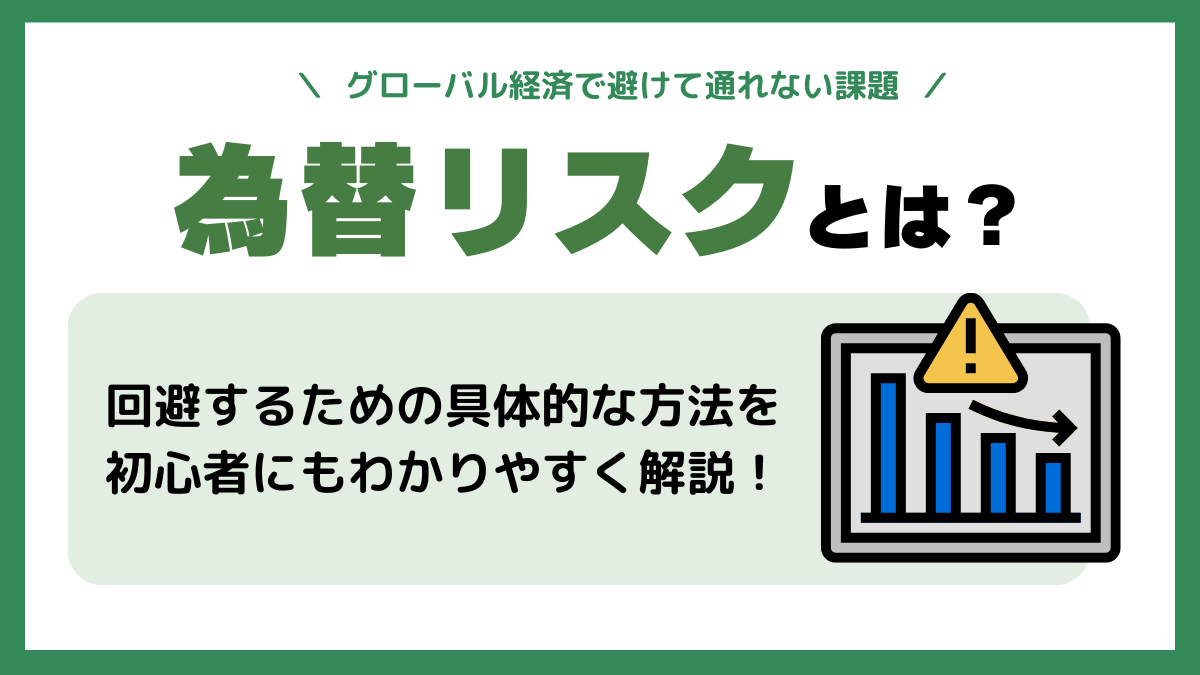
為替リスクは、グローバル経済の中で避けて通れない課題です。企業や個人投資家にとって、為替変動が資産や収益に与える影響は大きく、適切な対策が必要です。
NISAやiDeCoが注目される中、個人でも為替リスクとその対策について理解しておくことは、今後ますます重要になるでしょう。この記事では、為替リスクの種類や回避するための具体的な方法を、初心者にもわかりやすく解説します。
為替リスク管理の重要性を理解し、効果的な対策を考えましょう。
目次
為替リスクとは

為替リスクとは、円と外国通貨の為替相場の変動により、外貨建て資産の価値が変動する可能性のことです。国際取引や海外投資を行う企業や個人にとって、為替リスクへの考慮は欠かせません。
為替リスクを理解し、適切に管理することは、グローバル経済において成功を収めるための重要な鍵となります。
そもそも為替とは
為替とは、異なる国の通貨を交換する仕組みのことです。国際取引や海外旅行の際に不可欠な仕組みで、各国の経済状況や政治情勢によって常に変動しています。
【為替相場とは】

為替の変動要因
為替相場の変動にはさまざまな要因があります。主な要因として以下の3つが挙げられます。
- 金利差:各国の金利水準※の違い
- 貿易収支:輸出入のバランスが通貨の需要と供給に影響
- 物価変動:インフレ率の違いが通貨の相対的価値に影響
為替レートと実質為替レート
為替レートは、2つの異なる通貨間の交換比率を表します。一方、実質為替レートは、物価水準※の違いを考慮した為替レートで、国際競争力を測る指標として使用されます。
交易条件
交易条件とは、輸出品と輸入品の相対価格のことです。為替相場の変動は交易条件に影響を与え、国の経済厚生に大きな影響を及ぼす可能性があります。
例えば、円安が進行すると輸入品の価格が上昇し、同じ量の輸入品を購入するためにより多くの円が必要となります。これにより、国内の消費者の購買力が低下し、生活水準に影響を与える可能性があります
株式投資の主なリスクの1つ
株式投資にはさまざまなリスクが存在しますが、為替リスクもその1つです。特に外国株式に投資する場合、為替変動リスクに加えて、価格変動リスクや信用リスクなども考慮する必要があります。
【関連記事】【初心者向け】株式投資とは?仕組み・失敗しやすいポイントと始め方・おすすめの証券会社
為替リスクがもたらす影響
為替リスクは企業と個人の両方に影響を与えます。
- 企業:収益や競争力に直接的な影響
- 個人投資家:海外投資の収益性に大きく影響
為替リスクの種類
為替リスクには主に以下の3つの種類があります。
- 為替換算リスク:外貨建ての資産や負債の評価額が為替変動により変化するリスク
- 為替取引リスク:取引時と決済時の為替レートの違いによるリスク
- 為替経済性リスク:為替相場の変動が企業の競争力や生産構造に影響を与えるリスク
為替リスクは国際取引や投資において避けられない要素ですが、適切な理解と管理戦略を持つことで、そのリスクを軽減し、より安定した経済活動を行うことが可能です。
次の章では円高・円安について理解を深めていきましょう。*1)
円安と円高について

為替相場の変動は、私たちの日常生活や経済活動に大きな影響を与えます。円安と円高という2つの現象は、その影響の代表的な例です。
経済の動きを把握し、あなたの生活や投資判断に活かすために、ここで円安・円高について確認しておきましょう。
【関連記事】【小中学生でもわかる!】円安・円高とは?覚え方とそれぞれのメリット・デメリット・いつまで続くのか解説
円安とは
円安とは、外国通貨に対して日本円の価値が下がる現象です。対ドル相場では、1ドルと交換できる円の量が増えることを意味します。
例えば、1ドル=100円から1ドル=150円になった場合、「円安が進行した」と言えます。
円安のメリット
円安のメリットとしては、輸出企業の競争力向上が挙げられます。日本製品が海外で相対的に安くなるため、輸出が増加し、企業収益が改善する可能性があります。
また、インバウンド需要※の増加も期待できます。
円安のデメリット
一方、円安のデメリットとしては、輸入品の価格上昇があります。特に、エネルギーや原材料の輸入コストが上がることで、企業の生産コストが増加し、最終的に消費者物価の上昇につながる可能性があります。
円高とは
円高は円安とは逆の現象で、外国通貨に対して日本円の価値が上がることです。例えば、1ドル=150円から1ドル=100円になった場合、「円高が進行した」ことになります。
円高のメリット
円高のメリットには、輸入品の価格低下があります。円高の局面では、消費者は海外製品をより安く購入できるようになります。また、海外旅行や留学などの海外での支出が減少するため、個人の購買力が向上します。
円高のデメリット
円高のデメリットとしては、輸出企業の競争力低下が挙げられます。日本製品が海外で相対的に高くなるため、輸出が減少し、企業収益に悪影響を与える可能性があります。
【円安・円高】
| 円安 | 円高 | |
| 定義 | 外国通貨に対して円の価値が下がる | 外国通貨に対して円の価値が上がる |
| 例 | 1ドル=100円 → 1ドル=150円 | 1ドル=150円 → 1ドル=100円 |
| メリット | ・輸出企業の競争力向上 ・日本製品が海外で安くなる ・輸出増加の可能性 ・インバウンド需要の増加 | ・輸入品の価格低下 ・海外製品が安く購入可能 ・海外旅行・留学費用の減少 ・個人の購買力向上 |
| デメリット | ・輸入品の価格上昇 ・エネルギー・原材料の輸入コスト増加 ・企業の生産コスト増加 ・消費者物価の上昇の可能性 | ・輸出企業の競争力低下 ・日本製品が海外で高くなる ・輸出減少の可能性 ・企業収益への悪影響 |
円相場の現状
2025年2月現在、円相場は1ドル=150円台で推移しています。これは2カ月ぶりの円高水準となっています。
この背景には、日本銀行の金融政策に対する市場の見方の変化があります。日銀の次の利上げが早まるのではないかとの観測が広がり、円買いの動きが強まっています。
一方で、アメリカの雇用統計の発表を受けて、FRB(連邦準備制度理事会)が次回の利下げを見送るとの見方も強まっており、円相場の先行きは不透明な状況です。
円安と円高は、それぞれメリットとデメリットがあります。個人や企業は、これらの影響を理解し、適切な対策を講じることが重要です。*2)
【企業】為替リスクを回避するための対策

グローバル経済の中で事業を展開する企業にとって、為替リスクの管理は避けて通れない重要な課題です。為替相場の変動は企業の収益に大きな影響を与えるため、適切な対策を講じる必要があります。
企業が為替リスクを回避するための主な方法を紹介します。
為替ヘッジ:リスクを軽減する基本戦略
為替ヘッジとは、為替相場の変動によるリスクを軽減するための手法です。ヘッジは英語の「hedge」に由来し、直訳すると「避ける」という意味があります
為替ヘッジには、主に以下のような方法があります。
為替予約
為替予約は、将来の特定日の為替レートを事前に確定させる方法です。例えば、3ヶ月後に100万ドルの支払いがある場合、現時点で1ドル=150円の為替レートで予約しておけば、3ヶ月後の相場に関わらず150円で取引できます。
デリバティブ取引
デリバティブ取引では、先物取引やオプション取引などを利用して、為替リスクをヘッジします。デリバティブとは、「金融派生商品」とも呼ばれる、株式、債券、通貨、金利などの原資産(基礎となる金融商品)から派生した金融商品のことで、その価値は原資産の価格や指数に連動して決まります。代表的な例として以下の取引が挙げられます。
- 先物取引:将来の特定日に、事前に決めた価格で商品の売買を行う契約
- オプション取引:将来の特定日に、事前に決めた価格で商品を売買する権利を取引する
- スワップ取引:二者間で将来の特定の期間にわたり、キャッシュフローを交換する契約
これらは専門的な知識が必要なため、慎重に運用する必要があります。
為替ヘッジのメリットは、為替変動による損失を最小限に抑えられることです。一方、デメリットとしては、ヘッジにかかるコストや、円安時に得られる可能性のある為替差益を逃す可能性があることが挙げられます。
ナチュラルヘッジ:自然に為替リスクを減らす戦略
ナチュラルヘッジは、為替リスクを自然な形で相殺する戦略です。例えば、輸出企業が輸入も同時に行っている場合、輸出と輸入の通貨が同じであれば、為替変動の影響を最小限に抑えることができます。
例えば、アメリカから100ドルで部品を輸入し、完成品を150ドルでアメリカに輸出する場合を考えてみましょう。為替レートが変動しても、収益(150ドル)と費用(100ドル)の差額50ドルは変わりません。
このように、同じ通貨での取引を組み合わせることで、為替の変動による影響を自然に抑えられます。ナチュラルヘッジは特別な費用がかからず、簡単に実践できる点が大きなメリットです。
多通貨決済アカウントの活用
多通貨決済アカウント※を活用することで、複数の通貨での収入や支出を効率的に管理できます。このようなアカウントを利用することで、為替変動に左右されず、現地通貨での取引をスムーズに行えるメリットがあります。
多通貨口座のメリットには、
- 通貨換算コストの削減
- 透明性の高い手数料
- 運用の柔軟性
などがあります。例えば、海外のサプライヤーからのインボイス※の請求金額をすぐに支払う必要がある場合、多通貨口座を保有していれば素早く対応できます。
取引通貨の変更
円建てで取引を行うことで、為替リスクを回避する方法もあります。ただし、この方法は取引相手に為替リスクを負わせることになるため、自社製品が世界的に高いシェアを誇るなど、有利な立場にある場合に限られます。
決済時期の調整
決済時期や入金時期を相場状況に合わせて変更することでも、為替リスクをヘッジすることができます。これは「リーズ・アンド・ラグズ」※と呼ばれる手法で、為替相場の動向を見極めながら支払いや入金のタイミングを調整します。
為替マリーとネッティング
為替マリー※は、外貨建ての債権と債務を相殺する方法です。また、ネッティング※は同一企業内で債権と債務を相殺する手法です。これらの方法を用いることで、為替リスクにさらされる金額を減らすことができます。
企業が為替リスクを適切に管理することは、安定した経営と持続可能な成長のために欠かせません。これらの対策を適切に組み合わせ、自社の事業特性に合わせた為替リスク管理戦略を構築することが重要です。
また、為替リスク管理は単なるコスト削減だけでなく、企業の社会的責任の一環としても捉えるべきです。適切なリスク管理は、企業の安定性を高め、従業員の雇用を守り、地域経済の発展にも貢献します。
為替リスクを回避するための対策は、企業の規模や業種、取引内容によって最適な方法が異なります。個人レベルでも社会人として、これらの対策を理解することは、グローバルビジネスの現場で活躍するための重要なスキルとなるでしょう。*3)
【個人】為替リスクを回避するための対策

個人投資家にとって、為替リスクの理解と管理は資産運用の成功に不可欠です。NISAやiDeCoの普及により投資への関心が高まる中、個人でも為替変動が資産に与える影響を把握し、適切な対策をする必要があります。
個人投資家が為替リスクを回避するための実践的な方法の例を紹介します。
分散投資:リスクを分散させる基本戦略
分散投資は、為替リスクを含むさまざまな投資リスクを軽減するための最も基本的な戦略です。複数の通貨や資産クラスに投資することで、特定の通貨の変動による影響を緩和できます。
【実践方法の例】
- 複数の外貨建て資産に投資する
- 国内外の株式、債券、不動産など、異なる資産クラスを組み合わせる
- 新興国と先進国の通貨をバランスよく保有する
注意点
過度な分散は管理コストの増加や収益機会の損失につながる可能性があるため、自身の投資目的と許容リスクに応じて適切な分散度合いを決定することが重要です。
為替ヘッジ付き商品:為替変動の影響を抑える投資方法
為替ヘッジ付き商品は、為替変動による損失リスクを軽減しつつ、海外資産への投資機会を提供します。これらの商品は、ファンドマネージャーや自動化されたシステムなどが為替予約などの手法を用いて為替リスクを抑制します。
しかし、完全に為替リスクを排除できるわけではないことには留意しましょう。
【為替ヘッジ付き商品のメリット】
- 為替変動による損失リスクの軽減
- 海外資産への投資機会の確保
【為替ヘッジ付き商品のデメリット】
- ヘッジコストによる収益の減少
- 円安局面での為替差益機会の喪失
【実践方法の例】
- 為替ヘッジ付き外国債券ファンドへの投資
- 為替ヘッジ付き外国株式ETFの購入
外貨預金:円安時の資産運用として人気の方法
外貨預金は、円安局面で資産価値の保全や増加を目指す方法として注目されています。しかし、為替リスクや手数料に注意が必要です。
【外貨預金のメリット】
- 円安時の資産価値保全
- 外貨金利の享受
【外貨預金のデメリット】
- 為替変動リスク
- 手数料による実質的な収益減少
【実践方法の例】
- 複数通貨での外貨預金を行い、リスクを分散する
- ドル・コスト平均法を活用し、定期的に一定額を外貨に換金する
注意点
外貨預金は預金保険※の対象外であり、為替変動により元本割れのリスクがあることを認識しておく必要があります。
定期的な見直し:為替変動に合わせて投資を調整
為替市場は常に変動しているため、定期的なポートフォリオの見直しと調整が重要です。これにより、為替リスクを適切に管理し、投資目標の達成を目指すことができます。
【実践方法の例】
- 四半期ごとにポートフォリオの資産配分を確認し、必要に応じて調整する
- 大きな為替変動があった場合、臨時でポートフォリオを見直す
- リバランス※を行い、当初の資産配分比率を維持する
注意点
頻繁な売買は取引コストの増加につながるため、長期的な視点を持ちつつ、適度な頻度で見直しを行うことが重要です。
金融リテラシーの向上:自己防衛の基礎
為替リスクを含む投資リスクに適切に対処するためには、金融リテラシーの向上が不可欠です。基本的な金融知識を身につけることで、詐欺的な金融商品を見分け、自己防衛力を高めることができます。
【実践方法の例】
- 金融庁や日本証券業協会などの公的機関が提供する金融教育コンテンツを活用する
- 投資信託や株式投資の仕組みについて学ぶ
- 経済ニュースや金融市場の動向を定期的にチェックする
注意点
金融商品の複雑化が進む中、継続的な学習が重要です。また、自身の理解度を過信せず、必要に応じて専門家のアドバイスを求めることも検討しましょう。
為替リスクの回避は、個人投資家にとって重要な課題です。ここで紹介したような戦略を組み合わせ、自身の投資目標とリスク許容度に合わせた最適な方法を選択することが、長期的な資産形成の成功につながります。*4)
為替リスク対策とSDGs
為替リスク対策とSDGs(持続可能な開発目標)は、一見するとあまり関係がないように思えますが、実は深い関連性を持っています。どちらにも、長期的な視点で経済の安定と社会の持続可能性を追求するという共通点があるのです。
為替リスク対策は、SDGsの目標達成において重要な役割を担っています。適切な為替リスク管理は、企業の安定した経営を可能にし、雇用の創出や技術革新の促進につながります。また、個人投資家の資産保護にもつながり、経済的な安定性を高めることで、SDGsのさまざまな目標達成に、間接的にも貢献します。
為替リスク対策が特に貢献できるSDGs目標について見ていきましょう。
SDGs目標1:貧困をなくそう
為替リスク対策は、企業の安定した経営を支え、雇用の維持・創出に貢献します。これにより、人々の所得の安定化や向上が図られ、貧困削減につながります。
特に、新興国や途上国の企業が為替リスクを適切に管理することで、国際取引における損失を最小限に抑え、持続可能な経済成長を実現できます。
身近な例を挙げると、企業が為替リスクを適切に管理していない場合、急激な円高で輸出収入が減少し、工場の経営が悪化する可能性があります。その結果、従業員の給与カットや解雇につながり、地域の貧困率が上昇してしまいます。
SDGs目標8:働きがいも経済成長も
為替リスク対策は、企業の国際競争力を維持・向上させ、持続可能な経済成長を促進します。適切な為替リスク管理により、企業は安定した収益を確保し、雇用を維持・拡大することができます。
例えば、中小企業が為替予約を活用することで、為替変動による損失を回避し、安定した事業運営が可能になります。このような取り組みは、地域経済の活性化や雇用の創出にもつながり、働きがいのある人間らしい雇用の実現に貢献します。
SDGs目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう
為替リスク対策は、企業の研究開発投資や設備投資を安定させ、技術革新を促進します。為替変動による不確実性を軽減することで、企業は長期的な視点で投資を行うことができます。
具体的には、グローバル企業が為替ヘッジ戦略を適切に実施することで、海外での研究開発拠点の設立や最新技術の導入を積極的に進めることができます。これにより、産業の高度化や新たな技術革新が促進され、持続可能な産業への移行促進に貢献します。
SDGs目標17:パートナーシップで目標を達成しよう
為替リスク対策は、国際的な経済協力や投資を促進し、グローバルなパートナーシップの強化に貢献します。適切な為替リスク管理により、国境を越えた取引や投資が活性化し、持続可能な開発のための国際協力が促進されます。
例えば、国際機関や開発金融機関が為替リスクを適切に管理することで、途上国への安定した資金提供が可能になります。資産提供の安定化により、SDGs達成に向けた国際的な取り組みが強化され、グローバルなパートナーシップの促進につながります。
為替リスク対策とSDGsは、密接に結びついています。個人投資家や企業は、為替リスク対策の重要性を理解し、SDGsの達成に向けた取り組みを意識した経済活動を積極的に行うことが求められています。*5)
まとめ
為替リスク対策は、企業や個人の経済活動を安定させ、持続可能な社会の実現に貢献する重要な取り組みです。適切な為替リスク管理は、
- 企業の安定経営
- 雇用維持
- 個人の資産保護
- SDGsの目標達成
などにつながります。
2025年2月現在、ドル円相場は152円台半ばで推移しており、日銀の金融政策に関する発言を受けて円高傾向が続いています。また、トランプ次期大統領の政策に対する不確実性が、為替市場に影響を与えています。
為替リスクについて知識を深めることは、グローバル化が進む現代社会において、自身の経済活動を守り、より良い判断を行うためにとても重要です。私たちは、SDGsの実現に向けて、為替リスクを考慮した投資や消費行動をどのように実践できるでしょうか?
為替リスクへの理解を深め、適切な対策を講じることは、個人の経済的安定だけでなく、持続可能な社会の実現にもつながります。一人ひとりが金融リテラシーを高め、責任ある経済活動を行うことで、より良い未来を築いていくことができるのです。
今日から、為替リスクについて考え、新たな行動を起こしてみませんか?*6)
<参考・引用文献>
*1)為替リスクとは
J-FLEC『第4回 お金と経済』
J-FLEC『職域(若手層)向け社会人として知っておきたいお金の話』(2024年)
金融庁『家計の安定的な資産形成に必要な新 NISA 活用と金融能力向上』(2024年7月)
経済産業省『令和6年版 通商白書』(2024年7月)
日本証券業協会『為替変動リスク(かわせへんどうりすく)』
日本証券業協会『株式投資のリスクって何?』
日本証券業協会『FX(外国為替証拠金取引)(えふえっくす(がいこくかわせしょうこきんとりひき))』
JPX『東証為替ヘッジ指数の算出要領』(2025年1月)JPX『指数・指標の説明(ETN)』
JPX『「為替デリバティブが企業経営に及ぼすリスク」について考える』
東証マネ部!『為替変動のリスクの低減をめざすファンドの仕組みとは?』(2018年6月)
野村證券『為替リスク』
野村證券『リスクの種類』
国際通貨研究所『為替相場制度』
国際通貨研究所『外国為替リスク』
野村アセットマネジメント『為替とは?』
野村アセットマネジメント『為替変動の影響は、なくならないの?』
MUFG『円高が怖いなら為替ヘッジ!仕組みやポイントを解説』(2022年7月)
Yahoo!ファイナンス『FXに挑戦する前に! 為替取引のリスクを徹底解説』
【初心者向け】株式投資とは?仕組み・失敗しやすいポイントと始め方・おすすめの証券会社
*2)円安と円高について
【小中学生でもわかる!】円安・円高とは?覚え方とそれぞれのメリット・デメリット・いつまで続くのか解説
日本銀行『円高、円安とは何ですか?』
金融広報中央委員会『円高・円安とは』(2015年10月)
MUFG『外貨預金で円安になったら、円高になったら、どうなる?』
日本経済新聞『ドル円相場』(2025年2月)
日本銀行『為替介入(外国為替市場介入)とは何ですか? 誰が為替介入の実施を決定し、誰が為替介入を行うのですか?』
金融庁『わたしたちの生活と金融の働き』
金融庁『基礎から学べる金融ガイド』
経済産業省『第3節 為替動向と企業行動及び輸出数量への影響』
金融庁『投資入門』
全国銀行協会『円高、円安がわかる!為替相場のしくみと影響』
日本経済新聞『円安攻防24時 ドル円相場を動かすメカニズムは』(2024年5月)
日本経済新聞『為替相場の基本を知ろう どんな仕組みで動く?』(2024年3月)
日本銀行『)為替変動がわが国実体経済に与える影響 』(2022年1月)
厚生労働省『円高の進行と海外経済が国内雇用に与える影響』(2011年10月)
経済産業研究所『予想を超えた円高、円安における為替パススルーの非対称性:日本の機械輸出の事例』
経済産業省『為替レートの変化は、製造業の生産計画に影響を持つか?』(2017年1月)
NRI『円高・円安への変化が日本経済に与える影響』(2024年2月)
経済産業省『通商白書2023 我が国の貿易収支構造の強靱化に向けた課題』
Reuters『急速な円安進行「深刻な懸念」と神田財務官、必要に応じ対処と強調』(2024年6月)
*3)【企業】為替リスクを回避するための対策
財務省『企業の為替感応度と為替ヘッジ』(2022年6月)
財務省『外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン』
金融庁『為替取引分析業者向けの総合的な監督指針 基本的考え方』(2024年10月)
金融庁『為替取引分析業者向けの総合的な監督指針 II.為替取引分析業者の監督に係る事務処理上の留意点』(2024年10月)
金融庁『マネー・ローンダリング等対策の取組と課題』(2024年6月)
経済産業省『II リスクファイナンスの具体的な手法の紹介』
日本銀行『大手行の外貨流動性リスク管理の高度化に向けた取組み』(2024年5月)
日本貿易振興機構『2024年版 ジェトロ世界貿易投資報告』(2024年7月)
日本銀行『国際経済環境の変化と日本経済 ―論点整理―』(2024年2月)
内閣府『平成20年度 年次経済財政報告 第2節 日本企業のリスクヘッジ能力』(2008年)
経済産業研究所『為替エクスポージャーと為替リスクマネジメント-日本の輸出企業のケース-』
経済産業研究所『日本の輸出企業の貿易建値通貨選択と為替リスク管理の特徴-アンケート調査結果による-』
国際通貨研究所『外国為替リスク管理方法』
アライアンス・バーンスタイン『為替ヘッジ』
日本総研『中小企業財務の現状と求められる金融機関の役割』(2024年7月)
*4)【個人】為替リスクを回避するための対策
金融庁『外国為替証拠金取引について』(2020年2月)
金融庁『資産運用立国の実現』(2024年3月)
日本銀行『大学生の金融リテラシー向上と実践的投資スキル育成に向けた新たなアプローチ』
日本銀行『金融リテラシー~人生を豊かにする「お金」の知恵~』(2020年2月)
政府広報オンライン『「金融リテラシー」って何? 最低限身に付けておきたいお金の知識と判断力』(2024年10月)
政府広報オンライン『お金の勉強をしませんか?社会人として知っておきたいお金の話』(2024年12月)
厚生労働省『金融リテラシー・マップ』(2014年6月)
消費者庁『無登録業者との外国為替証拠金取引(FX)にご注意ください!』
金融広報中央委員会『金融商品をめぐる環境変化と適切な金融行動』(2015年)
金融広報中央委員会『金融商品の選び方・組合せ方』(2015年)
J-FLEC『リスクを抑えた運用方法を教えてください』
J-FLEC『第4回 お金と経済』
J-FLEC『第9回「お金をふやす」~「知っている」と「知らない」とでは~』
J-FLEC『第10回 投資信託の仕組みと特徴分散投資の意義』
三菱UFJ信託銀行『年金ポートフォリオにおける為替リスク管理の考え方』(2016年2月)
野村證券『投資信託のリスクと上手につきあうために』
NOMURAウェルスタイル『外国債券投資入門 もう過去のような円高には戻らない?大槻奈那氏が考える為替のゆくえ【後編】』(2024年7月)
日本経済新聞『個人の資産形成、金融教育・助言の重要性 識者に聞く』(2024年9月)
*5)為替リスク対策とSDGs
金融庁『今後の金融行政の方向性』(2025年1月)
金融庁『金融庁サステナブルファイナンス有識者会議 第四次報告書』(2024年7月)
金融庁『金融行政とSDGs』(2018年12月)
経済産業省『サステナブルファイナンス推進の取り組み』
経済産業省『世界の社会課題解決(SDGs)の促進に向けて 通商白書』(2020年)
環境省『持続可能な社会の形成に向けたお金の流れ』(2018年3月)
内閣府『日本証券業協会におけるSDGsにむけた取組み~サステナブルファイナンスの推進を中心に~』(2022年7月
国際協力機構『開発途上国での事業への民間資金動員と開発インパクトの創出』(2024年11月)
全国銀行協会『全銀協SDGレポート 2023‒2024』(2024年3月)
全国銀行協会『SDGs に金融はどう向き合うか』(2019年3月)
日本証券業協会『SDGsに貢献する金融商品について』
日本証券業協会『証券業界におけるSDGsへの取組み』
日本経済新聞『SDGsはアプローチを変えて』(2024年6月)
日本経済新聞『国連未来サミットでSDGs巻き返し 民間資金の動員探る』(2024年8月)
*6)まとめ
金融庁『金融経済教育等の推進に向けた調査等支援業務(職域等における金融経済教育を推進するための手法等に関する調査) 事業報告書』(2024年6月)
Reuters『BIS、トランプ政策巡る不確実性に警鐘 経済・中銀政策にリスク』(2025年2月)
Reuters『ドル上値重い展開、トランプ発言警戒続く 円高も限定か=来週の外為市場』(2025年2月)
東洋経済ONLINE『「トランプ2.0」でドル円相場はどこまで動くのか 日米金利差の縮小で2025年前半に円高局面も?』(2025年2月)
日本経済新聞『〈為替〉円、対ドルで大幅上昇』(2025年2月)
日本経済新聞『外為17時 円相場、3日続伸 152円台半ば 日銀委員の発言で』(2025年2月)
日本経済新聞『石破茂首相、為替問題「財務相間で議論」 日米記者会見』(2025年2月)
日本経済新聞『石破茂首相「対米投資を1兆ドルに」 日米首脳会談』(2025年2月)
MUFG『家庭における金融経済教育の在り方を考える(前編)~日本の金融経済教育の現状』(2024年12月)
MUFG『家庭における金融経済教育の在り方を考える(後編)~「投資思考」の活用』(2024年12月)
この記事を書いた人
松本 淳和 ライター
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。