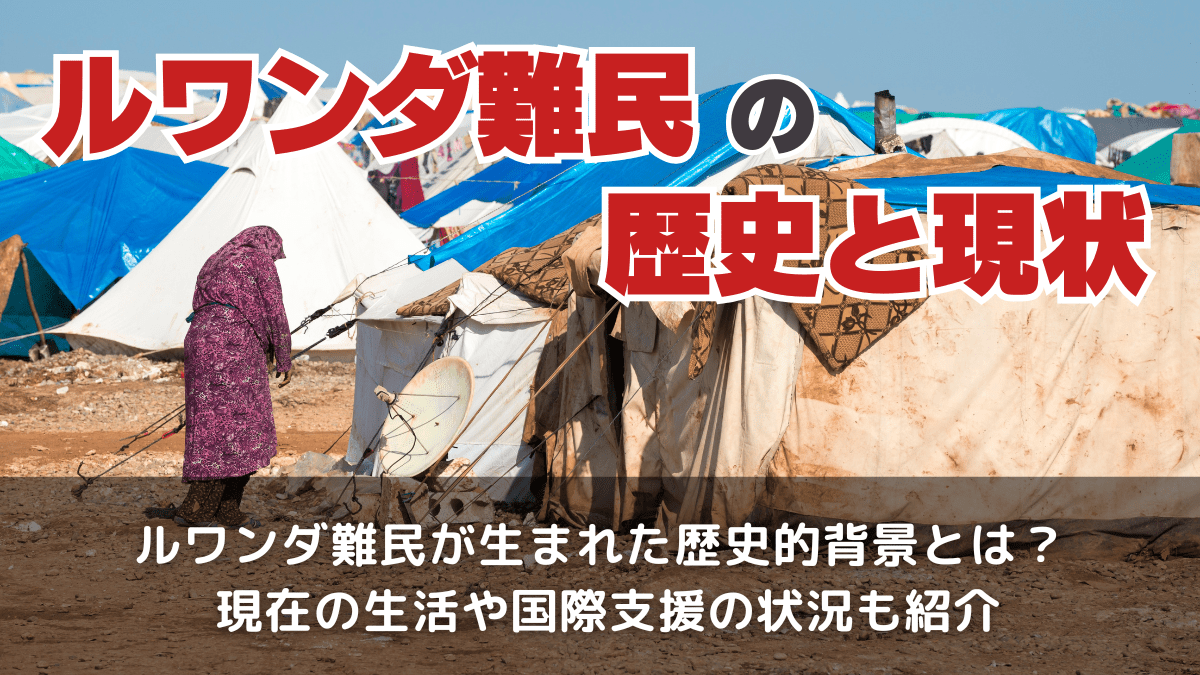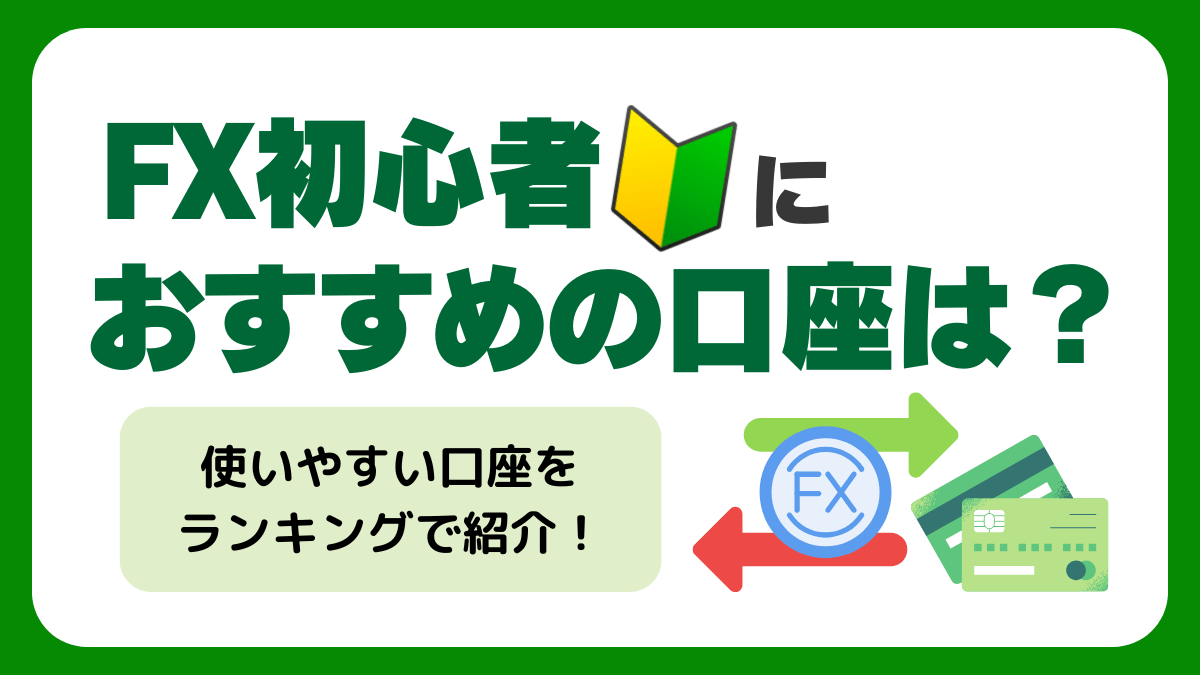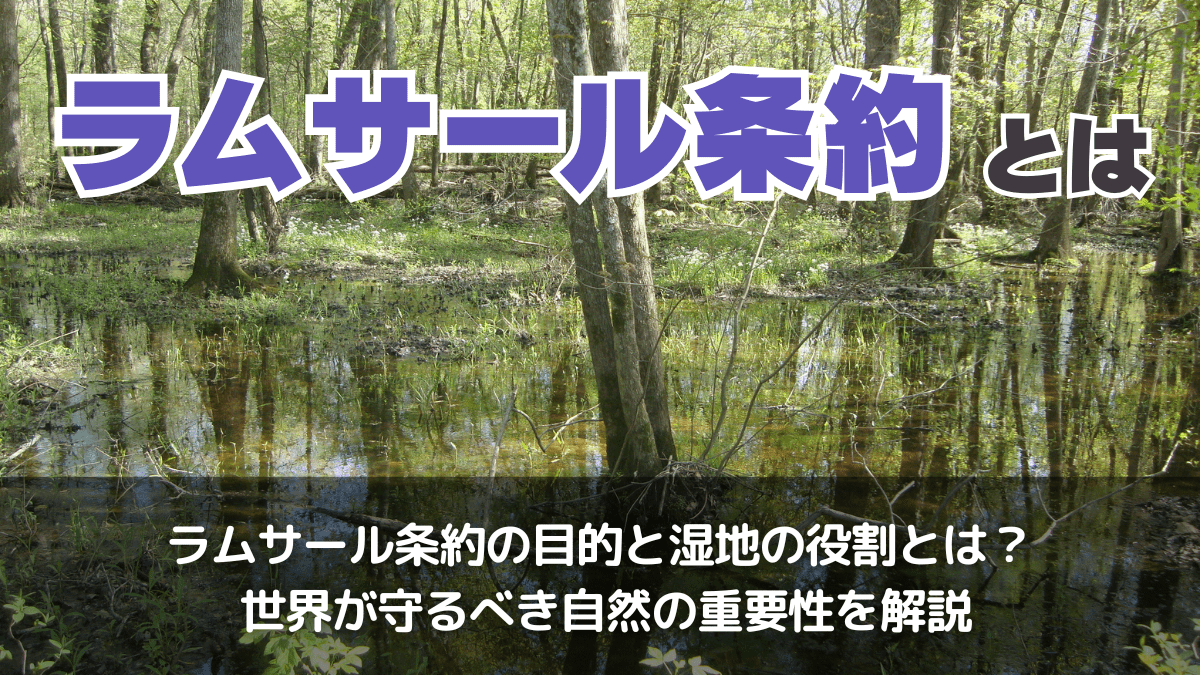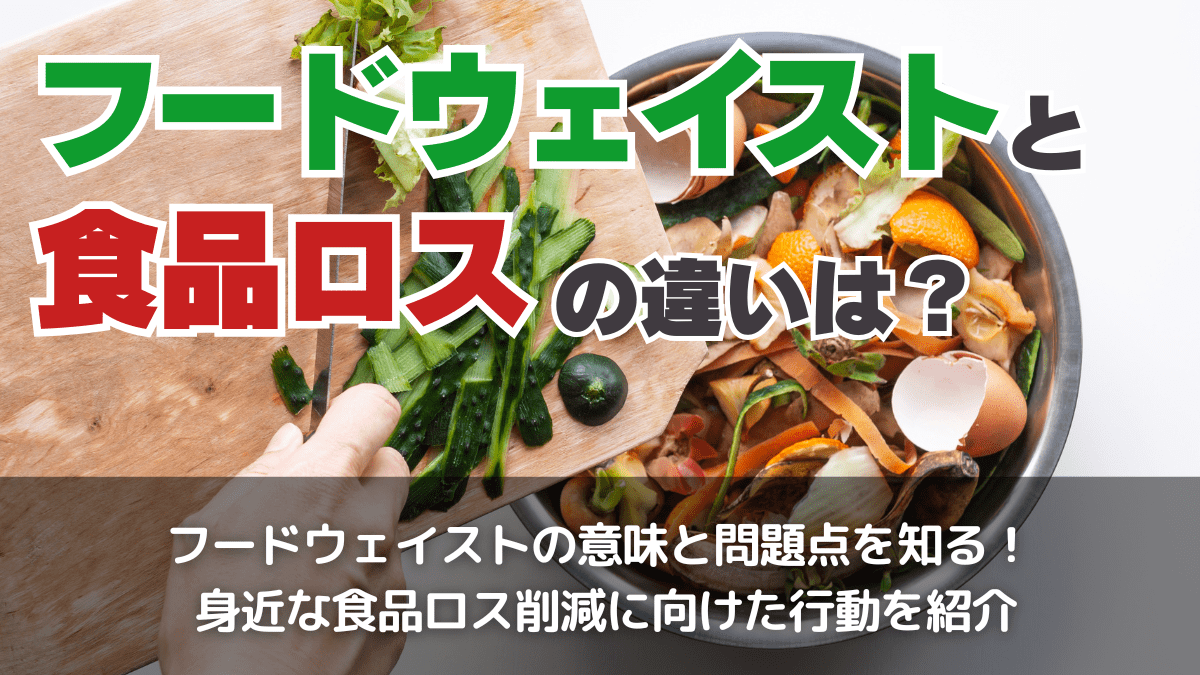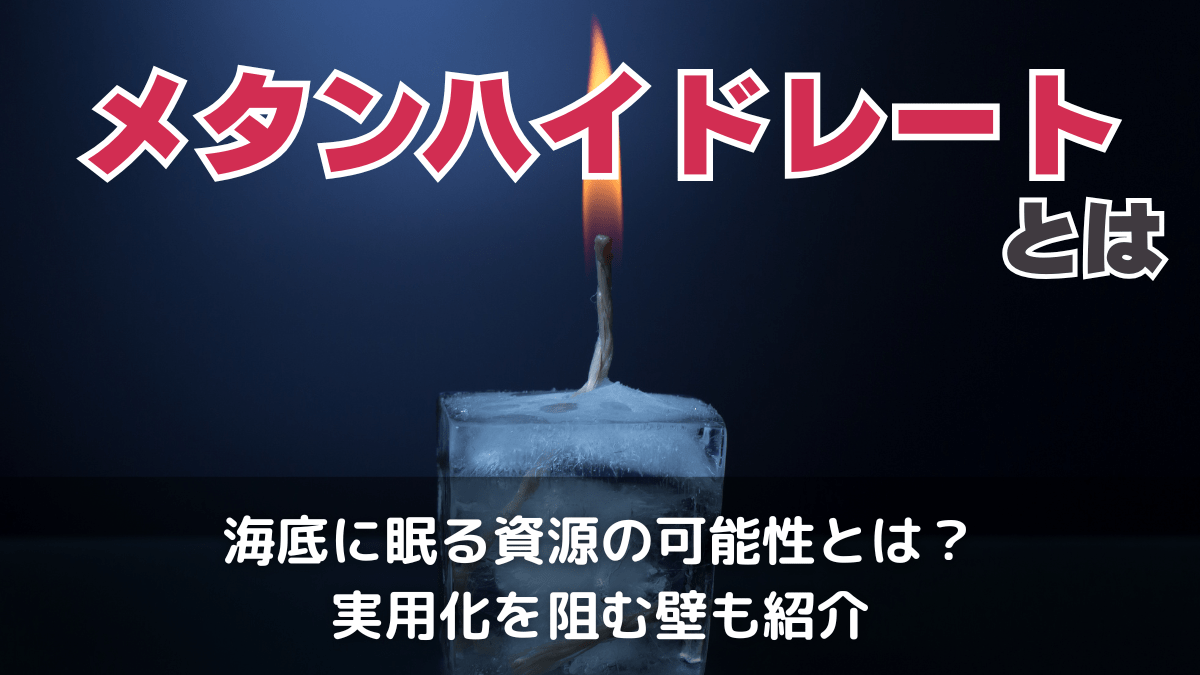ビジネスと人権は、世界をはじめ日本においても関心が高まっている問題です。過日、放送事業者が人権に関わるトラブルを巡り「人権への認識が不足していた」と謝罪する場面がありました。この放送業者とCM契約をしていたある企業は、「重大な人権侵害の疑義が生じている」として、放送を見合わせる事態になっています。これらはビジネスと人権の問題であり、あらゆる企業に関連しています。
この記事では、ビジネスと人権とは何か、注目される背景、指導原則について、日本や海外における行動計画、企業の取り組み方、取り組み事例、SDGsとの関係について解説します。
目次
ビジネスと人権とは

ビジネスと人権とは、企業が事業活動の中で人権を尊重すること、そしてそのための取り組みを進めることを言います。事業活動の中では、さまざまな人権侵害が起きる可能性があります。例えば、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント、性別や人種などを理由とした不当な差別、また、事業内容によっては、工場建設のための立退きの強制などが該当します。こうした問題は、自社の社員やアルバイト・パートはもちろんのこと、取引先従業員、顧客・消費者・地域住民の人権に関わる問題です。
人権侵害を防ぐことは、自社やグループ会社に加え、サプライチェーンにおいても求められています。
企業の人権への取り組みは、企業価値をはかる上でも重要な要素になりつつあります。また投資や公共調達において重視されるなど、企業にとってビジネスと人権は大きな問題です。人権問題を防ぐこと、そして起きてしまったときの適切な対処が企業に求められています。
そもそも人権とは
そもそも人権とは、誰もが生まれながらにして持っている人間らしく生きるための権利です。そしてその保護は、国家の義務です。日本国憲法では、基本的人権を侵すことのできない永久の権利として国民に与えられると記されています。(第十一条)さらに、世界人権宣言では、すべての人間は生れながらにして自由であり、尊厳と権利は平等であるとしています。(第一条)
人権はすべての人に等しく与えられた権利です。自分はもちろんのこと、他者の人権も尊重する必要のある大切なものです。
ビジネスと人権が注目される背景
ビジネスと人権は、世界をはじめ日本においても大きく注目されています。その背景には何があるのでしょうか。2つのポイントを確認しましょう。
企業活動が人権に影響
1つ目は、企業活動が及ぼす人権への影響が拡大していることです。経済のグローバル化により、企業活動は国境を超えるようになりました。ところが1990年代以降、グローバル企業が海外で事業を行う中で、強制労働や児童労働、土地の収奪や森林伐採などの問題が多く報告されるようになります。企業活動により人権問題が起きている実態が浮かび上がったのです。こうして企業は、人権尊重や環境問題への取り組みを求められるようになりました。
国際社会の考え方の転換
2つ目は、上記に関連して、人権尊重の責任を負うのは国家だけではないという考え方に国際社会が転換したことです。人権の保護は国家の義務であることは、先に述べた通りです。しかし、企業活動が人権に及ぼす影響を受けて、国家以外の主体も責務を負うべきだとし、国連は2011年「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下、指導原則)を定めました。指導原則は、企業と人権に関する国際的な規範です。
それでは次に、この指導原則の内容を見ていきましょう。
ビジネスと人権の指導原則について
指導原則
指導原則は「3つの柱」の上に成り立ち、「人権を保護する国家の義務」と、「人権を尊重する企業の責任」を定めています。「3つの柱」と、主に企業に関連する「人権を尊重する企業の責任」の内容を確認しましょう。
3つの柱
3つの柱は、すべての国家と規模や業種などを問わないあらゆる企業に適用されます。
第一の柱:人権を保護する国家の義務
国家は企業の人権尊重を支援することや、政策の一貫性を確保するなど
第二の柱:人権を尊重する企業の責任
企業方針によるコミットメントや、人権デューデリジェンス*を実施するなど
*人権に悪影響を及ぼす事項を特定し、予防・軽減する。それを追跡調査により検証し、情報提供を行った上で、ステークホルダーと対話をすること
第三の柱:救済へのアクセス
国家が司法・非司法にかかわらず救済手段を用意すること。企業が苦情処理の仕組みを整備するなど
次に「人権を尊重する企業の責任」を見ていきましょう。
人権を尊重する企業の責任
人権を尊重する企業の責任では、3つの柱を基に、企業に次の3つの行動を求めています。
人権方針の策定
はじめに、人権方針の策定です。企業は、人権を尊重する責任を果たすことを企業方針として発信することを求められています。指導原則では、人権方針を策定するに当たり、次の5つの要件を定めています。
■人権方針の策定に必要な5つの要件
1.企業の経営トップが承認していること
2.社内外から専門的な助言を得ていること
3.従業員、取引先、企業に直接関わる者に対し、人権について期待することを明記していること
4.一般に公開されており、すべての従業員、取引先、他の関係者に向けて社内外に知られていること
5.企業全体の事業方針や手続きに反映されていること
3つの柱のうちの第二の柱である企業方針によるコミットメントについて、具体的に示されています。
人権デューデリジェンスの実施
次に、人権デューデリジェンスの実施です。具体的には、4つのステップにより行います。
■人権デューデリジェンスのステップ
ステップ1:人権に悪影響を及ぼす事項を特定する
ステップ2:人権に悪影響を及ぼす事項の予防・軽減をする
ステップ3:対応の実効性を追跡調査する
ステップ4:情報発信と外部との対話
企業の規模や業種などに応じた人権デューデリジェンスの実施が推奨されています。
救済メカニズムの構築
最後に、救済メカニズムの構築です。人権に悪影響を及ぼす事項があれば、企業は正当な手続きにより救済する、または協力をします。救済メカニズムの構築は、国家だけでなく企業にも求められています。この要件は、次の8つとされています。
■救済メカニズムの要件
・正当性があること・利用可能であること
・手続きが明確であること
・公平であること
・透明性があること
・国際的に認められた人権と合致していること
・救済メカニズムの改善に活用できること
・ステークホルダーとのエンゲージメントや対話に基づくこと
以上は、指導原則に示されている原則や企業の責任についての内容です。指導原則は、オリンピック・パラリンピック、大型スポーツイベント、国際大会でも遵守することが求められています。
日本におけるビジネスと人権の行動計画
指導原則は国際的な枠組みであり、これを着実に進めていくために日本政府が策定したのが、「ビジネスと人権」に関する行動計画(以下、行動計画)です。
行動計画は2020年に開始し、国家の義務のほか、人権に対する企業の責任を促す政府の取り組みなどを示しています。内容のすべては、「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)に示されています。ここでは、政府が今後行う措置のうち、企業に関連する項目の2つを取り上げ、その具体的な内容について簡単に触れます。
人権デューデリジェンスの啓発
全府省庁は、業界団体を通じて行動計画の認知や、人権デューデリジェンスの啓発をサプライチェーンを含めて行う予定です。これにより、責任ある企業行動の推進を図っていきたいとしています。
中小企業の「ビジネスと人権」の支援
経済産業省は、「人権啓発支援事業」として、経済団体・市民社会などと共に、中小企業を対象とした人権教育やセミナーを引き続き実施するとしています。人権デューディリジェンスの理解を深めていくことも狙いです。
指導原則が企業の責任について直接説明している一方、行動計画は政府がその実現を促進するという立場から策定された点に2つの違いがあります。
海外におけるビジネスと人権の行動計画
2014年、国連は指導原則を進めるため、国ごとの行動計画の策定を求めました。これは「ビジネスと人権に関する国別行動計画:National Action Plan(NAP」」と呼ばれています。
NAPを策定した国は34カ国を数え、日本もこのうちの1カ国です。ここでは、2019年に行動計画を開始したタイと、策定中のインドの取り組みを紹介します。
タイ
タイは、アジアで初めてNAPを策定した国です。1980年代以降、タイは労働者をカンボジアなどから受け入れてきたほか、日本などへ送り出す、また中国などへ移送する中継国となっています。こうした背景から、ビジネスと人権においては、人身取引や強制労働の問題が国際的に注目されてきました。
第1次NAPの行動計画では、サプライチェーンを形成するビジネスセクターが、タイ労働基準を満たすマネジメントシステムを運用するための取り組みを調査しています。また、移民労働者を主要な生産力としている大企業や上場企業に人権デューデリジェンスレポートを作成することを義務付け、労働搾取を抑止する対策を行っています。
インド
インドはNAPの策定を表明していますが、2025年2月時点では草案の段階です。人権に関する現状は、憲法により基本的人権が保障されているほか、人種、カースト、性別、出生地を理由とした差別の禁止など、法の下の平等が規定されています。しかし、女性に対する職場での性暴力は十分に対応されていないなどの問題が指摘されています。
NAPの策定は、関係省庁、国家人権委員会、インド証券取引委員会の代表からなる作業部会と、企業、労働組合、市民社会組織の代表、関連する州政府などと協議を行いながら進めるとしています。ただし、救済措置のアクセスなどに課題があるのが現状です。
企業はビジネスと人権に関してどのように取り組めば良いのか
企業がビジネスと人権に関して取り組む際は、指導原則の「人権を尊重する企業の責任」に定められた3つの行動を起こす必要があります。この具体的な進め方や、取り組みの公表について紹介します。
ガイドラインの活用

取り組みを始める前に、ガイドラインを参照します。企業に求められているビジネスと人権の対応について詳細に説明されているのが、「今企業に求められる『ビジネスと人権』への対応【詳細版】」(法務省人権擁護局)です。企業が尊重すべき人権の全体像から取り組みの進め方までを示しています。
また、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」は、取り組みにあたっての考え方や実効性の評価、情報開示などについて解説しています。(ダイジェスト版はこちらから)さらに「『ビジネスと人権』早わかりガイド」(JETRO)も参考になるでしょう。
Myじんけん宣言

Myじんけん宣言は、企業や団体のトップ・幹部が人権に関する取り組みを行う決意を表明するサイトです。宣言の書式は自由ですが、世界人権宣言や行動計画を参考に作成します。人権方針などを作成している企業や団体は、URLを投稿するとサイト内に公表されます。
2025年2月6日時点で、宣言している企業や団体は1,060に上ります。宣言をすると、ウェブサイトや名刺などにMyじんけん宣言のバナーを表示できます。
ビジネスと人権に関する企業の取り組み事例
指導原則に基づくガイドラインを参考にビジネスと人権に関する取り組みを行うとはいえ、事業の規模によってはハードルが高い部分もあるのは事実です。そこで、小規模事業者の取り組み事例を2つ紹介します。
株式会社アンサーノックス[山梨県甲府市]
株式会社アンサーノックスは、外国人を派遣する事業を行う会社です。社名には、人種、国籍、性別、年齢、障がいの有無、宗教、文化、ライフスタイル、性的指向にかかわらず、「ドアをたたいてくれた人すべてに応えたい」という想いが込められています。従業員スタッフには、女性、シニア、外国籍、LGBTなど多様な人がいます。
取り組みのポイントは、⑴同社の想いに共感・賛同した企業と契約を結び、人材派遣を行う、⑵従業員に求める行動や企業理念を発信する、⑶子連れ出勤の推奨や、企業主導型保育園の経営を行うことです。⑵については、「アンサーノックスがメンバーに求める10のアクション」として明文化されています。
同社は、小規模事業者は経営者の決断一つで環境を変えられる柔軟性を持っていると言います。大規模事業者のような人権方針、人権デューデリジェンス、苦情処理メカニズムの整備のアプローチとは異なる取り組みが参考になる事例です。
エヌエル産業株式会社[広島県広島市]
エヌエル産業株式会社は、道路区画線設置や道路標識設置、防護柵設置などを手掛ける、常用労働者8名の会社です。従業員が働き続けられる職場を目指し、仕事と家庭の両立支援や、仕事と介護の両立支援に取り組む「広島県仕事と家庭の両立支援企業」に登録しています。また、子ども110番の家の活動をし、地域の子どもの健全育成に貢献しています。
同社は「Myじんけん宣言」において、⑴基本的人権の尊重、⑵ハラスメントの排除、⑶多様な発想・価値観の尊重を宣言しているほか、仕事と子育てを両立させるための行動計画を策定しています。
行動計画は、男性の育児休業取得を促進、ノー残業デーの設定、半日単位の年次有給休暇の拡充が挙げられています。従業員数の少ない企業における人権への取り組みを知ることのできる例です。
ビジネスと人権とSDGs
最後に、ビジネスと人権とSDGsとの関係を確認します。SDGsは「誰一人取り残されない」という人権尊重の考え方に基づいています。そのため、人権とビジネスにも深いつながりがあります。
目標5「ジェンダー平等を実現しよう」は、人身売買や女性への差別をなくすこと、そして目標8「働きがいも経済成長も」は、すべての人が働きがいのある人間らしい仕事をすることを掲げています。これらは、ビジネスにおける人権に関わりがあることです。
また、目標12「つくる責任つかう責任」、目標13「気候変動に具体的な対策を」は、人々が健康に生きる権利に関連します。企業が環境への負担を減らし、持続可能な開発を行うことは、SDGsとビジネスの人権の両方に貢献します。
大きなくくりでの人権とSDGsについては、国連人権高等弁務官事務所作成の一覧表(日本語訳)に詳細に記されています。→SDGs×人権一覧表
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
ビジネスと人権は、すべての企業にとって不可欠な取り組みです。企業の価値を左右するほか、事業の存続にも関わる重要な課題でもあります。
ビジネスと人権を実践するためには、指導原則に基づいた取り組みが必要です。とはいえ、すべての企業が定められた手順通りに行うことは難しいかもしれません。小規模事業者は、事例で紹介したような取り組みをヒントに進めていくのも1つの方法です。
<参考>
ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のために(A/HRC/17/31) | 国連広報センター
ビジネスと人権とは?ビジネスと人権に関する指導原則|外務省
「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)令和2年10月ビジネスと人権に関する行動計画に係る関係府省庁連絡会議
責任あるサプライチェーン等における 人権尊重のためのガイドライン 令和4年9月 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議
今企業に求められる『ビジネスと人権』への対応【詳細版】法務省
「ビジネスと人権」早わかりガイド|JETRO
この記事を書いた人
池田 さくら ライター
ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。
ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。