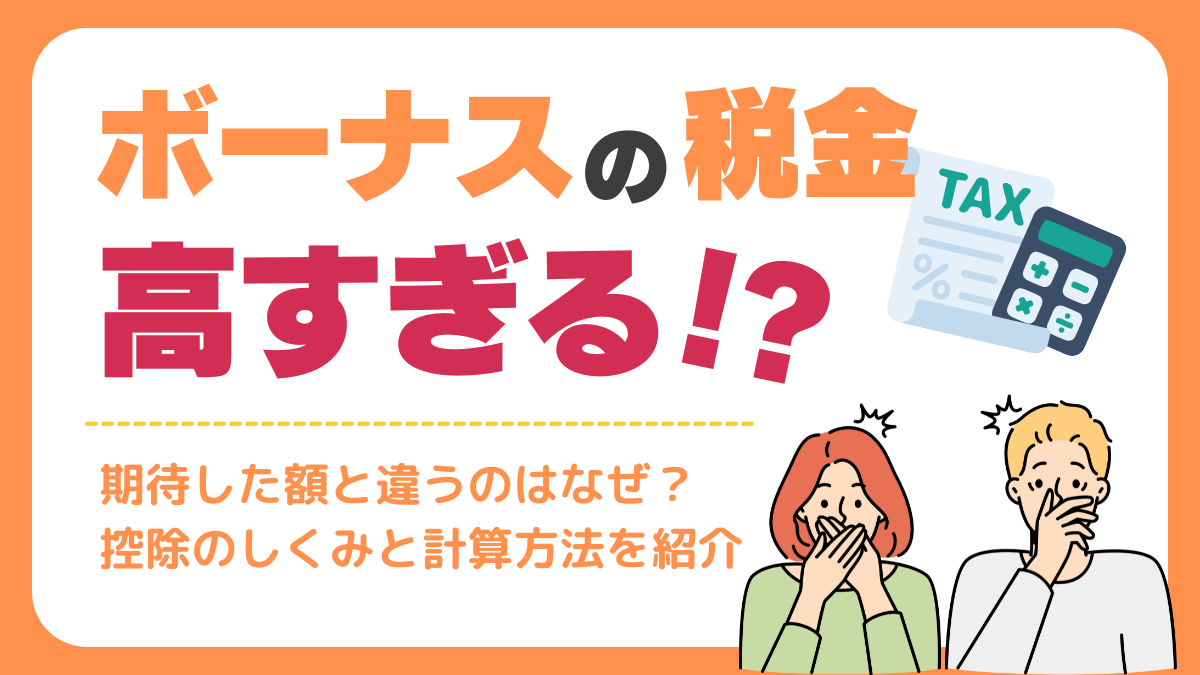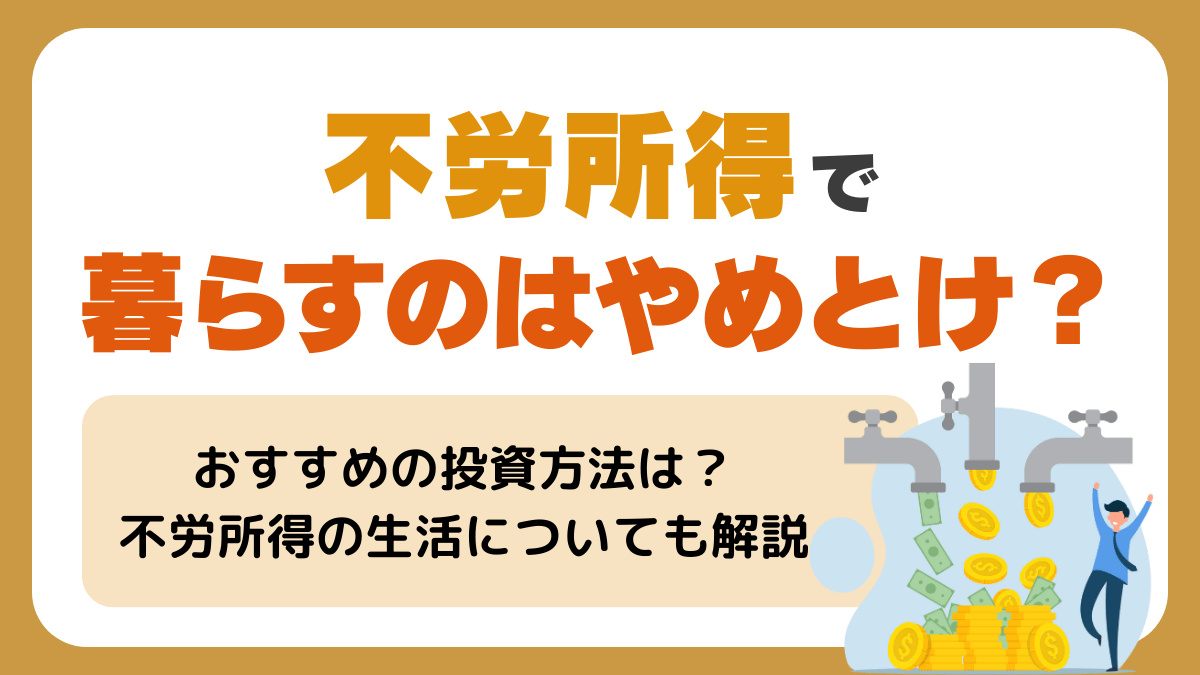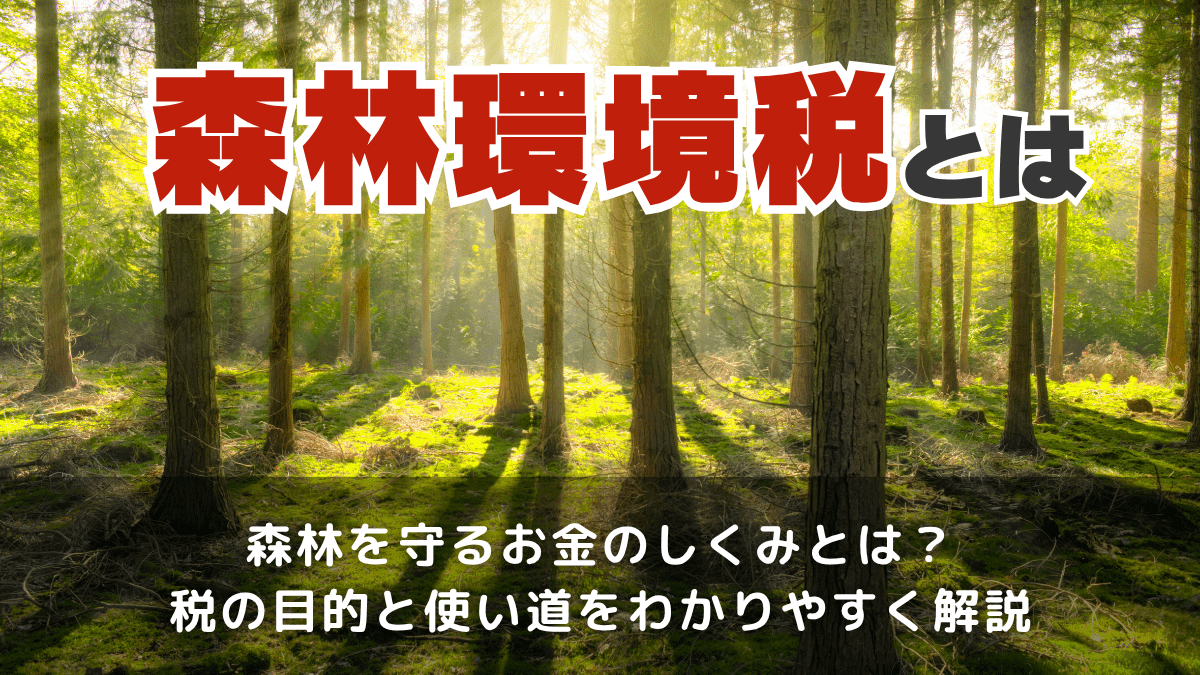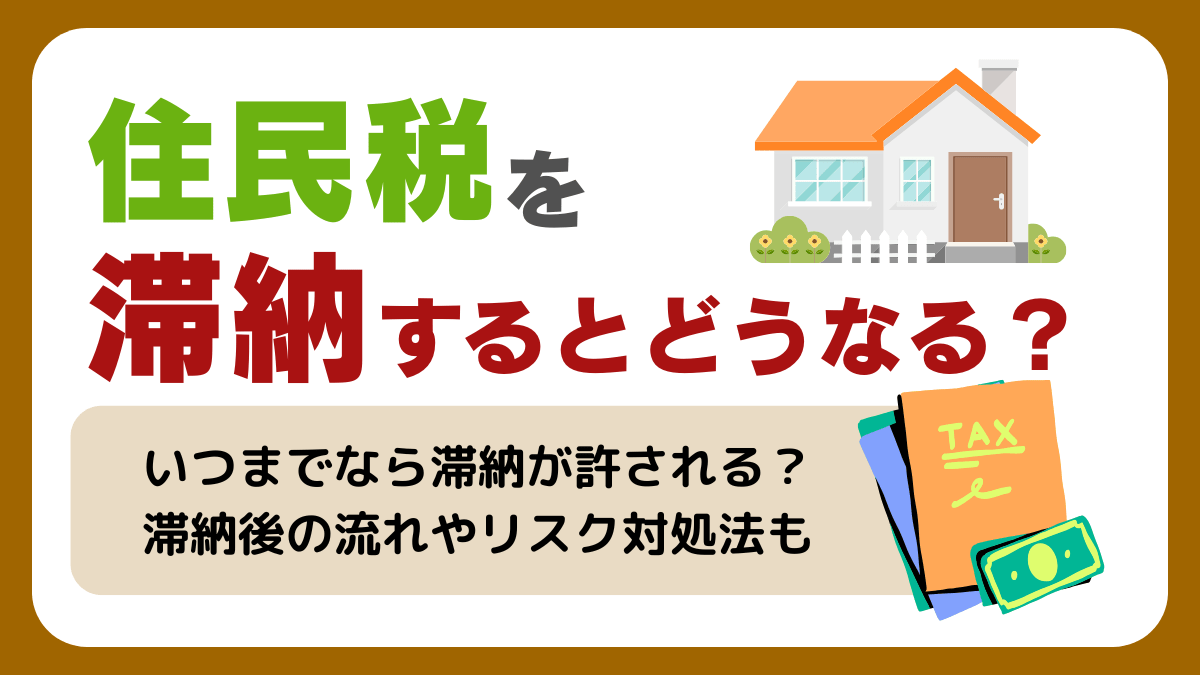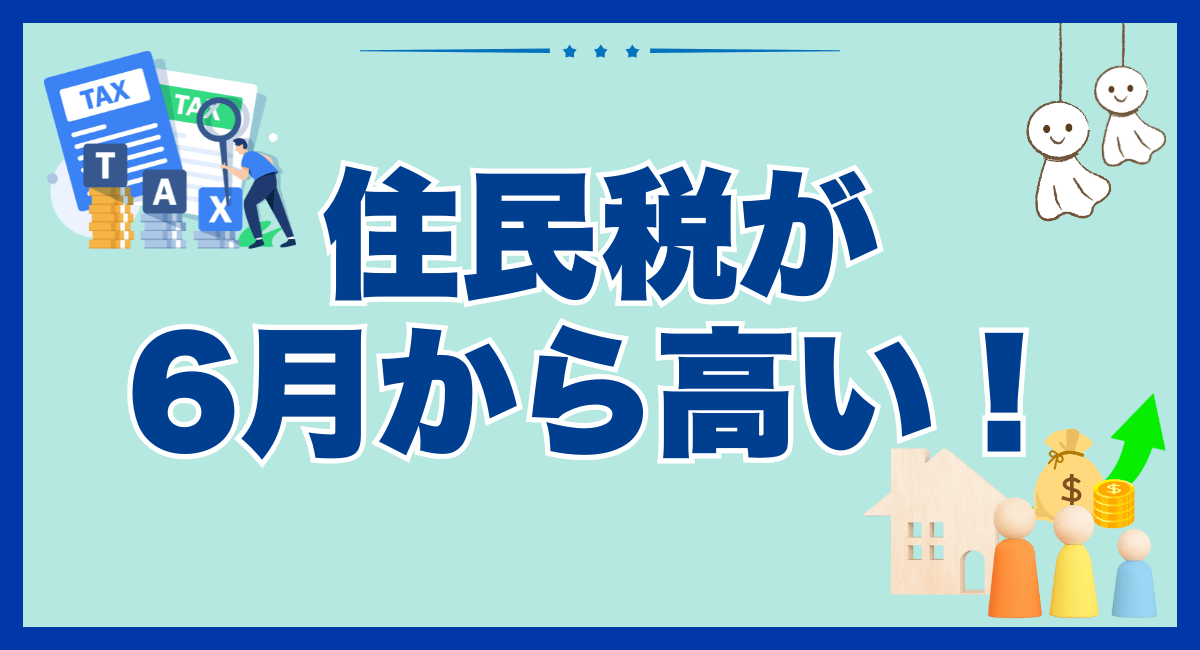
住民税は、前年の所得をもとに毎年6月から翌年5月まで支払う税金です。
2025年6月の住民税が高く感じるのは、2024年度に実施されていた定額減税が5月で終了し、その影響が反映されたためです。
毎年のように送られてくる通知に戸惑う人も多い住民税ですが、仕組みや計算方法、免除の条件、納付方法を正しく理解することで、金額の変動にも納得できるようになります。
生活設計や節税の視点からも、知っておきたい知識です。
目次
そもそも住民税とは?なぜ6月?仕組みや計算方法を解説
住民税は、私たちの身近な生活を支えるための税金で、毎年6月から納付が始まります。
「なぜ6月なの?」「どうやって金額が決まるの?」「非課税になることはある?」など、素朴な疑問を感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
実は、住民税には独特のルールや計算方法があり、制度を正しく理解することで、損を防いだり、節税のヒントを得ることも可能です。
ここでは、住民税の基本的な仕組みから計算方法、免除条件や納付の流れまでを解説していきます。
住民税の概要
住民税とは、「地方税」の一種で、国税である所得税と違い、あなたが住んでいる市区町村や都道府県に納める税金です。
地域の道路整備、保育園や小中学校の運営、福祉サービス、ごみ処理など、暮らしに直結する行政サービスの財源となっています。
住民税は、基本的に前年の所得を基準に翌年度に課税される構造であり、毎年6月から翌年の5月までの期間で税金を納めることになります。
この「6月開始」というタイミングは、前年分の所得が決まり、住民税の金額が自治体によって計算・通知されるタイミングに基づいています。
住民税の構成は2つからなり、「均等割」と「所得割」です。
・均等割
所得に関係なく一律でかかる税金です。
2025年度の東京都の場合は以下の通りです。
都民税1,500円+特別区民税3,500円=年額5,000円(災害対策の臨時加算を含む)
・所得割
前年の所得に応じてかかる税金です。
収入が多ければ税額も高くなります。
この2つを合算したものが、1年分の住民税になります。
身近な税金でありながら、意外と仕組みを知らない人が多いため、生活設計や節税のためにも、きちんと理解しておくことが大切です。
所得割の計算方法
住民税の「所得割」は、前の年に得た所得を使って計算される仕組みです。
たとえば2025年度の住民税は、2024年1月〜12月の所得に基づいて課税されます。
計算式は次のようになります。
課税所得 × 10%(市4%+県6%)− 税額控除
「課税所得」は、総収入から必要経費や各種所得控除(基礎控除48万円、配偶者控除、医療費控除など)を差し引いた金額です。
10%の税率は全国一律で、内訳は市町村民税6%、都道府県民税4%です。
たとえば、課税所得が200万円であれば、200万円に10%をかけ、20万円が所得割となります。
ここから住宅ローン控除や調整控除などが引かれた後の金額が最終的な住民税となります。
節税の視点でいえば、ふるさと納税や医療費控除を使うことで、課税所得を減らし、所得割も減らせます。
所得割は「がんばって稼いだ分だけ多く払う税金」ですが、その分、制度をうまく使えば節税効果も大きくなります。
住民税非課税になる条件
住民税は「全員が必ず払う税金」ではありません。
所得や世帯の状況によっては、課税されずに済むことがあり、これが非課税制度です。
非課税となる条件は大きく分けて2つあります。
・所得による条件
たとえば、単身で扶養もない人が、総所得45万円以下であれば、所得割・均等割、どちらも税がかかりません。
・特定の属性(障がい者・未成年・学生)による条件
これらの人で、所得を合わせた額が135万円より少ない際は、税が課せられません。
注意すべき点は、「総所得」や「合計所得」には給与だけでなく、年金、アルバイト収入、副業、雑所得なども含まれる点です。
また、扶養親族の有無や、同居家族の収入状況などによっても非課税条件は変わるため、自己判断せずに自治体の住民税担当窓口に相談するのが確実です。
非課税になることで、国民健康保険料の軽減、給付金制度といった恩恵を受けやすくなることもあります。
生活が厳しいときこそ、制度の正しい理解が家計の助けになります。
住民税の納付方法
住民税の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2つがあります。
自分の働き方や収入の有無によって、適用される徴収方法が違ってきます。
1. 特別徴収(給与からの天引き)
会社員や公務員などが対象で、住民税は毎月の給与から自動的に差し引かれます。
会社が住民に代わって自治体に納税する仕組みで、年12回(6月〜翌年5月)に分けて支払われます。
本人が支払い手続きをする必要がないため、最も一般的で手間がかからない方法です。
2. 普通徴収(自分で納付)
自営業者や退職者、年金受給者などが対象です。
市区町村から届く納付書を使って、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて支払います。
銀行・コンビニ・口座振替・スマホ決済(PayPay・LINE Payなど)など、多様な支払方法に対応しています。
注意すべきなのは、特別徴収から普通徴収への切り替え時期です。
転職や退職などで会社を辞めた際、特別徴収が中断され、次の職場で再開されるまでの「空白期間」に納付書が届きます。
この期間に支払いを忘れてしまうと、滞納や延滞金の対象になる可能性もあるため、注意が必要です。
自分が今、どちらの徴収方法なのかを把握しておくことが、税金トラブルを防ぐ第一歩です。
【合わせて読みたい記事】
2024年度に実施された住民税の定額減税とは?対象者や仕組みを解説
2024年度に行われた住民税の「定額減税」は、物価が高くなった対策として取り入れられた一時的に税額を減らす制度です。
対象者や減税される金額、適用される方法は少し複雑であり、誤解されやすい点もあります。
ここでは、仕組みから注意点について解説します。
定額減税の概要
定額減税は、生活必需品やエネルギー価格が上がったことに応じるための家計支援策として導入されました。
対象となるのは、住民税や所得税が課税されている人です。
住民税に関しては、1人あたり1万円が税額控除となる形で行われました。
注目すべき点は、「納税者本人」に限らず、「その人に扶養されている家族」も含まれ、たとえば配偶者と子ども2人を扶養している場合は、合わせて4人分の4万円が税から減らされるということです。
この減税は「税額控除」として行われるため、もともと住民税がかかっていない人には適用されません。
一方で、税金がかかっている人にとっては、自動的に税額が1万円(または人数分)引かれるため、手取りが増える効果があります。
なお、申請は不要で、勤務先や自治体が自動的に控除を反映する仕組みとなっています。
ただし、控除額や人数の反映にミスがある可能性もあるため、通知書の確認は欠かせません。
定額減税の対象者と減税額
定額減税の対象者は、「2024年度に住民税が課税されている人」です。
より具体的に言うと、2023年中に一定以上の所得があり、2024年度に住民税の納税義務がある人が対象です(※基準は市区町村によって若干変わることがあります)。
減税額は、納税者本人およびその扶養親族1人につき1万円です。
たとえば、本人+配偶者+子ども2人を扶養している際、合計4万円が控除されます。
この扶養親族には、「控除対象配偶者」だけでなく、「控除対象外の同一生計配偶者」も含まれる点がポイントです。
つまり、所得控除の対象外であっても同居していて扶養していればカウントされることがあるということです。
なお、所得制限は住民税においては設定されていません(※所得税の定額減税には年収上限があります)。
重要なのは「住民税が課税されているかどうか」です。
したがって、年収が高すぎて対象外になる心配は基本的にありませんが、扶養の申告が正しく行われていないと減税額が少なくなることがあるため、年末調整や確定申告時にきちんと扶養親族の届け出がされているかを確認しましょう。
減税の適用方法
住民税の定額減税は、特別な申請をしなくても自動的に適用される点が特徴です。
自治体が納税情報をもとに判断し、給与天引きや納付書に減税額を反映させます。
会社員などで住民税が「特別徴収(給与天引き)」となっている人は、2024年6月からの給与明細にて、住民税額が通常より1万円少なくなっていることが確認できます。
一方、自営業や退職者などの「普通徴収」の人には、市区町村から送付される納付書にあらかじめ1万円を差し引いた金額が記載されているため、自分で計算する必要はありません。
しかし、控除が反映されているか不安な場合は、「住民税決定通知書」または「納付書の摘要欄」を確認しましょう。
「特別減税1万円」などと書かれていれば、適用されている証拠です。
また、扶養人数に誤りがあると減税額が少なくなる可能性があるため、「年末調整結果」や「確定申告の控え」で自分の扶養申告が正しく反映されているか確認しておくと安心です。
分からないことがあれば、早めに自治体の税務課に問い合わせましょう。
定額減税に関する注意点
定額減税は魅力的な制度ですが、すべての人が満額の恩恵を受けられるわけではありません。
主な注意点は以下の3つです。
・住民税が1万円未満の人
税額控除は実際に課税されている住民税額を上限とするため、たとえば住民税が7,000円しかない時は、その分しか減税されません。
差額の3,000円は還付されず、減税を使いきれないことになります。
・住民税が非課税の人
そもそも課税されていない人には控除の対象が存在しないため、定額減税は適用されません。
つまり、収入が少なく住民税が免除されている人には、住民税側の減税メリットはありません。
・対象外の人にも誤解が広がりやすい
「全員に1万円もらえる」といった誤解がSNSや口コミで広がったことで、対象外の人が減税されていないと勘違いしやすい状況になっています。
ただし、住民税非課税世帯に対しては別途給付金などの支援策が実施されているケースもあります(※内閣府「住民税非課税世帯等への臨時特別給付金」など)。
制度の違いを正しく理解し、自分がどれに該当するのかを把握することが、損をしないポイントです。
2025年度も定額減税は実施されるのか
国税庁公式サイトにおいて、2025年度(令和7年度)の新たな定額減税の実施は予定されていません。
これは2024年度に実施された「定額減税」が、あくまで物価高など一時的な経済対策としての単年限りの措置であったためです。
実際に、政府の公式発表や財務省の資料でも、2025年度に新たな定額減税制度を続けるとの記載はありません。
しかし、2025年年度(令和7年度)にも一部の方に対して引き続き減税があります。定額減税が実施されるのは、2024年度(令和6年度)に定額減税を受けてない人です。2024年度に定額減税を受けた人は対象外になるのでご注意ください。
2025年度の定額減税は新制度ではなく、前年度の減税分が制度上後ずれで処理されるだけです。
つまり、2025年度には「新たな定額減税」はありません。
今後の経済状況によっては再度実施される可能性もゼロではありませんが、現時点では政府としてもそのような方針を示していないため、過度な期待は避けるようにしましょう。
制度の正確な理解は、家計管理にもつながります。
誤情報に惑わされず、公式発表をこまめに確認していくことが大切です。
参考:
住民税に関するよくある質問
住民税は毎年のように通知が送られてきますが、「なぜ金額が変わるのか?」「転職したらどうなる?」など、疑問を持つ人も多いはずです。
ここでは、特によくある5つの質問を厳選し、仕組みと理由をわかりやすく解説します。
住民税が上がったのはなぜですか?
「住民税が急に上がった」と感じた人の多くは、2024年度に実施されていた定額減税の終了が理由です。
昨年度は、物価高対策として1人あたり1万円の住民税が自動的に減額されていました(※参照:財務省「令和5年税制改正」 )。
しかし、これは2024年度だけの一時的なものであり、2025年度には同じような、もしくは新しい減税はありません。
そのため、2024年と税額を比べ「減税される前の金額に戻った」ことで、税額が増えたように感じる人が多いのです。
もちろん、所得が増えた場合や扶養人数が減った際なども、税額が増える要因となります。
一見、値上げのように感じますが、実際は「減税が終わっただけ」ということも多いため、自分の通知書をよく確認してみることをおすすめします。
住民税が0円の人は定額減税どうなる?
住民税がもともと0円の人には、定額減税の恩恵は基本的に適用されません。
なぜなら、定額減税は「住民税の税額控除」なので、税金が発生していない人にとっては控除するもの自体が存在しないからです。
たとえば、所得が少なくて住民税非課税の人や、扶養に入っていて課税対象外の人などが該当します。
こうした人たちは制度の対象外である一方で、別の形で給付金が出ることもあります(例:住民税非課税世帯向けの給付金制度など)。
そのため、定額減税が受けられないからといって損をしているとは限りません。
重要なのは、「減税」と「給付」の制度の違いを正しく理解し、自分がどちらに該当するかを確認することです。
疑問があれば、自治体の窓口に問い合わせてみましょう。
住民税はいつからいつまでの所得に対してかかる?
住民税は、「前年の1月1日から12月31日までの所得」に対して課税されます。
つまり、2025年度(6月から支払いが始まる)に支払う住民税は、2024年1月〜12月の所得が対象です。
このズレがあるため、「今は無職なのに住民税が高い」と感じる人も多いのが特徴です。
前年にしっかり収入があった人は、今年無職でも住民税の納税義務があるということです。
たとえば、2024年に転職して年収が高くなった場合、その所得が反映されて住民税が増えるのは2025年からです。
住民税は、前年の稼ぎに対する後払いという点を理解しておくと、将来の税金を見積もるうえでも役立ちます。
計画的な貯金や支出管理にもつながるので、年末調整や確定申告後に「いくら課税されそうか」を意識しておくと安心です。
転職した場合住民税はどうなる?
仕事を変えたとしても、住民税は納めなければなりません。
大事なのは、「どうやって支払うか」という方法が変わることです。
前の会社で住民税を「特別徴収」(給与からの天引き)で支払っていた人が退職すると、いったんその徴収は止まります。
その後、新しい職場で特別徴収が始まるまでの間に「普通徴収」と呼ばれる、納付書で自分で納税する方法に変わることが多くあります。
この切り替え時期にうっかり納付を忘れてしまうと、延滞金や督促が発生することもあるので注意が必要です。
特に、転職後すぐに特別徴収が始まらないケースでは、自宅に届いた納付書をよく確認しておきましょう。
自治体によって手続きが違うこともあるので、不明な点は早めに問い合わせておくと安心です。
退職・転職がある年は、税金まわりも見落とさずに確認するのがポイントです。
6月だけ住民税が高いのはなぜですか?
6月の給与明細を見て「住民税が急に高くなってる!」と驚く人も多いですが、これは毎年起こる制度上の現象です。
住民税の特別徴収(給与天引き)は毎年6月から翌年5月までの12ヶ月で均等に分けて支払う仕組みです。
5月までは前年の金額だったものが、6月から新年度の住民税額に切り替わるため、差が生まれます。
また、2024年度は定額減税の影響で税額が一時的に下がっていたため、2025年6月に「本来の税額」に戻ったことで、より一層高く感じるケースもあります。
決して「6月だけ多く取られている」わけではなく、単にその月から新しい年度の金額が反映されるだけです。
通知書と照らし合わせて冷静に確認すれば、必要以上に不安になることはありません。
まとめ
2025年6月から住民税が「急に高くなった」と感じる人が多い背景には、2024年度に実施された定額減税(1人あたり1万円)が終了したことがあります。
昨年度は物価高対策として住民税の税額が一時的に軽減されていましたが、これは単年限定の措置だったため、2025年度は通常の金額に戻っただけです。
住民税は「均等割(定額課税)」と「所得割(所得に応じた課税)」から成り、前年の所得に基づき6月から翌年5月までの1年分を納付する仕組みです。
非課税となる条件や納付方法(特別徴収・普通徴収)にも違いがあり、転職・退職時の納税ミスには要注意です。
制度を正しく理解することで、不安や誤解を防げます。
今後の生活設計や節税にも役立つため、一度自分の住民税の仕組みを確認してみましょう。
この記事を書いた人
エレビスタ ライター
エレビスタは「もっと"もっとも"を作る」をミッションに掲げ、太陽光発電投資売買サービス「SOLSEL」の運営をはじめとする「エネルギー×Tech」事業や、アドテクノロジー・メディアなどを駆使したwebマーケティング事業を展開しています。
エレビスタは「もっと"もっとも"を作る」をミッションに掲げ、太陽光発電投資売買サービス「SOLSEL」の運営をはじめとする「エネルギー×Tech」事業や、アドテクノロジー・メディアなどを駆使したwebマーケティング事業を展開しています。