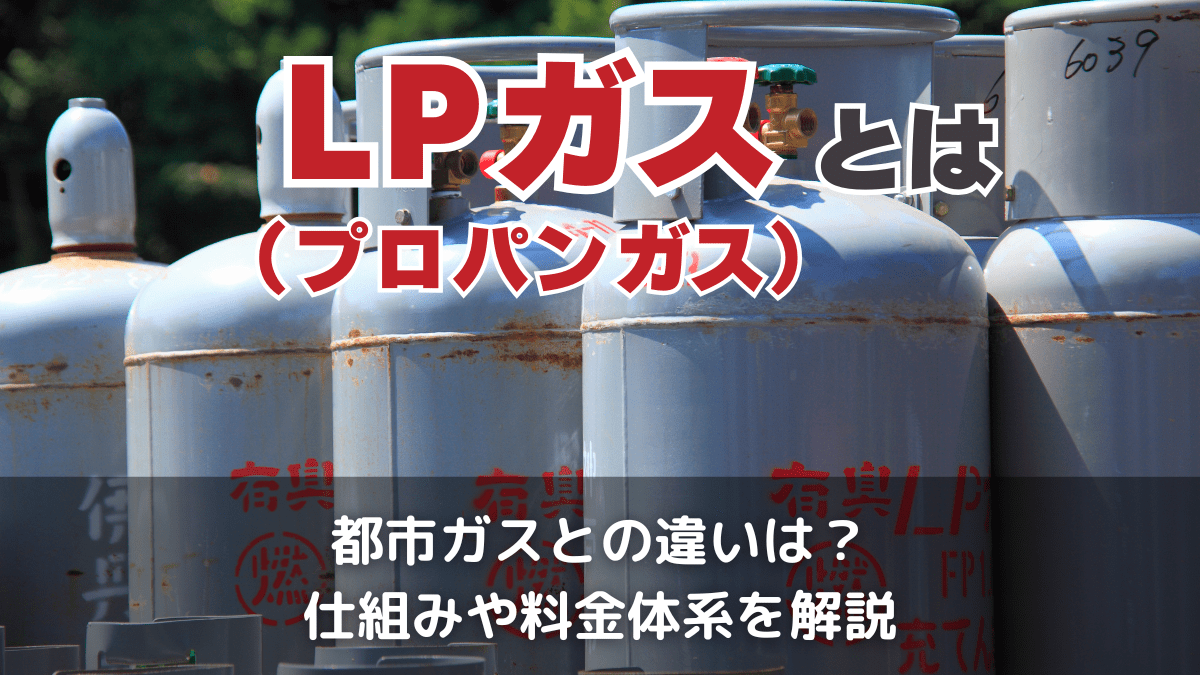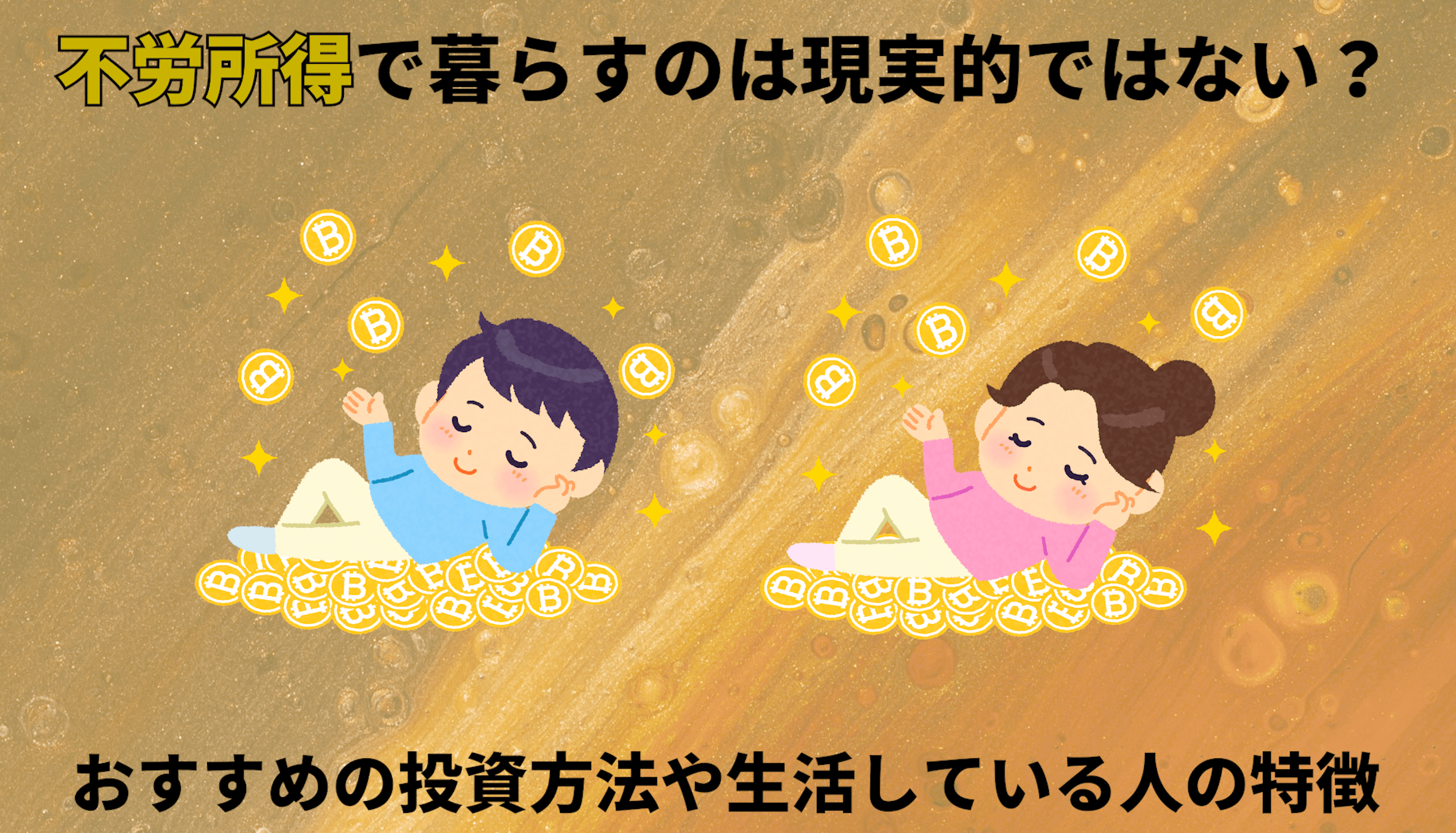
経済的自由を目指すにあたって鍵となる不労所得。あなたの生活をより豊かにできる、不労所得についてわかりやすく解説します。
- 初心者におすすめの5つの方法
- メリットやデメリット
- 税金について
- やるべきこと
- 注意点
などを、理解しやすい内容で紹介。不労所得獲得の第一歩を踏み出すにあたって必要な知識を提供します。
FIREに興味がある人、将来の生活に不安がある人はぜひ、将来の計画と資産形成に役立ててください。
目次
不労所得とは

不労所得とは、労働の直接的対価として得る賃金や報酬以外による所得のことです。簡単に言えば、働かなくても得られる収入を意味します。
不労所得の定義
不労所得は、権利や特定の状態を維持管理すれば継続して得られる収入源です。具体的には、
- 利子所得
- 配当所得
- 家賃収入
- 有価証券や不動産の売買差益
などが例として挙げられます。
不労所得が注目される理由
不労所得は近年、経済的な自由を求める人々の間で注目を集めており、副業や資産形成の一環として取り組みが広がっています。不労所得が注目される主な理由として、以下が考えられます。
- 経済環境の変化
低金利が長期化する中で、預貯金だけでは資産が増えないという状況が続いています。より高い収益を求めて、投資や不動産などへの関心が高まっています。 - ライフスタイルの変化
ワークライフバランスを重視する人が増え、時間的な自由を求めて副業や投資に興味を持つ人が増えています。 - 情報収集の容易さ
インターネットの普及により、投資に関する情報に簡単にアクセスできるようになりました。
日本の課題:収入の内訳における金融所得の割合
【世帯の現金収入の内訳(2019年)】
日本では、金融所得が収入に占める割合が、他の先進国と比較して低い傾向にあります。上のグラフは、日本証券業協会の調査による世帯の現金収入の内訳です。このグラフから、以下のことがわかります。
- 高所得層ほど金融所得が高い: 家計資産が多い層ほど、家賃収入や配当金などの金融所得が収入に占める割合が高い傾向
- 日本の金融所得割合の低さ: 日本全体で見ると、金融所得が収入に占める割合は依然として低い水準
- 高所得層でも金融所得の割合は高くない:利子・配当金の占める割合は、家賃・地代と比較しても非常に小さい
背景には、日本人の保守的な投資傾向や、金融教育の不足などが考えられます。
このように、不労所得は、働き方や経済状況の変化を背景に、近年注目を集めています。また、日本の場合は、金融所得が収入に占める割合が低く、まだまだ伸びしろがあると言えるでしょう。
次の章では、不労所得を得るための方法について見ていきます。*1)
不労所得の作り方の種類(代表例)

不労所得に定義される、主な所得の種類を確認していきましょう。
①投資による収入
投資は、お金を働かせ、収益を生み出すための有効な手段です。代表的な投資には以下のような種類があります。
- 株式投資: 株式を所有することで得られる配当金
- 投資信託: 投資信託の分配金
- FX: 外貨取引による収益
- 暗号資産: クリプトカレンシーの投資による収益
②不動産関連の収入
不動産は、初期投資が必要なものの、安定した収入源となるだけでなく、資産価値が上昇する可能性もあります。管理の手間や費用がかかることもあるので完全な不労所得とは言えないと言う意見もあります。
不動産投資の代表例には以下のようなものがあります。
- 土地・物件の賃貸: 賃貸物件から得られる家賃収入
- 駐車場経営: 駐車スペースの貸し出しによる収入
- コインロッカー・自動販売機: 設置による利用収入
③金融商品による収入
金融商品への投資は、比較的安定的な収入を得るための方法です。主に以下のような例が挙げられます。
- 預金: 銀行に預け預金額に応じて利息が支払われる
- 債券: 企業や政府が発行する債券を購入し、満期まで保有することで、利息と元本が返還される
- 受取配当金:株式を所有することで得られる配当金
預金による利息収入は、元本保証があり、安全性が高いものの、現在は金利が低く、物価上昇率を下回る可能性があります。まとまった金額の利息を受け取る手段としては、一般的な人にはあまり現実的ではない場合が多いでしょう。
④知的財産関連の収入
知的財産は、創造的な活動によって生み出された無形財産であり、これらを活用することで収入を得ることができます。具体的には、以下のようなものが例として挙げられます。
- 著作権や特許権の使用料: 本、音楽、特許などからのロイヤリティ収入
- ネットビジネスやコンテンツ関連の収入
- ブログ運営・YouTubeによるアフィリエイト・広告収入: コンテンツ制作による広告収入やアフィリエイト収入
- 商品の販売による収入: アプリ、SaaS型のサービス、デジタルコンテンツの販売
⑤その他
上記以外の不労所得として、
- シェアリングサービス: 自動車やスペースのシェアリングによる収入
- 印税収入: 書籍やデジタルコンテンツの販売による印税
なども不労所得に分類できます。
このように、不労所得には多様な種類があります。どの方法を選ぶ場合も、リスクとリターンをしっかりと理解し、自分に合った方法を選びましょう。
また、これらの不労所得には、税法上「不労所得」という独立した区分は存在せず、各所得区分(不動産所得、利子所得、配当所得など)に従って税金が課せられます。*2)
不労所得のメリット

不労所得を得ることは、単に収入を増やすだけでなく、私たちの生活に大きな変化をもたらします。 この章では、不労所得がもたらす具体的なメリットについて解説していきます。
経済的な安定と自由
不労所得によって、収入の多角化と経済的な安定をもたらし、時間の自由を手に入れることができます。
- 収入源の多様化: 給与収入だけに頼らず複数の収入源を持ち、経済的な安定性を高める
- 時間の自由: 働く時間を自由に調整でき、自分のやりたいことに時間を使える
- 早期退職の可能性: 不労所得で生活費を賄えるようになれば、早期退職ができる
豊かな暮らしの実現
不労所得は、豊かな暮らしを実現するための基盤となります。
- 消費の自由: 欲しいものを我慢せずに購入したり、旅行を楽しんだりできる
- 自己実現: 時間的な余裕が生まれることで、自分の興味関心に従い、さまざまなことに挑戦できる
- 社会貢献: 経済的な余裕があれば、ボランティア活動や寄付など、社会貢献活動にも積極的に参加できる
長生き社会に対応
不労所得によって、長生きするリスクに対応し、より安定した生活を確保できます。
- 物価上昇への対応: インフレによって生活費が上昇しても、不労所得があれば生活水準を維持できる
- 医療費への備え: 老後には医療費がかさむ可能性があるものの、不労所得があればその費用を賄うことができる
精神的な安定
不労所得は、経済的な不安から解放され、精神的な安定をもたらし、自信を高めます。
- ストレスの軽減: 金銭的な不安から解放され、精神的な安定を得る
- 自信の向上: 経済的な自立を実感することで、自信を持って生活を送る
資産の増殖
不労所得は、資産を複利で増やし、さらなる収入を生み出すことで、世代を超えて資産を継承することも可能にします。
- 複利効果: 投資によって資産を増やし、さらなる収入を生み出す
- 世代間の資産移転: 子孫に資産を残すことも可能
このように、不労所得は、経済的な安定だけでなく、精神的な豊かさも手に入れることができます。*3)
不労所得のデメリット:不労所得で失敗しないために

不労所得は、労働を伴わずに得られる収入と考えがちですが、実際には数々のデメリットやリスクが存在します。
初期資金の準備
不動産投資や株式投資には、相応の資金が必要です。資金の用意に時間がかかる点もデメリットの1つです。
例えば、不動産投資の場合、物件購入のためのローンや初期費用を準備するのに数ヶ月から数年かかることがあります。
高額セミナーの落とし穴
不動産投資や金融商品に関する高額セミナーや勉強会には、注意が必要です。
高額な参加料
有料の不動産投資セミナーや勉強会には、高額な参加料がかかることがあります。参加料が高額であることが、質の高い内容である保証ではありません。
実際に、数十万から百万以上の参加料を支払ったにもかかわらず、内容が本で学べるレベルであったり、業者から高額な物件を売りつけられたりするケースがあります。
業者の売り手意識
有料セミナーや勉強会では、業者が自身の売りたい物件を推奨することがあります。参加者は、現実的なシミュレーションを組むことが難しくなります。
例えば、セミナーの講師が実際に不動産投資をしているわけではなく、業者から紹介された物件を推奨しているケースがあります。
投資詐欺に注意
不労所得を得るための投資において、詐欺的な勧誘には注意が必要です。
高収入を約束する詐欺
「簡単に高収入を得られる」と謳う詐欺的な投資話が多く存在します。金融庁からも注意喚起されているように、元本保証がない場合、全財産を失う危険性があります。
近年でも、FXや暗号資産投資を名目とした詐欺グループが、高収入を約束し、多くの被害者を出しています。
「ポジショントーク」
SNSなどで蔓延している「ポジショントーク」にも警戒が必要です。発信者自身の利益のために、投資商品や銘柄を過度に美化し、フォロワーを誘導する行為が頻発しています。
こうした情報は客観性を欠き、投資判断を誤らせる危険性があります。
忍耐が必要な場合も
不労所得を得るためには、長期的な忍耐と努力が必要な場合があります。
時間と労力の投資
不労所得を確立するまでに、多大な時間と労力を投資する場合があります。特に、ブログ運営やYouTubeでの収益は、短期的な利益を期待することが難しい方法です。
さらに、コンテンツ制作やマーケティングに多くの時間を費やさなければ、収益が得られない場合もあります。
その他のリスク
不労所得に関連するその他のリスクも存在します。
空室リスクや滞納リスク
不動産投資の場合、空室リスクや入居者の家賃未払いリスクがあります。これにより、予想していた収益が得られない場合があります。
例えば、不動産投資で空室が続くと、家賃収入が得られず、赤字になる可能性があります。
修繕コストや税負担
また、不動産投資では、修繕コストや税負担が増加するリスクがあります。特に、駐車場経営の場合、減価償却ができず税負担が大きくなることがあります。
このように不労所得を得る際には、多くのデメリットやリスクが存在します。各手段においての注意点をよく理解し、慎重な判断と計画を立てることが重要で、金融リテラシーの向上が成功の鍵となるでしょう。*4)
不労所得で生活することは可能なのか

多くの人が夢見る不労所得による生活。その実現可能性と、成功への道筋を探ってみましょう。
不労所得の実現性と個人の適性
不労所得で生活することは、決して夢物語ではありません。しかし、その難易度は収入源によって大きく異なります。
株式投資、不動産投資、知的財産権など、さまざまな選択肢がある中で、
- 自身のリスク許容度
- 初期投資額
- 性格
- 時間的制約
を考慮し、最適な方法を選択することが重要です。
不労所得で生活するための時間的制約とは
不労所得で生活するには、十分な資産形成期間が必要です。一般的に、若いうちから始めるほど有利とされ、複利効果を最大限に活用できます。
しかし、中高年からでも、より積極的な投資戦略や支出の見直しにより、目標達成は可能です。重要なのは、自身のライフステージに合わせた現実的な計画を立て、早めに行動を起こすことです。
FIREムーブメントと現実的なアプローチ
近年注目を集めているFIRE(Financial Independence, Retire Early)は、早期退職を目指す金融戦略です。しかし、完全な経済的自立を目指す「フルFIRE」は、多くの人にとってハードルが高いのが現実です。
そこで注目されているのが「サイドFIRE」です。これは、不労所得と一部の労働収入を組み合わせるセミリタイアのスタイルで、より現実的なゴールとして支持を集めています。
長期的視点と分散投資の重要性
【長期投資の運用成果】

上のグラフは、金融庁が作成した1989年以降、毎月同じ金額ずつ国内外の株式と債券に積立投資を行い、5年間と20年間それぞれ保有した場合についての年間収益率と運用結果を計算したものです。長期的な視点で資産形成をすれば複利の効果も大きくなり、元本割れするリスクは低くなるものの、途中でやめてしまうと元本割れのリスクが高くなることがわかります。
このように、不労所得を安定的に得るには、長期的な視点が欠かせません。日経平均株価の長期シミュレーションによると、定期的な積立投資を続けることで、市場の変動を平準化し、安定的なリターンを得られる可能性が高まります。
また、リスクとリターンのバランスを考慮した分散投資も重要です。
【日経平均最高値の翌月から日経平均に毎月積立投資をした場合のシミュレーション】

結論として、不労所得で生活することは誰にでも可能ですが、その道のりは決して平坦ではありません。自身の状況を冷静に分析し、適切な戦略を立てることが成功への鍵となります。
初心者でも、慎重かつ前向きに取り組むことで、安定した不労所得の獲得ができるでしょう。*5)
不労所得を得るためにやるべきこと

不労所得の獲得は、誰もが実現可能な目標です。この章では、初心者に向けて、不労所得を作るための具体的な準備と実践方法を紹介します。
【安定的な資産形成のために必要なもの】
金融リテラシーの向上
不労所得を得るための第一歩は、金融リテラシー(マネーリテラシー)の向上です。つまり、お金に関する知識と判断力を身につけることです。
金融リテラシーを高めるには、以下の方法が効果的です。
- 金融関連の書籍や記事を定期的に読む
- 金融庁や消費者庁が提供する無料の教育コンテンツを活用する
- 信頼できる金融専門家のセミナーや講座に参加する
- 投資シミュレーションツールを使って、仮想的な運用を体験する
金融リテラシーを向上させることで、投資リスクの理解や詐欺的商品の見分け方など、自己防衛能力が高まります。
【リスク=リターンの不確実性の大きさ、振れ幅の大きさ】

お金にまつわる5つの力の習得
不労所得を安定的に得るためには、以下5つの力を習得しましょう。
- 貯める力:収支を管理し、収入の一部を定期的に貯蓄に回す習慣をつける
- 増やす力:適切な投資方法を選択し、資産を成長させる能力を養う
- 稼ぐ力:本業以外の収入源を開拓し、収入を多様化する
- 使う力:効果的に投資し、無駄な出費を抑える
- 守る力:リスク管理を行い、資産を保護する
これらの力を総合的に高めることで、安定した不労所得の基盤を築くことができます。
具体的な行動計画の立案
不労所得獲得への道のりは、具体的な行動計画から始まります。以下のステップを参考に、自分なりの計画を立ててみましょう。
- 現在の財務状況を把握する:収入、支出、資産、負債を明確にする
- 目標を設定する:具体的な金額と期限を決める
- 投資方法を選択する:リスク許容度に合わせて、適切な投資手段を選ぶ
- 定期的な見直しを行う:計画の進捗状況を確認し、必要に応じて調整する
継続的な学習と実践
不労所得の獲得は、一朝一夕には実現しません。継続的な学習と実践が不可欠です。
- 最新の金融情報をキャッチアップする
- 少額から始めて、徐々に投資額を増やす
- 失敗から学び、投資戦略を改善する
- 長期的な視点を持ち、短期的な変動に一喜一憂しない
顧客本位の金融サービスの活用
金融庁が推進する「顧客本位の業務運営」※に基づいたサービスを選択することが重要です。以下の点に注意しましょう。
- 金融事業者の透明性と情報開示を確認する
- 手数料体系を比較し、自身のニーズに合ったサービスを選ぶ
- 投資商品の特性とリスクを十分に理解してから取引を行う
新NISAの活用
2024年から始まった新NISAは、長期的な資産形成に適しています。NISAの特徴を理解し、活用を検討しましょう。
- 非課税投資枠の拡大:年間120万円まで
- 非課税期間の無期限化
- つみたて投資の推奨:長期的な資産形成に適している
【NISAのポイント】

不労所得を得るためにやめるべきこと
最後に、不労所得の妨げとなる代表的な行動をご紹介します。
- 衝動的な投資:十分な調査なしに投資を行う
- 過度なリスク:自身の許容範囲を超えたリスクを取る
- 情報の鵜呑み:SNSなどの情報を無批判に信じる
- 短期的な利益追求:長期的な視点を失い、短期的な利益にこだわる
- 投資の放置:定期的な見直しを怠る
これらの行動を避け、計画的かつ慎重に不労所得の獲得を目指しましょう。
不労所得の獲得は、決して簡単ではありませんが、適切な知識と行動により、誰もが達成可能な目標です。金融リテラシーの向上と5つの力の習得を基盤に、継続的な学習と実践を重ねることが大切です。*6)
不労所得にかかる税金:確定申告は必要か?
不労所得にも税金はかかるの? かかるとしたらどのくらい?
不労所得にも税金はかかります。税率は所得の種類や金額によって異なります。
例えば、株式の配当金や譲渡益に対しては、原則として20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率が適用されます。ただし、NISAなどの非課税制度を利用すれば、一定額まで非課税で運用できます。
不動産収入の場合は、必要経費を差し引いた所得に対して累進課税が適用されます。税率は所得金額に応じて5%から45%まで段階的に上がります。
※税法は頻繁に改正されるため、最新の情報を確認する必要があります。
不労所得に確定申告は必要?
一定額以上の不労所得がある場合は確定申告が必要です。具体的には、年間の不労所得が20万円を超える場合、確定申告の義務が生じます。
確定申告は毎年2月16日から3月15日までの期間に行う必要があります。ただし、給与所得者の場合、副業等による所得が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。
注意点として、医療費控除やふるさと納税の寄付金控除を受けたい場合は、20万円以下でも確定申告が必要となる場合があります。
不労所得だけで生活している人の特徴
不労所得だけで生活している人には、以下のような特徴が見られる傾向があります。
- 財務管理能力が高い:収支のバランスを適切に管理し、計画的な資産運用を行う
- リスク管理意識が強い:投資の分散や緊急時の備えなど、リスク管理を徹底
- 節約志向:不要な出費を抑え、効率的な生活を心がけている
- 継続的な学習:経済動向や投資知識に関心を持ち続ける
- 長期的視点:短期的な変動に一喜一憂せず、長期的な視点で資産管理を行う
- 時間の有効活用:仕事に縛られない時間を、自己啓発や趣味、社会貢献などに充てている
- 柔軟な生活スタイル:収入の変動に応じて、生活スタイルを柔軟に調整できる
これらの特徴は、不労所得で生活するための重要なポイントとなります。
不労所得に関してよくある疑問

不労所得は多くの人にとって魅力的な収入源ですが、多くの人がさまざまな疑問や不安も抱えています。よく寄せられる質問に対して、わかりやすく回答していきます。
不労所得で月5万円を得るにはいくらの元手が必要?
不労所得で月5万円(年間60万円)を得るために必要な元手は、投資方法によって大きく異なります。
例えば、株式投資の場合、配当利回りを3%と仮定すると、約2,000万円の投資が必要となります(60万円÷3%)。不動産投資の場合、利回りを5%と仮定すると、約1,200万円の物件購入が必要となります(60万円÷5%)。
ただし、これらは単純計算であり、実際には
- 税金
- 経費
- リスク
なども考慮する必要があります。また、複数の投資方法を組み合わせることで、より少ない元手でも目標を達成できる可能性があります。
不労所得で月20万円得るにはどうすれば良い?
月20万円の不労所得を得るには、多くの場合は元手が必要となります。投資初心者でも狙いやすい2.5~5&の年利を目標とする場合は4,800万円の元手が必要となります。
元手が多ければその分不労所得を得られる可能性は高まりますが、元手0円で月20万円の不労所得を得ることも不可能ではありません。ブログおアフェリエイトやYouTubeの広告収入による不労所得獲得を目指しましょう。
不労所得は本当に労力がかからないの?
完全に労力がかからない不労所得は稀です。多くの場合、初期投資や継続的な管理が必要となります。
例えば、不動産投資では物件の選定や管理、修繕などに時間と労力がかかります。株式投資でも、銘柄の選定や市場動向の分析が必要です。
ただし、投資信託やETFなどのパッシブ運用商品を選択したり、不動産管理を専門業者に委託したりすることで、労力を最小限に抑えることは可能です。
不労所得と副業の違いは?
不労所得と副業の主な違いは、労働の有無にあります。
- 不労所得:原則として直接的な労働を必要とせずに得られる収入(株式の配当金、不動産賃貸収入、著作権使用料など)
- 副業:通常、何らかの労働を伴う(フリーランスの仕事、パートタイムの勤務、オンラインでの物販など)
ただし、実際には両者の境界線が曖昧な場合もあります。例えば、ブログ運営によるアフィリエイト収入は、初期の労力投下後は比較的労力の少ない収入源となる可能性があります。
不労所得は将来的にも安定していると言える?
不労所得の安定性は、収入源や経済状況によって大きく異なります。
例えば、国債の利子収入は比較的安定していますが、利回りが低いのが一般的です。株式の配当金は企業業績に左右され、変動する可能性があります。
また、不動産賃貸収入は、長期契約であれば安定しやすいですが、空室リスクや物件の価値下落リスクがあります。
将来的な安定性を高めるには、
- 複数の不労所得源を持つこと(分散投資)
- 定期的な見直しと調整
- 経済情勢や法制度の変化にも注意を払う
などの必要があります。
やめとけと言われる理由は?
不労所得を得ることを否定的に捉える人がいる理由には、以下のようなものがあります。
- リスクの過小評価:初心者が投資リスクを軽視し、大きな損失を被る可能性
- 詐欺や悪質商法の存在:「簡単に儲かる」と謳う詐欺的な投資話に騙される危険性
- 税務上の複雑さ:確定申告などの手続きが必要となり、税務上の手間がかかる
- 労働倫理観との衝突:「楽して稼ぐ」という考え方に抵抗を感じる人も存在
- 長期的視点の欠如:短期的な利益を追求するあまり、長期的な資産形成を疎かにする危険性
これらの懸念は理解できますが、適切な知識と慎重な姿勢を持って取り組めば、不労所得は有効な資産形成の手段となり得ます。
初期投資はどれくらい必要?
初期投資の金額は、選択する不労所得の種類や目標収入によって大きく異なります。
- 株式投資:少額から始められる(安定した配当収入を得るには数百万円以上の投資が必要な場合が多い)
- 不動産投資:一般的なアパート経営では、数千万円の初期投資が必要(ただし、不動産クラウドファンディングなら数万円から始められる)
- 債券投資:国債や社債は通常10万円単位で購入可能
- 投資信託:数千円から始められるものもある
- オンラインビジネス(ブログ、YouTube等):初期費用は数万円程度ですが、収益化までに時間がかかることが多い
重要なのは、自己資金の範囲内で無理のない投資を行うことです。また、リスクを考慮し、分散投資を心がけることが賢明です。
不労所得の獲得に向かって、自己の状況を客観的に分析し、リスクと向き合いながら、着実に前進しましょう。*7)
不労所得を得るためのおすすめの方法
不労所得を得るためには、多くの方法が存在します。リスクとリターンのバランスを考えた上で、自分に合った方法を選びましょう。
【金融商品の3つの基準】

初心者にもおすすめできる不労所得を6つ紹介します。
【初心者にもおすすめな不労所得】
| 方法 | 内容 | 期待できる成果 | 必要な知識・スキル | リスク |
|---|---|---|---|---|
| ①投資信託 | 多様な資産に分散投資(1万円以下から可能な金融機関も) | 安定した収益、リスク低減 | 基本的な投資知識投資目的・リスク許容度の理解 | 市場変動による収益変動リスク |
| ②株式投資 | 配当金や長期分散投資(少額からの可能) | 長期的高リターン、安定収益(配当金) | 株式市場の理解投資先選定能力ドルコスト平均法 | 市場変動による収益変動リスク |
| ③太陽光発電投資 | 自宅・駐車場の屋根に設置した太陽光パネルで発電 | 再生した電力を自宅で使用、余った電力を電力会社へ売却 | 難しい知識は不要 | 設置場所や日照条件が収益に影響し、収入が不安定になるリスク |
| ④駐車場経営・コインランドリー | まとまった初期投資が必要運営が簡単 | 定期的な収入、手間少ない | 運営管理知識、顧客サービススキル | 初期投資が必要利用率低下・維持管理コスト増大リスク |
| ⑤広告収入(ブログ・YouTubeなど) | 初期費用が少ない継続的なコンテンツ制作必要 | 広告収入・アフィリエイト収入、人気コンテンツで高収入 | コンテンツ制作スキルSEO・マーケティング知識 | コンテンツ評判・視聴者数低下による収入減少リスク |
| ⑥印税収入 | 書籍、音楽、特許などからの収入初期制作労力が必要 | 継続的な収入 | 創作スキル著作権・特許知識 | 市場需要・競争による収入減少リスク |
不労所得は、少額の資金から始めることも可能ですが、リスクを伴うことも事実です。成功の鍵は、
- 自分にあった手段
- 継続的な学習
- 行動力
- 適切なリスクを取る
です。特に、金融リテラシーを身に着け、自分にとっての適切なリスクを取れるようになることは重要です。
6つの不労所得について順番に解説します。
投資信託
投資信託とは専門家に投資運用を任せ、利益と手数料の差を投資家が受け取る手法です。専門家が代わりに運用してくれるため、投資家は手間がかからず投資の利益を得られます。
投資家へ手数料を支払うため自分で投資するよりも利益が少なくなりますが、プロが投資してくれるリスクが低くなりやすいです。また、プライベートが忙しく投資に時間を割けない方にも適しています。
株式投資
インターネットや店舗で証券口座を開設後、口座に投資資金を入金し、株式を購入することで株式投資ができます。株式投資の主な収益の受け取り方は、以下の2つです。
- 株式の売却益
- 配当金
株価が安い時に株式を購入し、価格が上昇した段階で売却すれば、その差額が株式の売却益になります。
また、株式を保有し続けることで、株価購入の返礼として配当金を受け取れます。企業の業績次第では、一定期間配当金を受け取れるため、業績のよい企業の株式を購入できれば大きな不労取得になるでしょう。
しかし株式投資は、企業の業績によって収益がマイナスになる可能性があるため、投資商品を見極める能力が必要です。
太陽光発電投資
自宅の駐車場や屋根にソーラーパネルを設置して、充電する手法です。充電した太陽光は自宅利用したり、電力会社に売電できたりします。
日照条件や自宅場所がよければ、効果的に太陽光を集め大きな収益を得られるでしょう。また電気に変換する際に、多大の温室効果ガスを排出しますが、太陽光の電力を電気に変遷する際は二酸化炭素をほとんど排出しないため、環境に優しい手法としても注目を集めています。
しかし、ソーラーパネルの購入・設置で高額な初期費用がかかる点に注意が必要です。
駐車場経営・コインランドリー
空いた土地を利用して、駐車場・コインランドリーを経営する方法もあります。駐車場利用者の集め方は主に、不特定多数が利用するコインランドリーと固定客が利用する月極駐車場に分けられます。
駅前や繁華街といった多くの人が利用する場所では、コインランドリーのほうが利益を出しやすいです。一方で月極駐車場は、初期費用や手間を抑えられる点で地方の土地を活用する際におすすめです。
また駐車場管理会社や不動産会社に相談すると、その土地に適した空地の利用方法がわかるため相談を心がけてみてください。
広告収入(ブログ・YouTubeなど)
ブログやYouTubeを利用して不労所得を得る方法があります。ブログやYouTubeなどのSNSから広告収入を得るメリットは、以下の通りです。
- 初期費用が少ない
- 初心者でも始めやすい
- 軌道に乗れば高額の不労所得を得られる
- 隙間時間で取り組める
- 趣味や好きなことを仕事にできる
高額な費用をかけることなく、趣味や好きなことを仕事にできるメリットがあります。一方で、収益化するまでに多大な時間・労力がかかったり、継続が大変だったりするデメリットもあります。
SNS運用を利用して不労所得を得るには、かなりの手間がかかる点を把握しておきましょう。
印税収入
書籍や楽曲を販売すれば、作品が売れた際に収益を印税収入として受け取れます。印税収入のメリット・デメリットは、以下の通りです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・人気が出れば高額の収益を得られる ・好きなことをビジネスにできる | ・高額な利益を出すには手間がかかる ・自費で出版すると赤字の可能性がある |
趣味で不労所得を得られるメリットがありますが、利益が出るまでに時間がかかりやすいです。ある程度の実績を保有している方や、作品作りを継続できる方におすすめします。
注目の不労所得:個人にもできるシェアリングエコノミー
【シェアリングエコノミーの例】
新しい不労所得獲得のヒントとして、近年、注目を集めているシェアリングエコノミーを紹介します。これは、単なる流行語にとどまらず、私たちの生活や経済構造を大きく変えつつあります。
シェアリングエコノミーは、モノやサービスを所有するのではなく、必要な時に必要な分だけ共有し、利用する経済モデルです。従来の所有経済とは対照的で、インターネットやスマートフォンなどのテクノロジーの発展によって、その可能性が大きく広がっています。
【個人にもできるシェアリングエコノミーの例】
| 分類 | 方法 | 内容 | 特徴 | リスク |
| 空間(スペース)シェアリング | 民泊、駐車場シェアリング | 空き部屋や駐車場を貸し出す(Airbnb、スペースマーケット) | 定期的な収入運営が簡単空きスペースの有効活用 | 初期投資必要利用者トラブル破損リスク |
| モノのシェアリング | カーシェアリング高級アイテムレンタル | 車、自転車、高級ブランド品を貸し出す(カーシェアリング、高級バッグレンタル) | 利用されない時間に収入維持費の分散 | 高級アイテムの所有などが必要利用者トラブルアイテム破損リスク |
| スキルシェアリング | コーディングデザイン翻訳コンサルティング | 自身のスキルをオンラインで提供(クラウドソーシング、フリーランス) | 時間的柔軟性、高収入可能自己成長にもつながる | スキル向上の初期投資必要分野によっては競合が多い |
| 金融のシェアリング | P2Pレンディングクラウドファンディング | インターネット上のマッチング、資金調達(CAMPFIRE、Makuake) | 多様な投資機会元本保証がない場合が多い法的な知識が必要 | 資金調達失敗、プロジェクトの失敗による投資損失 |
シェアリングエコノミーは、個人にも大きなチャンスをもたらす経済モデルです。初期費用を抑えて始められるものも多く、副業や新たな収入源として注目されています。
しかし、始める前に、法規制やリスクについてしっかりと理解し、慎重に進めることが大切です。*8)
不労所得とSDGs
【SDGs】
不労所得とSDGsは、一見あまり関係がないように思えますが、実は持続可能な社会の実現という共通の目標を持っています。
- 不労所得:個人の経済的自立を促進
- SDGs:地球規模の課題解決を目指す
この2つは、長期的な視点で社会や環境の持続可能性を追求する点で一致しているのです。不労所得が、SDGsの達成において特に重要な役割を果たす可能性のある目標を見ていきましょう。
SDGs目標1:貧困をなくそう
不労所得は、個人の経済的自立を支援し、貧困リスクを軽減します。例えば、配当収入や不動産賃貸収入は、安定した収入源となり、経済的なセーフティーネットを提供します。
また、マイクロファイナンス※への投資は、発展途上国の起業家を支援し、貧困削減に貢献します。
SDGs目標8:働きがいも経済成長も
不労所得は、個人に経済的な余裕をもたらし、より創造的な仕事や社会貢献活動に時間を割くことを可能にします。これは、イノベーションの促進や生産性の向上につながり、持続可能な経済成長に貢献します。
また、クラウドファンディングを通じた新規事業への投資は、雇用創出と経済活性化にもつながります。
SDGs目標11:住み続けられるまちづくりを
不動産投資を通じて、老朽化した建物を改修したり、新しいコミュニティスペースを創出したりすることで、都市の再生に貢献できます。また、再生可能エネルギーを活用した不動産開発を行うことで、環境負荷の低減にもつながります。
SDGs目標12:つくる責任 つかう責任
不労所得を得るための投資活動において、環境や社会に配慮した企業や事業を選択することで、持続可能な生産と消費を促進できます。例えば、ESG投資を通じて、環境保護や社会的課題の解決に取り組む企業を支援することができます。
【ESG投資とは】

不労所得は、単なる経済的な目標ではなく、より大きな視点から社会貢献に繋がる可能性を秘めています。不労所得を獲得する上でも、SDGsの目標達成に目を向けて、自分のできることから少しずつ貢献していくことが大切です。*9)
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ

近年では、金融庁の政策後押しもあり、個人の資産形成に対する関心が高まっています。例として、積立NISAの口座数・買付額が年々増加していることは、長期的な資産形成への意識の高まりを示しています。
【NISA(一般・つみたて)口座数及び買付額の推移】
近年では、中国のスニーカー投資※のように短期的な高リターンを求める投資や、FIREムーブメントによる早期退職を焦る人も目立ちます。しかし、完全に不労所得だけで生活することは、不可能ではありませんが、人によってはかなりハードルが高い場合があります。
そんな多くの人にとっては不労所得を得ながら、ゆとりを持って働く「サイドFIRE」を目指すことも賢明な選択と言えます。収入減が複数あると、分散投資のようにリスクの分散効果も得られます。
また、不労所得だけで生活ができるようになったからと言って、幸せが約束されるわけではありません。あなたにとって最良の仕事と生活のバランスを見つけ、充実した日々を過ごすことが大切です。
たとえ自分にはFIRE達成が困難な状況にあるとしても、劣等感を感じる必要はありません。金融リテラシーを磨き、適切なリスクが取れるようになれば、不労所得より安定した生活を獲得することは誰にでも可能です。
不労所得獲得は私たちの生活を安定させる上で有効な手段です。不安のない充実した生活のために、あなたのライフプランを明確にし、適切な方法で効率的に資産を形成しましょう。
<参考・引用文献>
*1)不労所得とは
日本証券業協会『金融所得の実態に関する分析~「1億円の壁」を読み解く~』(2022年8月)
金融庁『資産運用立国の実現』(20224年3月)
国税庁『不動産所得の範囲について-「貸付けによる所得」の意義-』
内閣府『第3節 資産インフレの諸影響』
財務省『令和5年度税制改正の大綱の概要』(2023年12月)
金融庁『4 「貯める・増やす」 ~ 資産形成』
金融庁『資産運用立国について』(2024年11月)
日本経済新聞『不動産賃貸事業は「不労所得」にあらず 戦術が重要に』(2021年11月)
日本経済新聞『駐車場、自販機、太陽光…「置くだけ」投資で不労所得』(2016年5月)
内閣府『第2章 バブル崩壊と景気後退』
日本経済新聞『格差研究の気鋭、ピケティによるピケティ入門 『トマ・ピケティの新・資本論』』(2015年1月)
東洋経済ONLINE『「ピケティ」は人口減少の日本で成り立つのか 年5%の「不労所得」はそう簡単じゃない』(2015年2月)
東証マネ部『【日経記事でマネートレーニング35】資産形成編(2)金融副業力を身につける~4つの視点でポートフォリオ構築』(2023年2月)
金融庁『金融所得課税一体化論と証券投資優遇税制』
金融庁『資産所得倍増プランについて』(2023年1月)
金融庁『資産所得倍増プランと資産形成支援に関する取組み』(2023年8月)
MoneyForward『投資は副業にあたる?初心者におすすめの投資や、会社にバレない方法も紹介!』(2023年12月)
東洋経済ONLINE『今や錦の御旗となった「実質賃金の上昇」の残念感 抽象的すぎるフレーズ、実現の経路は複雑怪奇』(2024年12月)
*2)不労所得の種類(代表例)
金融庁『資産形成の基本』
金融庁『NISAを知る』
金融庁『外国為替証拠金取引について』(2020年2月)
金融庁『店頭FX取引の現状とそのリスク管理』(2018年3月)
金融庁『暗号資産関係』
金融庁『暗号資産(仮想通貨)に関連する制度整備について』(2021年4月)
金融庁『「決済」法制及び金融サービス仲介法制に係る制度整備についての報告 』(2019年7月)
国税庁『No.1500 雑所得』(2024年4月)
東洋経済『「不動産投資」は金持ちほど圧倒的に有利な理由 「利益ゼロの人」「大儲けする人」の大差』(2019年9月)
日本経済新聞『賃貸経営、節税封じ 税制改正や富裕層の監視強化』(2020年2月)
日本経済新聞『高配当株で資産2億円 配当は年470万円でFIRE果たす 新NISAで始めよう 憧れの配当生活(2)』(2023年8月)
MUFG『手元の100万円をふやすには?』
国税庁『利子・配当 特定口座 譲渡損益』
日本証券業協会『中間層の資産所得倍増に向けたNISAの抜本的拡充・恒久化について』(2022年11月)
日本経済新聞『不動産投資信託(REIT) 賃料収入を投資家に分配』(2022年7月)
日本経済新聞『REIT、資産査定の記録の保存要請 金融庁が監督指針改正』(2024年4月)
日本経済新聞『マンション投資、売却益は減少へ 「バブル末期と酷似」』(2024年12月)
日本経済新聞『FX規制強化へ 金融庁、証拠金倍率10倍に下げ』(2018年2月)
東洋経済ONLINE『零細企業が駐車場事業で大手参入を退けた理由 資本金5万円で創業のakippaは楽天にどう対抗したか』(2024年9月)
日本経済新聞『新興企業、ロッカーに商機 再配達の荷物預かり』(2019年3月)
金融調査研究会『わが国銀行を取り巻く環境変化と収益源の多様化』(2020年3月)
首相官邸『知的財産推進計画2024』(2024年6月)
日本経済新聞『技術力・知財、融資の担保に 中小・新興にマネー供給』(2022年10月)
日本経済新聞『重み増す知財や人権 金融庁・東証、企業統治指針改定へ』(2021年5月)
日本知財学会『知財金融の考え方と現状』(2016年)
MoneyForward『特許権の会計処理と償却方法を仕訳まで解説』(2024年8月)
MoneyForward『クリエイターの夢…それは印税生活!印税収入の相場について専門家に聞いてみた』(2019年2月)
消費者庁『シェアリングエコノミー』(2021年10月)
デジタル庁『シェアリングエコノミー活用ハンドブック』(2022年3月)
総務省『シェアリングエコノミーの持つ可能性』(2018年)
*3)不労所得のメリット
MUFG『FIREとは?メリット・デメリットや実現方法をわかりやすく解説!』(2024年8月)
MUFG『どうして資産形成が必要なの?』
投資信託協会『資産運用の必要性』
全国銀行協会『将来のためにできること、それが資産形成』(2024年11月)
JPX『なぜ資産形成が必要なのか?その背景・理由とは』
日本FP協会『FIREという考え方』(2022年5月)
日経ビジネス『岸田政権の目玉政策「資産所得倍増プラン」のメリットとリスク』(2023年12月)
NOMURA『人生100年時代でも怖くない。知っておきたい資産形成術とは【第1回】』
NOMURA『なぜ今、投資が重要なのか? インフレと人生100年時代における資産形成の必要性—親子で学ぶお金の話(8)』
J-FLEC『人生にかかるお金、資産形成の視点』
金融広報中央委員会『資産形成。「お金にも働いてもらう」という考え方』
リベラルアーツ大学『【あなたもなれる】不労所得で暮らせるようになって感じたこと7選を紹介!』(2023年5月)
*4)不労所得のデメリット:不労所得で失敗しないために
東洋経済ONLINE『「不動産投資に失敗する人」の甘すぎる考え サラリーマンが簡単にできるものじゃない』(2016年9月)
東洋経済ONLINE『早期リタイア「FIRE」を目指して結局後悔する理由 FIREの資金ができた頃、「つまらない人間」に』(2022年7月)
日本経済新聞『FIREは可能か 投資で生計、急落時やインフレに注意 会社員 第二の人生(下)』(2023年9月)
東証マネ部『課税タイミングは「売却時に利益が発生していた時」税率20%以上!? 投資で得た利益にかかる「税金」のキホン』(2021年3月)
日本経済新聞『不動産所得、目光らす税務当局 徴収強化に本腰 申告漏れや必要経費、細かく調査』(2013年9月)
金融庁『「FX取引・暗号資産投資の勧誘」にご注意!!』(2023年4月)
消費者庁『無登録業者との外国為替証拠金取引(FX)にご注意ください!』
消費者庁『簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などの勧誘により「副業」の「マニュアル」を消費者に購入させた事業者に関する注意喚起 』(2022年4月)
国民生活センター『SNS 上の投資グループで勧誘される詐欺的な FX 取引トラブル-その仲間、信じて大丈夫?-』(2024年1月)
国民生活センター『新たな“もうけ話トラブル”に注意-オンラインサロンで稼ぐ!?-』(2021年7月)
警視庁『令和4年における生活経済事犯の検挙状況等について』(2023年3月)
*5)不労所得で生活することは可能なのか
金融庁『4 「貯める・増やす」 ~ 資産形成』
金融庁『資産所得倍増プランについて』(2023年1月)
日本証券業協会『金融所得の実態に関する分析~「1億円の壁」を読み解く~』(2022年8月)
日本証券協会『とうしくんのギモン【第5回】 FIREって、なに?』
PRESIDENT Online『老後資金は「2000万円→1370万円問題」に…60歳から投資を始めて70歳以降は不労所得を確保する新NISA活用術』(2024年8月)
日経ビジネス『「不労所得だけ」の生活について考える』(2016年3月)
東洋経済ONLINE『年収400万円の人が「労働から解放」される方法 じわじわ広がるFIREムーブメントの実際』(2020年2月)
東洋経済ONLINE『「FIREしたい人」月にいくら必要か知っていますか 現在の年収と近い額を投資で得ることは超困難』(2022年9月)
東洋経済ONLINE『年収300万円OLが30代でセミリタイアできた理由 「ゆるFIRE」という悠々自適の生活スタイルとは』(2022年3月)
日本経済新聞『FIREするなら何歳? 3つのルートで考える 日本版FIREを考える(5)』(2021年8月)
中島 淳一『国民の安定的な資産形成と顧客本位の業務運営』(2023年4月)
野村アセットマネジメント『国民総NISA活用時代は訪れるか?~「本家」英国ISAの軌跡から読み解く~』
*6)労所得を得るためにやるべきこと
金融庁『資産所得倍増プランについて』(2023年1月)
金融庁『4 「貯める・増やす」 ~ 資産形成』
金融庁『「新しい NISA 制度」が国民の資産形成を強力に後押し 官民一体となって国民の投資意欲を醸成する 』(2023年2月)
金融庁『NISAを知る』
野村證券『マネーシミュレーター「みらい電卓」~積立編』
東洋経済ONLINE『「いつのまにか資産家になる人」に共通する習性 資産を築くには、収入より支出を意識すべき理由』(2023年3月)
PRESIDENT Online『老後2000万円には「貯金なら毎月6万円」だが「新NISAなら月2万5000円」…富裕層が必ず資産運用をするワケ 「つみたて投資」を続ければ、だれでも資産を築ける』(2023年7月)
日本経済新聞『FIREを成功に導く大事なスキル それは節約 日本版FIREを考える(3)』(2021年8月)
日本経済新聞『早期引退の夢「FIRE」したい人がいますべきこと 70歳リタイア時代の働き方(5)』(2021年3月)
日本経済新聞『FIREのリアル 米国株や不動産に投資、生活は質素』(2022年1月)
NRI『『貯蓄から投資へ』『資産所得倍増計画』推進の3本柱(2022年9月)
金融庁『つみたてシミュレーター』
消費者庁『マネープランシートを作成しながら収入と支出、家計の管理方法を学ぼう!』
政府広報ONLINE『「金融リテラシー」って何? 最低限身に付けておきたいお金の知識と判断力』(2024年10月)
リベラルアーツ大学『これを知らずにお金持ちになるのは無理!豊かなお金持ちが極めている5つの力』(2023年4月
リベラルアーツ大学『【人生を無駄にしないために】両学長が「絶対にやらない」と決めている25のことを公開』(2024年1月)
リベラルアーツ大学『【○○力を高める】貯金も投資もせず経済的に豊かになる方法』(2024年8月)
*7)不労所得に関してよくある疑問
国税庁『株式・配当・利子と税』
国税庁『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』
国税庁『定額減税について』
国税庁『所得税の現状と課題-包括的所得税の変容と所得税の今後の課題-』
財務省『金融所得課税・富裕層課税の新たな展開』(2024年8月)
財務省『金融・証券税制に関する資料』
総務省『個人住民税における金融所得課税について』(2022年7月)
日本証券協会『株式投資にかかる税金って?』
MoneyForward『株で得た利益は年末調整が必要?iDecoやNISAについても解説』(2024年11月)
NOMURA『NISAで投資を始める人たちへ 第3回 なぜ資産運用が必要なのか』
リベラルアーツ大学『図解でわかるお金の基礎知識まとめ【守る力-資産を減らさない力-】』(2024年10月)
*8)おすすめの不労所得5選
金融庁『4 「貯める・増やす」 ~ 資産形成』
中小企業庁『3 シェアリングエコノミーの認知度と活用に向けた課題』
日経ビジネス『「不労所得だけ」の生活について考える』(2016年3月)
日本経済新聞『不動産賃貸事業は「不労所得」にあらず 戦術が重要に』(2021年1月)
経済産業省『シェアリングエコノミービジネスについて』
経済産業省『シェアリングエコノミー認定制度の仕組みと展望』
総務省『第1部 特集 人口減少時代のICTによる持続的成長第5節 シェアリングエコノミーの持つ可能性』
nikkei4946『シェアリングエコノミーについて知る」(2018年3月)
日経ビジネス『シェアリングエコノミーが生み出す新しい経済と課題』(2021年9月)
日本経済新聞『シェアリングエコノミー経済規模は過去最高 1兆8,000億円超え、30年には11兆円と予測生活の充実度や幸福度向上にも寄与[一般社団法人シェアリングエコノミー協会]』(2019年4月)
リベラルアーツ大学『【ズルすぎ?】月3万円の配当金で出来るこれだけのこと』(2024年4月)
リベラルアーツ大学『図解でわかるお金の基礎知識まとめ【守る力-資産を減らさない力-】』(2024年10月)
リベラルアーツ大学『【おすすめ投資信託も紹介】インデックス投資の始め方から出口戦略まで徹底解説!』(2023年7月)
*9)不労所得とSDGs
国際連合広報センター『持続可能な開発目標(SDGs)とは』
金融庁『4 「貯める・増やす」 ~ 資産形成』
金融庁『金融行政とSDGs』(2018年12月)
金融庁『持続可能な社会を支える金融システムの構築』(2021年6月)
金融調査研究会『SDGs に金融はどう向き合うか』(2019年3月)
日本証券業協会『SDGsに貢献する金融商品について』
日本証券業協会『SDGs・ESGのいろは~証券投資でより良い世界を~』
日本銀行『SDGs/ESG金融を巡る最近の動向』(2021年1月)
*10)まとめ
金融庁『資産運用立国について』(2023年12月)
金融庁『資産所得倍増プランと資産形成支援に関する取組み』(2023年8月)
NRI『『資産運用立国実現プラン』は岸田政権が残した成果:金融所得課税強化は慎重な議論を』(2024年9月)
日本経済新聞『中国・スニーカー投資過熱 若者、不労所得に関心強く』(2019年10月)
日本経済新聞『FIREは可能か 投資で生計、急落時やインフレに注意』(2023年9月)
日本経済新聞『FIREを成功に導く大事なスキル それは節約』(2021年8月)
日本経済新聞『FIREの第一歩 月1万円でも多く稼ぐ覚悟』(2021年8月)
この記事を書いた人
松本 淳和 ライター
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。