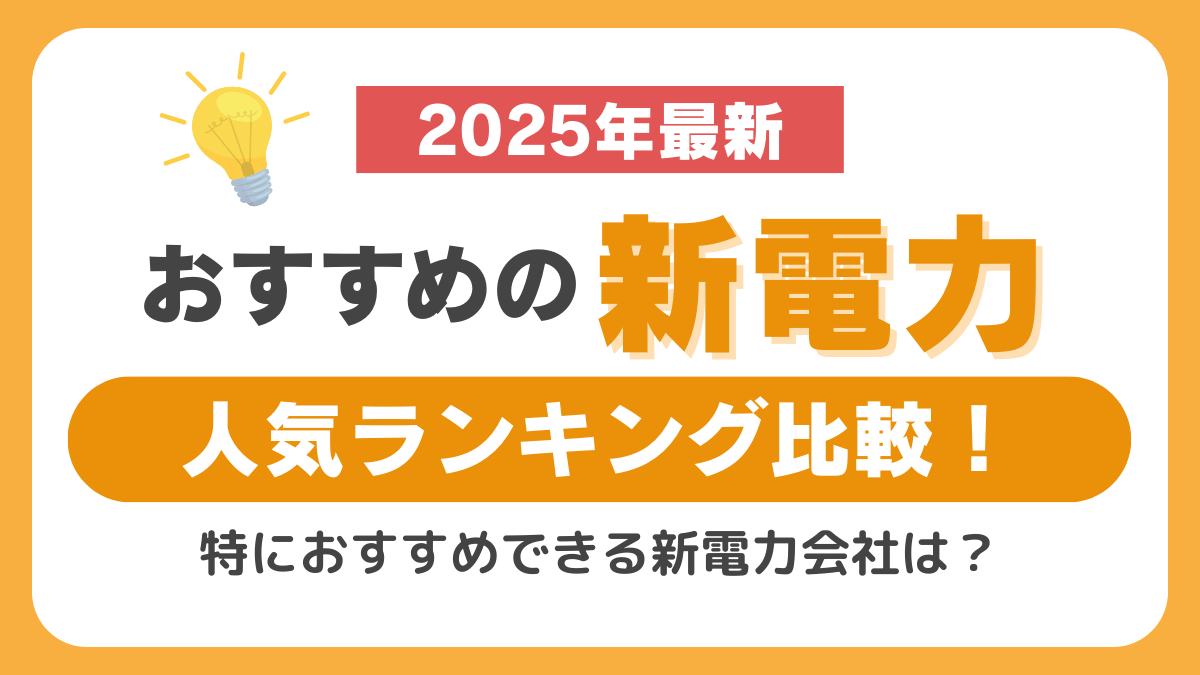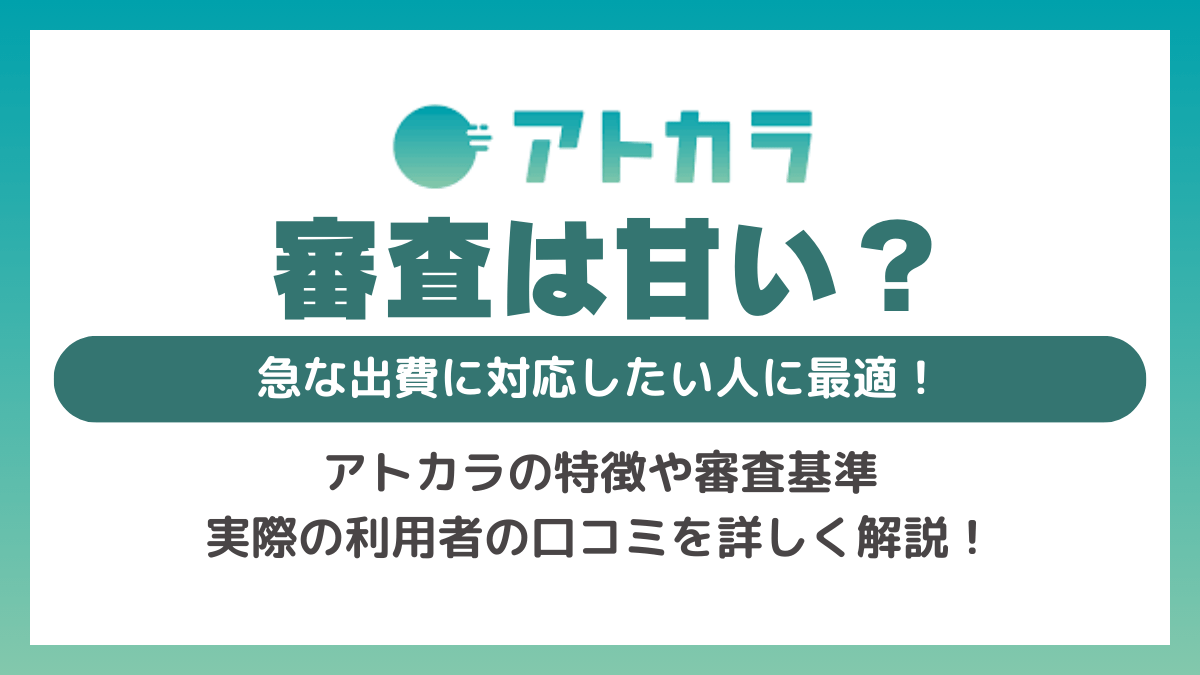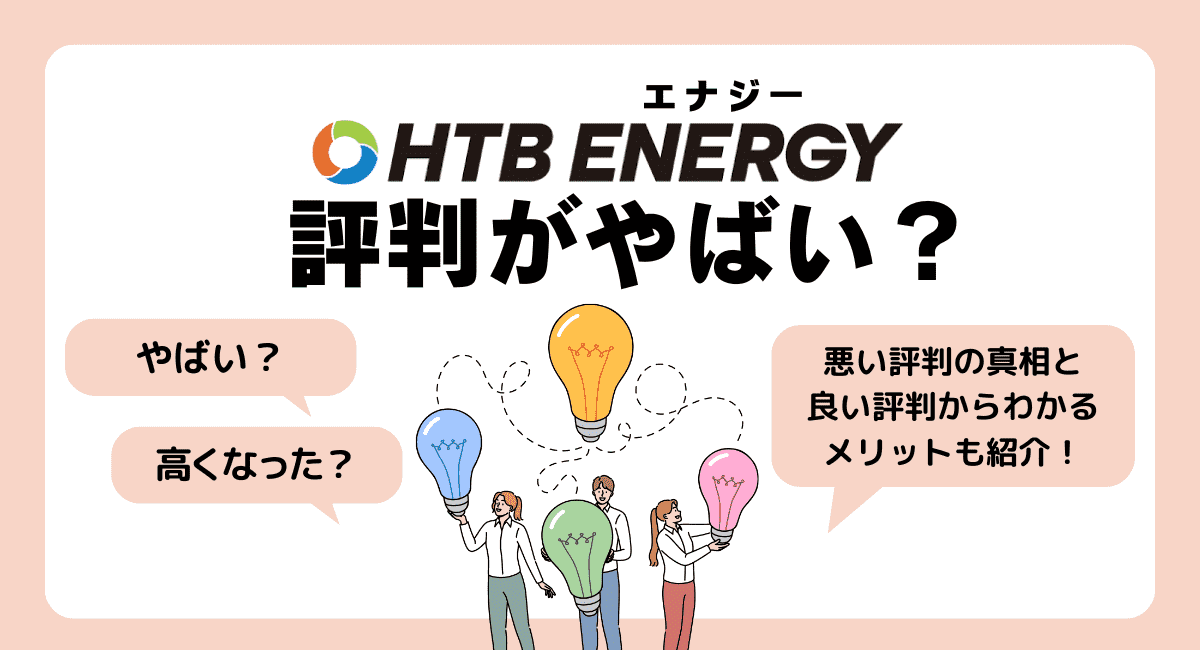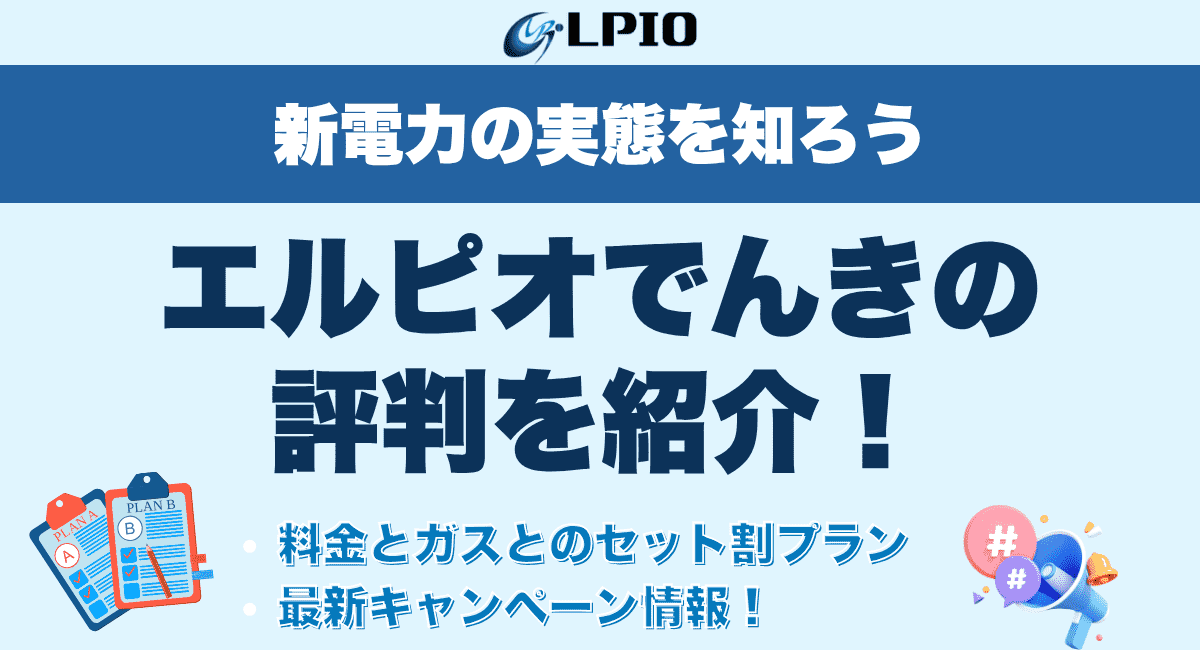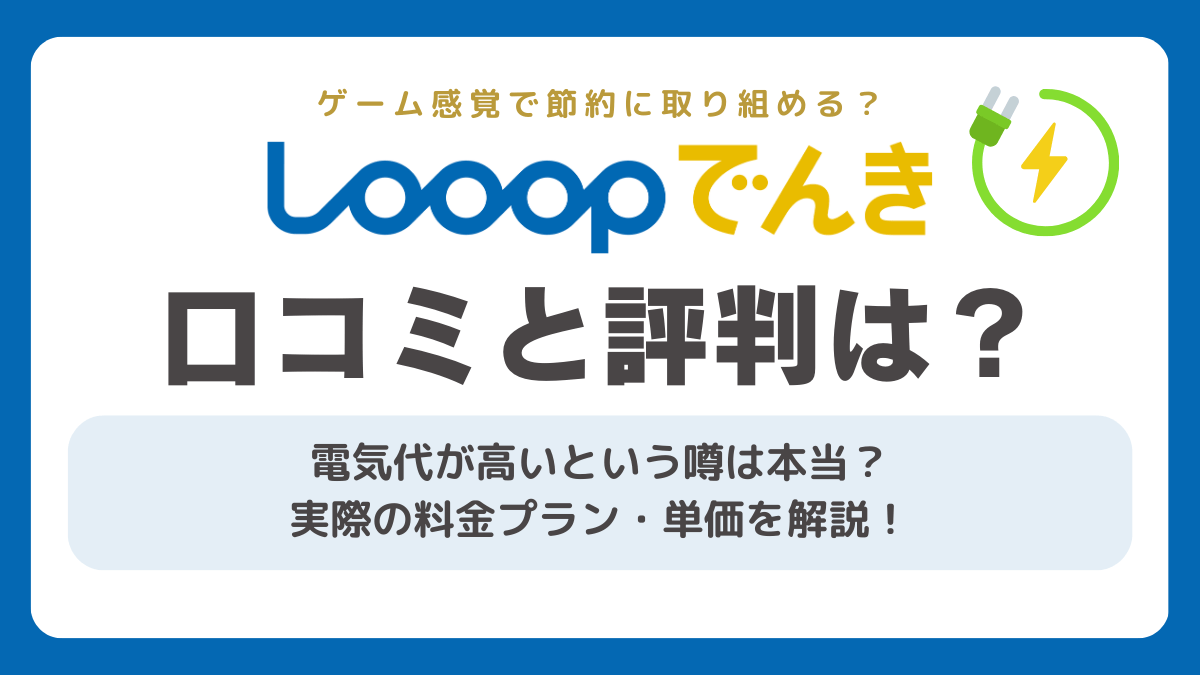テレプレゼンスとは、遠隔地にいながら同じ空間に存在するかのような臨場感を提供する革新的技術です。コロナ禍以降、リモートワーク普及により急速に注目が集まっています。
導入により出張費の大幅削減などのメリットがある一方、高額なコストなどのデメリットも存在します。具体事例を通じて企業導入のポイントやSDGs目標達成への貢献を解説し、テレプレゼンス技術の選択と活用方法をわかりやすく紹介します。
目次
テレプレゼンスとは

テレプレゼンスという言葉は、「Tele(遠隔)」と「Presence(存在)」を組み合わせた造語で、遠隔地にいながら、その場に「存在している」と感じられる臨場感を提供する技術です。従来のビデオ会議と比べ、より高品質な映像や音声、等身大の表示などによって、実際に会っているかのようなリアルな体験を可能にします。
まずはテレプレゼンスの基礎から確認していきましょう。
テレプレゼンスの特徴と技術的仕組み
テレプレゼンスの最大の特徴は、「物理的な距離を感じさせない臨場感」です。具体的には、
- 高精細な映像技術
フルHD(1920×1080)や4K(3840×2160)といった現代の高解像度基準による映像によって、相手の表情や仕草が鮮明にわかります。 - 立体音響技術
音の方向や距離感を再現し、より自然な聴覚体験を提供します。 - 等身大表示や空間再現
大画面ディスプレイや3D映像、360度カメラを活用し、まるで目の前に相手がいるかのような空間を再現します。 - ロボット技術
ディスプレイが頭部分についており、使用者はモバイル機器、タブレット、ポータブルコンピュータなどを使用して高品質なビデオ会議を行いながら、相手側にいるロボットを遠隔でコントロールできます。 - 触覚フィードバック(ハプティクス)
ハプティクスは、利用者に力、振動、動きなどを与えることで皮膚感覚フィードバックを得るテクノロジーで、触覚技術(haptic technology)とも呼ばれます。
など、複数の先端技術を組み合わせることで、従来の「画面越しの会話」では得られなかった没入感やリアルな存在感が生まれます。さらに、一部のシステムでは触覚を再現する技術(ハプティクス技術)を用いて、遠隔地の物体に触れた感覚を伝えることも可能になりつつあります。
テレプレゼンスとビデオ会議の違い
テレプレゼンスは、従来のビデオ会議システムと比較して、具体的に何が異なるのでしょうか。この違いを理解することで、テレプレゼンスの価値がより明確になります。
臨場感と没入感
最も大きな違いは、臨場感と没入感にあります。ビデオ会議は「画面越しの会話」にとどまりますが、テレプレゼンスは等身大表示や空間音響により、同じ空間にいるかのような感覚を重視します。
対話の自然さにおいても、テレプレゼンスでは対面に近い形で自然な会話が可能で、ビデオ会議でよくある話すタイミングが被る問題も軽減されます。
テレプレゼンスロボットの登場
また、空間的自由度の面では、テレプレゼンスロボットを利用して、遠隔地の空間を自走し、操作者が自由に視点を変えたり、現地の状況を観察することができます。これにより、現場にいるのと近い体験が得られ、従来のビデオ会議の受動的なコミュニケーションよりも能動的な交流が可能になります。
テレプレゼンスは、単なる「遠隔会議」ではなく、物理的な距離を超えて人と人がつながる新しい体験を提供する技術です。今後はメタバースやデジタルツインなどの概念と結びつくことで、さらに豊かな遠隔体験が実現できるでしょう。*1)
テレプレゼンスの具体事例
【カメラ、マイク、スピーカーを搭載した「ミーティングオウル」】
テレプレゼンス技術は、その用途や設置環境に応じて多様なスタイルで展開されています。会議室の壁面を占める大型システムから、オフィス内を自由に移動するロボット、そして未来的なホログラム技術まで、それぞれが異なる特徴と価値を提供しています。
代表的なテレプレゼンスのスタイルと、その分野をリードする製品について見ていきましょう。
会議室型テレプレゼンスシステム
会議室型テレプレゼンスは、専用の会議室に大型ディスプレイと高精細カメラ、立体音響システムを組み合わせたもので、参加者が同じ空間にいるかのような臨場感を提供します。このスタイルは企業の重要な意思決定会議や国際会議での利用が中心となっています。
【代表的な製品】
- MUSVIの「窓」
「窓」は決められた時間に自動で起動し、自動で終了するため電源操作が不要で、いつもつながっているからこそ何気ない会話が始まります。また、作業に集中したい時はカーテン機能でつながり度合いを調整でき、Web会議のように言葉がぶつかって会話を遮ってしまうこともありません。 - ロジクール「Rally Barシリーズ」
中規模〜大規模会議室向けのプレミア一体型ビデオバーで、卓越した光学性能とオーディオを備えたオールインワンのビデオ会議システムです。RightSenseテクノロジーによる自動カメラ制御「RightSight」、映像の光と色を最適化する「RightLight」、音声品質を向上させる「RightSound」などの技術により、ユーザーは操作や設定を意識せずに会議に集中できます。
【ロジクールRally Bar】
これらのシステムの特徴は、専用の会議室環境を構築することで、移動コストを削減しながら高品質なコミュニケーションを実現できることです。
テレプレゼンスロボット
テレプレゼンスロボットは、遠隔地からロボットを操作して現地を自由に移動しながらコミュニケーションを行うスタイルです。教育、医療、在宅勤務など幅広い分野で活用が進んでいます。
【代表的な製品】
- iPresenceの「temi」
AI搭載の「temi」は、2019年11月に日本で販売開始され、個人・法人の両方に展開されました。temiは距離測位センサーによる室内の俯瞰マップ作成機能や、目の前の人を自動で追いかける追従モードを備えています。 - アスラテック株式会社の「テレプレゼンス for Pepper」
AndroidスマートフォンとGoogle Cardboard対応ビューアを利用して遠隔操作を実現。操作者の音声をPepperで再生したり、Pepperのカメラ映像を操作端末で確認しながら自然な動きでコミュニケーションを行うことができます。介護施設や空港案内など幅広い分野での実証実験が行われています。
【テレプレゼンス for Pepper】
ホログラム・3Dディスプレイ型
最新のテレプレゼンス技術として、ホログラムや3Dディスプレイを活用したシステムが注目されています。立体映像で相手を再現し、従来のディスプレイでは体験できないリアルな存在感を提供します。
- ソニー:「3次元高画質化と低遅延伝送技術」
裸眼で実在感のある立体映像を視聴できる「空間再現ディスプレイ」を製品化しています。この技術は「Eye-sensing Light Field Display」方式を採用し、視線認識技術により左右の目に最適な立体映像を届けることが可能です。STEF 2022では、55インチ縦型の8K解像度プロトタイプを用いて、遠隔地にいるアイドルとの「握手会」を体験できるデモが実施されました。 - Microsoft社の「holoportation」
「HoloLens」を活用したこの技術では、人体の3Dモデルをリアルタイムで作成し、3D映像伝送技術と組み合わせることで、遠隔地の人物があたかも同じ部屋にいるかのような対話を実現しています。
【ソニーの3次元高画質化と低遅延伝送技術】
テレプレゼンス技術は、会議室型、ロボット型、ホログラム型という3つの主要なスタイルでそれぞれ異なる価値を提供しています。会議室型は企業の重要会議に、ロボット型は柔軟な移動とコミュニケーションに、ホログラム型は次世代の没入体験に特化しており、用途に応じた選択が可能です。*2)
テレプレゼンスが注目されている背景
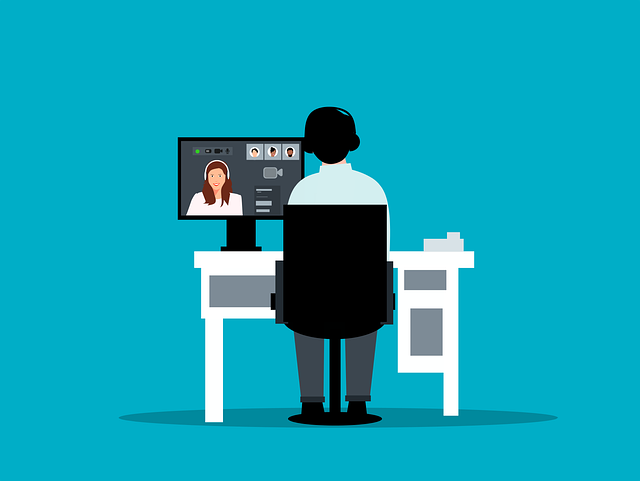
単なるビデオ会議を超え、「その場にいるかのような臨場感」を提供するテレプレゼンス技術は、社会構造の変化やテクノロジーの進化とともに、ビジネスや医療、教育など多様な分野で革新的なコミュニケーション手段として注目を集めています。この背景には、いくつかの重要な社会的・技術的要因が存在します。
コロナ禍による非接触コミュニケーションの需要拡大
2020年に始まった新型コロナウイルスの世界的流行は、人々のコミュニケーション方法を根本から変えました。感染防止対策として対面での接触を避ける必要性が高まり、テレプレゼンス技術への需要が急増しました。
特に医療分野では、医師が感染リスクを最小限に抑えながら患者を診察できるよう、テレプレゼンスロボットの活用が進みました。パンデミック期間中には医師による診断だけでなく、家族との面会にも活用されました。
また、水族館や美術館などの文化施設でも、テレプレゼンスロボットを通じた遠隔見学ツアーが登場するなど、新たな活用方法が広がっています。
働き方改革とリモートワークの普及
テレワークの急速な普及に伴い、「コミュニケーションの希薄化」が、多くの企業が直面する問題となっています。テレプレゼンスは、この課題に対する解決策として注目されています。
東京都文京区では、テレプレゼンスロボットを活用した「働き方DX推進」の実証実験が行われ、自宅にいながら職場にいるような臨場感をもたらす取り組みが進められました。また、「分身出勤ソリューション」と呼ばれる新しい働き方も登場し、在宅勤務者がオフィスに置かれたテレプレゼンスロボットを操作して、オフィス内を移動しながらコミュニケーションを取る方法が実践されています。
グローバル化と国際ビジネスの拡大
企業活動のグローバル化に伴い、国境を越えたコミュニケーションの重要性が高まっています。テレプレゼンスは、物理的な距離を超えて効果的なコミュニケーションを実現する手段として、国際ビジネスの現場で重要な役割を果たしています。
特に、海外出張にかかる時間やコストの削減効果は大きく、テレプレゼンスを活用することで移動費と宿泊費を最大100%節約できるとされています。また、グローバル企業では、テレプレゼンスによる迅速な意思決定が生産性を大きく向上させるという報告もあります。
米国と英国を中心に、テレプレゼンス会議室の数は急速に増加しており、多くの国の政府機関でもテレプレゼンス製品の採用が進んでいます。
少子高齢化と労働力不足への対応
日本全国で深刻化する人口減少と少子高齢化は、特に地方において顕著な社会問題となっています。沖縄県でも2015年頃から生産年齢人口の減少が始まり、労働力不足による生産性低下やサービス品質の低下が懸念されています。
テレプレゼンスロボットは、労働力不足の解消だけでなく、生産性向上にも貢献する技術として期待されています。また、高齢者人口の増加に伴い、遠隔地からの継続的な監視や相談のためのテレプレゼンス需要も高まっています。
さらに、未来を担う人材不足が招く成長の鈍化のリスクに対して、テレプレゼンス技術を活用した知識や技術の共有が重要な解決策となる可能性があります。
これらの背景が複合的に作用し、テレプレゼンスは単なる代替手段ではなく、現代社会におけるコミュニケーションインフラの一つとして、その価値を大きく高めているのです。*3)
テレプレゼンスのメリット

テレプレゼンス技術は、単なるビデオ会議を超えた価値を企業や組織にもたらします。その具体的なメリットを確認していきましょう。
コストと時間の大幅削減
テレプレゼンスの導入により、出張費や移動時間を劇的に削減できます。同時に、交通費や宿泊費だけでなく、移動に費やされていた時間の節約にもつながります。
【具体例】
- 海外出張や遠隔地への移動が不要になり、意思決定者の時間を有効活用
- 必要なときにすぐミーティングを設定できるため、距離を超えたコミュニケーションが活性化
リアルな臨場感による高品質コミュニケーション
テレプレゼンスの最大の特徴は、等身大サイズでの投影や高品質な音声により、まるで同じ空間にいるかのような臨場感を実現することです。
【具体例】
- 表情やボディランゲージなどの音声以外のコミュニケーションが活性化
- 自然な会話リズムで、オーバーなリアクションや話すスピードを調整する必要がない
意思決定の迅速化と生産性向上
離れた場所にいても即時の対話が可能になることで、業務スピードが向上します。グローバル企業では、テレプレゼンスによる迅速な意思決定が生産性を大きく向上させるという報告もあります。
【具体例】
- 早朝から米国、午後はインド、必要に応じて南米からも専門家を呼び寄せるなど、時差を超えた連携が可能
- 常時接続により、遠隔にいる相手の存在感が高まり、コミュニケーションのタイミングを見計らいやすくなる
- 雑談や簡単な質疑応答など、ささいなコミュニケーションの量が増加
新しい働き方の実現と人材活用の拡大
「分身出勤ソリューション」と呼ばれる新しい働き方では、在宅勤務者がオフィスに置かれたテレプレゼンスロボットを操作して、オフィス内を移動しながらコミュニケーションを取ることができます。
【具体例】
- 海外在住者や遠隔地の人材とのフレキシブルなコラボレーションが実現
- 様々な理由でオフィス出勤が難しい人材の継続雇用が可能に
- 管理職が在宅勤務中でもメンバーと気軽に相談でき、職場状況をリアルタイムに把握
テレプレゼンスは、単なるコスト削減だけでなく、コミュニケーションの質向上、意思決定の迅速化、そして新しい働き方の実現まで、多角的な価値を提供する革新的技術です。*4)
テレプレゼンスのデメリット・課題

テレプレゼンス技術は多くのメリットをもたらす一方で、導入や運用において様々な課題も存在します。これらの課題を理解することで、より効果的な活用が可能になるでしょう。
高額な導入・運用コスト
テレプレゼンスシステムの導入には、専用機器の購入や通信環境の整備など、相当の初期投資が必要です。特に高品質な映像・音声を実現するための設備は高額になりがちです。
【具体例】
- 専用の会議室型システムでは、高精細カメラやマイク・スピーカーアレイなどの設備費用が発生
- 継続的な保守・メンテナンス費用や通信費用も無視できない経済的負担となる
- 小規模企業や予算の限られた組織では導入のハードルが高い
技術的制約と通信環境への依存
テレプレゼンスの品質は、通信環境に大きく左右されます。不安定な通信環境では、せっかくの高品質な体験が台無しになってしまいます。
【具体例】
- 安定した高速回線(最低3Mbps以上のアップロード・ダウンロード速度)が必要不可欠
- 通信の遅延が操作性や会話のリズムに影響し、ストレスの原因となる
- 地域によるネットワークインフラの格差がデジタルデバイド(情報格差)を生み出す
身体性とコミットメントの欠如
テレプレゼンスでは、物理的な存在感や身体的接触が失われることで、コミュニケーションの質が変化する場合があります。
【具体例】
- 非言語的情報(視線、表情、身振り、息遣いなど)の一部が失われる
- 無意識的な身ぶりや微妙な表情変化が伝わりにくい
- 共感的コミットメントの表明が難しい場面では、対面に比べて不適切と感じられることがある
セキュリティとプライバシーのリスク
遠隔通信を介したコミュニケーションには、情報漏洩やプライバシー侵害のリスクが伴います。
【具体例】
- 通信の傍受や不正アクセスによる機密情報の漏洩リスク
- デフォルト設定のままでの使用によるセキュリティホール※の発生
- プライバシー保護のための適切な運用ルールの整備が必要
操作スキルと心理的障壁
テレプレゼンス技術を効果的に活用するには、一定の操作スキルと慣れが必要です。また、新しい技術への抵抗感が利用を妨げることもあります。
【具体例】
- 専用機器やアバター操作に習熟するための学習コストが発生
- 高齢者や技術に不慣れな人々にとっての心理的障壁
- 対面とは異なる緊張感や不安感が生じる場合がある
テレプレゼンスは革新的な技術ですが、これらの課題を認識し、適切な対策を講じることで、より効果的な活用が可能になります。*5)
企業がテレプレゼンスを導入する際のポイント
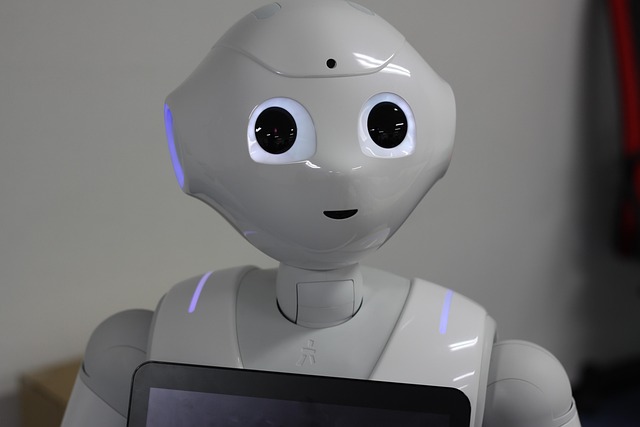
テレプレゼンス技術の導入は、単なる機器の購入ではなく、企業のコミュニケーション文化を変革する戦略的な取り組みです。高額な投資になりがちなテレプレゼンスシステムを最大限に活用し、失敗を避けるためには、計画段階から運用に至るまで、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
明確な目的と課題の特定
テレプレゼンス導入の第一歩は、自社が解決したい具体的な課題と達成したい目標を明確にすることです。漠然と「コミュニケーションを改善したい」という理由だけでは、適切なシステム選定ができません。
文京区役所での実証実験では、「管理職が在宅勤務中にメンバーと気軽に相談できず、職場の状況をタイムリーに把握しづらい」という具体的な課題に対応するため、テレプレゼンスロボットを導入しました。このように、
- 遠隔地のチーム間のコラボレーション強化
- 出張コストの削減
- 専門家の知識共有
など、具体的な目標を設定することで、導入後の効果測定も容易になります。
ニーズに合ったスタイルの選定
テレプレゼンスには
- 会議室型
- ロボット型
- ホログラム型
など様々なスタイルがあり、それぞれに特徴があります。自社のニーズに最適なタイプを選ぶことが重要です。
例えば、複数拠点間での定例会議が主な用途であれば会議室型が、現場の状況確認や偶発的なコミュニケーションが目的であればロボット型が適しています。選定の際は、利用頻度や参加人数、使用環境、移動の必要性などを考慮し、複数のタイプを試験的に導入して比較検討することも有効です。
通信環境とインフラの整備
テレプレゼンスの品質は通信環境に大きく左右されるため、事前の環境整備が必要です。特に高解像度映像の伝送には安定した高速回線が必要となります。
導入前に、現在の通信環境(帯域幅、安定性、遅延など)を評価し、必要に応じてネットワークのアップグレードを行いましょう。また、セキュリティ対策も重要で、通信の暗号化や適切なアクセス制御を確保する必要があります。さらに、停電や通信障害に備えたバックアッププランも検討しておくと安心です。
組織文化と利用者教育
テレプレゼンスの成功は、技術だけでなく組織文化や利用者の受け入れ態勢にも大きく依存します。新しい技術への抵抗感を軽減し、積極的な活用を促すための取り組みも重要です。
導入前に、利用者向けのトレーニングプログラムを用意し、操作方法だけでなく、効果的な活用シーンや成功事例も共有しましょう。また、経営層や部門長が率先して利用することで、組織全体への浸透を促進できます。
効果測定と継続的な改善
テレプレゼンスの導入効果を定期的に測定し、継続的な改善を図ることが長期的な成功につながります。ROI(投資対効果)を適切に評価することで、投資の正当性を示し、さらなる改善点を見出すことができます。
- 利用頻度
- 会議時間の短縮
- 出張費削減額
- 利用者満足度
などの指標を設定し、定期的に測定しましょう。また、利用者からのフィードバックを収集し、運用方法や設備の改善に活かすことも重要です。
テレプレゼンス導入の成功は、技術選定だけでなく、明確な目的設定、適切な環境整備、組織文化の醸成、そして継続的な効果測定と改善の積み重ねによってもたらされます。これらのポイントを押さえることで、単なる「高価な設備」ではなく、組織のコミュニケーションを変革する「戦略的ツール」としてテレプレゼンスを最大限に活用することができるでしょう。*6)
テレプレゼンスとSDGs
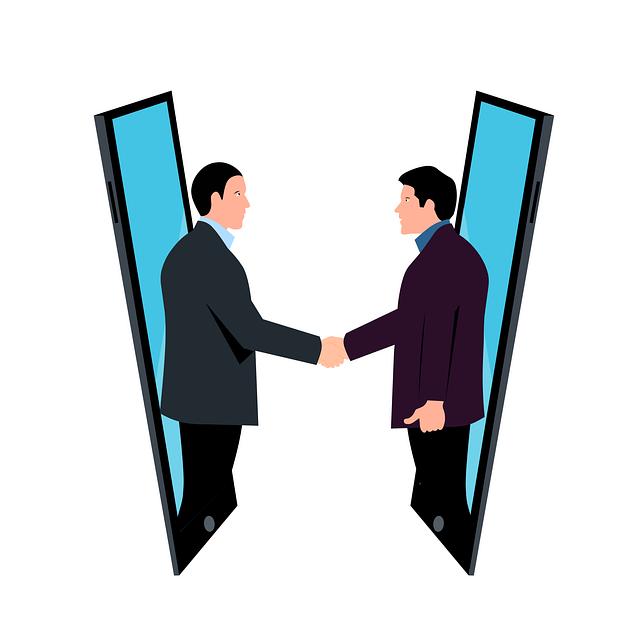
テレプレゼンス技術は、単にコミュニケーションを効率化するだけでなく、SDGsが目指す「誰一人取り残さない」社会の実現に大きく貢献します。この革新的な技術は、移動の削減による環境負荷低減、地域格差の是正、そして質の高い教育機会の提供を通じて、持続可能な社会の実現を後押しします。
SDGs目標3:すべての人に健康と福祉を
遠隔医療へのテレプレゼンスロボットや高精細ディスプレイシステムの導入により、地理的な制約や身体的な移動の困難さがある患者でも、専門医による診断や治療、カウンセリングを自宅や近隣の施設で受けられるようになります。例えば、過疎地の高齢者が専門病院まで移動する負担を軽減したり、感染症のリスクを低減しながら医療従事者と患者がコミュニケーションを取ったりすることが可能です。
これにより、医療格差の是正が進み、誰もが健康で文化的な生活を送るための基盤が強化されます。災害時における緊急医療支援や、医師不足に悩む地域への遠隔からのサポートも期待され、多くの人々の健康と福祉の向上に直結します。
SDGs目標4:質の高い教育をみんなに
テレプレゼンスロボットや等身大ディスプレイシステムを活用することで、遠隔地の学生がまるで教室にいるかのように授業に参加したり、世界中の優れた教師や専門家から直接指導を受けたりすることが可能になります。例えば、地方の学校の生徒が、都市部の有名大学の講義をリアルタイムで受講したり、海外の語学教師と直接対話しながら学ぶ機会を得たりすることが挙げられます。
教育機関が提供できる学習体験の幅が広がり、都市と地方、先進国と開発途上国といった地域間の教育格差の是正に貢献します。また、病気や身体的な理由で学校に通えない子どもたちも、自宅から教育に参加できるようになり、学びの機会が保障されることにも繋がります。
SDGs目標8:働きがいも経済成長も
リモートワークやハイブリッドワークを高品質なコミュニケーションで支援することにより、企業は従業員が場所にとらわれずに働ける環境を提供できるようになります。育児や介護と仕事の両立がしやすくなり、多様な人材が企業で活躍できる機会が増えます。
また、物理的な移動時間の削減は、従業員の生産性を向上させ、企業活動全体の効率化に繋がります。出張費の削減は企業の経済的負担を軽減し、その分を研究開発や人材育成など、より戦略的な投資に回すことが可能になります。これは、企業の持続的な成長を促し、より多くの働きがいのある雇用創出にも貢献すると考えられます。
SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を
会議や商談、研修のために物理的に移動する回数を減らすことで、航空機や自動車の利用を抑制できます。燃料消費が減少し、二酸化炭素(CO2)をはじめとする温室効果ガスの排出量を削減することが可能です。
特に、国際会議や頻繁な国内外への出張が多い企業にとっては、テレプレゼンスの活用が企業のカーボンフットプリント(炭素排出量)を大幅に削減する有効な手段となります。これは、地球温暖化対策への具体的な行動として、企業の社会的責任(CSR)を果たす上でも重要な役割を担います。
このように、テレプレゼンスは、経済活動の効率化と環境保護を両立させる、持続可能なビジネスモデルへの移行を促進する重要な技術と言えるでしょう。*7)
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
テレプレゼンスは、遠隔地にいながら「その場に存在している」かのような臨場感を提供する革新的なコミュニケーション技術として、ビジネスや医療、教育など多様な分野で活用が広がっています。高品質な映像・音声技術や等身大表示、ロボット技術などを組み合わせることで、従来のビデオ会議では得られなかった没入感と自然なコミュニケーションを実現する点が最大の特徴です。
最新の市場動向では、3Dテレプレゼンス市場が急成長すると予測されています。また、企業向けテレプレゼンスロボット市場では、ハイブリッドワークモデルの標準化に伴い、シームレスなモビリティとHDビデオ会議機能を備えたソリューションへの投資が拡大しています。
テレプレゼンス技術は単なる便利なツールではなく、人と人とのつながりを深め、地球環境への負荷を減らす手段です。あなた自身の日常で、
- どのようなコミュニケーションが対面でなければならないのか
- テレプレゼンスで代替したほうが効率的なものはなにか何か
などを考えてみませんか?
また、テレプレゼンスを通じて、これまで交流のなかった異文化や異分野の人々とつながることで、どのような新しい価値が生まれる可能性がある一方、私たち一人ひとりがサイバーセキュリティへの意識を高め、ネットワーク上での防御力を身につける必要があります。
距離という物理的な壁を超え、人々がより自由につながり合える世界の実現に向けて、テレプレゼンス技術はさらに進化していくでしょう。*8)
<参考・引用文献>
*1)テレプレゼンスとは
MUSVI『世界中の壁を「窓」に変える』
iPresence『テレプレゼンスアバターロボットとは?取扱い製品と事例をご紹介』
iPresence『”つながる” は進化し”そこにいる” へ』
NTT 研究開発『イマーシブテレプレゼンス技術「Kirari!」を活用したサービス』
Wikipedia『テレプレゼンス』
Wikipedia『テレプレゼンスロボット』
Wikipedia『ハプティクス』
KYOCERA『「触る」感覚を実現するハプティクス(Haptics)とは 触覚をフィードバックする最新技術』
ORIX Rentec『遠隔でのコミュニケーションをスムーズにする「テレプレゼンスロボット」とは』(2023年11月)
田中 由浩『触覚フィードバックによる感覚運動支援』(2023年8月)
NIKKEI COMPASS『テレプレゼンスロボット』
*2)テレプレゼンスの具体事例
SOURCENEXT『Meeting OWL 表情がわかる、一体感のある会議を実現』
Asratec『テレプレゼンス for Pepper』
SONY『遠隔空間を目の前にリアルに再現する3次元高画質化と低遅延伝送技術』(2022年)
MUSVI『どこにいても、いい気がする「窓」は、距離を超えた”会う”を実現します』
MUSVI『こんな場所で「窓」が使われています』
Logicool『Rally Bar Mini 小~中会議室向け一体型ビデオバー』
Cisco Systems『イマーシブ テレプレゼンス』日経XTECH『分身ロボ「temi」が11月発売、導入パートナーに大塚商会やパルコなど9社』(2019年10月)
UNIPOS『Ohmni Telepresence Robot | テレプレゼンスロボット』
OhmniLabs『Telepresence Robot Reimagined: Enhanced Remote Communication with Ohmni』
OhmniLabs『A New Standard in Virtual Care: OhmniCare』
OhmniLabs『Human-Centered Robotics for Healthcare』
Symbotic『Symbotic is the Backbone of Commerce』
iPresence『temi AI搭載のテレプレゼンスアバターロボット「そこにいる」を提供します。』
iPresence『temiの操作方法と操作画面を解説!使い慣れると快適!』(2022年8月)
iPresence『temiの仕組みをひも解く|ロボットの構造とユーザー体験の設計とは』(2025年6月)
SONY『3次元高画質化と低遅延伝送技術』(2023年9月)
SONY『ソニー独自の3DCG生成技術』
日経XTECH『重機の遠隔操作で「裸眼3Dディスプレーがほぼ必須に」、ソニー高橋氏が予測』(2023年8月)
NTT『NTT技術ジャーナル』(2025年1月)
Microsoft『Holoportation™What is Holoportation™?』
Microsoft『Holoportation™ Our earlier work』
Microsoft『3D Telemedicine』
*3)テレプレゼンスが注目されている背景
MUSVI『革新を続ける土木業界。伝統と新しい働き方を結ぶ「窓」の可能性とは』(2024年7月)
MUSVI『テレプレゼンスシステム「窓」が2024年度グッドデザイン賞受賞』(2024年10月)
NTT『ポリコム 映像コミュニケーション ソリューション 総合カタログ』
iPresence『文京区役所で取り組む「働き方DX推進」――実証実験が社会的インパクト×海外展開の足がかりに!iPresenceがキングサーモンプロジェクトで得た成果』(2025年3月
iPresence『分身出勤ソリューションとは?従業員満足度・生産性を向上させるハイクラスなテレワーク!』(2023年3月)
iPresence『テレプレゼンスロボットが変える“会う”の常識』(2024年12月)
東京都政策企画局『都と協働プロジェクト実施スタートアップ採択』(2025年1月)
日経XTECH『第47回 テレプレゼンス(前編)遠隔地の相手と“対面”で会議 導入前の確認と効果検証が必須』(2007年12月)
日経XTECH『あたかも同じ会議室にいるように,テレプレゼンスに進化するテレビ会議システム』(2007年5月)
厚生労働省『「情報通信機器を用いた診療に関するルール整備に向けた研究」研究報告』
*4)テレプレゼンスのメリット
MUSVI『立命館大、テレプレゼンスシステム「窓」で多様な地域との高大連携を加速(ZDNET Japan 2024/3/25 )』(2024年4月)
KADOKAWA ASCII『【38本目】1時間4.5万円で、あのテレプレゼンスが使える!』(2010年6月)
KADOKAWA ASCII『1時間5万2000円で世界の相手とフェイスツーフェイス 気品高きウェスティンホテルで高品質テレプレゼンスを』(2011年1月)
日経XTECH『変化にスピーディに対応できるボーダレスなテレプレゼンス環境』(2009年10月)
日経XTECH『テレプレゼンス,17年後の勝負』(2008年11月)
iPresence『テレプレゼンスアバターロボットとテレビ電話の違い』(2025年1月)
日本総研『テレプレゼンスシステム「窓」による遠隔「ご縁つなぎ」サービス 2020年度 利用状況・顧客反応報告』
労働政策研究・研修機構『近未来のワークプレイスを創り出す ソーシャルテレプレゼンス技術』(2019年8月)
教育システム情報学会『テレプレゼンスを導入したハイブリッド型学生実験手法の開発』(2020年8月)
*5)テレプレゼンスのデメリット・課題
総務省『通信自由化以降の通信政策の評価とICT社会の未来像等に関する調査研究』(2015年3月)
呉羽 真『テレプレゼンス技術は人間関係を貧困にするか?――コミュニケーションメディアの技術哲学*』(2020年3月)
呉羽 真『オンラインの身体性』(2022年)
中西 英之『近未来のワークプレイスを創り出すソーシャルテレプレゼンス技術』(2019年8月)
iPresence『指定のネットワーク環境を教えてください。』
情報処理推進機構『テレプレゼンス技術のための低遅延 IP 映像伝送システムの開発―低遅延な映像で、快適な遠隔操縦を可能にする「瞬景」―』(2023年)
情報処理推進機構『脆弱性対応におけるリスク評価手法のまとめ』(2024年8月)
ITmedia『Ciscoの「テレプレゼンス」に脆弱性、デフォルトパスワードでアクセスされる恐れ』(2013年8月)
山口大学『オンライン PCAGIP の実践と検討』(2023年1月)
Global Information『アジア太平洋地域の3Dテレプレゼンス:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2025年~2030年)』(2025年1月)
KDDI『セキュリティホール』
情報処理学会『分身ロボット「OriHime」を用いた外出困難者の遠隔接客に関する実証実験』(2024年4月)
*6)企業がテレプレゼンスを導入する際のポイント
日経XTECH『第47回 テレプレゼンス(前編)』(2007年12月)
日経XTECH『第48回 テレプレゼンス(後編)』(2007年12月)
日経XTECH『[小型テレプレゼンス]ロボットを操作しテレワーク、五感対応も現実に』(2014年10月)
iPresence『案内ロボットの選び方|導入メリット・デメリット、価格、おすすめ機種を徹底比較』(2025年6月)
NEC『ROIとは?意味や計算式、ROASとの違いや改善方法を解説』(2022年12月)
労働政策研究・研修機構『近未来のワークプレイスを創り出す ソーシャルテレプレゼンス技術』(2019年8月)
robotstart『スマホを装着する卵型テレプレゼンスロボット「動く電話テレピー」見回しながら会話もできる』(2020年11月)
robotstart『市役所案内を遠隔操作のアバターロボットで 分散アンテナとローカル5Gで実現した未来の市役所とは』(2025年5月)
SONY『あたかもそこにいるかのような”つながり”を届けたい 「NUROオンラインセッション」で子どもの体験格差の解消へ』(2022年3月)
*7)テレプレゼンスとSDGs
Spaceship Earth『デジタルデバイド(情報格差)とは?原因と問題点や解決策・高齢者支援として個人や企業が行う取り組み例を紹介』(2025年6月)
Spaceship Earth『カーボンフットプリントとは?算定方法や課題、企業の取組事例も』(2025年6月)
経済産業省『サプライチェーン全体でのカーボンニュートラルに向けたカーボンフットプリントを巡る動向』(2023年9月)
iPresence『テレロボ temi 病院事例| (財)第二川崎幸クリニック| 外来 / 案内業務におけるロボットの活用共同研究を開始 – 医療現場の人手不足解消を目指して』(2023年10月)
iPresence『大分県立情報科学高校 出張講義|先端技術への探求心を刺激するためには?』
iPresence『分身出勤ソリューションとは?従業員満足度・生産性を向上させるハイクラスなテレワーク!』(2023年3月)
MUSVI『「窓」を活用した遠隔オンライン診療の実証実験について』(2023年10月)
MUSVI『立命館大、テレプレゼンスシステム「窓」で多様な地域との高大連携を加速(ZDNET Japan 2024/3/25 )』(2024年4月)
科学技術振興機構『★DASAが危険な環境での活動を可能にする「テレイグジスタンス」(Telexistence)技術の公募を開始』(2020年9月)
敦賀市立看護大学『講演会「患者さんを笑顔にする テレロボット医療現場DX」』
パナソニック教育財団『テレプレゼンスロボットの活用による児童の思考力・表現力の育成』(2023年)
九州大学『遠隔教育におけるテレプレゼンスツールの比較実験: 英語授業でのテレプレゼンスロボット使用検証』(2018年3月)
NTT『テレプレゼンスロボットを活用したデータセンタ運用保守』
東京都立大学『動作コミュニケーションを 取り入れたテレプレゼンスシステム』(2023年12月)
*8)まとめ
Global Information『3Dテレプレゼンスの世界市場』(2025年6月)
Global Information『3Dテレプレゼンス:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2025年~2030年)』(2025年1月)
iPresence『”つながる” は進化し”そこにいる” へ』
NTT西日本『「All-Photonics Connect powered by IOWN」× 「tonari」シームレスな遠隔コミュニケーションの実現に向けた取り組みを開始!~リモートにおける表情や雰囲気の共有、遅延やゆらぎの改善に取り組む~』(2024年12月)
日本経済新聞『MUSVI・ソニーグループなど、テレプレゼンスシステム「窓」を活用した空間接続ソリューション事業を開始』(2022年9月)
docomo『3D アバターとなって仮想ミーティングルームへ参加!遠隔会議システム「XR テレプレゼンスミーティング」の実証実験を開始』(2021年1月)
情報通信研究機構『サイバネティック・アバターが切り開く未来の社会』(2021年)
この記事を書いた人
松本 淳和 ライター
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。