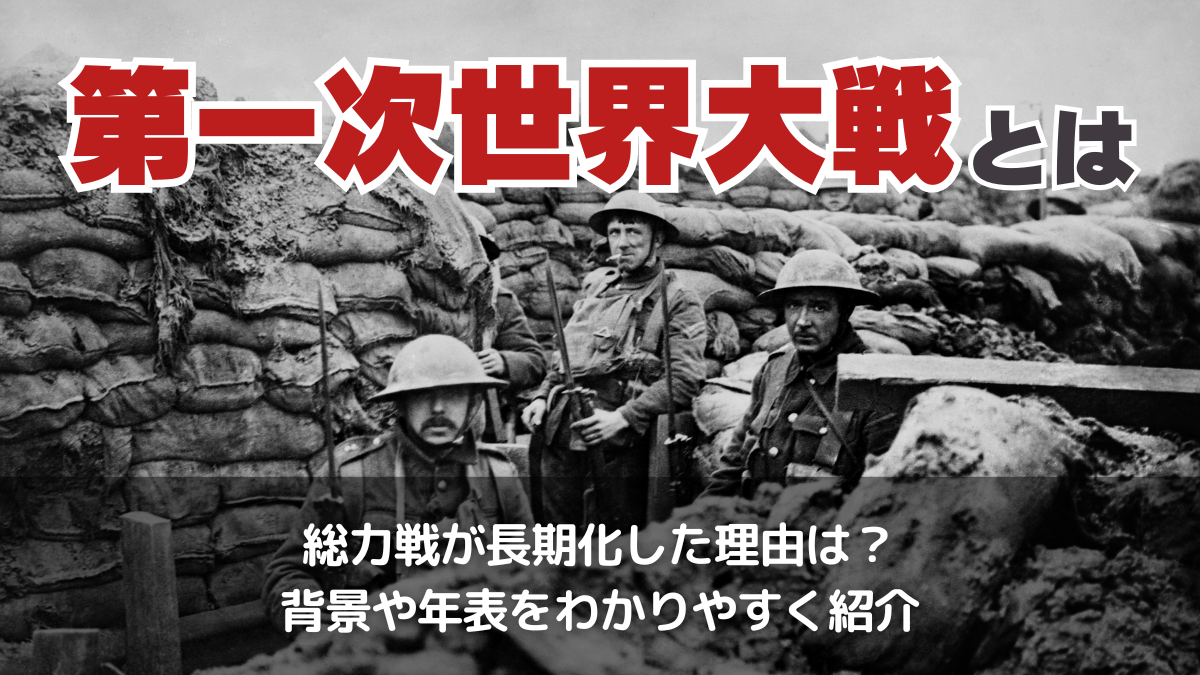
「戦争はクリスマスまでには終わる!」
当時、各国の指導者を含めて多くの人々は、戦争が長期化するとは思っていませんでした。しかし、戦争はクリスマスどころか4年半にわたって継続する長期戦となります。
短期間で終わるはずと皆が思い込んだ戦争は、なぜ4年半も続いたのでしょうか。その理由は、各国が国の持っている力の全てを戦争に注ぎ込む総力戦で戦争に挑んだからでした。それにより、新兵器が次々と投入され、これまでの戦争とは比較にならない死者を出す長期戦となったのです。
今回は、第一次世界大戦の特徴や流れ、戦争中の日本の動向、戦後の世界と日本の動向について解説します。また、総力戦とSDGsについても考えます。
目次
第一次世界大戦(WW1)とは?きっかけとどこ対どこで戦ったのかわかりやすく解説
第一次世界大戦とは、1914年から1918年にかけて、ヨーロッパを中心に世界を巻き込んだ大きな戦争です。25ヶ国もの国々が参戦し、世界の主要国もほとんどが戦いに加わり、4年半という長い間、国力を尽くした激しい戦いが続けられました*1)。
第一次世界大戦(WW1)はどこ対どこで戦った?
第一次世界大戦が始まる前、ヨーロッパはまるで火薬庫のようでした。 イギリス、フランス、ロシアを中心とする「協商国」と、ドイツ、オーストリア、イタリアを中心とする「同盟国」という二つの大きなグループが、睨み合っていたからです。
ヨーロッパを主戦場とする戦いでしたが、世界の国々が両陣営に参加します。中東の大国であるオスマン帝国は同盟国に加わり、日本やアメリカは協商国に加わりました。こうして、戦いはヨーロッパだけでなく、世界各地に広がっていったため、第一次世界大戦と呼ばれます。
第一次世界大戦(WW1)のきっかけ
第一次世界大戦のきっかけは、1914年6月28日に起きたサラエボ事件です。オーストリア皇太子フランツ・フェルディナントが、セルビア系青年によって暗殺されたこの事件を受け、オーストリア=ハンガリー帝国がセルビアに宣戦布告。
これにより、同盟国(ドイツ・オーストリアなど)と協商国(イギリス・フランス・ロシアなど)が連鎖的に参戦し、「どこ対どこ」という形でヨーロッパ全体、そして世界を巻き込んだ戦争へと発展しました。複雑な同盟関係や民族主義、帝国主義の対立が背景にあり、偶発的な事件が大戦の導火線となったのです。
第一次世界大戦(WW1)で勝った国
第一次世界大戦では、協商国側が勝利しました。中心となったのはイギリス・フランス・ロシア(途中で離脱)・アメリカなどです。特に1917年にアメリカが協商国側として参戦し、人的・物的支援を行ったことで戦局は一気に有利になりました。
一方、同盟国側のドイツ、オーストリア=ハンガリー、オスマン帝国などは敗北。1918年11月にドイツが降伏して戦争は終結しました。戦後はヴェルサイユ条約によってドイツが厳しい賠償を課せられ、これが後の第二次世界大戦の原因の一つとなりました。
第一次世界大戦(WW1)での日本の立場
第一次世界大戦における日本は、協商国側として参戦しました。当時、日本は日英同盟を結んでおり、同盟の義務に基づき1914年にドイツに宣戦布告。
主にアジア・太平洋地域でドイツの拠点(膠州湾や南洋諸島など)を攻撃・占領し、戦後にはこれらの領土を委任統治として獲得しました。日本本土が戦場にならなかったこともあり、被害は少なく、むしろ戦時景気で経済は一時的に成長しました。
国際的には戦勝国としてヴェルサイユ会議に参加し、国際連盟の常任理事国にもなりましたが、欧米列強との立場の違いも浮き彫りになっていきました。
第一次世界大戦の特徴
第一次世界大戦は、20世紀に入って最初の大戦争でした。戦争は4年半に及び、参戦国は総力戦を余儀なくされます。また、この戦争では数多くの新兵器が実戦投入され、戦争の姿を大きく変化させました。ここでは、総力戦体制と最新兵器について解説します。
世界初の総力戦となった
第一次世界大戦は、国家が持つすべての力を動員した総力戦となりました。
長期間の戦争に耐え抜くためには、武器・弾薬の調達や食料・原料の生産や輸送を効率的に行って大兵力を維持しなければなりません。そのためには、国の人的・物的資源のすべてを戦争に活用する必要があります。そのため、多くの国で食料や物資の配給、生産統制といった戦時統制経済が実施され、国民を否応なく戦争に巻き込みました。
最新兵器が投入された
第一次世界大戦の特徴の一つに、最新兵器の戦場投入があります。投入された主な最新兵器は以下の通りです。
- 飛行機
- 戦車
- 潜水艦
- 毒ガス
飛行機は、偵察や爆撃用の兵器として使用されました。大戦初期には簡易な装備だった飛行機でしたが、戦争中に研究が進められ、大型爆撃機や機関銃を装備した戦闘機が登場しました。
戦車を最初に使用したのはイギリス軍です。1916年のソンムの戦いで投入された戦車は、農業用トラクターを改造したもので、敵の機関銃から兵士を守り、塹壕を突破する際に使用されました。
潜水艦は、海軍が劣勢だったドイツが積極的に用いた兵器です。特に、商船や輸送船の破壊で威力を発揮しましたが、中立国の船舶も撃沈したため、アメリカ参戦の口実となりました。
毒ガスが初めて用いられたのは1915年のイープルの戦いでのことです。ドイツ軍が使用した毒ガスにより、5,000人もの協商国軍兵士が命を落としました。その後、連合国・協商国ともに毒ガスの開発と防御法の開発を繰り返し、毒ガスの威力は急速に上がっていきました。
戦争が長期化したことや最新兵器が次々と投入されたことで、戦死者が一気に増大し、800~900万人に達したといいます*4)。
第一次世界大戦(WW1)の歴史を年表で流れを解説
第一次世界大戦は4年半にも及ぶ大戦争でした。最初に、戦争の流れを整理します。
| 1914年6月 | サライェヴォ事件 →第一次世界大戦がはじまる イタリアは不参戦 |
| 1914年8月 | タンネンベルクの戦い |
| 1914年8月 | 日本がドイツに宣戦布告し、協商国側として参戦 |
| 1914年9月 | マルヌの戦い →西部戦線が膠着 |
| 1915年1月 | 二十一か条の要求 |
| 1915年5月 | イタリアが協商国側として参戦 |
| 1917年3月 | ロシア革命 |
| 1917年4月 | アメリカ参戦 |
| 1918年11月 | ドイツ降伏 |
| 1919年6月 | ヴェルサイユ条約調印 |
ここからは、重要事項に絞って戦争の流れを解説します。
サライェヴォ(サラエボ)事件
1914年6月、ボスニア・ヘルツェゴヴィナの州都であったサライェヴォを、オーストリアの帝位継承者のフランツ=フェルディナント夫妻が訪問しました。その際、セルビア人のプリンツィプによって暗殺されました*5)。
オーストリアは、フランツ=フェルディナント暗殺の背後にセルビアがいると考え、宣戦布告しました。セルビアを支援するロシアが軍隊を動員すると、ドイツがロシアに宣戦布告します。
さらに、ロシアと同盟関係にあったフランスもドイツに宣戦布告しました。このように、各国の同盟関係や利害関係が絡み合い、戦争の連鎖が急速に拡大していったのです。
また、ドイツは中立国のベルギーにも宣戦布告をしたため、それを理由にイギリスも参戦します。これにより、ドイツ・オーストリア対イギリス・フランス・ロシアという大国同士の大戦争が始まったのです。
イタリアの不参戦
イタリアは、三国同盟の一員でありながら、オーストリアと領土をめぐる争いがありました。これを、「未回収のイタリア」といいます。イタリア統一後もオーストリア領として残されたトリエステ・イストリア・南チロルの回復はイタリアの悲願でした*7)。
第一次世界大戦がはじまると、イタリアは中立を宣言し、1915年に協商国側として参戦しました。そして、戦争後に未回収のイタリアの大半を回復することに成功します。
タンネンベルクの戦いでロシアが大敗
開戦から2か月後の1914年8月、ドイツ軍とロシア軍が東プロイセンのタンネンベルクで激突しました。ドイツ軍司令官のヒンデンブルクは、ロシア軍を包囲・壊滅させて東プロイセンを取り返します*8)。
タンネンベルクの敗戦後、ドイツ・オーストリアとロシアが戦う東部戦線では、ロシアは劣勢となり、国民生活悪化の原因となりました。なお、戦後しばらくして、ヒンデンブルクはドイツの大統領に選ばれました。
塹壕戦となった西部戦線
ドイツとイギリス・フランスの戦いは西部戦線とよばれます。ドイツは中立国のベルギーを占領し、フランスのパリを攻め落とす作戦を立てますが、マルヌの戦いで阻止されてしまいます。以後、西部戦線は双方が塹壕を伸ばして戦う塹壕戦へと移行し、長期戦となりました。
ロシア革命
ロシアでは、第一次世界大戦前からロマノフ朝に対する不満が蓄積していました。タンネンベルクの戦いで敗れた後、ロシア軍は劣勢が続き、国民は食糧難・燃料難に苦しんでいました。にもかかわらず、皇帝ニコライ2世は戦いをやめようとしなかったため、ロマノフ朝への批判が高まっていたのです。
1917年3月、首都ペトログラード(現サンクトペテルブルク)で大規模なストライキが発生します。それをきっかけに、皇帝ニコライ2世は退位に追い込まれました。その後、ロシアでは混乱が続きますが、最終的にレーニンが権力を握り、ソヴィエト連邦(ソ連)を樹立します*9)。
【関連記事】ロシア革命とは?革命の流れをわかりやすく解説!
アメリカ参戦
第一次世界大戦がはじまったころ、アメリカは中立国でした。しかし、1915年に起きたルシタニア号事件をきっかけに、反ドイツの世論が高まります。
アメリカはイギリスやフランスを支援するため、多額の貸付を行っていましたが、敗北するとそれらの貸付が回収できない恐れがありました。そこで、アメリカは協商国側として参戦して、貸付の確実な回収を目指します。
ドイツ革命
ロシアの降伏により戦力を西部戦線に集中できるようになったドイツでしたが、アメリカの参戦などにより戦局が徐々に不利になっていきました。
1918年、ドイツのキール軍港で水兵たちが反乱を起こしたことをきっかけにドイツ革命が勃発します。皇帝ヴィルヘルム2世はオランダに亡命し、エーベルト率いる新政権は、協商国との休戦協定に応じました。
第一次世界大戦時の日本の動向
第一次世界大戦において、日本は日英同盟を理由として協商国側として参戦しました。大戦中、日本はどのような動きをしていたのでしょうか。大戦中の日本の動向をまとめました。
中国に二十一カ条の要求
協商国側として参戦した日本は、ドイツが東アジアに持っていた植民地を攻撃して占領します。占領したのは、ドイツ領南洋諸島と山東半島の膠州湾にあった青島です。
1915年1月、日本の大隈内閣は中華民国大総統の袁世凱に、21の要求を突きつけました。主な内容は、山東省のドイツ利権を日本のものとすることや南満州や東部内モンゴルに関する要求、日露戦争で手に入れた南満州鉄道の経営権の延長などです。
これに対して、中国側は外国の支援を受けようとしました。しかし、戦争中の諸外国の関心は薄く、最終的に日本の要求を受け入れました*10)。
シベリア出兵
ロシア革命が起きると、ロシア国内でソ連のレーニン率いる赤軍と、反発する勢力が内戦状態となりました。ソ連の誕生による社会主義の拡大を恐れたイギリス・フランス・アメリカ・日本は、ソ連を打倒するための干渉戦争をおこします。
各国が7,000人程の兵力を派遣したのに対し、日本は10倍の73,000人を派遣しました。その後、各国が順次撤退する中、日本は2022年までとどまったため各国の非難を浴びます。シベリア出兵は多数の死者を出したうえ、10億円もの戦費を費やして得るものがほとんどありませんでした*11)。
大戦景気で好況
第一次世界大戦の主戦場はヨーロッパであったため、戦場から離れた日本は貿易により莫大な利益を上げました。この好景気を大戦景気と呼びます。
ヨーロッパ諸国が第一次世界大戦に集中するため、アジアから欧米諸国の製品が姿を消しました。その空白を埋めたのが日本製品でした。加えて、戦争に必要な軍需物資の注文も相次いだため、日本は大きな利益を上げました。戦争前は外国からお金を借りる債務国でしたが、戦後は外国にお金を貸し付ける債権国となり、多くの成金を生み出しました。
世界における第一次世界大戦後の状況
1918年11月、4年半に及んだ大戦争がついに終わりを迎えました。戦後、世界はどのように変化したのでしょうか。戦後の大きな変化としてヴェルサイユ体制とアメリカの台頭の2つを取り上げます。
ヴェルサイユ条約の締結
1919年1月、フランスのパリで講和会議が開かれ、戦後秩序の話し合いが行われました。この会議で成立した条約をヴェルサイユ(ベルサイユ)条約といいます。この条約により、ドイツは植民地のすべてと本土の10%以上を失いました*12)。
また、軍備を制限され、多額の賠償金の支払いを課せられます。ドイツ抜きで話し合われたヴェルサイユ条約に対するドイツ人の不満は激しいものがあり、後のヒトラー登場や第二次世界大戦の原因となりました。ヒトラーはヴェルサイユ条約によってつくられたヴェルサイユ体制の打破を掲げ、国民の支持を獲得していきます。
アメリカの台頭による”黄金の20年代”の始まり
第一次世界大戦によりヨーロッパは荒廃しましたが、国土が戦場にならなかったアメリカは、空前の繁栄を迎えます。後に、1920年代のアメリカは”黄金の20年代”とよばれます。
アメリカが繁栄した理由は、第一次世界大戦中にイギリスやフランスに大量の物資を売却し、多額の貸付を行ったからです。アメリカが利益を上げる一方、イギリスやフランスは、戦争で勝ったにもかかわらず国力が低下します。第一次世界大戦は、アメリカが世界のナンバー1になるきっかけを作った戦争といってもよいでしょう。
日本における第一次世界大戦後の状況
第一次世界大戦では、日本もアメリカと同じく大きな利益を上げました。しかし、アメリカほど産業が発達していなかった日本では、大戦後に戦後恐慌に見舞われてしまいます。戦後恐慌の内容を見てみましょう。
戦後恐慌で成金が没落
第一次世界大戦後の1920年、日本では生糸や綿製品、銅といった貿易関連商品の価格が暴落して企業の倒産が相次ぎました。銀行の取り付け騒ぎなども発生したこの混乱を戦後恐慌といいます。
政府や日本銀行が救済のために動いたため、戦後恐慌は半年程度で鎮静化しました。第一次世界大戦中の船舶業を中心に成功していた成金の多くが、戦後恐慌によって没落しました。以後、日本は震災恐慌や金融恐慌などに見舞われ、経済的に不安定な1920年代を経験することとなります。
【関連記事】第二次世界大戦とは?特徴や歴史、日本の動向についてわかりやすく!
第一次世界大戦(WW1)に関するよくある質問
第一次世界大戦(WW1)は規模や影響が大きいため、多くの人がその原因や結果、関係国の動きについて疑問を持ちます。ここではよくある質問にわかりやすく答えます。
第一次世界大戦(WW1)のきっかけは何?
第一次世界大戦のきっかけは、1914年のサラエボ事件です。オーストリア=ハンガリー帝国の皇太子が、セルビア系の青年に暗殺されたことから両国の緊張が高まり、オーストリアがセルビアに宣戦布告しました。
この紛争に、ドイツ・ロシア・フランス・イギリスなどが次々と参戦し、ヨーロッパ全土に戦火が広がりました。背後には、帝国主義・民族主義・軍拡競争、そして複雑な同盟関係といった要因があり、偶発的な事件が大戦の引き金となったのです。
第一次世界大戦(WW1)はどのくらい続いたの?
第一次世界大戦は1914年から1918年までの約4年間続きました。開戦は1914年7月28日、オーストリアがセルビアに宣戦布告した日で、終戦は1918年11月11日、ドイツが休戦協定に調印した日とされています。
この4年間で、世界の多くの国が巻き込まれ、戦場はヨーロッパを中心に、アフリカやアジア、海上にも及びました。戦死者は1,000万人以上とされ、当時としては史上最大規模の戦争でした。総力戦体制や近代兵器の登場が、戦争の長期化と被害の拡大を招いた大きな要因です。
第二次世界大戦はいつから始まった?
第二次世界大戦は、1939年9月1日にドイツがポーランドへ侵攻したことをきっかけに始まりました。これを受けて、イギリスとフランスが9月3日にドイツへ宣戦布告し、戦争が本格化します。
以後、ヨーロッパ全土やアジア・太平洋地域に戦火が拡大し、最終的には60か国以上が参戦する史上最大の戦争となりました。
第一次世界大戦(WW1)で勝ったのはどの国?
一次世界大戦では、協商国側(イギリス・フランス・アメリカなど)が勝利しました。1917年にアメリカが参戦したことで、人的・物的支援が強化され、戦局は有利に進みました。
一方、同盟国側(ドイツ・オーストリア・オスマン帝国など)は戦力が限界に達し、1918年に次々と降伏。ドイツは厳しい条件のヴェルサイユ条約を結ばされ、領土の縮小や巨額の賠償を課せられました。
この結果、協商国が正式な勝者となりましたが、戦後の不満が第二次世界大戦の火種となっていきました。
WW1はなぜ「世界大戦」と呼ばれるの?
第一次世界大戦が「世界大戦」と呼ばれるのは、戦場がヨーロッパにとどまらず、アジア・中東・アフリカなど世界各地に広がったからです。発端はヨーロッパの同盟国と協商国の対立でしたが、イギリス・フランス・ロシア・ドイツ・オーストリアに加え、アメリカや日本、オスマン帝国など25か国以上が参戦しました。
植民地を持つ国々も巻き込まれたため、戦闘や物資供給の舞台は地球規模に拡大。戦場の広がりと国際的な参戦規模から、「第一次世界大戦=世界大戦」と呼ばれるようになったのです。
日本は第一次世界大戦でどんな役割を果たしたの?
日本は日英同盟を理由に、1914年に協商国側として第一次世界大戦に参戦しました。主に中国の膠州湾や南洋諸島など、ドイツの拠点を攻略・占領するなどアジア太平洋地域での軍事行動が中心でした。
日本本土が戦場になることはなく、むしろ戦時景気により産業が発展しました。戦後は戦勝国としてヴェルサイユ会議に参加し、国際連盟の常任理事国にもなりましたが、人種差別撤廃提案が退けられるなど、欧米列強との格差も明らかになりました。
第一次世界大戦とSDGs
19世紀以前の戦争は、国民に間接的な影響を与えるだけで済むケースがほとんどでした。しかし、第一次世界大戦は総力戦となったため、多くの国民が戦争に巻き込まれました。ここでは、総力戦とSDGsの関わりを考えてみます。
SDGs目標16「平和と公正をすべての人に」との関わり
SDGs目標16は、世界の平和と公正を実現するための目標です。戦争が起きると、戦場となった地域で暴力が発生して多くの人が亡くなります。第一次世界大戦は、直接戦場となった地域だけではなく、国全体を巻き込む総力戦となりました。
総力戦は、社会全体に戦争協力を求めます。大戦参加国の中でも国内経済が弱かったロシアでは、戦争によって経済が崩壊し、労働者を中心に政府に対する反発が強まりました。その結果、ロシア帝国は崩壊してしまいます。
国の崩壊にまで至らなかったにせよ、イギリスやフランスでも国民経済に大きな悪影響が出ていました。20世紀以降の戦争は、戦場以外の部分でも国民生活を圧迫してしまうのです。総力戦は、国の全ての力を戦争にそそぐものである以上、戦争の勝利が何よりも優先されるため、国民生活は否応なく犠牲となるのです。
まとめ
今回は、第一次世界大戦について解説してきました。第一次世界大戦は、参戦国のどの国も予想しない長期戦となりました。そのため、国力の弱いロシアは革命によって離脱し、他の国も大きな痛手を負いました。
戦争により、ドイツ帝国・オーストリア帝国・ロシア帝国が崩壊し、イギリスやフランスも大打撃を受けてヨーロッパが疲弊しました。かわって世界の中心となったのがアメリカです。
第一次世界大戦は、戦争に対する考え方を根本から変えました。国の全ての力を戦争に動員する総力戦を前提とした研究が進みます。第一次世界大戦から30年近くたった1939年、第二次世界大戦でより大規模化した総力戦が展開され、より多くの人々が亡くなりました。
総力戦は引き際が難しい戦いです。重要なのは総力戦の勝ち方よりも、総力戦にならないための事前の準備である政治・外交ではないでしょうか。
参考
*1)日本大百科全書(ニッポニカ)「第一次世界大戦」
*2)日本大百科全書(ニッポニカ)「総力戦」
*3)デジタル大辞泉「塹壕」
*4)山川 世界史小辞典 改定新版「第一世界大戦」
*5)改定新版 世界大百科事典「サラエボ事件」
*6)精選版 日本国語大辞典「ボスニアヘルツェゴヴィナ」
*7)山川 世界史小辞典 改定新版「未回収のイタリア」
*8)百科事典マイペディア「タンネンベルクの戦」
*9)改定新版 世界大百科事典「ロシア革命」
*10)山川 日本史小辞典 改定新版「対華二十一カ条の要求」
*11)旺文社日本史事典 三訂版「シベリア出兵」
*12)デジタル大辞泉「ベルサイユ条約」
*13)デジタル大辞泉「取付け」
この記事を書いた人
running.freezy ライター







