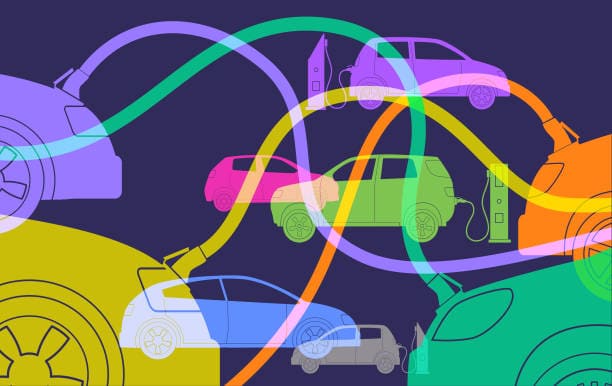
ZEV規制という言葉は、まだ一般に浸透していないかもしれませんが、「ガソリン車の販売が禁止になる!」というニュースを聞いたことはありませんか?日本政府は、2050年カーボンニュートラルに向けて、2035年までに新車販売でZEV100%を実現するという方針を打ち出しています。
ZEV規制はこのことに深く関係しています。ZEV規制とは何かを、ZEVクレジットの計算や世界・日本の現状、SDGsとの関係などから詳しく解説します。
目次
ZEV規制とは
ZEV規制のZEVは、Zero Emission Vehicle(ゼロエミッション・ビークル)の略称です。つまり、ZEV規制とは「排出ガスを全く出さない車両の普及を目指す規制」のことです。ZEV規制の目的は、
- 温室効果ガスの削減
- エネルギー安全保障の向上
- ZEVの普及や技術革新
- 産業競争力の強化
などが挙げられます。
ZEV規制の内容
ZEV規制は、アメリカのカリフォルニア州が1990年に制度を導入し、1998年から施行しました。ZEV規制では、カリフォルニア州内で一定台数以上、自動車を販売するメーカーに対し、ZEVを一定比率以上販売することを義務付けます。
企業はZEV規制による目標達成率に対し、ZEVクレジットやPZEV※(SULEV適合ガソリン車※など)クレジット(次の章で解説)で換算します。例えば、ZEV規制により与えられた目標よりもZEVの販売率が不足した場合は、ZEVクレジットやPZEVクレジットを多く所有している他企業などから購入して不足分を補うか、罰金を支払わなくてはなりません。
ZEV規制の歴史
ZEV規制は、1990年にカリフォルニア州で初めて導入された後、欧州や中国などでも導入が進み、現在では世界各地でZEVの普及が進められています。2021年までの歴史を大まかな表にまとめました。
| 時期 | 内容 |
| 1990年代初頭 | カリフォルニア州が、ZEV(Zero Emission Vehicle)の販売割合を規制する法案を制定。 |
| 1996年 | カリフォルニア州が、ZEV販売比率を2003年までに10%とする規制を制定。 |
| 2001年 | カリフォルニア州が、ZEV販売比率を2003年までに4.5%に緩和する規制を制定。 |
| 2003年 | カリフォルニア州が、ZEV販売比率を2008年までに10%に引き上げる規制を制定。 |
| 2004年 | 東京都が、環境先進都市宣言を行い、ZEVの導入を推進する方針を示す。 |
| 2011年 | カリフォルニア州が、ZEV販売比率を2025年までに15.4%に引き上げる規制を制定。 |
| 2012年 | 中国政府が、2020年までに新車販売の5%をZEVにする目標を掲げる。 |
| 2016年 | EUが、自動車メーカーに対して、2021年までに新車販売の3.5%をZEVにする目標を掲げる。 |
| 2018年 | カリフォルニア州が、ZEV販売比率を2025年までに22%に引き上げる規制を制定。 |
| 2020年 | EUが、自動車メーカーに対して、2025年までに新車販売の15%をZEVにする目標を掲げる。 |
| 2021年 | カリフォルニア州が、ZEV販売比率を2035年までに100%にする規制を制定。 |
続いては、そもそもZEVとは何かを詳しく確認していきましょう。
ZEVとは
ZEVは、CO2などの温室効果ガスを含む排出ガスを全く出さない車両のことを示します。このような車両は、地球温暖化の原因を抑制するための重要な手段とされています。
ただし、ZEVの定義は国や地域によって異なる場合があります。例えば、カリフォルニア州では、ZEVは車両からの排出ガスだけでなく、燃料生産や配送における排出ガスも考慮されます。
ZEVの特徴
ZEVの特徴は、エンジンからの温室効果ガスを含む排出ガスが全くないことです。これにより、大気汚染や地球温暖化の防止に寄与します。また、電気や水素などの再生可能エネルギーを利用することにより、化石燃料への依存を減らすことができます。
ZEVの種類
ZEVには現在、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV・FCEV)などがあります。プラグインハイブリッド車(PHV・PHEV)は一部の国や地域ではZEVに含まれますが、カリフォルニア州では含まれません。(プラグインハイブリッド車はエンジンを使って走ることができるため、ZEVの規定から外れる排出ガスが発生する可能性があります。)
- 電気自動車(EV):電池から電気を取り出してモーターで走る。充電スタンドで電気を補給する。
- 燃料電池自動車(FCV・FCEV):水素と空気から電気を作ってモーターで走る。水素スタンドで水素を補給する。
- プラグインハイブリッド自動車(PHV・PHEV):電池とエンジンの両方を使って走る。充電スタンドやガソリンスタンドでそれぞれ補給する。
【関連記事】EV車のメリットとデメリット・充電の仕組み、今後電気自動車は日本で普及するのか?
他にも、現在はまだ開発中ではあるものの、将来的にZEVに加わる可能性のあるタイプの自動車もあります。
- 水素エンジン自動車:水素を燃やしてエンジンで走る。水素スタンドで水素を補給する。現在、トヨタが開発中。
- ソーラーカー:太陽光を電気に変えてモーターで走る。太陽光が当たる場所で充電する。現在、一部の大学や企業が開発中。
などです。
【関連記事】水素自動車とは?仕組みや将来性、普及しない理由、販売しているメーカーは?
【ZEVのマッピング】
また、自動車の仕組みを変えるのではなく、燃料をカーボンニュートラル化する研究開発も進んでいます。このようなカーボンニュートラルの合成燃料には、例えば以下のようなものがあります。
| 燃料 | 特徴 | 課題 |
|---|---|---|
| e-fuel (イーフューエル) | ・CO2と再生可能エネルギー由来のH2を合成して製造される液体またはガス燃料。 ・ガソリンや軽油と同じように使えるため、既存のエンジン車やインフラを活用できる。 ・燃焼時に排出されるCO2は、製造時に回収したCO2と同量なので、カーボンニュートラルとなる。 | 製造コストと効率性 |
| バイオ燃料 | ・サトウキビや生ごみなどのバイオマスから作られるバイオエタノールやバイオディーゼルなど。 ・燃焼時に排出されるCO2は、植物が光合成で吸収したCO2と同量なので、カーボンニュートラルと考える。 ・すでに商用化されている。 | 原料不足や製造コスト |
カーボンニュートラルな合成燃料は解決すべき課題がまだあり、社会実装には今しばらくの時間がかかると考えられています。
ZEVのメリット
- 環境にやさしい
走行時に温室効果ガスや大気汚染物質を排出しないため、地球温暖化や大気環境の改善に貢献できます。 - 経済的にお得
燃料費やメンテナンス費が低く抑えられるため、ランニングコストが安くなります。また、国や地方自治体などから補助金や減税などの優遇措置を受けることができます。 - 静かで快適
走行時の騒音や振動が少なく、静かで快適な走りを楽しめます。また、EVやFCVは外部に電力を取り出すことができるため、非常時の電源としても役立ちます。
ZEVのデメリット
- 航続距離が短い
一度の充電や給油で走れる距離が、ガソリン車よりも短い場合があります。特にEVは、バッテリー容量や気温などによって航続距離が変わります。 - 充電・給油インフラが不足している
全国的に見ても、充電スタンドや水素スタンドの数はまだ十分ではありません。特に地方では、充電・給油できる場所が限られている場合があります。 - 購入価格が高い
ZEVは、ガソリン車よりも購入価格が高い場合があります。特にFCVは、水素タンクや燃料電池システムなどの高価な部品を搭載しているため、コストがかかります。
ZEVとZEV規制について、大体理解できましたか?次はZEV規制の内容で出てきた「クレジット」について解説します。*1)
ZEV規制のクレジットとは
ZEV規制では、自動車メーカーに対して一定割合のZEVの生産・販売を義務付けています。これを達成できないメーカーは、他のメーカーからZEVクレジットを購入することで不足分を埋め合わせることができます。
ZEVクレジットとは、ZEV(電気自動車や燃料電池車など)を販売したときに得られるポイントのことです。得られるクレジットの数は、ZEVの種類や航続距離によって異なります。
※ZEV規制は、メーカー(生産企業)のみに課せられる規制です。チェーン販売店や個人経営の小売店には、ZEV規制は適用されません。チェーン販売店や個人経営の小売店は、ZEVを販売するかどうかは自由です。
クレジットの利用・価格
- ZEVクレジットを多く持つメーカーは、自社のZEV販売比率が規制基準を上回った場合、余剰分のクレジットを他のメーカーに売却することができます。
- ZEVクレジットを少なく持つメーカーは、自社のZEV販売比率が規制基準を下回った場合、不足分のクレジットを他のメーカーから購入するか、規制当局に罰金を支払う必要があります。
- ZEVクレジットの売買価格は、市場の需要と供給によって決まりますが、一般に公開されません。
クレジットの収入
クレジットの収入は、ZEVを多く販売するメーカーにとって大きな利益源となっています。
特にテスラは、100%電気自動車を生産・販売しているため、ZEV規制の恩恵を受けています。
(テスラは、ZEV規制の下で獲得したクレジットを、ZEV販売比率が基準を下回った他のメーカーに売却することで、数百億円と言われる大きな収益を得ていると言われています。)
ZEV販売比率とクレジット
ZEV販売比率※は、自動車メーカーが販売する新しい車の中で、ZEVの割合を表しています。最初は10%で始まり、徐々に増えていきます。
ただし、ZEVだけでは難しいため、先進PZEVやPZEV※も組み合わせて販売することができます。例えば、2010年型では総販売台数の10%がZEVでなければならず、そのうち2%はZEV、2%は先進PZEVで、残りの6%はPZEVで代替することができます。
ZEVやPZEVの性能に応じてクレジット(係数)で換算し、より性能の高い車が販売される仕組みになっています。(=ZEV性能が高いほど得られるクレジットも多くなる)
【ZEV販売比率※とクレジット】
ZEVクレジットの計算式
ZEVクレジットは、
- ZEVクレジット = 車の販売台数 × ZEVの係数(クレジット単価)
という計算式で求められます。
ZEVの係数は、ZEVの性能によって異なります。性能が高いほど、係数が大きくなります。また、クレジット単価は、各州によって異なります。例えば、カリフォルニア州では、電気自動車1台あたり1クレジット、燃料電池車1台あたり2クレジットが付与されます。
例えば、あるメーカーが、
- 電気自動車100台
- 燃料電池車50台
を販売したとします。カリフォルニア州の場合、
- 電気自動車1台あたり1クレジット
- 燃料電池車1台あたり2クレジット
が付与されるため、このメーカーは合計で
- 100台 × 1クレジット + 50台 × 2クレジット = 150クレジット
を獲得することができます。ZEV規制のクレジットについてまとめると、
- ZEVクレジット:ZEVの性能に応じたポイント
- ZEVクレジットの取引:販売できないメーカーは購入か罰金、販売できるメーカーは収入源
という点が要点となります。次の章では、世界のZEV規制の現状について見ていきましょう。*2)
世界のZEV規制の現状
ZEV規制は、カリフォルニア州を含めたアメリカの16州とワシントンD.C.や欧州の一部で導入されています。また、イギリスやフランスなどでは2040年までに、インドでは2030年までにガソリン・ディーゼル車の新車販売を禁止する方針を表明しています。
アメリカでZEV規制を導入している州
アメリカでZEV規制を導入している主な州を下の表にまとめました。
| 州 | 開始時期 | 内容 | 管理機関 |
|---|---|---|---|
| カリフォルニア州 (California) | 1990年代から | 現在、最も厳しい規制を実施(先述) | カリフォルニア州エアリソースボード(California Air Resources Board) |
| ニューヨーク州 (New York) | 2013年 | 2025年までに州内の新車販売の7.5%がZEV | ニューヨーク州エネルギー研究開発局(New York State Energy Research and Development Authority) |
| マサチューセッツ州 (Massachusetts) | 2014年 | 2025年までに州内の新車販売の7.5%がZEV | マサチューセッツ州エネルギー及び環境事務所(Massachusetts Executive Office of Energy and Environmental Affairs) |
| オレゴン州 (Oregon) | 2018年 | 2025年までに州内の新車販売の10%がZEV | オレゴン州環境品質委員会(Oregon Environmental Quality Commission) |
EUを中心とした欧州
2022年2月、EU理事会(閣僚理事会)と欧州議会は、乗用車・小型商用車(バン)の二酸化炭素(CO2)排出基準に関する規則の改正案について、暫定的ですが合意に達しました。これにより、EUでは2035年までに「全ての新車をゼロエミッション化」(=2035年以降は内燃機関(エンジン)搭載車の生産を実質禁止)することを目指す方針になりました。
しかし、EU理事会の提案により、欧州委が2026年に進捗評価を行い、PHV(プラグインハイブリッド)技術などの開発状況を考慮して規則の見直しを行う余地を残しています。
現時点でのEUにおけるZEV規制に対する、賛成派と反対派の主張を簡単にまとめてみます。
賛成派
賛成派は主に、欧州議会やEU理事会(閣僚理事会)、欧州自動車工業会(ACEA)などです。賛成派の主張は以下のようなものが挙げられます。
- ZEV規制は、EUが掲げる2050年までの気候中立(温室効果ガスの排出量実質ゼロ)の目標に向けて、自動車部門の脱炭素化を加速させる必要がある。
- ZEV規制は、自動車業界にとってもイノベーションや競争力向上の機会を提供し、電動化やデジタル化などの技術革新に対応することができる。
- ZEV規制は、消費者や社会にとってもメリットがある。(空気質や騒音の改善、燃料費やメンテナンス費の削減、雇用や経済成長の創出など)
反対派
反対派は主に、ドイツやイタリアなどの自動車産業を抱える国や、欧州自動車部品工業会(CLEPA)などです。反対派の主張は以下のようなものが挙げられます。
- ZEV規制は、自動車業界にとって過酷な負担を強いるものであり、雇用や収益性に深刻な影響を与える恐れがある。
- ZEV規制は、消費者や社会にとってもデメリットがある。(電気自動車(EV)の価格高騰や充電インフラ不足、原材料供給不安やエネルギー価格上昇など)
- ZEV規制は、電動化以外にも脱炭素に貢献する技術を無視するものであり、ハイブリッド技術や水素自動車、合成燃料などの多様な技術を活用すべきである。
その他の国:インド、中国
日本以外のアジアの国では、インドと中国がZEVの普及に向けて動いています。この2つの国は、それぞれ異なる政策や目標を掲げています。
インド
【空気汚染のため空が濁る首都ニューデリー】
インドの2021年のZEVシェアは0.4%にとどまり、他の脱炭素政策と比較して遅れています。しかし、インドは2030年からZEV(電気自動車・水素自動車)のみを販売するという目標を掲げています。
【インドの新規EV登録台数の推移】
上のグラフからもわかるように、インドでのEV車両の新規登録台数は増加していますが、普及しているのは自動三輪・二輪車が主です。特に、自動三輪車がタクシーとして広まっており、新規登録の約8割がEVです。
また、インドでもEVは販売価格がまだ高く、充電ステーションやサービスステーションの数も限られています。そのため、インド政府はEV生産早期普及策FAME※を導入し、EV購入者に対する補助金給付や充電ステーション数の拡充などを行っています。
中国
2021年に世界で販売されたZEVの大半を中国産の自動車が占めています。2022年の世界のEV販売台数は約726万台で、2021年と比較すると約70%増加し、ガソリン車などを含む自動車販売市場全体の10%に迫る勢いですが、世界のEV販売台数のうち約453万台が中国車です。
中国は、2035年を目標に新車販売をEVやハイブリッド車などの環境適応車のみとする方針を示しています。中国のZEV規制には、NEV(ニューエネルギービークル)規制※とCAFC(コーポレート・アベレージ・フューエル・コンサンプション)規制※という異なる2つのアプローチの環境規制が存在し、この2つは「デュアルクレジット規制」※と呼ばれる仕組みの一部です。
次の章では、日本のZEV規制の現状を確認しましょう。*3)
日本のZEV規制の現状

日本では、2020年に国土交通省が「2050年までに新車のほぼ全てを電気化する」方針を発表しました。具体的なZEV規制の導入はまだですが、政府は電気自動車の普及を進めるための各種施策を進めています。
【自動車メーカー各社の目標(2022年6月時点)】
また、ZEV規制と同様の制度はまだありませんが、国土交通省が主導する「次世代自動車振興センター※」がZEVの普及促進に関する調査研究や広報・啓発などを行っています。しかし、実際のところ2023年6月現在では、ZEV規制をめぐって、賛成派と反対派が議論を繰り返している状況です。
政府の方針
日本政府は、2035年に新車販売に占めるZEV(EV、PHV、FCV)の比率を100%にするという目標を掲げています。しかし、具体的な規制やインセンティブの内容はまだ発表されていません。
一方で、欧米や中国では、ZEV規制と呼ばれる厳しい排出ガス規制が施行されており、日本車は対応に迫られています。日本政府は、日本版ZEV規制の導入を検討しているという見方もありますが、自動車メーカーや関連産業との調整が必要です。
ZEV規制賛成派
ZEV規制賛成派は、主に環境保護や気候変動対策の観点から、ガソリン車やディーゼル車の排出する二酸化炭素や窒素酸化物などの有害物質を減らすことが最優先だと考えています。さらに、ZEVの普及は、再生可能エネルギーの導入や電力インフラの改善にもつながると期待しています。
ZEV規制反対派
ZEV規制反対派は、主に経済や産業の観点から、ZEVへの移行には多くのコストや課題が伴うと指摘しています。例えば、ZEVは製造時に多くの二酸化炭素を排出することや、電池製造における再エネルギーの普及度合い、コスト面の問題があることが挙げられます。
また、ZEVの普及には充電インフラや水素インフラの整備が不可欠であり、商用車や大型車などの分野では電動化への対応が現在の技術では困難です。ZEVへの移行は、ガソリン税などの税収減少や自動車産業の競争力低下などの影響も懸念しています。
環境・経済・技術・政策など、まだ課題が多い
ZEV規制は、
- 世界的な環境問題への対応として必要な一歩であるという意見
- 日本の経済や産業への影響を考慮すべきであるという意見
が対立しています。日本政府は、国際的な規制動向や技術革新に適応しつつ、自動車メーカーや関連産業と協力して、電動化への移行を円滑に進めるための政策・インセンティブを検討する必要があります。
世界的な自動車メーカーを多数抱える日本にとって、ZEV規制についての決断はさまざまな方面に多大な影響があるでしょう。次の章では、自動車の脱炭素化に向けた日本政府の取り組みを紹介します。*4)
日本政府の取り組み
日本政府は、2030年までにZEVの普及率を20〜30%にすることを目標としています。これは、現状のZEVの普及率が1%程度(2023年時点)であることを考えると、非常に高い目標です。しかし、日本政府は、ZEVの普及を促進するためのさまざまな施策によって、この目標を達成することを目指しています。
日本政府は、2050年までに世界で供給する日本車について、世界最高水準の環境性能を実現することを長期的なゴールとしています。日本は自動車産業の盛んな国であり、世界に優れた環境性能の自動車を供給することで、地球温暖化対策に大きく貢献すると期待されています。
ZEVの普及促進
経済産業省は、「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」として、ZEVに必要な充電・充てんインフラの整備費や活動費の一部を補助する制度を実施しています。
EV購入時の補助金
政府は、EV・PHV・FCVの購入補助事業を実施しています。2022年度では予算を増額し、補助金の上限額も大幅に引き上げました。例えば、EVの場合、これまでの上限額40万円から85万円に増額されました。
【EVの補助上限額】
充電・充てんインフラの整備
充電・充てんインフラの整備はZEVの普及のためには必須です。政府は、2030年までに急速充電ステーション3万基、普通充電ステーション12万基、および水素ステーション1,000基を整備することを目指して、設備費や工事費を補助する事業を実施しています。
特に、EVやPHV用の充電設備については、集合住宅や高速道路のサービスエリア、山間部などの空白地域を重点的に整備していく方針です。また、FCV用の水素ステーションについても、民間企業と連携しながら、大都市圏とそれを結ぶ幹線沿いを中心に整備していく予定です。
【EVの充電設備】
蓄電池産業の確立
ZEV普及のためには、バッテリーなどの蓄電池の開発・普及も欠かせません。
【蓄電池の重要性】
- 次世代電池の実現及び人材育成・確保
2030年ごろには全固体電池を本格的に実用化し、技術リーダーの地位を維持・確保するために、人材育成に約1,000億円を投じます。 - 上流資源の確保
JOGMEC※の事業出資比率を引き上げるなどして、原材料調達の安定化を図ります。 - サプライチェーンの管理強化等のルール整備
ヨーロッパやアメリカなどと連携し、国際的なカーボンフットプリント規制や責任ある材料調達などのルール整備を行います。 - 需要拡大
EVや再生可能エネルギー普及に向けて政策的なインセンティブやインフラ整備を行い、需要拡大を目指します。 - リサイクル・リユース促進
蓄電池のリサイクル・リユース促進のため、回収・再利用・再資源化の制度や技術開発を推進します。
【蓄電池の国際競争力の強化に向けた3つの領域】
自動車産業全体がZEV対応するための移行
政府は、温室効果ガス排出を減らすのが難しい産業(Hard-to-Abate産業)が、排出を減らすための取り組みに必要な資金調達ができるよう、各分野ごとに技術開発の計画とトランジションファイナンス※に代表される金融システムの整備を進めています。自動車の分野では、製品作りやエネルギーの作り方や供給方法でCO2の排出を減らすだけでなく、自動車利用方法の変化をもたらす対策を含めたロードマップが作成されました。
自動車利用方法の変化をもたらす対策の具体的な例は、以下のとおりです。
- 自転車や公共交通機関の利用促進
- テレワークの推進
- カーシェアリングやライドシェアの利用促進
- 住宅地と商業地の分離
- 都市の再開発による歩行者や自転車の移動に配慮した街づくり
これらの対策により、自動車の利用を減らし、CO2の排出を削減することができます。
【関連基準】トランジション・ファイナンスとは?基本指針、国内事例、メリットや課題も
さらに、ヨーロッパやアメリカなどと協力し、カーボンフットプリント※規制や責任ある材料調達などの国際ルールの策定に参画することで、国際連携とルールの整備にも着手しています。グローバル市場での競争力強化・技術革新の促進に向け、海外市場への展開や国際共同研究等も推進しています。
【関連記事】カーボンフットプリントとは?算定方法や課題、企業の取組事例も
また、電動化が進むことによる自動車産業への影響に対応するため、自動車産業『ミカタ』プロジェクト※を立ち上げ、エンジン部品メーカーなどを支援し、電動化への対応を促進します。グリーンイノベーション基金を通じ、次世代電池・モーターの研究開発や、合成燃料、自動運転技術の省エネルギー化などの開発を進め、自動車のカーボンニュートラルに向けて様々な可能性を模索しています。
【日本が進めるシステム開発と予算】
日本政府が、ZEVに対応するためにさまざまな取り組みをしていることがわかりますね!次の章ではZEV規制の問題点と課題に焦点を当てます。*5)
ZEV規制の問題点
ZEV規制の問題点として、環境負荷の移転やレアメタルへの依存、安全性・信頼性の確保があります。詳しく見ていきましょう。
環境負荷の移転
ZEVは走行時に温室効果ガスを排出しないため、環境に優しいとされますが、その一方で、バッテリーやモーターなどの製造や廃棄には多くのエネルギーや資源が必要です。また、ZEVが使用する電力も、火力発電など化石燃料に由来する場合は、間接的に二酸化炭素を排出していることになります。
レアメタルへの依存
ZEVはバッテリーやモーターにレアメタルを多く使用しますが、その産出国は限られており、供給不安や価格高騰などのリスクがあります。また、レアメタルの採掘や製錬には多くの水やエネルギーを消費し、環境汚染や人権侵害などの社会問題も引き起こしています。
安全性・信頼性の確保
ZEVはガソリン車と比べて新しい技術であるため、まだ十分な実績やデータが蓄積されていない現状があります。ZEVには火災や爆発などの危険性もありますし、故障や事故の際の対処法も確立されていません。また、ZEVは静かすぎるため、歩行者や自転車などの他の交通参加者に気づかれにくく、事故の原因になる可能性もあります。
ZEV規制の課題
上記の問題点に加えて、充電インフラの整備や電力供給の安定性、バッテリー性能の向上も課題となっています。ひとつずつ説明します。
充電インフラの整備
ZEVの普及には、充電ステーションや水素ステーションなどのインフラが不可欠ですが、その建設や増設には多くのコストや時間がかかります。充電インフラの供給が需要に追い付かなければ、ZEVの利便性や魅力が低下する恐れがあります。
電力供給の安定性
ZEVは電力に依存します。そのため、電力不足や停電などの事態が発生した場合、ZEVの走行に影響が出る可能性があります。ZEVの急速充電には特別高圧の電力が必要ですが、その供給は現在の電力網では困難な場合もあります。
バッテリー性能の向上
ZEVの航続距離や充電時間は、バッテリーの性能に大きく左右されます。現在のバッテリーは、航続距離を伸ばすと重量やコストが増えるというトレードオフの関係にあります。また、バッテリーは温度や劣化によって性能が低下するという問題もあります。
レアメタルが調達できない場合の日本の解決策は?
【レアアース精錬所】
レアメタルが調達できない場合、ZEVの製造者は大きな影響を受ける可能性があります。レアメタルはZEVのモーターやバッテリーに必要な材料なので、その供給が不安定になれば、コストや品質に問題が生じるかもしれません。
解決策としては、以下のようなものが考えられます。
レアメタル供給源の多角化
レアメタルの産出国に偏りがあるため、鉱山開発や製錬工程において、日本企業が権益を獲得することで、供給リスクを低減することができます。
備蓄制度の見直し
レアメタルの短期的な供給途絶への対策として、国家備蓄や民間備蓄を行うことで、需要に応じて必要な量を確保することができます。
代替材料・省電力化の技術開発
レアメタルに代わる材料や、レアメタルの使用量を減らす技術を開発することで、需要を抑制することができます。
リサイクル推進
使用済みのZEVやバッテリーからレアメタルを回収することで、新たな資源として再利用することができます。
排他的経済水域(EEZ)でのレアメタル採掘
日本のEEZ内には、海底にレアメタルを含む鉱物資源が存在する可能性があります。これらを採掘することで、国内でレアメタルを確保することができます。
これらの解決策は、日本政府や産業界が積極的に取り組んでいるものです。しかし、それぞれの解決策にも課題やコストがあり、効果的かつ持続可能な方法や技術を開発する必要があります。次の章ではZEV規制の今後の動向について確認します。*6)
【関連記事】レアアースとは?レアメタルとの違い、使い道、世界の現状と産出国・今後の展望
ZEV規制の今後の動向
2023年6月現在、今後のZEV規制について、日本を含めた世界の予定や目標をまとめると以下のようになります。この内容は後に変更になる場合もありますので、注意してください。
| 時期 | 国・地域 | 予定・目標 |
|---|---|---|
| 2025年 | カリフォルニア州 | ZEV販売比率を22%から50%に引き上げる予定。 |
| EU | 新車販売の15%をZEVにする。 | |
| 中国 | 新車販売の20%をZEVにする。 | |
| 日本 | 新車販売の50%をZEVにする。 | |
| 2030年 | カリフォルニア州 | ZEV販売比率を50%から100%に引き上げる。 |
| EU | 新車販売の55%をZEVにする | |
| イギリス | 新車販売の100%をZEVにする。 | |
| 中国 | 新車販売の50%をZEVにする。 | |
| 日本 | 新車販売の70%をZEVにする。 | |
| 2040年 | カリフォルニア州 | ZEV販売比率を100%達成。 |
| EU | 新車販売の100%をZEVにする。 |
【各国・地域の電動化等の目標】
レアメタルの確保をどうするか
【EVに必要なレアアースの例】
ZEV規制の課題として、世界各国にとって重要な問題となっているのがレアメタルの確保です。レアメタルは、
- 存在する国が偏っている
- 政情に不安のある国が多い
などの理由により、いつでも安定的に供給されるとは限りません。
また、需要が供給を上回る可能性もあります。そのため、日本を含む多くの国は、レアメタルの確保に向けてさまざまな取り組みをしています。
【自動車製造に必要なレアメタルの現状の例】
日本のレアメタル確保への取り組み【JOGMEC】
JOGMECは、「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」の略称で、日本の資源・エネルギーの安定的な確保とカーボンニュートラルへの取り組みを目的とした国の機関です。2004年に設立され、石油・天然ガス、金属資源、石炭、地熱、洋上風力などの開発や備蓄、鉱害防止支援などの事業を行っています。
JOGMECは、鉱物資源をさまざまな国から調達できるようにするため、鉱山や工場の建設などに資金や技術を提供しています。また、鉱物資源が不足した場合に備えて、必要な量や期間を定め、鉱物資源を備蓄しています。
特にリスクの高い鉱物資源については、より多くの備蓄を行い、鉱物資源の流通を安定させるために、他国とも協力しています。また、無駄なく鉱物資源を活用するために、積極的に
- リサイクル・省資源
- 代替材料の技術開発
- 人材育成
などに取り組んでいます。
アメリカのレアメタル確保への取り組み
アメリカは2020年9月に、レアメタルなどの重要な鉱物資源の国内生産や調達を促進することを目指して、「アメリカの経済安全保障に関する臨時執行命令」を発令しました。この法令は、アメリカがレアメタルなどの鉱物資源に関して自立的で安全な立場を確保しようとするもので、中国との経済的・技術的・安全保障的な競争※が激化する中で出されました。
EUのレアメタル確保への協力体制
EUは2020年9月に、レアメタルなどの戦略的な鉱物資源の確保に向けて協力することを決め、「欧州原材料アライアンス(European Raw Materials Alliance:ERMA)」という組織を発足させました。この組織の目的は、気候変動対策やデジタル化対策に必要な「重要な原材料」の供給網を強化し、輸入依存度を低減することです。
特にレアメタルについては、EUは現在、その9割以上を中国からの輸入に頼っており、経済安全保障上のリスクが高まっています。
中国のレアメタル市場での影響力
中国は、世界で最も多くのレアメタルを生産しており、レアメタル市場において強い影響力を持っています。しかし、中国は過去にレアメタルの輸出を制限したことがあり、これによって世界のレアメタル市場が混乱したことがあります。また、中国がレアメタルの価格を独占的に操作することもあり、これによって世界のレアメタル市場に不安定要素が生じることがあります。
日本と他国との鉱物資源開発での協力関係
インド、ベトナム、モンゴル、ボリビアなどは日本との間で鉱物資源開発における協力に合意しており、日本企業が採掘や製錬に参画しています。
ZEV規制が私たちの生活に与える影響は?
今後のZEV規制によって、私たちの生活には次のような影響が出ることが考えられます。実際の影響は国や地域、自動車メーカーによって異なるため、一概には言えませんが、参考までに確認しておきましょう。
電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)の普及
ZEV規制によって、自動車メーカーはより多くのEVやPHEVを販売する必要があります。これによって、消費者はより多くの選択肢を得ることができます。
新しい技術の開発
ZEV規制に対応するため、自動車メーカーは新しい技術の開発に取り組む必要があります。これによって、消費者はより先進的な技術を搭載した車両を手に入れることができます。
環境に配慮した運転の促進
ZEV規制によって、環境に配慮した運転がより一般的になることが期待されます。EVやPHEVの普及によって、排出ガスの削減や騒音の低減などが実現されるため、より多くの人々の環境に配慮した運転を促進することができます。
車両購入などのコストの増加
ZEV規制によって、自動車メーカーはEVやPHEVの開発や販売促進に多額のコストを負担する必要があります。そのため、車両の販売価格や修理価格が高くなる可能性があります。
ガソリン車やディーゼル車の減少
ZEV規制によって、ガソリン車やディーゼル車の販売が減少することが予想されます。これによって、ZEV規制が採用される国や地域では、これらの車両を手に入れる機会が減る可能性があります。
【ZEV規制に備えて】私たちにできること
今後のZEV規制に対応するため、私たちができることは何でしょうか?代表的な例を見ていきましょう。
自動車の買い替えにエコカーを検討する
ZEV規制に備えるためには、一般人がエコカー(ゼロエミッション車)の購入や利用を積極的に検討することが重要です。
省エネに取り組む
私たちが省エネに取り組むことで、ZEVのエネルギー源の需要や供給にかかる環境負荷を低減することができます。省エネによって節約された電力や水素などのエネルギー源はZEVの動力として利用することができ、省エネによって節約されたコストをZEVの購入や維持に投資することができます。
再生可能エネルギーの利用を増やす
太陽光や風力などの再生可能エネルギーの利用を増やすことで、エネルギーの持続可能性を高めることができます。自宅やビジネスでの再生可能エネルギーの導入を検討してみましょう。
持続可能な交通手段の選択
公共交通機関の利用や自転車・徒歩などの持続可能な交通手段の選択を積極的に行うことで、車の利用によるエミッション※を削減することができます。
環境に配慮した生活スタイルの選択
エネルギーや鉱物資源は有限であり、効率的な利用が重要です。リサイクルや廃棄物の適切な処理、省エネルギーな暖房・冷房の利用、エコバッグの使用など、環境に配慮した生活スタイルを選択しましょう。
国際的な協力関係の重要性を理解する
鉱物資源開発においては、日本と他国との協力関係が重要です。鉱物資源の需要が高まる中で、持続可能な開発や供給のためには、他国との協力や国際的なルールの整備はもちろんのこと、その重要性を私たちが理解することも大切です。
経済成長と環境問題のバランスを考える
私たちは、ZEV規制のメリットやデメリットを理解し、自分自身の価値観やライフスタイルに合わせて適切な選択をすることが重要になります。また、ZEV規制に関する政策や情報にも関心を持ち、自分の意見や提案を発信することも大切です。
最後に、ZEV規制とSDGsの関係を確認しましょう。
ZEV規制とSDGs

SDGsとは、「持続可能な開発目標」のことです。17の目標で構成され、私たちが住む地球が、今後も健康で豊かな環境であり続けるために、世界中の人々が協力して取り組むべきことや方向性を示しています。その中でも、ZEV規制と関係性が深いSDGsの目標は以下の通りです。
目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」
ZEV規制によって、排出ガスや騒音の低減、エネルギー効率の向上が促進され、クリーンで持続可能な交通システムの実現に貢献します。また、エネルギーの持続可能な利用を促進することで、地球環境の保全や、貧困削減など、他のSDGsの達成にもつながります。
目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」
ZEV規制によって、電気自動車やプラグインハイブリッド車を製造する企業が増え、それに伴って充電器やバッテリーの開発など、新たな産業が生まれることが期待されています。また、電気自動車やプラグインハイブリッド車の普及によって、石油などの化石燃料に依存する産業から、より持続可能なエネルギー源への転換が進むことも期待されています。
目標11「住み続けられるまちづくりを」
ZEV規制によって、都市や地域の環境負荷を軽減し、住み続けられるまちづくりを進めることができます。同時に、より快適で健康的な都市環境を実現することで、住民の生活の質を向上させることにもつながります。
目標12「つくる責任つかう責任」
ZEV規制によって、資源の効率的な利用や環境への負荷の軽減が可能となります。また、クリーンなエネルギーを使用することで、大気汚染や温室効果ガスの排出を削減することもできます。
目標13「気候変動に具体的な対策を」
伝統的な車に比べて、電気自動車やプラグインハイブリッド車は電気を使用するため、燃料として石油をほとんど使わず、排出される二酸化炭素の量も少なくなります。これによって、大気中に放出される二酸化炭素の量を減らし、地球温暖化に対する具体的な対策を進めることができます。
あなたも日々の生活の中でSDGsに取り組むことができます。例えば、エコバッグを使ったり、自転車や公共交通機関を利用したりすることは、地球環境を守ることにつながります。
SDGsは、私たちだけでなく、未来の世代にも良い影響を与えます。だからこそ、私たちは今、SDGsに取り組むことが大切なのです。
>>各目標について詳しく解説した記事はこちらから
まとめ:ZEVの普及は地球温暖化対策として有効!
ZEV規制について抑えておくべきポイントをまとめます。
- EV・PHV・FCV・水素エンジン自動車などエコカーの普及を促進するための規制
- 目的は、地球温暖化に影響を与える温室効果ガスの排出量を削減すること
- 新たな産業の創出や持続可能なエネルギー源への転換が期待される
- 石油などの化石燃料に依存する産業から脱却し、持続可能な社会の実現に貢献する
これらのポイントを知っておくことで、ZEV規制の目的を理解し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みについて考えることができます。
日本ではZEV規制については、まだ確定事項ではありませんが、ZEVの普及は重要であり、SDGsの目標達成にも貢献します。
消費者としても、現在では以前より補助金や低価格モデルの登場でZEVを選択しやすくなっていますし、年々種類や利用できる環境は広がっています。あなたも、自動車を購入するときは、ZEVを選択することも検討してみてはいかがですか?
ZEVへの乗り換えや利用を積極的に検討することで、自動車の脱炭素化に貢献することができます。大切なのは、あなたの立場や状況に応じた具体的な行動を考え、無理のない範囲で実践することです。
ZEVだけにとどまらず、SDGsの目標や社会問題に関心を持ち、正しい判断ができるように、常に学び続けましょう!
<参考・引用文献>
*1)ZEV規制とは
経済産業省『2030年に向けたトヨタの取組みと課題』(2020年9月)
東京都環境局『ZEVの導入』(2020年7月)
東京都環境局『ゼロエミッション・ビークルの普及に向けて』
環境省『Let’s ゼロドラ!!』
JETRO『米国の自動車環境規制をめぐる動向』(2021年7月)
JETRO『米カリフォルニア州大気資源委員会、中型・大型トラックのゼロエミッション化を促進する規制を承認』(2023年5月)
JETRO『米環境保護庁が自動車排ガスの新規制案を発表、2032年までに2026年比56%の削減を要求』(2023年4月)
EV車のメリットとデメリット・充電の仕組み、今後電気自動車は日本で普及するのか?
水素自動車とは?仕組みや将来性、普及しない理由、販売しているメーカーは?
経済産業省『日本の自動車産業の国内販売・輸出・海外生産』p.21(2022年4月)
環境省・経済産業省・国土交通省『次世代モビリティガイドブック 2019-2020』
*2)ZEV規制のクレジットとは
一般社団法人 次世代自動車振興センター『ZEV規制』
JETRO『米環境保護庁、カリフォルニア州によるトラックの排出削減規制を許可』(2023年4月)
一般社団法人 次世代自動車振興センター『ZEV規制』
*3)世界のZEV規制の現状
国土交通省・経済産業省『欧州における規制の検討状況について』
JETRO『EU、2035年の全新車のゼロエミッション化決定、合成燃料に関する提案が焦点に(EU)』(2022年10月)
JETRO『欧州委、2035年までに全ての新車のゼロエミッション化提案』(2021年7月)
国土交通省・経済産業省『欧州における規制の検討状況について』
日本経済新聞『EU、エンジン車容認で合意 合成燃料限定で35年以降も』(2023年3月)
日経XTECH『脱炭素よりも自国の利益を優先、欧州ZEV法案とドイツ提案の「本音」』(2023年5月)
日経XTECH『米カリフォルニア州のエンジン車販売禁止、顧客視点欠く指摘も』(2020年9月)
JETRO『電気自動車の普及で製造業振興と環境対策を狙うインド』(2022年3月)
JETRO『IEA報告書、EV普及はアジア大洋州で遅れ』(2022年06月)
RETUTERS『Indian businesses seek government support to meet 2030 EV target』(2021年10月)
日経XTECH『中国・環境規制強化の衝撃』(2020年6月)
*4)日本のZEV規制の現状
資源エネルギー庁『自動車の“脱炭素化”のいま(後編)~購入補助も増額!サポート拡充でZEV普及へ』(2022年11月)
一般社団法人次世代自動車振興センター (cev-pc.or.jp)
一般社団法人次世代自動車振興センター『次世代自動車振興センターについて』
日本経済新聞『トヨタの脱炭素、規制強まる欧州から 35年全車排出ゼロ』(2021年12月)
日経ビジネス『急加速のEVシフトに潜む5つの課題』(2017年9月)
日経XTECH『EVに逆風か、新規制「ユーロ7」はタイヤ粉じんも対象』(2023年1月)
資源エネルギー庁『自動車の“脱炭素化”のいま(前編)~日本の戦略は?ZEVはどのくらい売れている?』(2022年10月)
*5)日本政府の取り組み
資源エネルギー庁『自動車の“脱炭素化”のいま(後編)~購入補助も増額!サポート拡充で電動車普及へ』(2022年11月)
経済産業省『蓄電池産業戦略』p.1(2022年8月)
経済産業省『蓄電池産業戦略』p.26(2022年8月)
日本経済新聞『蓄電池、生産能力10倍に 経産省が財政支援案』(2022年4月)
*6)ZEV規制の問題点と課題
JETRO『米カリフォルニア州、課題はEV充電器増設、2030年までに120万台以上必要に』(2021年9月)
日経ビジネス『見過ごされるEV普及への課題、2030年代前半までの「デスバレー」』(2021年12月)
資源エネルギー庁『日本の新たな国際資源戦略 ③レアメタルを戦略的に確保するために』(2020年7月)
経済産業省『レアーアース対策』
外務省『金属鉱物資源をめぐる外交的取組~ベースメタルとレアメタルの安定確保に向けて』(2011年2月)
*7)ZEV規制の今後の動向
経済産業省『自動車分野のカーボンニュートラルに向けた国内外の動向等について』p.6(2023年4月)
JOGMEC『金属鉱物資源開発の推進及び脱炭素化』
経済産業省『自動車分野のカーボンニュートラルに向けた国内外の動向等について』p.10(2023年4月)
THE WHITE HOUSE『Executive Order on America’s Supply Chains』(2021年2月)
MUFG『原材料の戦略的な確保を図る EU~欧州原材料同盟(ERMA)構想の特徴と問題点』(2021年8月)
ERMA『European Raw Materials Alliance』
ERMA『About us』
JOGMEC『JOGMECカーボンニュートラル・イニシアティブ概要』
JOGMEC『JOGMECカーボンニュートラル・イニシアティブ』(2022年11月)
この記事を書いた人
松本 淳和 ライター
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。





















