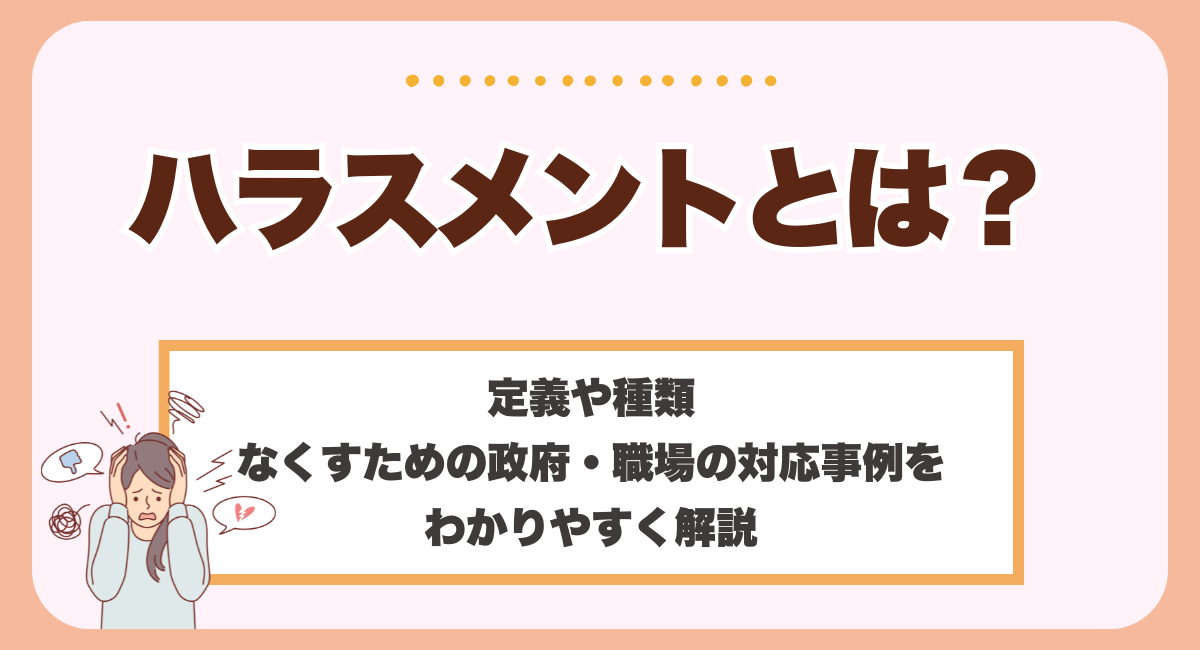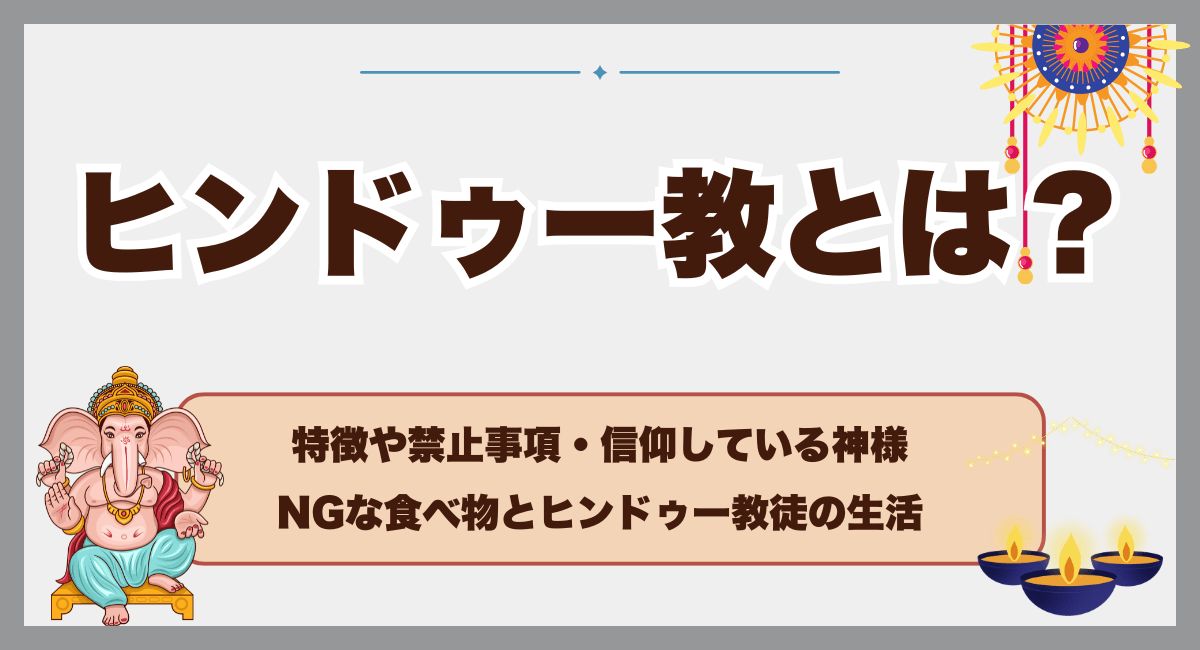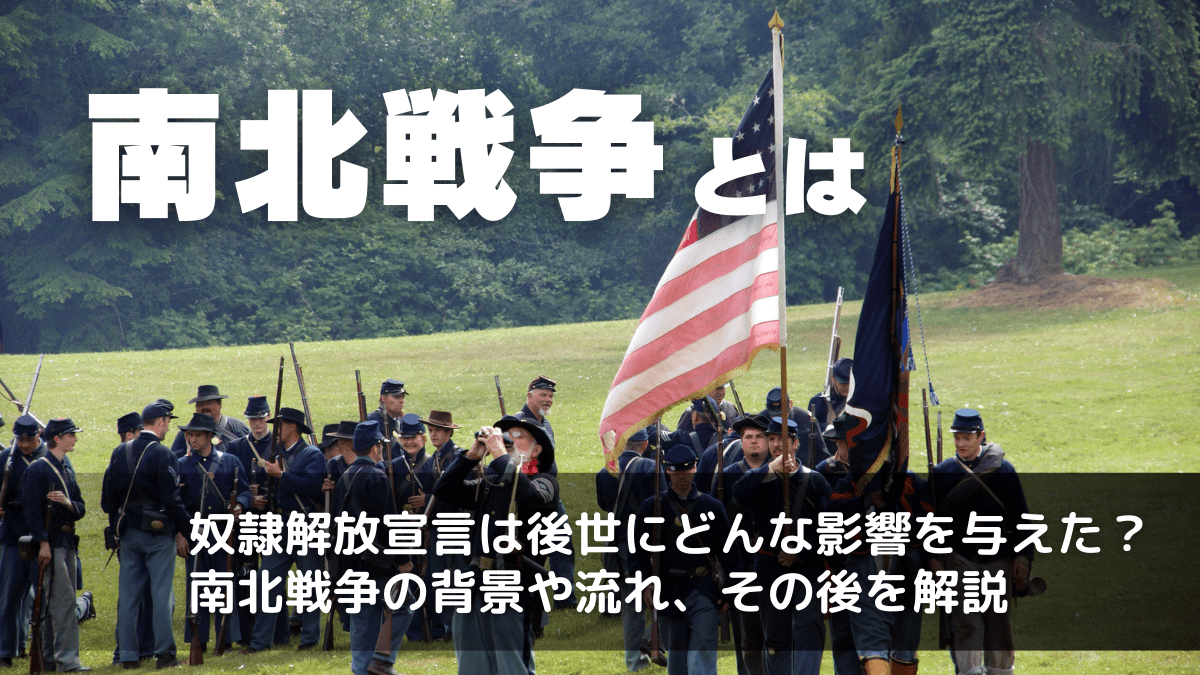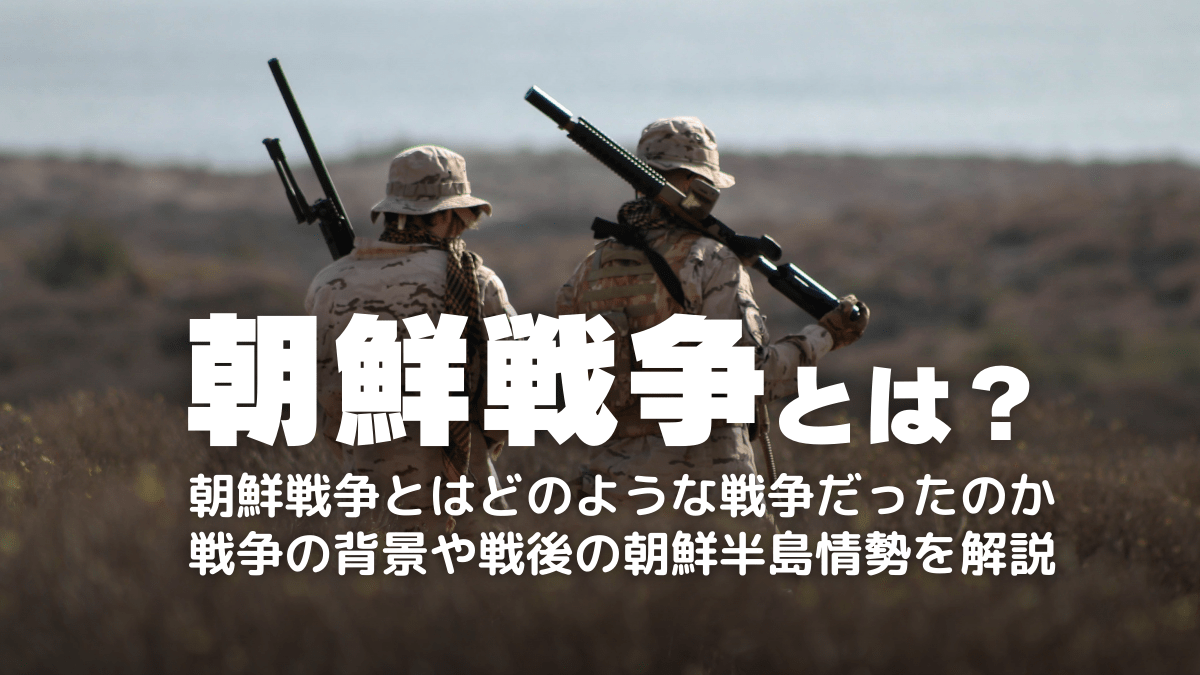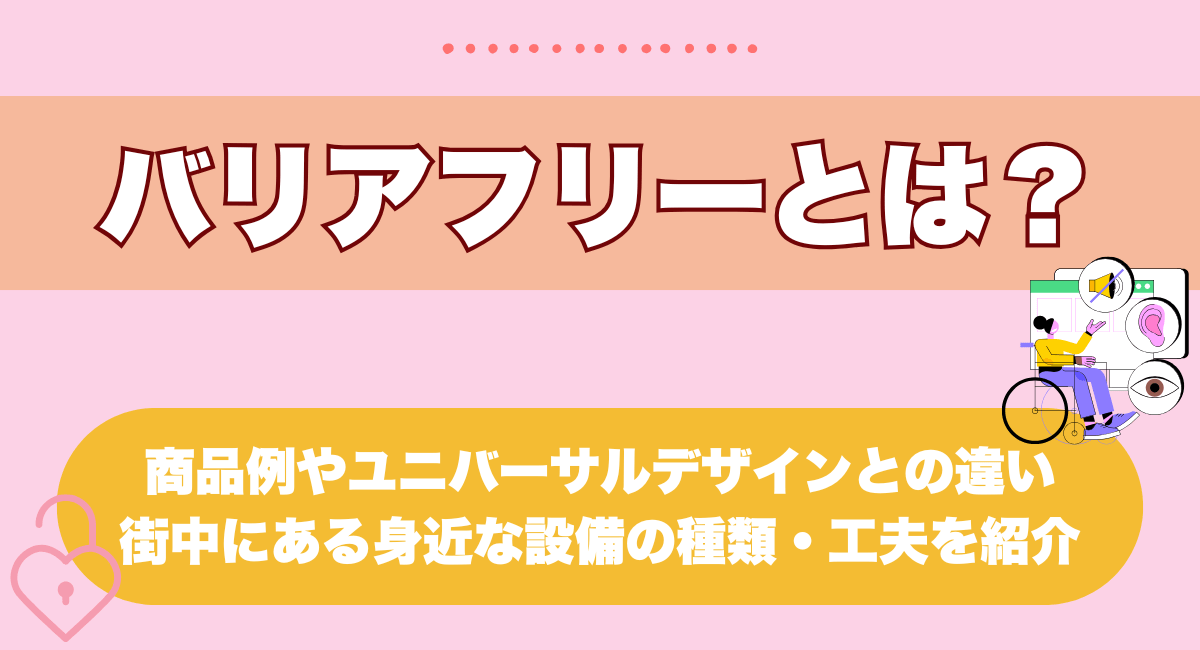現在の社会では、性的マイノリティへの認知や理解が進み、平等な権利を求める活動も活発化しています。しかし、日本では依然として世間の無知や無理解が多く、性的マイノリティへの偏見や差別が根強く残っています。その状況を改善する鍵となるのが「ally/アライ」と呼ばれる支援者の存在です。まだ日本ではなじみの薄いアライですが、その役割を理解し、自らもその一員となることは、社会全体にとって重要な意味を持つのです。
目次
ally(アライ)とは?名前の意味も解説
「アライ(ally/allies)」とは、LGBTなど性的少数者に理解と共感を示し、その権利を支援する人のことを指します。名前の由来は「連帯・同盟」を意味する英語の alliance(アライアンス) にあり、差別や偏見に立ち向かう姿勢を表す言葉として使われています。
この言葉は1988年ごろ、北米の学生や教職員の間で「異性愛者がゲイやレズビアンの市民権獲得を支援するネットワーク」の中で広まりました。現在では、LGBTQ+当事者ではない、いわゆる性的マジョリティの立場から、差別解消や社会的理解を後押しする支援者全般を「アライ」と呼ぶのが一般的です。
スラングではなく、連帯の意思を表すポジティブなカタカナ語として浸透しています。
ally(アライ)はスラング?カタカナで読み方を紹介
「ally(アライ)」はスラングではなく、LGBTなど性的少数者の権利や社会的理解を支援する人を指す正式な言葉です。日本語ではカタカナで「アライ」と表記され、英語の「アライ(ally)」の読み方をそのまま用いています。
語源は「同盟」や「連帯」を意味する英語の alliance(アライアンス) にあり、差別や偏見に反対し、共に行動する姿勢を示す言葉として使われています。1980年代後半に北米で誕生した用語であり、当初は異性愛者がLGBT当事者の権利向上を支援する立場として使われ始めました。
現在では、性的マイノリティに共感し支援する非当事者(マジョリティ)全般を指す広い意味で用いられています。カジュアルな言葉ではありますが、社会運動や教育現場でも広く使用されており、公式な用語といえます。
そもそもLGBTQ+とは
LGBTQ+という言葉はすでに広く知られるようになりましたが、改めてその意味をおさらいしておきましょう。LGBTQ+はあらゆる性的マイノリティを表す総称のひとつであり、
- Lesbian(レズビアン):性自認が女性で女性が性愛対象である人
- Gay(ゲイ):性自認が男性で男性が性愛対象である人
- Bisexual(バイセクシュアル):性愛対象が女性・男性両方である人
- Transgender(トランスジェンダー):出生時に割り当てられた性とは性自認が違う人
- Questioning(クエスチョニング):性的指向や性自認が決められない・分からない人
- +:アセクシュアルなど上記のカテゴリに当てはまらず、性的マジョリティとも違う性的指向や性自認を持つ人
などに分けられます。また、こうした性的マイノリティ全般を包括するものとして、クィア(Queer)というカテゴリーを使うこともあります。
そしてこうした性的マイノリティの割合は、さまざまな調査により人口の8〜10%程度存在することがわかっています。
ally(アライ)=性的マジョリティ?
LGBTQ+当事者を理解し、支援する性的マジョリティの人々だけがアライではありません。
- レズビアンの人がゲイやトランスジェンダーへのアライになるなど、当事者間の連帯
- Black Lives Matter運動や#MeToo運動など人種や性別の差別に対する抗議
などのように、あらゆる形で当事者ではない人々が当事者に寄り添い、支援する動きも見られます。こうした連帯を表明する当事者ではない人もまた、アライと呼ばれるようになりました。
本記事では主にLGBTQ+に対する理解者/支援者をアライとして取り上げます。しかし、現在の意味でのアライとは、公正な社会の実現を心から望み「誰もが誰かのアライになる」ことで、特定の人々が直面する困難や差別を解消する活動を理解し、支援する人と考える方がいいでしょう。
ally(アライ)が必要な理由
私たちの社会では、LGBTQ+やマイノリティの人々が生きやすい世の中をつくるために、一人でも多くの人たちがアライであることが望まれています。それはなぜなのでしょうか。
当事者の心理的安全性が高まる
アライの存在が重要なのは、LGBTQ+当事者の心理的安全性が確保されやすくなるからです。
LGBTQ+当事者の多くは、周りの人々が自分たちに対する偏見や差別感情を抱いているのではと不安を覚え、誰にも悩みを相談できず孤独を感じている人が多いといわれます。
また、調査によると社内でLGBTQ+当事者の存在を認識していない企業は7割にも上り、当事者たちは「いないと思われていること」に不安や生きづらさを抱えています。
しかし、身近にアライという存在がいれば当事者のメンタルヘルスに良い影響を与え、孤立感が和らぎます。カミングアウトもしやすくなり、人間関係も良くなります。
世論を動かす影響力を持つ
アライがLGBTQ+当事者の思いを代弁することで、世間の無理解や偏見を無くし社会変革を促しやすくなります。
当事者自身が勇気を出して社会や組織の中で声を上げても、周囲にLGBTQ+への理解がないと聞き入れてもらうことは困難です。
しかし、マジョリティにアライがいて、彼らが「仲間のため、同僚のため、困っている誰かのため」に共に行動することは、周囲を動かす大きな力となります。
その結果、近くにいる個人の意識が変わり、周囲の組織が変わります。
現在、新しい取り組みやルールづくりを進め、積極的にLGBTQ+施策を行っている企業や組織で主導しているのはほとんどがアライです。
最近では当事者とアライの協力によって世論が動き、パートナーシップ制度を導入する自治体も増加しています。アライの増加は、社会全体に新しい風潮をもたらすのです。
非当事者にとっても良い影響をもたらす
アライが増えてLGBTQ+が生きやすい世の中になることは、非当事者であるマジョリティにとっても良い影響を与えます。
ダイバーシティの推進、多様な人々への配慮は、個人の権利を尊重することでもあります。
そこでは、LGBTQ+や障害者への差別はもとより、人権を無視した労働環境やハラスメントなども許されません。
調査によれば、ダイバーシティ意識の高い企業では当事者だけでなく、非当事者にとっても勤続意欲が高くなることがわかっています。アライの存在は、LGBTQ+当事者だけでなく、すべての人にとっても生きやすい世の中になるのです。
ally(アライ)になるために私たちができること
私たちがアライになるためには特別な資格や技能は何もいりません。LGBTQ+も含む、すべての人たちの価値観を尊重し、向き合う姿勢があれば、誰でもアライであると表明していいのです。そして、良きアライであるために私たちができることは、あとほんの少しだけ前に踏み出すことです。
知る
まず必要なのは、LGBTQ+やマイノリティについて「知る」ことです。当事者がどんなことに悩み、何を求めているかを知ることから始まります。そのためには、
- 当事者と実際に会って交流を深める
- 本や資料、Webサイトなどから知識を深める
- 専門家から知識を得る
など、さまざまな方法で知見を広げていきましょう。
表明する
「自分はアライである」と周囲にわかるように表明することも大事な取り組みです。
そうすることによって、当事者はあなたを「自分を理解してくれる人、悩みを打ち明けられる存在」として認識し、心理的安全性や安心感を得ることができます。
また、周囲に表明することで、その他の非当事者ともLGBTQ+やアライについて話をするきっかけにもなります。具体的な表明方法としては、
- レインボーグッズや、アライであることを示すアイテムなどを身につける
- 普段からLGBTQ+やダイバーシティについてポジティブな話題を取り上げる
などがあります。
行動する
知識を得て、表明したら、行動に移すことが大事です。といっても、そこまで大げさに構えることはありません。まずは日々の生活の中でできることから始めましょう。具体的には
- LGBTQ+当事者が望まない言葉(ホモ、レズなど)を使わない
- 彼女・彼氏ではなく、恋人・パートナーなど、性別を特定しない言葉を使う
- 他人のLGBTQ+への誤解や差別的言動を指摘する
- LGBTQ+について周囲の人と話す
- レインボーパレードやイベントに参加する
- 当事者やアライの団体の活動を支援する、参加する
など、アライとして私たちができることは多岐にわたります。
ally(アライ)としての注意点
世の中にLGBTQ+へのアライが増えるのは好ましいことですが、一方では気をつけたいことがあります。それは「理解者・支援者」としての意識が強くなり過ぎるあまり、当事者を「助けてあげるべき存在」と見なしてしまうことです。
言うまでもなく、LGBTQ+やその他マイノリティの困難の背景にあるのはマジョリティ側に有利な社会構造です。当然、当事者たちは「かわいそうな存在」などではなく、「同等の権利を保障されるべき存在」です。
そうした構造を見落とした「助けてあげる」というニュアンスは、当事者にとって違和感を覚えるだけでなく、弱者と強者という好ましくない関係性を作ってしまいかねません。
アライとして当事者に寄り添う上では、そうした無意識の偏見にも気をつけるべきです。
ally(アライ)に関する日本の取り組み事例
ここでは、LGBTQ+を支援する団体・企業の中でも、特にアライとしての取り組みに力を入れている事例を紹介していきます。
認定NPO法人虹色ダイバーシティ
虹色ダイバーシティは、大阪に拠点を置く認定NPO法人です。
同法人は、調査研究や情報発信、LGBTQ+研修や企業向けコンサルティング、イベントや勉強会の企画など、あらゆる方法で性的マイノリティへの支援や啓発事業を行なっています。
アライを増やすための運動も継続的に行なっており、2020年には「LGBT & アライ サポートブック」を作成・販売することで、多くの職場・団体への普及を進めています。
【関連記事】虹色ダイバーシティ| 常設型のLGBTQセンターを拠点に、社会の課題を解決に導く
LGBT-Ally プロジェクト|OUT JAPAN
LGBT-Allyプロジェクトは、株式会社 アウト・ジャパンによる、より多くのアライを増やすための啓発プロジェクトです。
主な取り組みとしては、各地のPRIDEイベントなどでの企業の取り組み紹介、協賛企業とのイベントやパレードへの参加などで、参加企業には味の素や京セラ、ソフトバンクなど、国内の名だたる会社が名を連ねています。
同社ではその他にセミナーや研修の開催、LGBTQ+ツーリズム支援など、LGBTQ+への理解と権利拡充へ向けた取り組みも幅広く行なっています。
大阪ガス
大阪ガスでは、人権問題やLGBTQ+への取り組みをいち早く行い、性的指向や性自認についての差別禁止を打ち出しました。さらに、
- LGBTQ相談窓口の設置
- 社内理解の促進に向けた有識者講演会や勉強会・映画鑑賞会の開催
- アライステッカーの作成・配布
- 採用イベントでのアライの意思表明
など、LGBTQ+の当事者が活躍できる組織づくりに努めています。
さらに同社では、2024年4月から事実婚や同性パートナーに対し、法律上の配偶者と同じ福利厚生や社内制度が適用されるように規程を変えました。
同時にアウティングなどのハラスメントへの周知を改めて行うなど、LGBTQ+への理解促進を継続して行なっています。
野村ホールディングス
野村ホールディングスでは、リーマン・ブラザーズ証券のアジア拠点部門の継承を機に、LGBTQ+施策への取り組みを始めました。この時主導的役割を担ったのが、人材開発部の東由紀さんです。
東さんはすべての管理者研修にダイバーシティ研修を導入するなどLGBTQ+への啓発を進め、「アライになろう!」活動を推進してきました。
現在同社ではアライズ・イン・ノムラ・ネットワーク(ALLIES)と呼ばれる活動が行われています。これは
- LGBTQ+当事者を招いた講演会
- 本社や支店のカフェテリアに「アライになろう!」パンフレット設置
- 差別的な発言に対する指摘やLGBTQ+についての議論
などの取り組みを進めることで、社をあげてアライを増やす活動です。
ALLIESは同時に、国籍や人種、障害の有無などについても理解を深め、さまざまなマイノリティや社員一人ひとりが十分に活躍できる環境づくりを目指しています。
ally(アライ)に関するよくある質問
「アライ(ally)」という言葉を聞いたことはあるけれど、意味や役割がよく分からない…という方に向けて、よくある疑問をわかりやすく解説します。
アライと“理解しているつもり”の違いは?
「理解しているつもり」と「アライ」で最も違うのは、行動の有無です。単に「差別はよくない」「多様性は大切」と思うだけでは、当事者の支えにはなりません。アライとは、理解や共感を言葉にするだけでなく、実際に行動に移す人のことです。
たとえば、偏見的な発言を見過ごさない、正しい知識を学ぶ、当事者の声を聞いて職場や学校で発信する――そうした一歩がアライです。理解しているつもりでは、無意識にマイノリティの存在を“遠い問題”としてしまうことがあります。
アライは「誰もが生きやすい環境づくり」を自分ごととして考え、共に行動する姿勢を持つ人です。
アライとしてできる行動にはどんなものがある?
アライとしての行動は、日常の小さな気づきや配慮から始められます。たとえば、LGBTQ+に関する知識を学ぶ、差別的な言動に対して注意する、自分のSNSで多様性を尊重する発信をするなどが挙げられます。
また、職場や学校でジェンダー平等のための取り組みに参加したり、当事者が安心してカミングアウトできる雰囲気づくりに努めたりするのも有効です。アライは「完璧」ではなく、「学びながら支援する姿勢」が大切だとされています。
職場や学校でアライとしてできるサポートは?
アライとしてのサポートは、特別なことではありません。日常の小さな配慮や発信から始められます。職場であれば、LGBTQ+当事者が安心して働けるよう、性別を限定しない呼び方(彼氏・彼女ではなく「パートナー」)を使う、差別的な冗談や発言を聞いたときに軽くでも注意する、LGBTQ+に関する研修やイベントに積極的に参加するなどです。
学校であれば、いじめや偏見を見過ごさず、多様性をテーマに話す機会をつくることも立派な支援です。重要なのは、当事者を特別扱いせず、誰もが尊重される空気をつくること。小さな行動が、周囲の安心と信頼を広げていきます。
アライを名乗ることで気をつけるべきことは?
アライを名乗ることは善意の表れですが、「名乗るだけで満足しないこと」が大切です。当事者にとっては「本当に信頼できる人かどうか」が非常に重要であり、行動が伴わなければ逆効果になることもあります。
また、無理にカミングアウトを促す、当事者の代弁をしてしまうなど、善意が裏目に出るケースもあります。自分の考えを押し付けるのではなく、当事者の声に耳を傾け、常に謙虚な姿勢で関わることが、信頼されるアライへの第一歩です。
LGBTQ+当事者との違いや関わり方は?
アライはLGBTQ+当事者ではなく、彼らを支援・理解しようとする立場です。自分の経験では語れないことも多いため、当事者の声を尊重することがとても大切です。
たとえば、カミングアウトされたときに驚いた表情を見せたり、話を広めたりするのは信頼関係を損ねる原因になります。アライとしては「相手の立場に立って考える」ことが重要で、聞き役に徹する姿勢や、必要に応じて支援情報を紹介するなどの対応が望まれます。対等な関係を築くことが何よりの支援です。
ally(アライ)とSDGs
SDGs(持続可能な開発目標)ではLGBTQ+への具体的言及はありませんが、性的マイノリティの抱える問題はSDGsとも大きく関連してきます。同時にアライであることは、誰一人取り残さないというSDGsの理念とも合致します。
この目標で掲げられているのは女性および女児への差別撤廃や権利の確保です。一方ではジェンダー平等も掲げられており、多くの企業や自治体もLGBTQ+施策への取り組みと目標5を関連づけています。
その他にも、アライとしてLGBTQ+やマイノリティと連帯することは
- 目標1「貧困をなくそう」=マイノリティは差別や排除などで安定した職に就くことが困難
- 目標3「すべての人に健康と福祉を」=LGBTQ+は差別や制度の不備で適切な医療・福祉を受けられない場合がある
- 目標10「人や国の不平等をなくそう」
などの目標を達成する上で、大きな力となってきます。
>>各目標に関する詳しい記事はこちらから
まとめ
多様な背景を抱えた人々が誰でも生きやすい社会を実現するには、多数派である当事者以外の人々の理解と協力が不可欠です。
そのために必要なのが、社会に一人でも多くのアライが増えていくことです。
本文でも述べましたが、たとえLGBTQ+でなくてもアライになることは決して難しいことではありません。大事なのは誰かの困難を理解したい、共に歩みたい、という気持ちです。誰もが誰かのアライになることで、個人も、企業も、社会もより良い方向へと進んでいくことができます。これを読んだあなたも、今日からアライになってみませんか。
参考文献・資料
ALLYになりたい わたしが出会ったLGBTQ+の人たち:小島あゆみ著/かもがわ出版,2021年
職場のLGBT読本:柳沢正和・村木真紀・後藤純一著/実務教育出版,2015年
法律家が教えるLGBTフレンドリーな職場づくりガイド:LGBTとアライのための法律家ネットワーク(LLAN)著:藤田直介・東由紀編著/法研,2019年
LGBT-Ally プロジェクト|OUT JAPAN Co.,Ltd.
認定NPO法人 虹色ダイバーシティ | LGBTがいきいきと働ける職場づくりをサポートします (nijiirodiversity.jp)
「LGBT&アライサポートブック」発売!
データと事例で「アライ」がわかる : 知る・表明する・行動する : what we can do as ally_風間孝 監修 京都市文化市民局共生社会推進室 2023.3
本田杏子 社会運動から Ally/ アライを再考する ―東京レインボープライドを事例に― 社会デザイン学会 学会誌 2023 Vol.15
「LGBTQ+アライのためのハンドブック」導入、無償公開!|沖縄コカ・コーラボトリング 沖縄限定アクアバリュー・茶流彩彩 さんぴん茶 (ccbc.co.jp)
職場 × 多様性 | NOMURA (nomuraholdings.com)
事実婚・同性パートナーへの社内制度適用について (osakagas.co.jp)
この記事を書いた人
shishido ライター
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。