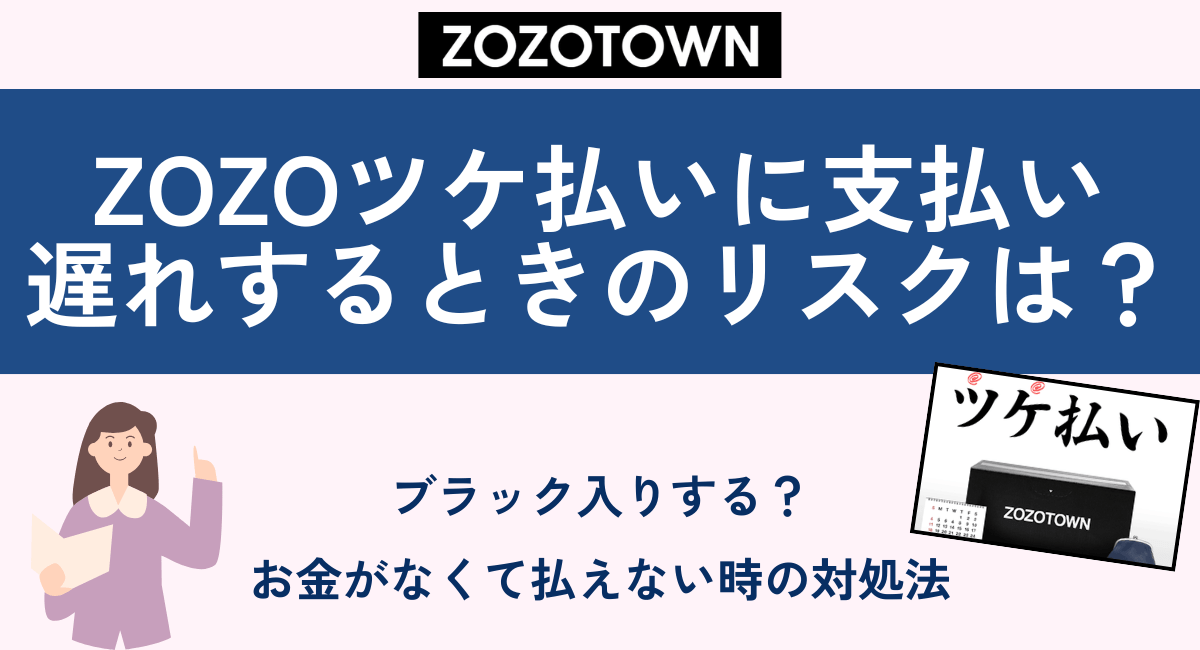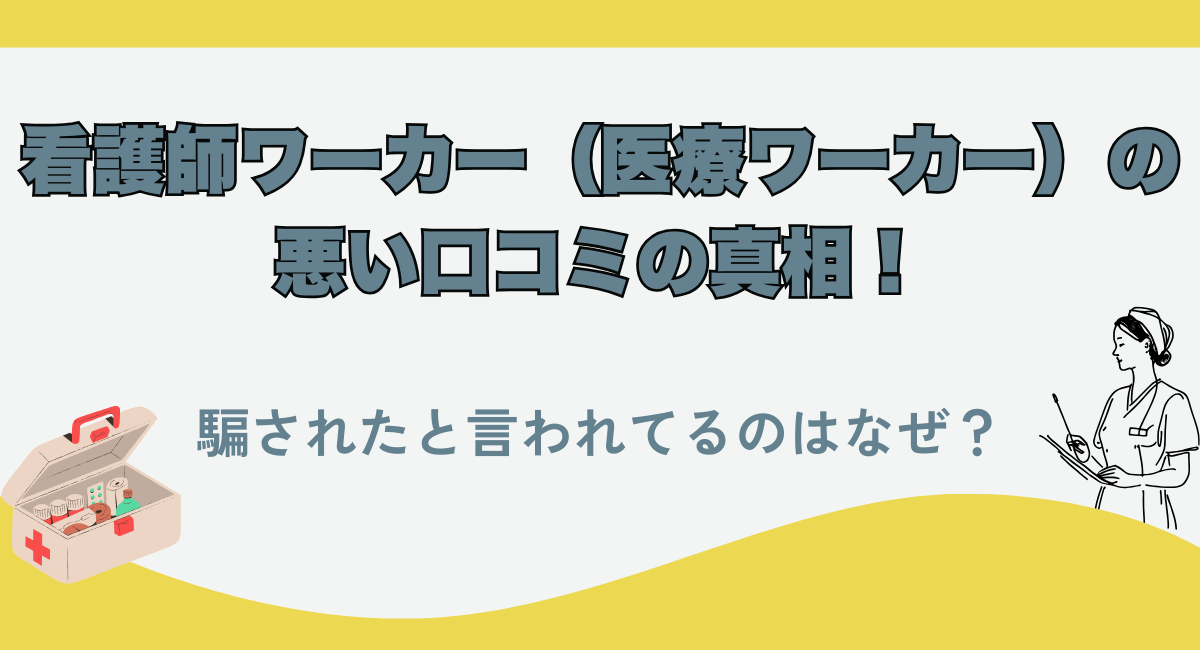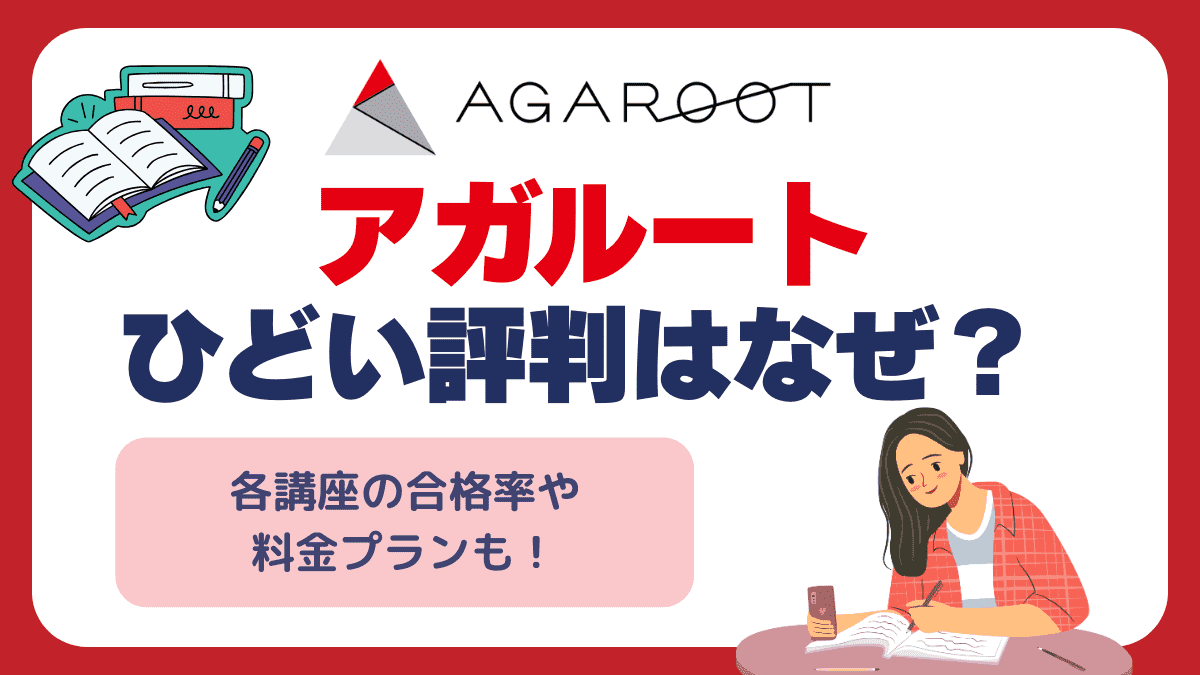睡眠不足は健康に悪影響を及ぼすことは、誰でも経験から知ってはいると思います。しかし、忙しさに睡眠時間を犠牲にしていませんか?
睡眠は私たちの健康にとって非常に重要です。十分な睡眠をとることで、体が休息を取り、回復する時間を確保することができます。
また、睡眠不足は免疫力の低下やストレスの増加、学習能力の低下など、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。
「思うように睡眠時間を取れない」という人のために、質の高い睡眠をとるためのポイントもわかりやすく解説します。
最新のスリープテックについてはこちらの記事を参照ください。→スリープテックとは
目次
まずは睡眠について知ろう

人間は、1日のうちの約3分の1を睡眠で過ごしています。睡眠は、脳や体の疲れを回復し、成長や発達を促すために欠かせません。
睡眠とは一般的に、目が閉じ、意識が失われ、体を休ませる状態のことです。睡眠中は、脳や体はさまざまな変化を起こしています。
睡眠の種類
睡眠には、大きく分けて2つの種類があります。
レム睡眠
レム睡眠は、夢を見たり、記憶の整理をしたりする睡眠です。
- 目が大きく動く
- 体はほとんど動かない
- 呼吸が浅くなり、脈拍が速くなる
- 筋肉が弛緩する
- 夢を見る
などがレム睡眠の特徴です。レム睡眠は、脳が活発に活動する睡眠です。
また、夢を見ることで、感情や不安を解消する効果もあると考えられています。
レム睡眠は、睡眠のサイクルの中で、約90分おきに訪れます。レム睡眠の割合は、幼児期が最も多く、成人期になると減少します。
ノンレム睡眠
ノンレム睡眠は、体の回復や成長を促す睡眠です。
- 目が動かない
- 体は動く
- 呼吸が深くなり、脈拍が遅くなる
- 筋肉が緊張する
などがノンレム睡眠の特徴で、脳や体の疲れを回復し、成長ホルモンの分泌を促します。このノンレム睡眠は、さらに3つの段階に分けられます。
- N1:浅い睡眠(入眠後すぐに訪れる、最も浅い睡眠)
- N2:中程度の睡眠(N1より深い睡眠で、筋肉の緊張が緩み、呼吸が規則的になる)
- N3:深い睡眠(最も深い睡眠で、脳波※が非常にゆっくりと波打つようになる)
質の高い睡眠をとるためには、毎日、ノンレム睡眠を十分に確保することが大切です。
「レム」とは?
レム睡眠・ノンレム睡眠の「レム」とは、Rapid Eye Movementの略で、日本語では「急速眼球運動」と訳されます。レム睡眠中は、目が大きく動くことから、この名前が付けられました。
逆に、眼球運動のない睡眠がノンレム睡眠というわけです。
睡眠習慣
もう少し踏み込んで、睡眠について理解を深めていきましょう。
睡眠習慣とは睡眠の、
- 量や質
- タイミング
- 環境
などを指します。睡眠習慣を整えることで、質の高い睡眠をとり、健康を維持することができます。
睡眠習慣を整えるポイント
睡眠習慣を整えるためには、
- 毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる
- 睡眠前にカフェインやアルコールを控える
- 寝る前にスマホやパソコンの画面を見ない
- 寝室を暗くして、静かにする
- 適度な運動をする
などが効果的です。良い睡眠と健康を維持するために、日頃から睡眠習慣を意識してみてください。
【眠りのメカニズム】
睡眠障害
【不眠症】
睡眠障害とは、睡眠の質や量が正常に保てなくなる病気です。睡眠不足や眠りづらさなどの症状を引き起こし、日常生活に支障をきたす可能性があります。
- 不眠症:眠りにつきづらい、途中で目が覚めてしまう、睡眠の質が悪い
- 過眠症:日中に強い眠気が襲ってくる、意図せず眠ってしまう
- 睡眠時無呼吸症候群:睡眠中に呼吸が止まってしまう
- レム睡眠行動障害:夢を見ているときに、実際に行動を起こしてしまう
- ナルコレプシー:昼間に突然眠気に襲われる、夢を見ている状態で行動を起こしてしまう
これらは、代表的な睡眠障害の例で、
- ストレス
- 生活習慣の乱れ
- 病気
- 薬の副作用
などが原因として考えられます。睡眠障害の症状は、人によって異なるので、もしも睡眠障害の症状に心当たりがある場合は、早めに医療機関を受診するようにしましょう。
【睡眠時無呼吸症候群】
次の章では、睡眠の間にあなたの体で起きていることに注目してみましょう。*1)
睡眠中に私たちの体で起きていること
睡眠中に、私たちの体で一体何が起きているのか知っていますか?実は、睡眠中には、私たちの健康維持に重要な、さまざまな働きが行われています。
成長ホルモンの分泌
成長ホルモンは、睡眠中に最も多く分泌されます。特に、深い睡眠のときに多く分泌されます。
十分な睡眠とバランスの良い食事、適度な運動を心がけることで、健康的に成長することができます。
【睡眠とホルモンの分泌】
細胞の修復
細胞は、日中は活動して傷ついたり、老化したりしています。睡眠中は、これらの傷や老化した細胞を修復する時間になります。
睡眠中に細胞を修復する働きをしているのは、成長ホルモンです。成長ホルモンは、脳の下垂体で分泌されるホルモンで、骨や筋肉の成長を促進する働きがありますが、細胞の修復にも関わっています。
脳の整理・記憶の定着
睡眠中は、脳が日中に得た情報を整理して、長期記憶に保存します。睡眠中に脳の整理が行われないと、日中に得た情報がうまく整理されず、忘れやすくなってしまいます。
そのため、十分な睡眠をとることは、記憶の定着のために大切です。これには大きく分けて2つのプロセスがあります。
①記憶の統合
日中に得た情報を、関連性のあるグループにまとめるプロセスです。例えば、学校で習った歴史の出来事や、友達と話した内容などをまとめて記憶に保存します。
②記憶の固定化
整理された情報を、長期記憶に保存するプロセスです。このプロセスによって、記憶が定着し、忘れにくくなります。
免疫力の向上
睡眠により、免疫力が向上します。これには以下の2つの理由があります。
①免疫細胞の活性化
睡眠中は、免疫細胞の活性化が促されます。免疫細胞とは、ウイルスや細菌などの病原体から体を守る細胞です。睡眠中は、これらの免疫細胞が活性化し、病原体と戦う準備を整えます。
②ストレスの軽減
ストレスは、免疫力を低下させる原因の1つです。睡眠中は、ストレスが軽減され、免疫力アップにつながります。
睡眠不足になると、免疫細胞の活性化が抑制され、ストレスも溜まりやすくなります。
睡眠は、私たちの体と心を健康に保つために欠かせないものです。十分な睡眠をとって、元気に毎日を過ごしたいですね!*2)
睡眠が健康に与える影響は?
では、睡眠が不足すると健康にどのような影響を与えるのでしょうか?
睡眠不足になると…
睡眠不足は、身体的、精神的な健康に悪影響を及ぼすことがあります。睡眠不足の影響として、具体的には、
- 集中力や注意力の低下
- 記憶力や学習力の低下
- 判断力の低下
- イライラや不安感
- 体調不良
- うつ病や認知症のリスク増加
などが、引き起こされると言われています。
睡眠と生活習慣病の関係
【睡眠と生活習慣病の関係】
生活習慣病は、私たちの生活習慣によって引き起こされる病気のことです。例えば、高血圧や糖尿病などが生活習慣病の代表的な病気です。
睡眠不足は、生活習慣病のリスクを高めることが知られています。具体的には、
- 交感神経が優位になり、血圧や血糖値が上昇する
- 食欲を増進させるホルモンが分泌され、肥満になりやすくなる
- 免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなる
などの影響により、睡眠不足によって生活習慣病のリスクが高まります。
【関連記事】NCDs(非感染性疾患)とは|生活習慣病との違いや対策方法と私たちにできること
睡眠と死亡率との関係
【睡眠不足・睡眠障害の影響】
先ほどの「睡眠と生活習慣病の関係」にも関連して、睡眠不足は死亡率を高めることが確認されています。
- 心臓病や脳卒中などのリスクが高まる
- 糖尿病や肥満などのリスクが高まる
- 自殺や交通事故などのリスクが高まる
などが原因で、睡眠不足は死亡率にも影響を与えます。つまり、
- 睡眠不足になる
- 脳や体の機能が低下
- 病気になりやすく、事故に遭いやすい状態になる
- 寿命が縮まる
といった負の連鎖が起こるのです。
次の章では「働きすぎ」とよく言われる日本人の、睡眠時間の現状に迫ってみましょう。*3)
日本人の睡眠時間に関する現状

日本人の睡眠時間は、近年減少傾向にあります。最新の調査によると、日本人の平均睡眠時間は6時間以上7時間未満が最も多いことがわかりました。
特に男性の30〜50歳代や女性の40〜50歳代では、4割以上の人々が6時間未満の平均睡眠時間でした。
【男女別、日本人の平均睡眠時間】
また、睡眠の質に関しては、20〜50歳代では「日中、眠気を感じた」が最も多く、70歳代の女性では「夜間、睡眠途中に目が覚めて困った」と回答する人が最も多いことがわかりました。
【客観的な睡眠時間の年齢による変化】
必要な睡眠時間は、年齢とともに短くなると言われています。一般的に、個人差はありますが働く世代の最適な睡眠時間は6〜9時間です。
6時間未満の睡眠や不眠は疾患リスクや死亡率の増加につながります。
睡眠時間の確保を妨げる要因については、
- 20歳代:スマートフォンやゲームに熱中すること
- 30~40歳代の男性:仕事
- 30歳代の女性:育児
と回答する人が最も多いという結果になりました。
諸外国と比較しても日本人の睡眠時間は短い
【 就労者の睡眠時間の国際比較】
上の調査結果からも、日本人の平均睡眠時間は外国と比較しても短いことがわかります。近年、日本人の睡眠不足は、健康や社会に大きな影響を及ぼす問題になっています。
この原因として、
- 仕事や学校などの時間外労働の増加
- スマートフォンやパソコンなどの電子機器の利用時間の増加
- 生活習慣の乱れ
- ストレス
- 24時間営業のお店やサービスが増えたことによる夜型化
などが考えられます。
このように、日本人の睡眠時間・睡眠の質についての現状は深刻です。*4)
質の高い睡眠をとるためのポイント
とはいえ、忙しい現代社会では、思うように睡眠時間を確保できない人も多いのではないでしょうか。そこで、同じ長さの睡眠時間でも、質の高い睡眠をとることで、効率的に心身を休めましょう。
【質の高い睡眠をとるための行動は生活習慣病の予防にも効果的】
ここからは、質の高い睡眠をとるためのポイントを紹介します。
規則正しい生活を心がける
毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる、という規則正しい生活を心がけましょう。これにより、体内時計が整い、自然と眠くなるようになります。
寝室環境を整える
寝室は、暗く、静かで、涼しい環境を整えましょう。また、寝具は自分に合ったものを選び、寝返りが打ちやすいようにしましょう。
寝る場所や寝具は、快適さと安心感を与えることが重要です。
寝る前の過ごし方に気を付ける
寝る前は、スマホやパソコンの画面を見たり、激しい運動をしたりするのは避けましょう。また、カフェインやアルコールの摂取も控えましょう。
また、夕食は過度の摂取を避け、軽めの食事を心がけると良いでしょう。これは睡眠時には消化器官などの内臓も休め、エネルギーをしっかりと成長や疲労回復に使うために重要です。
リラックスして眠りにつく
寝る前に、ゆっくりと湯船に浸かったり、アロマオイルを焚いたりして、リラックスしましょう。また、寝る前は、明日のことや心配事などをあれこれ考えるのは避けましょう。
瞑想やストレッチなどもリラックスする習慣としておすすめです。
適度な運動をする
適度な運動は、睡眠の質を高める効果があります。ただし、寝る直前の運動は、交感神経を刺激して眠りにくくなるため、避けましょう。
【良い睡眠のための12箇条】
【生活習慣と睡眠】
現代では、睡眠に関する悩みを持つ人が増えています。解決方法を知っておいて、もしもの時は深刻な状態になる前に、早めに対処しましょう。*5)
睡眠に関する悩みを解決するためには
睡眠の質と量は私たちの、
- 健康
- 幸福感
- 日々のパフォーマンス
などに大きな影響を与えることが分かりました。しかし、現代社会では多くの人々が睡眠に関する悩みを抱えています。
睡眠に関する悩みを解決するためには、まず自分自身の睡眠習慣や生活環境を見直すことが重要です。
自分で改善できる睡眠に関する悩み
- 睡眠不足
- 睡眠の質の低下
などの悩みの場合は、先ほどの「質の高い睡眠をとるためのポイント」の章で紹介した方法で、改善できる可能性があります。しかし、重度のストレスを感じる場合などは、早めに医療機関を受診した方が良いかもしれません。
また、仕事の時間が長すぎるなどが原因で睡眠時間が確保できない場合、働き方の改善が必要です。睡眠不足や質の悪い睡眠が続き、その職場では睡眠時間の確保が難しい場合、その仕事に働きがいを感じているかなどをよく考え、自分の健康を確保できる職場を探すことも1つの方法です。
医療機関での治療が必要な睡眠に関する悩み
- 不眠症
- 睡眠時無呼吸症候群
- ナルコレプシー
- レム睡眠行動障害
- 睡眠障害を伴う精神疾患(うつ病や不安障害)
これらの疾患は、自宅での対処では改善が難しい場合があるため、医療機関を受診して適切な治療を受けることが大切です。
睡眠障害を伴う精神疾患以外は、睡眠専門のクリニックや睡眠障害センターなどの医療機関に相談しましょう。睡眠障害を伴う精神疾患は、精神科医に相談することが適切です。
ただし、地域や病院によって異なる場合がありますので、具体的な医療機関や専門家を見つけるためには、かかりつけの医師や保健所、インターネットの検索などを活用することをおすすめします。
睡眠に関する悩みを解決するためには、まずは原因を突き止めることが大切です。原因が生活習慣の乱れなどであれば、日々の生活を見直すことで改善が期待できます。
しかし、病気が原因だと疑われる場合は、早期に医療機関を受診して適切な治療を受けましょう。
睡眠で健康になることはSDGsの達成にも貢献!

睡眠とSDGsは一見あまりつながりがないように見えるかもしれません。しかし、睡眠によって健康を維持することは、実はSDGsの目標達成に貢献するのです!
いくつか睡眠が達成に貢献するSDGs目標の例を挙げてみましょう。
SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」
睡眠は、健康な生活を送るために欠かせないものです。睡眠不足になると、集中力が低下し、事故やケガのリスクが高まります。また、免疫力が低下し、病気にかかりやすくなります。
良い睡眠習慣を身につけることで、私たちは健康で幸せな生活を送ることができます。このように、睡眠をしっかりとることは、SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」の達成に貢献することができます。
SDGs目標8「働きがいも経済成長も」
睡眠不足になると、仕事や勉強の効率が下がり、生産性が低下します。また、イライラしやすくなり、人間関係に悪影響を及ぼすこともあります。
さらに、睡眠不足は仕事や学業のパフォーマンスを低下させるだけでなく、事故やミスのリスクも高めます。良い睡眠習慣を持つことで、私たちは仕事や学業の成果を上げ、目標8「働きがいも経済成長も」に貢献することができます。
SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」
睡眠不足になると、交通事故や犯罪などのリスクが高まります。また、心身が疲弊し、心の病気にかかりやすくなります。
そのため、睡眠をしっかりとることで、安全で安心なまちづくりに貢献することができます。良い睡眠をとることは、住民の健康や幸福感を高め、SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」に貢献することができます。
SDGs目標12「つくる責任つかう責任」
安全で健康な生活を送ることができれば、医療や薬品の需要を減らすことができます。また、良い睡眠環境を整えるためには、エネルギー効率の高い寝具や照明の使用など、環境に配慮した選択をすることも重要です。
良い睡眠をとることは、SDGs目標12「つくる責任つかう責任」に貢献し、持続可能な消費と生産の実現につながるのです。
このように、私たちが普段当たり前に繰り返している睡眠は、SDGsの目標達成に無視できない存在なのです。私たちは、睡眠の重要性を理解し、より健康で幸せな生活を送るために、もっと睡眠に注目する必要があります。*6)
まとめ
睡眠は私たちの健康で幸福な生活に欠かせない重要な要素です。十分な睡眠をとることで、体が休息を取り、回復する時間を確保することができます。
しかし、日本人の睡眠時間は減少傾向にあり、睡眠不足が深刻な問題となっています。今後さらに、働き方やライフスタイルの変化がさらに進むことで、睡眠不足に陥る人が増える可能性があります。
忙しい日々の中でも、睡眠を犠牲にすることはできる限り避け、自分の健康を第一に考えましょう。仕事や学業の成果を上げ、健康で充実した生活を送るためには、睡眠の重要性を理解し、質の高い睡眠をとることが必要なのです。
良い睡眠をとるためには、自己管理も大切です。自分自身の体調や生活リズムをしっかりと把握し、適切な睡眠時間を確保しましょう。そして、日常生活でのストレスを軽減するために、リラックスする時間を作ることも大切です。
SDGsの目標達成にも、私たちひとりひとりが、自分自身の心と体を大切にし、健康で幸福な生活を送ることが欠かせません。質の高い睡眠を十分な時間とって、元気で充実した生活を送りましょう!
<参考・引用文献>
*1)まずは睡眠について知ろう
厚生労働省『眠りのメカニズム』
厚生労働省『良い目覚めは良い眠りから知っているようで知らない睡眠のこと』p.7(2023年3月)
厚生労働省『良い目覚めは良い眠りから知っているようで知らない睡眠のこと』p.8(2023年3月)
厚生労働省『快眠と生活習慣』
ワコール『3月と9月、年に2回の「睡眠の日」が定められています』
厚生労働省『良い睡眠の概要(案)』
*2)睡眠中に私たちの体で起きていること
厚生労働省『眠りのメカニズム』
厚生労働省『健康づくりのための睡眠指針検討会報告書』(2003年3月)
厚生労働省『健やかな眠りの意義』
*3)睡眠が健康に与える影響は?
厚生労働省『睡眠と生活習慣病との深い関係』
NCDs(非感染性疾患)とは|生活習慣病との違いや対策方法と私たちにできること
厚生労働省『健やかな睡眠と休養』
厚生労働省『睡眠と健康』
*4)日本人の睡眠時間に関する現状
厚生労働省『睡眠に関するこれまでの取組について』p.6(2023年7月)
厚生労働省『睡眠と生活習慣病との深い関係』
厚生労働省『令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要』
日本経済新聞『初めて増えた日本人の睡眠時間 最長は青森県』(2023年2月)
産経新聞『テレワークで睡眠18分、娯楽16分増 生活変化裏付け 総務省調査』(2022年12月)
朝日新聞『世界で最も寝ていないのは日本の女性? 睡眠時間のデータが示す実情』(2023年3月)
*5)質の高い睡眠をとるためのポイント
厚生労働省『睡眠と生活習慣病との深い関係』
厚生労働省『睡眠に関するこれまでの取組について』p.3S(2023年7月)
厚生労働省『快眠と生活習慣』
厚生労働省『良い目覚めは良い眠りから知っているようで知らない睡眠のこと』(2023年3月)
厚生労働省『健康づくりのための睡眠指針 2014』(2012年3月)
厚生労働省『第3章 より健康的な睡眠を確保するための生活術』
*6)睡眠で健康になることはSDGsの達成にも貢献!
経済産業省『SDGs』
この記事を書いた人
松本 淳和 ライター
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。