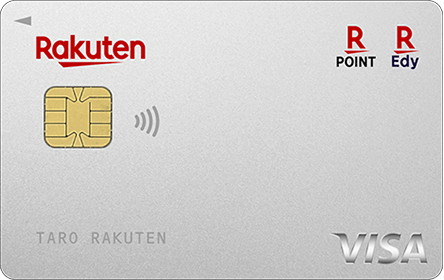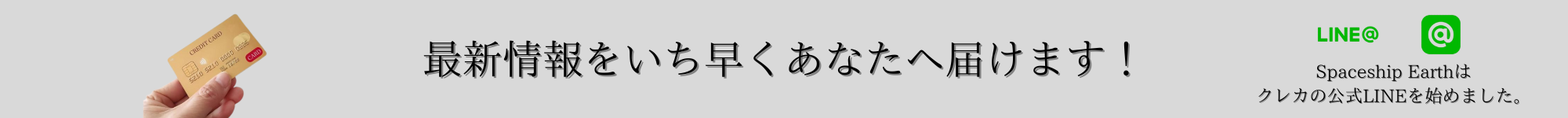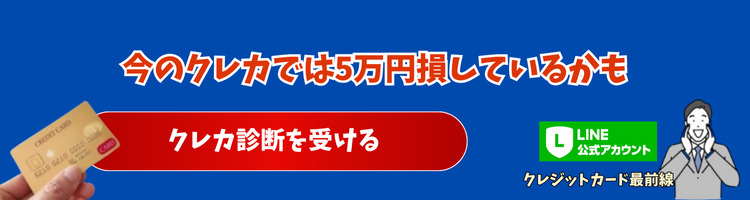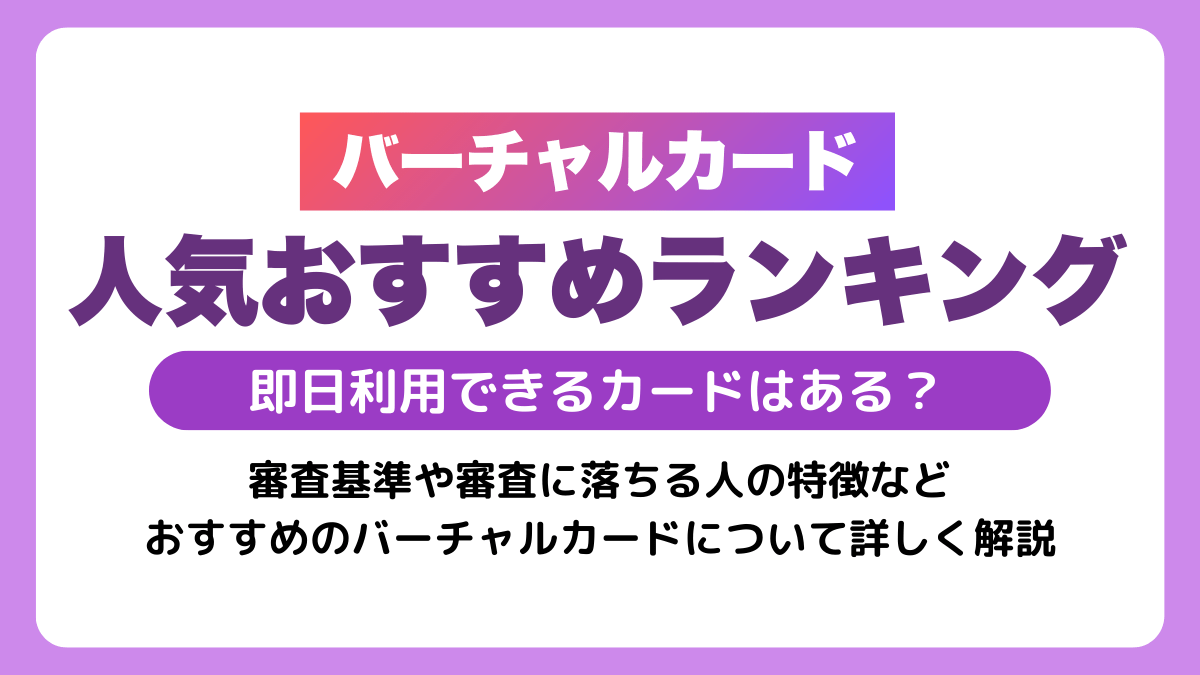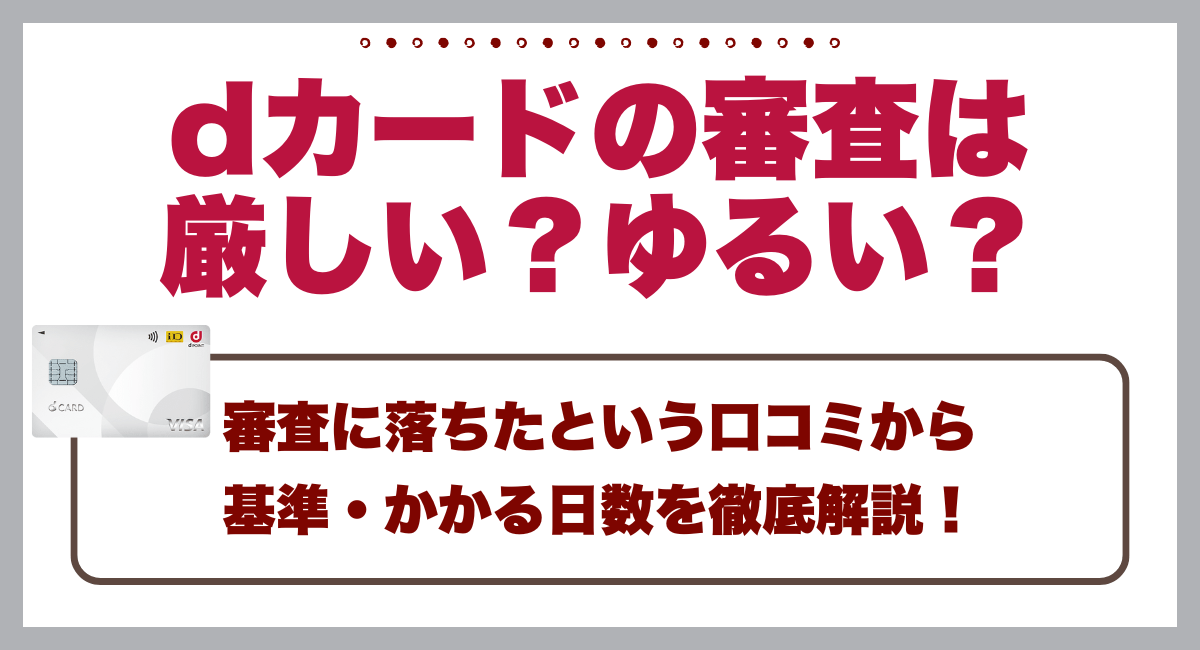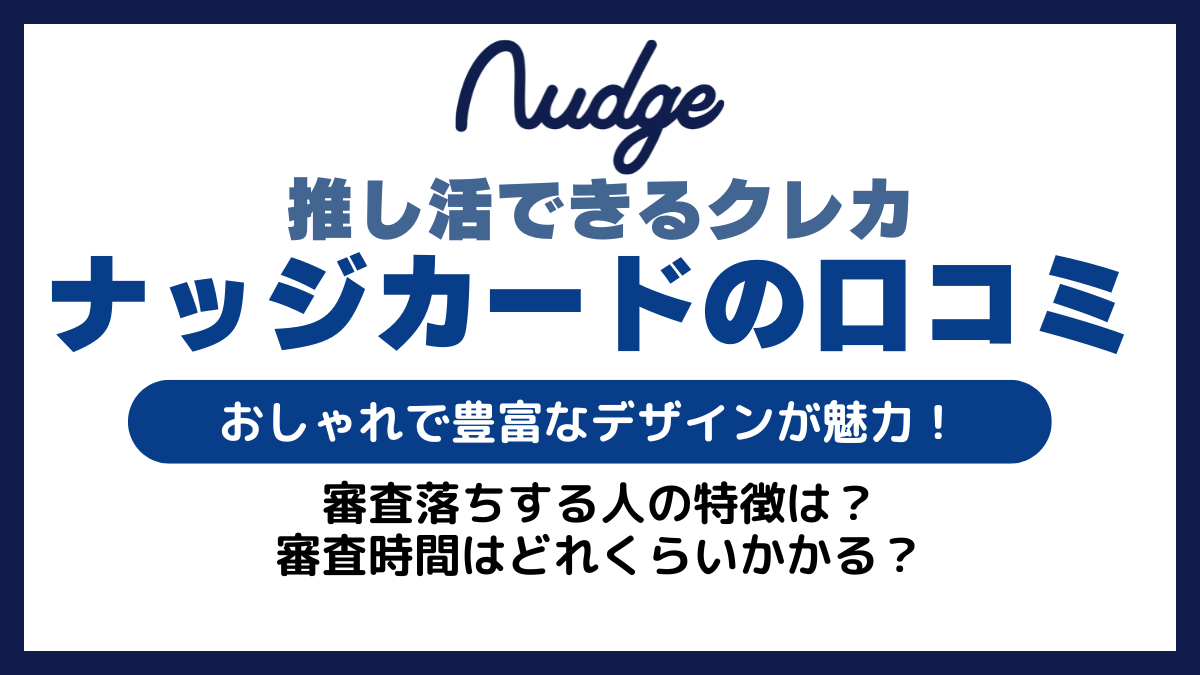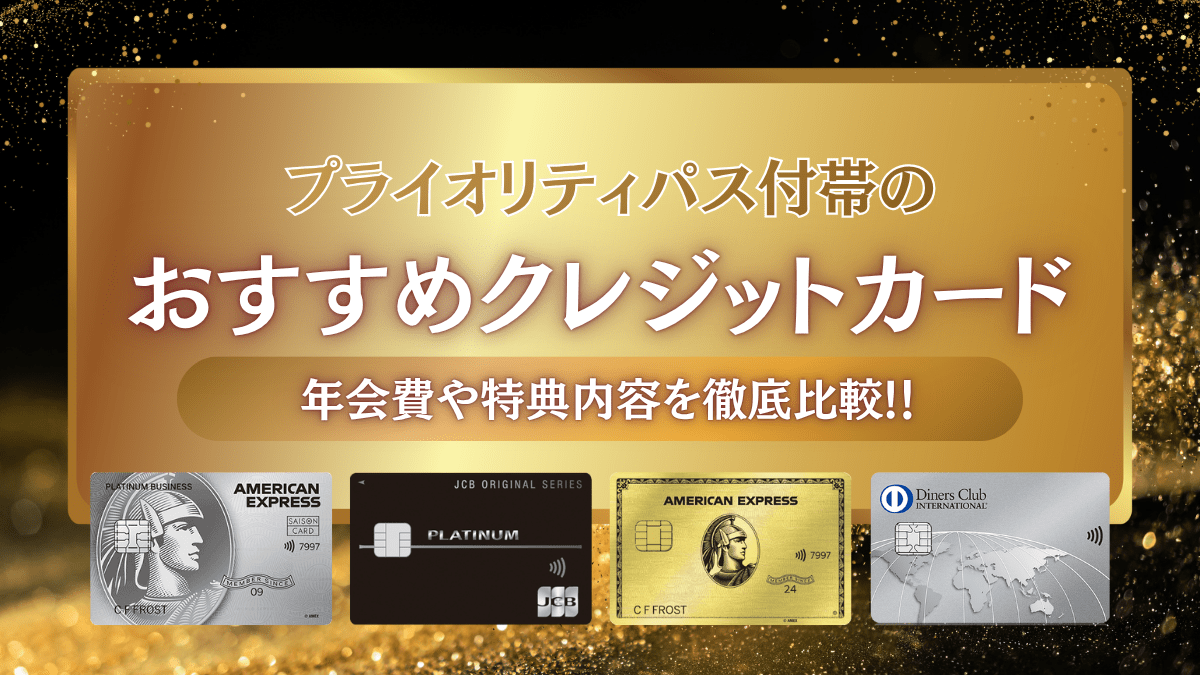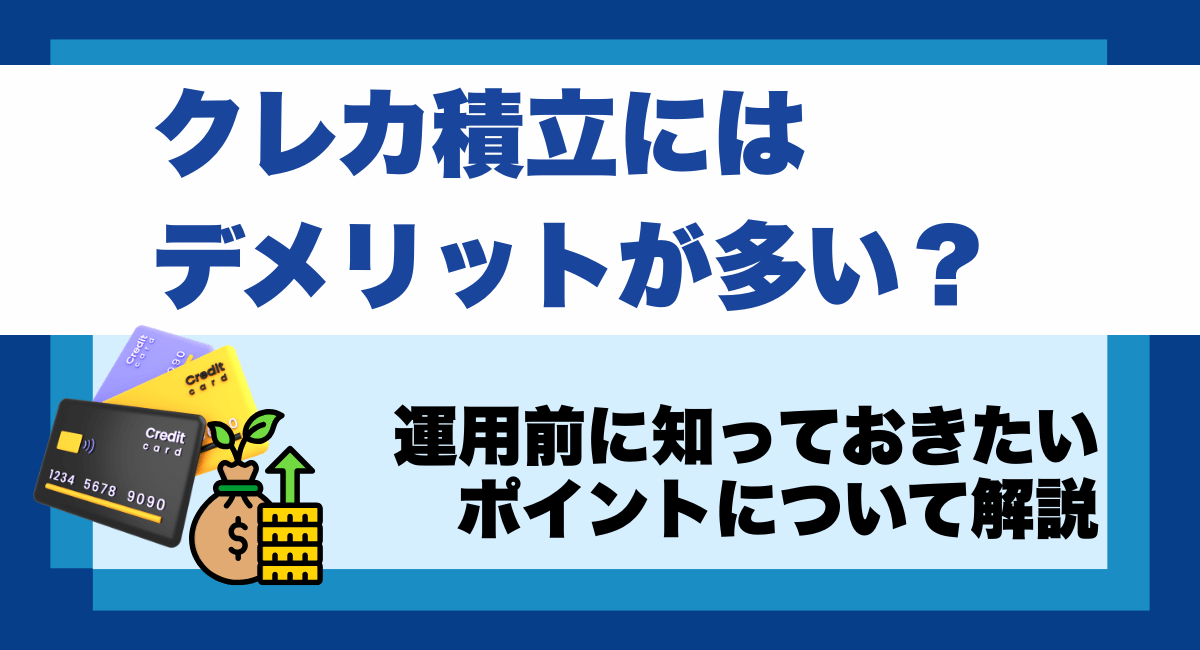
将来への不安が高まる中で、個人がもっと気軽に金融商品へ投資し、資産形成ができる「クレカ投資」が改めて注目されています。
クレカ投資とはその名の通りクレジットカードを用いて投資信託等に投資することであり、現金での買付では決して得られないメリットがあるため、多くの人におすすめできます。ただし、証券会社やカードの仕様、法律の制限等に関わるデメリットがあるのも確かです。
そこで今回はクレカ積立のメリットやデメリット、失敗しないための注意点にくわえ、おすすめできるクレジットカードの比較や、新NISA制度との賢い組み合わせ方についても詳しく解説していきます。
目次
クレカ積立って何?仕組みを表にまとめて解説
クレカ積立とは、現金ではなくクレジットカードを使って投資信託などの金融商品をを購入することです。もちろん「積立」なので1回だけでなく、毎月一定額を投資し、資産形成を行っていく方法になります。
クレカ積立自体は新しい仕組みではありませんが、投資によりクレジットカード特有のポイントが獲得できることや、新しいNISA制度が開始されたことで、改めて注目されることになりました。
クレジットカードで積立ができる仕組みを簡単に表で説明すると、次のとおりです。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 支払い方法 | ・毎月の投資信託の購入代金をクレジットカードで決済する・他のクレジットカード利用分と合わせて、指定の銀行口座からカード利用代金としてまとめて引き落とされる |
| 積立対象 | ・主に投資信託が対象・毎月一定額を積み立てる「積立購入」に利用される・個別株式の購入、スポット購入には対応していないことが多い |
| 積立頻度 | ・証券会社が定めた月ごとの「買付日」に自動で買付けが実行・利用者が自由に買付日を選択することは基本的にできない |
| ポイント還元 | ・クレジットカードごとに異なるポイントを積立額に応じて付与・獲得ポイントの還元率や条件は、カードや証券会社で異なる |
さらに、それぞれの立場におけるクレカ積立のステップを詳細化すると次のとおりです。
| ステップ | 利用者のアクション | クレジットカード | 証券会社 | 資金の流れ/情報連携 |
|---|---|---|---|---|
| ①設定 | ・証券会社口座の開設・クレカ積立の申し込み | ・証券口座と積立の申込受付・カード情報登録 | ・申込情報:利用者→証券会社 | |
| ②認証 | ー | ・証券会社からの依頼に基づきカード認証・結果通知 | ・カード会社にカード認証を依頼 | ・認証結果:証券会社→カード会社 |
| ③買付 | ー | ・投資資金を立替払い | ・投資信託を買付・利用者口座へ反映 | ・投資資金:カード会社 → 証券会社・買付報告:証券会社 → 利用者 |
| ④請求 | ・カード利用代金で投資額を支払う | ・利用者に投資額(カード利用代金)を請求 | ー | ・請求情報:カード会社 → 利用者・支払い:利用者 → カード会社 |
| ⑤ポイント | ・ポイントの受取 | ・利用額(積立額)に応じたポイントを付与 | ー | ・ポイント情報:カード会社 → 利用者 |
利用者はクレジットカードを用意し、証券会社で口座を作る必要があります。普段使っているカードを登録しても良いですが、いくつかの制限やデメリットがあります。この点については後ほど解説します。
次に、証券会社のマイページから積立設定や支払い方法としてクレジットカードを登録します。これにより毎月特定の日に自動で商品の買付が行われ、その支払いはすべてカード払い(カード会社による立替)となります。
カード払いには支払いを遅らせられるというメリットがありますが、それ以上に重要なのは、買付を忘れたり、口座間で資金移動をするといった手間がかからない点です。くわえて買付量が多ければ、それだけ多くのポイントが貯まることになります。
購入代金はカード払いなので、その支払いは当然ながらカード利用料に含まれます。支払日や締め日はカードごとに異なりますが、給料後の日付を設定できることが一般的です。そして投資額に応じてカード独自のポイントが付与されます。これも付与日はカードごとに異なります。
クレカ積立における即売りとは?
クレカ積立には、金融商品を購入した後に即売却し、購入分のポイントを得るという「即売り」という手法があります。たとえば還元率が1%のクレジットカードで3万円分の投資信託を購入すれば、一度の取引で300ポイントが貯まります。
即売りのメリットを最大化するためには、信託報酬が低いファンド、購入手数料が0円のノーロード投信を選ぶこと、そして積立上限を最大まで使い購入することです。また購入した当日に売却できるかどうか「最低保有日数」が0日である点も確認が必要です。
注意点として、即売り自体は禁止行為ではありませんが、マネックス証券や大和コネクト証券など、短期売買を制限する規約がある証券会社もあるため、事前に確認しておきましょう。
クレカ積立のデメリットは?利用時に大切な注意すべき点
クレカ積立には、主に5つのデメリットがあります。
- クレカのご利用可能枠を使用することになる
- ポイント還元率の急な変更
- 毎月クレカ積立の上限が設定されている
- 解約に手間がかかってしまう
- 積立は月に1回、証券会社の指定日のみ
これらのデメリットについて、それぞれ詳しく解説していきます。
クレカのご利用可能枠を使用することになる
投資代金の決済にクレジットカードを用いれば、購入した分だけ利用可能額が減ります。当然ながら積立額が大きくなるほど利用枠は圧迫され、他の買い物や支払いに使う余裕がなくなるかもしれません。
- 例:ショッピング枠が30万円のカードが1枚あるので、クレカ投資に使おう
- 毎月5万円のクレカ積立を設定しよう
- ショッピングに使える枠が25万円に減少したのに、支出総額はほぼ減らない
この問題を解決する一つの方法は、普段遣いとは別に投資信託専用のクレジットカードを作ることです。これにより投資額が上がってもメインのカードにおける利用可能枠は影響を受けませんし、出資管理も楽になります。
ただし複数枚カードを持つ場合は、積立額が影響を受けない分、毎月の支出額が大幅に増えるリスクがあります。カード1枚の限度額の中でやりくりするのではなく「2枚分の限度額を使える」と考えてしまうことが多いからです。
1枚だけでやりくりするとしても、複数枚で利便性を向上させる場合も、生活と投資のバランスを考えて、無理のない積立金額を設定しましょう。
ポイント還元率の急な変更
クレカ積立は積立額に応じて各カードのポイントが貯まるという大きなメリットがありますが、そのポイント還元率は将来的に下がる可能性があります。過去にも複数の大手カード会社が還元率や付与条件の見直しを行い、その度にユーザーからの反発を受けています。
たとえば、三井住友カードは2024年に「つみたて投資」のサービス内容を改定し、利用額に応じて付与ポイントが変動する仕組みの導入、年会費が高いカードにおける付与条件の変更を行いましたが、これは多くのユーザーから改悪だと評されました。
このように、他社よりも還元率が高いからそのカードを作ったのに、後から経営戦略の変更等を理由にポイントプログラムが改悪されて優位性がなくなる、というのはよくあることです。
そのためクレカ積立をする方はポイント制度が無限に続くものではなく、あくまで一時的なメリットであることを理解しておくべきです。カード会社が定期的に配信するお知らせや通知も必ずチェックしましょう。
毎月クレカ積立の上限が設定されている
クレカ積立は無限にできるわけではなく、毎月の投資上限額が決められています。新NISAの施行で年間120万円まで積立が可能となったため、多くのカード会社が上限を「5万円」から「10万円」に増やしましたが、それでも足りないと感じる方はおられるでしょう。
投資家の視点では積立上限があることはデメリットに見えるかもしれませんが、これはキャッシュレス投資における利便性の確立と、投資家が過度な投資を行って破綻してしまうことの防止を両立するために設けられています。
それでも10万円以上の積立を行いたい方は、クレカ投資だけでなく銀行口座からの引き落としによる投資を併用できます。
解約に手間がかかってしまう
クレカ積立は導入こそ簡単であるものの、解約には手間がかかります。たとえば途中で積立の設定を変更したい場合や解除したい場合は証券会社のマイページ上から行うのが一般的ですが、証券会社が定める締切日をすぎると変更の反映が翌々月からとなってしまいます。
また保有している資産を売却して現金化したい場合、単に積立設定を解除するだけでは不十分です。具体的には証券会社のマイページから売却手続きを行ったうえで、それとは別に積立の解除手続きをする必要があります。
積立は月に1回指定された日のみ
クレカ積立は月に一回だけ、決められた日に実行されます。買付日が固定されているのは明快で分かりやすいですが、その反面「今回だけは積立の日を早めたい(遅くしたい)」というように、柔軟性を持たせることはできません。
長期投資が前提なら1回あたりの買付タイミングが悪影響になることは少ないですが、それでも高い柔軟性を求める方にとっては不自由を感じるポイントになります。
クレカ積立を選ぶメリットは?
クレカ積み立てにはもちろんデメリットだけでなく、次のようなメリットもあります。
- ポイントを貯めることができる
- 資産形成の自動化
それぞれの点について詳しく解説します。
ポイントを貯めることができる
クレカ積み立てを利用すると、支払い方法として登録したカードのポイントが、積立した分だけ付与されるというメリットがあります。これは従来の現金投資(銀行引き落とし)では考えられないメリットであり、ポイントを貯めたい人にとって大きなアドバンテージです。
たとえば、還元率0.5%のカードで毎月10万円積み立てた場合は年間で6,000ポイント、還元率1.0%のカードなら年間で12,000ポイントも貯めることができます。
貯めたポイントはショッピングに使えますが、いくつかの証券会社が対応している「ポイントによる再投資」を利用すれば、それ自体が複利効果を生み出し、結果的にリターンの向上につながります。
資産形成の自動化
クレカ積立で達成できるのは、特別なことは何もせずにお金を貯められる「資産形成の自動化」です。毎月のように購入手続きを行ったり、証券口座に資金移動する手間がなくなるため、特に投資初心者や毎日が忙しい方にとってメリットが大きいです。
もちろん、カードの有効期限が切れたり、カード会社側のシステムが停止すると積立がストップするというリスクはあるため、100%放置できるわけではありません。しかし「考えることが減る」ことは、投資による資産形成を敬遠してきた方の心理的ハードルを大きく下げるでしょう。
NISAと併用することで非課税とポイントを二重に受け取ることができる
クレカ積立とNISAを併用すれば、非課税とポイント還元の二重のメリットを受けられます。
また、NISAを最大限活用する方法として、毎月の積立額をNISAの年間上限額に設定する方法があります。自動的にNISAの上限を埋められるため、NISA枠を使い切る最も効率的な方法と言えるでしょう。
実際にSBI証券の「NISA枠ぎりぎり注文」や、楽天証券の「積立NISA枠ぎりぎり注文」などの商品」があり、これらの商品を利用すれば、簡潔に枠を無駄なく使い切ることが可能です。
さらに、クレカ積立は容易に始められる投資手法であり、買い物の心理的がハードルが低くお手軽な特徴があります。
メリットの充実さと相まって、これから投資を始めたい初心者におすすめです。
クレカ積立におすすめのクレカを紹介
次は、実際にクレカ積立をするのにおすすめできる5つのクレジットカードを解説していきます。大前提として「クレカ積立に対応した証券会社を選ぶ必要がある」という点は留意しておきましょう。
| 証券会社 | カード名 | 還元率 | 年会費 | 貯まるポイント |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 三井住友カード(NL) | 最大0.5%※1 | 永年無料 | Vポイント |
| SBI証券 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 最大1.0% | 5,500円(税込) ※年間100万円のご利用で翌年以降の年会費永年無料 ※年間100万円利用の対象取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細は、三井住友カードのホームページを必ずご確認ください。 | Vポイント |
| 楽天証券 | 楽天カード | 0.5%~1.0% | 永年無料 | 楽天ポイント |
| マネックス証券 | マネックスカード dカード | 最大1.1% | 550円※無料化条件あり | マネックスポイント |
| 三菱UFJ eスマート証券 | au PAY カード | 1.0% | 実質無料※条件で変動 | Pontaポイント |
※各カードの還元率は積立額や代行手数料等によって変動する場合があります
※1特典を受けるには一定の条件がございますので、三井住友カードのHPをご確認ください。
三井住友カード(NL)
三井住友カード(NL)は、コストゼロで手軽にクレカ積立を始めたい方に適しています。当カードは券面にカード番号等が印字されていないナンバーレスカードで、セキュリティ面で安心感があります。
クレカ積立によるポイント付与率は「最大0.5%」※ですが前年の利用状況により変動するため、年間10万円未満だと0%になるケースがある点には注意が必要です。※特典を受けるには一定の条件がございますので、三井住友カードのHPをご確認ください。
普段遣いのクレジットカードの性能としては、対象のコンビニや飲食店でのタッチ決済で還元率が高くなる特典が魅力です。利用額に応じて貯まるVポイントは他社ポイントへの交換したり、ポイント投資も可能なので便利です。
※三井住友カード(NL)はおすすめしない?メリットないと言われる悪い評判は本当なのか解説
三井住友カード ゴールド(NL)
1つ目の三井住友カード(NL)の上位カードである「三井住友カード ゴールド(NL)」は年会費が5,500円ですが、年間で100万円以上のカード利用があれば、翌年度以降は年会費が無料になります 。
クレカ積立によるポイント付与率には年間利用額等の条件があるものの「最大1.0%※1」と、通常カードより高めに設定されています。※特典を受けるには一定の条件がございますので、三井住友カードのHPをご確認ください。
その他には、対象店舗を利用すると10%を超える還元率が適用されたり、空港ラウンジ特典、国内旅行傷害保険・海外旅行傷害保険両方が付帯されています。(利用付帯)
※年間100万円利用の対象取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細は、三井住友カードのホームページを必ずご確認ください。
楽天カード
楽天証券でクレカ積立したい方は楽天カードを作りましょう。年会費は永年無料なのでコストがかからず、楽天ポイントの還元率も代行手数料が0.4%以上のファンドを選択すれば、最大「1.0%」まで上がります。
楽天カードでクレカ積立する最大のメリットは、楽天経済圏との連携です。楽天市場で買い物をする際のポイント還元率が上がるため、楽天カードを普段遣いしている方におすすめできます。より高い還元率を狙いたい方は、上位の楽天ゴールドカード(年会費2,200円)という選択肢もあります。
マネックスカード
年会費550円のマネックスカードは、年に1度利用するだけで年会費が無料になります。クレカ積立で貯まるポイントはマネックスポイントで、積立5万円以下の分は最大還元率が「1.1」%と、他社よりも高還元であるのが特徴です。
マネックスポイントの使い道は幅広く、dポイントやVポイント、Pontaポイントなど他のポイントに交換できるほか、投資信託だけでなく株式売買の手数料や暗号資産の交換に充当することも可能です。
au PAY カード
旧名を「カブコム証券」という「三菱UFJ eスマート証券」では、auユーザーにとってメリットの大きい「au PAY」カードがクレカ積立に利用できます。auユーザーなら無条件で年会費無料ですし、クレカ積立の還元率も「1.0%」と高めです。
当カードは積立だけでなく保有でもPointaポイントが貯まるためお得です。さらにゴールドカードなら、最大3%還元という他社を大きく上回る還元も可能です。年会費は11,000円と高めですが、ポイントを重視する方にはおすすめです。
クレカ積立に関するよくある質問
最後に、クレカ積立に関してよくある4つの質問に回答していきます。
つみたてNISAとクレカ積立の違いって何?
つみたてNISAとクレカ積立はどちらも資産形成に関わる用語なので混同しがちですが、つみたてNISAは非課税制度の「制度名」であり、クレカ積立は資産形成の「方法」の一つであるという点で異なります。
- つみたてNISA:資産形成の「制度名」
- クレカ積立:資産形成の「支払い方法名」
つみたてNISAは長期的な視点で分散投資が可能な税制優遇制度で、運用益が非課税になるという特徴があります。通常であれば投資で利益が出ても「20.315%」の税金が発生するためお得ですが、年間投資上限が120万円まで、金融商品も金融庁が定めたもののみ、という制限があります。
つみたてNISAで投資信託を行う場合、支払い方法としてクレカ積立を選べる場合があります。これにより、つみたてNISAとクレカ積立両方のメリットを享受できます。
複数の金融機関でのクレカ積立は可能?
複数の金融機関でクレカ積立できるかどうかは、利用する口座の種類で次のように変わります。
- NISA口座:一つの金融機関のみ開設可能
- 課税口座(特定口座・一般口座):複数の金融機関でそれぞれ開設可能
つみたて投資枠や成長投資枠を含む新NISA口座は、一人あたり一つの金融機関でしか開設できません。そのためNISA口座でクレカ積立を行う場合は、必然的に開設した一つの金融機関でのみ行うことになります。
それに対して特定口座・一般口座といった課税口座を利用する場合は、複数の金融機関でそれぞれ開設できるという点で異なります。そのため、各証券会社がクレカ積立サービスを提供しており、その証券会社が対応しているクレジットカードを保有していれば、複数の金融機関でクレカ積立を行うことは可能です。
ただしつみたてNISAでは使えないほか、積立に使うカードを増やすことで管理が煩雑になったり、ポイントが分散されるといったデメリットもあるため注意が必要です。
どの投資信託でもポイントがつくのか?
基本的には、証券会社がクレカ積立に対応していれば、積立額に応じたポイントが付与されます。ただし、次のような例外もあります。
- 一部の投資信託ではポイントが付かないことがある
- ポイント付与に条件が設定されている場合がある
たとえば、信託報酬が低いファンドではポイント付与されないか、還元率が通常よりも下げられていることがあります。おすすめカード紹介の部分でも触れましたが、あるカードは代行手数料が0.4%以上でないと、1%の還元率が適用されません。
くわえて、ポイント付与そのものに条件があり、その条件をクリアしなければポイント自体が付与されないことがあります。その条件には年間の利用額や、カードの種類・ランクなどが挙げられます。
クレカ積立の上限が10万円なのはなぜですか?
クレカ積立の上限は以前の5万円から10万円に引き上げられていますが、それでも少ないと感じる方は多いでしょう。
もともとクレジットカードを支払い方法とする有価証券の購入は禁止されており、それでも翌月一括払いや積立投資であることを条件に、5万円という枠が設けられたのです。これには「投資のしすぎ」で破綻を招く投資家を保護するという意味合いがあります。
新NISAの発足により、投資家を増やし、利便性を向上するために法律が改正された結果、多くの証券会社がクレカ積立の上限を月額5万円から10万円に引き上げました。今後テクノロジーや国民の金融リテラシーの発達により選択肢が増えれば、積立の上限がまた上がる可能性はあります。
まとめ
クレカ積立は、これまで投資に関心がなかった人や、面倒だと感じていた人を資産形成の道に引き入れ、フィンテックやAIの発展により新たな市場を生み出すことが予想されます。
現金での投資とは異なるデメリット・リスクがあるのも確かですが、将来の不安を解消するために資産形成をしたい方は、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
この記事を書いた人
エレビスタ ライター
エレビスタは「もっと"もっとも"を作る」をミッションに掲げ、太陽光発電投資売買サービス「SOLSEL」の運営をはじめとする「エネルギー×Tech」事業や、アドテクノロジー・メディアなどを駆使したwebマーケティング事業を展開しています。
エレビスタは「もっと"もっとも"を作る」をミッションに掲げ、太陽光発電投資売買サービス「SOLSEL」の運営をはじめとする「エネルギー×Tech」事業や、アドテクノロジー・メディアなどを駆使したwebマーケティング事業を展開しています。

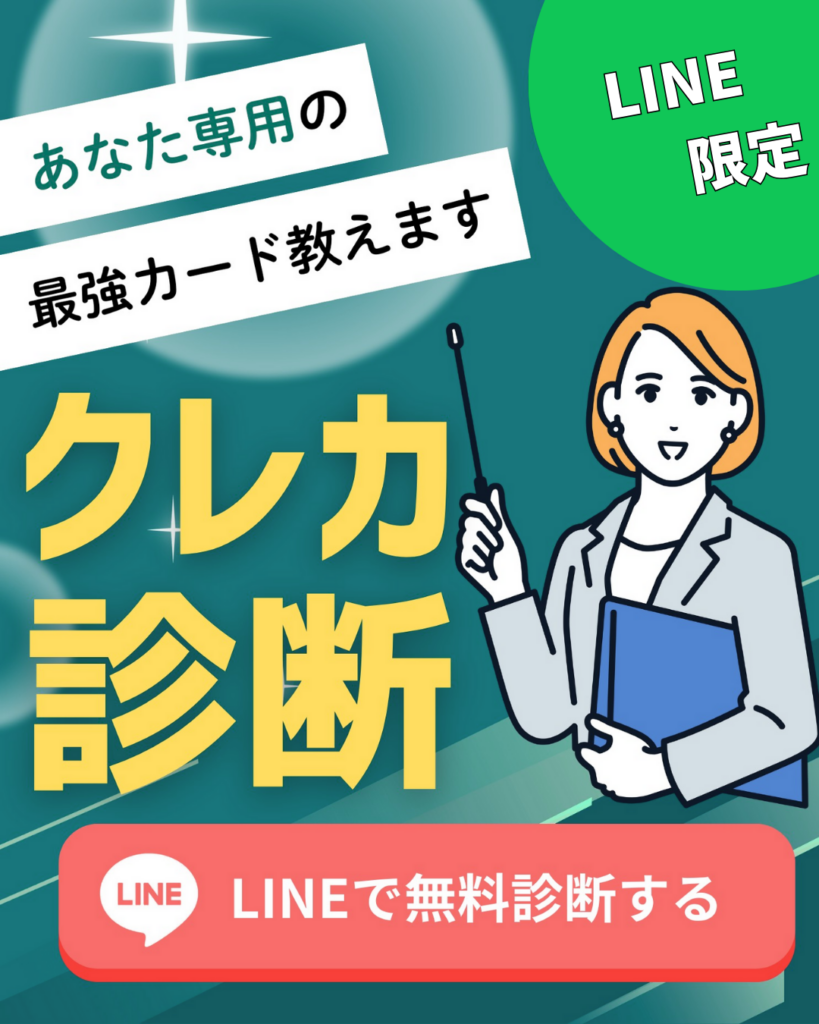

.png)