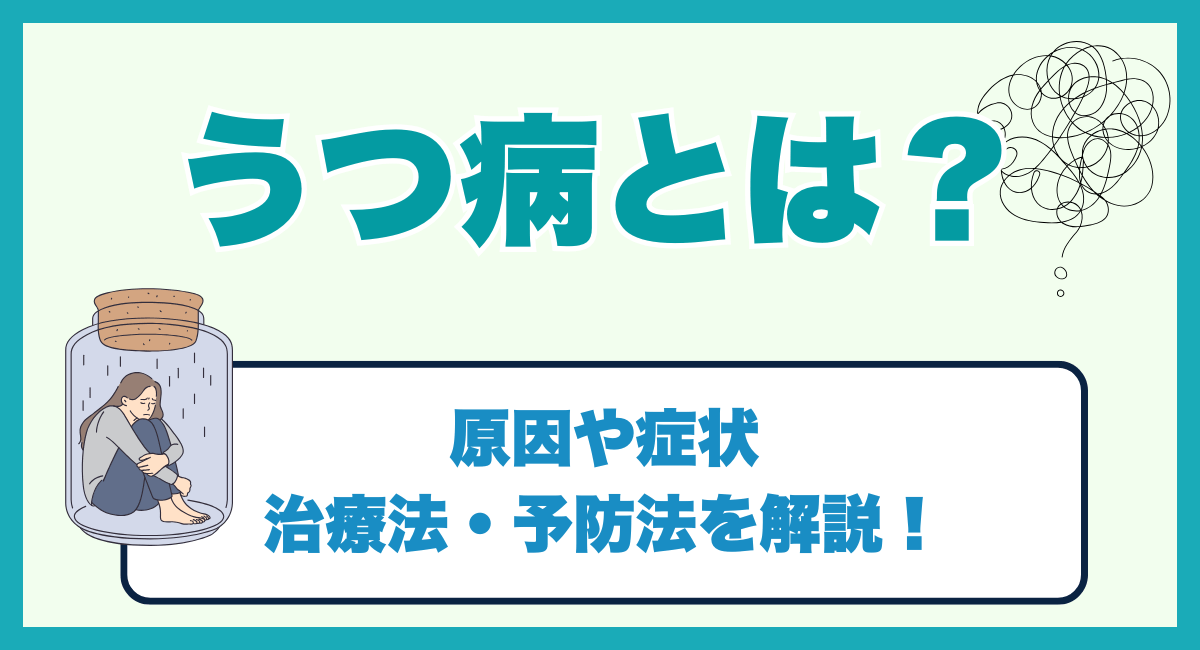
日常生活の中で「気分が落ち込む」「やる気が出ない」「体がだるい」と感じることは時々あります。しかし、その症状により日常生活に支障が出るなど、一定の基準を超えた場合、うつ病と診断されます。うつ病とはどのような病気で、どのようなことに気をつけたら良いのでしょうか。
この記事では、うつ病とは何か、種類、症状、原因、治療法、予防法、周りの人がうつ病になったときに私たちができること、よくある質問、SDGsとの関係について解説します。
目次
うつ病とは?簡単に解説
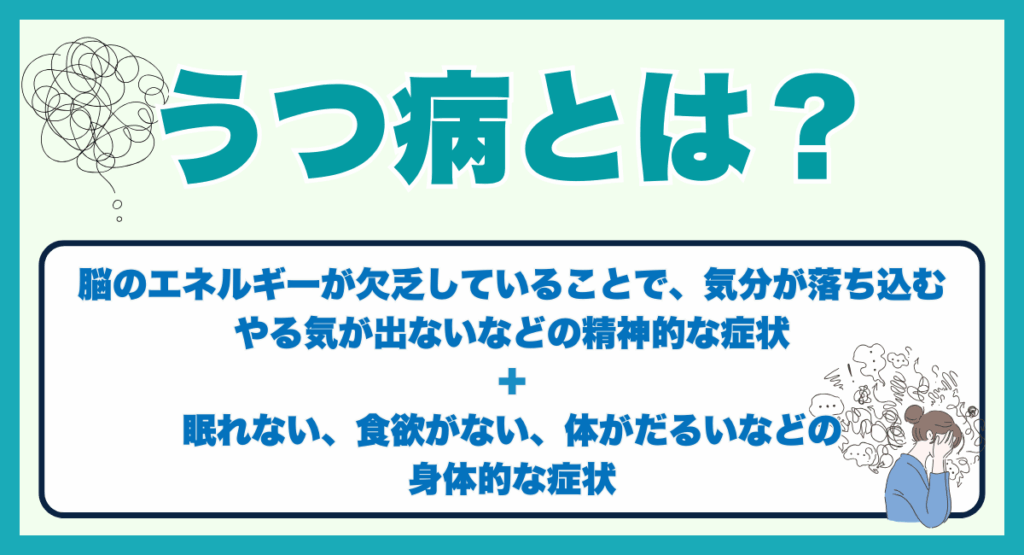
うつ病とは、脳のエネルギーが欠乏していることで、気分が落ち込む、やる気が出ないなどの精神的な症状に加えて、眠れない、食欲がない、体がだるいなどの身体的な症状のある病気を言います。気分の変化により日常生活に支障をきたす、気分障害の1つです。
「厚生労働省白書」(平成30年度版 )によると、気分障害などの患者数は、2017年に127.6万人と年々増えています。
また、生涯でうつ病を経験する人は、15人に1人ともいわれています。特に女性は、妊娠や出産、更年期などからうつ病になることもあり、男性よりも多い傾向にあるのが特徴です。
うつ病の人がとる行動
うつ病の人がとる行動には、いくつかの共通した特徴があります。まず、外出や人との交流を避けるようになり、以前は楽しめていた趣味や活動にも興味を示さなくなることが多く見られます。
また、無気力や疲労感から仕事や家事に手がつかなくなり、日常的な行動も億劫に感じるようになります。言動では「自分には価値がない」「消えてしまいたい」など自己否定的な発言が増えることもあります。
一方で、人前では無理に明るくふるまうケースもあり、周囲が気づきにくいこともあります。睡眠や食欲の乱れ、遅刻や欠勤の増加なども行動面に表れるサインです。こうした行動を見逃さず、優しく見守ることが大切です。
うつ病診断で自分がうつ傾向があるかチェック
気分の落ち込みは、誰にでもあるものです。「もしかしたら、うつ病かもしれない」と思うこともあるでしょう。そのようなときに、うつ病の診断基準を基にセルフチェックができる方法を紹介します。
セルフチェックは、当てはまる項目を数えることで、うつ病の軽症、中等症、重症が分かります。上図の内容をまとめたのが、次の「うつ病セルフチェック」です。
■うつ病セルフチェック
・診断基準1:どちらか1つに当てはまること
- 憂うつ
- 興味や喜びの喪失
・診断基準2:当てはまる数を合計する
- 食欲の異常
- 睡眠の異常
- そわそわする、または体が重い
- 疲れやすい
- 自分を責める
- 思考力・集中力の低下
- 死にたいと思う
いずれの症状も、ほとんど一日中、2週間以上続き、仕事や家庭などに何らかの問題が生じていることが基準です。
【軽症のうつ病】
・診断基準1…1つ当てはまる
・診断基準2…5つ当てはまる
【中等症のうつ病】
・診断基準1…1つ当てはまる
・診断基準2…6~7つ当てはまる
【重症のうつ病】
・診断基準1…1つ当てはまる
・診断基準2…8つ以上当てはまる
当てはまる数で診断するセルフチェックですが、「死にたいと思う」症状が強く出ている場合は、他の症状がなく軽症に分類されたとしても注意が必要です。セルフチェックはあくまでも目安として使用し、医療機関や専門医による正しい診断を受けるようにしましょう。
うつ病の種類
うつ病は、特徴的な症状により「メランコリー型」「非定型・現代型」「季節型」「産後」に分類されます。それぞれどのような特徴があるのかを確認していきましょう。
メランコリー型
うつ病の中でも、典型的といわれているのがメランコリー型です。メランコリー型の「メランコリー」には「憂鬱」という意味を持ち、次のような精神的・身体的特徴があります。
■メランコリー型の特徴
- 精神的:良いことがあっても気分が晴れない、朝に最も気分が落ち込みやすい、過度な罪悪感を持つなど
- 身体的:明らかな食欲不振、体重減少、早朝(通常の2時間以上前)に目が覚めるなど
非定型・現代型
非定型・現代型は、楽しい・うれしい、といった感情がある一方で、対人関係や環境により症状が変化しやすい特徴があります。そのため、周囲からは病気ではないと誤解されることもあるうつ病です。
■非定型・現代型の特徴
- 精神的:楽しいことやうれしいことには気分が明るい、他人の言動に敏感など
- 身体的:明らかな体重増加、食欲増加、過眠な
季節型
季節型は、特定の季節になると発症するうつ病です。特に、秋から冬にかけて起こる冬季うつ病が知られており、日照時間が関わっていると考えられています。精神的・身体的特徴は次の通りです。
■季節型の特徴
- 精神的:気力の低下など
- 身体的:過眠、過食、体重増加など
産後
産後は、出産後4週間以内に発症するうつ病を言います。妊娠や出産によるホルモンバランスの変化や、育児の不安、授乳などによる睡眠不足が影響していると考えられています。精神的・身体的特徴は次の通りです。
■季節型の特徴
- 精神的:気分の落ち込み、気力の低下など
- 身体的:疲労感、不眠、食欲不振など
双極性障害との違い
うつ病と同じく、気分障害の1つに分類されているものに双極性障害があります。双極性障害は、気分の落ち込みと高揚を繰り返す病気です。うつ病の症状がある一方で、活動的になる時期は気分が良いため、病気の自覚がありません。双極性障害は、うつ病とは治療法も異なります。
うつ病の症状
うつ病の治療は、症状が軽いうちに始めることが大切です。症状が進行すると、日常生活にさまざまな支障が生じるからです。どのような段階があるのかを知るために、うつ病の症状について確認していきましょう。
症状のきざし
気分の落ち込みは、うつ病の症状の1つです。そしてこの症状が現れる前に、何もやる気が起きないなどのきざしが見られます。症状のきざしには、次のようなものがあります。
■うつ病のかかりはじめのきざし
- 何もやる気が起きない
- 物事に集中できない
- 物事が決められない
- 疲れがとれないなど
これらのきざしは、普段の生活の中でも程度の差こそあれ、日常的にあることです。ただし、うつ病につながる可能性があることを覚えておく必要があります。
初期・中期症状
うつ病の初期・中期症状は、気分の落ち込みなどがあります。その他の具体的な症状としては、次のようなものがあります。
■うつ病の初期・中期
- 将来のことが不安になる
- 物忘れが多くなる
- 不眠・過眠・食欲不振
- 体重減少など
これらの症状が現れると、仕事や家事の能率が上がらず、日常生活にもさまざまな支障が出ます。
末期症状
うつ病が進行して重症になると、気分の落ち込みが深まり、動作にも変化が現れます。例えば、次のような症状は、うつ病が進行した状態と考えられます。
■うつ病が進行すると
- 将来のことが不安になる
- 消えてしまいたいと思う
- 生きていく希望がない
- 動きがゆっくりになる
- 落ち着きなく動き回るなど
これらの症状により、仕事を辞める、離婚する、といった結果になる場合もあります。さらに、うつ病の症状のつらさから、消えてしまいたくなるほどに思い詰めてしまうこともあります。
気になる症状がある場合は、医療機関に相談しましょう。
うつ病の原因
そもそもうつ病は、脳内の神経細胞が行う情報伝達にトラブルが起きている状態であると考えられています。こうした状態になる原因は1つではなく、さまざまな要因により引き起こされることが分かっています。
環境要因、性格傾向、その他の3つに分けて、うつ病の原因を見ていきましょう。
環境要因
うつ病になるきっかけとして最も多いのが、環境要因です。家族や親しい人など、大切な人の死や離別などがこれに当てはまります。また、仕事や財産を失う、病気になるなども、うつ病の要因になります。
他には、人間関係や家庭内のトラブル、昇格、降格、結婚、妊娠など、職場や家庭での役割の変化が挙げられます。こうした環境の変化は、多くの人が経験することです。身近なところに、うつ病のきっかけがあることが分かります。
性格傾向
性格傾向も、うつ病の原因の1つです。先述のように、うつ病は脳のエネルギーが欠乏している状態です。脳のエネルギーを多く放出する性格は、うつ病の要因になりやすいと言えます。例えば、正義感が強い、仕事熱心、完璧主義、きちょうめん、凝り性、他人に気を遣うなどです。
こうした性格は決して珍しくなく、多くの人に見られます。うつ病を発症する可能性の高まる要因として、脳のエネルギーを使い過ぎないことも知っておく必要があるでしょう。
その他
その他の要因に、がん、糖尿病などの慢性的な身体疾患や遺伝があります。糖尿病に関しては、患者の約30%にうつ症状があるという調査があり、両者の関係性の研究が進められているところです。
遺伝的要因については、うつ病を引き起こしやすいタイプの遺伝子が存在することが発見されています。原理的には、うつ病を起こしにくいワクチンを新生児期に接種することで、遺伝を抑制できることになります。
これらの原因は日常生活の中にあり、誰もが経験しうるものです。それでは実際にうつ病になったときには、どのような治療が行われるのか、次に確認していきましょう。
うつ病の治療法
うつ病の治療法は、休養、薬物治療、精神療法の3つの方法があります。それぞれの内容について触れていきましょう。
休養
休養は、心身の休まる環境をつくり、脳をしっかり休ませます。職場や学校を休んで療養する、あるいは入院するなどさまざまです。脳のエネルギーを回復させるために、使い過ぎないように過ごします。
薬物治療
薬物療法は、休養が取れない場合や、脳の機能改善、症状の軽減に用いられます。主に使用される薬は抗うつ剤です。また、症状によっては、睡眠導入剤や精神安定剤などが併用されます。
精神療法
精神療法は、カウンセリングなどを通じて、思考・行動パターンを見直します。うつ病の再発防止が主な目的です。精神療法には、認知行動療法、森田療法、内観療法などの種類があります。
その他
その他のうつ病の治療法に、高照度光療法、修正型電気けいれん療法、経頭蓋磁気刺激法などがあります。
高照度光療法は、強い光を浴びることで体内時計をリセットする治療法です。冬季うつ病の治療に使われることの多い療法です。
修正型電気けいれん療法や経頭蓋磁気刺激法は、脳に電気刺激を与えることで症状を改善させます。
うつ病の予防法
「うつ病の原因」で見てきたように、うつ病を引き起こすのは特別な出来事というわけではありません。そのため、日ごろから予防を心掛けることも大切です。ここでは3つの予防法を紹介します。
ストレスをため過ぎない
1つ目の予防法は、ストレスをため過ぎないことです。ストレスが蓄積すると、体がだるくなる、よく眠れない、食欲がないなどの症状が現れ、うつ病のきっかけになる場合があります。
好きな音楽を聴く、本を読む、散歩をする、サークルに参加するなど、余暇をストレス解消に充てる方法があります。
生活習慣を見直す
もう1つは、生活習慣を見直して健康的な生活を送ることです。糖尿病は、うつ病と関わりのあることは先に述べた通りです。睡眠を十分にとり、バランスのとれた食事を心掛けるようにします。
また運動も、良質な生活習慣をつくる上で必要です。ウォーキングや水泳、ヨガなど、運動習慣を身に付けることで予防につなげていきます。
周りの人がうつ病になったときに私たちができること
うつ病になる可能性は自分だけではありません。身近な人がうつ病を発症することもあります。そのとき、私たちは何ができるのでしょうか。
周りの人がうつ病になったときに「できること」と「やってはいけないこと」を確認していきましょう。
うつ病の人に対して周りの人ができること
「できること」は、本人の話に耳を傾けることです。このとき、相手の言うことを否定せず、理解しようという姿勢で臨みます。アドバイスをしないで、不安や悩みを受け止めます。
また、無理に話を聞き出すのではなく、「いつでも話を聞くからね」と、味方であることを伝えます。
うつ病になりやすい人の特徴
真面目で責任感が強く、周囲に気を遣いすぎる傾向のある人は、ストレスを内に抱え込みやすく発症リスクが高いとされています。また、完璧主義で失敗を許せないタイプや、頼まれごとを断れない人も注意が必要です。
加えて、過去に心の傷を抱えている人や、孤独感を感じやすい人、遺伝的に精神疾患のリスクがある家系の人なども発症しやすい傾向があります。ストレスの蓄積や環境変化にも注意が必要です。
うつ病の人にやってはいけないこと
「できること」がある一方で、「やってはいけないこと」もあります。3つのポイントを確認していきましょう。
話を否定する
「できること」で触れたように、話を否定することは控えます。例えば、「私はダメな人間なんだ」と本人が言えば「そんなことないよ!」と返したくなるかもしれませんが、これも否定する言葉です。
また、「そんなに悲観的にならないで」という言葉も、相手の感情を否定することになってしまいます。相手に寄り添い、気持ちを受け止めることを心掛けます。
励ます
「がんばって」「大丈夫だよ」などの励ましの言葉は、うつ病を患った人を追い詰めることになり逆効果です。本人は、がんばりたくてもがんばれないことに悩んでいます。温かく見守ることが、一番の励ましになります。
無理に外に連れ出す
気分転換にと、ドライブや外食、旅行などに連れ出すことは、相手にとって良いことだと思いがちです。しかし、うつ病を患った人は心身が疲れているため、負担になることがあります。まずはしっかり休んでもらうことが大切です。
「できること」「やってはいけないこと」は、この他にもあります。さらに知りたい方は、医療機関のサイトなどで調べると詳しい情報を得ることができます。
うつ病に関してよくある疑問
うつ病について解説してきましたが、この他にも知っておきたい情報を、よくある質問に回答する形でまとめました。
うつ病の症状で顔つきも変わる?
うつ病になると、顔つきも変わるといわれています。医師の診察においても、表情は診断の参考にされる場合があるようです。
具体的には、無表情になる、目がうつろになるなどです。うつ病の症状である気持ちが落ち込んでいる、やる気がない、不眠などの状態が顔に現れていると考えられています。
うつ状態とうつ病の違いは?
うつ状態という言葉は、日常でも使われることがあります。ただし、うつ病とは意味が異なり、気分が落ち込んだ状態を表します。つまり、うつ状態は気分、うつ病は病気を示す別々の意味を持つ言葉です。
うつ状態は、うつ病の症状を説明するのに使えるほか、日常の気分を表す言葉としても使用できます。
うつ病が治るきっかけは?
うつ病が治るきっかけは人それぞれですが、共通しているのは「適切なサポートと治療環境が整うこと」です。まず、病院での早期診断と薬物療法やカウンセリングなどの適切な治療が始まることが重要です。
また、仕事や家庭などのストレス要因から一時的に距離を置き、心身を休めることも大きなきっかけになります。さらに、信頼できる家族や友人との会話や共感によって「一人じゃない」と感じられることも回復の助けになります。
生活習慣の改善や、少しの成功体験を積み重ねることでも前向きな気持ちを取り戻せるようになります。完治には時間がかかることもありますが、焦らず、少しずつ日常を取り戻すことが回復への第一歩です。
うつ病とSDGs
最後に、うつ病とSDGsとの関係について確認します。うつ病は、SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」に該当します。
目標3「すべての人に健康と福祉を」
目標3「すべての人に健康と福祉を」は、すべての人々の健康的な生活を実現し、福祉を推進することを掲げています。また、健康リスクについて早期に発見することなどを定めています。
うつ病は、世界の人口の約3.8%が経験している病気です。2019年には2億8千万人がかかり、毎年70万人以上が自殺で亡くなっています。
人々が健康的な生活を送るためには、心の健康が欠かせません。うつ病の予防や治療、再発予防などの観点から、国や自治体、医療機関、そして私たちも取り組みを進めていく必要があります。この取り組みは、SDGsの目標達成につながります。
まとめ
うつ病は、脳のエネルギーが欠乏することで、精神的・身体的な症状のある病気です。気分が落ち込む、やる気が出ない、眠れない、食欲がないなどの症状が現れます。原因は、環境要因や性格傾向などがありますが、複数の要因が関わっている場合が多いのが特徴です。
うつ病の治療は、薬物治療や精神療法もありますが、休養が最も大切です。そのため、ストレスをため過ぎないことは予防にもつながります。治療や予防は、SDGsの目標3にも貢献する取り組みです。
日本で生涯うつ病を経験する人は、15人に1人ともいわれています。自分の心と体の健康に心掛けるとともに、周囲がうつ病になったときにできることを知ることは重要です。気になる症状があれば、医療機関や専門家に相談しましょう。
<参考>
こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
こころの情報サイト
うつ病Q&A | 日本うつ病学会 Japanese Society of Mood Disorders
社会医療法人 博友会 | 社会医療法人博友会は医療・看護・介護を通して地域に貢献いたします。社会医療法人 博友会
MSDマニュアル家庭版
うつ病症状の進行 | うつ病の情報・サポートサイト こころの陽だまり
e-ヘルスネット(厚生労働省)
産業保健新聞|ドクタートラスト運営 RSS Feed
うつ状態の家族との接し方 | 千葉県精神神経科診療所協会(千葉精診)
この記事を書いた人
池田 さくら ライター
ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。
ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。








